解説記事2019年06月10日 【税理士のための相続法講座】 相続法改正(2)―自筆証書遺言の方式緩和(2019年6月10日号・№790)
税理士のための相続法講座
第47回
相続法改正(2)
―自筆証書遺言の方式緩和
弁護士 間瀬まゆ子
1 はじめに 本連載では、以下の改正事項について、施行の早いものから順に、具体的に解説していきます。
そして、今回のテーマは自筆証書遺言の方式緩和です。この部分は、本年1月13日に施行済みです。
※相続開始が施行後であっても、遺言が施行前に書かれたものである場合には適用がないことは前回も述べたとおりです。
2 全文自書の負担 旧法では、自筆証書遺言は、その全文を自書しなければならないことになっていました(968条1項)。これは、偽造や変造を防止し、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保するためと言われます。
全文自書と言っても、例えば、「自宅を妻に相続させる」という一文を残すだけであれば、大した負担にはならないでしょう。しかし、そのような曖昧な記載では登記が通るか等、遺言の執行の際に問題が生じる可能性があり、それでは遺言を残した意味も減殺されてしまいます。更に、自宅の敷地が遺言作成後に分筆されていたような場合に、「自宅」がどこまで含めるのかの解釈をめぐって相続人間で紛争が生じる恐れもあります。
そこで、対象となる財産を特定するため、不動産であれば地番や地積等、銀行口座であれば支店名や口座番号等を特定して記載するのが一般的です。ですが、特に遺言者が高齢者の場合には、それが大きな負担となります。筆者も依頼を受けて自筆証書遺言の文案を作成することがありますが(なお、あくまで公正証書遺言を作るまでの暫定的なものと説明しています。)、筆者から見るとかなりシンプルな内容であったとしても、依頼者から「これを全部書くのか」と驚かれてしまうこともあります。
3 改正の内容 そのため、上記のような負担を軽減し、自筆証書遺言の利用促進を図るため、新法では、自筆証書遺言の方式が一部緩和されました。具体的には、自筆証書遺言に財産目録等を添付する場合に、その目録については「自書することを要しない」とされました(968条2項)。
つまり、例えばパソコンで作成した目録を添付することも認められるようになりました(後掲の例1、2枚目)。その目録は遺言者本人が作成したものでなくて構いません。更には、わざわざ目録を作らずとも、不動産の登記事項証明書(例2)や預貯金通帳(例3)のコピーをそのまま目録として添付することも可能とされていますので、筆者から見ても、自筆証書遺言を作成する手間は相当に削減されたと思います。
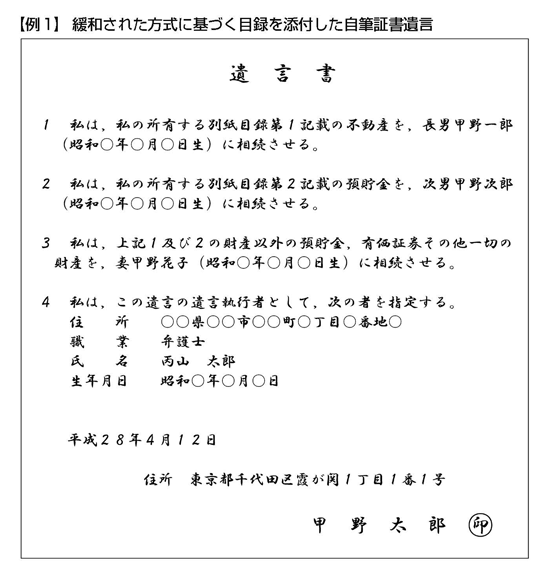
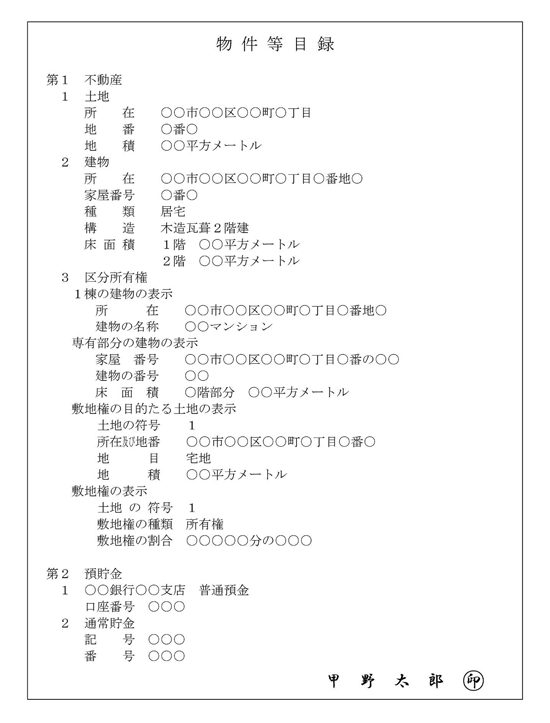
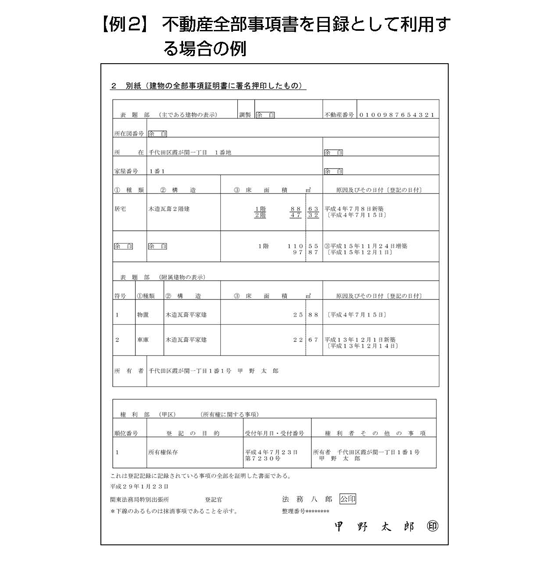
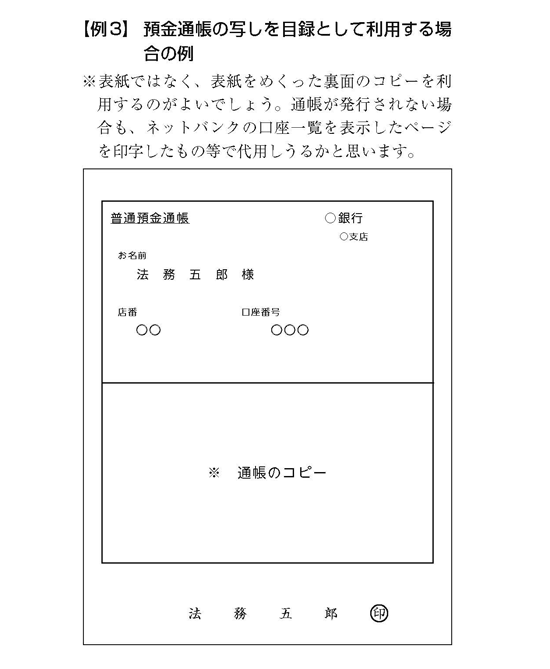
※いずれも、法制審議会民法(相続関係)部会の参考資料を法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00294.html)より転載。
4 自書によらない財産目録の方式 まず、財産目録の全てのページに遺言者が署名押印をする必要があります。両面に記載がある場合は、表面裏面の両方に署名押印をしなければなりません。これに対し、本文や他の目録と綴る際の契印は、法律上要求されていません。ただ、本文と目録の一体性を確保するために、契印をする、同一の封筒に封緘する、遺言書全体を編綴するといった方法のいずれかを行うことが望まれます。また、押印は実印による必要はありません。本文と同じ印鑑であることも要求はされていませんが、偽造等の疑いを持たれないためにも同じ印鑑にしておくのが無難です。
次に、目録が「添付」されるものである点にも注意が必要です。すなわち、目録が印字された用紙に自筆で本文を追加したような場合、目録を「添付」したとは言えなくなります。必ず、本文と目録は別の用紙にする必要があります(堂薗幹一郎ほか編著「概説改正相続法-平成30年民法等改正、遺言書保管法制定-」85ページ参照)。
5 財産目録の記載の加除訂正 自筆証書遺言の加除訂正の方式について定めていた旧法968条2項が改正され、目録の加除訂正についても適用されることになりました(新法968条3項)。ただ、万一、加除訂正の方式に不備があった場合、せっかくの遺言が無効とされてしまう恐れが生じます。ですので、書き損じ等があった場合には、加除訂正によるのではなく、新しく書き直すことを推奨しています。
6 実務への影響 この改正は、弁護士以上に税理士が活用し得るのではないかというのが私見です。というのも、既に所得税の確定申告を受任していて財産債務調書を作成している場合、財産や債務の内容をある程度把握できているはずですので、自筆証書遺言に添付する財産目録を作成するのも容易と思われます。とすれば、目録の作成を提案し、それをきっかけとして、依頼者の遺言の作成に関与することが考えられます。そうなれば、将来相続が開始したときに、遺言の執行に加えて、所得税や相続税の申告といった業務の受任に繋がる可能性も出てきます。特に若い税理士であれば、遺言者との年齢が離れていることがプラスに働きますので、よりチャンスが広がるかもしれません。
加えて、新しく始まる自筆証書遺言の保管制度を利用すれば、依頼者の安心も増すでしょう。この制度は、公正証書遺言よりも費用等の面で手軽という利点もあります。この自筆証書遺言の保管制度については、別稿で解説する予定です。
第47回
相続法改正(2)
―自筆証書遺言の方式緩和
弁護士 間瀬まゆ子
1 はじめに 本連載では、以下の改正事項について、施行の早いものから順に、具体的に解説していきます。
| ◆自筆証書遺言の方式緩和 ◆配偶者への居住用不動産の贈与・遺贈について持戻し免除の意思表示を推定する規定の新設 ◆仮払い制度の創設 ◆遺留分制度に関する見直し ◆特別の寄与の制度の創設 ◆配偶者の居住権の新設 ◆法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 |
※相続開始が施行後であっても、遺言が施行前に書かれたものである場合には適用がないことは前回も述べたとおりです。
2 全文自書の負担 旧法では、自筆証書遺言は、その全文を自書しなければならないことになっていました(968条1項)。これは、偽造や変造を防止し、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保するためと言われます。
全文自書と言っても、例えば、「自宅を妻に相続させる」という一文を残すだけであれば、大した負担にはならないでしょう。しかし、そのような曖昧な記載では登記が通るか等、遺言の執行の際に問題が生じる可能性があり、それでは遺言を残した意味も減殺されてしまいます。更に、自宅の敷地が遺言作成後に分筆されていたような場合に、「自宅」がどこまで含めるのかの解釈をめぐって相続人間で紛争が生じる恐れもあります。
そこで、対象となる財産を特定するため、不動産であれば地番や地積等、銀行口座であれば支店名や口座番号等を特定して記載するのが一般的です。ですが、特に遺言者が高齢者の場合には、それが大きな負担となります。筆者も依頼を受けて自筆証書遺言の文案を作成することがありますが(なお、あくまで公正証書遺言を作るまでの暫定的なものと説明しています。)、筆者から見るとかなりシンプルな内容であったとしても、依頼者から「これを全部書くのか」と驚かれてしまうこともあります。
3 改正の内容 そのため、上記のような負担を軽減し、自筆証書遺言の利用促進を図るため、新法では、自筆証書遺言の方式が一部緩和されました。具体的には、自筆証書遺言に財産目録等を添付する場合に、その目録については「自書することを要しない」とされました(968条2項)。
| 民法968条(自筆証書遺言)
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(略)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載が両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。 3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 ※下線が改正部分。 |
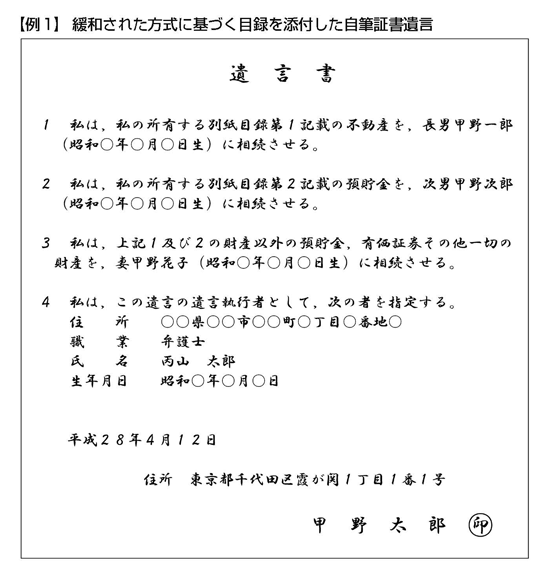
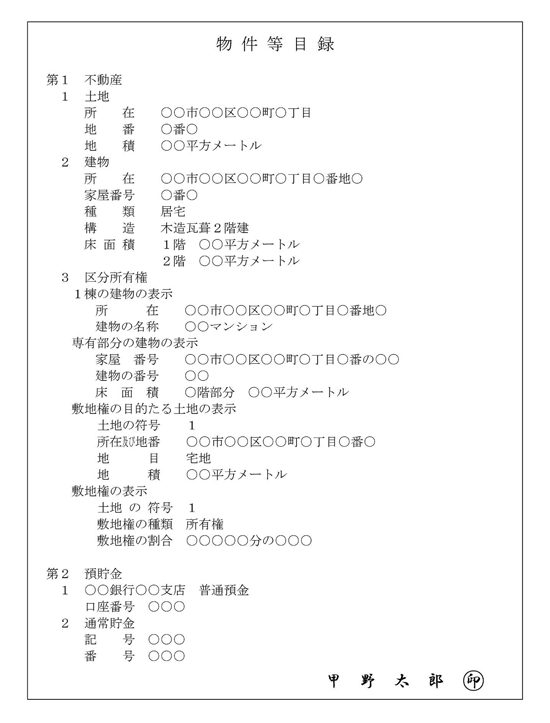
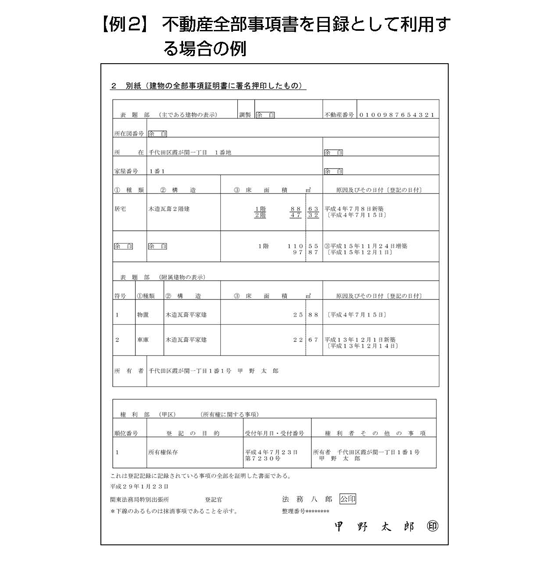
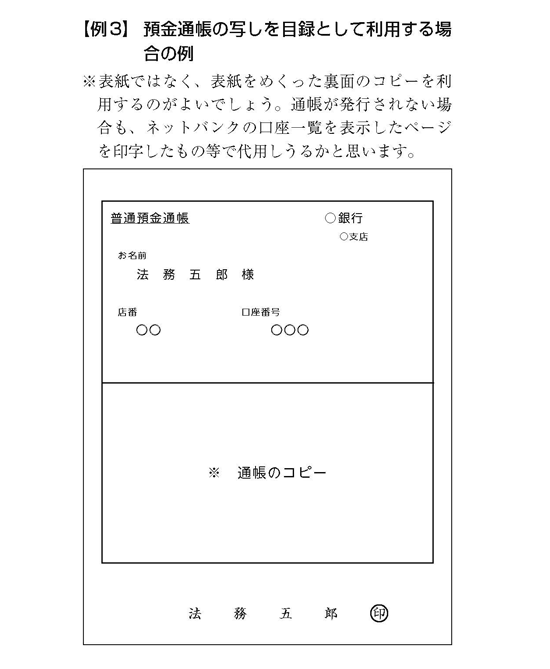
※いずれも、法制審議会民法(相続関係)部会の参考資料を法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00294.html)より転載。
4 自書によらない財産目録の方式 まず、財産目録の全てのページに遺言者が署名押印をする必要があります。両面に記載がある場合は、表面裏面の両方に署名押印をしなければなりません。これに対し、本文や他の目録と綴る際の契印は、法律上要求されていません。ただ、本文と目録の一体性を確保するために、契印をする、同一の封筒に封緘する、遺言書全体を編綴するといった方法のいずれかを行うことが望まれます。また、押印は実印による必要はありません。本文と同じ印鑑であることも要求はされていませんが、偽造等の疑いを持たれないためにも同じ印鑑にしておくのが無難です。
次に、目録が「添付」されるものである点にも注意が必要です。すなわち、目録が印字された用紙に自筆で本文を追加したような場合、目録を「添付」したとは言えなくなります。必ず、本文と目録は別の用紙にする必要があります(堂薗幹一郎ほか編著「概説改正相続法-平成30年民法等改正、遺言書保管法制定-」85ページ参照)。
5 財産目録の記載の加除訂正 自筆証書遺言の加除訂正の方式について定めていた旧法968条2項が改正され、目録の加除訂正についても適用されることになりました(新法968条3項)。ただ、万一、加除訂正の方式に不備があった場合、せっかくの遺言が無効とされてしまう恐れが生じます。ですので、書き損じ等があった場合には、加除訂正によるのではなく、新しく書き直すことを推奨しています。
6 実務への影響 この改正は、弁護士以上に税理士が活用し得るのではないかというのが私見です。というのも、既に所得税の確定申告を受任していて財産債務調書を作成している場合、財産や債務の内容をある程度把握できているはずですので、自筆証書遺言に添付する財産目録を作成するのも容易と思われます。とすれば、目録の作成を提案し、それをきっかけとして、依頼者の遺言の作成に関与することが考えられます。そうなれば、将来相続が開始したときに、遺言の執行に加えて、所得税や相続税の申告といった業務の受任に繋がる可能性も出てきます。特に若い税理士であれば、遺言者との年齢が離れていることがプラスに働きますので、よりチャンスが広がるかもしれません。
加えて、新しく始まる自筆証書遺言の保管制度を利用すれば、依頼者の安心も増すでしょう。この制度は、公正証書遺言よりも費用等の面で手軽という利点もあります。この自筆証書遺言の保管制度については、別稿で解説する予定です。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























