解説記事2019年08月12日 【税務マエストロ】 純資産価額方式を適用する場合における決算日(2019年8月12日号・№799)
税務マエストロ
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
純資産価額方式を適用する場合における決算日
#235 梶野研二(税理士)
略歴 国税庁 課税部 資産評価企画官付企画専門官、同資産課税課課長補佐、東京地方裁判所 裁判所調査官、国税不服審判所本部 国税審判官、東京国税局 課税第一部資産評価官、玉川税務署長などを経て、平成25年6月 税理士登録。現在、相続税を中心に税理士業務を行っている。○主な著書 「ケース別 相続土地の評価減」、「非公開株式評価実務マニュアル」(新日本法規)、「判例・裁決にみる非公開株式評価の実務」(共著)(新日本法規)、「株式・公社債評価の実務」、「土地評価の実務」(共著)(大蔵財務協会)
今回のテーマ 財産評価基本通達は、取引相場のない株式の原則的評価方法として純資産価額方式と類似業種比準方式を定めている。このうち純資産価額方式は、課税時期における評価会社の総資産価額から総負債価額を控除し、さらに評価差額に対する法人税等相当額を控除し、算出された純資産価額を課税時期における発行済株式数で除して、1株当たりの株式の評価額を求める方法である。しかしながら、課税時期における資産及び負債を正確に把握することは困難な場合が多く、実務上は、ほとんどのケースにおいて直前期末の資産及び負債に基づいて評価額が算出されている。今回は、このような実務上の取扱いについて考えることとする。
マエストロの解説
1 純資産価額方式 相続税及び贈与税の課税上、相続や遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式の価額は、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)に定められた評価方法により評価されている。評価通達は、同族株主等が取得した株式については、原則として、純資産価額方式若しくは類似業種比準方式、またはこれらの評価方式の併用方式により評価することとされている(評基通179)。
このうち純資産価額方式とは、次の算式により求めた評価会社の株式1株当たりの純資産価額をもって当該会社の株式1株当たりの評価額とする評価方法である(評基通185)。
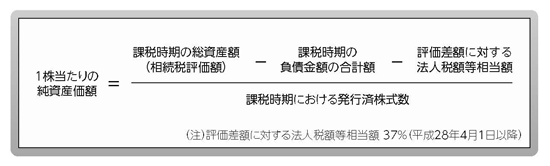
この純資産価額方式の適用に当たっては、次の点に注意する必要がある。
(1)「課税時期の総資産価額(相続税評価額)」の計算に当たっては、評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利(土地等)並びに家屋及びその附属設備又は構築物(家屋等)を有する場合には、それらの価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、これらの資産に係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、その帳簿価額に相当する金額によって評価することができるものとされている(評基通185かっこ書き)。
(2)評価会社が取引相場のない株式を保有する場合において当該株式を純資産価額方式で評価するときには、評価差額に対する法人税等相当額は控除しない(評基通186-3)。
(3)「評価差額に対する法人税等相当額」の計算に当たっては、評価会社の有する各資産の中に、現物出資若しくは合併により著しく低い価額で受け入れた資産又は株式交換若しくは株式移転により著しく低い価額で受け入れた株式(これらの資産又は株式を「現物出資等受入れ資産」という。)がある場合には、当該各資産の帳簿価額の合計額に、現物出資、合併、株式交換又は株式移転の時において当該現物出資等受入れ資産をこの通達に定めるところにより評価した価額から当該現物出資等受入れ資産の帳簿価額を控除した金額(これを「現物出資等受入れ差額」という。)を当該各資産の帳簿価額に加算することにより、当該現物出資受入差額に対応する法人税等相当額は控除しない(評基通186-2(2))。
(4)評価会社の株式を取得した者及びその同族関係者が有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下である場合には、上記により計算した1株当たりの純資産価額に100分の80を乗じて計算した価額により評価する(評基通185ただし書き)。
2 直前期末の資産負債による純資産価額の計算
(1)直前期末の資産負債による評価が認められる趣旨 純資産価額は、課税時期、すなわち相続、遺贈又は贈与により評価会社の株式を取得した時における評価会社の資産及び負債に基づいて評価することとされている。しかしながら、評価会社が事業活動を行っているならば、その資産及び負債の状況は日々変動している。課税時期という期中の特定の日における資産及び負債を特定し、それらを評価するためには、毎期行われる決算事務と同様に多額の費用と膨大な時間を要することとなる。課税時期における正確な純資産価額を算定するためには、課税時期における正確な資産及び負債を把握するための仮決算を行うこととなるが、すべての場合に多額の費用と膨大な時間を投じて仮決算を実施することは必ずしも現実的な評価方法とはいえない。
そこで、実務上は、評価会社が課税時期において仮決算を行っていないために課税時期における資産及び負債の金額が明確でない場合において、直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるときは、課税時期における各資産及び各負債の金額に代えて、直前期末の資産及び負債の課税時期の相続税評価額により1株当たりの純資産価額を計算する簡便的な方法によっても差し支えないこととされている(脚注1)。
(2)直前期末の資産負債による純資産価額の計算 直前期末の資産及び負債の課税時期の相続税評価額により1株当たりの純資産価額を計算する簡便的な方法の詳細及び留意すべき点は次のとおりである。
イ 直前期末の資産及び負債
この簡便的な方法は直前期末に評価会社が有する資産及び負債を基に評価する方法である。直前期末に評価会社が保有していた資産が、直前期末から課税時期までの間に譲渡され又は滅失してしまったとしても直前期末に存するならば評価会社が有する資産として評価明細書第5表に計上しなければならない。また、直前期末後に取得し又は発生した資産があってもこれを評価明細書第5表に計上する必要はない。同様に、評価会社の負債についても、直前期末に存するものは直前期末後に返済したり消滅したものであっても評価明細書第5表に計上し、直前期末後に発生した債務は同表に計上しない(ただし、上記「○直前期末の資産負債を基に純資産価額を計算する方法」の(注)1に該当するものは負債として取り扱われる。)。
このように、課税時期に存しない資産負債を評価額の計算に含め、反対に課税時期に存する資産負債を評価額の計算に含めない取扱いは、相続税法第22条に定める「当該財産の取得の時における時価」の概念に反することとなるのではないかとの疑義が生じるが、直前期末の資産負債による簡便的な評価が認められている趣旨に照らせば、一種の割り切りと理解すべきであり、同条の許容するところであると考えられる。
なお、直前期末における資産負債の状況と課税時期における資産負債の状況が大きく異なり、評価額に与える影響が大きいと認められる場合には、直前期末における資産負債を基に評価することは相当ではなく、この場合には課税時期における資産負債を基に評価することとなる。
ロ 簿外資産の計上等 直前期末の資産負債に基づいて評価するということは、直前期の貸借対照表に記載されている資産負債のみを基に評価するということではない。自然発生借地権や営業権などのように評価の対象となる資産について、帳簿価額がないものであっても相続税評価額が算出される場合には、その評価額を評価明細書第5表の「相続税評価額」欄に記載することになる。なお、この場合、「帳簿価額」欄への記載は「0」となる。
また、借家権や営業権など評価の対象となる資産で帳簿価額のあるものであっても、その課税価格に算入すべき相続税評価額が算出されない場合(脚注2)には、「相続税評価額」欄への記載は「0」とし、その帳簿価額を「帳簿価額」欄に記載する。
なお、財産性のない創立費、新株発行費等の繰延資産、繰延税金資産などの評価の対象とならないものについては、「相続税評価額」欄及び「帳簿価額」欄のいずれにも記載しない。
ハ 各資産の評価時期 直前期末の資産負債を基に純資産価額を計算する簡便的な方法を採用した場合であっても、評価会社が直前期末に有する各資産については、課税時期における評価額を評価明細書第5表の「相続税評価額」欄に記載する。
例えば、課税時期が平成31年4月15日、直前期末が平成30年11月30日であるA社の株式の評価に当たり、同社が直前期末に保有していた土地は、直前期末の属する年である平成30年分の路線価又は評価倍率により評価するのではなく、課税時期の属する年である平成31年分(令和元年分)の路線価又は評価倍率により評価することになる(倍率方式における固定資産税評価額も平成31年度(令和元年度)の評価額による。)。また、直前期末に保有していた上場株式は、課税時期である平成31年4月15日の金融商品取引所の最終価格、課税時期の属する月である4月の最終価格の月中平均、その前月である3月の最終価格の月中平均及び前々月である2月の最終価格の月中平均のうち最も低い価額を採用することとなる。
ニ 課税時期前3年以内に取得した土地等又は家屋等 純資産価額方式においては、評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利(土地等)並びに家屋及びその附属設備又は構築物(家屋等)を有する場合には、それらの価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとされている。評価会社の保有する土地等又は家屋等が、課税時期前3年以内に取得又は新築された土地等又は家屋等であるかどうかの判定は、これらの資産の取得又は新築の日から直前期末までの期間で判定するのではなく、これらの資産の取得又は新築の日から課税時期までの期間で判定することとなる。例えば、課税時期が平成31年4月15日、直前期末が平成30年11月30日であるA社が平成28年2月に取得した土地を所有していた場合には、取得の日から直前期末までの期間は3年に満たないが、取得の日から課税時期までの期間は3年を超えるので、この土地等は課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する必要はなく、平成31年分(令和元年分)の路線価等により評価することとなる。
ホ 保険金請求権の計上 被相続人の死亡により評価会社が生命保険金を取得する場合には、その生命保険金請求権(未収保険金)の金額を評価明細書第5表の「資産の部」の「相続税評価額」欄及び「帳簿価額」欄のいずれにも記載する。この場合、その保険料が資産に計上されているときは、その金額を資産から除外する。また、保険差益に対する法人税等相当額は負債に計上するが、その生命保険金を原資として被相続人に係る死亡退職金を支払った場合には、その支払退職金の額を負債に計上するとともに、支払退職金を控除した後の保険差益について課されることとなる法人税額等を負債に計上する。課税時期における仮決算を行わず、直前期末の資産負債により純資産価額を計算する場合には、課税時期の属する事業年度の法人税額(期首から課税時期までの期間に対応する法人税額)を負債として控除することはできないが、被相続人の死亡により評価会社が取得する保険金請求権を資産に計上する場合には、このように当該保険金請求権に係る法人税額相当額(脚注3)の控除が認められている。当該保険金請求権に関係する部分についてのみ仮決算を行ったと同様に考えることができるからであると思われる。
ヘ 特定の評価会社の判定等 純資産価額方式の適用に当たり、直前期末の資産負債により純資産価額を求める簡便的な方法によった場合には、株式等保有特定会社及び土地保有特定会社の判定における「総資産価額」、「株式等の価額の合計額」及び「土地等の価額の合計額」についても、直前期末の資産により判定し、また、株式等保有特定会社のS2の計算時期についても同様に行うこととなる。
(3)直前期末の資産負債による純資産価額の計算が認められない場合 直前期末の資産負債による純資産価額の計算は、評価会社が課税時期において仮決算を行っていないために課税時期における資産及び負債の金額が明確でない場合であって、直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるときに限って認められることとされている。
イ 簡便的な方法の選択 直前期末の資産負債による純資産価額の計算は、評価会社が課税時期において仮決算を行っていないために課税時期における資産及び負債の金額が明確でない場合に認められる評価方法である。したがって、仮決算を行うことにより課税時期における資産及び負債の金額が明確になっている場合には、仮決算に基づく課税時期における資産及び負債の金額により純資産価額を計算しなければならない。記載方法通達の文言上は、課税時期の資産負債に基づいて計算した純資産価額と直前期末の資産負債に基づいて計算した純資産価額とを比較し、いずれか低い価額を選択することができるという扱いではないことに留意すべきである。また、課税時期における資産負債に基づいて算出した純資産価額により相続税又は贈与税の課税価格を計算して申告を行った場合に、直前期末の資産負債に基づいて算出した純資産価額により相続税又は贈与税の課税価格を計算して更正の請求や修正申告を行うことは認められない。
ロ 評価額の計算に影響が少ないと認められない場合 直前期末の資産負債による純資産価額の計算は、直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるときに認められる簡便的な評価方法である。この評価方法は、相続税法第22条の規定に照らせば、本来、課税時期における正確な資産及び負債を把握するための仮決算を行うことが好ましいが、すべての場合に多額の費用と膨大な時間を投じて仮決算を実施することを求めることは現実的ではないために、同条が許容する範囲内において認められている評価方法であると解される。直前期末後に「資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ない」と認められるかどうかについては個々のケースごとに増減額や増減割合その他の事情から個別に判定することとなる。この取扱いが記載方法通達に明記された一般的な取扱いであることに照らせば、直前期末から課税時期までの間において評価会社に相当程度の利益が出ているとしても、それが評価会社の通常の事業活動の結果生じたものであるならば、特殊な事例を除き、直前期末の資産負債による純資産価額の計算が否定されることはないと思われる。しかしながら、直前期末後に多額の固定資産の売買が行われた場合や合併その他の組織再編があった場合には、慎重な判断が必要である。評価会社が直前期末から課税時期までの間に、A社の出資23,995口を941,443,825円で取得しており、当該取得価額の純資産に占める割合が71%にも相当した事例において、評価会社はA社の出資を著しく低い価額の対価により譲り受け、これにより評価会社の資産の金額が著しく増加していると認められるとして、評価会社の直前期末の資産及び負債の金額を基礎として計算することは相当でなく、課税時期において仮決算をした資産及び負債の金額を基礎として評価するのが相当であるとされた裁決例は参考となるであろう(脚注4)。
(4)直前期末の資産負債による計算が認められない場合の純資産価額の計算 直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減があり評価会社の株式の評価額の計算に影響があると認められる場合には、課税時期の資産負債により純資産価額を計算しなければならない。しかしながら、課税時期における資産負債を特定するために仮決算を行うことは困難なケースが多いと考えられる。課税時期から長期間が経過した後、税務調査で問題点を指摘され課税時期の資産負債による評価を行うような場合には、一層の困難が想定されるところである。このような場合に、例えば、直前期末の資産及び負債のうち、特定の財産又は種類の資産又は負債についてのみ課税時期の状況に置き換えて評価額を算出することもやむを得ないであろう。例えば、平成22年7月26日裁決(脚注5)では、国税不服審判所は次のような認定を行っている。
上記(2)のホの生命保険金請求権の計上についても、評価額に影響を与える部分のみを取り出して、その部分についてのみ仮決算を行っているとみることもできるであろう。
3 直後期末の資産負債による純資産価額の計算 直前期末の資産負債による純資産価額の計算が通達により認められている一方、直後期末の資産負債による純資産価額の計算も、事実上、一定の条件の基に認められている。
例えば、東京国税局課税第一部資産評価官の職員が執筆した書籍において、個人的見解としつつ「課税時期が直後期末に非常に近く、課税時期から直後期末までの間に資産及び負債の金額について著しく増減がないと認められる場合には、財産・債務について経理操作を行っているなどの課税上弊害がある場合を除き、直後期末の各資産及び負債の金額を課税時期における各資産及び負債の金額として計算しても差し支えないものと考えます。」とされている(脚注6)。
上記2の直前期末の資産負債による純資産価額の計算が、「直前期末の資産負債」を基に評価会社の株式を評価する方法であるのに対し、実務上認められているとされる直後期末の資産負債による純資産価額の計算は、あくまでも直後期末の資産負債を課税時期の資産負債として計算するものであり、直後期末の資産負債を課税時期の資産負債とみなすことができるほど両者に差異がないと認められる場合に限っての事実上の取扱いであることに留意する必要があろう。すなわち、課税時期において仮決算を行ったのと同様の結果が得られるときにのみこの取扱いが適用されると理解すべきであり、このような事実上許容されている取扱いは、上記2の(4)と同様の課税時期における資産負債を確定しようとする試みの一形態と捉えるべきであろう。
したがって、直前期末の資産負債と直後期末の資産負債とを比較して、後者の方が課税時期の資産負債の実態に近いとの理由だけで後者を選択をすることができると解することはできないと考える。
4 おわりに 直前期末の資産負債による純資産価額の計算は、実務上の要請から認められた簡便的な方法であり、時間とコストのかかる純資産価額方式の適用において、若干なりとも手順を省略できるこの方法は、実務上あたかも原則的な方法であるかのように採用されている評価方法である。しかし、課税時期を含む事業年度において事業が奮わず赤字決算が見込まれる場合や、多額の損失を被った場合など、課税時期における仮決算による資産負債により計算した純資産価額が、直前期末の資産負債による純資産価額を下回ることが容易に想像できるときには、多少の時間とコストを費やすこととなろうとも仮決算を実施すべきである。また、仮決算が困難であるとしても、合理的な方法によって課税時期における資産負債を推定することができるのであれば、そのような手法による評価も検討すべきであろう。
脚注
1 この取扱いは、法令解釈通達である平成2年12月27日付直評23・直資2-293「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」通達において、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の「第5表 1株当たりの純資産(相続税評価額)の計算明細書」の記載方法として定められている。本稿においては、この通達を「記載方法通達」という。
2 権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にある借家権は評価しないこととされている(評基通94ただし書き)。また、営業権の評価方法は、財産評価基本通達165以下に定められているところであるが、平均利益金額が5,000万円以下の場合には、営業権の評価額は算出されない(評基通166(2)(注)。)。
3 評価会社が仮決算を行っていないため、課税時期の直前期末における資産及び負債を基として1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を計算する場合における保険差益に対応する法人税額等は、この保険差益によって課税所得金額が算出される場合のその課税所得の37%相当額によることができる(国税庁ホームページホーム/法令等/質疑応答事例/財産評価/「評価会社が受け取った生命保険金の取扱い」)。
4 平成22年7月26日裁決(東裁(諸)平22-22・非公表)(TAINZ F0-3-407)。
5 4に同じ。
6 「株式・公社債評価の実務(平成31年版)」(加藤千尋編・大蔵財務協会)264頁。この書籍では、課税時期を5月25日、直後期末を5月31日とする事例を掲げている。また、税務研究会WEB版資産税通信「課税時期が直後期末に近い場合の純資産価額の算定(税理士懇話会・資産税研究会事例より)」(09.11/2更新)(https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-05.html)では、課税時期を3月20日、直後期末を3月31日とする事例で、「評価会社の株式の評価に大きな影響を及ぼす取引等がなされていなければ直後期末の資産負債により純資産価額を求めても特に問題とされることはないと考えます」とされている。
この記事に関するご意見・お問合せは ta@lotus21.co.jp にお寄せください。
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
純資産価額方式を適用する場合における決算日
#235 梶野研二(税理士)
略歴 国税庁 課税部 資産評価企画官付企画専門官、同資産課税課課長補佐、東京地方裁判所 裁判所調査官、国税不服審判所本部 国税審判官、東京国税局 課税第一部資産評価官、玉川税務署長などを経て、平成25年6月 税理士登録。現在、相続税を中心に税理士業務を行っている。○主な著書 「ケース別 相続土地の評価減」、「非公開株式評価実務マニュアル」(新日本法規)、「判例・裁決にみる非公開株式評価の実務」(共著)(新日本法規)、「株式・公社債評価の実務」、「土地評価の実務」(共著)(大蔵財務協会)
今回のテーマ 財産評価基本通達は、取引相場のない株式の原則的評価方法として純資産価額方式と類似業種比準方式を定めている。このうち純資産価額方式は、課税時期における評価会社の総資産価額から総負債価額を控除し、さらに評価差額に対する法人税等相当額を控除し、算出された純資産価額を課税時期における発行済株式数で除して、1株当たりの株式の評価額を求める方法である。しかしながら、課税時期における資産及び負債を正確に把握することは困難な場合が多く、実務上は、ほとんどのケースにおいて直前期末の資産及び負債に基づいて評価額が算出されている。今回は、このような実務上の取扱いについて考えることとする。
マエストロの解説
1 純資産価額方式 相続税及び贈与税の課税上、相続や遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式の価額は、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)に定められた評価方法により評価されている。評価通達は、同族株主等が取得した株式については、原則として、純資産価額方式若しくは類似業種比準方式、またはこれらの評価方式の併用方式により評価することとされている(評基通179)。
このうち純資産価額方式とは、次の算式により求めた評価会社の株式1株当たりの純資産価額をもって当該会社の株式1株当たりの評価額とする評価方法である(評基通185)。
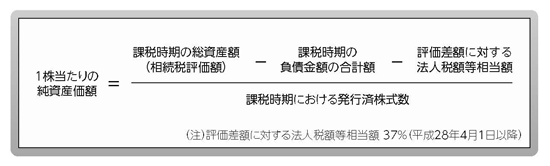
この純資産価額方式の適用に当たっては、次の点に注意する必要がある。
(1)「課税時期の総資産価額(相続税評価額)」の計算に当たっては、評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利(土地等)並びに家屋及びその附属設備又は構築物(家屋等)を有する場合には、それらの価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、これらの資産に係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、その帳簿価額に相当する金額によって評価することができるものとされている(評基通185かっこ書き)。
(2)評価会社が取引相場のない株式を保有する場合において当該株式を純資産価額方式で評価するときには、評価差額に対する法人税等相当額は控除しない(評基通186-3)。
(3)「評価差額に対する法人税等相当額」の計算に当たっては、評価会社の有する各資産の中に、現物出資若しくは合併により著しく低い価額で受け入れた資産又は株式交換若しくは株式移転により著しく低い価額で受け入れた株式(これらの資産又は株式を「現物出資等受入れ資産」という。)がある場合には、当該各資産の帳簿価額の合計額に、現物出資、合併、株式交換又は株式移転の時において当該現物出資等受入れ資産をこの通達に定めるところにより評価した価額から当該現物出資等受入れ資産の帳簿価額を控除した金額(これを「現物出資等受入れ差額」という。)を当該各資産の帳簿価額に加算することにより、当該現物出資受入差額に対応する法人税等相当額は控除しない(評基通186-2(2))。
(4)評価会社の株式を取得した者及びその同族関係者が有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下である場合には、上記により計算した1株当たりの純資産価額に100分の80を乗じて計算した価額により評価する(評基通185ただし書き)。
2 直前期末の資産負債による純資産価額の計算
(1)直前期末の資産負債による評価が認められる趣旨 純資産価額は、課税時期、すなわち相続、遺贈又は贈与により評価会社の株式を取得した時における評価会社の資産及び負債に基づいて評価することとされている。しかしながら、評価会社が事業活動を行っているならば、その資産及び負債の状況は日々変動している。課税時期という期中の特定の日における資産及び負債を特定し、それらを評価するためには、毎期行われる決算事務と同様に多額の費用と膨大な時間を要することとなる。課税時期における正確な純資産価額を算定するためには、課税時期における正確な資産及び負債を把握するための仮決算を行うこととなるが、すべての場合に多額の費用と膨大な時間を投じて仮決算を実施することは必ずしも現実的な評価方法とはいえない。
そこで、実務上は、評価会社が課税時期において仮決算を行っていないために課税時期における資産及び負債の金額が明確でない場合において、直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるときは、課税時期における各資産及び各負債の金額に代えて、直前期末の資産及び負債の課税時期の相続税評価額により1株当たりの純資産価額を計算する簡便的な方法によっても差し支えないこととされている(脚注1)。
(2)直前期末の資産負債による純資産価額の計算 直前期末の資産及び負債の課税時期の相続税評価額により1株当たりの純資産価額を計算する簡便的な方法の詳細及び留意すべき点は次のとおりである。
| ○直前期末の資産負債を基に純資産価額を計算する方法
1 評価明細書第5表の「相続税評価額」欄には、直前期末の資産及び負債の課税時期の相続税評価額を記載する。 2 評価明細書第5表の「帳簿価額」欄には、直前期末の資産及び負債の帳簿価額を記載する。 (注)1 上記1及び2の場合において、帳簿に負債としての記載がない場合であっても、次の金額は、負債として取り扱う。 (1)未納公租公課、未払利息等の金額 (2)直前期末日以前に賦課期日のあった固定資産税及び都市計画税の税額のうち、未払いとなっている金額 (3)直前期末日後から課税時期までに確定した剰余金の配当等の金額 (4)被相続人の死亡により、相続人その他の者に支給することが確定した退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与の金額(ただし、経過措置適用後の退職給与引当金の取崩しにより支給されるものは除く。) 2 被相続人の死亡により評価会社が生命保険金を取得する場合には、その生命保険金請求権(未収保険金)の金額を「資産の部」の「相続税評価額」欄及び「帳簿価額」欄のいずれにも記載する。 |
このように、課税時期に存しない資産負債を評価額の計算に含め、反対に課税時期に存する資産負債を評価額の計算に含めない取扱いは、相続税法第22条に定める「当該財産の取得の時における時価」の概念に反することとなるのではないかとの疑義が生じるが、直前期末の資産負債による簡便的な評価が認められている趣旨に照らせば、一種の割り切りと理解すべきであり、同条の許容するところであると考えられる。
なお、直前期末における資産負債の状況と課税時期における資産負債の状況が大きく異なり、評価額に与える影響が大きいと認められる場合には、直前期末における資産負債を基に評価することは相当ではなく、この場合には課税時期における資産負債を基に評価することとなる。
ロ 簿外資産の計上等 直前期末の資産負債に基づいて評価するということは、直前期の貸借対照表に記載されている資産負債のみを基に評価するということではない。自然発生借地権や営業権などのように評価の対象となる資産について、帳簿価額がないものであっても相続税評価額が算出される場合には、その評価額を評価明細書第5表の「相続税評価額」欄に記載することになる。なお、この場合、「帳簿価額」欄への記載は「0」となる。
また、借家権や営業権など評価の対象となる資産で帳簿価額のあるものであっても、その課税価格に算入すべき相続税評価額が算出されない場合(脚注2)には、「相続税評価額」欄への記載は「0」とし、その帳簿価額を「帳簿価額」欄に記載する。
なお、財産性のない創立費、新株発行費等の繰延資産、繰延税金資産などの評価の対象とならないものについては、「相続税評価額」欄及び「帳簿価額」欄のいずれにも記載しない。
ハ 各資産の評価時期 直前期末の資産負債を基に純資産価額を計算する簡便的な方法を採用した場合であっても、評価会社が直前期末に有する各資産については、課税時期における評価額を評価明細書第5表の「相続税評価額」欄に記載する。
例えば、課税時期が平成31年4月15日、直前期末が平成30年11月30日であるA社の株式の評価に当たり、同社が直前期末に保有していた土地は、直前期末の属する年である平成30年分の路線価又は評価倍率により評価するのではなく、課税時期の属する年である平成31年分(令和元年分)の路線価又は評価倍率により評価することになる(倍率方式における固定資産税評価額も平成31年度(令和元年度)の評価額による。)。また、直前期末に保有していた上場株式は、課税時期である平成31年4月15日の金融商品取引所の最終価格、課税時期の属する月である4月の最終価格の月中平均、その前月である3月の最終価格の月中平均及び前々月である2月の最終価格の月中平均のうち最も低い価額を採用することとなる。
ニ 課税時期前3年以内に取得した土地等又は家屋等 純資産価額方式においては、評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利(土地等)並びに家屋及びその附属設備又は構築物(家屋等)を有する場合には、それらの価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとされている。評価会社の保有する土地等又は家屋等が、課税時期前3年以内に取得又は新築された土地等又は家屋等であるかどうかの判定は、これらの資産の取得又は新築の日から直前期末までの期間で判定するのではなく、これらの資産の取得又は新築の日から課税時期までの期間で判定することとなる。例えば、課税時期が平成31年4月15日、直前期末が平成30年11月30日であるA社が平成28年2月に取得した土地を所有していた場合には、取得の日から直前期末までの期間は3年に満たないが、取得の日から課税時期までの期間は3年を超えるので、この土地等は課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する必要はなく、平成31年分(令和元年分)の路線価等により評価することとなる。
ホ 保険金請求権の計上 被相続人の死亡により評価会社が生命保険金を取得する場合には、その生命保険金請求権(未収保険金)の金額を評価明細書第5表の「資産の部」の「相続税評価額」欄及び「帳簿価額」欄のいずれにも記載する。この場合、その保険料が資産に計上されているときは、その金額を資産から除外する。また、保険差益に対する法人税等相当額は負債に計上するが、その生命保険金を原資として被相続人に係る死亡退職金を支払った場合には、その支払退職金の額を負債に計上するとともに、支払退職金を控除した後の保険差益について課されることとなる法人税額等を負債に計上する。課税時期における仮決算を行わず、直前期末の資産負債により純資産価額を計算する場合には、課税時期の属する事業年度の法人税額(期首から課税時期までの期間に対応する法人税額)を負債として控除することはできないが、被相続人の死亡により評価会社が取得する保険金請求権を資産に計上する場合には、このように当該保険金請求権に係る法人税額相当額(脚注3)の控除が認められている。当該保険金請求権に関係する部分についてのみ仮決算を行ったと同様に考えることができるからであると思われる。
ヘ 特定の評価会社の判定等 純資産価額方式の適用に当たり、直前期末の資産負債により純資産価額を求める簡便的な方法によった場合には、株式等保有特定会社及び土地保有特定会社の判定における「総資産価額」、「株式等の価額の合計額」及び「土地等の価額の合計額」についても、直前期末の資産により判定し、また、株式等保有特定会社のS2の計算時期についても同様に行うこととなる。
(3)直前期末の資産負債による純資産価額の計算が認められない場合 直前期末の資産負債による純資産価額の計算は、評価会社が課税時期において仮決算を行っていないために課税時期における資産及び負債の金額が明確でない場合であって、直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるときに限って認められることとされている。
イ 簡便的な方法の選択 直前期末の資産負債による純資産価額の計算は、評価会社が課税時期において仮決算を行っていないために課税時期における資産及び負債の金額が明確でない場合に認められる評価方法である。したがって、仮決算を行うことにより課税時期における資産及び負債の金額が明確になっている場合には、仮決算に基づく課税時期における資産及び負債の金額により純資産価額を計算しなければならない。記載方法通達の文言上は、課税時期の資産負債に基づいて計算した純資産価額と直前期末の資産負債に基づいて計算した純資産価額とを比較し、いずれか低い価額を選択することができるという扱いではないことに留意すべきである。また、課税時期における資産負債に基づいて算出した純資産価額により相続税又は贈与税の課税価格を計算して申告を行った場合に、直前期末の資産負債に基づいて算出した純資産価額により相続税又は贈与税の課税価格を計算して更正の請求や修正申告を行うことは認められない。
ロ 評価額の計算に影響が少ないと認められない場合 直前期末の資産負債による純資産価額の計算は、直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるときに認められる簡便的な評価方法である。この評価方法は、相続税法第22条の規定に照らせば、本来、課税時期における正確な資産及び負債を把握するための仮決算を行うことが好ましいが、すべての場合に多額の費用と膨大な時間を投じて仮決算を実施することを求めることは現実的ではないために、同条が許容する範囲内において認められている評価方法であると解される。直前期末後に「資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ない」と認められるかどうかについては個々のケースごとに増減額や増減割合その他の事情から個別に判定することとなる。この取扱いが記載方法通達に明記された一般的な取扱いであることに照らせば、直前期末から課税時期までの間において評価会社に相当程度の利益が出ているとしても、それが評価会社の通常の事業活動の結果生じたものであるならば、特殊な事例を除き、直前期末の資産負債による純資産価額の計算が否定されることはないと思われる。しかしながら、直前期末後に多額の固定資産の売買が行われた場合や合併その他の組織再編があった場合には、慎重な判断が必要である。評価会社が直前期末から課税時期までの間に、A社の出資23,995口を941,443,825円で取得しており、当該取得価額の純資産に占める割合が71%にも相当した事例において、評価会社はA社の出資を著しく低い価額の対価により譲り受け、これにより評価会社の資産の金額が著しく増加していると認められるとして、評価会社の直前期末の資産及び負債の金額を基礎として計算することは相当でなく、課税時期において仮決算をした資産及び負債の金額を基礎として評価するのが相当であるとされた裁決例は参考となるであろう(脚注4)。
(4)直前期末の資産負債による計算が認められない場合の純資産価額の計算 直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減があり評価会社の株式の評価額の計算に影響があると認められる場合には、課税時期の資産負債により純資産価額を計算しなければならない。しかしながら、課税時期における資産負債を特定するために仮決算を行うことは困難なケースが多いと考えられる。課税時期から長期間が経過した後、税務調査で問題点を指摘され課税時期の資産負債による評価を行うような場合には、一層の困難が想定されるところである。このような場合に、例えば、直前期末の資産及び負債のうち、特定の財産又は種類の資産又は負債についてのみ課税時期の状況に置き換えて評価額を算出することもやむを得ないであろう。例えば、平成22年7月26日裁決(脚注5)では、国税不服審判所は次のような認定を行っている。
| 平成17年4月30日(筆者注:課税時期前に行った仮決算日)から本件贈与時(同年5月9日)までの間に、評価会社の資産及び負債の金額について著しい増減はないと認められるから、出資1口当たりの純資産価額は、次に掲げる事項に基づいて、同年4月30日現在の価額を算定した。 A 評価会社が保有する山林・土地の価額は、同社作成の平成17年4月30日付貸借対照表の帳簿価額に、平成17年2月9日に取得した○○所在の土地19,582,035円が計上されていなかったため、これを加算し、1,284,238,228円となる。 B 評価会社が保有する有価証券のうち、○○○○の株式の相続税評価額は、課税時期の直前期末(平成16年12月31日)現在の帳簿価額等を基に、類似業種比準方式より別表のとおり算定した1株当たりの相続税評価額に保有株式数○○○○株を乗じた価額○○○○となる。 C 評価会社が保有する有価証券のうち、○○○○の出資の相続税評価額は、課税時期の直前期末(平成16年12月31日)現在の資産及び負債の金額(帳簿価額)に次の修正を加えた資産及び負債の金額を基に、評価基本通達189-3により別表とおり算定した1口当たりの相続税評価額74,288円に保有出資口数23,995口を乗じた価額1,782,540,560円となる。 (A)「現金預金」は、当審判所の調査の結果によれば、評価会社は、平成17年4月25日、同社が保有する○○○○の株式250,000株を1株当たり3,503円、総額875,750,000円で○○○○に対し譲渡していることから、直前期末の帳簿価額28,823,555円に875,750,000円を加算した価額904,573,555円となる。 (B)「有価証券」は、上記(A)と同じ理由により、直前期末の帳簿価額50,000,000円から、1株当たりの帳簿価額25円に譲渡株式数250,000株を乗じた6,250,000円を減算した価額43,750,000円となる。 (C)「未払法人税等」は、○○○○の株式250,000株の譲渡において発生した譲渡益869,500,000円(譲渡価額875,750,000円-譲渡原価6,250,000円)に対する法人税等相当額365,190,000円(譲渡益×42%)を、直前期末の帳簿価額2,925,300円に加算した価額368,115,300円となる。 (D)評価会社が保有する有価証券はすべて○○○○の株式であり、その相続税評価額は上記Bと同様に算定した1株当たりの相続税評価額に保有株式数○○○○株を乗じた価額○○○○となる。 (E)評価会社が保有する土地の相続税評価額は、別表のとおり46,219,977円となる。 (F)評価会社が保有する建物の相続税評価額は、別表のとおり54,751,980円となる。 D 評価会社が保有する有価証券のうち、上場株式の相続税評価額は評価基本通達169の定めにより算定した価額1,207,574,582円となる。 |
3 直後期末の資産負債による純資産価額の計算 直前期末の資産負債による純資産価額の計算が通達により認められている一方、直後期末の資産負債による純資産価額の計算も、事実上、一定の条件の基に認められている。
例えば、東京国税局課税第一部資産評価官の職員が執筆した書籍において、個人的見解としつつ「課税時期が直後期末に非常に近く、課税時期から直後期末までの間に資産及び負債の金額について著しく増減がないと認められる場合には、財産・債務について経理操作を行っているなどの課税上弊害がある場合を除き、直後期末の各資産及び負債の金額を課税時期における各資産及び負債の金額として計算しても差し支えないものと考えます。」とされている(脚注6)。
上記2の直前期末の資産負債による純資産価額の計算が、「直前期末の資産負債」を基に評価会社の株式を評価する方法であるのに対し、実務上認められているとされる直後期末の資産負債による純資産価額の計算は、あくまでも直後期末の資産負債を課税時期の資産負債として計算するものであり、直後期末の資産負債を課税時期の資産負債とみなすことができるほど両者に差異がないと認められる場合に限っての事実上の取扱いであることに留意する必要があろう。すなわち、課税時期において仮決算を行ったのと同様の結果が得られるときにのみこの取扱いが適用されると理解すべきであり、このような事実上許容されている取扱いは、上記2の(4)と同様の課税時期における資産負債を確定しようとする試みの一形態と捉えるべきであろう。
したがって、直前期末の資産負債と直後期末の資産負債とを比較して、後者の方が課税時期の資産負債の実態に近いとの理由だけで後者を選択をすることができると解することはできないと考える。
4 おわりに 直前期末の資産負債による純資産価額の計算は、実務上の要請から認められた簡便的な方法であり、時間とコストのかかる純資産価額方式の適用において、若干なりとも手順を省略できるこの方法は、実務上あたかも原則的な方法であるかのように採用されている評価方法である。しかし、課税時期を含む事業年度において事業が奮わず赤字決算が見込まれる場合や、多額の損失を被った場合など、課税時期における仮決算による資産負債により計算した純資産価額が、直前期末の資産負債による純資産価額を下回ることが容易に想像できるときには、多少の時間とコストを費やすこととなろうとも仮決算を実施すべきである。また、仮決算が困難であるとしても、合理的な方法によって課税時期における資産負債を推定することができるのであれば、そのような手法による評価も検討すべきであろう。
脚注
1 この取扱いは、法令解釈通達である平成2年12月27日付直評23・直資2-293「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」通達において、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の「第5表 1株当たりの純資産(相続税評価額)の計算明細書」の記載方法として定められている。本稿においては、この通達を「記載方法通達」という。
2 権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にある借家権は評価しないこととされている(評基通94ただし書き)。また、営業権の評価方法は、財産評価基本通達165以下に定められているところであるが、平均利益金額が5,000万円以下の場合には、営業権の評価額は算出されない(評基通166(2)(注)。)。
3 評価会社が仮決算を行っていないため、課税時期の直前期末における資産及び負債を基として1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を計算する場合における保険差益に対応する法人税額等は、この保険差益によって課税所得金額が算出される場合のその課税所得の37%相当額によることができる(国税庁ホームページホーム/法令等/質疑応答事例/財産評価/「評価会社が受け取った生命保険金の取扱い」)。
4 平成22年7月26日裁決(東裁(諸)平22-22・非公表)(TAINZ F0-3-407)。
5 4に同じ。
6 「株式・公社債評価の実務(平成31年版)」(加藤千尋編・大蔵財務協会)264頁。この書籍では、課税時期を5月25日、直後期末を5月31日とする事例を掲げている。また、税務研究会WEB版資産税通信「課税時期が直後期末に近い場合の純資産価額の算定(税理士懇話会・資産税研究会事例より)」(09.11/2更新)(https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-05.html)では、課税時期を3月20日、直後期末を3月31日とする事例で、「評価会社の株式の評価に大きな影響を及ぼす取引等がなされていなければ直後期末の資産負債により純資産価額を求めても特に問題とされることはないと考えます」とされている。
この記事に関するご意見・お問合せは ta@lotus21.co.jp にお寄せください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















