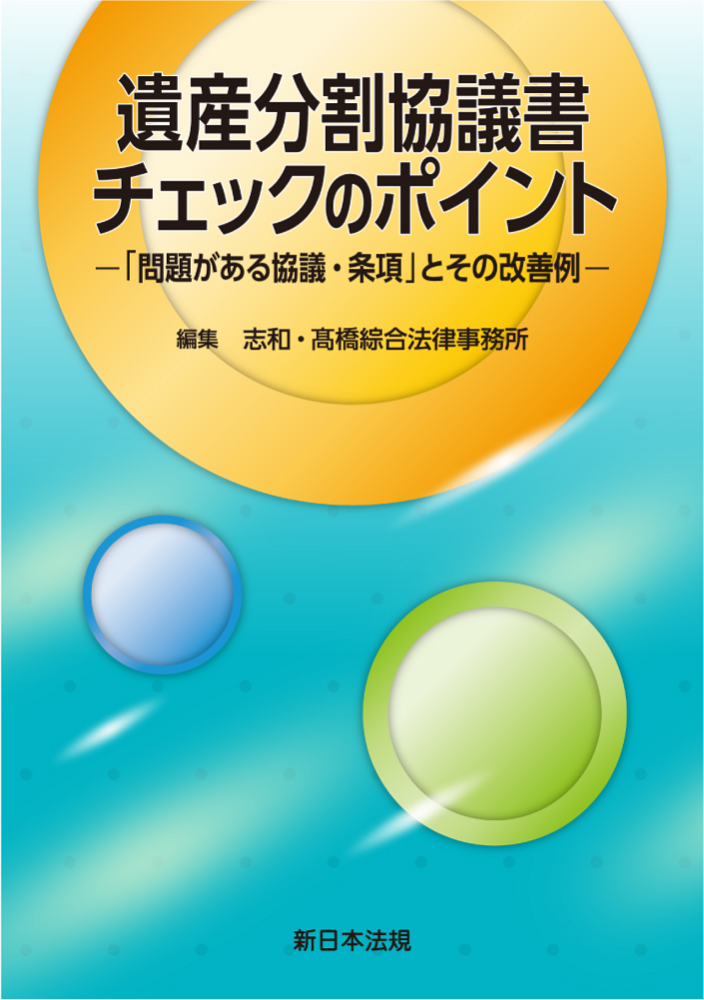解説記事2019年11月18日 特別解説 生物資産等の注記~IAS第41号「農業」~(2019年11月18日号・№811)
特別解説
生物資産等の注記~IAS第41号「農業」~
はじめに
これまで、我が国や米国においては農業活動や生物資産に関する会計基準がなかったため、IAS第41号「農業」は、我が国では最もなじみがない基準書のうちの一つではなかったかと思われる。そして、2018年3月期までは、IFRSを任意で適用し、連結財務諸表を作成・公表する日本企業(IFRS任意適用日本企業)のうちでも、住友商事や三菱商事といった大手総合商社が投資する海外の子会社(林業や魚の養殖事業)において、わずかに適用例が見られるのみであったが、2019年3月期から、家畜(生物資産)の生育や食肉の販売を「本業」とする日本ハムがIFRSを任意適用したことにより、IAS第41号の本格的な適用事例が我が国でも出てきた(日本ハムはこれまで、連結財務諸表について米国会計基準を適用してきた)。
本稿では、日本ハムが2019年3月期の有価証券報告書で行った農業会計や生物資産に関する開示を中心に、IFRS任意適用日本企業が行った開示を紹介することとしたい。
農業活動を規定する会計基準を設定する必要性
我が国では、一般的に、農業を手掛けている主体は「農家」や「農業協同組合(農協)」というイメージであり、企業に対して農業会計が適用されるということが、そもそもあまり想定されていないかもしれない。IAS第41号にも、次のような記載が見られる(B5項)。
「農業活動に従事している大部分の事業体は小規模で、独立した、現金及び税金だけに注意する家族事業であり、一般目的の財務諸表を作る必要はないと考えられていることが多い。このため、農業に関する国際会計基準は広く適用されないと考えている人もいる。しかし、小規模農業企業といえども、外部、特に銀行や政府機関からの資本及び補助金を求めており、これらの資金提供者の財務諸表に対する要求は高まっている。さらに、規制撤廃の国際的動向、国際上場数の増加及び投資額の増加は、農業活動の規模、範囲及び商業化の増大をもたらしている。これにより、信頼できる、一般に認められた会計原則に基づく財務諸表に対するより大きなニーズが生まれている。」
農業活動は、伝統的な物品の製造や役務の提供等とはかなり性質が異なるため、農業活動に対して取得原価と実現を基礎とした会計モデルを適用しようとすると、不確実性や矛盾を生じる可能性がある。特に、生物資産の実質を変える生物的変化(成長、変性、生産及び生殖)に関連する重要な事象を取り扱うために、IAS第41号は、生物資産を公正価値に基づいて評価することとしている。
IAS第41号「農業」とは
IAS第41号「農業」は、国際会計基準審議会(IASB)に衣替えする前の前身である国際会計基準委員会(IASC)が開発した最後の基準書であり、2001年2月に公表された。
この基準書は農業活動に関連する会計処理と開示を定めており、農業活動とは、「生物資産を販売するため、農産物にするため、又は追加的な生物資産を得るために、企業が生物資産の生物学的変化又は収穫を管理することをいう。」とされている。
また、IAS第41号は、生物資産(生きている動物または植物)、収穫時点における農産物及び政府補助金が農業活動に関連する場合の会計処理に適用されるとされており(第1項)、農産物として収穫するために栽培されている植物(例えば、材木として使用するために生育されている木)や動物、魚等がIAS第41号の適用対象となる。そして、生物資産は、売却費用控除後の公正価値で測定される。
なお、農業活動に関連する果実生成型植物(注)に対しては、従来はIAS第41号が適用されていたが、IAS第16号「有形固定資産」の適用範囲とするように2014年に修正された(ただし、果実生成型植物の上で生育する生産物は、生物資産である。)。
(注)果実生成型植物とは、生きている植物のうち次のすべてに該当するものをいう。
(a)農産物の生産又は供給に使用され、
(b)複数の期間にわたり生産物を生成すると見込まれ、
(c)付随的な廃品売却を除き、農産物として販売される可能性が低い。
IAS第41号が要求する開示事項
IAS第41号が要求する開示事項をまとめると、次のとおりである(第40項~第57項)。
・生物資産及び農産物の当初認識時に発生した利得又は損失の合計額、並びに生物資産の売却コスト控除後の公正価値の変動により発生した利得及び損失の合計額
・各生物資産グループについての説明
・各生物資産グループが関連する活動の性質
・次の物理的な数量に関する非財務的な測定値又は見積り
(i)当該企業の期末日現在の各生物資産グループ
(ii)期中の農産物の産出高
・所有権が制限されている生物資産について、その存在と帳簿価額、及び負債の担保として差し入れている生物資産の帳簿価額
・生物資産の開発又は取得に関するコミットメントの金額
・農業活動に関する金融リスク管理方針
・生物資産の帳簿価額の期首から期末への変動の調整表(売却費用控除後の公正価値の変動により発生した利得または損失、購入による増加、収穫による減少等)
・生物資産の公正価値が信頼性をもって測定できない場合の追加開示
・政府補助金に関する開示
日本ハムが行った生物資産に関する開示
日本ハムが2019年3月期(IFRSを任意適用して初めての事業年度)の有価証券報告書において行った開示は、次の通りであった。
(重要な会計方針)
生物資産について、公正価値が信頼性をもって測定できる場合は、当初認識時及び各期末において、売却コスト控除後の公正価値で測定しております。当該会計処理に伴う公正価値の変動額は、純損益として認識しております。一方、公正価値が信頼性をもって測定できない場合には、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定しております。
生物資産から収穫された農産物は、収穫時において公正価値から売却コストを控除した金額で棚卸資産に振り替えております。
(貸借対照表の注記(生物資産))
当社グループは、主に国内において牛、豚及び鶏の生産・飼育を行っており、海外においてはオーストラリアで牛の飼育を、トルコで鶏の生産・飼育を行っております。
流動資産に計上されている生物資産は、主に食肉生産のために肥育されている牛、豚、鶏といった家畜で構成されております。また、非流動資産に計上されている生物資産は、主に繁殖を目的として飼育される繁殖牛や種豚から構成されております。
当社グループが保有している生物資産の内訳は以下のとおりであります。
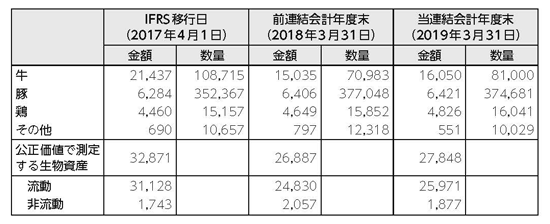
主に食肉生産のために肥育されている牛、豚、鶏といった家畜が流動資産に計上され、主に繁殖を目的として飼育される繁殖牛や種豚が非流動資産に計上される、という区分方法は大変興味深い。なお、熊本県畜産広場のホームページ((社)日本食肉協議会がデータを提供)によると、繁殖に供用出来る月齢が、鶏は6ヶ月齢、豚8ヶ月齢に対して、牛は15~16ヶ月齢と約2倍もかかっており、また、妊娠期間も、豚の114日に対して285日と2.5倍も長くなっているとのことであった。さらに、肉牛生産には豚や鶏の生産より出荷するまでの期間が長いため金利が多くかかるし、価格変動によるリスクも大きくなる、との説明もあった。そして、日本ハムにおける、前連結会計年度及び当連結会計年度における生物資産の生産量は以下のとおりである、とされている。
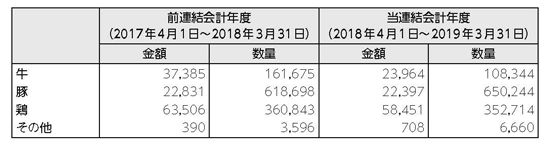
数量の単位は以下のとおりであります。
金額:百万円 牛:頭数 豚:頭数 鶏:トン
単純な計算ではあるが、2019年3月期の牛一頭の値段は221千円、豚一頭は34千円、鶏は1トン当たり166千円ということになる。
さらに、期中の生物資産の増減を金額単位で表したものが、次の表である。
生物資産の増加の要因としては、出産、購入及び飼育、減少としては売却と屠畜がある。そのほか、公正価値の変動による損益や、海外で家畜を飼育することに伴う為替換算差額も発生している。
前連結会計年度及び当連結会計年度における生物資産の増減は以下のとおりであります。
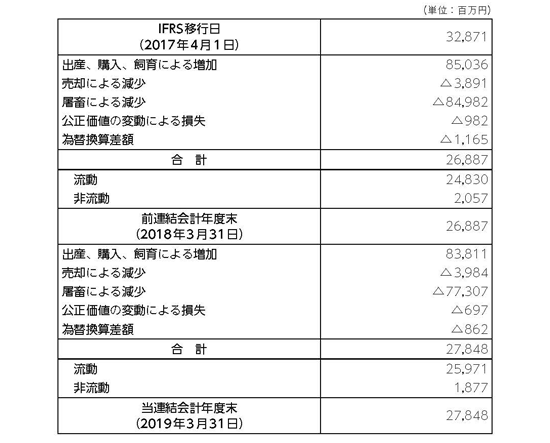
生物資産の公正価値の変動に伴う損益は、連結損益計算書の「売上原価」に含まれております。
生物資産の金額/数量ベースでの残高や増減の開示の後には、公正価値の測定方法に関する注記が続いている。
当社グループの生物資産である牛と豚については、同種の資産の売買価格をインプットとしたマーケット・アプローチを基にした評価モデルにより生物資産の公正価値を測定しており、観察不能なインプットを含むためレベル3に分類しております。また、鶏については、取得原価をインプットとしたコスト・アプローチを基にした評価モデルにより、生物資産の公正価値を測定しており、観察不能なインプットを含むため、レベル3に分類しております。
当社グループが行う生物資産の生産活動においては、生産及び飼育コストにより生じるキャッシュ・アウトから、第三者への販売から得られるキャッシュ・インまでの時間を要します。この財務リスクを管理するため、当社グループでは運転資本の適正な水準維持に努めております。
牛、豚等の家畜については、それぞれの市場で値段がついており、公正価値の測定にあたっては、マーケット・アプローチ(鶏については取得原価)を基にした評価モデルが利用されているが、やはり資産の性質上、上場株式等とは異なり、観察不能なインプットが含まれざるを得ないため、公正価値の階層はレベル3に分類されている。
その他のIFRS任意適用日本企業が行った生物資産に関する開示
次に、日本ハム以外のIFRS任意適用日本企業が行った、生物資産に関する開示を見てみたい。まず、大手総合商社である住友商事は、ニュージーランドで保有する山林資産に関する開示を次のように行った。なお、重要な会計方針(生物資産の会計処理方法)は、記述の内容が日本ハムのそれと大差がないため省略した。
① 住友商事が行った貸借対照表の開示
生物資産の増減は次のとおりであります。
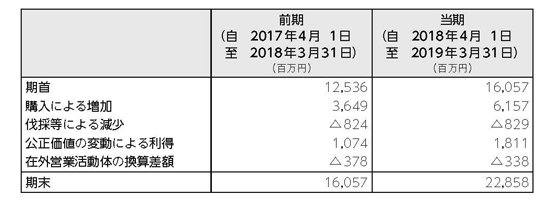
当社はニュージーランドにおいて、山林資産(主に松)を保有しております。売却費用控除後の公正価値にて当該資産を測定しております。なお、すべての生物資産はIFRS第13号「公正価値測定」におけるレベル3-観察不能な価格を含むインプットにて測定しております。
住友商事による生物資産の公正価値の測定に関する開示は、きわめてシンプルであった。
② 三菱商事が行った貸借対照表の開示
次に、三菱商事が行った貸借対照表の開示は次のとおりである。三菱商事は、ノルウェー、チリ及びカナダにおける連結子会社において、鮭鱒等の養殖事業を営んでいる。
生物資産の期末残高、及び期中の増減については、次のような開示を行っている。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における生物資産の内訳は以下のとおりです。
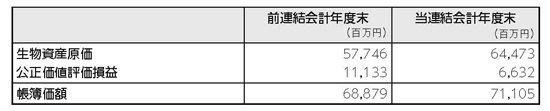
前連結会計年度及び当連結会計年度における生物資産の期中変動は、以下のとおりです。
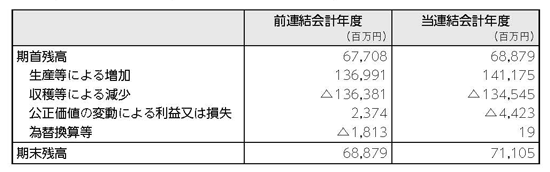
さらに、前連結会計年度及び当連結会計年度における鮭鱒養殖事業の生物資産の期中重量推移は次のとおりであるとしている。
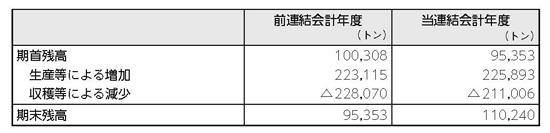
そして、生物資産の公正価値の測定方法については、次のような開示を行っている。
生物資産の公正価値の変動による利益または損失は、連結損益計算書の「その他の損益―純額」に含まれています。連結会社は、報告日時点の各国の市場における取引価格や生物資産の成長率・へい死率等のインプット情報に基づき、マーケット・アプローチにより、生物資産の公正価値を評価しています。生物資産の公正価値評価は、公正価値ヒエラルキーのレベル3に該当します。連結会社は、生物資産の生産活動において需給バランスの影響による商品の相場変動リスクにさらされており、商品相場変動リスクを軽減する目的から、必要に応じて公設市場を通じて商品先物契約を締結しています。
終わりに
2000年前後の世紀の変わり目は、会計基準の世界においても、大きな転換点であった。本稿の冒頭にも記載したように、この時期に国際会計基準委員会(IASC)は国際会計基準審議会(IASB)に改組され、国際会計基準(IAS)は、国際財務報告基準(IFRS)に衣替えされた。本稿で取り上げたIAS第41号は、最後に作られた国際会計基準(IAS)である。
そして、これらの変革と時を同じくして、「誰も利用者がいない、机上の会計基準であったIAS」は、「グローバル・スタンダードとしてのIFRS」への道を歩んでいくことになる。
金融商品の公正価値評価が本格的に始まったばかりであった今世紀の初頭において、一般的に金融商品よりも公正価値インプットの入手や測定が難しい生物資産について、(一部の例外を除いて)取得原価による評価を認めずに公正価値による評価(かつ、評価損益は期間損益として計上)で一本化するためには、相当な困難や紆余曲折があったことは想像に難くない。IAS第41号とほぼ同時に公表されたIAS第40号「投資不動産」では、公正価値モデルで一本化しようとしたものの果たせず、原価モデル(公正価値は注記)と併存する形で落ち着いたことを考えてもそれは明らかであり、IAS第41号が、当時いかに革新的な会計基準書であったかが伺える。
今回検討の対象とした生物資産を計上しているIFRS任意適用日本企業のうち、日本ハムは牛、豚、鶏等の家畜(動物)、住友商事は山林資源(木材)、三菱商事は魚類と、扱っている項目が分かれたため、本稿では様々な種類の生物資産に関する開示や公正価値の測定方法等を紹介することができた。IAS第41号を適用して生物資産を計上するIFRS任意適用日本企業の数は限られ、収益認識やリース、金融商品会計のように、農業会計が我が国の会計基準として取り入れられるようなことは現状では考えづらいが、今後もユニークかつ充実した開示例が我が国においても出てくることを期待したい。
参考文献
週刊経営財務 No.3414 「生物資産の会計処理と評価」税務研究会
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.