解説記事2021年06月28日 税務マエストロ 令和3年度消費税改正(課税売上割合に準ずる割合)(2021年6月28日号・№888)
税務マエストロ
令和3年度消費税改正(課税売上割合に準ずる割合)
税理士 熊王征秀
マエストロの解説
令和3年度の消費税改正は、昨年度のような大きな改正はなく、全体的に小粒な内容となっている。改正内容については次頁の表を参照されるとして、本稿では、これらの改正内容のうち、比較的実務への影響が大きいと思われる「課税売上割合に準ずる割合の承認申請手続き」について、制度の概要を確認すると共に、実務での活用方法(たまたま土地の譲渡があった場合の承認申請手続き)を紹介する。
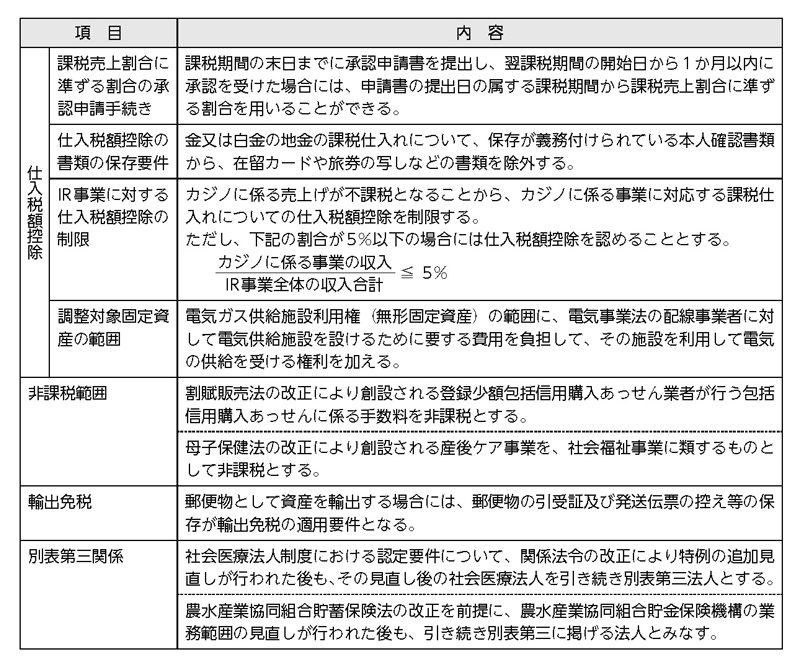
1 概要と承認申請手続
個別対応方式で仕入れに係る消費税額を計算する際に、共通対応分の税額を計算する場合には、税務署長の承認を受けることにより、課税売上割合以外の合理的な割合(課税売上割合に準ずる割合)を採用することが認められている(消法30③)。
(消基通11−5−7)
課税売上割合に準ずる割合とは、使用人の数又は従事日数の割合、消費又は使用する資産の価額、使用数量、使用面積の割合その他課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものの性質に応ずる合理的な基準により算出した割合をいう。
具体的には、「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し、翌課税期間の開始日から1か月以内に承認が下りた場合には、その申請日の属する課税期間から承認を受けた割合を適用することができる(改消令47⑥)。
なお、課税売上割合に準ずる割合は、個別対応方式により共通対応分の税額を計算する場合に適用するものであるから、たとえ承認申請を受けていたとしても、一括比例配分方式により仕入税額を計算する場合には、課税売上割合しか使えないことに注意する必要がある。
この課税売上割合に準ずる割合は、事業の種類の異なるごと、費用の種類の異なるごと、事業場の単位ごとにバラバラに適用することができる。また、本来の課税売上割合の計算方法を課税売上割合に準ずる割合として申請することにより、事実上、課税売上割合との併用も認められている(消基通11−5−8)。
この課税売上割合に準ずる割合の適用承認を受けている事業者は実際には少ないようであるが、消費税法基本通達11−2−19(共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合)と同様に、節税対策として今後活用していくべき規定であると思われる。
なお、いったん承認を受けた課税売上割合に準ずる割合の適用をやめる場合には、「課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書」を提出すれば、その提出日の属する課税期間から原則的な計算によることができる。
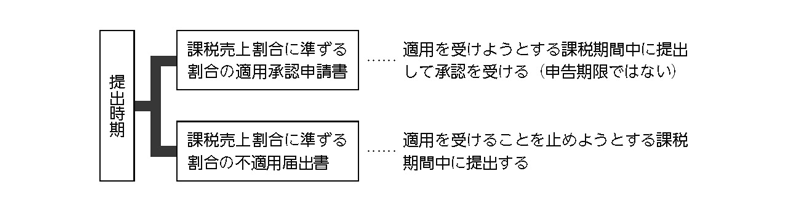
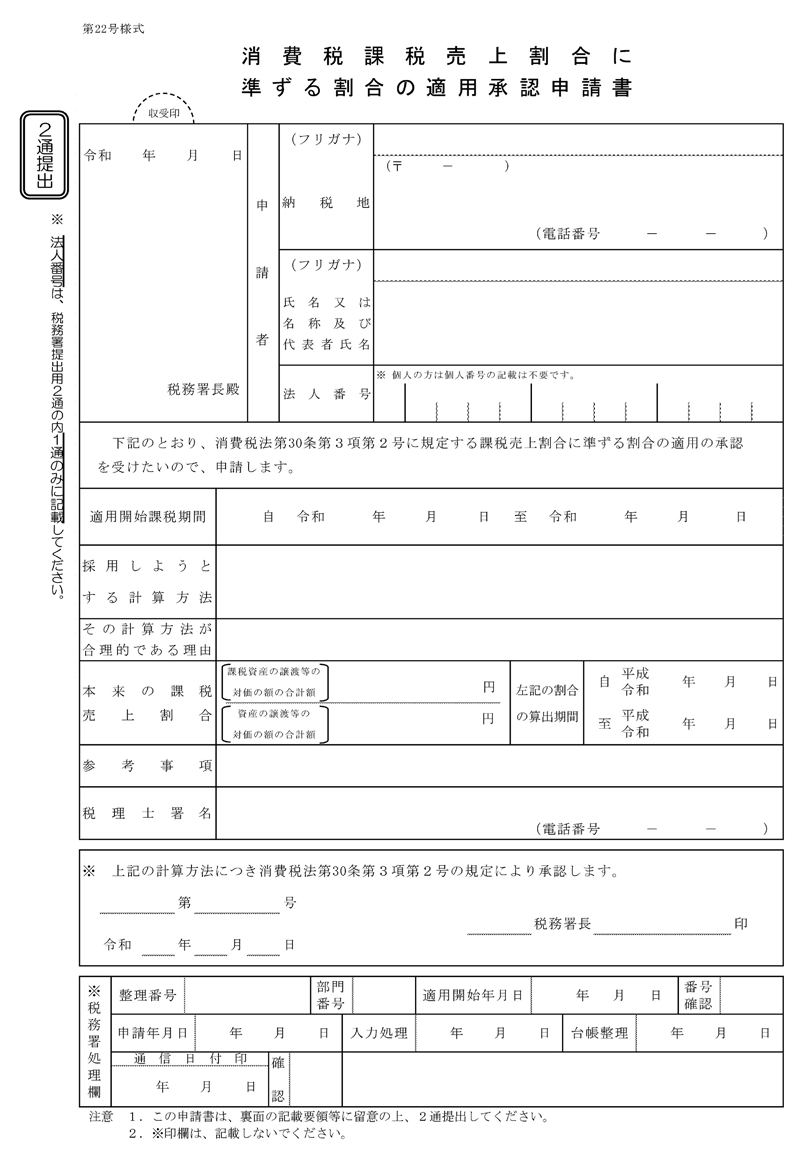
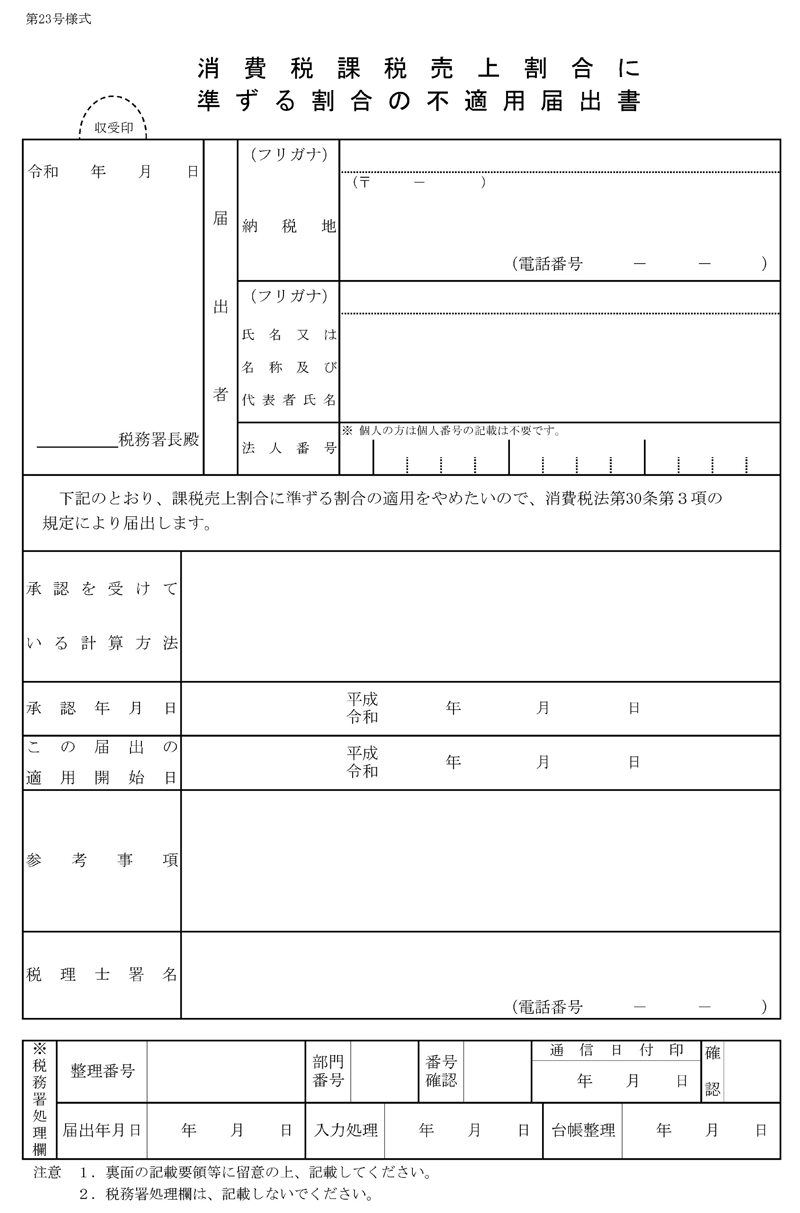
税務署長は、承認した割合を不適当とする特別の事情が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる(消令47③)。
承認取消の処分があった場合には、その処分があった日の属する課税期間以後については、その承認に係る課税売上割合に準ずる割合を用いることはできない(消令47⑤)。
(注)課税売上割合に準ずる割合の承認申請については、一定の日までに承認又は却下の処分がなかった場合における「みなし承認制度」は採用されていない。
物品販売業と不動産賃貸業(賃貸物件はすべて居住用の貸室である)を営んでいる事業者について考えてみたい(円単位:省略表示)。
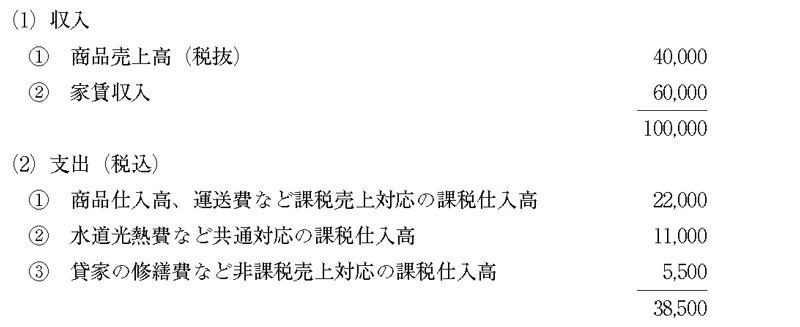
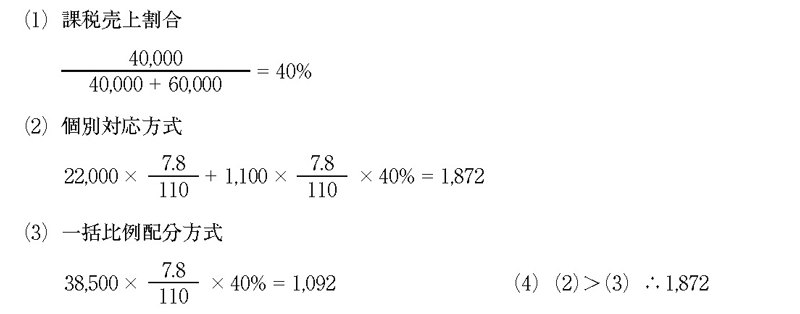
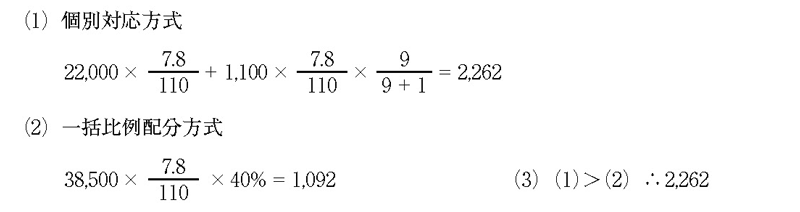
2 たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の活用方法
不動産業や医療業、金融業などの場合には、主たる売上げに非課税のものがあるので課税売上割合は常に95%未満となり、課税仕入れ等の税額について、個別対応方式か一括比例配分方式によるあん分計算が必要となる。
しかし、課税資産の販売業などの場合には、受取利息、社宅使用料収入、有価証券売却収入などの非課税売上げがあったとしても一般的にその額は僅少であり、結果、課税仕入れ等の税額のほぼ全額が控除対象となるケースがほとんどである。
このような事業者が、たまたま土地を売却したことにより課税売上割合が95%未満となったような場合には、たまたま土地を売却したことにより、共通対応分の課税仕入れ等の税額について大幅に仕入税額控除が制限されてしまい、事業の実態を反映しないこととなってしまう。
個別対応方式を適用する場合、課税仕入れ等の税額は
① 課税売上対応分
② 共通対応分
③ 非課税売上対応分
のいずれかに区分することになるわけであるが、この場合、②の共通対応分とは、言葉のとおり課税売上げと非課税売上げのどちらにも関係している課税仕入れのほか、売上げと明確な対応関係のないもの、たとえば贈与、寄付などをした課税資産の仕入れなどもこれに該当することになる。
課税資産の販売業であっても、福利厚生費や事務用品費、水道光熱費などの販売管理費は課税売上げと明確な対応関係はなく、言い換えれば受取利息などの非課税売上げにも多少なりとも関係している。つまり、課税仕入れの用途区分をする場合には、これらの費用は、共通対応分に区分されることになるわけである。
共通対応分に区分された場合、当然のことながら課税売上割合を乗じた分だけしか税額控除はできないことになり、たまたま土地の譲渡などがあった場合には、土地の売上げにまったく関係していない費用についてまで、結果として税額控除がカットされることになってしまう。そこで、たまたま土地の譲渡があったことにより課税売上割合が95%未満となるような場合には、課税売上割合に準ずる割合の承認申請をすることにより、合理的な割合により共通対応分の消費税額を計算することが認められている。
(注)有価証券を譲渡した場合には、譲渡対価の全額ではなく、5%だけを非課税売上高に計上すればよいこととされている(消令48⑤)。
こういった理由から、有価証券の譲渡については、「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認」と同様の方法で承認を受けることはできない(仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A【基本的な考え方編】(問31)の(答)の3)。
□要件
次の①〜③の要件をすべて満たす場合に限り、承認申請が認められている。
① 土地の譲渡が単発のものであること
② その土地の譲渡がなかったとした場合に、事業者の営業の実態に変動がないと認められること
③ 過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内であること
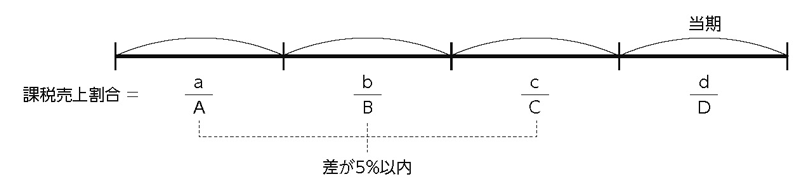
□計算方法
次の①または②の割合のうち、いずれか低い割合により課税売上割合に準ずる割合の承認を受け、仕入れにかかる消費税額の計算を行うことができる。
① 土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合
② 土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
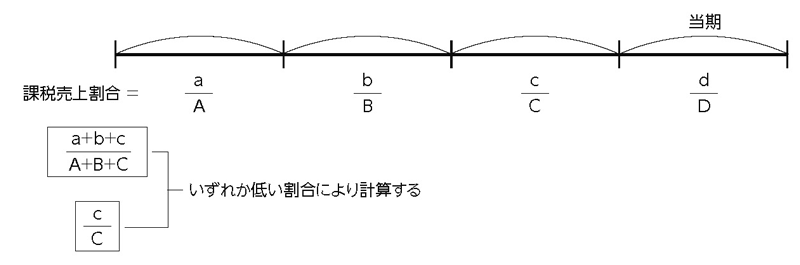
土地の譲渡がたまたま(偶発的に)発生したものでない場合には、この方法により承認を受けることは認められない。ただし、事業計画の変更などに伴い、土地を断続的に売却処分している場合などは、課税売上割合をそのまま適用すると、本来業務における事業内容等の実態が仕入控除税額の計算に反映されないこととなってしまう。このような場合には、土地を整理売却する事業と本来の事業を部門別に区分して管理することにより、それぞれの部門ごとの課税売上割合を課税売上割合に準ずる割合として申請することを検討すべきである(仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A【基本的な考え方編】(問31))。
A社は電化製品の販売業を営んでいるが、当課税期間中に土地を売却したことにより、課税売上割合が95%未満になることが予想された。そこで、次の①または②の割合のいずれか低い割合により課税売上割合に準ずる割合の承認を受け、仕入税額を計算することとしている(円単位:省略表示)。
① 当課税期間前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合
② 前課税期間の課税売上割合
[営業状況]
(1)当期の売上高(収入)の内訳は次のとおりである。
① 課税売上高(税抜) 500,000
② 非課税売上高 500,000
(2)当期の課税仕入高の内訳は次のとおりである。
① 課税売上対応分 330,000
② 共通対応分 110,000
③ 非課税売上対応分 22,000
(3)前期以前の売上高は次のとおりである。

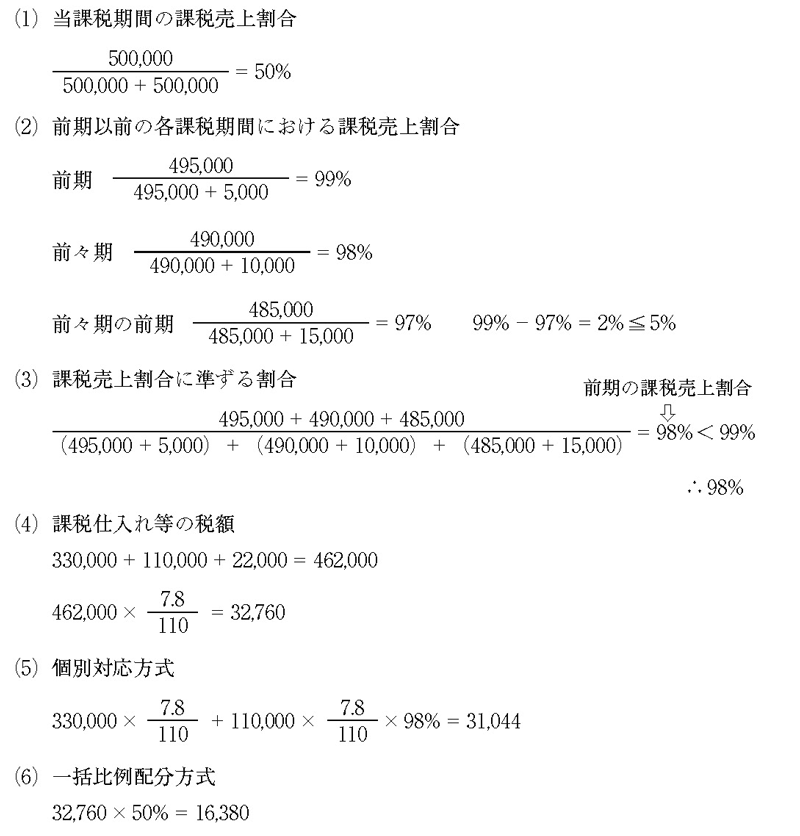
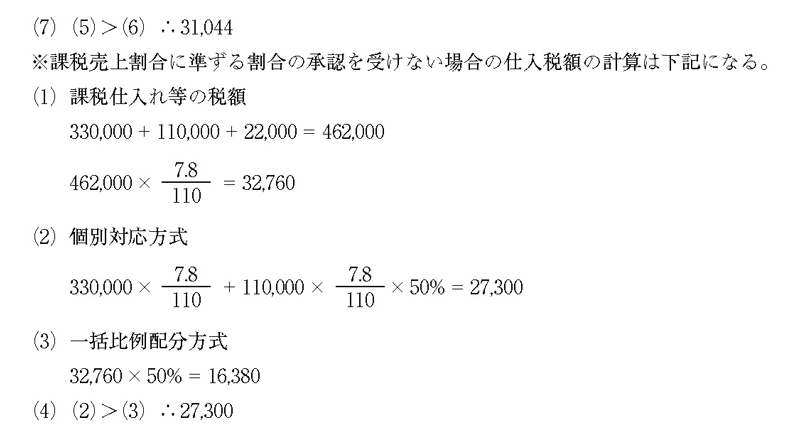
3 令和3年度改正
課税売上割合に準ずる割合は、「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受けることによって、その承認を受けた日の属する課税期間から採用することができる(消法30③)。
そうすると、課税期間の末日間際にたまたま土地を売却し、課税売上割合に準ずる割合を適用する必要が生じたような場合には、「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出したとしても、その提出日の属する課税期間の末日までに税務署長の承認が受けられないケースが想定される。
そこで、課税売上割合に準ずる割合により仕入控除税額を計算しようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日以後1か月を経過する日までに税務署長の承認が下りた場合には、その承認申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割合に準ずる割合を採用することができることとなった(消令47⑥)。
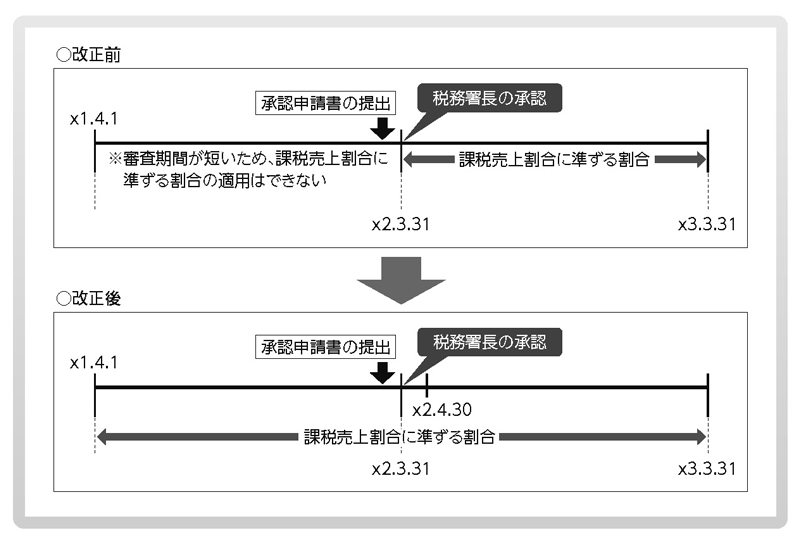
この改正は、令和3年4月1日から施行することとされている(令和3年改正法施行令附則)が、附則の規定だけでは、令和3年4月1日以後に承認申請をした場合に適用できるのか、令和3年4月1日以後に承認された場合に適用できるのかを読み取ることができない。
令和3年4月1日以後に承認された場合に適用できるとした場合には、令和3年3月決算法人が決算日までに承認申請をし、令和3年4月30日までに承認された場合には、令和3年3月決算期から課税売上割合に準ずる割合が適用できることになるのであるが……。
そこで、令和3年4月に国税庁が公表したパンフレットには、適用開始時期について、『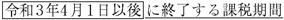 から適用されます』という説明がされたものと思われる(下記「消費税法改正のお知らせ」(抜粋)を参照)。
から適用されます』という説明がされたものと思われる(下記「消費税法改正のお知らせ」(抜粋)を参照)。
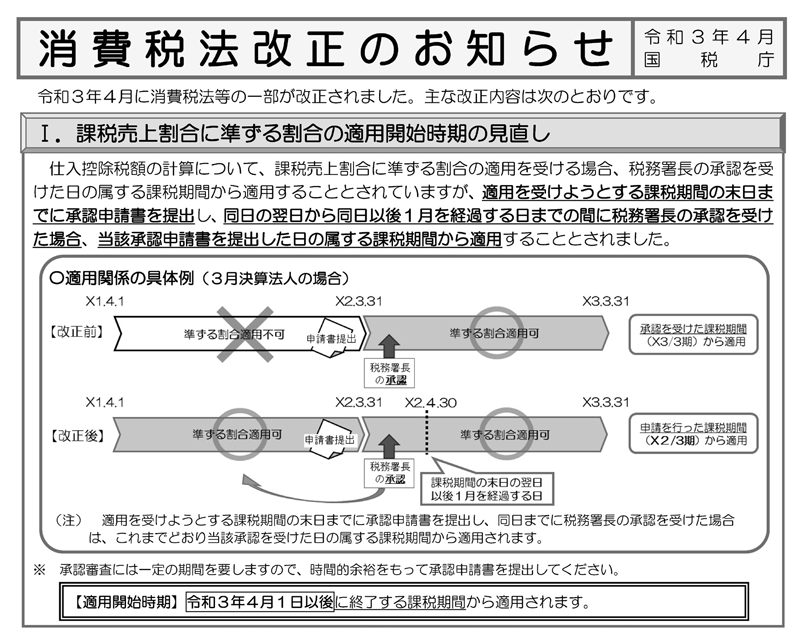
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















