解説記事2022年03月28日 ニュース特集 詳報 キャプティブへのCFC税制適用事案(2022年3月28日号・№924)
ニュース特集
日産自動車ら納税者の敗訴相次ぐ
詳報 キャプティブへのCFC税制適用事案
キャプティブ保険会社を巡っては、平成31年度のタックスヘイブン対策税制(CFC税制)の見直しで一定のキャプティブ保険会社が事実上のキャッシュ・ボックスとして会社単位の合算課税の対象とされるなど、税務当局の目が厳しくなっているが、今年に入り東京地裁でも、キャプティブ保険子会社へのCFC税制の適用を巡り争われていた2件の事案について、処分の取消しを求めた納税者の請求が棄却されている。
そのうちの1件の日産自動車事件(令和4年1月20日判決言渡し、春名茂裁判長)については既に速報したところだが(本誌919号)、本特集では、もう1件の事案(令和4年3月10日判決言渡し、清水知恵子裁判長)とともに、本誌取材で判明した判決の詳細をお伝えする。
両事案の争点は全く異なるものの、いずれにおいても国側の主張が全面的に認められ、納税者にとっては厳しい結果となった。平成31年改正前の事案ではあるが、キャプティブ保険会社への課税強化を図る税務当局にとっては追い風となりそうだ。
大規模災害やコロナ禍、リスクの多様化で高まる海外損保のニーズ
まず、キャプティブの仕組みについておさらいしておこう。
一般的にキャプティブ(captive)とは、「自社及び自社グループのリスクを専門的に引き受けるための保険子会社」を指す。
通常、日本企業の多くは、様々なリスクをヘッジするため国内の損害保険会社と保険契約(元受保険契約)を締結し、当該損害保険会社も自社のリスクを回避するため、他の保険会社との間で、保険契約の責任の一部または全部を引き受けてもらう「再保険」契約を締結している。
昨今、日本の保険会社の保険料が高額であることに加え、大規模災害やコロナ禍など、リスクの増大化、多様化により、日本の保険会社ではリスクをカバーすることができない事象が増えてきたため、日本企業の間では、海外の損害保険市場から低コストで高額かつ広範な補償を確保したいというニーズが高まっている。しかし日本企業は、保険業法186条により、日本に支店等を設けていない海外保険会社と直接契約をすることができない。この問題をクリアするため、海外に子会社(キャプティブ保険会社)を設立し、国内損保会社から(日本国内に本店を持つ)キャプティブ保険会社に再保険をかけ、キャプティブ保険会社が海外の保険会社に再び再保険をかける(再々保険)という仕組みがとられている(図1参照)。
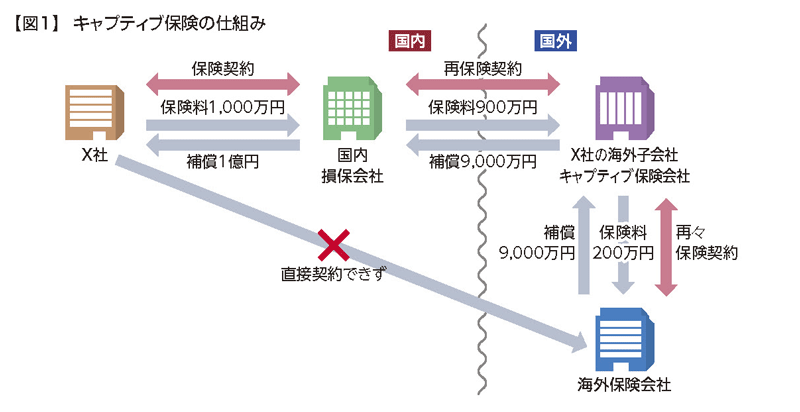
以前は、設立費用がかかる上に維持費も莫大だったため、大企業しかキャプティブを利用することができなかったが、現在では中小企業であっても低コストでキャプティブを利用できるようになっている。
また、このキャプティブの仕組みを利用することにより、国内保険会社に支払った保険料の一部を再保険料としてグループ内に再び取り込むことができ、さらに、タックスヘイブンにキャプティブ保険会社を設立すれば、キャプティブ保険会社が国外損保会社に支払う安い再々保険料との差額について税負担を抑えることができるという大きな節税メリットが生じる。
このような状況を問題視した税務当局は、いくつかのキャプティブにCFC税制を適用して課税処分を行うとともに、平成31年度税制改正で、一定のキャプティブ保険会社について、特に租税回避リスクが高い事実上のキャッシュ・ボックスとして、会社単位の合算課税の対象とするなど課税強化の動きを見せてきた。
具体的には、次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係会社が対象とされている。
・外国関係会社の各事業年度の非関連者等収入保険料の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として計算した割合が10%未満であること(措法66の6②二ハ(1))
・外国関係会社の各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として計算した割合が50%未満であること(措法66の6②二ハ(2))
地裁、「保険の目的」は関連者の債権であり、非関連者基準を満たさず
今回納税者敗訴となった2つの事案のうち最初に紹介するのは、日産自動車の子会社で保険業を営むバミューダ法人(NGRE社)が、CFC税制の適用除外基準である非関連者基準を満たすかどうかが争われた事案である(事案の概要は図2参照)。具体的には、NGRE社が非関連者(AVM社)との間で締結した再保険契約の対象となった元受保険契約に係る保険が、「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係るもの」(現行の措令39条の114の2第13項一号括弧書(本件括弧書))に規定する保険に該当するか否かが争点となった。
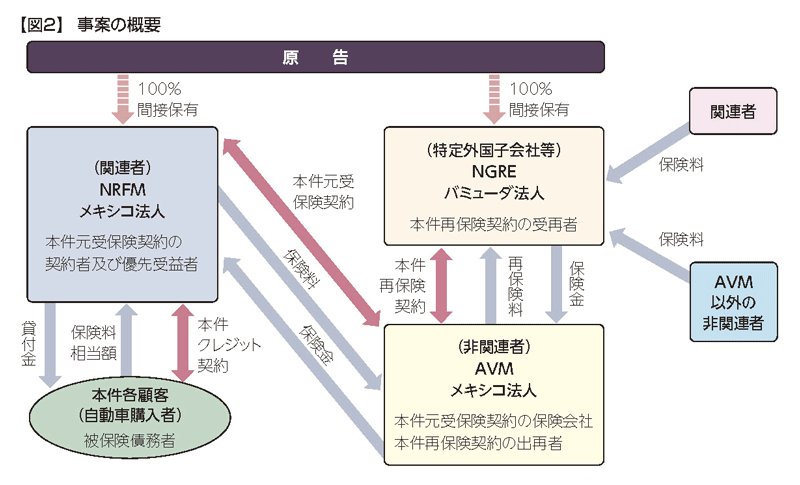
原告の関連者であるNRFM社は、自動車を購入する顧客との間で、その購入資金を貸し付ける旨の契約(本件クレジット契約)を締結したが、本件クレジット契約において、顧客は所定の条件を満たす生命保険等への加入を義務付けられていた(日本で住宅を購入する際に加入が求められる団信のようなもの)。顧客は、他の保険に加入しない場合は、NRFM社がAVM社(非関連者)との間で締結した元受保険(本件元受保険)に加入することとなっており、さらに、AVM社は、本件元受保険契約上引き受ける全保険リスクの70%をNGRE社に出再する内容の再保険契約をNGRE社との間で締結した。
国は、本件元受保険は、関連者であるNRFM社が各顧客(本件各顧客)に対して有する債権を保険の目的とする保険であるから、本件括弧書に規定する保険には該当せず非関連者基準を満たさないと主張。これに対し日産自動車側は、本件元受保険契約における保険事故事由や免責事由の定め等を根拠に、本件元受保険契約は、本件各顧客の生活を維持する能力や所得を稼得する能力の喪失という保険危険を担保するものであって、その「保険の目的」は本件各顧客の生命や身体等であるから、本件括弧書に規定する保険に該当すると主張した。つまり、本事案の争点の核心は、本件元受保険の「保険の目的」は、関連者が有する債権であるのか、非関連者である本件各顧客の生命や身体等なのかにある。
この点につき東京地裁は、本件括弧書きにいう「保険の目的」とは、「保険事故が生じた際に保険契約に基づき保険金の支払を受けることにより保障、填補を得ようとする対象のことをいうもの」との解釈を示し、「保険契約により保障、填補を受けようとする対象は、当該保険契約における保険事故や免責事由の定めのみではなく、個々の保険契約の内容や取引の実態等を踏まえて実質的に判断するのが相当である。」との考えを示した。
その上で、本件の事実関係を検討し、「本件クレジット契約を締結した本件各顧客は、NRFMが優先受益者として保険給付を受けるという内容を含む保険契約の締結を事実上義務付けられ、本件各顧客の死亡等の保険事故が生じた場合に、優先受益者であるNRFMに対し、『死亡』、『失業』、『恒久的な障害』及び『一時的な全身の障害』のいずれの事由であっても、本件クレジット債権の未償還残高又は月額賦払金6か月分を限度として保険給付がされ、本件各顧客が同保険給付を自己の財産として自由に利用することは予定されておらず、本件元受保険契約の成立及び消滅は本件クレジット債権に付従することとされていることなどの事情を踏まえると、本件元受保険契約は、NRFMが優先受益者として受領する保険給付を本件クレジット債権の弁済に充てることによって、本件クレジット債権が回収不能となることに伴いNRFMに生じる経済的不利益を填補することをその内容とするものであると解される。」と指摘、「そうすると、本件元受保険契約に基づき保険金の支払を受けることにより保障、填補を得ようとする対象は、NRFMが有する本件クレジット債権である」として、「本件元受保険契約は、NRFMの有する資産を「保険の目的」とする保険に該当する」と結論づけた。
そして、原告の主張については、「『死亡』や『失業』等の保険事故の事由により生じた能力の喪失の期間、程度に応じて保険給付の額を定めているものではなく、上記保険給付の上限額の内容も本件各顧客の『死亡』という保険事故に対応した内容とは評価できないこと、本件クレジット債権が完済された場合には本件元受保険契約が終了するとされていることなどの諸点は、本件元受保険契約が本件各顧客の生命や身体等について生じた損害を填補するものと解することとは相容れない」「本件元受保険契約においては、本件各顧客の死亡等が保険事故事由とされているが、これは、本件各顧客の死亡等が、債務者である本件各顧客の支払能力に影響し、本件クレジット債権の回収不能リスクを高める事情であるからである。」などと指摘し、すべて排斥した。
米国で「課税されない所得」は租税負担割合の計算上「分母」に算入
次に紹介する事案は、ハワイで設立された原告のキャプティブ保険子会社がCFC税制の適用対象となる租税負担割合20%以下要件を満たすかどうかが争われた事案である。事案の概要及び租税負担割合の計算式については、図3のとおり。
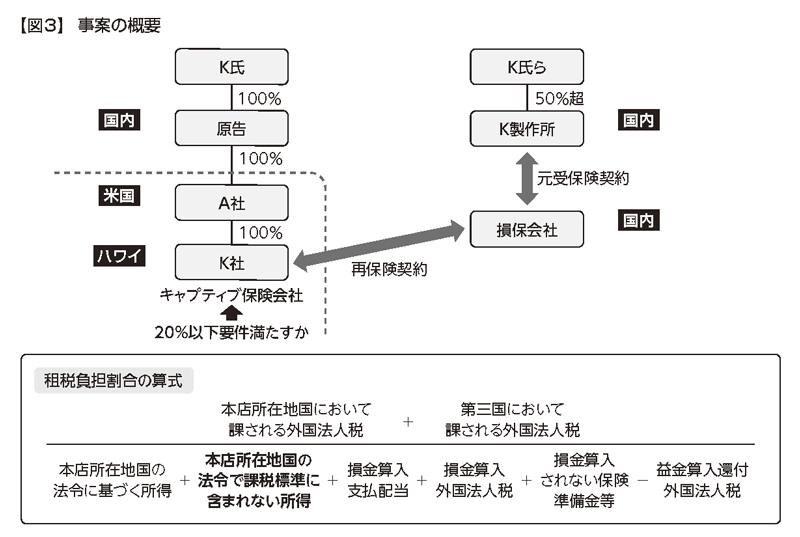
米国歳入法によれば、保険料収入が120万米ドルを超えない場合であって、保険会社が同法831条(b)項に定める小規模保険会社課税の適用を選択するときは、課税投資所得に対して税が課されることとなるが、保険料収入はこの課税投資所得には含まれない。つまり、この場合、保険料収入については課税を受けない特別な措置が設けられているということだ。本件では、この措置により課税されなかったK社の保険料収入が、租税負担割合の計算式の分母に加算する「その本店所在地国の法令の規定により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(課税標準外所得金額)」(現行の措令39条の17の2第2項一号イ(1))に当たるか否かが争われた。分母に含まれれば、租税負担割合は20%以下となり、CFC税制が適用されることになる。
東京地裁は、この分母の計算式の仕組みについて、「外国法令による所得金額に課税標準外所得金額を含む一定の金額を加減算することとしているのは、外国子会社合算税制を定めた趣旨に鑑み、本店所在地国と本邦における税負担の比較をするための基礎となる外国関係会社の所得の金額(すなわち分母)を、本店所在地国において我が国と同様の法制度が採用されていたならば加えられ(除かれ)たであろう金額を加(減)算することによって、上記の比較がより実態に即した適切なものとなるように図ったものと解される。」との考えを示した。そして、「『課税標準外所得金額』には、本店所在地国の法令により非課税とされる所得が生じた場合だけでなく、課税の対象となる所得の金額の計算上、本店所在地国の法令による特別な措置として、決算に基づく所得の金額から控除される結果、その控除された部分に対する課税がされないこととなる場合も含まれると解するのが相当である。」との解釈を示し、K社について「保険料収入が120万米ドルを下回り、かつ、米国歳入法831条(b)項に定める小規模保険会社課税の適用を選択したために、同項が適用されている」として、本件保険料収入は「課税標準外所得金額」に算入されるとの判断を示している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















