解説記事2020年01月06日 時価評価課税・欠損金の取扱い&グループ調整計算(2020年1月6日号・№817)
ニュース特集
詳報・グループ通算制度第一弾
時価評価課税・欠損金の取扱い&グループ調整計算
既報の通り、令和2年度税制改正では連結納税制度制度が大幅に見直され、令和4年度から「グループ通算制度」へと移行する。
平成30年10月23日に開催された政府税調で「連結納税制度に関する専門家会合」(以下、専門家会合)の設置が了承されて以来、令和2年度税制改正に向け急ピッチで議論が進んできた連結納税制度の見直しだが、調整が難航したのが、開始・加入時の時価評価課税・欠損金の切り捨てとグループ調整計算の取り扱いだ。
本特集では、グループ通算制度に関する解説の第一弾として、今回の改正の二大論点と言える開始・加入時の時価評価課税・欠損金の切り捨てとグループ調整計算をとり上げる。
理解が困難な「開始・加入時の時価評価課税・欠損金の切り捨て」については、適用の有無等が一目で分かるフローチャート(805号10頁に掲載したものを、令和2年度税制改正大綱に沿ってアップデートしたもの)を掲載しているので参考にされたい。
時価評価課税・欠損金
現金買収による完全子会社、親法人の開始・加入前欠損金の持ち込みも
現行の連結納税制度では、個別の連結法人で修正・更正が生じた場合に他の連結法人で計算のやり直しが生じ、地方税も含め、多大な事務負担が生じていた。
こうした現状を踏まえ、新たな連結納税制度(以下、適宜「グループ通算制度」という)では、仕組みの簡素化という観点から「個別申告方式」を採用するという制度の基軸は早々に固まったもの、その後、調整が難航した改正項目の1つが、連結納税制度開始あるいは連結納税グループ加入時(以下、開始・加入時)の時価評価課税・欠損金の切り捨ての取り扱いだ。
特に「現金買収による完全子会社化⇒連結納税グループ加入」という局面における取り扱いは、連結納税制度の参入障壁の1つという観点からも問題となっていたが、今回の改正では、組織再編税制の「適格要件」に類似した要件を組み込みつつ、「連結納税制度開始時」「連結納税グループ加入時」それぞれのケース別に、次頁以降に示したフローチャートの流れで時価評価課税の有無、欠損金等の取り扱いを判定することとなった。
すなわち、「現金買収による完全子会社化⇒連結納税グループ加入」というプロセスを経た子会社であっても、「完全支配関係継続」「従業員継続」「主要事業継続」といった組織再編税制の適格要件に類似した要件を満たすことにより、時価評価課税を受けることなく、また、加入前欠損金額の持ち込みも可能となる(大綱109頁(2)(3))。
このように、時価評価と欠損金切り捨てに関する取り扱いは現行制度より緩和されたが、その後のプロセスとして、含み損の損金算入制限等を「恒常的に損失が発生する事業」等に該当するかどうかにより吟味するプロセスが追加された点もポイントの一つと言える(同(4))。なお、「構造的に損失が発生する事業」とは、フローチャートの注2のとおり「減価償却費/原価及び費用の額の合計額>30%」となる(大綱109頁の下部)。
さらに大綱110頁の(5)では組織再編税制における「みなし共同事業要件」に類似した要件をクリアしている場合には、この含み損の制限等のプロセスを免れる旨が規定されている点も要チェックだ。
また、大綱110頁の(6)に、「グループ通算制度の適用開始又は通算グループへの加入前の欠損金(現行:特定連結子法人の連結納税制度の適用開始又は連結グループへの加入前の欠損金)のうち上記(3)及び(4)により切り捨てられなかったものは、特定欠損金とする」とあるように、親法人の開始・加入前欠損金が「特定欠損金」(42頁参照)となるとされた点も注目される。
次頁以降のフローチャートは、開始・加入時の時価評価課税・欠損金の切り捨ての有無等を判定する際に活用されたい。
※なお、本フローチャートの著作権は株式会社ロータス21に属しており、無断転載、無断引用は禁止とさせていただきます。
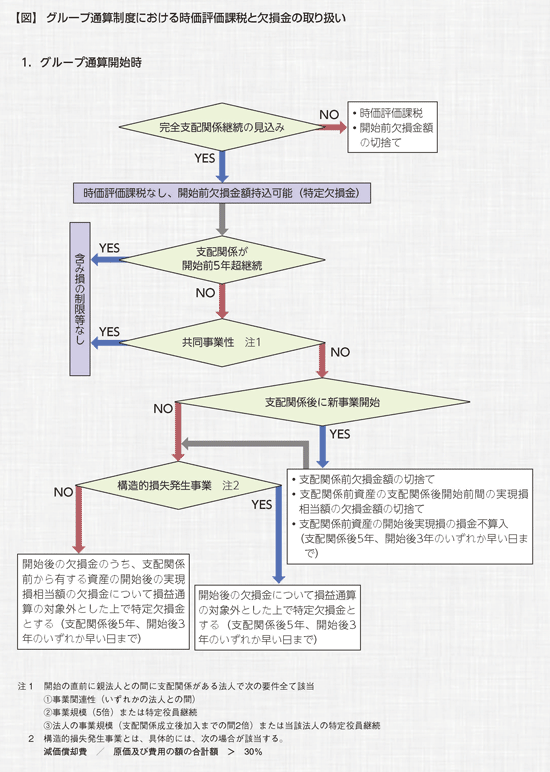
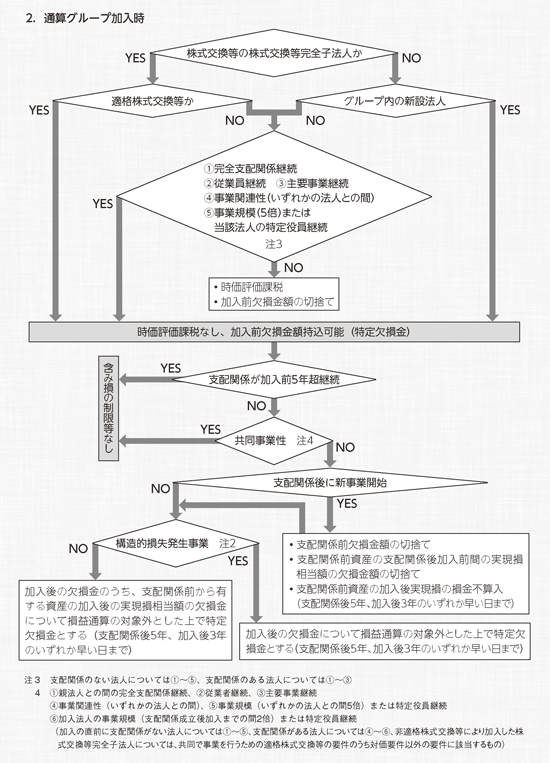
グループ調整計算
研究開発「調整前法人税額」の比で按分の上、税額控除相当額を精算
昨年8月に政府税調総会に提出された専門家会合の報告では、研究開発税制、外国税額控除、受取配当(国内・国外)、寄附金について、いずれもグループ調整計算の廃止の是非を両論併記する格好となっていた。この時点から調整の難航は予想されていた。
基本的に寄附金以外はグループ調整計算が維持されることとなったが、現行制度からの変更点や(寄附金に関する)救済措置なども含まれているので留意したい。
まず研究開発税制(大綱115頁)では、グループ全体の税額控除可能額の各法人への配分方法が変更される。
現行制度では各法人の試験研究費の支出割合に応じ配分するところ、グループ通算制度においては調整前法人税額(研究開発税制適用前の各法人の法人税額)の比で按分する。これは、グループ通算制度は「個別申告方式」となるため、これまで通り試験研究費の支出割合で按分すると、試験研究費の額は多いが所得・税額がそれほど多くない法人(例えばコストセンターの親会社)では控除対象額を控除しきれないという事態が起こり得る一方、逆に、試験研究費の額は少ないが所得・税額が多い法人(例えば販売子会社)では控除対象額が少なくなり控除枠が余ってしまうという問題が生じるからだ。
ただ、試験研究費を調整前法人税額の比で按分することとした場合、試験研究を行った法人と実際に税額控除額が配分される法人が異なる可能性がある。この不一致を解消するためには、事後に税額控除相当額をグループ内で精算することが考えられるところだが、その場合に授受される金額(通算税効果額、大綱107頁)は益金不算入・損金不算入とされた。
また、グループ内の法人で修・更正が生じた場合には、他の法人への影響を遮断する。ただし、増額更正の場合と減額更正の場合では取り扱いが異なる。増額更正の場合、所得の増加→法人税額の増加→法人税キャップ(法人税額×25%)の増加という流れで、理論的には税額控除可能額は増えるはずだが、実際にはそうはならず、当初申告額で固定する。一方、減額更正の場合、過大とされる控除額は、更正のあった法人において減少させることになる。
外国税額控除 過年度の計算誤りは進行年度で処理
外国税額控除(大綱113頁)では、個別の法人で計算間違いがあった場合の取り扱いに注意する必要がある。
仮にX期に行われた税務調査でX-2期の計算誤りが見つかったとしても、改正後はX-2期の控除額は当初申告額で固定する。その上で、X-2期の外税控除の再計算自体は行い(これ自体は修更正にあたらない)、税額控除限度超過額や控除余裕枠の変動額をX-1年度に持ち越し再計算(これも修更正にあたらない。
なお、X-1期の控除額も当初申告額で固定)、さらに進行年度のX期に関連数値を持ち越したうえで、すべての処理をX期で行うことになる。この結果、控除しきれず還付となる場合もあろう。
受取配当 負債利子控除割合の上限を「負債利子の額の10分の1相当額」に
国内の受取配当益金不算入制度(大綱112頁、68頁)については、持株割合の判定をグループ全体で行う基本構造は維持されたものの、ここでいう「グループ全体」の意義が現行制度から若干変更されているので留意したい。
現行制度上、完全子法人株式等に該当するかどうかの判定は、100%グループ内の法人(外国法人経由で保有する内国法人を含む)かどうかで判定するが、この点については変更がない。
一方、関連法人株式等や非支配目的株式等に該当するか否かの判定は、連結グループ内の法人(外国法人経由で保有する内国法人を含まない)ではなく、100%グループ内の法人(外国法人経由で保有する内国法人を含む)で行うこととされた。この結果、外国法人経由で100%支配する内国法人を有する場合、持分割合の上昇により益金不算入割合の区分が変更となり、僅かではあるが益金不算入額が増加する可能性がある。
なお、単体納税法人にあっては、現状、個社ごとに持株割合を判定しているところであるが、改正後はグループ通算制度と同様、100%グループ内の法人全体で持株割合を判定することになる。普通に考えれば、益金不算入割合が増加することはあったとしても、減少することはないため、減税と捉えてよいであろう。
関連法人株式等に係る負債利子控除については、簡素化の観点から一律に概算控除が適用される。これは連結納税・単体納税、共通の措置となる。現状の負債利子控除額は、「負債利子額×(関連法人株式等簿価/総資産簿価)」により計算するが、仮に関連法人株式等に係る配当に占める負債利子控除額の割合を「負債利子控除割合」と呼ぶとすると、その数値は法人の置かれた状況(負債利子の額、総資産の額、関連法人株式等に係る簿価/配当の額)によって大きく異なることになる。
そこで大綱では、概算控除として関連法人株式等に係る配当の「100分の4相当額」(4%)との割合を一旦設定した上で、「負債利子控除割合」が0~3%台の企業(このレンジ内の企業は少なくない)において不相応な増税が生じないよう、エスケープ規定として、「その事業年度において支払う負債利子の額の10分の1相当額を上限とする」とのキャップを設けた。
なお、外国子会社配当益金不算入制度については、連結納税・単体納税ともに変更はない。
寄附金 グループ調整計算廃止も救済措置を手当て
寄附金(大綱112頁)については、重要性の観点からグループ調整計算が廃止され、個別の法人ごとに損金算入限度額を計算することになったが、一定の救済措置が講じられる。
具体的には、損金算入限度額の計算の基礎となる資本金等の額を、「資本金の額及び資本準備金の額の合計額」とすることとなった。これは法人事業税の資本割を参考に、「会計上の資本金+資本準備金」の基準を取り入れたもの。
ただし、資本割では「資本金等の額」と「資本金+資本準備金の合計額」を比較し、高い方を採用することになっているのに対し、寄附金の場合、大綱では、資本金等の額から「資本金+資本準備金の合計額」に強制的に“置き換える”ような表現となっていることに注意が必要である。
なお、単体納税についても同様の改正が行われる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















