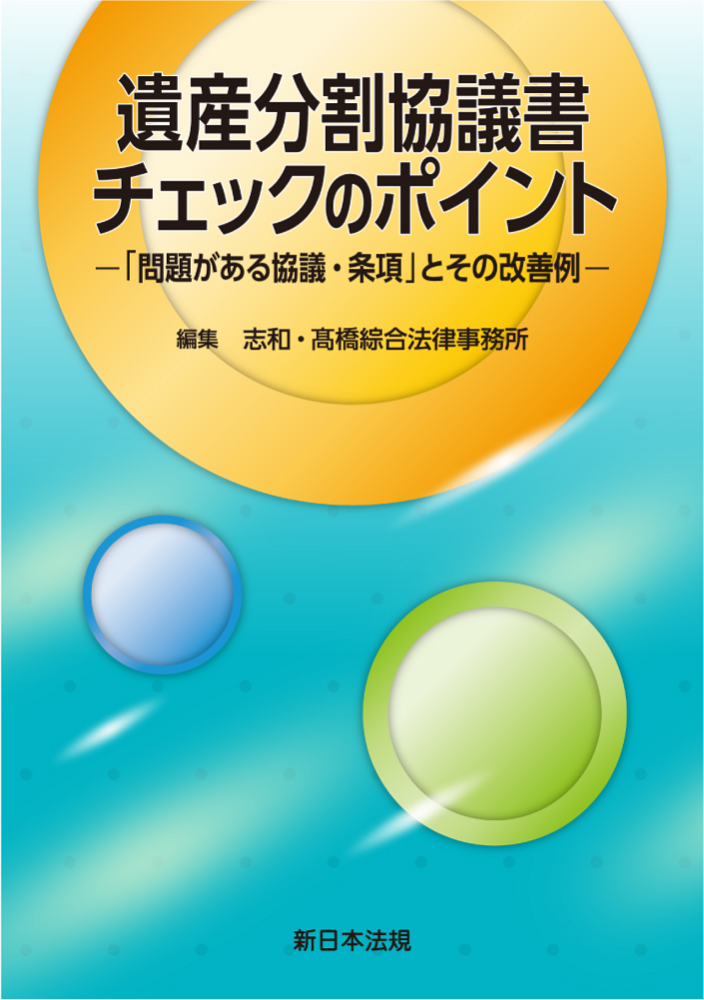税務ニュース2022年10月07日 立替経費の渡航費等は源泉徴収必要(2022年10月10日号・№949) 東京地裁、一旦経済的利益が生じたものとして扱うことが相当と判断
原告は、「立替払された経費の精算として支払われたものであれば、結局、同支払を受けたことによる課税所得は生じない」と主張。また、その主張の根拠として、所基通161−19第2文の定め(「人的役務の提供に係る対価」の支払者が宿泊施設、交通機関等に対して滞在費、旅費等を直接支払い、その額が費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、同「対価」に含まれないものとすることができる旨の定め)を挙げ、「外国音楽家の報酬とは区別して立替金精算払をすることは、航空会社等に対し同渡航費等を直接支払うこととその経済的実質が同一である」などと主張していた。
東京地裁は、①所得税法の規定の文言、②「人的役務の提供に係る対価」の支払を受けた外国事業者は、同「対価」について最終的に純所得課税を受けるためには、非居住者の総合課税の対象となる所得税又は法人税の確定申告をしなければならないという課税の構造、③昭和40年改正の趣旨を挙げ、「人的役務の提供に係る対価」(所得税法161①六)は、「対価」として支払われる外国事業者の収入金額の総額であり、「対価」を得るために要した費用相当の支払額を含むとの判断を下した。
その上で、原告の主張に対しては、所基通161−19の趣旨について、「人的役務の提供を受ける者が宿泊施設、交通機関等に対して直接、滞在費、旅費等を支払うことによって得られるサービスは、人的役務の提供を受ける者がその役務の提供者を自己の支配下に置くためのものであって、それによって人的役務の提供をする者に経済的利益が生じたと見ることが必ずしも妥当しない場合がある」との考えを示し、「そうすると、少なくとも、人的役務の提供をする外国芸能法人等又は外国音楽家自身において、自らにとって最も利便性の高い条件で渡航や運送等のサービスの内容を決定して料金を支払い、人的役務の提供を受ける者が立替金精算払をするにとどまる場合には、上記のようにいいきれない部分が少なからず生ずるから、一旦、人的役務の提供をする外国芸能法人等又は外国音楽家自身にサービス相当額の経済的利益が生じたものとして扱うことが、経済的な実態にそぐわない扱いであるということはできない。」として斥けている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.