解説記事2023年01月16日 ニュース特集 租税回避スキーム、プロモーター資料情報は(2023年1月16日号・№962)
ニュース特集
当局作成資料、「部内版MDR連絡せん」から名称変更
租税回避スキーム、プロモーター資料情報は
国税当局は近年、国際化事案、富裕層等への対応を強めており、調査事案の企画、調査、審理等の際に各種税制や複雑な取引・契約を用いて租税回避を図っていると想定される事案を把握した場合、「租税回避スキーム等連絡せん」(令和3事務年度に導入した「部内版MDR連絡せん」から名称変更)を作成している。
本特集では、令和4事務年度において確実な作成が指示されている「租税回避スキーム等連絡せん」の記載内容(プロモーター情報、スキーム態様、課税上の問題点及び事案の検討の方向性、必要な税制改正の内容等)のほか、国税当局が調査担当者等に周知している「租税回避スキーム等連絡せん」「国際取引連絡せん」「調査情報連絡せん」の作成区分について、Q&A形式で確認する。
Q
国税当局が令和3事務年度に「部内版MDR連絡せん」を導入した背景を教えてください。
A
資産運用の多様化や国際化が進展する中、国税当局は、各種税制や複雑な取引・契約等を用いて租税回避を図っていることが想定される「真に調査すべき納税者」に対して、より一層的確に対応する必要があると考えていました。そこで、このような租税回避を図っていると想定される事案や現行の制度では課税が困難である事案(スキーム事案)を組織的に蓄積・分析して制度改正や運用改善につなげていく観点から、令和3事務年度において、当面の措置として「部内版MDR(Mandatory Disclosure Rules)連絡せん」に係る手続を定めました。
部内版MDRは、租税回避スキームのプロモーター及び利用者等について国税組織内で情報集約を行うものであり、調査(企画)担当者等が作成した「部内版MDR連絡せん」は、局の統括国税実査官(国際担当、富裕層担当)等を経由して、庁課税総括課の担当者に送付されます(本誌911号72頁参照)。
なお、令和3事務年度においては、国税当局内で数十件の「部内版MDR連絡せん」が庁に上申されたもようです。
Q
「租税回避スキーム等連絡せん」に記載される内容を教えてください。
A
「部内版MDR連絡せん」は、令和4年7月に発遣された資料情報事務に係る指示文書によって、「租税回避スキーム等連絡せん」に名称変更されました。
「租税回避スキーム等連絡せん」には、①税目、②利用者、③プロモーター等、④スキーム態様、⑤非違額、⑥スキーム概要・想定図、課税上の問題点、事案の検討の方向性、必要な税制改正の内容などが記載されます(下掲参照)。
具体的に③「プロモーター等」欄では、記載する租税回避スキームを策定、販売、評価したプロモーターまたは関係者の属性が記載され、把握している場合には、氏名・名称、住所・所在地も記載されます。また、④「スキーム態様」欄の「オーダーメード型」は、特定の利用者のために特別に作られた租税回避スキーム、「商品型」は、多くの者の利用を目的として作られたスキームを指します。
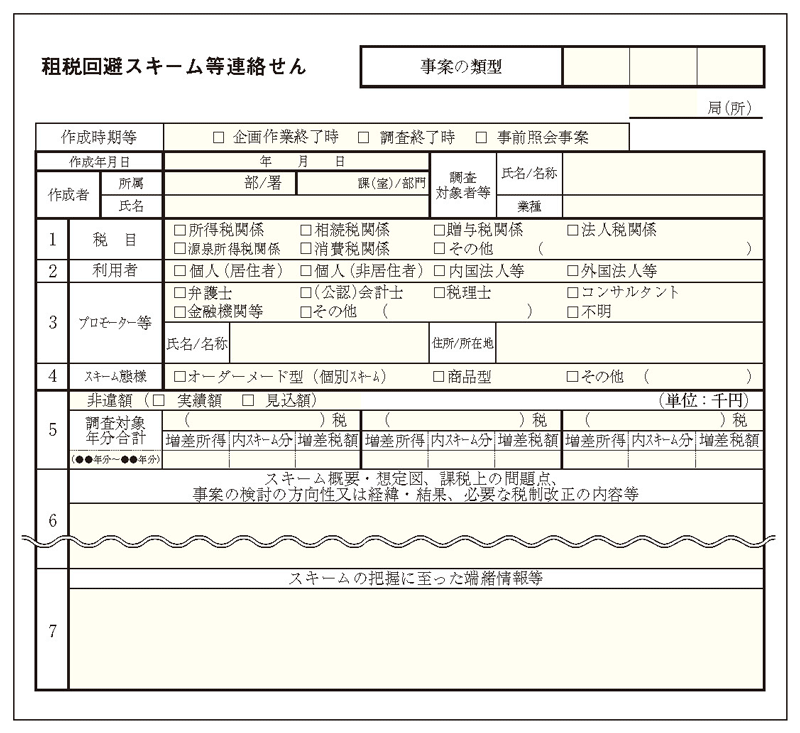
Q
課税上の問題点及び検討の方向性、必要な税制改正の内容等の記載事項は?
A
「租税回避スキーム等連絡せん」の作成時期等が「企画作業終了時」または「事前照会事案」の場合に課税上の問題点及び検討の方向性が記載されます。
一方、連絡せんの作成時期等が「調査終了時」の場合には、課税上の問題点及び検討の経緯・結果を記載し、否認につながった事案については、租税回避スキームの解明に有用であった調査手法、否認の根拠となった証拠及びその収集過程等、租税回避スキームの検討に役立つ情報も併せて記載されるようです。
また、税制改正を要すると考えられる法令の規定がある場合は、該当する法令名及び条項が記載されます(改正案を検討している場合は、検討内容も併記)。
Q
租税回避が想定される取引等を把握した場合に当局が作成する「国際取引連絡せん」と「租税回避スキーム等連絡せん」の違いは?
A
上述のとおり、「租税回避スキーム等連絡せん」は、調査企画、調査、審理等の際に、各種税制や複雑な取引・契約等を利用して、現行制度では課税が困難となる状況を作出している(租税回避を図っている)と想定される事案を把握した場合に作成されます。
一方、「国際取引連絡せん」は、国際的な取引のうち、①租税回避を図っていると想定されるもの、②海外取引のうち特殊なもの、③実態や事実関係が十分に解明されていないもの、④国際的な租税回避であるか否かの判別が困難なもの、⑤活用先において現行制度では課税が困難となることが想定されるもの(収集先と活用先が異なる場合に限る)を把握した場合に作成されます(「国際取引連絡せん」の記載内容は、下掲参照)。
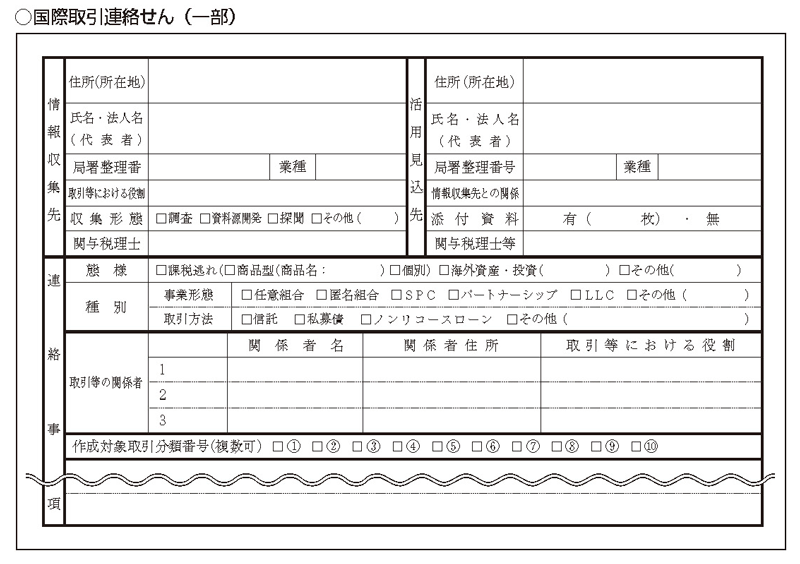
Q
「租税回避スキーム等連絡せん」と「国際取引連絡せん」の作成基準に重複もありそうですが、各連絡せんの作成区分はどのようなものですか?
A
国税当局は、調査(企画)担当者に対して、「租税回避スキーム等連絡せん」「国際取引連絡せん」「調査情報連絡せん」等の仕分けフローを示しています。それによれば、調査企画(実施)中に把握した租税回避・課税逃れと思われる取引等が、現行制度では課税が困難となることが想定され、かつ、租税回避の効果を享受する者が企画(調査)対象者自身である場合に「租税回避スキーム等連絡せん」が作成されます。
また、把握した取引等が「租税回避スキーム等連絡せん」の作成対象とならない国際的な取引等の場合に「国際取引連絡せん」が作成され、それ以外の類型的な不正取引・不正経理等については「調査情報連絡せん」が作成されます(前頁図参照)。
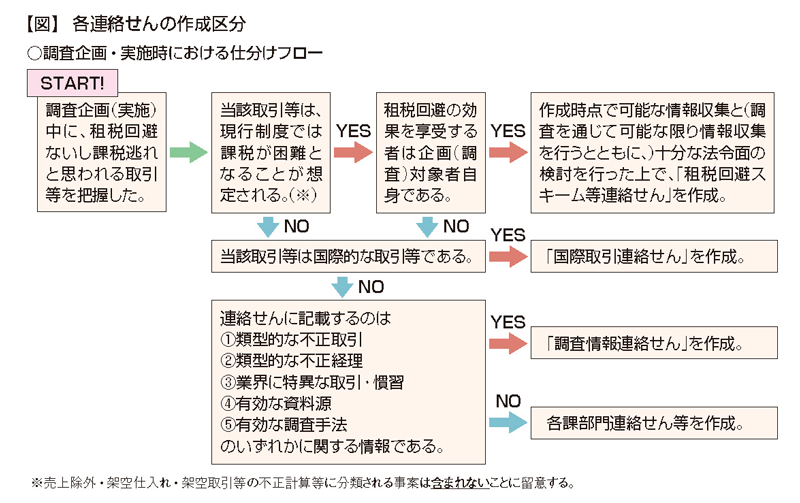
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























