解説記事2023年03月06日 法令解説 令和4年公認会計士法改正に伴う政令・内閣府令の改正(2023年3月6日号・№969)
法令解説
令和4年公認会計士法改正に伴う政令・内閣府令の改正
金融庁企画市場局企業開示課 課長補佐 鳥屋尾大介
金融庁企画市場局企業開示課 係長 尾崎祐二
一.はじめに
上場会社監査の担い手の裾野の拡大、共働き世帯の増加や女性活躍の進展といった会計監査を取り巻く環境変化を踏まえ、上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う監査法人等に対する登録制度の導入、監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限の見直し等を内容とする「公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律(令和4年法律第41号。以下「改正法」という。)」が令和4年5月18日に公布された(図表1参照)。
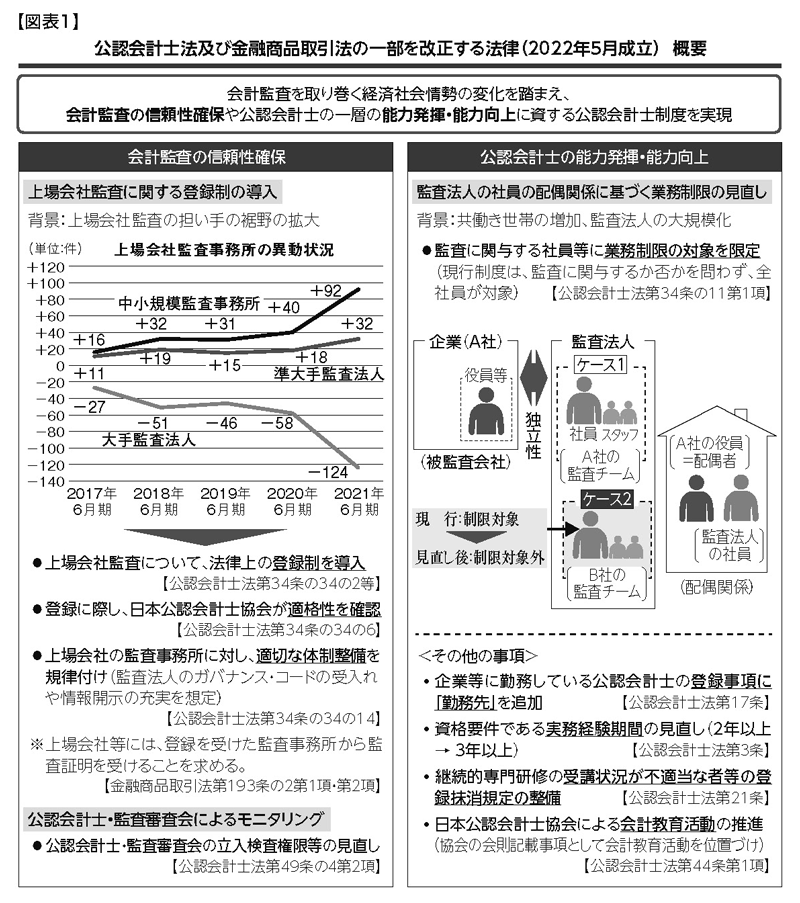
金融庁では、改正法の公布以降、その施行に伴い必要となる制度整備として、改正法の施行日を令和5年4月1日とする「公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年政令第14号)」のほか、「公認会計士法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第15号。以下「改正政令」という。)」及び「公認会計士法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第9号。以下「改正府令」という。)」の制定作業を行い、令和5年1月25日にこれらが公布された(図表2参照)。
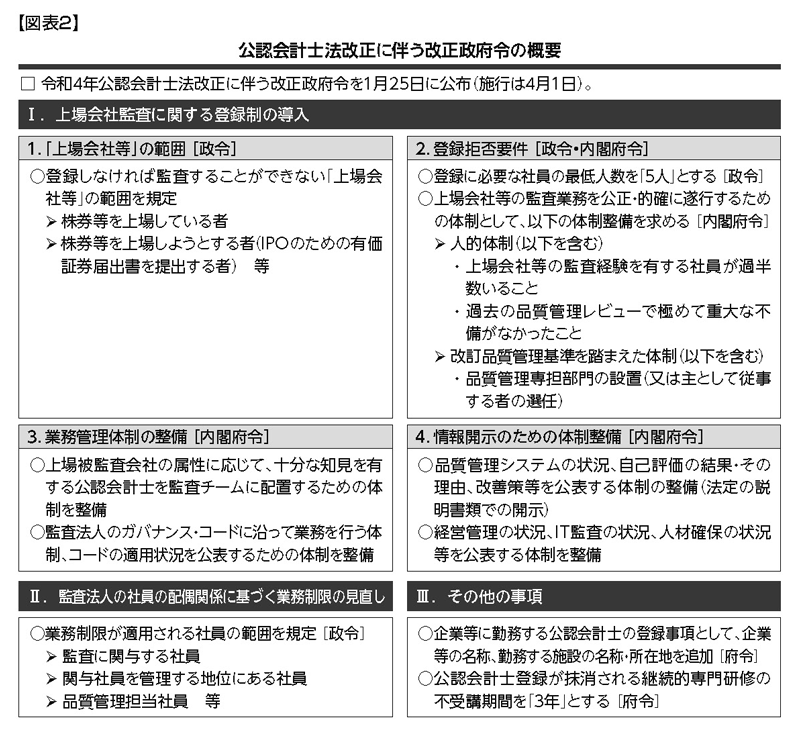
本稿では、改正政令及び改正府令の概要を解説する。なお、本文中、意見にわたる部分は、筆者らの個人的見解である。
二.上場会社等監査人登録制度に係る政令・内閣府令の改正
1 「上場会社等」の範囲
改正法による公認会計士法(昭和23年法律第103号。以下「法」という。)の改正により、公認会計士又は監査法人が「上場会社等」の財務書類に係る監査証明業務(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第193条の2第1項及び第2項の監査証明(以下「金商法上の監査証明」という。)に係るものに限る。)を行うときは、法第34条の34の2の登録を受けなければならないこととされた。
改正政令による改正後の公認会計士法施行令(昭和27年政令第343号。以下「施行令」という。)第29条の2においては、この「上場会社等」の範囲について、
・流動性の高い有価証券を発行し、一般投資家を含む多数のステークホルダーを有しており、その財務報告の信頼性を確保することは我が国資本市場の十全な機能発揮のために不可欠な会社等であること
・業務内容の複雑性・多様性等から、より質の高い監査が求められる会社等であること
との考え方から、
イ.金融商品取引所に上場されている株券等(特定上場有価証券(いわゆるプロ向け銘柄)を除く。)の発行者(脚注1)
ロ.金融商品取引所にその発行する株券等を上場しようとする者であって、当該金融商品取引所の定める規則により当該株券等に係る有価証券の募集又は売出しを行うため、有価証券届出書を提出しようとするもの
としている(脚注2)。
また、イ及びロ中の「株券等」の範囲についても、上記の考え方から、
ⅰ.金商法第2条第1項第7号に規定する優先出資証券
ⅱ.金商法第2条第1項第9号に規定する株券
ⅲ.金商法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券(有価証券信託受益証券に該当するものであって、受託有価証券がⅰ、ⅱ又はⅳに掲げるものであるものに限る。)
ⅳ.金商法第2条第1項第17号に掲げる有価証券(外国有価証券)でⅰ又はⅱの性質を有するもの
ⅴ.金商法第2条第1項第20号に掲げる有価証券(預託証券)でⅰ、ⅱ又はⅳに係る権利を表示するもの
ⅵ.ⅰからⅴまでに掲げるものに表示されるべき権利であって、金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの
ⅶ.金商法第2条第2項第1号に規定する信託の受益権(有価証券信託受益証券に該当するものであって、受託有価証券がⅰ、ⅱ又はⅳに掲げるものであるものに限る。)
としている(脚注3)。
なお、例えば、上場投資信託(ETF)や不動産投資信託(J-REIT)は、それぞれ、金商法第2条第1項第10号の投資信託受益証券、同項第11号の投資証券であるから、その発行者は「上場会社等」に含まれないこととなる。これは、これらの有価証券の発行者も流動性の高い有価証券を発行しており一般投資家を含む多数のステークホルダーを有しているという点では株券等の発行者と共通するが、これらの有価証券は資産金融型有価証券に当たるものであって、発行者の事業内容の複雑性等からより質の高い監査が求められるような株券等の発行者とは基本的な性格が異なるためである。
ここで、「上場会社等」に該当する者は、改正法による改正後の金商法第193条の2第1項及び第2項により、法第34条の34の2の登録を受けた公認会計士又は監査法人(以下「登録上場会社等監査人」という。)から金商法上の監査証明を受ける必要がある。
この点は、上記ⅳ(又はこれに係るⅴからⅶまで)の株券等を発行し、「上場会社等」に該当することとなる外国法人も同様である。
ただし、当該外国法人が、外国監査法人等(法第1条の3第7項)から「監査証明に相当すると認められる証明」を受ける場合には、当該外国法人は、登録上場会社等監査人である公認会計士又は監査法人から金商法上の監査証明を受けることを要しない(脚注4)。(法第34条の34の2、金商法第193条の2第1項第1号及び第2項第1号参照)。
2 登録申請の手続
登録申請書の様式及び記載事項並びに添付書類については、改正府令による改正後の公認会計士法施行規則(平成19年内閣府令第81号。以下「施行規則」という。)第83条から第85条までに規定している。添付書類のうち、法第34条の34の4第2項第2号及び第3号に規定する添付書類は、施行規則第85条第1項及び第2項において、申請者が公認会計士である場合にあっては施行規則第14条各号、監査法人である場合にあっては施行規則第39条各号に掲げる説明書類の記載事項を記載した書類としている。ただし、後述の業務の品質の管理の状況等に関する評価の結果及びその理由等の記載を求める施行規則第14条第1号ハ(3)及び第39条第1号ホ(3)の事項は、実際に上場会社等の財務書類に係る監査証明業務が実施された上で、当該業務を含む業務の品質の管理の状況等について記載されるべきものであるから、登録申請の時点では記載を要しないとしている。また、施行規則第14条第3号及び第39条第6号の事項は、施行規則第85条第3項第3号において契約締結を予定している上場会社等の名称を記載した書類の添付を求めていることから、記載を要しないとしている。
3 登録拒否要件
(1)施行令の内容
施行令では、法第34条の34の6第1項第3号ヘ及び第4号ロの登録拒否要件として、次の事項を定めている。
まず、登録申請者が監査法人である場合の公認会計士である社員の最低人数を「5人」とした(施行令第29条の3)。これは、令和4年1月4日に公表された「金融審議会公認会計士制度部会報告−上場会社の監査品質の確保と公認会計士の能力発揮に向けて−」(脚注5)(以下「制度部会報告」という。)において、「現行の公認会計士法の監査法人制度に倣い、制度導入当初は公認会計士である社員を5人以上有することとしつつ、制度導入後における日本公認会計士協会による中小監査事務所への育成支援による体制整備の進展等を踏まえ、見直すことが考えられる。」とされたことを踏まえたものである。
次に、申請者が有限責任監査法人である場合の最低資本金の額について、登録有限責任監査法人の最低資本金の金額(施行令第22条)と同一の、社員の総数に100万円を乗じて得た額に相当する金額とした(施行令第29条の4)。
(2)施行規則の内容
施行規則においては、法第34条の34の6第1項第5号の上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための体制として、施行規則第87条に以下の体制を定めている。
① 当該監査証明業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制(次に掲げる事項を含むものに限る。)
イ.当該監査証明業務に関する十分な知識及び経験を有する公認会計士を確保していること(申請者(監査法人にあっては、社員の過半数)が公認会計士の登録後3年以上の当該監査証明業務の経験を有する者であることを含む。)
ロ.申請者(監査法人にあっては、社員の過半数)が、次の要件の全てに該当すること。
ⅰ.日本公認会計士協会(以下「協会」という。)の品質管理レビューを拒否したことがある者でないこと、又は品質管理レビューを拒否したことがある監査法人の社員であった者でないこと。
ⅱ.品質管理レビューにおいて監査証明業務の運営の状況に重大な不備があるとして協会の認定を受け、その日から3年を経過しない者でないこと、又は当該認定を受けた監査法人の社員であった者でその日から3年を経過しないものでないこと。
なお、ロの要件は、例えば、品質管理レビューを拒否したことや、品質管理レビューにおいて監査証明業務の運営の状況について重大な不備を指摘されたことがある監査法人に社員として所属していた者が、別の監査法人を組織して登録を受けようとすることを防ぐための規定である。この点、監査法人の運営に責任を有していなかった者や、指摘の原因となった監査証明業務に関与しなかった者の登録を排除することとならないよう、上記ⅰ、ⅱの「社員であった者」については、それぞれ、一定の範囲の者に限定している。
② 当該監査証明業務を公正かつ的確に遂行するために必要な業務の品質の管理を行うための体制(次のいずれかを含むものに限る。)
イ.業務の品質の管理に係る専任の部門の設置
ロ.業務の品質の管理に主として従事する公認会計士(監査法人にあっては、社員である者に限る。)の選任
②の要件は、「会計監査の在り方に関する懇談会(令和3事務年度)論点整理」における、「監査業務部門から独立した品質管理部門の設置が求められるとの意見があった」との記述を踏まえたものである(脚注6)。中小監査法人や公認会計士個人については、イの独立した部門を設置することが難しいことも想定されるが、その場合であっても、上記論点整理の記述の趣旨を踏まえて業務の品質の管理を行うため、ロの体制を確保する必要がある(脚注7)。
なお、①のイ・ロ及び②のイ・ロは、いずれも最低限満たしていなければならない内容を示しているものであり、これらの内容を備えていることのみをもって①及び②の体制が整備されていることにはならないことに留意が必要である。
その他、法第34条の34の6第1項第3号トの申請者が監査法人である場合の公認会計士である社員の占める割合については、登録有限責任監査法人の登録要件(施行規則第64条)と同一の、100分の75としている(施行規則第86条)。
4 共同監査人等
法第34条の34の13は、登録上場会社等監査人が公認会計士個人である場合には、
・上場会社等監査人登録を受けた監査法人と共同して行うこと
・政令で定める数以上の他の上場会社等監査人登録を受けた公認会計士と共同し、かつ、当該他の公認会計士の数と補助者として使用する他の公認会計士の数を合計した数が政令で定める数以上であること
のいずれかの要件を満たさなければならないこととしている。
これを受け、公認会計士における組織的監査の実現という観点から、施行令第29条の5は、共同監査人の数を「1」(本人を含めて2人)、共同監査人と補助者の数を合計した数を「4」(本人を含めて5人)としている(脚注8 9)。
5 登録上場会社等監査人の業務管理体制
法第34条の34の14に規定する登録上場会社等監査人の業務管理体制として、施行規則に次の体制を定めている。
第1に、施行規則第93条では、登録上場会社等監査人に対し、業務の品質の管理の状況等を適切に評価し、かつ、当該評価結果及びその理由等、同条各号に掲げる事項を公表する体制の整備を求めている。
令和3年11月に「監査に関する品質管理基準」が改訂され、リスク・アプローチに基づく品質管理システムが導入されるとともに、品質管理システムに関する最高責任者は少なくとも年に一度、基準日を定めて品質管理システムを評価し、当該システムの目的が達成されているという合理的な保証を監査事務所に提供しているかを結論付けなければならないとされた。さらに、同改訂の前文において、評価の結論や当該結論に至った理由を含む品質管理システムの状況等については、各監査事務所において公表することが望ましいとされている(脚注10)。
施行規則第93条の規定は、上記改訂品質管理基準の内容を踏まえたものである。
なお、同条の「業務の品質の管理」の内容については、改訂品質管理基準における「品質管理システム」の内容と整合するよう、施行規則第26条の改正を行っている。
また、施行規則第93条各号に掲げる事項は、法定の説明書類の記載事項とした(施行規則第14条第1号ハ(3)及び第39条第1号ホ(3))。これは、従来から、業務の品質の管理の状況等が説明書類の記載事項とされているため、その評価結果等についても併せて説明書類に記載することとし、当該説明書類を法第28条の4及び第34条の16の3の規定により公衆縦覧に供することで、施行規則第93条にいう「公表」を満たせることとすることが、作成者及び利用者の利便に資すると考えたためである。
第2に、施行規則第94条では、上場会社等の財務書類の監査証明業務について十分な知識及び経験を有する公認会計士を当該業務に関与させる体制の整備を求めている。
これは、当該業務を行う中で、上場会社等である被監査会社等の数やその業務内容に変動が生じることが想定されるところ、被監査会社等の属性に応じて監査チームに十分な知識及び経験を有する公認会計士を確保することを求めるものである。
第3に、施行規則第95条では、登録上場会社等監査人の経営管理の状況等を公表する体制の整備を求めている。
これは、制度部会報告において、登録を受けた者に対して情報開示に係るより高い規律付けを求めるとされ、その情報開示の内容として、「例えば、①品質管理、②ガバナンス、③IT・デジタル、④人材、⑤財務、⑥国際対応の6つの観点が考えられるとの意見があった」と記述されていることを踏まえたものである。これらの項目の公表媒体は特段定めていないが、その理由は、例えば、これらの項目を法定の説明書類の記載事項とすると、罰則(脚注11)の適用があることから、法令上、記載事項の明確化が求められることとなるが、これらの項目ごとの重要性は、登録上場会社等監査人やその被監査会社等の規模・特性によって異なると考えられ、全ての登録上場会社等監査人に一律の項目の開示を求めることは適切ではないためである。登録上場会社等監査人が、自身にとって重要と考えられる開示項目を主体的に判断し、創意工夫によって充実した情報開示を行うことが期待される。
第4に、施行規則第96条では、組織的な運営に関する原則として金融庁長官が指定するものに沿って業務を実施するための体制及び当該原則の適用状況を公表するための体制の整備を求めている。
これは、制度部会報告において、登録を受けた者に対する体制整備に係るより高い規律付けとして、監査法人のガバナンス・コードの受入れを求めるとされていることを踏まえたものである。これに伴い、同条の「金融庁長官が指定するもの」として、「監査法人のガバナンス・コード」を指定するための告示を新設している(脚注12)。
現行のコードは、コンプライ・オア・エクスプレインの考え方が採用されているところであるが(脚注13)、施行規則第96条により公認会計士法令の中にコードが取り込まれることとなっても、その考え方は、従前と変わるものではない。
なお、前述した「当該原則の適用状況」の公表は、施行規則第95条と同様に、公表媒体を特段定めていない。これについても、登録上場会社等監査人自身が創意工夫し、充実した情報開示を行っていくことが期待される(脚注14)。
6 経過措置
改正後の施行規則の規定について、所要の経過措置を置いている(改正府令附則第2条)。
すなわち、
・業務の品質の管理の内容についての第26条の規定は、改訂品質管理基準の実施日と同一の令和6年7月1日(法第34条の11の4第2項の大規模監査法人にあっては、令和5年7月1日)以後最初に開始する被監査会社等の会計期間の開始の日(以下「適用開始日」という。)から
・業務の品質の管理の状況等に係る評価結果等を公表する体制についての第93条の規定は、適用開始日以後に開始する公認会計士の年度又は監査法人の会計年度に係るものから
・経営管理の状況等を公表する体制、組織的な業務運営体制についての第95条、第96条の規定は、適用開始日から
それぞれ適用することとしている。
三.監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限の見直しに係る政令・内閣府令の改正
1 監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限が適用される社員の範囲
法第34条の11第1項第2号は、監査法人の社員のうちにその配偶者が会社等の役員等である(又は過去1年以内に役員等であった)者がある場合にあっては、当該社員が当該会社等に係る監査証明業務に関与する社員等である場合のみ、当該監査法人による当該監査証明業務の提供が禁止されることとなるよう改正されている。
施行令第14条の2は、かかる社員の範囲を、
イ.当該監査証明業務(対象業務)に関与する社員
ロ.対象業務について法第34条の10の4第1項の規定による指定を受けた社員(無限責任監査法人における指定社員)
ハ.対象業務について法第34条の10の5第1項の規定による指定を受けた社員(有限責任監査法人における指定有限責任社員)
ニ.イからハまでの者を管理する者としての地位にある社員
ホ.業務の品質の管理の方針を策定し、及びその実施の状況を検証する社員
ヘ.対象業務に重要な影響を与えることができる社員(内閣府令で規定(脚注15))
としている。
ここで、施行令第15条は、法第34条の11第2項の委任を受け、監査証明業務が提供できないこととなる会社等との間の「著しい利害関係」を定めているところ、その第6号において、上記イからハまでの社員と同一範囲の社員に対し、他の社員に比して一段高い独立性を要求している。上記イからヘまでの社員の範囲は、この例を踏まえつつも、「監査法人の社員のうちにその配偶者が会社等の役員等である(又は過去1年以内に役員等であった)者がある場合」の利害関係としての重要性に鑑みて、より広い範囲の社員としている(脚注16)。また、協会の「倫理規則」上、自主規制上の利害関係規定が適用される者の範囲として「監査業務チーム」という概念がある。上記イからヘまでの社員の範囲を定めるに当たっては、「監査業務チーム」との整合性も一部考慮しているが、その範囲を超えるものではない。
2 1に関連する改正
1に関連して、次の2点の改正を行っている。
(1)社員の半数以上の者が有する利害関係
施行令第15条第7号は、社員が特定の監査証明業務に関与するか否かにかかわらず、社員の半数以上の者が会社等と一定の利害関係を有している場合には、監査法人の意思決定に影響を与えることができるとの考え方から、当該会社等に対し監査証明業務が提供できないとしている。
ここで、今般の法第34条の11第1項第2号の改正及び施行令第14条の2の新設により、「監査法人の社員のうちにその配偶者が会社等の役員等である(又は過去1年以内に役員等であった)者がある場合」であっても、その者が1のイからヘまでの社員でなければ、監査証明業務の提供ができることとなるため、場合によっては、社員の半数以上の者がかかる利害関係を有するという状況も生じうる。
このため、施行令第15条第7号の趣旨に照らし、こうした状況が生じた場合には監査証明業務の提供ができないこととするため、同条に第8号を新設している。
(2)登録有限責任監査法人の監査に係る特別の利害関係
登録有限責任監査法人(法第34条の24の登録を受けた有限責任監査法人)は、財務基盤の確保等を通じて債権者保護を図る観点から、その開示書類の信頼性を確保するため、特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査報告書を計算書類に添付しなければならないこととされている(法第34条の32第1項)。
かかる「特別の利害関係」は施行令第23条各号に列挙されているところであるが、その第2号及び第3号は、「(監査する側の)監査法人の社員のうちにその配偶者が(監査される側の)当該登録有限責任監査法人の社員である(又は過去1年以内に社員であった)者がある場合」という趣旨の規定となっている。これは、上記1で記載した「監査法人の社員のうちにその配偶者が会社等の役員等である(又は過去1年以内に役員等であった)者がある場合」と同義であるから、同条第2号及び第3号の利害関係の適用対象社員の範囲を上記1のイからヘまでと同一の範囲に限定することとした。
四.公認会計士等の登録・登録抹消に係る内閣府令の改正
(1)登録事項の変更に関する改正
法第17条は、公認会計士登録において「事務所」の登録を必須としていたところ、企業等に勤務するいわゆる組織内会計士については、この事務所として自己の住所等を登録することがあり、その者の実態を表していないとの問題が指摘されていた。このため「勤務先」等の登録ができるよう、同条につき所要の改正を行っている。
これを受け、公認会計士の登録事項を定める公認会計士等登録規則(昭和42年大蔵省令第8号。以下「登録規則」という。)第2条第3号を改正し、組織内会計士を念頭に、
イ.公認会計士等(公認会計士及び外国公認会計士)が会社その他の者の役員又はこれに準ずる者(脚注17)である場合には、当該会社その他の者の商号又は名称並びに主として執務する事業所その他の施設の名称及び所在地
ロ.公認会計士等が会社その他の者に勤務する場合(脚注18)には、当該会社その他の者の商号又は名称並びにその勤務する事業所その他の施設の名称及び所在地
を登録事項に追加することとした。
なお、同号には、上記イ及びロのほか、公認会計士等が自らその業務を営む場合、監査法人の社員である場合等が列挙されているところ、これらのうち複数の場合に該当することも想定し得る。また、どの場合に該当するかは、各公認会計士等が自らの活動の実態に鑑みて判断し、登録規則第4条又は第6条に基づく申請を行い、当該申請を踏まえて協会において登録が行われることになると考えている(脚注19 20)。
(2)登録抹消に関する規定の整備
今般の法改正において、協会が、資格審査会の議決を経て公認会計士の登録を抹消できる規定を整備し、その抹消事由の一つとして、内閣府令で定める期間以上の期間にわたり、法第28条に規定する研修(CPE)を受けていないことを掲げている(法第21条第2項第3号)。
これを受け、登録規則第10条において、
・登録抹消の対象となるCPEの不受講期間を3事業年度(脚注21)とすること
・不受講期間のうちに公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第2条第3項の規定による研修の免除がされた期間がある場合(脚注22)には、当該抹消事由に該当しないこと
を定めている。
また、登録抹消事由の追加に伴い、登録規則において、登録事項、届出手続、協会による抹消手続、様式の整備など、所要の改正を行っている。
五.その他内閣府令の改正
その他の改正事項の概要は次のとおりである。
改正法により、公認会計士と同様、特定社員、会計士補についても、資格審査会の議決に基づきその登録を抹消できる規定が整備されたことから、これに伴う内閣府令の改正を行っている。
また、施行規則第69条に規定する登録有限責任監査法人の計算書類に添付する監査報告書の記載事項について、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和32年大蔵省令第12号)第4条を参考とした改正を行っている。
六.施行日
改正政令及び改正府令の施行日は、改正法と同日の令和5年4月1日としている。
七.おわりに
以上が、改正法に伴う改正政令・改正府令の概要である。
会計監査の信頼性を確保していくためには、当局を含む関係者によって、一連の改正法令の趣旨・目的を踏まえた取組みが着実に実施されることが重要と考えている。
脚注
1 本登録制度は、監査証明業務のうち金商法第193条の2第1項及び第2項の監査証明に係るものを対象としている。この点、特定取引所金融商品市場(いわゆるプロ向け市場。金商法第2条第32項)のみに上場されている特定上場有価証券(金商法第2条第33項)の発行者については、同法上の有価証券報告書の提出義務がなく、同法上の監査証明を受けることが求められていないことから、当該発行者を「上場会社等」から除外するため、イの「株券等」から「特定上場有価証券」を除いている。
2 施行令第29条の2第1項では、このほか、認可金融商品取引業協会の登録を受けた株券等(特定店頭売買有価証券を除く。)の発行者、その発行する株券等について認可金融商品取引業協会の定める規則により当該株券等に係る有価証券の募集又は有価証券の売出しを行うため、有価証券届出書を提出しようとするものも「上場会社等」に含まれるとしている。ただし、現在、これらに該当する「上場会社等」は存在しない。
3 これらの有価証券は、内部統制報告書や四半期報告書の提出義務者を定める金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第4条の2の7第1項各号や第4条の2の10第1項各号に掲げる有価証券と同一範囲である。
4 同時に、外国監査法人等が「監査証明に相当すると認められる証明」をする場合には、法第34条の34の2の登録を受けることを要しない。
5 金融審議会「公認会計士制度部会」報告の公表について(令和4年1月4日)(https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20220104.html)
6 「会計監査の在り方に関する懇談会(令和3事務年度)」論点整理の公表について(令和3年11月12日)
(https://www.fsa.go.jp/news/r3/singi/20211112.html)
7 ロの体制の考え方については、以下の「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」No.4を参照。
令和4年公認会計士法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について(令和5年1月25日)
(https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230125/20230125.html)
8 法第34条の34の13第2号ロは「補助者として使用する」と規定している。この点、同条及び施行令第29条の5は、本人及び共同監査人を含め、特定の監査証明業務を全体として5人以上で行うことを求める趣旨であるから、共同監査人が補助者として使用する者であっても、その者が実質的に当該監査証明業務に従事できる状況が確保されていれば、その者を施行令第29条の5第2項の補助者の数に含めることができると考えられる。
9 共同監査等を行うことができないやむを得ない事情として、共同監査人や補助者の公認会計士登録の抹消等の事情を規定している(施行規則第92条)。
10 「監査に関する品質管理基準の改訂に係る意見書」の公表について(令和3年11月19日)
(https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20211116.html)
11 法第52条の2第1号。
12 公認会計士法施行規則第九十六条の規定に基づき組織的な運営に関する原則を指定する件(令和5年1月25日金融庁告示第10号)
13 監査法人のガバナンス・コードの改訂案においても、この考え方は維持されている。
「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)(案)の公表について(令和4年12月26日)
(https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221226_2/20221226.html)
14 この点について、協会は、主に中小監査事務所の支援の観点から、施行規則第95条及び第96条による公表事項を記載するための自主規制上の書類として、「監査品質のマネジメントに関する年次報告書」の作成を求めることとしている。(「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」(第7回)の資料2を参照)
(https://www.fsa.go.jp/singi/governance_code/siryou/20221114.html)
15 ローテーション制度における「監査関連業務」の範囲を定める施行規則第9条第3項第3号を参考に、対象業務に補助者として従事しているにもかかわらず、イからハまでの社員と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる社員とした(施行規則第22条の2)。
16 例えば、社員の配偶者が会社等の使用人である場合には、その社員が当該会社等の監査証明業務の関与社員であるときのほか、全社員の半数以上の者がかかる関係を有しているときは、それぞれ施行令第15条第6号、同条第7号により当該業務の提供が禁止されている。これに対し、社員の「配偶者が会社等の役員等である(又は過去1年以内に役員等であった)」関係については、該当社員の業務内容や人数を問わず、業務提供ができないとされていた。社員の配偶者に着目した利害関係において同様の例は他にないことから、当該関係は、公認会計士法令上の利害関係の中でも特に重要性の高いものとして認識されているものと考えられる。
17 「役員に準ずる者」とは、法律上の役員ではないものの、実質的に役員と同等の地位にある者を想定している。例えば、相談役、顧問等の名称を持つ者が会社等の基本的な方針に影響を与えているような場合には、その者は、「役員に準ずる者」に該当すると考えられる。
18 ロの場合には、文理上、国家公務員・地方公務員として勤務する者や独立行政法人に勤務する者も含まれると考えられる。
19 登録規則第2条3号の考え方については、前掲の「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」No.7からNo.10までを参照。
20 登録規則第2条第3号の改正に伴い、施行日において現に本文に記載したイ又はロの場合に該当している公認会計士等については、施行日から起算して6月以内に同令第6条第1項の変更登録申請書を協会に提出しなければならないとする経過措置を置いている(改正府令附則第4条)。
21 事業年度とは、4月1日から翌年3月31日までの期間をいう(公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(平成16年内閣府令第17号)第1条第1項)。
22 研修の免除を受けている場合であっても外形的には法第21条第2項第3号の「研修を受けていないとき」に当たり得るため、これを除くものである。なお、不受講期間が4事業年度以上である場合には、その1事業年度目に研修の免除を受け、その後3事業年度について研修を受講せず、かつ、免除を受けていないというケースも考えられる。かかるケースは抹消事由に該当するものとして取り扱うことが相当であるから、登録規則第10条第2項の規定上、その旨明文化している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























