解説記事2023年06月19日 レポート 相続土地国庫帰属制度、境界を明らかにすれば山林も対象(2023年6月19日号・№983)
レポート
相続土地国庫帰属制度、境界を明らかにすれば山林も対象
高度な測量の実施までは求めず
全国で広がる所有者不明土地問題の解決策の一環として、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が令和5年4月27日から施行され、「相続土地国庫帰属制度」が導入されている。相続人の中には、農地や山林・森林などを相続したものの、売却が難しいことや、管理しきれないために本制度を利用して手放すことを検討する人もいるだろう。山林等においては境界が不明であることが多く、本制度の対象外であると考えられる向きもあるが、境界が明らかであれば山林であっても対象になる。境界を明らかにするための高度な測量は不要であり、登記事項証明書や地図証明書などで境界を確認して、自分の土地の範囲にプレートなどを設置すれば申請することは可能となっている。
制度開始前に相続した土地も対象
相続土地国庫帰属制度は、相続等により土地の所有権を取得したものの、管理に負担がかかる等の理由から、不要な土地を国に引き取ってもらう仕組みだ。土地を適切に管理することで、将来的な所有者不明土地の発生を抑制することを目的に創設されている(本誌875号16頁参照)。
とはいえ、国が全ての土地を引き取ってくれるわけではない。制度の対象となるのは、相続又は遺贈によって土地を取得した個人で、相続以外(売買など)で自ら土地を取得した個人や、法人による利用はできない。また、土地が共有地である場合には、共有者の中に相続等によって土地を取得した人がいれば、共有者全員で申請することで本制度を利用できる。
このほか、制度の開始前に相続した土地であっても本制度の対象となり、例えば、数十年前に相続で取得した土地も、一定の要件を満たしていれば国庫に帰属させることが可能である。
境界が明らかでない土地等は申請できず
続いて、制度を適用することができない土地の要件を確認する。国が引き取ることができない土地は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下「法」)により定められており、申請をすることができないケースと、承認を受けることができないケースに分かれている(表1参照)。法務省HPには、「相談したい土地の状況について」というチェックシート(https://www.moj.go.jp/content/001390236.pdf)が掲載されており、所有している土地が制度を適用できるか否かを18項目で細かく確認することができる。
【表1】制度が却下・不承認となる要件
| 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項) |
A 建物がある土地 |
| 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項) |
| A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地 |
国による整備が必要な山林は承認できず
制度の概要を確認する限りでは、境界が不明であることが多い山林や森林に本制度を適用することは難しいように見えるが、山林や森林であっても申請することは可能である。
ただし、国による整備(造林、間伐、保育)が必要な山林等に該当する場合は、帰属の承認が得られないとされているため、一律に引き取ってもらえるわけではない。例えば、不承認となる山林には、間伐の実施を確認することができない人工林や、一定の生育段階に到達するまで更新補助作業が生じる可能性がある標準伐期齢に達していない天然林などが該当する(表2参照)。このほか、隣接する土地の所有者が、境界線について異議申し立てをした場合も、境界に争いがあるものとして帰属の承認を得ることはできない。
【表2】帰属の承認ができない森林(山林)
以下のア~ウの3要件、全てに該当する土地は、帰属の承認をすることができない。 |
申請時に境界を明らかにする必要あり
その上で、境界が明らかではない山林等を引き取ってもらうには、申請時に境界を明らかにしておく必要がある。しかし、申請するために高度な測量を実施したり、登記簿等を申請書類として添付する必要はない。法務省によると、地図上に線が引いてあるから境界が明らかであるという判断にはならないため、山林等を帰属させる際は、①現地調査の際に、帰属させる土地の範囲に目印があるか、②帰属させたい土地と、隣接する土地の所有者との間に争いがないか、の2点を確認して判断するとしている。
したがって、境界が明らかではない山林等については、土地家屋調査士に依頼するほか、自分で登記事項証明書や地図証明書などで確認した上で、帰属させたい自分の土地の範囲に目印(紅白ボールやプレートなど)を設置し、それらの写真を申請書に「境界点」として添付することで申請することが可能となる。申請後、国による審査が必要になるが、承認を得ることができれば帰属が決定される。
手数料等の負担金が発生
全ての条件をクリアした場合であっても、国に引き取ってもらう場合は審査手数料や管理費相当額の負担金が発生する。具体的には、申請時に土地一筆あたり14,000円の審査手数料(相当額の収入印紙)が必要になる。手数料の納付後は、申請を取り下げたり、審査の結果、却下・不承認になったりした場合でも返還されない。管理費相当の負担金とは、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費用相当額で、面積にかかわらず原則として20万円(一定の宅地や田・畑の場合、面積区分に応じて算定した額を加算)を支払うことになるが、森林の場合は面積区分に応じて算定される(表3参照)。
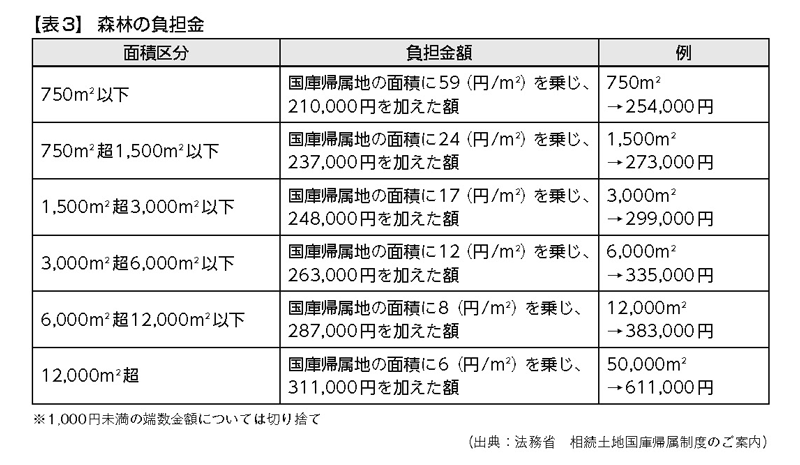
国庫帰属までは、決して低くないハードルだが、不要な土地を手放す一つの選択肢になろう。
原野商法で取得した土地は帰属承認の対象か?
相続した山林等の中には、原野商法(※)で取得した土地である可能性もあるだろう。相続土地国庫帰属制度は、原野商法関連の土地というだけで申請承認できないわけではない。
法務省は、原野商法で取得した土地であっても、相続等によって取得した土地であることや、承認申請する土地の範囲が明らかであること、そして引き取ることができない土地の要件に該当していない土地であれば、承認申請をすることは可能であるとしている。
※原野商法 値上がりの見込みがほとんどない山林や原野を、実際に建築計画がないにもかかわらず「開発計画がある」「もうすぐ道路ができる」などの嘘の説明をすることや、「将来高値で売れる」などと勧誘して、不当に購入させる詐欺的な商法のこと。1970~80年頃に被害が多発したとされている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























