解説記事2024年03月25日 ニュース特集 大量保有報告制度及び公開買付制度の見直し(2024年3月25日号・№1020)
ニュース特集
金商法改正法案が国会提出、施行は公布の日から2年以内
大量保有報告制度及び公開買付制度の見直し
政府は3月15日、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出した。今回の改正法案は、資本市場の活性化に向け、「公開買付」「大量保有報告」「投資運用業」等に関する制度を整備するもの(法律案要綱は今号8頁参照)。公開買付制度の見直しでは、市場内取引(立会内)を同制度の規制の対象とするとともに、公開買付けの実施が義務付けられる議決権割合を現行の「3分の1」から「100分の30」(30%)に引き下げる。また、大量保有報告制度の見直しでは、「共同保有者」の範囲が法令上不明確であることが協働エンゲージメントの支障になっていることから、法令によりその範囲を明確化する。公開買付制度及び大量保有報告制度の見直しに関しては、改正金融商品取引法の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。
今回の改正法案は、金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ」(座長:神田秀樹学習院大学大学院法務研究科教授)が取りまとめた報告書を踏まえたもの。同WGでは、2023年6月から6回にわたり、公開買付制度、大量保有報告制度、実質株主の透明性のあり方について検討を行ってきたが、結論までには至らなかった項目も多かったため、今回の改正は必要最低限のものにとどまっている。
市場内取引(立会内)も公開買付けの対象
現行の公開買付制度では、①多数の者(60日間で10名超)からの市場外取引による買付け等の後の株券等所有割合が5%超となる場合(いわゆる5%ルール)、②市場外取引又は市場内取引(立会外)による買付け等の後の株券等所有割合が3分の1超となる場合(いわゆる3分の1ルール)に公開買付けの実施が義務付けられているが、立会内については、誰もが参加でき、取引の数量や価格が公表され、競争売買の手法によって価格形成が行われるといった点で、一定の透明性・公正性が担保されているとの考え方に基づき、公開買付制度の対象となっていない。
投資判断に必要な情報・時間が不十分
公開買付けの実施が義務付けられているのは、会社支配権に重大な影響を及ぼすような証券取引の透明性・公平性を確保する観点から設けられたものであるが、昨今では市場内取引等を通じた非友好的買収事例が増えているといった状況がある。
例えば、アジア開発キャピタルが東京機械製作所の買収防衛策の差し止めを求めた事件では、東京高裁が「抗告人らは、TOBの適用対象外である市場内取引における株式取得を通じて、株券等所有割合が3分の1を超える株式を短期間のうちに買収しており、このような買収行為は、一般株主からすると、投資判断に必要な情報と時間が十分に与えられず、買収者による経営支配権の取得によって会社の企業価値がき損される可能性があると考えれば、そのリスクを回避する行動をとりがちであり、それだけ一般株主に対する売却への動機付けないし売却へ向けた圧力(強圧性)を持つものと認められる」と判示(令和3年11月9日決定)し、東京機械製作所の買収防衛策を認めている。同事件では、アジア開発キャピタルが約4か月間で39.94%の東京機械製作所の株式を市場内取引(立会内)により取得していたものである。
諸外国と同様、閾値を30%に引き下げ
このような状況を踏まえ、改正法案では、市場内取引(立会内)についても3分の1ルールの適用対象に見直すこととされた(改正法案27条の2、図1参照)。
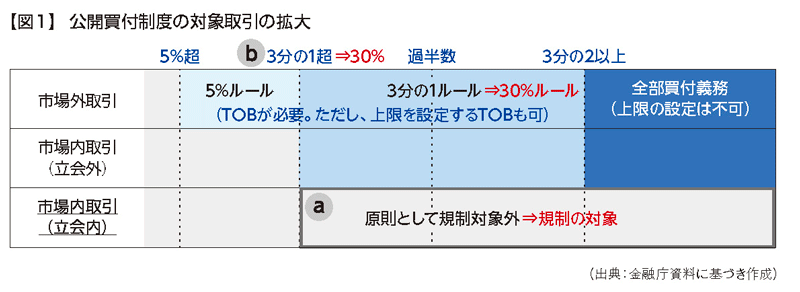
また、この3分の1ルールの閾値については、「30%」に引き下げる(改正法案27条の2)。諸外国の公開買付制度では30%としている例が多く、加えて日本の上場会社の議決権行使割合が90%未満であることを勘案すると、30%の議決権を有していれば、多くの上場会社において株主総会の特別決議を阻止することが可能であるからだ。
公開買付説明書の内容を簡素化
そのほか、公開買付説明書の内容が公開買付届出書とほぼ同じ内容となっており、その効果に比べて公開買付説明書の交付・訂正に関する事務負担が大きいとの指摘を踏まえ、公開買付届出書を参照すべき旨を記載した場合には、公開買付説明書に記載したものとみなすことができるようにする(改正法案27条の9)。
施行の以後に行う公開買付けから適用
なお、これらの改正の施行日は公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日とされており、施行日以後に行う公開買付けに適用することとされている(改正法案附則1条三号、2条)。
公開買付WG報告で結論出ず、法改正は見送りに
金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ」での議論は多岐にわたって行われたが、結論までには至らなかった項目も多い。このため、結論の出ていない項目については、軒並み今回の改正項目には盛り込まれていない。
例えば、第三者割当増資(新株発行)により議決権の3分の1超を取得するような場合には公開買付制度の対象とすべきか否かが検討されたが、企業の資金調達を阻害しないためには例外を柔軟に認めるための体制(専門性・機動性を有する機関)が必要との意見もあり、公開買付けの実施を義務付けるまでにはなっていない。また、急速な買付け等の規制の廃止や、部分買付けの禁止なども結論には至っていない。
そのほか、公開買付けに関する事前の救済制度として、対象会社やその株主に法令違反又は著しく不公正な方法による公開買付けを差し止める権利を付与する制度の導入を、事後の救済制度として、公開買付制度に違反して取得した株式について議決権を停止する制度や売却命令を賦課する制度の導入について検討が行われたが、導入に賛成する意見があった一方、乱用的な制度利用のおそれに関する懸念などから必要に応じて引き続き検討することとされている。
配当方針や資本政策の変更の提案であれば「共同保有者」に該当せず
大量保有報告制度とは、市場の透明性・公正性を高め、投資者保護を図ることを目的として、株券等の大量保有者(株券等保有割合が5%超である者)となった場合には、その日から5営業日以内に大量保有報告書を提出し、また、その後、株券等保有割合が1%以上増減するなど重要な変更があった場合には、その日から5営業日以内に変更報告書を提出するというもの(一般報告制度)。また、金融商品取引業者等については、提出頻度や期限等を緩和する「特例報告制度」が設けられている。具体的には、事前に届け出た月2回の基準日において、大量保有報告書・変更報告書の提出義務を判断し、当該基準日から5営業日以内に大量保有報告書・変更報告書を提出すればよいとされている。
「共同保有者」の範囲が不明確
昨今では、投資家が企業と対話することが求められており、複数の投資家が協調して個別の投資先企業に対し特定のテーマについて対話を行うこと(協働エンゲージメント)により、質的・量的なリソース不足を補い、対話の実効性を高めることが重要とされている。
この点、大量保有報告制度では、複数の投資家が「共同保有者」(共同して株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している者)に該当すれば、合意した保有割合が5%超になれば、大量保有報告書の提出が求められることになる。しかし、大量保有報告制度における「共同保有者」の範囲が法令上不明確であることが協働エンゲージメントを行う上での支障になっていると指摘されている。
一定の外形的事実があれば「共同保有者」
このため、改正法案では、協働エンゲージメントの促進の観点から「共同保有者」の範囲を明確化する(図2参照)。
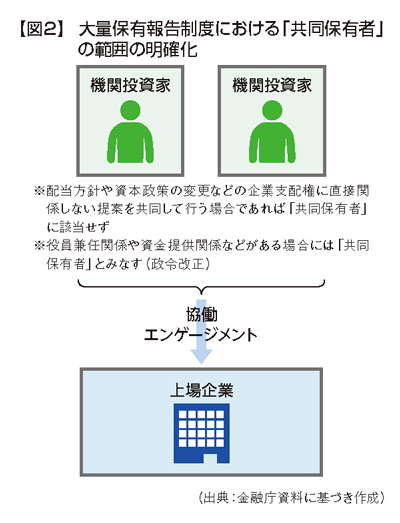
複数の投資家が「経営に重大な影響を与えるような合意」を行わない限り、例えば、配当方針や資本政策の変更などの企業支配権に直接関係しない提案を共同して行う場合であれば、「共同保有者」に該当しないこととしている(改正法案27条の23第5項)。
その一方で、役員兼任関係や資金提供関係などがある場合には「共同保有者」とみなす規定を講じる。2008年の金商法の改正により、大量保有報告書等の不提出及び不実記載が課徴金制度の対象とされたものの、その後も大量保有報告書等の提出遅延は相次いでおり、実効性の面で懸念が生じている。特に共同保有者の認定に係る立証が難しいことから、複数の投資家が協調して株券等を取得していることが疑われる事例なども見受けられるため、一定の外形的事実がある場合には「共同保有者」とみなす政令改正を行うとしている。
現物決済型への変更が前提のデリバティブは大量保有報告制度の対象
そのほか、現行、現金決済型のデリバティブについては、基本的に大量保有報告制度の適用対象となっていないが、現物決済型デリバティブに変更することを前提としているものについては、大量保有報告制度の適用対象とする(改正法案27条の23第3項)。このようなデリバティブについては、取引を開始した時点で潜在的に経営に対する影響力を有しているものと考えられるからだ。
例えば、①取引の相手方から株券等を取得することを目的とするもの、②取引の相手方が保有する株券等に係る議決権行使に一定の影響力を及ぼすことを目的とするもの、③これら①②のような地位にあることをもって発行会社に重要提案行為等を行うことを目的とするもの等が想定されている。
「共同保有者」の見直しで新旧の株券等保有割合が異なる場合は?
なお、大量保有報告制度の見直しについても、施行日は公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日とされている(改正法案附則1条三号)。
ただし、留意しなければならないのは、今回の「共同保有者」の見直しにより、株券等の保有割合が異なってしまうケースだ。当該差については、新しい株券等保有割合が増加又は減少したものとみなして、改正後の大量保有報告制度が適用されることになる(改正法案附則5条)。
重要資料
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案要綱
市場の透明性・公正性を確保しつつ、資産運用の高度化・多様化を図るため、取引所における競売買の方法による取引を公開買付規制の対象に追加するほか、大量保有報告制度において保有割合の合算が求められる者の範囲の明確化、委託を受けて投資運用業に関する業務の一部を行う業者の任意的登録制度の創設等の措置を講ずる必要がある。このため、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正することとする。
一 金融商品取引法の一部改正(第1条関係)
1.株券等の公開買付規制に関する規定の見直し
(1)取引所における競売買の方法による取引を公開買付規制の対象に追加することとする。
(金融商品取引法第27条の2関係)
(2)公開買付けの実施が義務付けられる議決権割合を3分の1から100分の30に引き下げることとする。
(金融商品取引法第27条の2関係)
(3)公開買付届出書を参照すべき旨等を記載した場合には、公開買付説明書に記載したものとみなすこととする。
(金融商品取引法第27条の9関係)
2.株券等の大量保有報告制度に関する規定の見直し
(1)大量保有報告制度において保有割合の合算が求められる者の範囲に関し、金融商品取引業者等が経営に対して重要な影響を及ぼす行為を行うことを目的とせずに、株主としての権利を共同して行使する場合については、保有割合の合算が求められないこととする。
(金融商品取引法第27条の23関係)
(2)現金による決済が予定されているデリバティブ取引のうち、一定の要件を満たすものを大量保有報告書の提出義務の対象とすることとする。
(金融商品取引法第27条の23関係)
3.投資運用関係業務受託業に係る制度の導入
(1)任意的登録制の創設
① 投資運用関係業務受託業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受けることができることとし、登録申請書の記載事項及び添付書類、登録拒否要件その他の登録手続に関する規定を整備することとする。
(金融商品取引法第2条、第66条の71~第66条の75関係)
② 投資運用関係業務受託業者について、誠実義務、忠実義務、業務管理体制の整備義務、禁止行為その他の業務に関する規定を整備することとする。
(金融商品取引法第66条の76~第66条の81関係)
③ 投資運用関係業務受託業者に対する業務改善命令、業務停止命令、登録取消処分、報告徴取及び検査その他の監督に関する規定を整備することとする。
(金融商品取引法第66条の82~第66条の89関係)
(2)金融商品取引業者等に関する規定の整備
① 金融商品取引業者等が投資運用関係業務を委託する場合には、登録申請書又は届出書に委託先の商号等を記載させることとする。
(金融商品取引法第29条の2、第33条の8、第63条の9、附則第3条の3関係)
② 金融商品取引業者等の登録拒否要件等のうち、人的構成要件の内容を明確化するとともに、投資運用関係業務受託業者に投資運用関係業務を委託する場合には、当該業務の執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員等の確保に代えて、当該業務の執行の監督に係る役員等を確保していれば足りることとする。
(金融商品取引法第29条の4、第33条の5、第33条の8、第63条の9、附則第3条の3関係)
4.投資運用業に関する規定の整備
(1)金融商品取引業の登録申請書の記載事項として、投資運用業に関して顧客から金銭等の預託を受けない場合にはその旨を記載させることとする。
(金融商品取引法第29条の2、第31条関係)
(2)投資運用業者が運用を行う権限を委託する場合に、運用の対象及び方針を決定する権限を委託してはならないこととし、それ以外の運用を行う権限の全部を委託できることとする。
(金融商品取引法第42条の3関係)
5.非上場有価証券特例仲介等業務に関する規定の整備
特定投資家等を対象とした非上場有価証券の仲介等の業務のみを行う第一種金融商品取引業者について、自己資本規制比率に関する規制、兼業規制及び金融商品取引責任準備金の積立に関する規制の適用を除外することとする。
(金融商品取引法第2条、第29条の4の4関係)
6.私設取引システム運営業務に関する規定の整備
(1)流動性の低い非上場有価証券のみを取り扱い、かつ、取引規模が限定的である私設取引システム運営業務については、その業務を行うに当たっての認可を要さないこととし、第一種金融商品取引業の登録により行えることとする。
(金融商品取引法第30条関係)
(2)金融商品取引業者が(1)の私設取引システム運営業務に関する業務の内容及び方法のうち公益又は投資者保護の観点から特に必要がある事項を変更する場合は、変更の30日前までに内閣総理大臣に届け出なければならないこととする。
(金融商品取引法第31条関係)
7.その他
その他所要の規定の整備を行うこととする。
二 投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正(第2条関係)
1.運用権限の委託に関する規定の整備
投資信託委託会社及び投資法人の資産運用会社の運用の委託に関し、金融商品取引法第42条の3の改正に準じて、所要の規定の整備を行うこととする。
(投資信託及び投資法人に関する法律第12条、第202条、第204条、第214条関係)
2.その他
その他所要の規定の整備を行うこととする。
三 その他
1.施行期日
この法律は、原則として、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
(附則第1条関係)
2.経過措置等
(1)この法律の施行に伴い、所要の経過措置を定めることとする。
(附則第2条~第10条、第17条、第18条関係)
(2)金融商品取引法の改正に伴い、関係法律の改正を行うこととする。
(附則第11条~第16条関係)
(3)この法律の施行の状況等に関する検討規定を設けることとする。
(附則第19条関係)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























