解説記事2024年05月20日 法令解説 四半期報告書制度の廃止等に係る金融商品取引法等の改正(2024年5月20日号・№1027)
法令解説
四半期報告書制度の廃止等に係る金融商品取引法等の改正
金融庁企画市場局企業開示課開示企画調整官 上利悟史
元 金融庁企画市場局企業開示課課長補佐 牧野一成
金融庁企画市場局企業開示課課長補佐 鹿子木慎亮
金融庁企画市場局企業開示課専門官 七海健太郎
一 はじめに
2023年11月20日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号。以下、「改正法」という。)が成立した。
これにより、本年4月1日より、金融商品取引法上の四半期報告書制度が廃止され、四半期開示制度は証券取引所規則に基づく四半期決算短信に「一本化」されるとともに、有価証券報告書提出会社に対し、一律に半期報告書の提出が求められることとなる。また、同法では、四半期報告書制度の廃止に伴い、各開示書類の公衆縦覧期間の延長も行われている。
なお、同法の施行に伴い、本年3月27日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(令和6年政令第71号。以下、「整備政令」という。)及び「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(令和6年内閣府令第29号。以下、「整備府令」という。)等が公布されている。
本稿では、これらの改正の経緯、内容及び施行時期について解説を行うものであるが、意見にわたる部分については、筆者らの個人的見解である。
二 本改正の経緯
四半期報告書は、2008年度から、上場企業の四半期ごとの経営成績や財政状態に関する充実した情報を、比較可能性と信頼性を確保しながら投資家に提供する役割を担ってきた。しかし他方で、近年、企業経営や投資家の投資判断において、サステナビリティに関する情報を重視する動きが見られる中、企業開示においても、中長期的な企業価値に関連する非財務情報の重要性が増大し、企業に対し、これらの非財務情報のより充実した開示が求められるようになった。また、このような開示事項の拡充により企業の開示負担が増加傾向にある中で、四半期ごとの開示はその負担が大きく、特に、四半期報告書と四半期決算短信の開示内容等には重複も見られることから、開示負担の軽減や効率化の観点から、四半期開示制度の見直しを図るべきであるとの指摘もされるようになった。
このような状況を踏まえ、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(以下、「DWG」という。)において四半期開示制度についての検討が行われ、2022年6月に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告(脚注1)において、
・四半期報告書と四半期決算短信について、内容面の重複や開示タイミングの近接がみられることから、両者の「一本化」による開示の効率化が考えられる
・「一本化」の具体的な方法については、速報性や投資家にとっての有用性の観点から、法律上の四半期開示義務(第1・第3四半期)を廃止し、四半期決算短信に「一本化」することが適切である
との方向性が示された。
その後、DWGは、2022年12月に、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告(脚注2)を公表し、四半期決算短信への「一本化」を前提に、その具体的な方向性について提言を行った。その詳細は図表1のとおりであるが、概要としては、①四半期報告書制度を廃止し、上場企業に対しては、現行の第2四半期報告書と同程度の記載内容の半期報告書を決算後45日以内に提出することを求めること、②半期報告書及び臨時報告書の公衆縦覧期間を5年間に延長すること、③その他「一本化」に伴う四半期決算短信制度の見直しについての提言がされた。
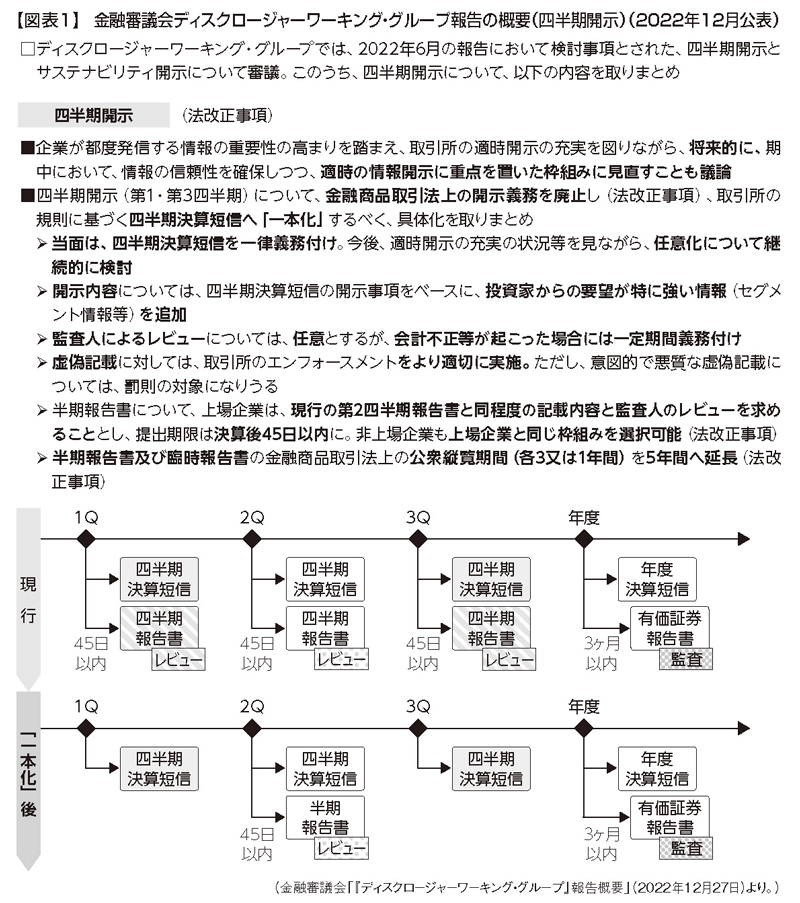
これらの提言を踏まえ、金融商品取引法の規定の見直しを行い、2023年11月20日、第212回国会において、四半期報告書制度の廃止等を内容とする「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立した(脚注3)。
三 本改正の内容
改正法の概要は図表2のとおりである。本改正は、四半期報告書制度を廃止し、すべての有価証券報告書提出会社に対して半期報告書の提出を義務付けるとともに、各種開示書類の公衆縦覧期間を延長するものとなっている。また、整備府令の概要は図表3のとおりであるが、上場会社等が提出する半期報告書に関する規定の整備のほか、有価証券届出書に記載する四半期情報に関する規定の見直しや臨時報告書の提出事由の追加等を行うこととしている。
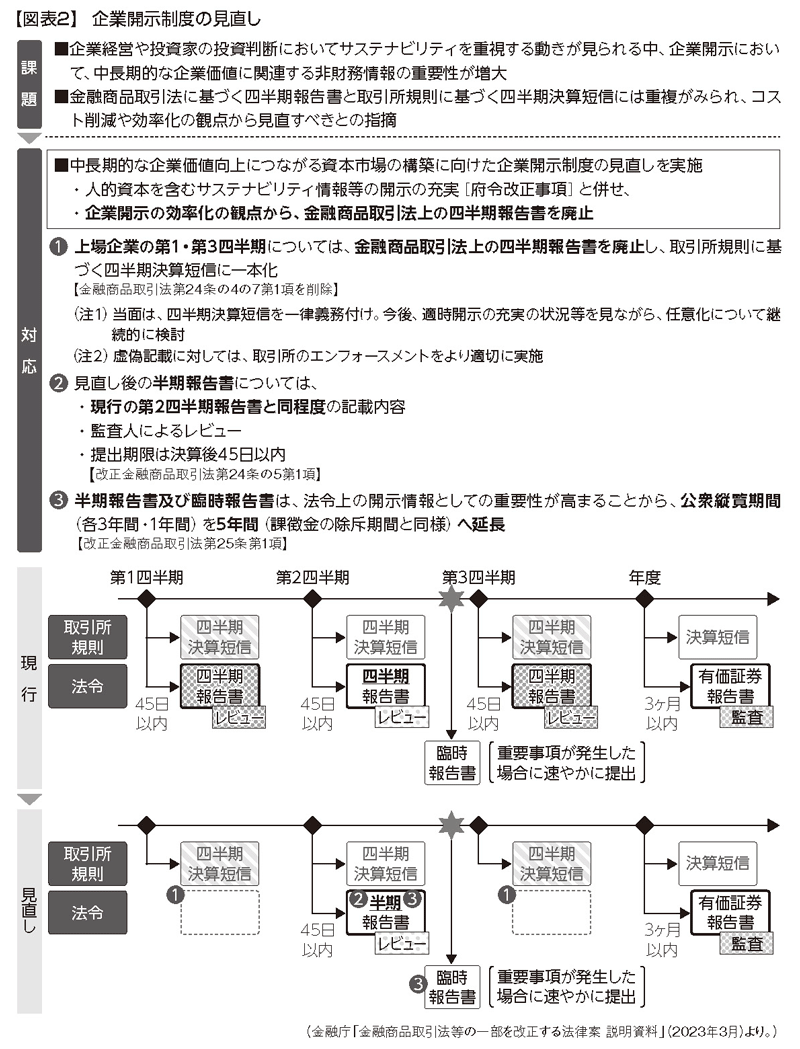
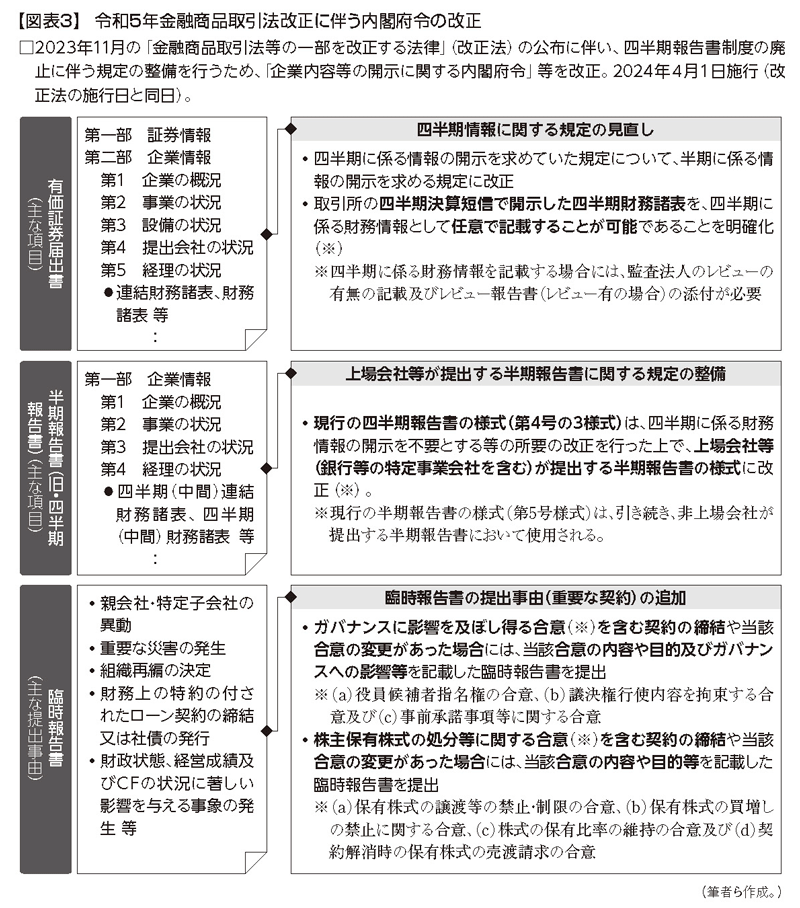
以下、改正点の解説を行う。なお、以下では、本改正前の金融商品取引法を「旧法」、本改正後の金融商品取引法を「新法」、整備政令による改正後の金融商品取引法施行令を「新令」、整備府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令を「新開示府令」という。
1 四半期報告書に関する規定の廃止
新法では、四半期報告書に関する規定(旧法第24条の4の7及び第24条の4の8等)を削除している。これにより、これまで上場会社等に要請されていた四半期報告書の提出義務が撤廃されることとなる。
2 半期報告書に関する規定の改正
新法では、四半期報告書の提出義務が廃止されたことに伴い、これまで四半期報告書提出会社以外の有価証券報告書提出会社に義務付けていた半期報告書の提出を、すべての有価証券報告書提出会社に対して義務付けることとした(新法第24条の5第1項)。
そして、新法では、提出会社の種類に応じ、以下のとおり、提出すべき半期報告書の内容及びその提出期限について定めている。
(1)上場会社等が提出する半期報告書
新法では、上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものを含む)の発行会社等(以下「上場会社等」という。)について、事業年度開始後6月間の当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項(これまでの上場事業会社の四半期報告書の記載事項を想定。以下「半期報告書共通記載事項」という。)を記載した半期報告書を、半期経過後45日以内の政令で定める期間内に提出しなければならないこととしている(新法第24条の5第1項の表の第1号)。この記載内容及び提出期限は、旧法において上場会社等に提出が求められていた第2四半期に係る四半期報告書の記載内容及び提出期限と同様である。
旧法における半期報告書(上場会社等以外の会社に提出が求められていたもの)は、当該会社の属する企業集団に係る財務情報(以下「連結情報」という。)に加え、当該会社単体の財務情報(以下「単体情報」という。)も記載しなければならず、その提出期限は半期経過後3月以内とされていた。しかし、DWGにおいて、
・流通性の高い有価証券を発行する上場会社等に対しては情報の早期開示を求めるべき
・これまで四半期報告書において連結情報のみを開示していた上場会社等に対してさらに単体情報の開示を求めることは、定期開示の負担軽減による企業開示の効率化という趣旨に反する結果となりかねない
などの意見が出されたことを踏まえ、新法では、旧法における四半期報告書と同様、上場会社等に対し、連結情報のみを記載した半期報告書を半期経過後45日以内の政令で定める期間に提出することを求めることとしたものである。
具体的な提出期限及び開示内容(半期報告書共通記載事項の内容)については、上記の改正経緯を踏まえ、整備政令及び整備府令において、提出期限については旧法に基づく第2四半期報告書と同じ45日以内とし(新令第4条の2の10第2項)、記載内容についても、旧法に基づく第2四半期報告書と同程度のものとすることとしている(新開示府令第4号の3様式)。さらに、半期報告書に含まれる財務諸表に対する監査証明についても、これまでの実務への配慮や国際的な整合性の観点から旧法における半期報告書に含まれる財務諸表に対して求められていた中間監査ではなく、旧法における四半期報告書に含まれる財務諸表と同様、レビューとしている(脚注4)。
なお、当該レビューは、企業会計審議会が2024年3月27日に公表した期中レビュー基準(脚注5)に準拠して行われる。
(2)上場会社等のうち特定事業会社が提出する半期報告書
新法では、上場会社等のうち金融システムの安定を図るためその業務の健全性を確保する必要がある事業として内閣府令で定める事業を行う会社について、事業年度開始後6月間の半期報告書共通記載事項に加え、当該会社に係るこれと同様の事項として内閣府令で定める事項(これまで特定事業会社の第2四半期報告書において記載が求められてきた単体情報を想定)を記載した半期報告書を、半期経過後60日以内の政令で定める期間内に提出しなければならないこととしている(新法第24条の5第1項の表の第2号)。
本規定は、旧法における四半期報告書の提出義務を負う銀行や保険会社等のいわゆる特定事業会社に対する取扱いを、新法においても引き継ぐものであり、そのため、この規定における「上場会社等のうち金融システムの安定を図るためその業務の健全性を確保する必要がある事業として内閣府令で定める事業を行う会社」とは、銀行や保険会社など、旧法における「上場会社等のうち内閣府令で定める事業を行う会社」(旧法第24条の4の7第1項後段)に該当する会社を想定している。
すなわち、銀行や保険会社等は、その業務運営の健全性を確保し、金融システムの安定を図る観点から、半期ごとに、単体情報を基準とした自己資本比率に係る規制を受けており、これに反すると、業務停止などの行政処分を受けることになる。このことから、これらの会社に係る単体情報は、当該会社の自己資本比率の状況を把握し、同社に対する行政処分の可能性を検討するなどの手段として、投資家の投資判断にとって重要な情報であるといえる。そこで、旧法では、上場会社のうち、銀行や保険会社等のいわゆる特定事業会社に対し、第2四半期に係る四半期報告書において、連結情報のみならず単体情報である中間財務諸表の開示を義務付けるとともに、その提出期限を60日に延長していたものであるが、これらの会社に係る単体情報の重要性は改正後も変わらないことから、新法においても、上記の取扱いを継続することとしたものである(脚注6)。
具体的な提出期限及び開示内容については、上記の改正経緯を踏まえ、整備政令及び整備府令において、提出期限については旧法に基づく第2四半期報告書と同じ60日以内とし(新令第4条の2の10第3項)、記載内容についても、旧法に基づく第2四半期報告書と同程度のものとすることとしている(新開示府令第4号の3様式)。
(3)非上場会社が提出する半期報告書
上場会社等以外の有価証券報告書提出会社(非上場会社)の半期報告書の提出義務については、旧法からの実質的な変更はない。すなわち、非上場会社は、事業年度開始後6月間の半期報告書共通記載事項に加え、当該会社に係るこれと同様の事項(単体情報)及びこれらを補足する事項として内閣府令で定める事項(これまで非上場会社の半期報告書において記載が求められてきた事項を想定)を記載した半期報告書を、半期経過後3月以内に提出しなければならないこととしている(新法第24条の5第1項の表の第3号)。
もっとも、旧法において、非上場会社に対して任意で四半期報告書を提出することが認められていたこと(旧法第24条の4の7第2項)からすると、新法においても、より簡易な内容の半期報告書を早期に提出する企業側のニーズが引き続き存在するものと考えられる。そこで、非上場会社については、上記の半期報告書を提出する代わりに、連結情報のみを記載した半期報告書(上記(1)の半期報告書)を、半期経過後45日以内の政令で定める期間内に提出(当該非上場会社が、銀行や保険会社など新法第24条の5第1項の表の第2号上欄に掲げる会社に当たる場合にあっては、上記(2)の半期報告書を半期経過後60日以内の政令で定める期間内に提出)することも可能としている(新法第24条の5第1項ただし書)。
(4)有価証券届出書における「四半期に係る財務情報」の記載
本改正前の有価証券届出書においては、四半期報告書を提出する会社は、その提出時期に応じて特定の四半期に係る四半期連結財務諸表や四半期財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)を併せて掲げる必要があった。しかし、改正法により四半期報告書の提出義務が廃止されたことに伴い、上場会社等は、金融商品取引法の規定に基づく四半期財務諸表等を作成する必要がなくなったため、新開示府令においては、有価証券届出書において四半期財務諸表等の記載を求めないこととした(新開示府令第2号様式等)。
一方で、上場会社は、引き続き、金融商品取引所の定める規則による四半期財務諸表等を記載した四半期決算短信を公表する必要があるが、資金調達に当たって、当該四半期財務諸表等を記載した有価証券届出書を提出する実務の継続を望む意見もあることから、当該四半期財務諸表等を「四半期に係る財務情報」として任意で有価証券届出書に記載できることとした(脚注7)。そして、四半期に係る財務情報を有価証券届出書に記載する場合には、期中レビュー(脚注8)の有無の記載を求めることとし、期中レビューが行われている場合には当該期中レビューに係る期中レビュー報告書の添付を求めることとした(開示ガイドライン5−21−2)。
なお、有価証券届出書における四半期に係る財務情報の記載は任意であるため、当該記載を行わなかったこと自体をもって、金融商品取引法第21条の2等の規定により賠償責任が求められる場合となる「記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているとき」に該当するものではないと考えられるが、記載した四半期に係る財務情報において、重要な事項についての虚偽の記載等がある場合には、賠償責任等の対象になると考えられる(脚注9)。
(5)臨時報告書の提出事由の追加
2022年12月に公表された「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告では、四半期報告書の廃止に伴い、四半期報告書において直近の有価証券報告書の記載内容から重要な変更があった場合に開示が求められてきた事項については、当該事項が元々、有価証券報告書における記載事項であることを踏まえると、これらに重要な変更があれば、同じ金融商品取引法上の報告書である臨時報告書の提出事由とすることが考えられるとしており、具体的な提出事由の例示として、「重要な契約」を示している。
本改正では、これらの提言を踏まえて、2023年12月22日に公布された内閣府令改正により新たに有価証券報告書の開示事項とされた、「企業・株主間のガバナンスに関する合意」及び「企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意」を含む契約の締結・変更について、新たに臨時報告書の提出事由に追加することとした(脚注10)(新開示府令第19条第2項第12号の2及び第12号の3)。
(6)財務諸表等規則の見直し
本改正前は、財務諸表等に係る規則は、それぞれ、連結・単体、そして、年度・中間・四半期の組み合わせで合計6つの内閣府令及びガイドラインから構成されていた。この財務諸表等に係る規則の構成に関し、利用者の利便性向上の観点などから、内閣府令については連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下合わせて「財務諸表等規則等」という。)、ガイドラインについては連結財務諸表規則ガイドライン及び財務諸表等規則ガイドラインを存続することとし、四半期及び中間に係る内閣府令及びガイドラインを廃止の上、当該規定は年度の規則に統合することとした。
整備府令による改正後の財務諸表等規則等(以下「新財務諸表等規則等」という。)の構成について、まず、四半期報告書制度の廃止により、上場会社も半期報告書を提出することとなり、銀行や保険会社等のいわゆる特定事業会社や非上場会社と同様に「中間財務諸表」を作成することとなったため、本改正後は「中間財務諸表」が2種類存在することとなる。これらを見分けるため、条文上、旧法に基づく第2四半期報告書に係る四半期財務諸表を「第一種」中間財務諸表と、特定事業会社や非上場会社が提出する半期報告書に係る中間財務諸表を「第二種」中間財務諸表と区分している(連結も同様。以下同じ。)。そして、各中間財務諸表のうち、第一種中間財務諸表については、四半期から半期に制度が変わることとなるが、記載する内容は旧法に基づく第2四半期報告書と同程度のものとされているため、原則として、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(2024年4月1日廃止)で規定されていた内容をそのまま第一種中間財務諸表の規定として移設している。また、第二種中間財務諸表については、旧法からの実質的な変更はないため、原則として、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(2024年4月1日廃止)で規定されていた内容をそのまま第二種中間財務諸表の規定に移設している。なお、第一種中間財務諸表、第二種中間財務諸表の別について、半期報告書の「経理の状況」の冒頭に記載を求めることとした。
以上のとおり、新財務諸表等規則等の内容面における変更はほとんど無いが、財務諸表等に係る規則の見直しに関して留意すべき点を3点挙げておく。
まず、会計期間の単位についてである。今般の改正により、四半期開示は決算短信に一本化され、法定制度としての四半期開示制度は廃止されたことから、期中の法定開示である半期報告書を作成するにあたっては、6か月を一つの会計期間として作成することとなる。
2点目は、比較情報の取扱いについてである。新財務諸表等規則等の附則において、比較情報の記載を免除する規定は設けていない。これは、従前四半期報告書を提出していた上場会社(上場特定事業会社を除く。)にとっては、本改正は四半期報告書制度から半期報告制度への移行という制度変更があり、適用される会計基準も四半期財務諸表に関する会計基準(以下「四半期会計基準」という。)から中間財務諸表に関する会計基準(以下「中間会計基準」という。)に変わるものの、中間会計基準における各種経過措置により従来の四半期会計基準で認められていた会計処理をそのまま継続することが可能なものとなっている。したがって、前第2四半期累計期間と同一の会計処理を継続していれば、当該期間の情報を修正することなく比較情報として掲載が可能であると考えられることから、原則どおり比較情報を求めることとしたものである。
3点目は、四半期会計基準の告示指定削除についてである。財務諸表等規則等においては、「金融商品取引法の規定により提出される財務諸表」を作成するうえで必要となる企業会計の基準を告示指定することとしているところ、本改正に伴い、四半期会計基準を指定から削除するとともに、中間会計基準を新たに指定している。この四半期会計基準の告示指定からの削除に関し当該指定からの削除という事実のみをもって、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準として実務の中で取り扱われなくなることは想定していない。また、期中レビュー基準における「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」は、財務諸表等規則等に基づき金融庁長官が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとして告示指定した企業会計の基準に限られるものではなく、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準として実務の中で取り扱われる企業会計の基準も含まれるものと考えられる。
3 公衆縦覧期間の延長
新法では、参照方式の届出書、発行登録書及び発行登録追補書類、半期報告書及び半期報告書の確認書並びに臨時報告書(これらの訂正書類を含む)の公衆縦覧期間を5年に延長することとしている(新法第25条第1項)。
四半期報告書の廃止により期中の法定開示として残る半期報告書及び臨時報告書は、旧法において、半期報告書は3年間、臨時報告書は1年間、それぞれ公衆縦覧に供することとされていた。しかし、DWGにおいて、
・半期報告書及び臨時報告書の公衆縦覧期間は、いずれもこれらの書類の虚偽記載に対する課徴金納付命令の除斥期間(5年間。金融商品取引法第178条第11項)よりも短く、課徴金納付命令の際に当該命令の対象となる縦覧書類の公衆縦覧期間が終了していることがあり、全体的な企業情報の把握等の観点から問題がある
・四半期報告書の廃止に伴い、半期報告書及び臨時報告書の法定開示上の重要性が高まることに加え、特に臨時報告書は、今後、取引所規則による適時開示情報の信頼性を確保する役割をより一層担っていくことが期待されていることから、これらの書類の公衆縦覧期間を延長することは、より適切な投資判断に資すると考えられる
などの指摘がされ、半期報告書及び臨時報告書の公衆縦覧期間を、課徴金納付命令の除斥期間である5年間に延長することが考えられる旨の提言がされた。
そこで、上記提言を受け、半期報告書及び臨時報告書のほか、課徴金納付命令の除斥期間よりも短い公衆縦覧期間が設定されていた他の開示書類について、その公衆縦覧期間を5年間に延長することとしたものである。
四 施行時期
これらの四半期報告書等に関する規定は、いずれも2024年4月1日を施行日としている(改正法附則第1条第3号、整備政令附則第1条及び整備府令附則第1条)が、以下の経過措置が設けられている。
1 四半期報告書の廃止に関する経過措置
四半期報告書の提出義務は、施行日から廃止されるが、施行日前に開始した四半期については、施行日以後も、引き続き旧法の規定に基づく四半期報告書の提出義務を負う(改正法附則第2条第1項)。例えば、12月決算会社の場合、第1四半期(2024年1月1日から2024年3月31日まで)が施行日前に開始するため、2024年4月1日以後も、旧法の規定に基づき、当該四半期に係る四半期報告書を提出する義務を負う。
なお、施行日前に提出された四半期報告書や、上記経過措置に基づいて施行日以後に提出された四半期報告書については、旧法の規定が引き続き適用される(改正法附則第2条第3項)。例えば、有価証券届出書において組込方式や参照方式を利用する場合には、施行日以後も、新たに有価証券報告書が提出されるまでは、直近の有価証券報告書以後に提出された四半期報告書を添付しなければならず(同条第4項)、四半期報告書の不提出や虚偽記載に対する課徴金に関する規定についても、施行日後も旧法の規定が適用される(同条第5項から第7項)。
2 半期報告書の提出に関する経過措置
新法の規定に基づく半期報告書は、施行日以後に開始する事業年度から提出が義務付けられ(改正法附則第3条第1項)、新開示府令の規定に基づく半期報告書の様式も同日以後に開始する事業年度に提出するものから適用となる。そして、施行日前に事業年度が開始する四半期報告書提出会社については、旧法の規定が適用されることから、当該事業年度に係る半期報告書の提出は求められない。
しかし、このような四半期報告書提出会社のうち、施行日前に事業年度が開始し、かつ、施行日以後に第2四半期が開始する会社(12月決算会社、1月決算会社及び2月決算会社)については、施行日を含む事業年度から、半期報告書を提出する必要がある(改正法附則第3条第2項)。このような会社は、第2四半期が施行日以後に開始することから、第2四半期に係る四半期報告書の提出義務を負わない(同附則第2条第1項参照)ため、半期報告書の提出を義務付けないと、施行日以後の最初の第2四半期に、四半期報告書・半期報告書のいずれも提出されないことになり、投資家に対する情報提供の観点から問題がある事態となる。そのため、このような会社については、例外的に、施行日を含む事業年度から、半期報告書の提出を求めることとしたものである。
四半期報告書の廃止及び半期報告書の提出に関する経過措置の具体例については、図表4のとおりである。
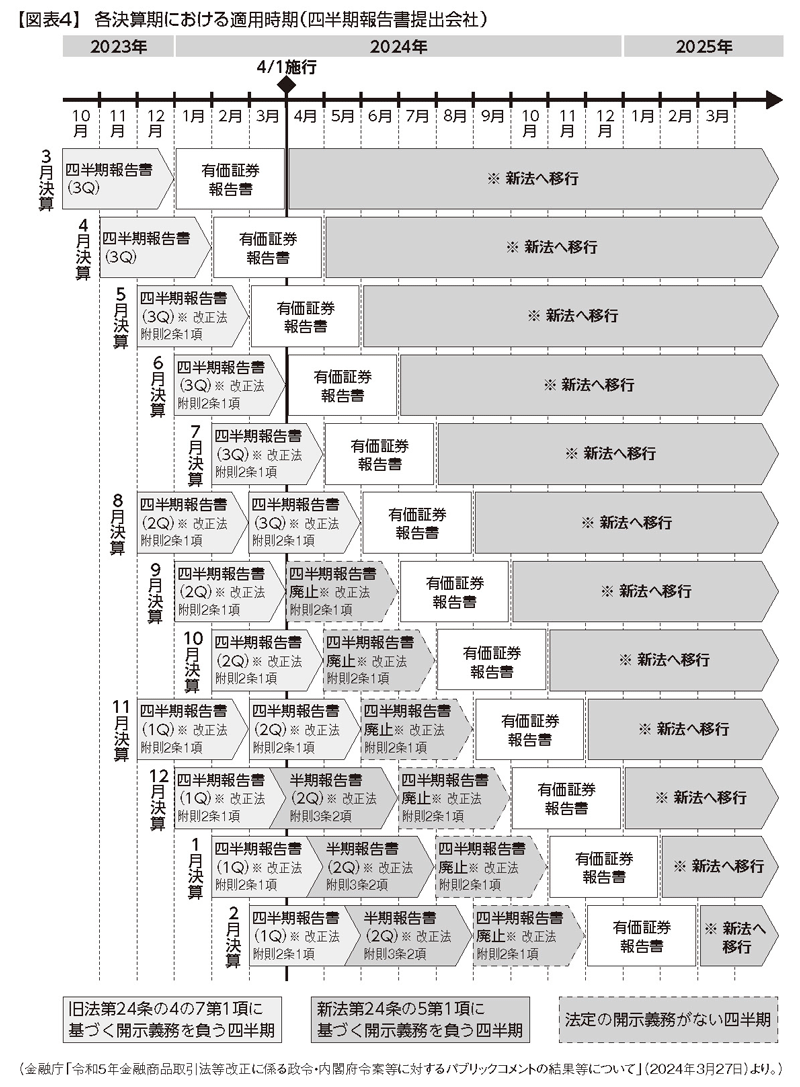
3 有価証券届出書及び有価証券報告書の提出に関する経過措置
新開示府令における有価証券届出書に関する様式については、施行日以後最初に有価証券報告書を提出した時から適用することとしている(整備府令附則第4条第1項~第4項)。ただし、改正法附則第3条第2項の規定により、施行日前から開始している事業年度についての半期報告書を提出する会社にあっては、当該半期報告書を提出した時から、改正後の様式を適用することとなる(整備府令附則第4条第3項)。
なお、改正法により、施行日以後開始する四半期から四半期報告書が廃止されるため、上場会社等の決算日によっては、例えば、第1四半期及び第2四半期に係る四半期報告書は提出するものの、第3四半期に係る四半期報告書は提出しないといったことも考えられる(例えば、11月決算会社の場合)。そこで、本改正前の有価証券届出書においては、その提出時期に応じて特定の四半期に係る四半期財務諸表等の記載が求められているが、四半期報告書の提出を要しない四半期については、四半期財務諸表等の記載を不要とすることとしている(整備府令附則第4条第5項)。
一方、有価証券届出書や有価証券報告書・半期報告書においては、提出会社以外の者が提出した四半期報告書に関する記載(割当予定先の状況、継続会社たる保証会社に関する事項等)が求められている。これについては、改正法附則第2条第3項において、旧法の規定により施行日前に提出された四半期報告書及び改正法附則第2条第1項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る金融商品取引法第2章(企業内容等の開示)の規定はなお従前の例によることとされ、提出された四半期報告書は従前どおり取り扱う趣旨が示されていることに照らして、提出会社以外の者が施行日前又は施行日以後に四半期報告書を提出している場合には、有価証券届出書等において当該四半期報告書に関する記載が必要になることに留意する必要がある。
また、有価証券報告書に関する様式については、施行日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書について適用することとしているが、有価証券届出書における取扱いと同様、改正法附則第3条第2項の規定により、施行日前から開始している事業年度についての半期報告書を提出する会社にあっては、当該事業年度に係る有価証券報告書から、改正後の様式を適用することとなる(整備府令附則第4条第6項)。
4 臨時報告書の提出に関する経過措置
2025年4月1日以後に提出される臨時報告書から適用される(整備府令附則第5条第2項)。ただし、施行日前に既に締結された契約について、当該契約に含まれる合意の内容に変更があった場合には、2026年3月31日までは、臨時報告書の提出義務が免除される(整備府令附則第5条第3項)。
5 財務諸表等規則の改正に関する経過措置
新財務諸表等規則等の規定は、施行日以後に開始する事業年度(連結会計年度)に係る財務諸表(連結財務諸表)について適用し、施行日前に開始した事業年度(連結会計年度)に係る財務諸表(連結財務諸表)については、なお従前の例によるとされる。ただし、改正法附則第3条第2項の規定により施行日を含む事業年度(連結会計年度)から半期報告書を提出する会社にあっては、当該事業年度に係る半期報告書に含まれる財務諸表(連結財務諸表)から新財務諸表等規則等の規定が適用されることとなり、この場合、例えば「経理の状況」の冒頭に記載する条項は新財務諸表等規則等の条項が記載されることとなる。また、新財務諸表等規則等の規定が最も早く適用されるケースは12月決算会社となる。
6 公衆縦覧期間の延長に関する経過措置
新法により公衆縦覧期間が延長される書類については、施行日以後に提出されるものから公衆縦覧期間を延長することとし、施行日において既に提出されているものについては、旧法の規定に従った期間で公衆縦覧を行うこととしている(改正法附則第4条)。
脚注
1 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告−中長期的な企業価値向上につながる資本市場の構築に向けて−」(2022年6月13日)(https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20220613.html)
2 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」(2022年12月27日)(https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20221227.html)
3 なお、「一本化」後の四半期決算短信制度の見直しについては、東京証券取引所において検討が進められており、以下のとおり検討結果が公表されている。
・東京証券取引所「四半期開示の見直しに関する実務の方針」(2023年11月22日)(https://www.jpx.co.jp/news/1023/20231122-01.html)
・東京証券取引所「金融商品取引法改正に伴う四半期開示の見直しに関する上場制度の見直し等について」(2023年12月18日)(https://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/20231218-01.html)
そして、東京証券取引所は、2024年3月28日に、決算短信・四半期決算短信作成要領や有価証券上場規程等を改正しており、その中では、経営上重要視する指標の開示についての明確化も含まれている。
4 政令及び内閣府令の具体的な改正内容については、金融庁「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について」(2024年3月27日)を参照。(https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240327/20240327.html)
5 「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に係る意見書」及び「監査に関する品質管理基準の改訂に係る意見書」の公表について(2024年3月27日)を参照。(https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240327-2/20240327.html)
6 なお、DWGにおいては、銀行等に求められる半期報告書についても、上場会社と同様の制度(第2四半期報告書と同程度の記載内容及び監査人によるレビュー)に見直すべきとの意見があったが、破綻処理制度等との関連も踏まえ、金融監督上の観点から引き続き検討していくことが必要であるとして、本改正による見直しの対象とはならなかった。
7 なお、組込方式の有価証券届出書並びに参照方式の有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類における四半期に係る財務情報の記載の取扱いについては、本改正前の取扱いを踏まえて、組込方式の有価証券届出書の場合にあっては追完情報に、参照方式の有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類においては添付書類として、記載又は添付することができる(「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」(以下「開示ガイドライン」という。)5−21−8)。
そして、四半期に係る財務情報を添付書類として参照方式の有価証券届出書等に添付した場合には、当該添付書類は目論見書の特記事項となることに留意する(開示ガイドライン7−4)。
8 四半期決算短信に含まれる四半期財務諸表等に対するレビューは、企業会計審議会が2024年3月に公表した期中レビュー基準に準拠して行われる。
9 金融庁「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(2024年3月27日)No.33-36
10 これらの契約について、「重要性の乏しい」合意・契約は、臨時報告書の提出は不要である。その重要性の判断に当たっては、当該契約における合意が、提出会社等のガバナンス若しくは支配権又は市場等に与える影響の程度や当該契約が通常の事業過程において締結されたものであるか否か等を踏まえて個別具体的に検討されるべきであるが、例えば、ガバナンスに対する影響が限定的であるものや市場における株式の流動性に対する影響が限定的であるもの、少数株主の保護の乏しい場合については、「重要性の乏しい」場合に該当することが多いと考えられる(開示ガイドライン5−17−6)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























