解説記事2025年05月26日 解説 SSBJによるサステナビリティ開示基準の概要(2)(2025年5月26日号・№1075)
解 説
SSBJによるサステナビリティ開示基準の概要(2)
サステナビリティ基準委員会 ディレクター 小西健太郎
サステナビリティ基準委員会 ディレクター 桐原和香
Ⅰ はじめに
2025年3月5日、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は我が国最初のサステナビリティ開示基準(以下あわせて「SSBJ基準」という。)を公表した。
SSBJ基準は、SSBJのウェブサイト(脚注1)より入手可能である(日本語のみ)。また、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が開発したIFRSサステナビリティ開示基準(以下「ISSB基準」という。)との差異の一覧(脚注2)及び項番対照表(脚注3)も、日本語及び英語で公表している。
・サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」(以下「適用基準」という。)
・サステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」(以下「一般基準」という。)
・サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」(以下「気候基準」という。)
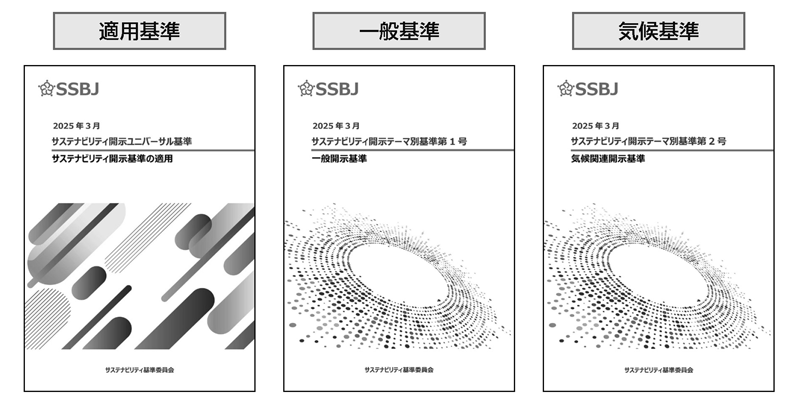
本稿では、SSBJ基準について3回に分けて概説する予定であり、第2回となる今回は、一般基準(適用時期及び経過措置を除く。)及び気候基準(指標及び目標並びに適用時期及び経過措置を除く。)について説明する。
なお、本稿の意見にわたる部分は筆者の私見であり、SSBJの公式見解ではないことをあらかじめ申し添える。
Ⅱ 一般基準の概要
※以下、本節の項番号は一般基準の項番号を示している。
1 目 的
一般基準の目的は、財務報告書の主要な利用者が企業に資源を提供するかどうかに関する意思決定を行うにあたり有用な、当該企業のサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報の開示について定めることにある(第1項)。
2 範 囲
一般基準は、SSBJ基準に従ってサステナビリティ関連財務開示を作成し、報告するにあたり、適用しなければならない(第3項)。
一般基準以外のSSBJ基準が、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報の開示について具体的に定めている場合、これに従わなければならない(第4項)。
3 ガバナンス
ガバナンスに関するサステナビリティ関連財務開示の目的は、サステナビリティ関連のリスク及び機会をモニタリングし、管理し、監督するために企業が用いるガバナンスのプロセス、統制及び手続を理解できるようにすることにある(第8項)。
この目的を達成するため、サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関又は個人に関して、定められた開示を行わなければならない(第9項)。また、サステナビリティ関連のリスク及び機会をモニタリングし、管理し、監督するために用いるガバナンスのプロセス、統制及び手続における経営者の役割に関して、定められた開示を行わなければならない(第10項)。
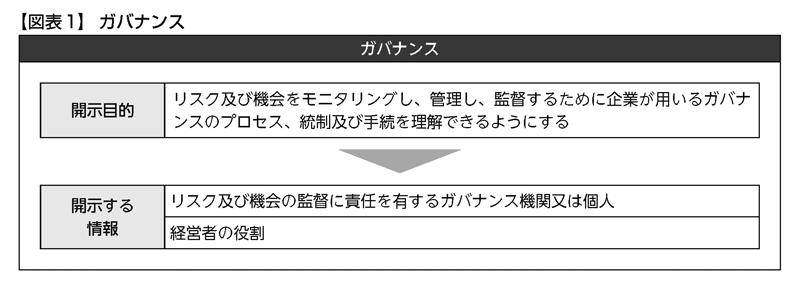
4 戦 略
(1)開示目的
戦略に関するサステナビリティ関連財務開示の目的は、サステナビリティ関連のリスク及び機会を管理する企業の戦略を理解できるようにすることである(第11項)。
具体的には、企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会のそれぞれについて、次の事項を開示しなければならない(第12項)。
(1)当該リスク及び機会
(2)(1)のリスク及び機会が企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与える影響
(3)(1)のリスク及び機会の財務的影響
(4)(1)のリスク及び機会が企業の戦略及び意思決定に与える影響
(5)(1)のリスクに関連する企業の戦略及びビジネス・モデルのレジリエンス(サステナビリティ関連のリスクから生じる不確実性に対応する企業の能力)
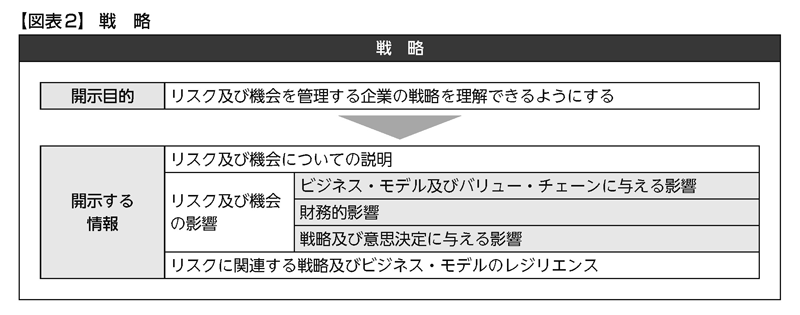
(2)サステナビリティ関連のリスク及び機会
企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会について、次の事項を開示しなければならない(第14項)。
(1)適用基準第36項に従い識別した、企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会
(2)(1)のサステナビリティ関連のリスク及び機会のそれぞれについて、その影響が生じると合理的に見込み得る時間軸(短期、中期又は長期により表す。)
(3)企業による「短期」、「中期」及び「長期」の定義
(4)(3)の定義と企業が戦略的意思決定に用いる計画期間との関係
(3)ビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与える影響
企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会について、次の事項を開示しなければならない(第15項)。
(1)サステナビリティ関連のリスク及び機会が現在の企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与えている影響
(2)サステナビリティ関連のリスク及び機会が将来の企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与えると予想される影響
(3)企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンにおいて、サステナビリティ関連のリスク及び機会が集中している部分
(4)財務的影響
企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会について、次の事項に関する定量的及び定性的情報を開示しなければならない(第17項)。
(1)サステナビリティ関連のリスク及び機会が、当報告期間において、企業の財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローに与えた影響
(2)(1)のサステナビリティ関連のリスク及び機会のうち、翌年次報告期間において、関連する財務諸表に計上する資産及び負債の帳簿価額に重要性がある影響を与える重大なリスクがあるもの
(3)サステナビリティ関連のリスク及び機会を管理する企業の戦略を踏まえた、短期、中期及び長期における、企業の財政状態の変化に関する見込み
(4)サステナビリティ関連のリスク及び機会を管理する企業の戦略を踏まえた、短期、中期及び長期における、企業の財務業績及びキャッシュ・フローの変化に関する見込み
(5)戦略及び意思決定に与える影響
企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会について、次の事項を開示しなければならない(第23項)。
(1)企業の戦略及び意思決定において、サステナビリティ関連のリスク及び機会にどのように対応してきたか、また、今後対応する計画であるか
(2)過去の報告期間に開示した計画に対する進捗(定量的及び定性的情報を含む。)
(3)(1)の対応を決定するにあたり考慮した、サステナビリティ関連のリスク及び機会の間のトレードオフ
(6)レジリエンス
次の事項に関する情報を開示しなければならない(第24項)。
(1)サステナビリティ関連のリスクに関連する、報告期間の末日における戦略及びビジネス・モデルのレジリエンスに関する定性的評価
(2)該当ある場合、サステナビリティ関連のリスクに関連する、報告期間の末日における戦略及びビジネス・モデルのレジリエンスに関する定量的評価
なお、2024年3月に公表した公開草案では、SSBJ基準独自の定めとして、レジリエンスの評価は、原則として、報告期間ごとに実施しなければならないとしたうえで、他のSSBJ基準において具体的な定めが存在せず、かつ、レジリエンスの評価結果について、前報告期間における評価結果と大きく相違しないことが見込まれる場合、前報告期間におけるレジリエンスの評価結果に基づき開示を行うことができるとする定めを追加することを提案していたが、SSBJ基準の内容を可能な限りISSB基準にあわせるため、この定めは削除している。
5 リスク管理
リスク管理に関するサステナビリティ関連財務開示の目的は、次のことをできるようにすることにある(第28項)。
(1)サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするプロセスを理解すること
(2)企業の全体的なリスク・プロファイル及び全体的なリスク管理プロセスを評価すること
この目的を達成するため、次の事項を開示しなければならない(第29項)。
(1)サステナビリティ関連のリスクを識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセス及び関連する方針に関する情報
(2)サステナビリティ関連の機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセスに関する情報
(3)サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセスが、全体的なリスク管理プロセスに統合され、用いられている程度、並びにその統合方法及び利用方法に関する情報
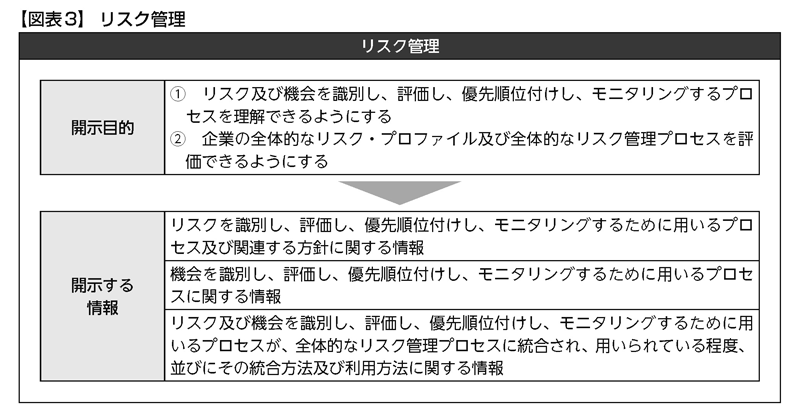
6 指標及び目標
(1)開示目的
指標及び目標に関するサステナビリティ関連財務開示の目的は、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関連する企業のパフォーマンスを理解できるようにすることにある(第30項)。
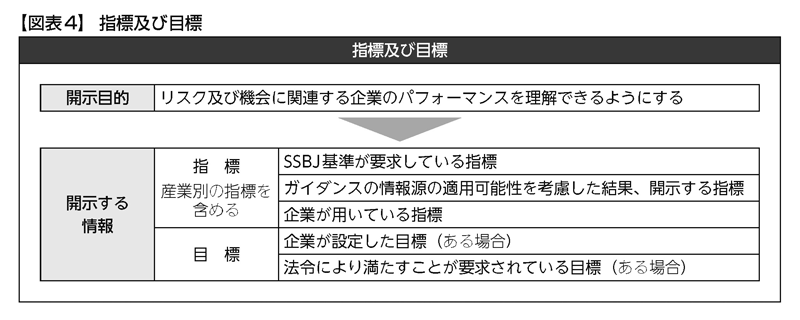
(2)指標
指標及び目標に関する開示目的を達成するため、企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会のそれぞれについて、次の事項を開示しなければならない(第32項)。
(1)SSBJ基準が要求している指標
(2)次のものを測定し、モニタリングするために企業が用いている指標
i.識別したサステナビリティ関連のリスク又は機会
ii.識別したサステナビリティ関連のリスク又は機会に関連する企業のパフォーマンス
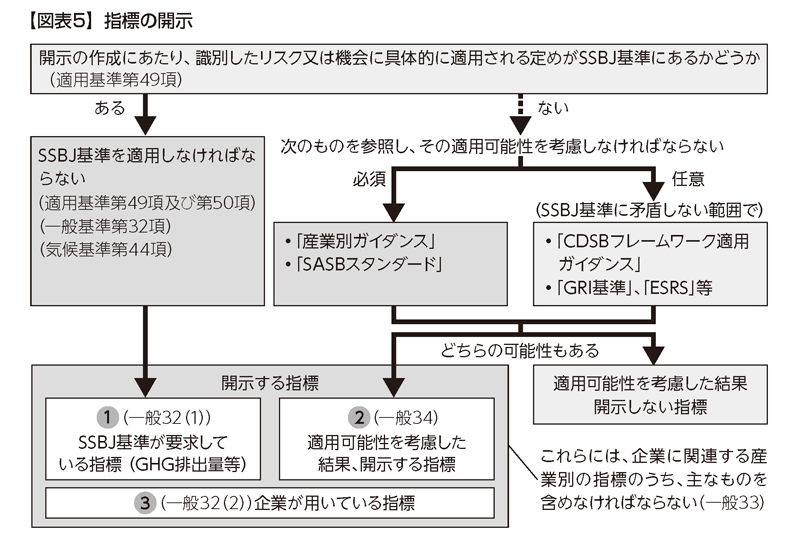
(3)目標
戦略的目標の達成に向けた進捗をモニタリングするために設定した目標及び企業が活動する法域の法令により満たすことが要求されている目標がある場合、当該目標に関する情報を開示しなければならない(第39項)。
Ⅲ 気候基準の概要
※以下、本節の項番号は気候基準の項番号を示している。
1 目 的
気候基準の目的は、財務報告書の主要な利用者が企業に資源を提供するかどうかに関する意思決定を行うにあたり有用な、当該企業の気候関連のリスク及び機会に関する情報の開示について定めることにある(第1項)。
2 範 囲
気候基準は、企業がさらされている気候関連のリスク(気候関連の物理的リスク及び気候関連の移行リスクを含む。)及び企業が利用可能な気候関連の機会に適用しなければならない(第3項)。
3 ガバナンス
ガバナンスに関する気候関連開示の目的は、気候関連のリスク及び機会をモニタリングし、管理し、監督するために企業が用いるガバナンスのプロセス、統制及び手続を理解できるようにすることにある(第9項)。
この目的を達成するため、気候関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関又は個人に関して、定められた開示を行わなければならない(第10項)。また、気候関連のリスク及び機会をモニタリングし、管理し、監督するために用いるガバナンスのプロセス、統制及び手続における経営者の役割に関して、定められた開示を行わなければならない(第11項)。
開示にあたっては、不必要な繰り返しを避けなければならない。サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督が統合的に管理されている場合、統合されたガバナンスの開示を提供することにより繰り返しを避けることになる(第12項)。
4 戦 略
(1)開示目的
戦略に関する気候関連開示の目的は、気候関連のリスク及び機会を管理する企業の戦略を理解できるようにすることにある(第13項)。
具体的には、企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る気候関連のリスク及び機会のそれぞれについて、次の事項を開示しなければならない(第14項)。
(1)当該リスク及び機会
(2)(1)のリスク及び機会が企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与える影響
(3)(1)のリスク及び機会の財務的影響
(4)(1)のリスク及び機会が企業の戦略及び意思決定に与える影響
(5)(1)のリスク及び機会を考慮した企業の戦略及びビジネス・モデルの気候レジリエンス(気候関連の変化、進展又は不確実性に対応する企業の能力)
戦略に関する気候関連開示の作成にあたり、後述する産業横断的指標等及びISSBが公表する「IFRS S2号の適用に関する産業別ガイダンス」(2023年6月公表)(以下「産業別ガイダンス」という。)に定義されている、開示トピックに関連する産業別の指標を参照し、その適用可能性を考慮しなければならない。考慮した結果、適用する場合と適用しない場合とがある(第16項)。
(2)気候関連のリスク及び機会
企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る気候関連のリスク及び機会について、次の事項を開示しなければならない(第19項)。
(1)企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る気候関連のリスク及び機会
(2)(1)の気候関連のリスクのそれぞれについて、気候関連の物理的リスク又は気候関連の移行リスクのいずれであるか
(3)(1)の気候関連のリスク及び機会のそれぞれについて、その影響が生じると合理的に見込み得る時間軸(短期、中期又は長期により表す。)
(4)企業による「短期」、「中期」及び「長期」の定義
(5)(4)の定義と企業が戦略的意思決定に用いる計画期間との関係
(3)ビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与える影響
企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る気候関連のリスク及び機会について、次の事項を開示しなければならない(第20項)。
(1)気候関連のリスク及び機会が現在の企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与えている影響
(2)気候関連のリスク及び機会が将来の企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与えると予想される影響
(3)企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンにおいて、気候関連のリスク及び機会が集中している部分
(4)財務的影響
企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る気候関連のリスク及び機会について、次の事項に関する定量的及び定性的情報を開示しなければならない(第22項)。
(1)気候関連のリスク及び機会が、当報告期間において、企業の財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローに与えた影響
(2)(1)の気候関連のリスク及び機会のうち、翌年次報告期間において、関連する財務諸表に計上する資産及び負債の帳簿価額に重要性がある影響を与える重大なリスクがあるもの
(3)気候関連のリスク及び機会を管理する企業の戦略を踏まえた、短期、中期及び長期における、企業の財政状態の変化に関する見込み
(4)気候関連のリスク及び機会を管理する企業の戦略を踏まえた、短期、中期及び長期における、企業の財務業績及びキャッシュ・フローの変化に関する見込み
(5)戦略及び意思決定に与える影響
企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る気候関連のリスク及び機会について、次の事項を開示しなければならない(第28項)。
(1)企業の戦略及び意思決定において、気候関連のリスク及び機会にどのように対応してきたか、また、今後対応する計画であるか(企業が設定した気候関連の目標及び企業が活動する法域の法令により満たすことが要求されている目標がある場合、当該目標をどのようにして達成する計画であるかを含む。)
(2)(1)に従い開示した対応について、報告期間の末日において資源を確保している方法及び将来において資源を確保するための計画の内容
(3)過去の報告期間に開示した計画に対する進捗(定量的及び定性的情報を含む。)
(4)(1)の対応を決定するにあたり考慮した、気候関連のリスク及び機会の間のトレードオフ
(6)気候レジリエンス
気候レジリエンスに関しては、気候関連のシナリオ分析に基づき気候レジリエンスを評価しなければならない。気候関連のシナリオ分析は、最低限、戦略計画サイクルに沿って更新しなければならないが、報告期間ごとに実施する必要はない。気候レジリエンスの評価は、報告期間ごとに実施しなければならない(第30項)。
気候レジリエンスに関して、識別した気候関連のリスク及び機会を考慮したうえで、次の事項を開示しなければならない(第31項)。
(1)実施した気候関連のシナリオ分析の手法及び実施時期
(2)報告期間の末日における気候レジリエンスの評価
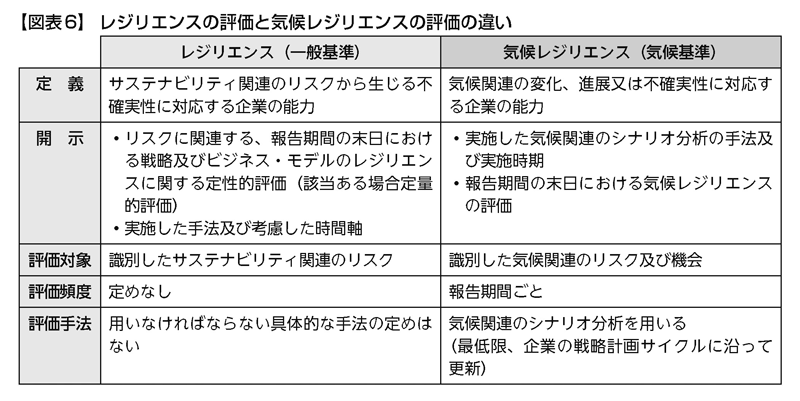
5 リスク管理
リスク管理に関する気候関連開示の目的は、次のことをできるようにすることにある(第40項)。
(1)気候関連のリスク及び機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするプロセスを理解すること
(2)企業の全体的なリスク・プロファイル及び全体的なリスク管理プロセスを評価すること
この目的を達成するため、次の事項を開示しなければならない(第41項)。
(1)気候関連のリスクを識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセス及び関連する方針に関する情報
(2)気候関連の機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセスに関する情報
(3)気候関連のリスク及び機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセスが、全社的なリスク管理プロセスに統合され、用いられている程度、並びにその統合方法及び利用方法に関する情報
開示にあたっては、不必要な繰り返しを避けなければならない。サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督が統合的に管理されている場合、サステナビリティ関連のリスク及び機会のそれぞれについての個別の開示ではなく、統合されたリスク管理の開示を提供することにより繰り返しを避けることになる(第42項)。
Ⅳ 小 括
今回は、一般基準(適用時期及び経過措置を除く。)及び気候基準(指標及び目標並びに適用時期及び経過措置を除く。)について概説した。次回は、気候基準(指標及び目標)並びに適用時期及び経過措置について説明する予定である。
脚注
1 https://www.ssb-j.jp/jp/ssbj_standards/2025-0305.html
2 (日本語)https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/ssbj_20250331_01.pdf
(英語)https://www.ssb-j.jp/en/wp-content/uploads/sites/7/ssbj_20250331_01_e.pdf
3 (日本語)https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/ssbj_20250331_02.pdf
(英語)https://www.ssb-j.jp/en/wp-content/uploads/sites/7/ssbj_20250331_02_e.pdf
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























