解説記事2025年07月28日 税制改正解説 令和7年度における消費税・個別間接税関係の改正について(下)(2025年7月28日号・№1084)
税制改正解説
令和7年度における消費税・個別間接税関係の改正について(下)
安田圭吾
個別間接税関係
一 酒税関係の改正
リファンド方式への見直し等に伴う輸出酒類販売場制度の見直し
(1)改正前の制度の概要
輸出酒類販売場制度は、輸出酒類販売場において免税購入対象者に対して一定の手続により免税の対象となる一定の酒類(以下「免税対象酒類」という。)を販売した場合には、消費税に加えて、当該免税対象酒類に係る酒税を免税とする制度である。
免税販売を行う酒類製造者は、酒類の製造場ごとにあらかじめ税務署長から輸出酒類販売場としての許可を受ける必要がある。また、免税販売を行う場合には、免税対象酒類を購入する者から旅券等の提示を受け、その者が免税購入対象者に該当することを確認する等、免税要件を満たしているか否かを確認した上で販売することになる。その上で、免税対象酒類に関する情報を記録した電磁的記録(酒類購入記録情報)を、消費税の購入記録情報と併せて、国税庁の免税販売管理システムに送信することとされている。なお、酒類購入記録情報の送信については、消費税の輸出物品販売場制度においてあらかじめ税務署長から承認を受けた「承認送信事業者」を通じて行うことも可能とされている。
本制度は、上記のとおり免税購入対象者が一定の手続により購入した免税対象酒類の移出について、輸出酒類販売場を経営する酒類製造者における酒類購入記録情報の保存を前提として、その場で免税が確定する制度であるため、現行制度において実務上、免税購入対象者に対して免税価格で販売することとなる。また、免税購入対象者は、出国の際に税関長に対して旅券等を提示し、必要に応じて持ち出しの確認を受けることとされており、免税対象酒類を所持していない場合には、免除された酒税額に相当する酒税を直ちに徴収することとされている(旧措法87の6)。
(2)改正の内容
令和7年度税制改正では、消費税の輸出物品販売場制度を前提としている酒税の輸出酒類販売場制度についても、消費税と同様に、出国の際に免税対象酒類の持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、免税販売の成立後に免税店から免税購入対象者に対して酒税相当額を返金するリファンド方式に見直すこととされた。具体的には、輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が免税購入対象者に、輸出するため一定の手続により購入される免税対象酒類を販売するため、当該免税対象酒類を当該輸出酒類販売場から移出した場合に、当該免税購入対象者が、その購入した日から90日以内に、当該免税対象酒類を輸出することにつき税関長の確認を受けたときは、当該移出に係る酒税を免除することとされた(措法87の6)。
(3)適用関係
上記の改正は、令和8年11月1日以後に輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が免税購入対象者に対して販売するため輸出酒類販売場から移出する酒類について適用され、同日前に輸出酒類販売場から移出した酒類については、なお従前の例によることとされている(改正法附則1四ハ、57①)。
二 たばこ税関係の改正
防衛力強化に係る財源確保のためのたばこ税の措置
(1)改正前の制度の概要
① 加熱式たばこに係る課税方式(課税標準の換算方法)
たばこ税の課税標準は、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数とされている。この場合の製造たばこの本数は、紙巻たばこの本数によるものとされているが、紙巻たばこ以外の製造たばこについては、加熱式たばこ以外のものは、その重量に応じて紙巻たばこの本数に換算することとされている。一方で、加熱式たばこについては、その製品特性を踏まえ、加熱式たばこの製品間や紙巻たばことの税負担の公平性を確保していく技術的な方法として、「重量」と「価格」に応じて紙巻たばこの本数に換算することとされ、具体的には、次のイの方法とロの方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数とすることとされていた(た法10③、た令3、た規3、4)。
イ 「重量」に応じた換算方法
加熱式たばこの重量の0.4gをもって紙巻たばこの0.5本に換算することとされていた(た法10③一)。
ロ 「価格」に応じた換算方法
小売定価が定められている加熱式たばこについては、その小売定価に相当する金額(消費税及び地方消費税に相当する金額を除く。)の紙巻たばこ1本の金額に相当する金額をもって紙巻たばこの0.5本に換算することとされていた(た法10③二)。
なお、この場合の「紙巻たばこ1本の金額に相当する金額」とは、たばこ税、たばこ特別税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分の60で除した金額とされていた(た令3④)。
② たばこ税の税率
製造たばこの製造場から移出される製造たばこ又は保税地域から引き取られる製造たばこに係る国のたばこ税の税率については、次の税率を適用することとされていた(た法11)。
イ 製造たばこの製造場から移出され、又は特定販売業者により保税地域から引き取られる製造たばこ
1,000本につき6,802円
ロ 特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこ
1,000本につき14,424円
(2)改正の内容
令和7年度税制改正においては、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として、防衛特別法人税が創設されたほか、たばこ税による対応として、以下のとおり加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例及びたばこ税の税率の特例が創設された。
① 加熱式たばこに係る課税方式(課税標準の換算方法)の見直し
現行の加熱式たばこの課税方式は、平成30年度税制改正において、加熱式たばこの消費量が急速に増加している中で、紙巻たばこと同様の価格帯で販売され、かつ、代替性が高いにも関わらず紙巻たばこと比べて低い税負担となっており、税負担の公平性の観点から問題が生じていたこと、また、紙巻たばこから加熱式たばこへの消費のシフトが急速に進んでいる状況を踏まえると財政面からも早急な対応が必要となっていたことを背景に、当時の加熱式たばこの製品実態や製品特性を踏まえて、「重量」と「価格」に応じた課税方式として創設されたものである。
こうした課税方式であることにより、近年、製品の軽量化を図ることや価格を引き下げることで税負担をより低くした製品が販売されている実態があり、また、加熱式たばこの区分において様々な形態の製品が登場してきている中で一律の課税方式が設定されていることにより、加熱式たばこの製品間での税負担差が引き続き生じていた。
このような状況を是正するため、加熱式たばこの課税標準の計算方法については、「価格」に応じた課税方式を廃止し、「重量」のみに応じて紙巻たばこの本数に換算する方式とした上で、紙巻たばこと類似した製品形態であり加熱式たばこのシェアの大宗を占めるスティック型のものとそれ以外のものとに区分し、かつ、それぞれの区分ごとに紙巻たばこの本数に換算する際の換算係数について製品実態等を踏まえて見直すとともに、軽量化による税負担の不公平が生じないよう、一定の重量以下の加熱式たばこを紙巻たばこ1本に換算する等の仕組み(以下「最低課税」という。)を設けることとされた。
具体的には、次に掲げる2つの区分に応じて、それぞれ次のとおりその重量を紙巻たばこの本数に換算することとされた。
イ 葉たばこを原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(葉たばこを原料の全部又は一部としたものを直接加熱することによって喫煙の用に供されるものに限る。)≪スティック型の加熱式たばこ≫
当該加熱式たばこの重量の0.35gをもって紙巻たばこの1本に換算する方法とされた。なお、最低課税として、1本当たりの重量が0.35g未満である場合には、当該加熱式たばこの1本を紙巻たばこの1本に換算する方法とされた(措法88①一)。
(注)「直接加熱すること」は、当該加熱式たばこに係る喫煙用具の熱源を用いて葉たばこを原料の全部又は一部としたものを直接加熱することによるものとされている(措規37の4の14)。
ロ イ以外の加熱式たばこ≪スティック型以外の加熱式たばこ≫
当該加熱式たばこの重量の0.2gをもって紙巻たばこの1本に換算する方法とされた。なお、最低課税については、当該加熱式たばこには1本と捉え難い様々な製品形態のものが含まれることから、1本単位で換算することは適切ではなく、製品の1パッケージ単位で換算することが適切であると考えられることから、当該加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量が4g未満である場合には、品目ごとの1個をもって紙巻たばこ20本に換算する方法とされた(措法88①二)。
(注)加熱式たばこに係る課税方式の見直しは、課税の適正化を行うものであるものの、加熱式たばこは市場に出てからまだ10年程度であり今後も従来にない形態の製品が出てくる可能性もあること、今般の見直しが当面の防衛力強化に係る財政需要に対応するための当分の間の措置として行われるものであること等を踏まえ、課税標準の特例として租税特別措置法に設けることとされた。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについては、製品によっては大幅に税負担が増加することを踏まえ、消費者への影響に配慮する観点から、所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)の公布の日から1年の期間を空けた上で、令和8年4月1日及び同年10月1日の2回に分けて段階的に実施することとされた。
具体的には、令和8年4月1日から新たな課税方式に移行することとした上で、同日から同年9月30日までの間の加熱式たばこの課税標準は、改正前の加熱式たばこの課税標準となる紙巻たばこの本数(以下「旧換算本数」という。)及び改正後の加熱式たばこの課税標準となる紙巻たばこの本数(以下「新換算本数」という。)のそれぞれに、0.5を乗じて計算した本数の合計本数とすることとされている(改正法附則58②)。
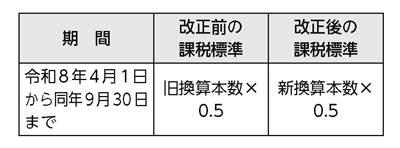
② たばこ税の税率の特例の創設
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置については、防衛力を抜本的に強化し、抜本的に強化された防衛力を安定的に維持していく必要がある限りにおいて措置するものであるとの観点から、当分の間の措置として、たばこ税については、国のたばこ税率を1,000本につき1,500円引き上げることとされた。
具体的には、令和9年4月1日以後に、製造たばこの製造場から移出される製造たばこ又は保税地域から引き取られる製造たばこに係る国のたばこ税の税率については、当分の間、次の税率を適用することとされた(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和5年法律第69号)49)。
イ 製造たばこの製造場から移出され、又は特定販売業者により保税地域から引き取られる製造たばこ
1,000本につき8,302円
ロ 特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこ
1,000本につき15,924円
(注)税率の引上げは、当面の防衛力強化に係る財政需要に対応するための措置そのものであることから、たばこ税の税率の特例という形で我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法に設けることとされた。
また、税率の引上げに当たっては、消費者やたばこ関係事業者の将来の予見可能性を確保する観点から、令和9年4月1日、令和10年4月1日及び令和11年4月1日の3回に分けて、国のたばこ税について1,000本につき500円ずつ段階的に実施することとされた(改正法附則63②③)。
三 自動車重量税関係の改正
1 新車新規登録から18年又は13年を経過した一定の検査自動車に係る自動車重量税率の特例措置の改正
(1)改正前の制度の概要
道路運送車両法施行規則では、自動車検査登録制度(以下「車検制度」という。)において、自動車検査証の残存する有効期間を失うことなく継続検査(いわゆる「車検」)を受けられる期間の起算日について、本土に使用の本拠の位置を有する自動車は自動車検査証の有効期間が満了する日の「1月前」とし、離島に使用の本拠の位置を有する自動車は、自動車検査証の有効期間が満了する日の「2月前」と定めていた。
(注)「離島」とは、橋又はトンネルによる本土(本州、北海道、四国、九州及び沖縄島をいう。)との間の交通又は移動が不可能な島をいう。
自動車重量税は、自動車検査証の交付等の時点で燃費等の環境性能に関する一定の基準を満たしている自動車は本則税率が適用され、それ以外の自動車は新車新規登録からの経過年数(18年超、13年超、13年以下)に応じた特例税率が適用されることとなっている。
この経過年数について、上記の車検制度を踏まえ、一定の自動車を除き、
① 本土に使用の本拠の位置を有する自動車は新車新規登録を受けた日の属する月から起算して18年又は13年を「経過する月」、
② 離島に使用の本拠の位置を有する自動車は新車新規登録を受けた日の属する月から起算して18年又は13年を「経過する月の前月」
の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車を18年超又は13年超として取り扱うこととされていた(旧措法90の11の2、90の11の3、旧措令51の3、旧措規40の3)。
(参考)13年を「経過する月」とは、例えば、新車新規登録が平成24年(2012年)6月の場合には、令和7年(2025年)5月となる。
(2)改正の背景
昨今の自動車整備士の不足に伴い、一部の自動車整備工場において車検に対応できるキャパシティを超えた結果、指定の期間内に車検を受検することができないといった事例が生じている。
このため、自動車整備業界の働き方改革及び自動車の使用者の利便性向上を図る観点から車検制度の見直しとして、道路運送車両法施行規則について、自動車検査証の残存する有効期間を失うことなく車検を受けられる期間の起算日を、使用の本拠の位置にかかわらず自動車検査証の有効期間が満了する日の「2月前」とする改正が行われた(令和7年4月1日施行)。
(3)改正の内容
車検制度の見直しに伴い、本特例措置の対象となる検査自動車については、使用の本拠の位置にかかわらず新車新規登録を受けた日の属する月から起算して18年又は13年を「経過する月の前月」の初日以後に自動車検査証の交付等を受けるものを18年超又は13年超として取り扱うこととされた(措法90の11の2、90の11の3、措令51の3)。
(注)本特例措置の対象となる検査自動車のうち軽自動車については、初めて車両番号の指定を受けた年のみがデータ管理の対象となっていたことを踏まえ、初めて車両番号の指定を受けた年から起算して18年又は13年を経過した年の「12月」の初日以後に自動車検査証の交付等を受けるものに適用することとされていたが、上記の見直しに伴い、初めて車両番号の指定を受けた年から起算して18年又は13年を経過した年の「11月」の初日以後に自動車検査証の交付等を受けるものに適用することとされた。
(4)適用関係
上記の改正は、令和7年4月1日以後に自動車検査証の交付等を受ける自動車に係る自動車重量税について適用されている(改正法附則1、改正措令附則1、改正措規附則1)。
2 使用済自動車に係る自動車重量税の還付措置の見直し
(1)改正前の制度の概要
自動車重量税は、自動車が車検を受け、又は届出を行うことにより、道路を走行することが可能になるという法的地位の取得あるいは利益の享受に着目して課税される一種の権利創設税であり、自動車検査証の交付等を受ける際に課されることとなる。
このような税の性格から、一旦車検が有効なものとなっている自動車については、廃車された場合であっても、自動車重量税の還付措置は設けられていなかったが、平成14年度税制改正において、使用済自動車の不法投棄防止及びリサイクル促進という政策的観点から、自動車検査証の有効期間内に使用済自動車となり、適正に解体された自動車(以下「使用済自動車」という。)について還付措置が設けられた。
その後、平成29年度税制改正においては、災害が頻発していることを踏まえ、被災者や被災事業者の不安を早期に解消するとともに、復旧や復興の動きに遅れることなく税制上の対応を手当する観点から、自然災害(被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害をいう。以下同じ。)により被災した自動車(以下「被災自動車」という。)に係る自動車重量税の還付措置が講じられた。
なお、使用済自動車又は被災自動車に係る自動車重量税の還付措置(以下「本措置」という。)の適用を受けようとする場合には、使用済自動車又は被災自動車の所有者が、還付申請書を国土交通大臣等を通じて税務署長に提出することにより、還付を受けることとなる(措法90の15④)。
また、当該還付申請書に係る還付金額については、一定の区分に応じて定められた日(以下「確定日」という。)に基づき、以下のとおり計算されることとなる(措令51の5③)。
(注1)災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第9条の規定の適用を受ける場合は、本措置は適用されない(措法90の15③)。
(注2)被災自動車が本措置の適用を受けようとする場合は、当該被災自動車に係る自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に還付申請書を国土交通大臣等を通じて税務署長に提出する必要がある(措令51の5⑧)。
① ②以外の場合は、自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を自動車検査証の有効期間の月数で除し、これに確定日から当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日までの月数を乗じて計算した金額(措令51の5③一本文)
(注1)使用済自動車又は被災自動車が特定自動車(自動車検査証の有効期間が満了する日の2月前の日から当該満了する日の1月前の日の前日までの間に車検を受けた一定の自動車をいう。)であり、かつ、確定日が新自動車検査証(当該車検の結果、返付を受ける自動車検査証をいう。以下同じ。)の返付の日から旧自動車検査証(当該返付を受ける前の自動車検査証をいう。以下同じ。)の有効期間の満了する日の1月前の日までの間の日である場合には、旧自動車検査証の交付又は返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を旧自動車検査証の有効期間の月数で除して計算した金額及び新自動車検査証の返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額の合計額(旧措令51の5③一括弧書)
(注2)月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数があるときは切り捨てる(措令51の5⑤)。
② 使用済自動車又は被災自動車に係る自動車重量税の額につき、既に、本措置の適用により還付された金額がある場合又は還付を受けようとしている場合は、①により計算した金額から当該還付された金額又は当該還付を受けようとする金額を控除した金額(措令51の5③二)
(注)この還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は付されない(措法90の15⑤)。
(2)改正の内容
1の改正により上記(1)①(注1)における特定自動車に関する規定が削除されたことから、本措置に係る還付金額の計算方法について見直しが行われた。
具体的には、自動車検査証の有効期間の満了する日の2月前の日から当該満了する日の1月前の日までの間に車検を受け、その結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の起算日が従前の有効期間の満了する日の翌日とされる場合であって、かつ、確定日が新自動車検査証の返付の日から旧自動車検査証の有効期間の満了する日の1月前の日までの間の日である場合には、旧自動車検査証の交付又は返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を旧自動車検査証の有効期間の月数で除し、これに確定日から当該旧自動車検査証に記録された有効期間の満了する日までの月数を乗じて計算した金額及び新自動車検査証の返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額の合計額とすることとされた(措令51の5③一括弧書)。
(3)適用関係
上記の改正は、令和7年4月1日から施行されている(改正措令附則1)。
四 印紙税関係の改正
1 独立行政法人日本学生支援機構等が作成する非課税文書の見直し
(1)制度の概要
印紙税は、経済取引等に伴う文書の作成・行使の背後には経済的利益が存在すると推定されること等から、各種の契約書、有価証券、定款、預貯金証書、保険証券、金銭又は有価証券の受取書など、印紙税法別表第1に掲げる20種類の課税文書に対して軽度の負担を求めている。
ただし、印紙税法別表第3の文書名の欄に掲げる文書で、同表の作成者の欄に掲げる者が作成したものについては、同法第5条第3号の規定に基づき非課税とされている。同表には様々な文書が掲名されているが、事業団その他の特殊法人が作成する文書の一部を非課税とするものの1つとして、独立行政法人日本学生支援機構(以下「JASSO」という。)等が作成した独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号。以下「支援機構法」という。)に規定する学資の貸与(以下「貸与型奨学金」という。)に係る業務に関する文書が掲名されている。
(2)改正の背景等
JASSOが実施する学資の支給(以下「給付型奨学金」という。)については、一定の事由に該当し、支給対象としての認定を取り消した際、支給した給付型奨学金の返還が必要となる場合がある(支援機構法17の3)。この返還に当たっては、JASSOが確実に返還金を回収する必要がある一方で、貸与型奨学金と同様に、経済的な理由で返還が困難な場合は学生等が返還猶予や減額返還制度などの返還支援策を利用できるようにし、返還に係る負担軽減を図る必要があるという観点から、JASSOと学生等との間で金銭消費貸借の目的を有する返還誓約書が作成されている。
上記(1)のとおり、貸与型奨学金に係る業務に関する文書については印紙税が非課税とされているが、給付型奨学金に係る返還誓約書については印紙税が課税されていた。
(3)改正の内容
給付型奨学金を利用する学生等は経済的理由により修学に困難があり、返還が発生することでさらに経済的に厳しい状況に陥る可能性があること、従来から非課税とされているJASSOの他の業務に関する文書との関係を踏まえ、JASSO等が作成する支援機構法第13条第1項第1号に規定する学資の支給に係る業務に関する文書を印紙税が非課税となる文書の範囲に加えることとされた(印法別表第3)。
(4)適用関係
上記の改正は、令和7年4月1日以後にJASSO等が作成する支援機構法第13条第1項第1号に規定する学資の支給に係る業務に関する文書について適用される(改正法附則24)。
2 国民健康保険団体連合会が作成する非課税文書の見直し
(1)改正前の制度の概要
印紙税法別表第3には、社会保険、年金、退職金共済等に関する文書を非課税とするものの一つとして、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が作成する児童福祉法(昭和22年法律第164号)等に基づく一定の業務に関する文書が掲名されている。
(2)改正の背景等
政府により設置された医療DX推進本部において、「医療DXの推進に関する工程表」(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)が取りまとめられ、「関係機関や行政機関等の間で必要な情報を安全に交換できる情報連携の仕組みを整備し、自治体システムの標準化の取組と連動しながら、介護保険、予防接種、母子保健、公費負担医療や地方単独の医療費助成などに係る情報を共有していく」こととされた。
また、「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年6月21日閣議決定)では、より質の高い効率的な医療・介護を提供する体制を構築するとともに、医療データを活用し、医療のイノベーションを促進するため、政府を挙げて医療・介護DXを確実かつ着実に推進することとされている。
現在、自治体が実施主体となっている医療費助成・母子保健・予防接種・介護保険等分野の業務については、国民、自治体、医療機関・薬局といった当事者にとって、紙での情報連携にかかる業務負担が多く、改善が必要な状況にある。
こうした状況を踏まえ、関係機関や行政機関等の間で必要な情報を安全に交換できる情報連携の仕組みを整備し、介護保険、予防接種、母子保健、公費負担医療や地方単独の医療費助成などに係る情報を共有していくための環境整備として、自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub。以下「PMH」という。)が開発され、今後運用されていくこととされている。
このPMHのうち、予防接種及び母子保健のデジタル化に必要なシステムについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号。以下「感染症法等一部改正法」という。)等により、自治体は予防接種法等に基づく一定の業務を連合会に委託することができることとされた。
(3)改正の内容
現行、印紙税が非課税とされている連合会の他の業務に関する文書との関係を踏まえ、連合会が作成する以下①及び②の文書を印紙税が非課税となる文書の範囲に加えることとされた(印法別表第3)。
① 予防接種法第43条第2号及び第3号(同条第2号の業務に係る業務に限る。)に掲げる業務に関する文書
② 母子保健法第22条の14各号に掲げる業務に関する文書
(4)適用関係
上記(3)①の改正は、感染症法等一部改正法の公布の日(令和4年12月9日)から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日以後に作成する文書に係る印紙税について適用される(改正法附則1十)。
上記(3)②の改正は、令和6年度地域分権一括法の公布の日(令和6年6月19日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日以後に作成する文書に係る印紙税について適用される(改正法附則1十一)。
3 特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の延長
(1)改正前の制度の概要等
我が国においては、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、教育の機会均等の実現を図ることが、国や地方公共団体はもとより、国民全体に対して求められている(旧子どもの貧困対策の推進に関する法律3~5)。
(2)改正の内容
本特例措置については、引き続き、教育の機会均等の実現を図るため、その補完的な役割を担う公益法人等が実施する奨学金事業が重要であること等を踏まえ、その適用期限を3年延長し、令和10年3月31日までの措置とすることとされた(措法91の3②)。
(3)適用関係
上記の改正は、令和7年4月1日から施行されている(改正法附則1)。
4 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の延長
(1)改正前の制度の概要
公的貸付機関等又は金融機関が特定事業者(新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者をいう。以下同じ。)に対して新型コロナウイルス感染症等によりその経営に影響を受けたことを条件として他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う特別貸付けに係る消費貸借契約書のうち、特定日として規定された令和3年1月31日までに作成されるものについては、印紙税を課さないこととされた。
令和3年1月31日の適用期限の到来に際しては、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受ける事業者が多くあり、これを受け、多くの公的貸付機関等及び金融機関が引き続き特定事業者に対する特別貸付制度を存置していることを踏まえ、令和3年度税制改正において、その適用期限が延長され、令和4年3月31日までの措置とされた。
令和4年度税制改正から令和6年度税制改正までの各年度において、その適用期限がそれぞれ1年延長され、令和7年3月31日までの措置とされた(新型コロナ税特法11、旧新型コロナ税特令8、新型コロナ税特規6)。
(注1)上記の「公的貸付機関等」とは、地方公共団体、株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構などをいう(新型コロナ税特法11①、新型コロナ税特令8①、新型コロナ税特規6①)。
(注2)上記の「金融機関」とは、銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、信用金庫連合会、協同組合連合会、労働金庫連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行をいう(新型コロナ税特法11②、新型コロナ税特令8④)。
(2)改正の内容
本措置については、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進み、経営上の課題が売上減少から人手不足・賃上げ・原材料費高騰等への対応にシフトしていることから、各種資金繰り支援策についても、経営改善・再生はもちろん、成長促進も含め、多岐にわたる経営課題に対応できるよう見直しが行われ、公的貸付機関等による新型コロナウイルス感染症対策に係る資金繰り支援策の実行が令和7年8月31日で終了することに鑑み、その適用期限を令和7年8月31日まで延長することとされた(新型コロナ税特令8③)。
(3)適用関係
上記の改正は、令和7年4月1日から施行されている(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第133号)附則)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























