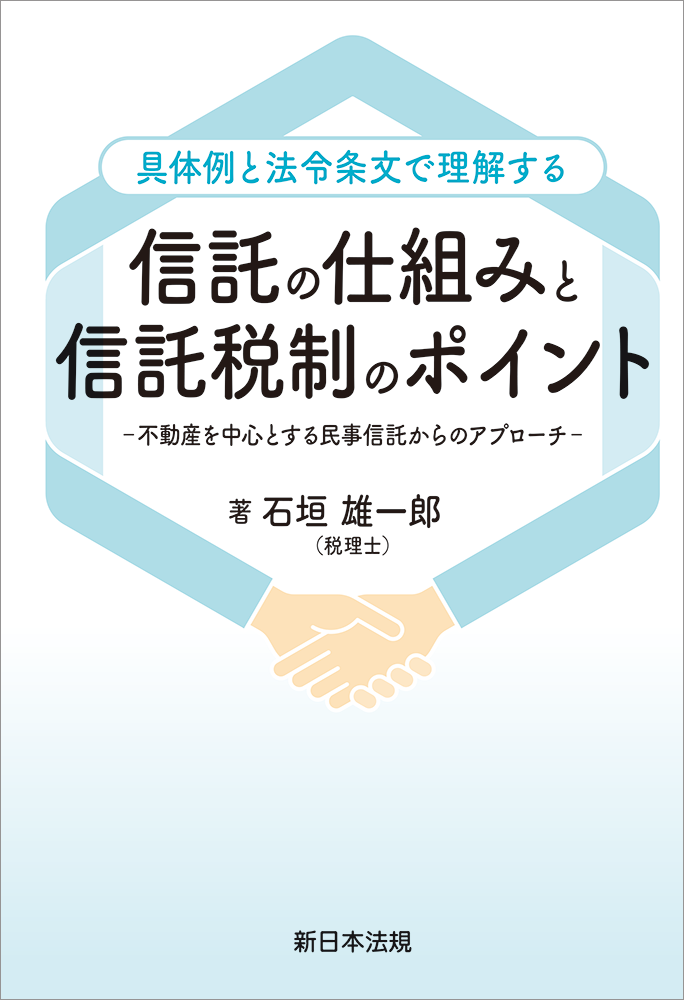税務ニュース2025年11月07日 控除率UPで自己否認の常態化が転換も(2025年11月10日号・№1098) インボイス登録交渉を難しくする「代替えの効かない不動産」の壁
現行インボイス制度上、適格請求書発行事業者ではない事業者(以下、「インボイス未登録事業者」)からの課税仕入れでも仕入税額相当額の80%が控除対象とされているが、この控除率が来年10月1日以降、50%へと引き下げられることは周知の通り。その影響が早くも顕在化している。
税理士からは、顧問先の申告書付表2−3における「適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける課税仕入れに係る支払い対価の額(税込み)」欄の金額が想定以上に大きくなっているとの声が多く聞かれる。その背景には、仕入先がインボイス未登録事業者であっても、仕入側が仕入先との関係悪化を避けるため、経過措置の適用を受けることを前提に仕入税額相当額の20%を自ら控除しないという“自己否認”を選択しているという実態がある。
ただ、控除率が50%となれば自己否認額も看過できないものとなる。特に問題になりそうなのが不動産賃貸の場面だ。不動産賃貸事業者には個人事業主や高齢者の大家も多く、インボイス未登録事業者の割合が高い。小規模な不動産賃貸業者の場合、長年保有している不動産を賃貸しているのみで、そもそも仕入れがほぼ発生しないことや、売上の多くが住宅の賃貸料(非課税)であるため、インボイス登録に消極的な事業者も多いものとみられる。
一方、借主(テナント)は法人をはじめとする課税事業者であることが多く、また、契約が長期にわたり金額も大きいため、控除できない消費税額が積み上がることになる。借主としては貸主にインボイスの発行を求めたいところだが、不動産には物件の立地や希少性によっては代えが効かないという特性があり、強硬な交渉がやりにくいとの声も聞かれる。ましてや、仕入税額控除できない分の賃貸料減額交渉を持ちかけることは憚られるところだろう。
一方、代替物件がある場合は、契約更新時にインボイス登録を条件とする、あるいは仕入税額控除の影響を踏まえた賃貸料見直しを検討するなど事前に取引条件を整理した上で早めに交渉に着手し、その結果次第では取引をやめることも検討に値しよう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -