解説記事2025年11月10日 第2特集 サステナビリティ情報の開示と保証、残された論点の方向性(2025年11月10日号・№1098)
第2特集
登録要件を満たせば監査法人以外も保証の実施者に
サステナビリティ情報の開示と保証、残された論点の方向性
金融審議会に設置された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」では、サステナビリティ情報の開示と保証のあり方について検討を行っているが、10月30日の会合では、7月17日に公表された中間論点整理で残された論点の方向性が明らかとなった。
保証義務付けの段階における有価証券報告書の提出期限の延長については実施しない方針であることが明らかとなったほか、保証の担い手については当初の予定どおり、監査法人以外も一定の登録要件を満たせば保証業務実施者となることができるとした。なお、業務執行責任者については、要件として公認会計士資格を求めないこととされている。
時価総額1兆円未満5千億円以上のプライム上場企業は2029年3月期から
「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(以下、「WG」)の会合が10月30日に開催され、7月17日に公表された金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」中間論点整理(本誌1084号21頁参照)で結論が出ていなかった項目について検討を行った。
まず、適用スケジュールに関しては、中間論点整理では時価総額1兆円未満5千億円以上のプライム上場企業は2029年3月期から適用する方向性を示した上で、国内外の動向等に注視しつつ、令和7年中を目途に結論を出すこととされていた。
この点については、中間論点整理の公表以降、サステナビリティ情報についての国内外の動向には特段の変化が見られないことから、中間論点整理で示した通り、2029年3月期から適用することとされている(図1参照)。
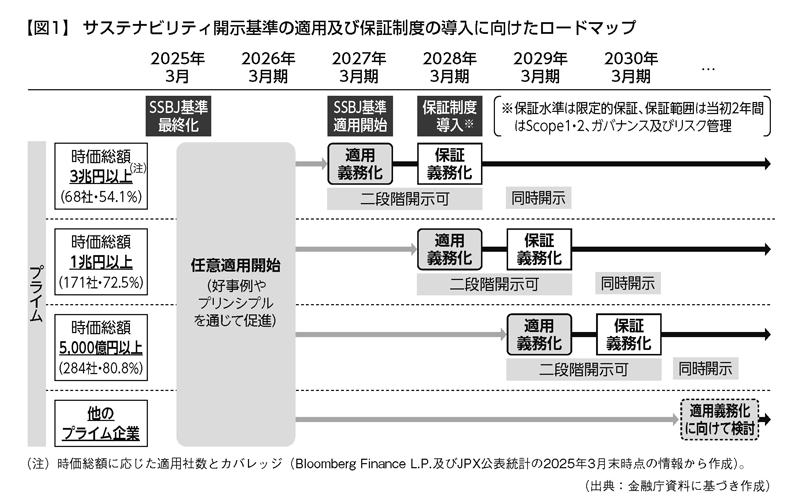
対象企業は5年平均時価総額で判断
SSBJ基準の適用対象企業の判断基準については、5年平均時価総額を基礎とすることとなった。具体的には、プライム市場上場企業のうち、前期末及びその前4事業年度末における時価総額の平均(5年平均時価総額)が1兆円以上の企業とする。適用開始期の末日時点ではプライム市場に上場している必要があるが、過去5事業年度の末日において上場している市場は、時価総額の算定ができれば足りるため、プライム市場に限らないとしている。したがって、2026年3月31日を基準として算定した5年平均時価総額が3兆円以上の企業は2027年3月期から適用となり、3兆円未満1兆円以上の企業については、2028年3月期から適用となる(図2参照)。ただし、2027年3月31日を基準として算定した5年平均時価総額が1兆円未満となった場合には、さらに適用が1年後ろ倒しとなる。
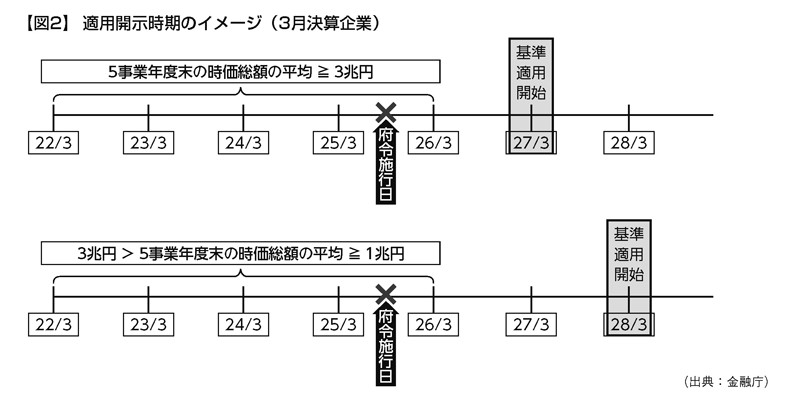
有価証券報告書の提出期限延長は実施せず
一方、中間論点整理から大きく方向転換となったのは保証義務付けの段階における有価証券報告書の提出期限の延長だ。提出期限を事業年度経過後4月以内に延長することも考えられるとされていたが、早期の情報開示を望む意見や、当初2年間の保証の範囲をスコープ1・2、ガバナンス及びリスク管理に限定する方向で検討されていることなどを踏まえ、提出期限の延長は実施せず、現行どおり事業年度終了後3月以内とすることとされた。WGの議論では概ね賛同する意見が聞かれたが、一部企業出身のメンバーからは、実務が定着していない中、企業の実務負担を軽減する観点から反対意見が聞かれている。
11月中にはSSBJ基準適用義務付けの内閣府令案を公表へ
SSBJ基準が2026年4月1日から適用されることを踏まえ、金融庁は11月中にも内閣府令等の改正案を公表する。来年1月中に公布し、施行する予定だ。
具体的には、サステナビリティ開示基準として、企業会計基準と同様、SSBJ基準を告示指定することとするほか、適用開始時期が確定している時価総額1兆円以上のプライム市場上場企業を対象にSSBJ基準を義務付けることとする。また、当初2年間における有価証券報告書の二段階開示や、SSBJ基準の適用状況及び二段階開示等の経過措置の適用状況の開示、将来情報等に係る社内開示手続等に係る情報の開示なども手当てする。そのほか、スコープ3排出量の虚偽記載等に係るセーフハーバーの整備については、ガイドラインを改正する予定だ。
業務執行責任者に公認会計士の資格を求めず
保証の担い手については、関係者の間で意見が分かれていたため、令和7年中に結論を出すこととされていた項目だ。この点、サステナビリティ情報の保証は、国際基準(保証基準(ISSA5000)、品質管理基準(ISQM1)、倫理・独立基準(IESSA))と整合性が確保された基準に準拠して実施するものとした上で、保証業務実施者を登録制とし、監査法人に限らず、監査法人以外であっても要件を満たす場合には登録可能とすることにしている。
登録要件については、「人的体制」及び「品質管理体制」が整備されていることとする。人的体制とは、サステナビリティ開示・保証に必要な専門的知識・経験及び能力を有する「業務執行責任者」が十分確保されていること、現行の実務経験者の知見を活用するなど、保証が実施できる十分な業務従事者が配置されていることなどを求める予定だ。業務執行責任者については、要件として公認会計士資格を求めるべきとの提案がなされていたが、資格自体は不要となっている。
また、品質管理体制については、保証業務実施者が業務の品質管理の状況を適切に評価する体制を整備するため、品質管理部門又は品質管理に主として従事する者が設置されていることや、保証業務チームが行った重要な判断及び到達した結論についての客観的評価を実施する審査担当者が十分確保されていることなどが求められる。
そのほか、品質管理のためのガバナンスを実効的なものとするため、保証業務実施者は「法人」であることとし、一定の資本金や出資金など財産的基礎を求めることとしている。
ローテーションルールなどを導入
また、保証業務実施者に対しては、保証の質を確保する観点から、財務諸表監査と同様、ローテーションルールや非保証業務との同時提供の禁止、守秘義務を課すこととしている。加えて、保証業務実施者が、サステナビリティ情報の適正性の確保に影響をおよぼすようなおそれがある事実(法令違反事実等)を発見し、企業において是正されない場合、当局へその旨を通知する制度を導入するとしている。会合では、金融商品取引法193条の3と同様、サステナビリティ情報の保証に関しても監査役等に通知した上で、是正が図られない場合には、内閣総理大臣(金融庁)への報告を義務付けるべきとの意見があった。
当面は金融庁が検査・監督
なお、自主規制機関については、制度導入時は見送りとなった。このため、当面の間は金融庁が検査・監督を行うこととし、実務が定着してから改めて検討することとしている。
要件を満たさない任意保証には一定の開示
「任意の保証」については、有価証券報告書における義務的保証の対象でない情報について保証を受けること、及び義務化対象ではない企業が保証を受けることと定義し、①SSBJ基準に基づいて作成されたサステナビリティ情報に対するもので、②登録されたサステナビリティ保証業務実施者によるものであり、かつ③登録業者が遵守する保証基準に沿ったものである場合、有価証券報告書へ保証報告書を添付できることとしている(図3参照)。
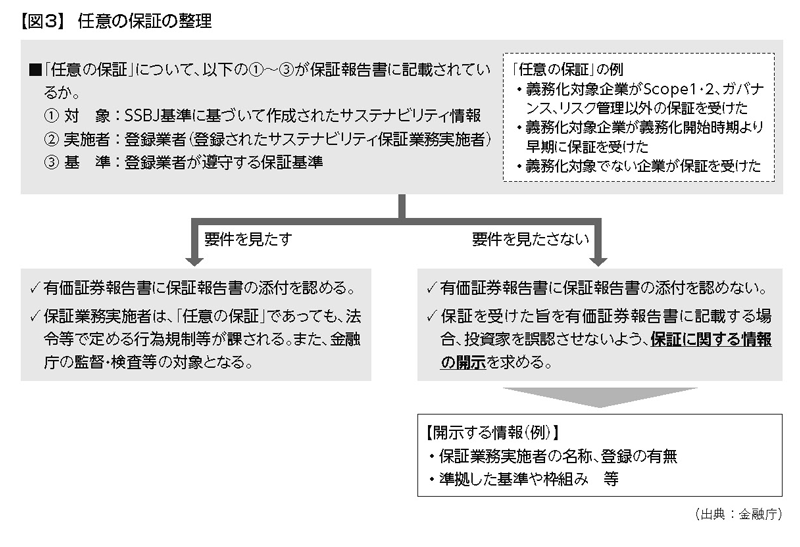
一方、これらの要件を満たさない場合については、有価証券報告書へ保証報告書の添付を認めない。また、要件を満たさない場合、企業が任意に保証を受けた旨を有価証券報告書に記載するときは、投資家が誤認することがないよう、例えば、保証業務実施者の名称・登録の有無、準拠した基準や枠組み等を開示することが考えられるとした。加えて、WGでは、警告的な文言の開示を求めるべきとの意見が複数寄せられている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























