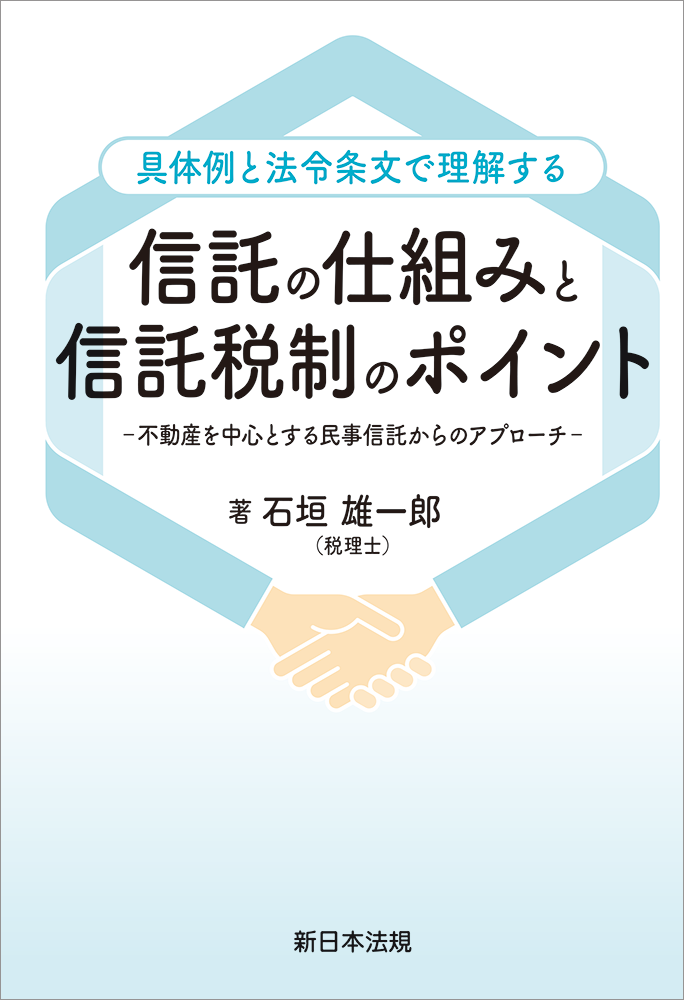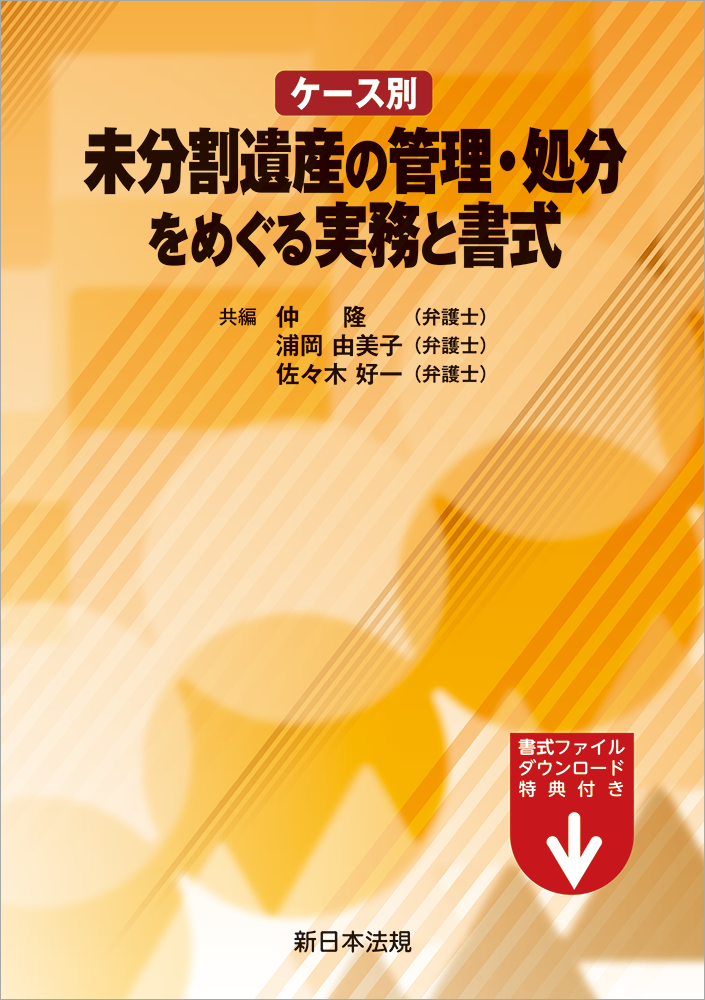税務ニュース2025年11月21日 最判後初の不動産事案への総則6項裁決(2025年11月24日号・№1100) 実質的な租税負担の公平に反する事情認め、鑑定評価による課税支持
国税不服審判所が令和7年1月10日、相続直前に被相続人が高額不動産を取得した事案について総則6項の適用を認め、通達評価額ではなく不動産鑑定評価額による課税を支持する裁決を出していたことが判明した(東裁(諸)令6第103号)。
本件では、被相続人(当時高齢)は、入院後間もない平成30年1月30日から4月12日にかけて、代理人である相続人らを介し合計約20億円規模の借入金により都内のマンション等5件を購入した。相続発生は最後の不動産の取得直後であり、相続人らは本件各不動産を通達評価額で申告したが、原処分庁は総則6項を適用し、鑑定評価額に基づき相続税の更正処分等を行った(通達評価額の合計380,718,601円に対し、鑑定評価額の合計は1,387,200,000円)。
審判所は最高裁令和4年4月19日判決の示した判断枠組みに依拠し、特定の者の相続財産の価額についてのみ通達評価額を上回る価額によることは、合理的な理由がない限り平等原則に反し違法としつつも、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが「実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」がある場合には、合理的な理由があると認められ、平等原則に違反しないとした。その上で、①本件各不動産の取得・借入れにより相続人らの相続税負担は著しく軽減され、また、②本件各不動産の取得・借入れは相続人らの租税負担の軽減を意図して行われたものであるから、上記の「実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」があると判断した。
②の認定に当たっては、(1)相続人らは、高齢の被相続人が入院し集中治療室で治療を受けていた平成29年12月末頃には、近い将来の相続発生を予想していたと推認されること、(2)相続直前に3か月という短期間で連続して高額不動産を複数取得したこと、(3)相続人が本件各不動産の取得・借入れに積極的に関与したこと、(4)被相続人の妻の相続時の経験や相続人に税理士がいたことなどから課税価格圧縮・相続税負担軽減効果を認識していたことなどを挙げ、本件各不動産の取得・借入れは、「相続人らの相続税の負担を減免させるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて企画して急ぎ実行されたもの」と認められるから、相続人らの租税負担の軽減を意図して行われたものと言えるとした。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -