解説記事2020年06月15日 ニュース特集 コロナ禍における研究開発税制の論点(2020年6月15日号・№838)
ニュース特集
控除上限引上げ、自社利用ソフトウェアも対象に……etc.
コロナ禍における研究開発税制の論点
コロナ禍が企業の業績に深刻なダメージを与える中、所得の大幅減により研究開発税制の「総額型」における法人税額の控除上限に抵触し、同税制の適用を十分に受けられなくなる企業が続出する可能性が高まっている。
研究開発税制のうち、総額型の控除率「10%超〜14%」の部分や売上高試験研究費割合が「10%超」の場合の控除上限・控除率の上乗せ措置等が令和2年度末をもって適用期限を迎えるが、研究開発税制はこれまで2年ごとに制度全体の改組が行われてきたことからすると(前回は平成31年度税制改正)、令和3年度税制改正ではこれらの措置の見直しが議論されることも予想される。
また、企業や実務家の間では、研究開発税制の取扱いの一部が時代に合わない部分が出て来ているとの指摘もある。現行制度上、「自社利用ソフトウェア」は将来の収益獲得等が見込まれる場合には資産計上しなければならないこととされているが、自社利用ソフトウェアに係る研究開発費の損金算入が認められない現状を放置したままでは、日本は世界で急速に進展するデジタル化に後れをとるのではないかとの懸念も浮上している。
コロナ禍で総額型の控除上限に抵触する企業続出も
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、企業の業績は急激に悪化しており、さらに、早期の完全な収束が見通せない中で、今期のみならず来期以降も十分な所得が生じないと見込む企業は多い。
こうしたなか懸念されるのが、研究開発税制の「総額型」における法人税額の控除上限への抵触だ。現行制度上、総額型における控除上限は原則として「法人税額の25%」相当額、最大で35%相当額とされている。現在でも控除上限に抵触する企業は多いが、所得の大幅な減少に伴い法人税額も減少すれば、控除上限に抵触する企業がさらに増加する可能性がある。
控除上限への抵触を回避するためには“天井”、すなわち控除上限を引き上げるしかない。研究開発税制のうち、総額型の控除率「10%超〜14%」の部分(図1参照)や売上高試験研究費割合が「10%超」の場合の控除上限・控除率の上乗せ措置等は令和2年度末をもって適用期限を迎えるが(図2、図3参照)、研究開発税制は2年に一度、制度全体の改組が行われており、試験研究費の増加インセンティブの大幅強化などが行われた平成31年度税制改正から2年目となる令和3年度税制改正では、単なる期限切れ部分の延長あるいは廃止に留まらない議論が展開されることも予想される。仮にこの見直し議論の中で控除上限という “天井”が引き上げられれば、コロナ禍で所得が減少した企業にとっては救済策となる。
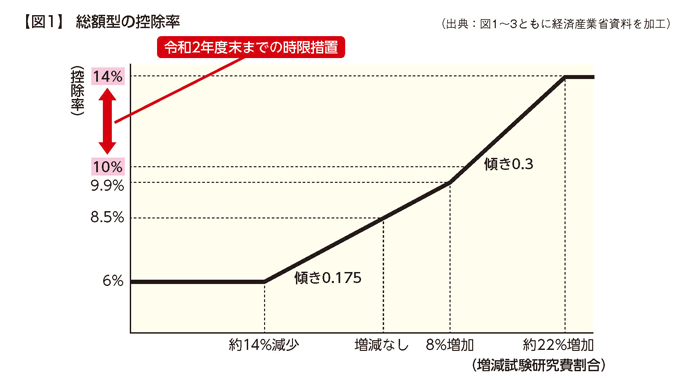
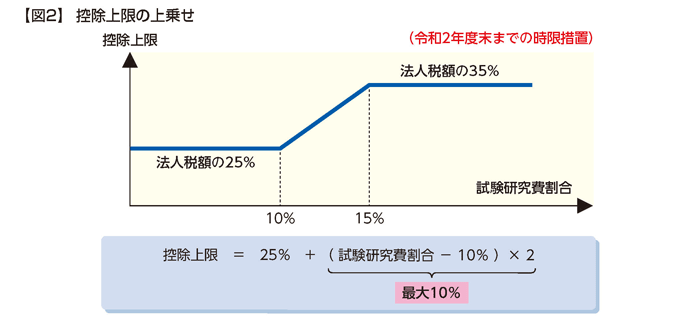
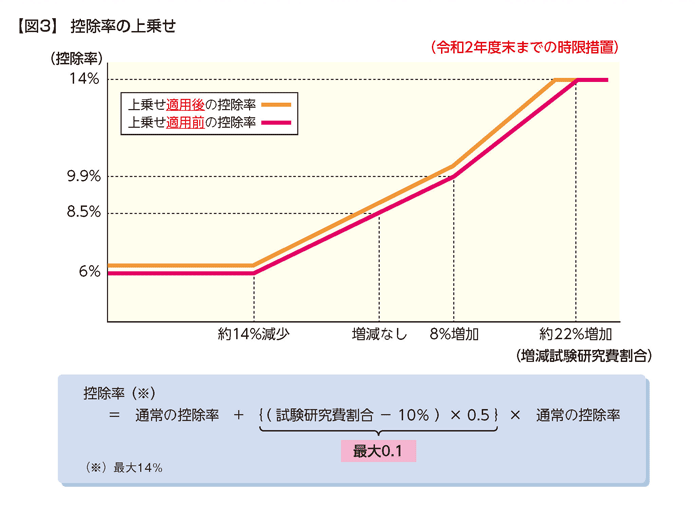
また、一部では繰越控除復活への期待も高まっている。特に業績が極めて悪化すると見込む企業からは、控除不足分を翌期において繰越控除できるようにすべきとの声も聞かれる。ただし、翌期で繰越控除ができるのは翌期に十分な課税所得(=税額)があるケースに限られる。なお、業績の悪化が長期化すると見込む企業からは、そもそも控除すべき法人税額が発生しないため、研究開発税制の拡充よりも欠損金の繰越控除制度の拡充(例えば繰越期間の延長)の方が有用との声もある。
リーマンショック時には繰越控除復活も、法人税率引下げ財源として廃止
実現に向けまず問題となるのが財源だ。コロナ禍で巨額の財政支出を余儀なくされている中、財源の裏付けがなければ実現は困難だろう。租特透明化法に基づく最新の適用実態の調査結果報告書によると、研究開発税制全体の適用額は平成30年度で6,216億円となっており、平成28年から3年連続で6,000億円程度で推移している。業績悪化に伴い、総額型における法人税額の控除上限に抵触する企業が続出すれば、適用額を例年並みに維持するために控除上限の引上げ、場合によっては控除不足分の繰越控除が議論される可能性はあろう。
過去には、リーマンショック時の経済危機対策として時限的に控除上限が20%から30%に引き上げられるとともに、控除限度超過額の繰越控除制度が拡充された実績もある。ただ、その後、紆余曲折を経て、30%の控除上限、繰越控除制度ともに平成27年度税制改正における法人税率引下げの財源として縮減・廃止されたという経緯があるだけに、税制当局としては、これらの“復活”は認めがたいというのが基本的な立場だろう。一方、リーマンショックを上回る景気後退が見込まれる中、危機対応という観点から実現に向けた議論が必要との意見も企業サイドにはある。
また、試験研究費の増加インセンティブ措置も議論の対象になる可能性がある。平成29年度改正により、総額型は増減試験研究費割合に基づき控除率が決定される仕組みとなり(図1参照)、試験研究費が増加した企業ほど高い控除率を享受できるようになった。これに対し、試験研究費が減少した企業は低い控除率に甘んじることとされた。さらに平成31年度改正(令和元年度改正)では、民間試験研究費対GDP割合3%達成という政府目標の下、この控除率のカーブの傾斜がきつくなった(図3参照)。コロナ禍の影響で業績が悪化する中、企業はそれでも試験研究費を「維持」しようとはするだろうが、「増加」はなかなか見込めない。政府が民間試験研究費の拡大という旗を下ろしていない中で、令和3年度税制改正でさらに控除率のカーブが急傾斜になれば、結果として控除率が低下する企業も出て来ることが想定されるため、企業の間では早くも警戒感が広がっている。
研究開発税制が見直されれば、“中小企業版の研究開発税制”である中小企業技術基盤強化税制についても同様の見直しが実施されることになろう。
パッケージソフトからクラウドへ ビジネスモデルの変化に税制が追い付かず
また、企業や実務家の間では、研究開発税制の取扱いの一部が時代に合わない部分が出て来ているとの指摘もある。具体的には、自社利用ソフトウェアが対象外となっている点だ。
現行の法人税基本通達7−3−15の3(ソフトウェアの取得価額に算入しないことができる費用)には次のような取扱いが規定されている。
次に掲げるような費用の額は、ソフトウェアの取得価額に算入しないことができる。
(1)略
(2)研究開発費の額(自社利用のソフトウェアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る。)
(3)略
すなわち、研究開発費の額は原則として取得価額に算入(資産計上)せず、試験研究費として研究開発税制の対象となるのに対し、自社利用ソフトウェアについてはその限りではなく、「将来の収益獲得」等が見込まれる場合には資産計上しなければならないこととされている。
この通達によれば、販売したパッケージソフトを顧客のPCにインストールして利用に供する場合は「販売目的ソフト」に該当し、研究開発費の損金算入が認められる一方、当該ソフトと同種・類似のソフトをプロバイダ側がクラウド環境に用意し顧客の利用に供する場合は「自社利用ソフト」に該当することとなり、研究開発費を資産計上しなければならないという異なる取扱いとなっている。
ネットワーク化の進展により、パッケージソフトを客先に売り切りで提供する形から、プロバイダ側が用意したクラウド環境を顧客の利用に供するサービスへとビジネスモデルの移行が急速に進んでいる。コロナ禍は日本のデジタル化の遅れを露呈させたが、自社利用ソフトに係る研究開発費の損金算入が認められない現状を放置したままでは、日本は益々他国に遅れをとるのではないかとの懸念も浮上している。
この問題を解決するため、試験研究費の範囲の明確化(あるいは拡大)として令和3年度改正で議論すべきとの声が高まっている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















