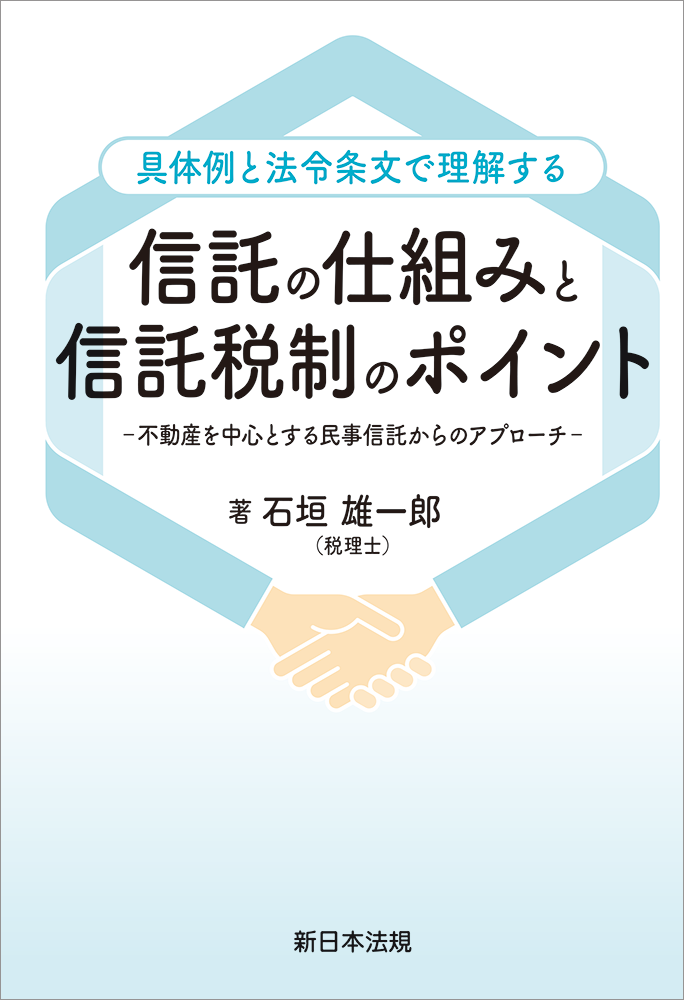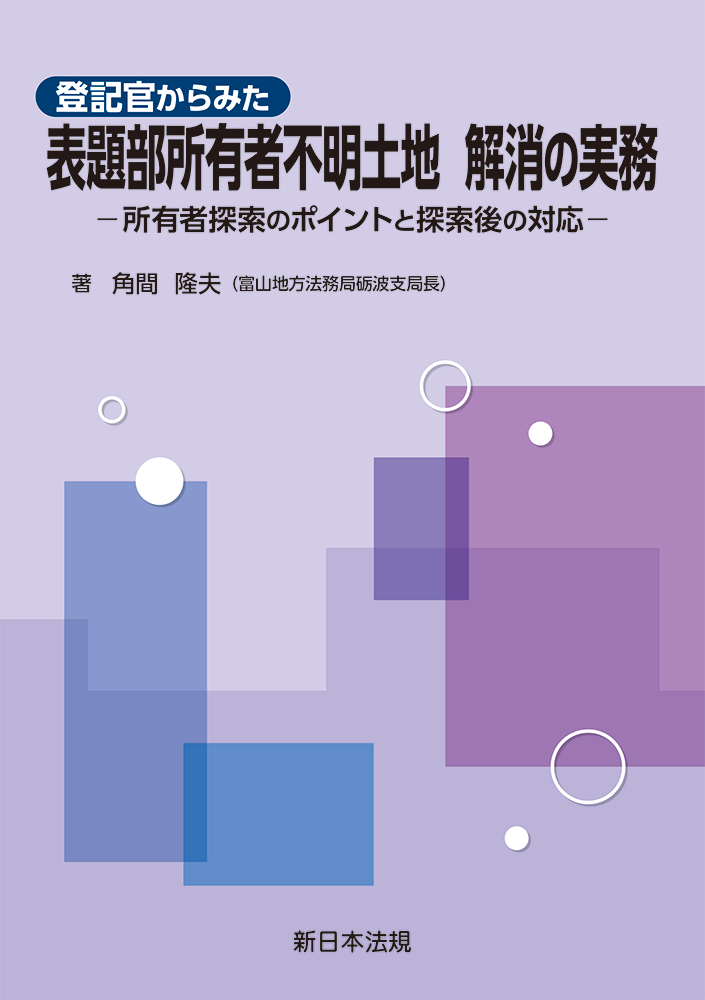教育・宗教2025年11月04日 “問題児”生徒の居場所は部活動、ならばそこで「複雑さを受け止めたい」 今も残る後悔と責任感、その陰で残業時間は積み上がる【私がここにいる理由 教員働き方改革の現場から】 提供:共同通信社

部室の床に散乱するたばこの吸い殻、カップ麺の空き容器―。西日本の公立中の教諭舟山誠(28)=仮名=が顧問を務める運動部には、世間的には「問題児」とされる生徒が何人か所属していた。
将則(まさのり)=仮名=もその一人。喫煙や飲酒を繰り返し、深夜に飲食店で暴れた際には駆け付けたこともある。両親は息子を心配し悩んでいたが「俺は親に見捨てられてる」と複雑な思いをのぞかせ、自宅に帰らないこともしばしばだった。(共同通信=池田絵美)
▽見捨てられたと感じた生徒、過去の苦い経験
ただ、将則は生活こそ荒れていたものの、部活動には熱心でチームメートにも優しかった。「子どもの心は大人の物差しでは測れない」と舟山。厳しく生活指導することなどは逆効果になりかねないと感じていた。
「クラスでのことは担任が見ている。僕は部活でつながっている」。将則が部活動をよりどころにしているのなら、顧問としてできることは何か。「あのプレー良かったな」。試合のことなど、とにかく一緒に競技の話をするよう心がけた。
舟山には過去に苦い経験がある。部内でトラブルを起こした生徒を巡り、様々な意見が出る中で守り切れず、退部に至らせてしまったのだ。「俺のこと見てくれるって言ったやん!」。生徒が吐き捨てるように言った言葉が、今も頭から離れない。
自分を頼って入部してきたはずなのに―。子どもが荒れる背景には、家族関係や貧困などさまざまな要因がある。「トラブルはしっかり指導した上で、部には残すべきだった。義務教育段階で切り捨ててしまえば負の連鎖を断ち切れない」。後悔は残る。
▽仕事は膨大、だけれども…
部活動が居場所になっている生徒は少なくない。不登校で授業には出なくても、部活動のために学校に来るケースもある。舟山はこの一件以来、「部活は大事なセーフティーネット」として、どんな生徒も受け止めるとの思いを強くした。
競技の指導以外にも、部活動関連の仕事は膨大だ。休日の試合の調整や遠征のバス手配など、担任業務と合わせると月の残業は80時間を超える。部活動の指導をやりたくて教員になったわけではなく、負担の軽減は今すぐにでも必要だと感じている。
だが部活動をやり遂げ、堂々と卒業していく生徒の姿を見るたびに、学校はこうした場をなくしてはいけないと強く思う。「迷惑ばっかかけてごめん。先生と過ごした部活は生きてきた中で一番楽しかった」。卒業生にもらった手紙の言葉が、日々の糧となっている。
▽教員の負担減へ「地域展開」目指すも、改革は道半ば
公立学校の教員の勤務時間は休憩時間を除き1日に7時間45分とされている。残業は「超勤4項目」と呼ばれる①実習②学校行事③職員会議④非常災害―にかかわる、やむを得ない仕事に限られる。それ以外の残業は存在しないとの建前だが、実際には事務作業や部活動指導などで多くの教員が長時間労働になっている。
とりわけ部活動は過剰な負担になっているとして、国は、公立中の部活動を地域のスポーツ団体などに委ねる「地域移行」を推進している。今年5月に開かれたスポーツ庁と文化庁の有識者会議が取りまとめた提言では、学校と地域を分断する印象を避け、地域全体で部活動を支えることを明確にするとして、名称を地域移行から「地域展開」とすると説明。2026年度からの6年間を「改革実行期間」と設定し、休日だけでなく平日の負担軽減にも取り組むことが確認された。
ただ、2024年度までに休日の地域移行や他校と合同での活動などに乗り出した部活動の割合は、運動部で37%、文化部で28%にとどまっている。
有識者会議では2025年度は運動部で53%、文化部で45%となる見通しが示されたが、関東地方の公立中の校長は「うちの地域にはそもそも受け入れ先となるようなスポーツクラブや団体がなく、指導者も時間帯や謝礼の壁がありなかなか見つからない」とこぼす。
また、学校内には部活動指導をやりたい教員もいれば、やりたくない教員もいる。どちらの意思も尊重されるべきで、どちらの考えも理解できるからこそ「学校として部活動の在り方をどうしていきたいかという総意をまとめるのも、一筋縄ではいかない」と悩む。
「子どもの機会を奪ってしまうことがないようにしたい」と語るのは、野球部の顧問を務める40代教員だ。中学から競技を始める生徒もいる中で、スポーツクラブなどではなく、さまざまな経歴を持つ子どもたちが集う部活動という“場”は「教育的効果が大きい」と指摘する。
「子どもたちのことを考えれば、教員の数を増やすことでひとりひとりの負担を軽減しつつ、現状を維持してあげたいと思うのが自分の本音だ」と話した。
(2025/11/04)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
関連カテゴリから探す
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -