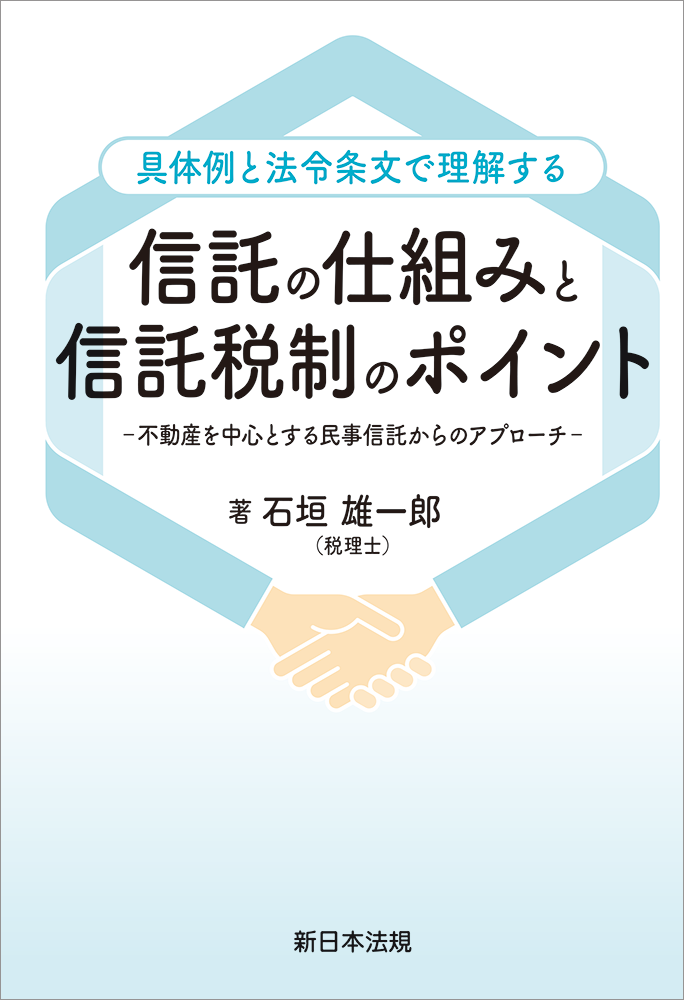民事2025年11月08日 生活保護一部補償が妥当 最高裁違法判決、厚労省 首相、初めて謝罪 提供:共同通信社

厚生労働省は7日、生活保護費の2013~15年の引き下げを違法とした最高裁判決を巡る専門委員会で対応の方向性を示した。減額分の補償は全額ではなく一部が妥当とした。当時の引き下げのうち適法とされた部分もあり「許容される」と理由を指摘した。次回会合で対応策の取りまとめを目指す。原告側は全額補償を求めており批判は必至だ。
高市早苗首相は衆院予算委員会で最高裁判決について「厚労相の判断の過程や手続きに過誤や欠落があったと指摘された。深く反省し、おわびする」と述べ、政府として初めて謝罪した。補償に関しては「専門委の審議結果を踏まえ適切に対応する」と語った。
訴訟弁護団の尾藤広喜(びとう・ひろき)弁護士は東京都内で記者会見し「謝罪するなら被害回復をどうするのか示してほしい」と訴えた。
厚労省は08年のリーマン・ショック以降に物価が下落していたなどとして、食費や光熱費などの「生活扶助」の基準を13~15年にかけて平均6・5%引き下げた。
今年6月の最高裁判決は、物価下落を反映する「デフレ調整」の引き下げは専門家の議論を経なかったとして「裁量の範囲の逸脱、乱用があった」と認定した。一方、受給者間の公平を図った「ゆがみ調整」は違法としなかったほか、補償について明示せず、国の賠償責任も否定した。
対応の方向性で厚労省は、一般低所得世帯の消費水準は当時落ち込んでいたとして、均衡を図る観点から消費水準分の引き下げを補償額に反映することも提案。少なくとも2・49%の引き下げを示したが、専門委で意見はまとまらなかった。
生活保護
最低生活費より収入が少ない人に不足分を支給する制度。最低生活費は、食費や光熱費といった日常生活の費用である「生活扶助」、家賃が中心の「住宅扶助」、医療サービス費用「医療扶助」などの合計額としている。金額は厚生労働相が定める生活保護基準を使って計算し、家族構成や地域で異なる。ここから年金などの収入を差し引いた額が生活保護費として支給される。8月時点で約165万世帯、約199万人が受給している。
(2025/11/08)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -