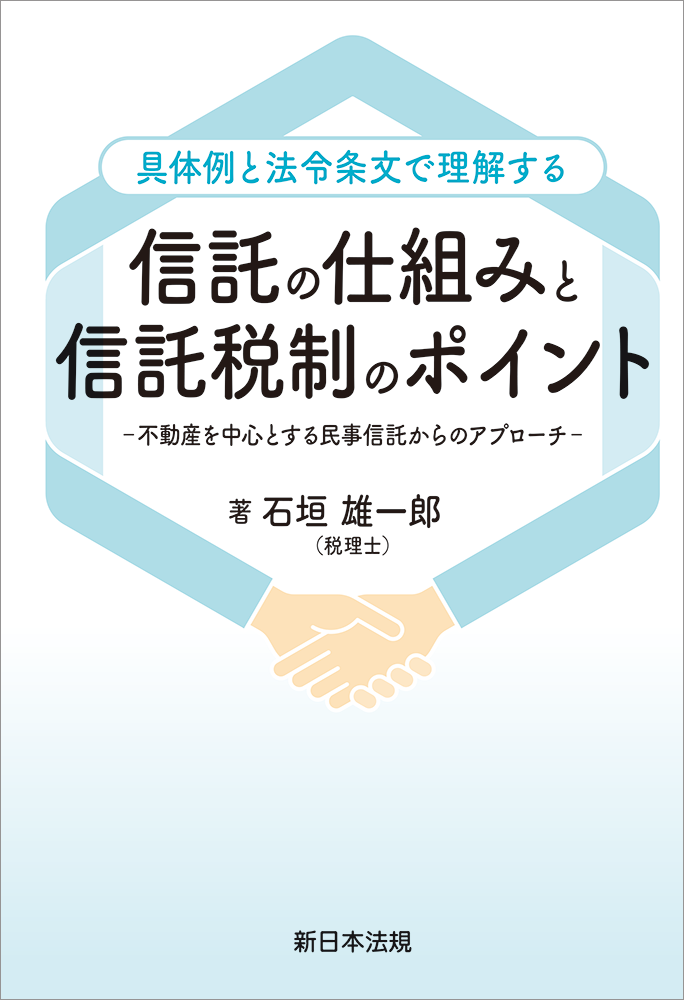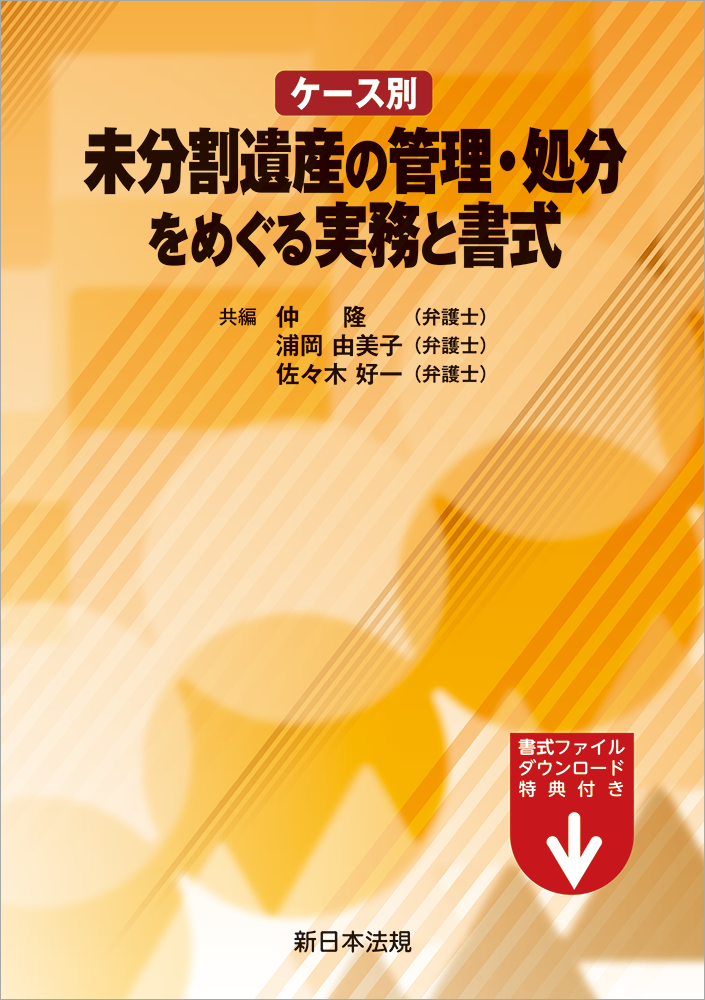一般2025年11月22日 9割の女性が家事や仕事をボイコットしてアイスランドが変わった日 男女平等への道は50年前、右派も左派もつながった「女性の休日」から始まった 提供:共同通信社

世界で男女平等が最も実現していると言われる、北欧のアイスランドで1975年10月24日、この国の女性の9割が参加したと言われる「ストライキ」が起きたことを知っているだろうか。
その日は「女性の休日」と呼ばれ、職場や家庭での男女格差や差別に憤った女性たちが一斉に家事や仕事をボイコットし、休んだ。自分たちがいなければ社会も家庭も立ちゆかないということを示し、アイスランドがジェンダー格差を縮めていく大きなきっかけになった。
それから半世紀がたった今年10月、この歴史的な一日を振り返ったドキュメンタリー映画「女性の休日」(パメラ・ホーガン監督)が日本で公開され、全国に反響が広がっている。さらに「女性の休日」の一日を子ども向けにつづった絵本「本当にやる! できる! 必ずやる! アイスランドの『女性の休日』」(ゆぎ書房)も出版された。注目が集まる中、国内でも男女平等に向けた、ムーブメントを起こそうという動きも活発化している。
年齢や党派、立場を超えて、なぜアイスランドの女性たちは団結し、ストライキを実現できたのだろうか。(共同通信編集委員・宮川さおり)
▽女の子は船乗りになれない?
50年以上前、アイスランドに生まれた、ある女の子は「大きくなったら船乗りになって世界を旅したい!」と話すと、「女の子にはそんなことはできない」と大人に言われた。銀行では女性たちが仕事を教えた新人の男性たちがみるみるうちに出世し、給料も追い抜いた。水産加工場でも、女性の方が魚の量が多くさばけるのに、なぜか男性の方が給料が高かった―。
世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数ランキングで16年連続1位で(日本は今年118位)、今や世界で最も男女平等を実現しているといえるアイスランドだが、ドキュメンタリー映画「女性の休日」が映し出す、1970年代までの様子は全く違う。家庭でも、家事や育児は、女性が担うことが当たり前だった。クリスマスともなると母親たちは、子どもたちのために新しい服を縫い、家の飾り付けをしてごちそうを作った。疲れ果てて休暇を楽しむどころではなかった。
そんな状況を変えようと、最初に立ち上がったのは革新的な女性グループ「レッドストッキング」の女性たち。疲れ切ったお母さんの人形を作って、クリスマスツリーに飾ってみたり、〝男性が選ぶ〟美人コンテストの会場に雌牛を連れて行ってみたり…。過激ではあるが、ユニークなプロテスト(抗議)が少しずつ注目を集め、人々の中に男女格差についての問題意識が芽生えていった。
性差別を撤廃するため、国連が「国際婦人年」と宣言した1975年。6月にアイスランドの各地から約300人の女性が集まり、女性会議を開いた。格差を解消するためには、どうすればいいのかを話し合い、その年の10月24日に一斉に仕事や家事を休む、事実上のスト決行を決めた。
ただし、その名前は「ストライキ」ではなく「女性の休日」。右派の女性たちから「ストライキなんて!」と反発があったので、「それなら『休日にしたら』」と誰かが提案した。それぞれ意見や主張があっても時には〝妥協〟も必要で、このあたりに幅広い人が団結できた秘訣があったようだ。
▽長い金曜日
運命の日に向け、女性たちが動き出した。男性たちは最初、「そんなことができるものか」とばかにしていた。けれでも、労働組合が各地で集会を開いただけでなく、女性たちはインターネットのない時代に、地域で、職場で、学校で、「女性の休日」を行うことを口コミで伝えていった。
ついにやってきた10月24日当日、首都レイキャビクの広場には、仕事や家事を休んだ2万5千人の女性たちが集結した。手をつなぎ、歌い、広場に来られなかった女性たちも家庭や地域で集った。外国に向かう船の上では、女性船員が船室にたてこもり、集会に向けて連帯を示す電報を送った。こうして全土の女性の9割がストに参加したと言われている。
一方、男性たちはそれまでしたことのない仕事や家事、子どもの世話を突然することになり、大混乱した。彼らはこの日を「長い金曜日」と呼んでいるという。
翌年、アイスランドでは男女平等法が制定され、5年後には選挙で民主的に選ばれた世界で初めての女性大統領が誕生した。このヴィグディス・フィンボガドッティルさんが「女の子は船乗りになれない」と言われた、まさにその少女だった。船乗りにはならなかったが、大統領になった。
▽女性が大切な存在であることを示す
現在のアイスランドのハッラ・トーマスドッティル大統領もストを目撃した一人だ。1975年当時は7歳の少女だった。今年5月に来日し、共同通信のインタビューで「女性の休日」をこう振り返った。
「その日は母の誕生日でした。母の姉妹やその夫たちが家に来て、男性陣が料理の準備や後片付けをしました。いつもと違ったので私が、『なぜ?』と尋ねたら、おばの一人が『女性が大切な存在だということを示すため』と教えてくれました。その言葉は私の心に刻まれ、人生に大きな影響を与えました」
「女性がいなければ職場も家庭も全く機能しないことに男性たちも気づいたんです」
トーマスドッティル大統領は、ストを「ジェンダー平等実現に向けた私たちの旅の大きな転機」と位置づけながらも、「まだ旅は終わったわけではない」と語る。アイスランドですら、一部の職種では男女の賃金格差が残り、性別に基づく暴力や性暴力の問題もなくなってはいないという。1975年以降もストは何度か実施され、2023年には48年ぶりに丸一日に及ぶ大規模ストも行われた。
50年目となった今年の10月24日には、女性だけでなく男性や、LGBTQ、移民といったマイノリティーを含む5万人以上が、記念の大規模ストに参加した。
首都レイキャビクの大通りには、かつての「女性の仕事」を連想させる洗濯物が掲げられ、彫刻にエプロンやベビーカーが飾られた。参加者は、会話をしたり、コーヒーを飲んだりしながら広場まで和やかに歩き、誰もが生きやすい社会の実現を誓った。
▽普通の女性たちが持っている力
10月に日本で公開されたドキュメンタリー映画「女性の休日」は1975年10月24日の一日とそこに至る過程を、当事者による証言とアーカイブ映像で振り返る。アメリカ出身で、ジャーナリストでもあるパメラ・ホーガン監督は、虐殺後のアフリカ・ルワンダの女性のリーダーシップを描いた作品など、報道で光が十分当たっていないテーマを多く取り上げてきた。どんな思いでこの映画を撮ったのか。
ホーガン監督がこのストについて知ったのは7年前。家族でアイスランドを旅行した際、ガイドブックを読んで知った。「初めはこんなことがあったなんて信じられなかった。『なんでみんなこのことを知らなかったの?』と。ほとんどおとぎ話に思えた」
公開までに時間がかかったのは、当時の映像が極めて少なかったことや、途中で新型コロナウイルス感染症の大流行があったため。映画の中で語る、スト参加者や活動家たちの現在の姿と、古い写真や映像に残る彼女たちを見つけ出して結びつける作業は困難を極めたという。そんな状況だったが、製作の歩みを止めなかったのは「彼女たちがどれだけ勇気ある行動をしていたのかを見せたかったから」。
こうしたテーマに興味を持つ背景を尋ねると、「セラピストに分析してもらわないといけないけれど」と前置きをしつつ、自身の母親の経験との関連性を挙げた。
「母は広告代理店のコピーライターでした。会議では彼女がアイデアを出すと男性たちに却下されるのに、1週間後には男性の一人が同じアイデアを出して昇進する…。母は同僚男性の半分の給料しかもらっていなかった。母の仕事への貢献や努力がどれほど見落とされていたのかを大人になってから知りました」。映画製作中、アイスランドで話を聞いていた女性にこう言われたという。「あなた、この映画をお母さんのために作っているんでしょう」
映画を通じて最も伝えたかったのは「普通の女性たちが、想像もできないようなことをかなえる力を持っているということ」。
「多くの女性たちに、社会を変える力を自分たちが持っていると気付いてほしい」
▽右派も左派も一緒に
映画だけでなく、「女性の休日」にまつわる関連書籍も国内で出版されている。絵本「本当にやる! できる! 必ずやる! アイスランドの『女性の休日』」(ゆぎ書房)は、ストを子ども向けにわかりやすく解説した。
女性同士の連帯を意味するシスターフッドをテーマにした近著のエッセー集「シスター〝フット〟エンパシー」(集英社)の冒頭で50年前のストを取り上げたのは、イギリス在住のコラムニスト、ブレイディみかこさんだ。
家の近所のカフェで「女性は未婚・既婚、子どものあるなしで分断されがちだよね」と話していたら、アイスランド出身の女性の店長が「私たちの国にすごいことがあってね」と、ストのことを教えてくれた。
調べてみると、全ての女性の9割が参加した「すごいスト」。右派も左派も、労働者階級もインテリ層も動いたことに「SNSがない時代に対面で話し合い、立場が違っても、お互いを尊重して『一緒にやろう』とつながっていたことに心が動いた」とブレイディさんは言う。
カフェの店長の「あの日起きたことを見た子どもは、男の子も女の子もフェミニストになった」という言葉に胸が熱くなった。ブレイディさんは「最近、自分や日本の将来への不安を口にする若い女性が増えた気がする」と語り、著書には彼女たちに向けて「縮こまらないで。元気を出して」とのメッセージを込めた。
▽つながり、変える
階層や年齢、党派を問わず、女性たちが連帯した「女性の休日」のコンセプトを取り入れ、変わらない日本でも何かアクションが起こせないだろうか―。触発された有志が「ジェンダー平等に向けたムーブメントを」とプロジェクトを立ち上げ、SNSの投稿に「#女性の休日」と付けて発信している。各地で映画を見たり絵本を読んだりして語り合う会が開かれ、多様なイベントが草の根的に広がる。
名古屋市の市民団体「ママライフバランス」は10月25日、ムーブメントの仕掛け人の一人でジャーナリストの山本恵子さんをゲストに招き、映画を見た後、ジェンダーにまつわる〝もやもや〟を語る会を開いた。
「短大卒女性だけお茶くみの練習をさせられた」「女性医師は男性の1・5倍働いて一人前と言われた」「専業主婦なのに旧姓を名乗る必要があるのかと言われた」…。
もやもやしているのは男性も同じ。「会社は製造業。男性(社員)を前提として成り立っている職場で、女性の部下にどう接していいか分からない」と打ち明ける人もいた。幅広い年代の約20人が参加し、2時間にわたって語り合った。
「それぞれの思いをシェアすることで、問題の原因は自分にではなく、社会の構造にあるということに気づく」と山本さんは指摘する。
山本さん自身がストを知ったのは今年5月。来日したアイスランドのハッラ・トーマスドッティル大統領の講演を聞いたことがきっかけだった。
「日本でも何かできないか」と考えていたところ、ジャーナリストの浜田敬子さん、地方の女性就労を支援する小安美和さんらと集まり、グループを結成した。それぞれのネットワークで、各地の女性グループや企業、大学関係者につながり、映画を見たり絵本を読んだりして語り合う会、ストについて学ぶ授業などプロジェクトが次々実現している。
山本さんは「まず語り、つながり合って、課題解決を考える。変革のための行動の第一歩。種まきです」と話す。
【編集後記】
最初に筆者が「女性の休日」を知ったのは、2020年。当時アイスランド駐日大使だったエーリン・フリーゲンリングさんへのインタビューだった。学生だったフリーゲンリングさんは、当時恋人だった夫とデモに参加したという。
彼女の話で印象的だったのは、働き始めたばかりの長女が「会議で男の人ばっかりが発言する」と文句を言うのに対して、「お母さんも同じ経験をした。あなたも大きな声で話せばいい」と励ましたというエピソード。
さらに「日本の女性の多くがフラストレーションを抱えているのがよく分かります。一方で誰かが何かを変えてくれるのを待っているようにも見えます。私の国だったらみんな『そんなの待っていられない』と立ち上がっています」と付け加えた。
誰かと激しく対立する必要はないけれど、何もしなかったら何も変わらない。立ち上がって、つながって、変えた国の女性の先輩の言葉は胸に響いた。
(2025/11/22)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
関連カテゴリから探す
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -