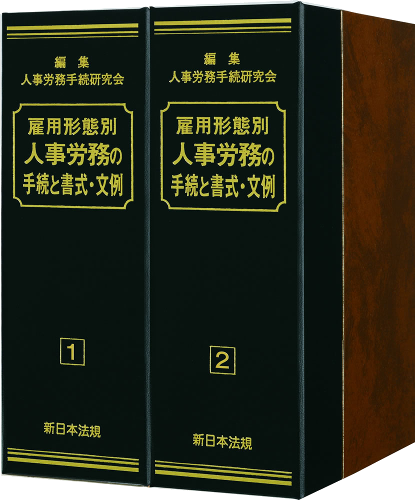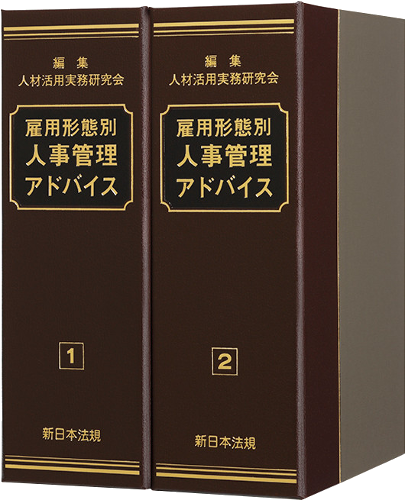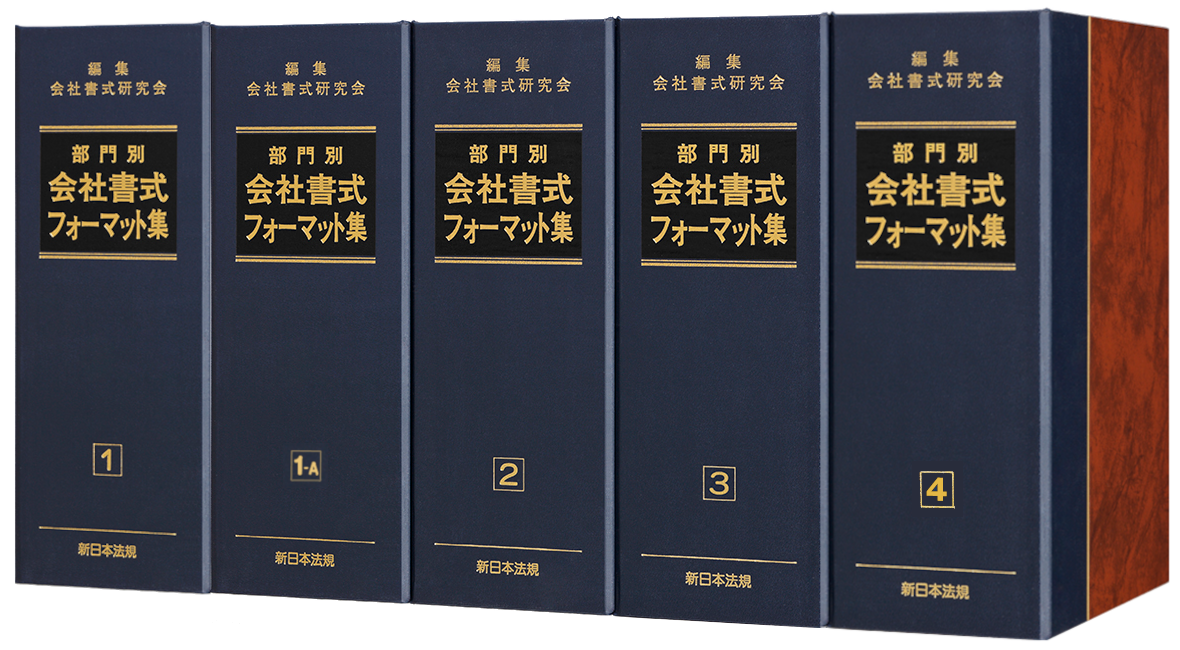PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(令和7年6月11日法律第63号〔第4条〕 公布の日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月11日
- 施行日 令和7年06月11日
厚生労働省
平成27年法律第64号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月11日
- 施行日 令和7年06月11日
厚生労働省
平成27年法律第64号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(法律第六三号)(厚生労働省)
一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正関係
1 職場における労働者の就業環境を害する言動に関する規範意識を醸成するための国による啓発活動
国は、職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策の充実に取り組むに際しては、何人も職場における労働者の就業環境を害する言動を行ってはならないことに鑑み、当該言動が行われることのない就業環境の形成に関する規範意識の醸成がなされるよう、必要な啓発活動を積極的に行わなければならないものとした。(第四条第四項関係)
2 治療と就業の両立支援対策
㈠ 事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業によって疾病又は負傷の症状が増悪すること等を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとした。(第二七条の三第一項関係)
㈡ 厚生労働大臣は、㈠の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を定め、これを公表するものとした。(第二七条の三第二項関係)
㈢ ㈡の指針は、労働安全衛生法第七〇条の二第一項に規定する指針と調和が保たれたものでなければならないものとした。(第二七条の三第三項関係)
㈣ 厚生労働大臣は、㈡の指針に従い、事業主又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができるものとした。(第二七条の三第四項関係)
3 職場における顧客等の言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等
㈠ 事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(以下4の㈤において「顧客等」という。)の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの(以下この㈠及び4の㈠において「顧客等言動」という。)により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとした。(第三三条第一項関係)
㈡ 事業主は、労働者が㈠の相談を行ったこと又は事業主による㈠の相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとした。(第三三条第二項関係)
㈢ 事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずる㈠の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならないものとした。(第三三条第三項関係)
㈣ 厚生労働大臣は、㈠から㈢までの事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとした。(第三三条第四項関係)
4 職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務
㈠ 国は、労働者の就業環境を害する顧客等言動を行ってはならないことその他当該顧客等言動に起因する問題(以下この4において「顧客等言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、各事業分野の特性を踏まえつつ、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならないものとした。(第三四条第一項関係)
㈡ 事業主は、顧客等言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる㈠の措置に協力するように努めなければならないものとした。(第三四条第二項関係)
㈢ 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならないものとした。(第三四条第三項関係)
㈣ 労働者は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる3の㈠の措置に協力するように努めなければならないものとした。(第三四条第四項関係)
㈤ 顧客等は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深めるとともに、労働者に対する言動が当該労働者の就業環境を害することのないよう、必要な注意を払うように努めなければならないものとした。(第三四条第五項関係)
二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正関係
1 求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等
㈠ 事業主は、求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この1の㈠及び㈡並びに2において「求職者等」という。)によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動(以下この1の㈠及び2の㈠において「求職活動等」という。)において行われる当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により当該求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう、当該求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとした。(第一三条第一項関係)
㈡ 事業主は、労働者が当該事業主による求職者等からの㈠の相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとした。(第一三条第二項関係)
㈢ 厚生労働大臣は、㈠及び㈡の事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとした。(第一三条第三項関係)
2 求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務
㈠ 国は、求職者等の求職活動等を阻害する1の㈠の言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この2において「求職活動等における性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならないものとした。(第一四条第一項関係)
㈡ 事業主は、求職活動等における性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる㈠の措置に協力するように努めなければならないものとした。(第一四条第二項関係)
㈢ 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならないものとした。(第一四条第三項関係)
㈣ 労働者は、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる1の㈠の措置に協力するように努めなければならないものとした。(第一四条第四項関係)
3 男女雇用機会均等推進者
事業主が選任する職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者の業務として、事業主の講ずる1の㈠及び2の㈡の措置等を加えるものとした。(第一九条関係)
三 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部改正関係
1 基本原則
女性の職業生活における活躍の推進に当たり留意すべき事項として、女性の健康上の特性を加えるものとした。(第二条第一項関係)
2 基本方針
女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針において定める事項として、職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な措置に関する事項を加えるものとした。(第五条第二項第三号関係)
3 基準に適合する認定一般事業主の認定の基準
基準に適合する認定一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けたものをいう。)の認定の基準として、事業主が講じている二の1の㈠の措置に関する情報を公表していることを加えるものとした。(第一二条関係)
4 特定事業主行動計画の変更手続の見直し
特定事業主(国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものをいう。以下同じ。)が特定事業主行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。)について内閣府令で定める軽微な変更を行う場合には、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況把握、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情についての分析等を行う義務を課さないものとした。(第一九条第三項及び第四項関係)
5 女性の職業選択に資する情報の公表の義務の適用拡大等
㈠ 一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が一〇〇人を超えるものに限る。)が、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関して定期的に公表すべき情報に、その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異及びその雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合を加えるものとした。(第二〇条第一項及び第二項関係)
㈡ 特定事業主が、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関して定期的に公表すべき情報に、その任用する職員の男女の給与の額の差異及びその任用する管理的地位にある職員に占める女性職員の割合を加えるものとした。(第二一条関係)
6 期限の延長
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の有効期限を一〇年間延長し、令和一八年三月三一日までとすることとした。(附則第二条第一項関係)
四 施行期日等
1 検討
㈠ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした。(附則第八条関係)
㈡ 政府は、特定受託事業者(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する特定受託事業者をいう。以下この㈡において同じ。)が受けた業務委託(同条第三項に規定する業務委託をいう。)に係る業務において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該業務に関係を有する者の言動であって、当該特定受託事業者に係る特定受託業務従事者(同条第二項に規定する特定受託業務従事者をいう。以下この㈡において同じ。)が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該特定受託業務従事者の就業環境が害されることのないようにするための施策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした。(附則第八条の二関係)
2 経過措置及び関係法律の整備
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行うこととした。(附則第二条~第七条及び第九条~第一六条関係)
3 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、次に掲げる事項は、次に定める日から施行することとした。
㈠ 一の1、三の1、2及び6並びに四の1の㈡ 公布の日
㈡ 一の2並びに三の4及び5 令和八年四月一日
一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正関係
1 職場における労働者の就業環境を害する言動に関する規範意識を醸成するための国による啓発活動
国は、職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策の充実に取り組むに際しては、何人も職場における労働者の就業環境を害する言動を行ってはならないことに鑑み、当該言動が行われることのない就業環境の形成に関する規範意識の醸成がなされるよう、必要な啓発活動を積極的に行わなければならないものとした。(第四条第四項関係)
2 治療と就業の両立支援対策
㈠ 事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業によって疾病又は負傷の症状が増悪すること等を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとした。(第二七条の三第一項関係)
㈡ 厚生労働大臣は、㈠の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を定め、これを公表するものとした。(第二七条の三第二項関係)
㈢ ㈡の指針は、労働安全衛生法第七〇条の二第一項に規定する指針と調和が保たれたものでなければならないものとした。(第二七条の三第三項関係)
㈣ 厚生労働大臣は、㈡の指針に従い、事業主又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができるものとした。(第二七条の三第四項関係)
3 職場における顧客等の言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等
㈠ 事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(以下4の㈤において「顧客等」という。)の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの(以下この㈠及び4の㈠において「顧客等言動」という。)により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとした。(第三三条第一項関係)
㈡ 事業主は、労働者が㈠の相談を行ったこと又は事業主による㈠の相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとした。(第三三条第二項関係)
㈢ 事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずる㈠の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならないものとした。(第三三条第三項関係)
㈣ 厚生労働大臣は、㈠から㈢までの事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとした。(第三三条第四項関係)
4 職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務
㈠ 国は、労働者の就業環境を害する顧客等言動を行ってはならないことその他当該顧客等言動に起因する問題(以下この4において「顧客等言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、各事業分野の特性を踏まえつつ、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならないものとした。(第三四条第一項関係)
㈡ 事業主は、顧客等言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる㈠の措置に協力するように努めなければならないものとした。(第三四条第二項関係)
㈢ 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならないものとした。(第三四条第三項関係)
㈣ 労働者は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる3の㈠の措置に協力するように努めなければならないものとした。(第三四条第四項関係)
㈤ 顧客等は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深めるとともに、労働者に対する言動が当該労働者の就業環境を害することのないよう、必要な注意を払うように努めなければならないものとした。(第三四条第五項関係)
二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正関係
1 求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等
㈠ 事業主は、求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この1の㈠及び㈡並びに2において「求職者等」という。)によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動(以下この1の㈠及び2の㈠において「求職活動等」という。)において行われる当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により当該求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう、当該求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとした。(第一三条第一項関係)
㈡ 事業主は、労働者が当該事業主による求職者等からの㈠の相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとした。(第一三条第二項関係)
㈢ 厚生労働大臣は、㈠及び㈡の事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとした。(第一三条第三項関係)
2 求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務
㈠ 国は、求職者等の求職活動等を阻害する1の㈠の言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この2において「求職活動等における性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならないものとした。(第一四条第一項関係)
㈡ 事業主は、求職活動等における性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる㈠の措置に協力するように努めなければならないものとした。(第一四条第二項関係)
㈢ 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならないものとした。(第一四条第三項関係)
㈣ 労働者は、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる1の㈠の措置に協力するように努めなければならないものとした。(第一四条第四項関係)
3 男女雇用機会均等推進者
事業主が選任する職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者の業務として、事業主の講ずる1の㈠及び2の㈡の措置等を加えるものとした。(第一九条関係)
三 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部改正関係
1 基本原則
女性の職業生活における活躍の推進に当たり留意すべき事項として、女性の健康上の特性を加えるものとした。(第二条第一項関係)
2 基本方針
女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針において定める事項として、職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な措置に関する事項を加えるものとした。(第五条第二項第三号関係)
3 基準に適合する認定一般事業主の認定の基準
基準に適合する認定一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けたものをいう。)の認定の基準として、事業主が講じている二の1の㈠の措置に関する情報を公表していることを加えるものとした。(第一二条関係)
4 特定事業主行動計画の変更手続の見直し
特定事業主(国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものをいう。以下同じ。)が特定事業主行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。)について内閣府令で定める軽微な変更を行う場合には、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況把握、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情についての分析等を行う義務を課さないものとした。(第一九条第三項及び第四項関係)
5 女性の職業選択に資する情報の公表の義務の適用拡大等
㈠ 一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が一〇〇人を超えるものに限る。)が、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関して定期的に公表すべき情報に、その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異及びその雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合を加えるものとした。(第二〇条第一項及び第二項関係)
㈡ 特定事業主が、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関して定期的に公表すべき情報に、その任用する職員の男女の給与の額の差異及びその任用する管理的地位にある職員に占める女性職員の割合を加えるものとした。(第二一条関係)
6 期限の延長
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の有効期限を一〇年間延長し、令和一八年三月三一日までとすることとした。(附則第二条第一項関係)
四 施行期日等
1 検討
㈠ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした。(附則第八条関係)
㈡ 政府は、特定受託事業者(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する特定受託事業者をいう。以下この㈡において同じ。)が受けた業務委託(同条第三項に規定する業務委託をいう。)に係る業務において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該業務に関係を有する者の言動であって、当該特定受託事業者に係る特定受託業務従事者(同条第二項に規定する特定受託業務従事者をいう。以下この㈡において同じ。)が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該特定受託業務従事者の就業環境が害されることのないようにするための施策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした。(附則第八条の二関係)
2 経過措置及び関係法律の整備
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行うこととした。(附則第二条~第七条及び第九条~第一六条関係)
3 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、次に掲げる事項は、次に定める日から施行することとした。
㈠ 一の1、三の1、2及び6並びに四の1の㈡ 公布の日
㈡ 一の2並びに三の4及び5 令和八年四月一日
関連商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -