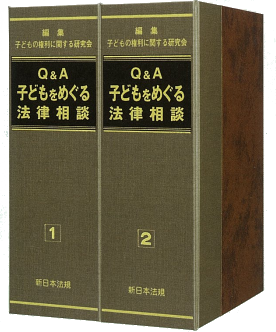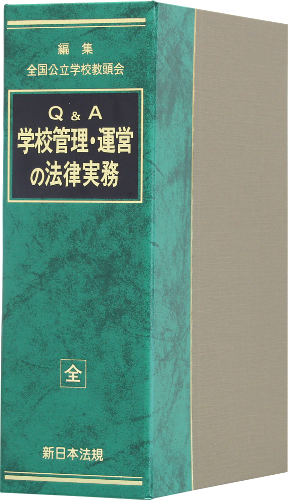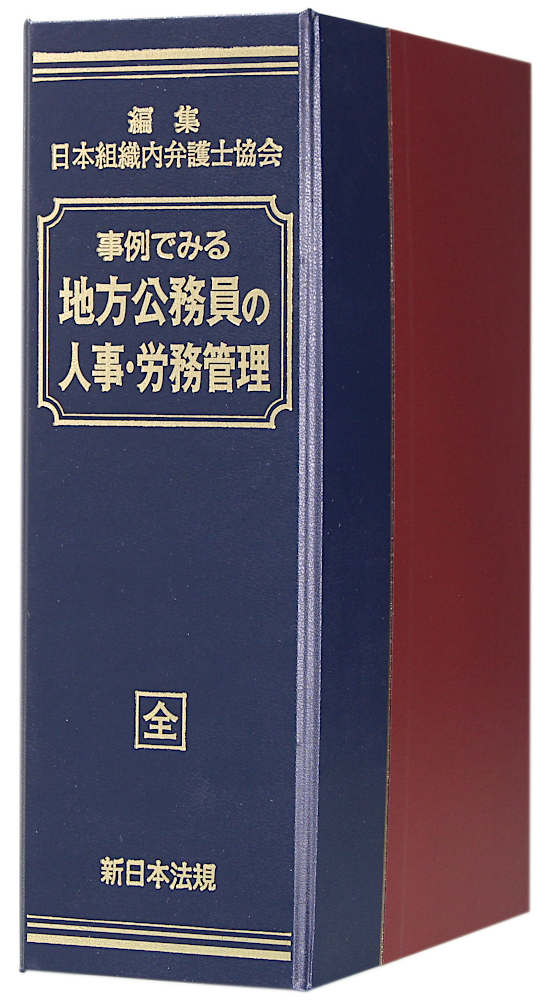PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
私立学校教職員共済法の一部改正(令和7年6月20日法律第74号〔第25条〕 令和9年9月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月20日
- 施行日 令和9年09月01日
厚生労働省
昭和28年法律第245号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月20日
- 施行日 令和9年09月01日
厚生労働省
昭和28年法律第245号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(法律第七四号)(厚生労働省)
一 国民年金法の一部改正関係
1 基礎年金の子の加算の見直し
㈠ 老齢基礎年金に子の加算を創設し、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の子があるときは、その子一人につきそれぞれ二六万九、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を加算することとした。(第二七条の六関係)
㈡ 障害基礎年金の子の加算を拡充し、受給権者によって生計を維持しているその者の子があるときは、その子一人につきそれぞれ二六万九、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を加算することとした。(第三三条の二第一項関係)
㈢ 遺族基礎年金の子の加算を拡充し、受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた子があるときは、その子一人につきそれぞれ二六万九、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を加算することとした。(第三九条第一項関係)
2 遺族厚生年金の受給権者について、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を可能とすることとした。(第二八条第一項関係)
3 子に対する遺族基礎年金について、生計を同じくするその子の父又は母があるときにその支給を停止する規定を削除することとした。(第四一条第二項関係)
4 国民年金基金又は国民年金基金連合会の加入員又は受給権者の死亡の届出について、届出義務者が戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、当該者は国民年金基金又は国民年金基金連合会に対する死亡の届出を不要とすることとした。(第一三八条関係)
5 脱退一時金の支給の請求について、再入国の許可を受けて日本を出国した者は、当該再入国の許可を受けている間、その請求ができないこととした。(附則第九条の三の二第一項関係)
二 厚生年金保険法の一部改正関係
1 厚生年金保険の適用拡大
㈠ 厚生年金保険の適用事業所について、事業の種類にかかわらず、常時五人以上の従業員を使用する事業所を適用事業所とすることとした。(第六条第一項関係)
㈡ 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である等の短時間労働者に係る厚生年金保険の適用除外の要件のうち、報酬が八万八、〇〇〇円未満であることとする要件を削除することとした。(第一二条関係)
2 厚生年金保険の標準報酬月額の等級区分について、最高等級の上に段階的に等級を加えるとともに、最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合に着目して、最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができることとした。(第二〇条関係)
3 遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金の請求を行っていない場合に、当該遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日後も老齢厚生年金の支給繰下げの申出を可能とすることとした。(第四四条の四及び第四四条の五関係)
4 在職老齢年金制度の支給停止調整額を六二万円とすることとした。(第四六条第三項関係)
5 厚生年金の加給年金の見直し
㈠ 老齢厚生年金の額に加算する加給年金額について、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の子があるときは、その子一人につきそれぞれ二六万九、六〇〇円に改定率を乗じて得た額とするとともに、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の六五歳未満の配偶者があるときは、二〇万二、二〇〇円に改定率を乗じて得た額とすることとした。(第四四条第一項及び第二項関係)
㈡ 障害厚生年金に子の加給年金を創設し、受給権者によって生計を維持しているその者の子があるときは、その子一人につきそれぞれ二六万九、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を加算することとした。(第五〇条の二関係)
㈢ 遺族厚生年金に子の加給年金を創設し、受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた子があるときは、その子一人につきそれぞれ二六万九、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を加算することとした。(第六二条の二関係)
6 遺族厚生年金の見直し
㈠ 遺族厚生年金を受けることができる遺族を、被保険者又は被保険者であった者の配偶者(以下この6において単に「配偶者」という。)、子、父母、孫又は祖父母(父母又は祖父母については、六〇歳以上である者に限る。)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとすることとした。(第五九条第一項関係)
㈡ 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた六〇歳未満である配偶者は、㈠にかかわらず、遺族厚生年金を受けることができる遺族とすることとした。(第五九条第二項関係)
㈢ 中高齢寡婦加算を段階的に減額し、令和三五年四月二日以降に遺族厚生年金の受給権を取得した者については当該加算をしないこととしつつ、遺族厚生年金の受給権を取得した当時、六〇歳未満の配偶者であって、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する期間がないもの又は当該遺族基礎年金の受給権を有する期間があり、かつ、六〇歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したものに支給される遺族厚生年金(以下この6において「六〇歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金」という。)については、遺族厚生年金の額に死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の四分の一に相当する額を加算することとした。(第六二条第一項関係)
㈣ 六〇歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権は、㈤による当該遺族厚生年金の全部の支給の停止が二年間継続したとき、老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は六五歳に達したときは、消滅することとした。(第六三条第二項関係)
㈤ 六〇歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金は、その受給権者が当該遺族厚生年金の受給権を取得した日等から起算して五年を経過した日の属する月の翌月以後の月分について、その受給権者の前年の所得が、国民年金法第九〇条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないものとされる所得の額を勘案してその者の扶養親族の有無及び数に応じて政令で定める額を超えるときは、その前年の所得の額に応じ、当該遺族厚生年金の全部又は一部の支給を停止することとした。(第六五条第一項~第三項関係)
㈥ 障害厚生年金又は障害基礎年金の受給権者であって、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するものであるとき等は、その該当する間は、㈤を適用しないこととした。(第六五条第四項関係)
㈦ 死亡した被保険者が被保険者であった期間中に配偶者を有していた場合において、当該被保険者の配偶者(以下この㈦において「死別配偶者」という。)が六〇歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権者であるとき又は当該遺族厚生年金の受給権者であったときは、死別配偶者は、実施機関に対し、死別配偶者の婚姻等対象期間(当該被保険者と当該死別配偶者との婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間であった期間をいう。)の標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定を請求することができることとした。(第七八条の二一の二第一項関係)
7 離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定の請求について、その請求の期限を五年とすることとした。(第七八条の二第一項関係)
8 厚生労働大臣は、第一号厚生年金被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、銀行、信託会社その他の機関に対し、第一号厚生年金被保険者又は第一号厚生年金被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求めることができることとした。(第一〇〇条の二第六項関係)
9 脱退一時金の支給の請求について、再入国の許可を受けて日本を出国した者は、当該再入国の許可を受けている間、その請求ができないこととした。(附則第二九条第一項関係)
三 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五五年法律第八二号)の一部改正関係
二の5の㈡及び㈢並びに6の㈢の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(附則第六三条関係)
四 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号)の一部改正関係
1 支給事由の生じた日が令和一八年四月一日前にある障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金及び遺族厚生年金について、直近一年間に保険料未納期間がないときは、保険料納付要件を満たしているものとすることとした。(附則第二〇条及び第六四条関係)
2 一の1の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(附則第一八条第五項関係)
3 二の3の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(附則第五九条第一項、第六二条第一項、第八二条第三項並びに第八四条第三項及び第四項関係)
4 二の5の改正に伴う所要の改正を行うとともに、老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額の特別加算額について二の5の㈠に準じた改正を行うこととした。(附則第六〇条第二項、第七八条第二項及び第八七条第三項関係)
5 二の6の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(附則第五四条、第七三条並びに第七四条第一項、第四項及び第五項関係)
五 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八二号)の一部改正関係
二の3の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(附則第三三条の三関係)
六 国民年金法等の一部を改正する法律(平成一二年法律第一八号)の一部改正関係
二の3の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(附則第九条第四項、第二〇条第一項、第二一条第二項、第二三条第三項及び第二四条第五項関係)
七 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正関係
移行農林共済年金について、二の3及び5の㈡に準じた改正を行うこととした。(附則第一六条第四項及び第一三項関係)
八 国民年金法等の一部を改正する法律(平成一六年法律第一〇四号)の一部改正関係
三〇歳未満の国民年金第一号被保険者等であって本人及び配偶者の所得が一定以下であるものに係る国民年金の保険料の免除の特例を五年間延長し、令和一七年六月までとすることとした。(附則第一九条第二項関係)
九 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正関係
1 被用者保険の適用拡大
㈠ 特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)に使用される特定四分の三未満短時間労働者を厚生年金保険及び健康保険の被保険者としない取扱いについて、令和一七年九月三〇日までの間の措置とすることとした。(附則第一七条及び第四六条関係)
㈡ ㈠の取扱いについては段階的に縮小することとし、短時間労働者を適用対象とすべき特定適用事業所の範囲について、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、令和九年一〇月一日から令和一一年九月三〇日までは当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時三五人を超えるものとし、令和一一年一〇月一日から令和一四年九月三〇日までは当該総数が常時二〇人を超えるものとし、令和一四年一〇月一日から令和一七年九月三〇日までは当該総数が常時一〇人を超えるものとすることとした。(附則第一七条の三の二及び第四六条の二関係)
一〇 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正関係
二の5の㈠及び6の㈢の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(附則第二一条及び第三五条第一項関係)
一一 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正関係
1 存続厚生年金基金又は存続連合会の受給権者の死亡の届出について、届出義務者が戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、当該者は存続厚生年金基金又は存続連合会に対する死亡の届出を不要とすることとした。(附則第五条第一項及び第三八条第一項関係)
2 存続厚生年金基金について、二の3に準じた改正を行うとともに、二の6の㈦の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(附則第五条第二項関係)
3 個人型年金の加入要件について、存続厚生年金基金の脱退一時金相当額を個人型年金に移換しようとする者及び存続連合会の年金給付等積立金等又は積立金を個人型年金に移換しようとする者は個人型年金加入者となることができることとした。(附則第五条第三項及び第三八条第三項関係)
一二 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正関係
三〇歳以上五〇歳未満の国民年金第一号被保険者等であって本人及び配偶者の所得が一定以下であるものに係る国民年金の保険料の免除の特例を五年間延長し、令和一七年六月までとすることとした。(附則第一四条第一項関係)
一三 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正関係
独立行政法人福祉医療機構は、令和九年四月一日から当分の間、貸付金の弁済に充当した後の残余の金銭の支払を行う業務その他厚生労働省令で定める関連業務を行うことができることとした。(附則第三九条第一項関係)
一四 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正関係
1 一の1及び二の5の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(第三一条第六項、第三二条第四項、第六項及び第七項並びに第三三条の二関係)
2 二の6の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(第一六条第四項、第二七条、第三一条第一項、第三三条第一項及び第三項並びに第四〇条第六項及び第七項関係)
一五 国家公務員共済組合法の一部改正関係
標準報酬の等級について、二の2に準じた改正を行うこととした。(第四〇条第一項関係)
一六 地方公務員等共済組合法の一部改正関係
標準報酬の等級について、二の2に準じた改正を行うこととした。(第四三条第一項関係)
一七 私立学校教職員共済法の一部改正関係
標準報酬月額の等級について、二の2に準じた改正を行うこととした。(第二二条第一項関係)
一八 確定給付企業年金法の一部改正関係
1 確定給付企業年金における受給権者の死亡の届出について、届出義務者が戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、当該者は事業主及び企業年金基金又は企業年金連合会に対する死亡の届出を不要とすることとした。(第九九条関係)
2 厚生労働大臣は、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書の提出を受けたときは、当該報告書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものを公表することとした。(第一〇〇条第四項関係)
一九 確定拠出年金法の一部改正関係
1 企業型年金の規約の承認申請の際に添付すべき書類のうちその一部の提出を要しないこととした。(第三条第四項関係)
2 簡易企業型年金に係る規定を削除することとした。(第三条第五項、第一九条第二項及び第二三条第一項関係)
3 企業型年金の規約で企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合において、企業型年金加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えてはならない旨の要件を削除することとした。(第四条第一項関係)
4 厚生労働大臣は、企業型年金に係る業務についての報告書の提出を受けたときは、当該報告書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものを公表することとした。(第五〇条第二項関係)
5 個人型年金の加入要件について、改正前の加入要件に該当しない六〇歳以上七〇歳未満の者であって、申出の日の前日において個人型年金加入者であったもの若しくは個人型年金運用指図者であったもの、個人別管理資産の移換の申出をしたもの、脱退一時金相当額の移換の申出をしようとするもの、残余財産の移換の申出をしようとするもの又は積立金の移換の申出をしようとするものは、個人型年金加入者となることができることとした。(第六二条第一項関係)
6 中小事業主掛金を拠出しようとする中小事業主が行う届出について、厚生労働省令で定める事項等の届出先を国民年金基金連合会とするとともに、国民年金基金連合会が当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に当該届出に係る書類の写しを送付しなければならないこととした。(第六八条の二第六項及び第七項関係)
7 企業型年金運用指図者等の死亡の届出について、届出義務者が戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、当該者は国民年金基金連合会に対する死亡の届出を不要とすることとした。(第一一三条第一項関係)
二〇 石炭鉱業年金基金法の一部改正関係
石炭鉱業年金基金について、定款において解散及び清算に関する事項を定めなければならないものとし、事業の継続の困難を理由として厚生労働大臣の認可を受けた場合又は厚生労働大臣の解散命令があった場合に解散するものとし、石炭鉱業年金基金が解散する日における積立金の額が、基金が負う坑内員及び坑内員であった者並びに坑外員及び坑外員であった者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務その他当該給付の支給に係る事情を考慮して厚生労働省令で定めるところにより算定した額を下回る場合は、当該下回る額を会員が一括して拠出しなければならないこととした。(第八条第一項、第三二条第五項、第三六条及び第三六条の三関係)
二一 石炭鉱業年金基金法を廃止することとした。
二二 独立行政法人福祉医療機構法の一部改正関係
独立行政法人福祉医療機構は、令和九年三月三一日までの期間、小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務を行うこととした。(附則第五条の二第二項関係)
二三 健康保険法の一部改正関係
1 健康保険の適用拡大
㈠ 健康保険の適用事業所について、事業の種類にかかわらず、常時五人以上の従業員を使用する事業所を適用事業所とすることとした。(第三条第三項関係)
㈡ 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である等の短時間労働者に係る健康保険の適用除外の要件のうち、報酬が八万八、〇〇〇円未満であることとする要件を削除することとした。(第三条第一項関係)
2 二の8に準じた改正を行うこととした。(第一九九条第一項関係)
二四 船員保険法の一部改正関係
二の8に準じた改正を行うこととした。(第一四七条関係)
二五 独立行政法人農業者年金基金法の一部改正関係
二の1の㈠により農業者年金の被保険者が農業者年金の被保険者でなくなった場合において、その農業者年金の被保険者でなくなった日の属する月からその者を農業者年金の被保険者とみなして独立行政法人農業者年金基金法第一三条の規定を適用したとすればその者が農業者年金の被保険者の資格を喪失することとなる日又はその者が事業所に使用されなくなった日のいずれか早い日の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間は、その者の申出により、保険料納付済期間等に算入することとした。(附則第九条関係)
二六 検討規定等
1 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二条第一項関係)
2 政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二条第二項関係)
3 政府は、高齢者の就業の実態等を踏まえ、将来の基礎年金の給付水準の向上等を図るため、所要の費用を賄うための安定した財源を確保するための方策も含め、国民年金第一号被保険者の被保険者期間を延長することについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二条第三項関係)
4 政府は、国民年金第三号被保険者の在り方について国民的な議論が必要であるという認識の下、その議論に資するような国民年金第三号被保険者の実情に関する調査研究を行い、その在り方について検討を行うこととした。(附則第二条第四項関係)
5 令和六年における国民年金法に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法に規定する財政の現況及び見通しを踏まえ、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条第一項及び第三項の規定による検討を引き続き行うに際して今後の社会経済情勢の変化を見極めるため、この法律の公布の日の属する年度の翌年度から、厚生年金保険法に規定する財政の現況及び見通しが同日以後初めて作成される日の属する年度の翌年度までの間は、同法第三四条第一項に規定する調整期間とすることとした。この場合、マクロ経済スライドによる調整においては、その調整率を三分の一に軽減することとした。(附則第三条関係)
6 政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、この法律の公布の日以後初めて作成される財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法に規定する調整期間の見通しと厚生年金保険法に規定する調整期間の見通しとの間に著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により老齢基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権者の将来における老齢基礎年金の給付水準の向上を図るため、国民年金法第一六条の二第一項の調整と厚生年金保険法第三四条第一項の調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずることとした。この場合において、給付と負担の均衡がとれた持続可能な公的年金制度の確立について検討を行うこととした。(附則第三条の二第一項関係)
7 政府は、6の法制上の措置を講ずる場合において、老齢基礎年金の額及び老齢厚生年金の額の合計額が、当該措置を講じなかったとしたならば支給されることとなる老齢基礎年金の額及び老齢厚生年金の額の合計額を下回るときは、その影響を緩和するために必要な法制上の措置その他の措置を講ずることとした。(附則第三条の二第二項関係)
二七 施行期日等
1 厚生年金保険等の適用事業所に関する経過措置
㈠ 二の1の㈠の施行の際現に存する改正前の厚生年金保険法第六条第一項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所又は事務所(国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であって、常時従業員を使用するものを除く。)については、当分の間、なお従前の例により、厚生年金保険の適用事業所としないこととした。(附則第一八条関係)
㈡ 二三の1の㈠の施行の際現に存する改正前の健康保険法第三条第三項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所(国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するものを除く。)については、当分の間、なお従前の例により、健康保険の適用事業所としないこととした。(附則第三七条関係)
2 短時間被保険者の厚生年金保険料等に関する経過措置
㈠ 厚生年金保険の適用拡大の対象となる適用事業所等の事業主は、実施機関に申出をした場合は、七〇歳未満であるその短時間被保険者(厚生年金保険の標準報酬月額等級のうち第一級から第六級までに該当する者に限る。)に係る事業主の負担すべき厚生年金保険料(標準賞与額に係るもの等を除く。)の負担の割合を、短時間被保険者の標準報酬月額等級に応じて別に定める割合に増加することができるものとし、この場合において、短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額(申出があった日の属する月から通算して三六月間の各月に係るものに限る。)のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に厚生年金保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合を乗じて得た額は、徴収を行うことを要しなかったものとみなすこととした。(附則第二二条及び第二三条並びに附則別表第二関係)
㈡ 健康保険の適用拡大の対象となる適用事業所等の事業主は、保険者等に申出をした場合は、その短時間被保険者(健康保険の標準報酬月額等級のうち第一級から第九級までに該当する者に限る。)に係る事業主の負担すべき健康保険料(標準賞与額に係るもの等を除く。)の負担の割合を、短時間被保険者の標準報酬月額等級に応じて別に定める割合に増加することができるものとし、この場合において、短時間被保険者に係る健康保険料の額(申出があった日の属する月から通算して三六月間の各月に係るものに限る。)のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に一般保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合を乗じて得た額は、徴収を行うことを要しなかったものとみなすこととした。(附則第二四条及び第二五条並びに附則別表第三関係)
3 二六の5から7まで並びに1及び2のほか、この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行うこととした。(附則第一条第二項及び第三項、第四条~第一七条、第一九条~第二一条、第二六条~第三六条並びに第三八条~第五五条並びに附則別表第一関係)
4 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行することとした。
一 国民年金法の一部改正関係
1 基礎年金の子の加算の見直し
㈠ 老齢基礎年金に子の加算を創設し、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の子があるときは、その子一人につきそれぞれ二六万九、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を加算することとした。(第二七条の六関係)
㈡ 障害基礎年金の子の加算を拡充し、受給権者によって生計を維持しているその者の子があるときは、その子一人につきそれぞれ二六万九、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を加算することとした。(第三三条の二第一項関係)
㈢ 遺族基礎年金の子の加算を拡充し、受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた子があるときは、その子一人につきそれぞれ二六万九、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を加算することとした。(第三九条第一項関係)
2 遺族厚生年金の受給権者について、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を可能とすることとした。(第二八条第一項関係)
3 子に対する遺族基礎年金について、生計を同じくするその子の父又は母があるときにその支給を停止する規定を削除することとした。(第四一条第二項関係)
4 国民年金基金又は国民年金基金連合会の加入員又は受給権者の死亡の届出について、届出義務者が戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、当該者は国民年金基金又は国民年金基金連合会に対する死亡の届出を不要とすることとした。(第一三八条関係)
5 脱退一時金の支給の請求について、再入国の許可を受けて日本を出国した者は、当該再入国の許可を受けている間、その請求ができないこととした。(附則第九条の三の二第一項関係)
二 厚生年金保険法の一部改正関係
1 厚生年金保険の適用拡大
㈠ 厚生年金保険の適用事業所について、事業の種類にかかわらず、常時五人以上の従業員を使用する事業所を適用事業所とすることとした。(第六条第一項関係)
㈡ 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である等の短時間労働者に係る厚生年金保険の適用除外の要件のうち、報酬が八万八、〇〇〇円未満であることとする要件を削除することとした。(第一二条関係)
2 厚生年金保険の標準報酬月額の等級区分について、最高等級の上に段階的に等級を加えるとともに、最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合に着目して、最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができることとした。(第二〇条関係)
3 遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金の請求を行っていない場合に、当該遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日後も老齢厚生年金の支給繰下げの申出を可能とすることとした。(第四四条の四及び第四四条の五関係)
4 在職老齢年金制度の支給停止調整額を六二万円とすることとした。(第四六条第三項関係)
5 厚生年金の加給年金の見直し
㈠ 老齢厚生年金の額に加算する加給年金額について、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の子があるときは、その子一人につきそれぞれ二六万九、六〇〇円に改定率を乗じて得た額とするとともに、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の六五歳未満の配偶者があるときは、二〇万二、二〇〇円に改定率を乗じて得た額とすることとした。(第四四条第一項及び第二項関係)
㈡ 障害厚生年金に子の加給年金を創設し、受給権者によって生計を維持しているその者の子があるときは、その子一人につきそれぞれ二六万九、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を加算することとした。(第五〇条の二関係)
㈢ 遺族厚生年金に子の加給年金を創設し、受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた子があるときは、その子一人につきそれぞれ二六万九、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を加算することとした。(第六二条の二関係)
6 遺族厚生年金の見直し
㈠ 遺族厚生年金を受けることができる遺族を、被保険者又は被保険者であった者の配偶者(以下この6において単に「配偶者」という。)、子、父母、孫又は祖父母(父母又は祖父母については、六〇歳以上である者に限る。)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとすることとした。(第五九条第一項関係)
㈡ 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた六〇歳未満である配偶者は、㈠にかかわらず、遺族厚生年金を受けることができる遺族とすることとした。(第五九条第二項関係)
㈢ 中高齢寡婦加算を段階的に減額し、令和三五年四月二日以降に遺族厚生年金の受給権を取得した者については当該加算をしないこととしつつ、遺族厚生年金の受給権を取得した当時、六〇歳未満の配偶者であって、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する期間がないもの又は当該遺族基礎年金の受給権を有する期間があり、かつ、六〇歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したものに支給される遺族厚生年金(以下この6において「六〇歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金」という。)については、遺族厚生年金の額に死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の四分の一に相当する額を加算することとした。(第六二条第一項関係)
㈣ 六〇歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権は、㈤による当該遺族厚生年金の全部の支給の停止が二年間継続したとき、老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は六五歳に達したときは、消滅することとした。(第六三条第二項関係)
㈤ 六〇歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金は、その受給権者が当該遺族厚生年金の受給権を取得した日等から起算して五年を経過した日の属する月の翌月以後の月分について、その受給権者の前年の所得が、国民年金法第九〇条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないものとされる所得の額を勘案してその者の扶養親族の有無及び数に応じて政令で定める額を超えるときは、その前年の所得の額に応じ、当該遺族厚生年金の全部又は一部の支給を停止することとした。(第六五条第一項~第三項関係)
㈥ 障害厚生年金又は障害基礎年金の受給権者であって、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するものであるとき等は、その該当する間は、㈤を適用しないこととした。(第六五条第四項関係)
㈦ 死亡した被保険者が被保険者であった期間中に配偶者を有していた場合において、当該被保険者の配偶者(以下この㈦において「死別配偶者」という。)が六〇歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権者であるとき又は当該遺族厚生年金の受給権者であったときは、死別配偶者は、実施機関に対し、死別配偶者の婚姻等対象期間(当該被保険者と当該死別配偶者との婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間であった期間をいう。)の標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定を請求することができることとした。(第七八条の二一の二第一項関係)
7 離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定の請求について、その請求の期限を五年とすることとした。(第七八条の二第一項関係)
8 厚生労働大臣は、第一号厚生年金被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、銀行、信託会社その他の機関に対し、第一号厚生年金被保険者又は第一号厚生年金被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求めることができることとした。(第一〇〇条の二第六項関係)
9 脱退一時金の支給の請求について、再入国の許可を受けて日本を出国した者は、当該再入国の許可を受けている間、その請求ができないこととした。(附則第二九条第一項関係)
三 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五五年法律第八二号)の一部改正関係
二の5の㈡及び㈢並びに6の㈢の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(附則第六三条関係)
四 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号)の一部改正関係
1 支給事由の生じた日が令和一八年四月一日前にある障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金及び遺族厚生年金について、直近一年間に保険料未納期間がないときは、保険料納付要件を満たしているものとすることとした。(附則第二〇条及び第六四条関係)
2 一の1の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(附則第一八条第五項関係)
3 二の3の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(附則第五九条第一項、第六二条第一項、第八二条第三項並びに第八四条第三項及び第四項関係)
4 二の5の改正に伴う所要の改正を行うとともに、老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額の特別加算額について二の5の㈠に準じた改正を行うこととした。(附則第六〇条第二項、第七八条第二項及び第八七条第三項関係)
5 二の6の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(附則第五四条、第七三条並びに第七四条第一項、第四項及び第五項関係)
五 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八二号)の一部改正関係
二の3の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(附則第三三条の三関係)
六 国民年金法等の一部を改正する法律(平成一二年法律第一八号)の一部改正関係
二の3の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(附則第九条第四項、第二〇条第一項、第二一条第二項、第二三条第三項及び第二四条第五項関係)
七 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正関係
移行農林共済年金について、二の3及び5の㈡に準じた改正を行うこととした。(附則第一六条第四項及び第一三項関係)
八 国民年金法等の一部を改正する法律(平成一六年法律第一〇四号)の一部改正関係
三〇歳未満の国民年金第一号被保険者等であって本人及び配偶者の所得が一定以下であるものに係る国民年金の保険料の免除の特例を五年間延長し、令和一七年六月までとすることとした。(附則第一九条第二項関係)
九 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正関係
1 被用者保険の適用拡大
㈠ 特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)に使用される特定四分の三未満短時間労働者を厚生年金保険及び健康保険の被保険者としない取扱いについて、令和一七年九月三〇日までの間の措置とすることとした。(附則第一七条及び第四六条関係)
㈡ ㈠の取扱いについては段階的に縮小することとし、短時間労働者を適用対象とすべき特定適用事業所の範囲について、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、令和九年一〇月一日から令和一一年九月三〇日までは当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時三五人を超えるものとし、令和一一年一〇月一日から令和一四年九月三〇日までは当該総数が常時二〇人を超えるものとし、令和一四年一〇月一日から令和一七年九月三〇日までは当該総数が常時一〇人を超えるものとすることとした。(附則第一七条の三の二及び第四六条の二関係)
一〇 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正関係
二の5の㈠及び6の㈢の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(附則第二一条及び第三五条第一項関係)
一一 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正関係
1 存続厚生年金基金又は存続連合会の受給権者の死亡の届出について、届出義務者が戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、当該者は存続厚生年金基金又は存続連合会に対する死亡の届出を不要とすることとした。(附則第五条第一項及び第三八条第一項関係)
2 存続厚生年金基金について、二の3に準じた改正を行うとともに、二の6の㈦の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(附則第五条第二項関係)
3 個人型年金の加入要件について、存続厚生年金基金の脱退一時金相当額を個人型年金に移換しようとする者及び存続連合会の年金給付等積立金等又は積立金を個人型年金に移換しようとする者は個人型年金加入者となることができることとした。(附則第五条第三項及び第三八条第三項関係)
一二 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正関係
三〇歳以上五〇歳未満の国民年金第一号被保険者等であって本人及び配偶者の所得が一定以下であるものに係る国民年金の保険料の免除の特例を五年間延長し、令和一七年六月までとすることとした。(附則第一四条第一項関係)
一三 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正関係
独立行政法人福祉医療機構は、令和九年四月一日から当分の間、貸付金の弁済に充当した後の残余の金銭の支払を行う業務その他厚生労働省令で定める関連業務を行うことができることとした。(附則第三九条第一項関係)
一四 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正関係
1 一の1及び二の5の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(第三一条第六項、第三二条第四項、第六項及び第七項並びに第三三条の二関係)
2 二の6の改正に伴う所要の改正を行うこととした。(第一六条第四項、第二七条、第三一条第一項、第三三条第一項及び第三項並びに第四〇条第六項及び第七項関係)
一五 国家公務員共済組合法の一部改正関係
標準報酬の等級について、二の2に準じた改正を行うこととした。(第四〇条第一項関係)
一六 地方公務員等共済組合法の一部改正関係
標準報酬の等級について、二の2に準じた改正を行うこととした。(第四三条第一項関係)
一七 私立学校教職員共済法の一部改正関係
標準報酬月額の等級について、二の2に準じた改正を行うこととした。(第二二条第一項関係)
一八 確定給付企業年金法の一部改正関係
1 確定給付企業年金における受給権者の死亡の届出について、届出義務者が戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、当該者は事業主及び企業年金基金又は企業年金連合会に対する死亡の届出を不要とすることとした。(第九九条関係)
2 厚生労働大臣は、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書の提出を受けたときは、当該報告書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものを公表することとした。(第一〇〇条第四項関係)
一九 確定拠出年金法の一部改正関係
1 企業型年金の規約の承認申請の際に添付すべき書類のうちその一部の提出を要しないこととした。(第三条第四項関係)
2 簡易企業型年金に係る規定を削除することとした。(第三条第五項、第一九条第二項及び第二三条第一項関係)
3 企業型年金の規約で企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合において、企業型年金加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えてはならない旨の要件を削除することとした。(第四条第一項関係)
4 厚生労働大臣は、企業型年金に係る業務についての報告書の提出を受けたときは、当該報告書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものを公表することとした。(第五〇条第二項関係)
5 個人型年金の加入要件について、改正前の加入要件に該当しない六〇歳以上七〇歳未満の者であって、申出の日の前日において個人型年金加入者であったもの若しくは個人型年金運用指図者であったもの、個人別管理資産の移換の申出をしたもの、脱退一時金相当額の移換の申出をしようとするもの、残余財産の移換の申出をしようとするもの又は積立金の移換の申出をしようとするものは、個人型年金加入者となることができることとした。(第六二条第一項関係)
6 中小事業主掛金を拠出しようとする中小事業主が行う届出について、厚生労働省令で定める事項等の届出先を国民年金基金連合会とするとともに、国民年金基金連合会が当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に当該届出に係る書類の写しを送付しなければならないこととした。(第六八条の二第六項及び第七項関係)
7 企業型年金運用指図者等の死亡の届出について、届出義務者が戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、当該者は国民年金基金連合会に対する死亡の届出を不要とすることとした。(第一一三条第一項関係)
二〇 石炭鉱業年金基金法の一部改正関係
石炭鉱業年金基金について、定款において解散及び清算に関する事項を定めなければならないものとし、事業の継続の困難を理由として厚生労働大臣の認可を受けた場合又は厚生労働大臣の解散命令があった場合に解散するものとし、石炭鉱業年金基金が解散する日における積立金の額が、基金が負う坑内員及び坑内員であった者並びに坑外員及び坑外員であった者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務その他当該給付の支給に係る事情を考慮して厚生労働省令で定めるところにより算定した額を下回る場合は、当該下回る額を会員が一括して拠出しなければならないこととした。(第八条第一項、第三二条第五項、第三六条及び第三六条の三関係)
二一 石炭鉱業年金基金法を廃止することとした。
二二 独立行政法人福祉医療機構法の一部改正関係
独立行政法人福祉医療機構は、令和九年三月三一日までの期間、小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務を行うこととした。(附則第五条の二第二項関係)
二三 健康保険法の一部改正関係
1 健康保険の適用拡大
㈠ 健康保険の適用事業所について、事業の種類にかかわらず、常時五人以上の従業員を使用する事業所を適用事業所とすることとした。(第三条第三項関係)
㈡ 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である等の短時間労働者に係る健康保険の適用除外の要件のうち、報酬が八万八、〇〇〇円未満であることとする要件を削除することとした。(第三条第一項関係)
2 二の8に準じた改正を行うこととした。(第一九九条第一項関係)
二四 船員保険法の一部改正関係
二の8に準じた改正を行うこととした。(第一四七条関係)
二五 独立行政法人農業者年金基金法の一部改正関係
二の1の㈠により農業者年金の被保険者が農業者年金の被保険者でなくなった場合において、その農業者年金の被保険者でなくなった日の属する月からその者を農業者年金の被保険者とみなして独立行政法人農業者年金基金法第一三条の規定を適用したとすればその者が農業者年金の被保険者の資格を喪失することとなる日又はその者が事業所に使用されなくなった日のいずれか早い日の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間は、その者の申出により、保険料納付済期間等に算入することとした。(附則第九条関係)
二六 検討規定等
1 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二条第一項関係)
2 政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二条第二項関係)
3 政府は、高齢者の就業の実態等を踏まえ、将来の基礎年金の給付水準の向上等を図るため、所要の費用を賄うための安定した財源を確保するための方策も含め、国民年金第一号被保険者の被保険者期間を延長することについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二条第三項関係)
4 政府は、国民年金第三号被保険者の在り方について国民的な議論が必要であるという認識の下、その議論に資するような国民年金第三号被保険者の実情に関する調査研究を行い、その在り方について検討を行うこととした。(附則第二条第四項関係)
5 令和六年における国民年金法に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法に規定する財政の現況及び見通しを踏まえ、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条第一項及び第三項の規定による検討を引き続き行うに際して今後の社会経済情勢の変化を見極めるため、この法律の公布の日の属する年度の翌年度から、厚生年金保険法に規定する財政の現況及び見通しが同日以後初めて作成される日の属する年度の翌年度までの間は、同法第三四条第一項に規定する調整期間とすることとした。この場合、マクロ経済スライドによる調整においては、その調整率を三分の一に軽減することとした。(附則第三条関係)
6 政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、この法律の公布の日以後初めて作成される財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法に規定する調整期間の見通しと厚生年金保険法に規定する調整期間の見通しとの間に著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により老齢基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権者の将来における老齢基礎年金の給付水準の向上を図るため、国民年金法第一六条の二第一項の調整と厚生年金保険法第三四条第一項の調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずることとした。この場合において、給付と負担の均衡がとれた持続可能な公的年金制度の確立について検討を行うこととした。(附則第三条の二第一項関係)
7 政府は、6の法制上の措置を講ずる場合において、老齢基礎年金の額及び老齢厚生年金の額の合計額が、当該措置を講じなかったとしたならば支給されることとなる老齢基礎年金の額及び老齢厚生年金の額の合計額を下回るときは、その影響を緩和するために必要な法制上の措置その他の措置を講ずることとした。(附則第三条の二第二項関係)
二七 施行期日等
1 厚生年金保険等の適用事業所に関する経過措置
㈠ 二の1の㈠の施行の際現に存する改正前の厚生年金保険法第六条第一項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所又は事務所(国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であって、常時従業員を使用するものを除く。)については、当分の間、なお従前の例により、厚生年金保険の適用事業所としないこととした。(附則第一八条関係)
㈡ 二三の1の㈠の施行の際現に存する改正前の健康保険法第三条第三項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所(国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するものを除く。)については、当分の間、なお従前の例により、健康保険の適用事業所としないこととした。(附則第三七条関係)
2 短時間被保険者の厚生年金保険料等に関する経過措置
㈠ 厚生年金保険の適用拡大の対象となる適用事業所等の事業主は、実施機関に申出をした場合は、七〇歳未満であるその短時間被保険者(厚生年金保険の標準報酬月額等級のうち第一級から第六級までに該当する者に限る。)に係る事業主の負担すべき厚生年金保険料(標準賞与額に係るもの等を除く。)の負担の割合を、短時間被保険者の標準報酬月額等級に応じて別に定める割合に増加することができるものとし、この場合において、短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額(申出があった日の属する月から通算して三六月間の各月に係るものに限る。)のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に厚生年金保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合を乗じて得た額は、徴収を行うことを要しなかったものとみなすこととした。(附則第二二条及び第二三条並びに附則別表第二関係)
㈡ 健康保険の適用拡大の対象となる適用事業所等の事業主は、保険者等に申出をした場合は、その短時間被保険者(健康保険の標準報酬月額等級のうち第一級から第九級までに該当する者に限る。)に係る事業主の負担すべき健康保険料(標準賞与額に係るもの等を除く。)の負担の割合を、短時間被保険者の標準報酬月額等級に応じて別に定める割合に増加することができるものとし、この場合において、短時間被保険者に係る健康保険料の額(申出があった日の属する月から通算して三六月間の各月に係るものに限る。)のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に一般保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合を乗じて得た額は、徴収を行うことを要しなかったものとみなすこととした。(附則第二四条及び第二五条並びに附則別表第三関係)
3 二六の5から7まで並びに1及び2のほか、この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行うこととした。(附則第一条第二項及び第三項、第四条~第一七条、第一九条~第二一条、第二六条~第三六条並びに第三八条~第五五条並びに附則別表第一関係)
4 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行することとした。
関連商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -