資料2003年08月13日 【税務通達等】 「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
資産評価企画官情報第1号
資産課税課情報第12号
平成15年7月4日
国税庁課税部資産評価企画官 資産課税課
「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
平成15年6月25日付課評2-15ほか二課共同「財産評価基本通達の一部改正について」及び平成15年6月25日付課評2-17ほか二課共同「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等の改正について』の一部改正について」により、取引相場のない株式等の評価について所要の改正を行い、併せてストックオプション及び不動産投資信託証券の評価を定めたところであるが、そのあらましは別添のとおりであるので、参考のため送付する。
別添
目 次
1 上場株式の評価(2以上の証券取引所に上場されている場合)
2 取引相場のない株式の評価(同族株主以外の株主等が取得した株式の判定基準の改正)
3 取引相場のない株式の評価(種類株式を発行している場合の議決権総数等)
4 取引相場のない株式の評価(自己株式を有する場合)
5 取引相場のない株式の評価(法人税法上の同族会社の判定基準の改正による影響)
6 ストックオプションの評価
7 利付公社債等の評価
8 不動産投資信託証券等の評価
9 取引相場のない株式等の評価明細書の改正
1 上場株式の評価(2以上の証券取引所に上場されている場合)
上場株式の評価において、その株式が2以上の証券取引所に上場されている場合の証券取引所の選択は、「納税義務者が選択した証券取引所」によることとした。(評基通169=改正)
1 従来の取扱い
上場株式の価額は、証券取引所の公表する課税時期の最終価格と課税時期の属する月以前3か月間の各月の毎日の最終価格の月平均額のいずれか低い価額によって評価することとしている。この場合、2以上の証券取引所に上場されている株式については、その株式発行会社の本店所在地の最寄りの証券取引所を選択することを原則とし、納税義務者が納税地の最寄りの証券取引所を選んだときはこれを認めることとしていた。
このように、原則として本店所在地の最寄りの証券取引所の取引価格によることとしたのは、一般的に株主は株式発行会社の本店所在地付近に多く分布しており、その株式の取引が本店所在地の最寄りの証券取引所において比較的多く認められることから、その証券取引所における取引価格が最も適正な時価を表すとの考え方によっていたものである。また、納税義務者が納税地の最寄りの証券取引所を選択した場合にそれを認めることとしたのは、納税義務者は住所地の最寄りの証券取引所において取引する場合が多いので、これによっても差し支えないとの考え方によっていたものである。
2 通達改正の趣旨及び概要
近年の株式の取引をみると、株主は証券会社を通じて全国どこの証券取引所でも取引ができるとともに、インターネット等の普及によりネット証券会社を通じての取引も増加し、納税義務者が住所地(納税地)の最寄りの証券取引所において株式を取引する場合が多いとはいえなくなっている。また、株式発行会社の本店所在地の最寄りの証券取引所において株式の取引が多いものもあるが、複数の証券取引所に上場している会社の中には、コスト削減の目的で、上場証券取引所の数を減らすものも出てくるなど、必ずしも株式発行会社の本店所在地の最寄りの証券取引所において株式の取引が多いとはいえなくなってきたといえる。この結果、株式発行会社の本店所在地又は納税地の最寄りの証券取引所において、課税時期における取引が成立していないなど、従来の通達の定めにより評価することができないケースが生じるようになった。
証券取引所の選択については、評価しようとする株式の「取引の多い証券取引所における取引価格が最も適正な時価を表している」という考え方があり、これは「時価」の解釈からしても合理性を失うものではないが、一方において、正常な取引がなされている以上、どの証券取引所において成立した価格も「時価」を表している(値幅制限等もあり、証券取引所間の取引価格に大きな差はない。)といえることから、評価しようとする株式の取引の多い証券取引所に限定することなく、証券取引所の選択は納税義務者に委ねることとした。
なお、この取扱いでは、納税義務者に証券取引所の選択を委ねることとなるが、「課税時期の最終価格」がある証券取引所があるにもかかわらず、その最終価格がない証券取引所を選択することを認める趣旨ではないことに留意する。また、税務署において決定処分等をするときには、「課税時期の最終価格」及び「最終価格の月平均額」がある証券取引所のうち納税者が選択すると認められる(納税者に有利となる証券取引所の)価格を使用することにも留意する。
2 取引相場のない株式の評価(同族株主以外の株主等が取得した株式の判定基準の改正)
平成13、14年の商法改正において、単元株制度の創設及び株式の多様化(種類株式の種類の増加)が図られたことにより、同族株主以外の株主等が取得した株式であるか否かについては、株主が有する「株式数」は「議決権の数」に、評価会社の「発行済株式数」は「議決権総数」に変更して判定することとした。(評基通185・188・188-3・188-4・188-5・188-6・189-2・189-3・189-4関係=改正)
1 従来の取扱い
事業経営への影響が少ない同族株主の一部及び従業員株主等のような少数株主が所有する株式の価額は、単に配当を期待するにとどまるという実質のほか、評価手続の簡便性をも考慮して、原則的評価方式である類似業種比準方式、純資産価額方式等ではなく、特例的評価方式である配当還元方式(評基通188-2)により評価することとしているが、その配当還元方式が適用される株式の範囲については、財産評価基本通達188(同族株主以外の株主等が取得した株式)等の定めにより、評価会社における株主の構成及びその持株割合(発行済株式数に占める持株数の割合)により判定することとしていた。
2 通達改正の趣旨及び概要
平成13、14年の商法改正により、単元株制度の創設及び株式の多様化(種類株式ごとに単元を定めることができる。)が認められることとなり、株主が有する株式の数と議決権の数が必ずしも一致しなくなった(従来は、原則として株式の数と議決権の数が一致していた。)。このため、従来の株主が有する「株式数」又は評価会社の「発行済株式数」を基とした持株割合による判定では、本来の会社支配力が十分に測れない場合も出てくることから、より適正に会社支配力を測ることができる基準、すなわち、株主が有する「議決権の数」又は評価会社の「議決権総数」を基とした議決権割合による判定に変更し、「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当するか否かを判定することとした。
そこで、財産評価基本通達188(同族株主以外の株主等が取得した株式)のほか、同通達188-3(評価会社が自己株式を有する場合の発行済株式数)、同通達188-4(議決権を有しないこととされる株式がある場合の発行済株式数)、同通達188-5(議決権のない株式がある場合の発行済株式数)、同通達188-6(投資育成会社が株主である場合の同族株主等)において使用している株主が有する「株式数」は「議決権の数」に、評価会社の「発行済株式数」は「議決権総数」に変更することとした。
また、株式の取得者とその同族関係者の持株割合が50%以下(改正前50%未満)である場合に1株当たりの純資産価額に80%を乗じて計算することを定めた財産評価基本通達185(純資産価額)のほか、同通達189-2(比準要素数1の会社の株式の評価)、同通達189-3(株式保有特定会社の株式の評価)及び同通達189-4(土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価)においても、上記と同様の変更をすることとした。
(注)商法の親子会社の定義においても、平成13年6月改正前は発行済株式総数を基準として定義していたのを、同改正で総株主の議決権を基準とすることに変更している(商法211ノ2①)。
(参 考1)単元株制度
単元株制度は、会社が一定の数の株式をもって、一単元の株式とする旨を定める(ただし、一単元の株式の数は1,000株及び発行済株式数の200分の1を超えることはできない。)ことにより、一単元の株式につき1個の議決権を与えることとする制度である。なお、単元未満株式については議決権がない。また、数種類の株式を発行するときは、株式の種類ごとに一単元の株式の数を定款により定めなければならないとするものである(商法221①、③)。
平成13年6月の商法改正(同年10月施行)により、株式の大きさに関する規制が撤廃され、会社が自由に株式の大きさを決めることができることとして、資金調達の便宜が図られた。これにより、昭和56年に株式の額面金額を原則5万円と定めたことに伴い、暫定的かつ過渡的な制度として導入された単位株制度が廃止され、単元株制度が創設された。
(参 考2)株式の多様化
平成13、14年の商法改正において、「ベンチャー企業が支配権を維持しながら資金調達をしたい」又は「企業の特定部門や子会社の業績に対して配当が連動(トラック)する、いわゆるトラッキング・ストックを発行したい」とのニーズがあることに配慮し、一定の範囲で権利内容が異なる株式の発行が拡大された。換言すれば、株式による資金調達の多様化と支配関係の多様化の機会が会社に与えられることとなった。
(商法改正前) 「利益もしくは利息の配当、残余財産の分配、株式の買受又は利益をもってする株式の消却」についてのみ、権利内容の異なる株式(種類株式)を認め、利益配当優先株式に付随する性質のものとして無議決権株式の発行を認め、優先配当がなかった場合には、議決権が法律上強制的に復活することとされていた。
(商法改正後) 従来の種類株式に加え、株主総会におけるすべて又は一部の事項について議決権を行使できない議決権制限株式や種類株主総会での取締役・監査役の選解任(株式譲渡制限のある非公開会社のみ)ができる株式の発行ができるようになった。
(参 考3)所有株式数の割合と議決権の数の割合とで同族株主判定が異なる場合
・ 普通株式の一単元の株式の数は100株とする。
・ 株主甲は、株主乙の同族関係者にならない。
・ 株主乙の所有する種類株式の一単元の株式の数は25株とする。
・ 「その他」は、株主甲又は株主乙の同族関係者にならない少数株主である。
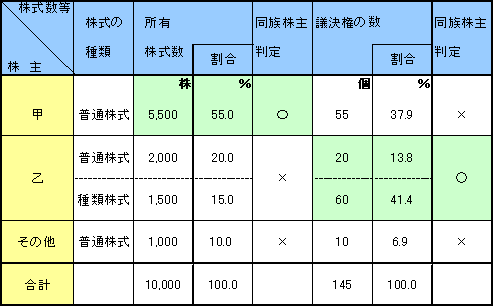
【判定結果】
所有株式数により判定すれば、株主甲の持株割合が55.0%となるため、甲が同族株主となるが、議決権の数で判定すれば、株主乙の議決権総数に占める議決権の数の割合が55.2%(=13.8%+41.4%)となるため、株主乙が同族株主となる。
3 取引相場のない株式の評価(種類株式を発行している場合の議決権総数等)
平成13、14年の商法改正により、株主総会におけるすべての事項について議決権を行使できない株式(無議決権株式)又は一部の事項について議決権を行使できない株式(議決権制限株式)等の種類株式の種類の増加等が認められた。これらの改正により、財産評価基本通達 188(同族株主以外の株主等が取得した株式)における判定基準を「持株割合」から「議決権割合」に変更したことに伴い、評価会社が種類株式のうち議決権制限株式を発行している場合における議決権総数等の取扱いを明らかにした。(評基通188-5関係=改正)
1 従来の取扱い
財産評価基本通達188(同族株主以外の株主等が取得した株式)は、株主の評価会社に対する実質的支配関係を基に「同族株主以外の株主等が取得した株式」であるか否かを判定していることから、改正前の同通達188-5(議決権のない株式がある場合の発行済株式数)前段の本文では、評価会社が会社の支配関係に影響のない議決権のない株式(改正前商法では配当優先株式についてのみ認められていた。)を発行している場合には、株主の有する株式数及び評価会社の発行済株式数から議決権のない株式の数を控除して同判定を行うこととしていた。
また、同項前段のただし書では、①議決権のない株式でも優先配当がなかった場合には、議決権が復活すること、②議決権のない株式であっても、議決権を有する普通株式に転換できる転換権を付すことができること、③商法の解釈上、株主全員の同意があれば普通株式に転換できることなどから、その潜在的支配力を考慮し、議決権のない株式を控除しない株式数によっても、「同族株主以外の株主等が取得した株式」であるか否かの判定を行うこととし、この控除を行わない場合に、その株主の取得した株式が「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当しないときは(同族株主が取得した株式に該当するときは)、上記の判定とは別に、その株主が取得した株式については、「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当しないものとすること(原則的評価方式によること)としていた。
2 通達改正の趣旨及び概要
平成13、14年の商法改正により、次のような株式の多様化が図られ、株式の種類(種類株式)ごとに、一単元の株式の数を定めることが認められた。
①株主総会におけるすべての事項について議決権を行使できない様式(無議決権株式)又は一部の事項について議決権を行使できない株式(議決権制限株式、商法上は無議決権株式も含めて議決権制限株式という。)等の種類株式の種類の増加
②株主側ではなく会社側がある種類の株式から他の種類の株式へ(例えば、配当優先株式から普通株式へ)転換する権利を有する株式(強制転換条項付株式)についての明文化
これらの商法改正により、前述したとおり、同族株主以外の株主等が取得した株式(配当還元方式が適用される株式)であるか否かの判定基準を「持株割合」から「議決権割合」に変更することとした。
この場合、議決権制限株式については、会社の定款に株主総会で決議できる事項を定めることができるようになり、普通株式と同程度の議決権を有する株式から、ほとんどの事項に議決権を有せず無議決権株式に類似する株式まで、様々な形態のものを発行することができるようになったことから、議決権割合による会社支配力を判定する上での取扱いを定める必要が生じた。
普通株式とともに議決権制限株式を評価会社が発行している場合における議決権割合による会社支配力の判定に当たっては、本来ならば議決権制限株式ごとにその議決権を行使できる事項によって評価会社の支配の度合いを判定すべきと考えられる。
しかし、制限された範囲内で会社経営に関与することも可能であり、また、議決権を行使できる事項によって会社支配に影響する度合いを区別することは困難な場合が多いものと考えられることから、議決権制限株式については、商法における親子会社の判定(商法211ノ2④)と同様に、普通株式と同様の議決権があるものとし、その議決権の数を「株主の有する議決権の数」及び「評価会社の議決権総数」に含めるものとした。
なお、評価会社が、①無議決権株式等の種類株式を普通株式への転換権を付して発行している場合(例えば、無議決権株式を普通株式に転換することにより議決権の数が増えたり、種類株式ごとに一単元の数が普通株式と異なる場合には、種類株式を普通株式に転換することにより議決権の数が変わることになる。)、②会社の買受け又は利益による消却が予定されている株式(償還株式)の中で、会社側が株主の意思に関わらず一方的に強制償還できる株式(強制償還株式)を発行している場合等には、上記の取扱いによったとしても、課税時期における本来の会社支配力が十分に測れないことも予想される。
したがって、これらの場合等に備えた判定方法(従来の潜在的支配力を測る判定方法に相当するもの)を定める必要があるとも考えられるが、商法改正は行われたばかりであり、種類株式の活用実態が明らかではないことから、その判定方法については財産評価基本通達に定めないこととした。
(注)平成13年改正後の商法における親子会社の判定について、「議決権制限株式を有する株主であっても、制限された範囲内で、その会社の経営への関与が可能でありますし、親子会社の基準は法律上明確に定まっている必要がありますが、議決権を行使することができる事項によって経営への関与の度合いを区別することは困難です。そこで、このたびの改正により、議決権制限株式については、親子会社の判定の基準となる議決権に含まれることとしました。(原田晃治編著「平成13年改正商法Q&A株式制度の改善・会社運営の電子化」35ページ、商事法務)」との説明がある。
(参考)種類株式について
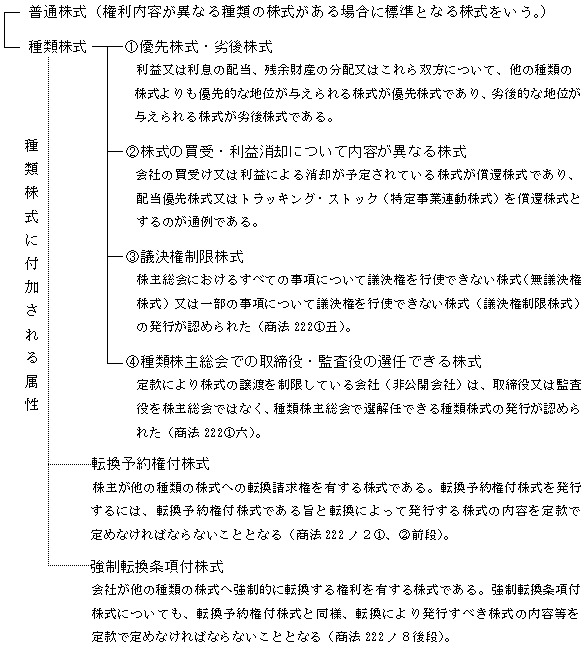
3 改正通達により難い場合の考え方
上記2のなお書のとおり、①普通株式への転換権を付して種類株式を発行している場合、②強制償還株式を発行している場合等には、課税時期における本来の会社支配力が十分に測れないことが予想されるため、次のように判定すべきケースも出てくると考えられる。
(1) 普通株式への転換権を付して種類株式を発行している場合
平成13年の商法改正により、転換予約権付株式(商法222ノ2)のほかに強制転換条項付株式(商法222ノ8)の規定が新設された(両者を併せて「転換株式」という。)。転換株式は、種類株式自体ではなく、種類株式が発行された場合にその株式に付加される属性の1つとされており、種類株式を転換株式とする場合、株式の内容及び転換条件(転換率等)は、原則として、定款に定めることとなっている(商法222ノ2②、222ノ8後段)。転換株式としては、議決権のない配当優先株式に普通株式への転換請求権を付す場合等が典型的と考えられるが、これらの中には、種類株式1株につき普通株式10株に転換するといったものも見受けられ、今後、様々な転換株式である種類株式の発行が予想される。
このような転換株式である種類株式が発行されている場合、種類株式の発行価額(時価)、発行済株式数又は転換条件等にもよるが、その時点での会社支配力とその種類株式が転換されたときの会社支配力には違いが出る場合があると考えられる。したがって、同族株主以外の株主等が取得した株式であるか否かを判定する場合において、これまで議決権のない株式についてのみ普通株式に転換したものとして、潜在的な会社支配力に着目してきたが、議決権のない株式(無議決権株式)に限らず、すべての種類株式(ただし、強制償還株式を除く。下記(2)参照)について、普通株式に転換したものとして潜在的な会社支配力を判定すべきケースが出てくると考えられる。
なお、その種類株式が転換株式であり、転換率が定まっていれば、その転換率に基づき転換したものとみなして潜在的な会社支配力を判定することになるが、種類株式の中には、転換条件等が定まっていないものもあり、この場合には、課税時期における種類株式と普通株式の時価の相違等を確認した上で、転換率を決める必要があると考えられる。
【普通株式への転換権を付して種類株式を発行している場合】
・ 普通株式の一単元の株式の数は100株とする。
・ 株主甲は、株主乙の同族関係者にならない。
・ 株主乙の所有する種類株式の一単元の株式の数は20株であり、種類株式1株につき、普通株式10株に転換する。
・ 「その他」は、株主甲又は株主乙の同族関係者にならない少数株主である。
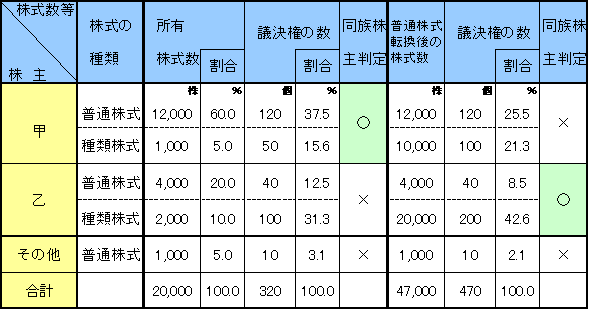
【判定結果】
普通株式転換前の議決権の数により判定すれば、株主甲の議決権総数に占める議決権の数の割合が53.1%(=37.5%+15.6%)となるため、株主甲が同族株主となるが、普通株式転換後の議決権の数で判定すれば、株主乙の議決権総数に占める議決権の数の割合が51.1%(=8.5%+42.6%)となるため、株主甲が同族株主となる。したがって、この場合には、株主甲及び株主乙のいずれもが同族株主となる。
(2) 強制償還株式を発行している場合
種類株式のうちには、株式の発行時点において、会社の買受け又は利益による消却が予定されている償還株式(商法222①三、四)がある。この償還株式の中で、会社側が株主の意思に関わらず一方的に強制償還できる株式(以下「強制償還株式」という。)については、課税時期において議決権があるとしても、将来的には会社に買受けられるか、消却されて確実にその株主の手を離れ、議決権も失うこととなることを踏まえると、その強制償還株式は既に償還されたものとして、潜在的な会社支配力を判定すべきケースが出てくると考えられる。
【強制償還株式を発行している場合】
・ 普通株式の一単元の株式の数は100株とする。
・ 株主甲は、株主乙の同族関係者にならない。
・ 株主乙の所有する種類株式は会社側から償還することができる強制償還株式であり、一単元の株式の数は100株である。
・ 「その他」は、株主甲又は株主乙の同族関係者にならない少数株主である。
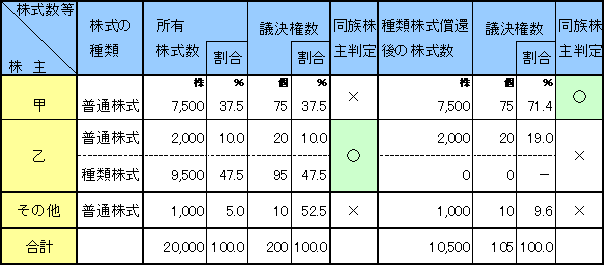
【判定結果】
乙の有する種類株式償還前の議決権の数により判定すれば、株主乙の議決権総数に占める議決権の数の割合が57.5%(=10.0%+47.5%)となるため、株主乙が同族株主となる。種類株式償還後の議決権の数で判定すれば、株主甲の議決権総数に占める議決権の数の割合が71.4%となるため、株主甲が同族株主となる。したがって、この場合には、株主甲及び株主乙のいずれもが同族株主となる。
(3) その他(取締役等を選解任できる種類株式を発行している場合)
平成14年6月に商法改正が行われ、定款により株式の譲渡制限をしている非公開会社は、種類株主総会にて取締役又は監査役を選解任できる種類株式を発行することが可能となった。この種類株式については、一定の発行制限(取締役又は監査役を選解任できない株式の数は、発行済株式総数(単元株制度を採用している会社の場合には、単元が基準となる。)の2分の1を超えることはできない。)があるとはいえ、この種類株式を活用することにより、財産評価基本通達188(同族株主以外の株主等が取得した株式)の判定上は「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当するとしても、会社支配権を有している場合もあり得るのではないかと考えられる。したがって、この取締役又は監査役を選解任できる種類株式が発行されている場合には、潜在的な会社支配力を有しているか否かを個別に判定すべきケースも出てくると考えられる。
(参 考) 種類株式の評価方法
取引相場のない株式の価額は、原則的評価方式である類似業種比準方式、純資産価額方式等又は特例的評価方式である配当還元方式により評価しているが、評価対象としている株式は、議決権制限株式等の種類株式ではなく、普通株式である。
平成13、14年の商法改正により、株式制度が大幅に見直され、従来に比べて議決権制限株式等の様々な種類株式が発行できることとなった。これまで株式の評価は、普通株式の評価を基本としてきたが、今後様々な種類株式が発行されれば、その種類株式に応じた評価方法を定めることが必要になると予想される。上場会社の事例ではあるが、種類株式が普通株式の10倍の価額で発行され、一定の配当が優先的に確保されるとともに、普通株式への当初の転換率も10倍程度となるような種類株式が発行されている。また、普通株式に比べて議決権のみがない無議決権株式(他の権利は普通株式と同じ)の発行価額を決定するに際し、他の銘柄で海外の市場に上場している普通株式と無議決権株式の流通価格差を参考に、普通株式の時価(証券取引所の一定期間の普通株式の平均株価)から5%程度をディスカウントしているものもある。
種類株式については、普通株式に比べて権利内容及び転換条件等がどのように異なるのかにより、個々にその発行価額が設定されるとともに、その後の様々な要因により時価が決まっていくと考えられる。したがって、今後、評価方法が問題となる種類株式が出てきた場合には、その種類株式について普通株式の権利内容に比べてどのような相違があるのか、転換条件はどうなっているのかなどを確認することが重要となる。例えば、種類株式の発行価額が普通株式の時価と同じであり、転換時も種類株式1株に対し普通株式1株となるようなものについては、種類株式の時価と普通株式の時価に価格差がない場合もあると考えられる。また、種類株式の発行価額及び権利内容が普通株式のそれらとかなりの相違があり、普通株式への転換条件も種類株式1株に対し普通株式X株となっているものについては、その種類株式の評価額を決定する場合、それらの内容等を十分に考慮する必要がある。種類株式については、上記を参考にして個別に評価することとする。
4 取引相場のない株式の評価(自己株式を有する場合)
平成13年6月の商法改正等により、自己株式について資産性がないことが明らかになったことから、財産評価基本通達中、自己株式を資産という前提で規定している部分について、所要の改正を行った。(評基通185、同189、同189-3=改正)
1 自己株式に関する取扱い
自己株式(商法241条第2項に規定する自己の株式をいう。)に関しては、平成6年、9年及び11年に商法改正が行われた。その結果、評価会社が自己株式を保有するケースが増加したことから、平成12年に財産評価基本通達を改正し、次のとおり、評価会社が自己株式を保有している場合における取引相場のない株式の評価に関する取扱いを明らかにしていた。
①純資産価額方式における1株当たりの純資産価額は、自己株式以外の財産に係る純資産価額を自己株式の株式数を控除した後の発行済株式数で除して求めた価額とする(評基通185(純資産価額))。
②評価上の株主区分の判定は、発行済株式数から自己株式の株式数を控除した数を評価会社の発行済株式数として判定する(評基通188-3(評価会社が自己株式を有する場合の発行済株式数))。
③株式保有特定会社に該当するか否かの判定は、評価会社の有する資産のうち自己株式を除いた各資産に基づいて行う(評基通189(特定の評価会社の株式)(2)及び(3))。
2 通達改正の趣旨
平成11年の商法改正後においても、自己株式の取得については、①株式消却する場合、②株主から株式の買取請求権の行使がある場合、③ストックオプションや従業員持株会へ譲渡する場合等に限られていた。また、自己株式の保有については、ストックオプション、従業員持株会への譲渡、質権(発行済株式総数の5%まで)の目的とするものに限られ、自己株式の保有期間についても、ストックオプションの場合が10年、従業員持株会への譲渡の場合が6か月と限られていた。
しかし、平成13年6月の商法改正(同年10月施行)により、自己株式の取得・保有に係るすべての規制がなくなり、配当可能利益の範囲内において、所有期間・数量等に制限なく、自己株式を取得・保有することができるようになった(いわゆる「金庫株の解禁」)。また、自己株式が資産の部に計上されることを前提としていた規定(改正前商法290①五、293ノ5③四)は、同商法改正により削除され、商法上、自己株式に資産性はないことが明らかとなった。
(参 考)改正前商法第290条第1項第5号及び第293条の5第3項第4号の規定は、利益配当及び中間配当の限度額の算定に関して、自己株式が貸借対照表上の資産の部に計上されることを前提として、一定範囲の自己株式の計上額を貸借対照表上の純資産額から控除すべきことを定めたものであるが、自己株式が資本の部の控除項目として表示されることを前提とすると、規定を設けることが不要となるため、削除されたものである。
自己株式の保有が原則として禁止されていた平成13年6月の商法改正前は、自己株式は他の有価証券と同様に貸借対照表の「資産の部」に表示することとされていたが、同商法改正後は、自己株式の取得は「一種の減資」と同様な効果があり、「自己株式の資産としての価値を認めない」とする考え方が一般的となったことから、自己株式は資産の部ではなく、資本の控除項目として表示することとされた。
そこで、同商法改正に伴い「株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び付属明細書に関する規則の一部を改正する省令」(現在の商法施行規則)が改正され、平成13年10月1日以降に終了する事業年度の決算に関して作成される貸借対照表から、自己株式は「資本の部」の控除項目として表示されることとなった(下図参照)。
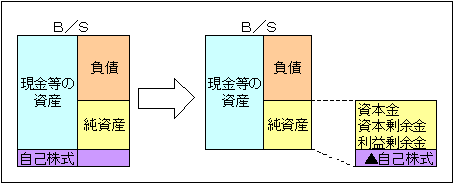
以上のとおり、自己株式に資産性がないことが明らかとなったことから、財産評価基本通達中の自己株式が貸借対照表上「資産」として表示されていることを前提としている規定について、所要の改正を行った(次のアンダーラインを付している部分を削除することとした。)。
①財産評価基本通達185(純資産価額)
「・・・・課税時期における各資産(商法(明治32年法律第48号)第241条第2項に規定する自己の株式(以下「自己株式」という。)を除く。186-2((評価差額に対する法人税額等に相当する金額))の(1)及び186-3((評価会社が有する株式等の純資産価額の計算))において同じ。)・・・・」
②同通達189(特定の評価会社の株式)の「(2) 株式保有特定会社の株式」
「課税時期において評価会社の有する各資産(自己株式を除く。)を・・・・」
③同通達189の「(3) 土地保有特定会社の株式」のイ
「・・・・で、その有する各資産(自己株式を除く。)を・・・・」
④同通達189-3(株式保有特定会社の株式の評価)の「(1) S1の金額」のイ(イ)①
「・・・・の(1)に定める総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)から自己株式の帳簿価額を控除した金額のうちに・・・・」
5 取引相場のない株式の評価(法人税法上の同族会社の判定基準の改正による影響)
法人税における同族会社となる持株割合の基準が「50%以上」から「50%超」へ改正されたことから、同族株主となる判定基準についても「50%以上」から「50%超」へ改正するほか、所要の改正を行った。(評基通185、188、189-2、189-3、189-4=改正)
1 従来の取扱い
取引相場のない株式の評価において、同族株主以外の株主等が取得した株式(評基通188)の価額は、原則的評価方式である類似業種比準方式、純資産価額方式等ではなく、特例的評価方式である配当還元方式により評価することとしている。同族株主以外の株主等が取得した株式であるか否かを判定する上で、同族株主の範囲が重要となるが、一般に、会社を支配するためには、一族でその会社の発行済株式数の50%を占めるか、50%を占めなくても相当数の株式を所有することが必要となる。したがって、同族株主の範囲については、このような会社支配の考え方から、法人税法による同族会社の判定基準(3グループで所有する株式数が発行済株式総数の50%以上)では1グループの持株割合がおおむね17%を中心として考えられていることに着目し、そのおおむね2倍相当の30%を同族株主となる割合としたものである。しかし、1グループの持株割合が30%以上(50%未満)を占めるとしても、他に持株割合50%以上を占めているグループがある場合には、30%以上の持株割合を占めているグループであっても、会社を支配することはできないこととなる。この場合の同族株主の判定は、持株割合50%以上を占めているグループの株主だけを同族株主とし、持株割合30%以上(50%未満)を占めているグループの株主は同族株主以外の株主とすることとしていた。
2 通達改正の趣旨及び概要
平成15年3月の法人税法の一部改正により、法人税における同族会社となる持株割合の基準が50%以上から50%超と改正された。この改正理由については、「ある議案について50:50に分かれた場合には、議案が可決できない事態も生じかねないため、こうした不都合を解消するためにも50%超に改正する」と説明されている。
この改正を受け、「持株割合が50%以上」の場合に同族株主となる基準については、①法人税における同族会社となる持株割合の基準を参考としていること、②法人税法における同族会社となる持株割合の基準の改正理由は、同族株主を判定する場合にも当てはまることから、「持株割合が50%超」という基準に改正した。
なお、この「持株割合が50%超」とする改正に伴い、財産評価基本通達185(純資産価額)に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)に100分の80を乗じて計算した金額とする。」場合を「株式の取得者とその同族関係者・・・・の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下(改正前50%未満)である場合」とするなどの所要の改正を行った。
(注) 従来は同族株主の範囲を「持株割合」等により判定してきたが、前述したとおり、これを「議決権割合」等により判定することとした。
6 ストックオプションの評価
課税時期が権利行使可能期間内にあるストックオプションの価額は、課税時期における 株式の価額から権利行使価格を控除した金額(その金額が負数のときは、0とする。)に、ストックオプション1個の行使により取得することができる株式数を乗じて計算した金額によって評価することとした。(評基通193-2関係=新設)
1 通達制定の趣旨
平成13年11月の商法改正(平成14年4月施行)により新株予約権制度が創設され、これまでのストックオプション、すなわち、会社が自社の取締役、従業員に対して、あらかじめ定められた価額(権利行使価額)で会社の株式を購入する権利を無償で付与するものは、新株予約権制度の一形態として整理された。また、この商法改正により、取締役、従業員のほか、子会社・関係会社の役員、顧問弁護士等、誰に対してもストックオプションを付与できることとされて、付与対象者の制限が撤廃されるとともに、発行済株式総数の10分の1という付与株式数の上限が撤廃されたことなどから、ストックオプション制度を導入する会社が増加し、平成14年8月現在で上場会社の約3割(約1,000社)が導入しているといわれている。
このことは、ストックオプション制度が、取締役等の業績向上に対する意欲や士気を高め、優秀な人材を確保するためのインセンティブプランとして定着しつつある現れと考えられるところであり、今後、ストックオプションの利用の拡大とともに相続税の課税対象となるケースが増加すると予想されることから、その評価方法を明らかにしたものである。
(参 考) 新株予約権制度の概要
新株予約権とは、「会社に対して一定の期間あらかじめ定めた一定の価額で新株の発行を請求することができる権利」であり、その権利が行使されたときは、会社がその権利者に対して新株を発行し、又はこれに代えて会社が有する自己株式を移転する義務を負うものをいう(商法280ノ19以下)。
新株予約権制度は、商法改正前の新株引受権付社債(ワラント債)における新株引受権(改正前商法 341ノ8)及び取締役等に付与する新株引受権(改正前商法280ノ19、いわゆるストックオプション)に相当するものであるが、商法280ノ2に規定する「新株引受権」(新株の発行に際して、株主がその持株数に応じて新株の割当てを受ける権利)と区別する必要があるため、「新株予約権」という名称となったものである。
2 通達の内容
一般に、オプションとは、ある商品を将来の一定期日に特定の価格で買う又は売ることができる権利をいい、前者がコールオプション(買う権利)、後者がプットオプション(売る権利)である。ストックオプションは、将来のある一定時期に特定の株式を特定の価格で買うことができる権利であることから、「特定株式のコールオプション」と考えることができる。
ストックオプションの価額は、他のオプションと同様、現時点でどれくらいの利益が発生しているか、今後どれくらいの利益が得られる可能性があるかということにより決定されるとされ、ストックオプションの価格形成要因は、一般に「本質的価値」と「時間的価値」の2つからなるといわれている。
①本質的価値
本質的価値とは、「現時点で権利を行使した場合の価値」をいい、その時点での株価と権利行使価額の差額をさすものである。
②時間的価値
時間的価値とは、「将来への期待度(株価が変動すれば、そこから利益が生ずるかもしれない)に対するストックオプションの価値」をいい、次の4要素を尺度として計算することとされている。
イ 見積株価変動率(ボラティリティ)[大きいほど、オプションの価値が高い]
ロ オプションの期間[長いほど、オプションの価値が高い]
ハ 金利[高いほど、オプションの価値が高い]
ニ 予想配当[少ないほど、オプションの価値が高い]
ストックオプションを評価するに当たっては、ブラック・ショールズ・モデルなどのいわゆるオプション・プライシング・モデルを使用することも考えられる。しかし、これらのモデルを使用すると、見積株価変動率などの数値の取り方次第で、算出されるストックオプションの評価額が大きく変動してしまうことから、相続税における財産評価の方法としては必ずしも適当ではない。したがって、ストックオプションの価額は、評価の簡便性をも考慮した上で、見積株価変動率等の不確定な要素が含まれている時間的価値を捨象し、課税時期において実際にどれくらいの経済的価値を得ることができるかという「本質的価値」に基づいて評価することとし、具体的には、次の算式によることとした。
(算式)
ストックオプションの価額= 課税時期における株式の価額-権利行使価額
(負数の場合は0とする。)
なお、上記算式中の「課税時期における株式の価額」については、必ずしも課税時期に権利行使が行われるわけではなく、一時点における需給関係による偶発性を排除するなどの必要性があることから、通達の定めに基づいて株式(上場株式及び気配相場等のある株式)を評価することとなる。また、上記算式中の「権利行使価額」については、実際に権利行使する場合、ストックオプションの発行会社が定めた権利行使価額を払い込むことから、発行会社により定められた金額によることとなる。
(参 考)ストックオプションの価値測定方法
ストックオプションの価値測定方法としては、「公正価値法(本質的価値と時間的価値の合計を測定する方法)」や「本質的価値法(現時点で権利を行使した場合の価値を測定する方法)」等があり、公正価値は「オプション・プライシング・モデル」により測定することができる。
オプション・プライシング・モデルの代表的なものには「ブラック・ショールズ・モデル」が ある。ブラック・ショールズ・モデルとは、「オプションの行使日に持っていると期待される本質的価値を現在価値に直したものがオプションの価値であるとして測定する方法」であり、①原資産価格(株価)、②オプションの行使価格、③オプション行使までの見積期間、④見積株価変動率、⑤見積配当率及び⑥リスク・フリー・レート(割引率)の6つの要素からストックオプションの価額が測定されるとしている。
(参考)ストックオプションの付与~課税時期までの株価の推移等(イメージ)
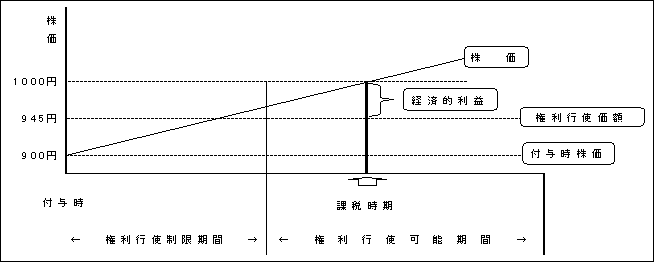
3 通達の適用対象となるストックオプション
(1) 通達の適用対象となるストックオプションの範囲
ストックオプションは、あらかじめ定められた価額(権利行使価額)でその会社の株式を購入することができる権利であり、会社が自社の取締役・従業員等を対象としてこれを付与するものである。ストックオプションを付与された取締役等は、権利行使によって 取得した株式を譲渡して初めて利益が実現できることから、ストックオプションを付与 する会社は、一般的には株式を自由に譲渡できる環境にある会社、換言すれば公開会社又は公開予定会社であると考えられる。このようなことから、通達に定める上場株式、気配相場等のある株式を目的とするストックオプションについて、この通達の対象としている。
なお、非上場会社が発行するストックオプションの価額については、その発行内容等 (権利行使価額の決定方法や権利行使により取得する株式の譲渡方法等を含む。)を勘案し、個別に評価することとする。
(2) 課税時期と権利行使可能期間との関係
通達では「課税時期が権利行使可能期間内にある」ストックオプションについて評価方法を定めているが、課税時期が権利行使可能期間前であっても、相続の開始と同時に、そのストックオプションを取得した相続人が権利行使できる場合もある。このような場合には、課税時期が権利行使可能期間内にある場合と同様、この通達を適用してそのストックオプションを評価することに留意する。なお、ストックオプションを相続により取得することはできても、権利行使可能期間前であることから、その相続人が権利行使できない場合がある。この場合のストックオプションについては、株価及び権利行使できるまでの期間等を考慮に入れて個別に評価することとする。
(参 考) ストックオプションの付与後、権利行使可能期間に入る前に相続が発生した場合の発行会社の取扱いは右のグラフのとおりであり、相続開始と同時に権利行使ができるストックオプションは、全体の14%と想定される。
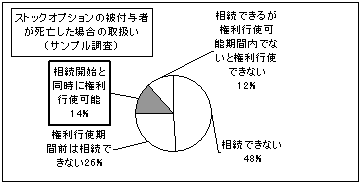
7 利付公社債等の評価
基準気配発表制度が廃止され、売買参考統計値発表制度が創設されたことから、利付公社債又は割引発行の公社債を評価する場合の「基準気配銘柄」を「売買参考統計値が公表される銘柄」に、「基準気配」を「平均値」に改めることとした。(評基通197-2、同197-3=改正)
1 従来の取扱い
利付公社債又は割引発行の公社債を評価する場合において、その公社債が日本証券業協会において基準気配銘柄として選定された銘柄であるときには、その価額は同協会の公表する課税時期の「基準気配」(売買の目安となる価格の平均値)を基に評価することとしていた。
2 通達改正の趣旨
日本証券業協会は、さらなる精緻性の向上、対象銘柄の拡大、迅速な発表等のニーズに応えるため、従来の基準気配発表制度を平成14年8月をもって廃止し、新たに売買参考統計値発表制度を創設した。これにより、「基準気配」という価格は存在しないこととなったが、従来の基準気配発表制度の「基準気配」に相当するものが、新たな売買参考統計値発表制度では「平均値」として引き続き公表されている。この平均値は、基準気配と同様に、課税時期現在の適正な時価を表しているものと認められることから、「基準気配」に代えて「平均値」により評価することとした。
(参 考)売買参考統計値発表制度の概要
売買参考統計値発表制度では、従来の平均値(「基準気配」から「平均値」に名称変更)に、「最高値」、「最低値」、「中央値」を加えた4つの価格を公表している。
(注)1 公表される値は、既経過利息の額を含まない金額(いわゆる裸値段)である。
2 売買参考統計値発表制度の選定銘柄から新株予約権付社債は除かれている。
8 不動産投資信託証券等の評価
証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券及び不動産投資信託の受益証券をいう。)の価額は、上場株式と同様に評価することとした。また、不動産投資信託証券に係る投資口の分割等に伴う無償交付期待権の価額は、新株無償交付期待権の評価(評基通192)に準じて評価し、不動産投資信託証券に係る金銭分配期待権の価額(利益超過分配金の額を含む。)は、配当期待権の評価(評基通193)に準じて評価することとした。(評基通213関係=新設)
1 通達制定の趣旨
平成12年5月に投資信託及び投資法人に関する法律が改正(同年11月施行)され、投資信託の運用対象が「主として有価証券」に限定されていたものが、「主として有価証券、不動産その他の資産(特定資産という)」と変更された。この改正により、投資法人又は投資信託委託業者等は、多くの投資家から資金を集め、これを不動産を中心とする資産に投資して運用し、賃料等の収益を投資家に分配することができるようになった。このような投資証券は、一般に不動産投資信託と呼ばれており、アメリカではREIT(Real Estate Investment Trust、リート)と呼ばれているが、我が国の不動産投資信託はアメリカのREITとは制度上の相違があり、この日本版ということからJ-REITと呼ばれている。
また、東京証券取引所が平成13年3月に不動産投資信託証券の流通市場を開設したことから、上場された不動産投資信託証券は市場を通じて自由に売買されることとなった。不動産投資信託証券は、平成13年9月に第1号が上場されて以来、平成15年6月までに6銘柄が東京証券取引所に上場されるとともに、出来高が増加しており、今後、相続税等の課税対象となるケースが増加していくと見込まれることから、その評価方法を明らかにしたものである。
(参 考)不動産投資信託の仕組み
不動産投資信託は、その仕組みから会社型と契約型(信託型)に大別されるが、現在、東京証券取引所に上場されているものは、すべて会社型(その概要は、下の図のとおり)となっている。
なお、会社型とは、資産運用を目的とした投資法人を設立し、投資家から集めた資金で不動産等を運用するファンドである。実際の不動産の選定や投資判断は投資信託委託業者が行い、投資法人が取得した不動産は資産保管会社によって保管される。
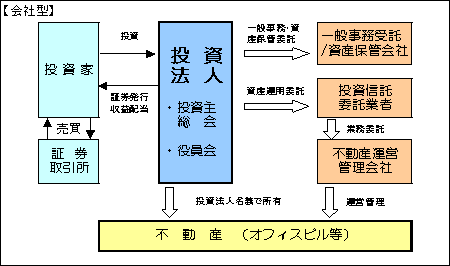
2 通達の内容
上場されている不動産投資信託証券は、上場株式と同様、証券取引所において取引され、日々の取引価格及び最終価格の月平均額が公表されている。上場されている不動産投資信託証券については、日々の取引価格が最も適正な時価を表していると考えられるが、日々の取引価格には変動があることから、上場株式の評価と同様、一時点における需給関係による偶然性を排除して評価する必要がある。
したがって、上場されている不動産投資信託証券の価額(負担付贈与により取得したものを除く。)は、次の①によって評価することを原則とするが、評価上のしんしゃくを行い、次の①から④のうち最も低い価額によって評価することとした。
①課税時期の最終価格
②課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
③課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
④課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
また、不動産投資信託証券には、株式に係る新株交付期待権又は配当期待権と同様に、投資口の分割等に伴う無償交付期待権又は金銭分配期待権があることから、これらの価額は、新株無償交付期待権の評価(評基通192)又は配当期待権の評価(評基通193)に準じて評価することとした。
なお、金銭分配期待権の価額には、利益からの分配である「利益分配金」の額だけでなく、出資の払戻し(利益を上回る金銭の分配)である「利益超過分配金」の額が含まれることに留意する。
(参 考) 非上場不動産投資信託証券の価値測定等
不動産投資信託の資産は、そのほとんどが不動産で占められており、その不動産から安定的な賃料収入が生み出されることになる。また、その賃料収入の大半は、投資家に支払われることになっている。このような不動産投資信託の仕組みからすると、市場における取引価格がない(上場されていない)不動産投資信託証券の場合には、①純資産価値、②配当利回り、③キャッシュフローなどに着目して個別にその価値測定を行うことになると考えられる。ただし、現在のところ、上場されていない不動産投資信託については、投資口のほとんどが投資法人の関係法人等に引き受けられるため、個人投資家が取引することはまずないといわれている。
9 取引相場のない株式等の評価明細書の改正
取引相場のない株式の評価方法等を改正したことに伴い、取引相場のない株式の評価明細書の様式及びその記載方法についても、所要の改正を行った。
平成15年6月25日付課評2-15ほか「財産評価基本通達の一部改正について」により、取引相場のない株式の評価方法の一部を改正したことなどに伴い、平成2年12月27日付直評23ほか「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等の改正について」についても、次のとおり所要の改正を行った(平成15年6月25日付課評2-17ほか「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等の改正について』の一部改正について」)。
1 財産評価基本通達の改正に伴う主な改正事項 (1) 同族株主以外の株主等が取得した株式の判定基準の変更
同族株主以外の株主等が取得した株式の判定基準を「株式数」から「議決権数」に改正したことから、議決権数を記入する欄を設けるとともに、会社支配力を議決権割合により判定できるよう取引相場のない株式等の評価明細書(以下「評価明細書」という。)及びその記載方法を改めた。
・ 「第1表の1 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書」関係
(2) 同族株主以外の株主等の判定をする際の判定割合の変更
同族株主以外の株主等を判定する場合の筆頭株主グループの議決権割合を「50%以上」から「50%超」に改正したことから、評価明細書及びその記載方法を改めた。
・ 「第1表の1 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書」関係
2 明確化のための主な改正事項 (1) 評価会社が種類株式を発行している場合の記載方法
評価会社が種類株式を発行している場合が見込まれることから、評価明細書に株式の種類の記入欄を設けるとともに、その記載方法を明らかにした。
・ 「第1表の1 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書」関係
・ 「第1表の2 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書(続)」関係
(参考)種類株式を発行している場合の記載例
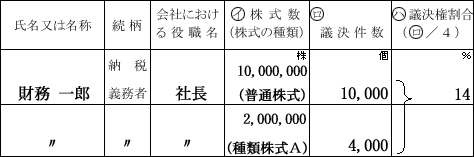
(2) 自己株式の記入欄の追加
平成13年の商法改正により、今後、自己株式を取得する評価会社が増加すると見込まれることから、自己株式の記入欄を設けた。
・「第1表の1 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書」関係
・「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」関係
(3) 額面株式の廃止への対応
平成13年の商法改正により、額面株式制度が廃止されたことから、各明細書の「1株当たりの券面額」の欄を削除した。
・「第3表 一般の評価会社の株式及び株式に関する権利の価額の計算明細書」関係
・「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」関係
・「第6表 特定の評価会社の株式及び株式に関する権利の価額の計算明細書」関係
(4) 評価差額に対する法人税額等相当額の計算方法
評価差額に対する法人税額等相当額を計算するときの「帳簿価額による純資産価額」又は「評価差額に相当する金額」については、それぞれの項目の計算結果がマイナスとなる場合には、「0」とすることを明らかにした。
・「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」関係
資産課税課情報第12号
平成15年7月4日
国税庁課税部資産評価企画官 資産課税課
「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
平成15年6月25日付課評2-15ほか二課共同「財産評価基本通達の一部改正について」及び平成15年6月25日付課評2-17ほか二課共同「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等の改正について』の一部改正について」により、取引相場のない株式等の評価について所要の改正を行い、併せてストックオプション及び不動産投資信託証券の評価を定めたところであるが、そのあらましは別添のとおりであるので、参考のため送付する。
別添
目 次
1 上場株式の評価(2以上の証券取引所に上場されている場合)
2 取引相場のない株式の評価(同族株主以外の株主等が取得した株式の判定基準の改正)
3 取引相場のない株式の評価(種類株式を発行している場合の議決権総数等)
4 取引相場のない株式の評価(自己株式を有する場合)
5 取引相場のない株式の評価(法人税法上の同族会社の判定基準の改正による影響)
6 ストックオプションの評価
7 利付公社債等の評価
8 不動産投資信託証券等の評価
9 取引相場のない株式等の評価明細書の改正
1 上場株式の評価(2以上の証券取引所に上場されている場合)
上場株式の評価において、その株式が2以上の証券取引所に上場されている場合の証券取引所の選択は、「納税義務者が選択した証券取引所」によることとした。(評基通169=改正)
1 従来の取扱い
上場株式の価額は、証券取引所の公表する課税時期の最終価格と課税時期の属する月以前3か月間の各月の毎日の最終価格の月平均額のいずれか低い価額によって評価することとしている。この場合、2以上の証券取引所に上場されている株式については、その株式発行会社の本店所在地の最寄りの証券取引所を選択することを原則とし、納税義務者が納税地の最寄りの証券取引所を選んだときはこれを認めることとしていた。
このように、原則として本店所在地の最寄りの証券取引所の取引価格によることとしたのは、一般的に株主は株式発行会社の本店所在地付近に多く分布しており、その株式の取引が本店所在地の最寄りの証券取引所において比較的多く認められることから、その証券取引所における取引価格が最も適正な時価を表すとの考え方によっていたものである。また、納税義務者が納税地の最寄りの証券取引所を選択した場合にそれを認めることとしたのは、納税義務者は住所地の最寄りの証券取引所において取引する場合が多いので、これによっても差し支えないとの考え方によっていたものである。
2 通達改正の趣旨及び概要
近年の株式の取引をみると、株主は証券会社を通じて全国どこの証券取引所でも取引ができるとともに、インターネット等の普及によりネット証券会社を通じての取引も増加し、納税義務者が住所地(納税地)の最寄りの証券取引所において株式を取引する場合が多いとはいえなくなっている。また、株式発行会社の本店所在地の最寄りの証券取引所において株式の取引が多いものもあるが、複数の証券取引所に上場している会社の中には、コスト削減の目的で、上場証券取引所の数を減らすものも出てくるなど、必ずしも株式発行会社の本店所在地の最寄りの証券取引所において株式の取引が多いとはいえなくなってきたといえる。この結果、株式発行会社の本店所在地又は納税地の最寄りの証券取引所において、課税時期における取引が成立していないなど、従来の通達の定めにより評価することができないケースが生じるようになった。
証券取引所の選択については、評価しようとする株式の「取引の多い証券取引所における取引価格が最も適正な時価を表している」という考え方があり、これは「時価」の解釈からしても合理性を失うものではないが、一方において、正常な取引がなされている以上、どの証券取引所において成立した価格も「時価」を表している(値幅制限等もあり、証券取引所間の取引価格に大きな差はない。)といえることから、評価しようとする株式の取引の多い証券取引所に限定することなく、証券取引所の選択は納税義務者に委ねることとした。
なお、この取扱いでは、納税義務者に証券取引所の選択を委ねることとなるが、「課税時期の最終価格」がある証券取引所があるにもかかわらず、その最終価格がない証券取引所を選択することを認める趣旨ではないことに留意する。また、税務署において決定処分等をするときには、「課税時期の最終価格」及び「最終価格の月平均額」がある証券取引所のうち納税者が選択すると認められる(納税者に有利となる証券取引所の)価格を使用することにも留意する。
2 取引相場のない株式の評価(同族株主以外の株主等が取得した株式の判定基準の改正)
平成13、14年の商法改正において、単元株制度の創設及び株式の多様化(種類株式の種類の増加)が図られたことにより、同族株主以外の株主等が取得した株式であるか否かについては、株主が有する「株式数」は「議決権の数」に、評価会社の「発行済株式数」は「議決権総数」に変更して判定することとした。(評基通185・188・188-3・188-4・188-5・188-6・189-2・189-3・189-4関係=改正)
1 従来の取扱い
事業経営への影響が少ない同族株主の一部及び従業員株主等のような少数株主が所有する株式の価額は、単に配当を期待するにとどまるという実質のほか、評価手続の簡便性をも考慮して、原則的評価方式である類似業種比準方式、純資産価額方式等ではなく、特例的評価方式である配当還元方式(評基通188-2)により評価することとしているが、その配当還元方式が適用される株式の範囲については、財産評価基本通達188(同族株主以外の株主等が取得した株式)等の定めにより、評価会社における株主の構成及びその持株割合(発行済株式数に占める持株数の割合)により判定することとしていた。
2 通達改正の趣旨及び概要
平成13、14年の商法改正により、単元株制度の創設及び株式の多様化(種類株式ごとに単元を定めることができる。)が認められることとなり、株主が有する株式の数と議決権の数が必ずしも一致しなくなった(従来は、原則として株式の数と議決権の数が一致していた。)。このため、従来の株主が有する「株式数」又は評価会社の「発行済株式数」を基とした持株割合による判定では、本来の会社支配力が十分に測れない場合も出てくることから、より適正に会社支配力を測ることができる基準、すなわち、株主が有する「議決権の数」又は評価会社の「議決権総数」を基とした議決権割合による判定に変更し、「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当するか否かを判定することとした。
そこで、財産評価基本通達188(同族株主以外の株主等が取得した株式)のほか、同通達188-3(評価会社が自己株式を有する場合の発行済株式数)、同通達188-4(議決権を有しないこととされる株式がある場合の発行済株式数)、同通達188-5(議決権のない株式がある場合の発行済株式数)、同通達188-6(投資育成会社が株主である場合の同族株主等)において使用している株主が有する「株式数」は「議決権の数」に、評価会社の「発行済株式数」は「議決権総数」に変更することとした。
また、株式の取得者とその同族関係者の持株割合が50%以下(改正前50%未満)である場合に1株当たりの純資産価額に80%を乗じて計算することを定めた財産評価基本通達185(純資産価額)のほか、同通達189-2(比準要素数1の会社の株式の評価)、同通達189-3(株式保有特定会社の株式の評価)及び同通達189-4(土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価)においても、上記と同様の変更をすることとした。
(注)商法の親子会社の定義においても、平成13年6月改正前は発行済株式総数を基準として定義していたのを、同改正で総株主の議決権を基準とすることに変更している(商法211ノ2①)。
(参 考1)単元株制度
単元株制度は、会社が一定の数の株式をもって、一単元の株式とする旨を定める(ただし、一単元の株式の数は1,000株及び発行済株式数の200分の1を超えることはできない。)ことにより、一単元の株式につき1個の議決権を与えることとする制度である。なお、単元未満株式については議決権がない。また、数種類の株式を発行するときは、株式の種類ごとに一単元の株式の数を定款により定めなければならないとするものである(商法221①、③)。
平成13年6月の商法改正(同年10月施行)により、株式の大きさに関する規制が撤廃され、会社が自由に株式の大きさを決めることができることとして、資金調達の便宜が図られた。これにより、昭和56年に株式の額面金額を原則5万円と定めたことに伴い、暫定的かつ過渡的な制度として導入された単位株制度が廃止され、単元株制度が創設された。
(参 考2)株式の多様化
平成13、14年の商法改正において、「ベンチャー企業が支配権を維持しながら資金調達をしたい」又は「企業の特定部門や子会社の業績に対して配当が連動(トラック)する、いわゆるトラッキング・ストックを発行したい」とのニーズがあることに配慮し、一定の範囲で権利内容が異なる株式の発行が拡大された。換言すれば、株式による資金調達の多様化と支配関係の多様化の機会が会社に与えられることとなった。
(商法改正前) 「利益もしくは利息の配当、残余財産の分配、株式の買受又は利益をもってする株式の消却」についてのみ、権利内容の異なる株式(種類株式)を認め、利益配当優先株式に付随する性質のものとして無議決権株式の発行を認め、優先配当がなかった場合には、議決権が法律上強制的に復活することとされていた。
(商法改正後) 従来の種類株式に加え、株主総会におけるすべて又は一部の事項について議決権を行使できない議決権制限株式や種類株主総会での取締役・監査役の選解任(株式譲渡制限のある非公開会社のみ)ができる株式の発行ができるようになった。
(参 考3)所有株式数の割合と議決権の数の割合とで同族株主判定が異なる場合
・ 普通株式の一単元の株式の数は100株とする。
・ 株主甲は、株主乙の同族関係者にならない。
・ 株主乙の所有する種類株式の一単元の株式の数は25株とする。
・ 「その他」は、株主甲又は株主乙の同族関係者にならない少数株主である。
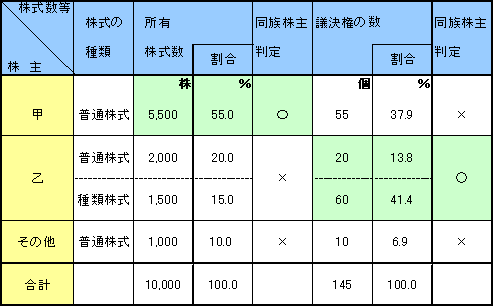
【判定結果】
所有株式数により判定すれば、株主甲の持株割合が55.0%となるため、甲が同族株主となるが、議決権の数で判定すれば、株主乙の議決権総数に占める議決権の数の割合が55.2%(=13.8%+41.4%)となるため、株主乙が同族株主となる。
3 取引相場のない株式の評価(種類株式を発行している場合の議決権総数等)
平成13、14年の商法改正により、株主総会におけるすべての事項について議決権を行使できない株式(無議決権株式)又は一部の事項について議決権を行使できない株式(議決権制限株式)等の種類株式の種類の増加等が認められた。これらの改正により、財産評価基本通達 188(同族株主以外の株主等が取得した株式)における判定基準を「持株割合」から「議決権割合」に変更したことに伴い、評価会社が種類株式のうち議決権制限株式を発行している場合における議決権総数等の取扱いを明らかにした。(評基通188-5関係=改正)
1 従来の取扱い
財産評価基本通達188(同族株主以外の株主等が取得した株式)は、株主の評価会社に対する実質的支配関係を基に「同族株主以外の株主等が取得した株式」であるか否かを判定していることから、改正前の同通達188-5(議決権のない株式がある場合の発行済株式数)前段の本文では、評価会社が会社の支配関係に影響のない議決権のない株式(改正前商法では配当優先株式についてのみ認められていた。)を発行している場合には、株主の有する株式数及び評価会社の発行済株式数から議決権のない株式の数を控除して同判定を行うこととしていた。
また、同項前段のただし書では、①議決権のない株式でも優先配当がなかった場合には、議決権が復活すること、②議決権のない株式であっても、議決権を有する普通株式に転換できる転換権を付すことができること、③商法の解釈上、株主全員の同意があれば普通株式に転換できることなどから、その潜在的支配力を考慮し、議決権のない株式を控除しない株式数によっても、「同族株主以外の株主等が取得した株式」であるか否かの判定を行うこととし、この控除を行わない場合に、その株主の取得した株式が「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当しないときは(同族株主が取得した株式に該当するときは)、上記の判定とは別に、その株主が取得した株式については、「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当しないものとすること(原則的評価方式によること)としていた。
2 通達改正の趣旨及び概要
平成13、14年の商法改正により、次のような株式の多様化が図られ、株式の種類(種類株式)ごとに、一単元の株式の数を定めることが認められた。
①株主総会におけるすべての事項について議決権を行使できない様式(無議決権株式)又は一部の事項について議決権を行使できない株式(議決権制限株式、商法上は無議決権株式も含めて議決権制限株式という。)等の種類株式の種類の増加
②株主側ではなく会社側がある種類の株式から他の種類の株式へ(例えば、配当優先株式から普通株式へ)転換する権利を有する株式(強制転換条項付株式)についての明文化
これらの商法改正により、前述したとおり、同族株主以外の株主等が取得した株式(配当還元方式が適用される株式)であるか否かの判定基準を「持株割合」から「議決権割合」に変更することとした。
この場合、議決権制限株式については、会社の定款に株主総会で決議できる事項を定めることができるようになり、普通株式と同程度の議決権を有する株式から、ほとんどの事項に議決権を有せず無議決権株式に類似する株式まで、様々な形態のものを発行することができるようになったことから、議決権割合による会社支配力を判定する上での取扱いを定める必要が生じた。
普通株式とともに議決権制限株式を評価会社が発行している場合における議決権割合による会社支配力の判定に当たっては、本来ならば議決権制限株式ごとにその議決権を行使できる事項によって評価会社の支配の度合いを判定すべきと考えられる。
しかし、制限された範囲内で会社経営に関与することも可能であり、また、議決権を行使できる事項によって会社支配に影響する度合いを区別することは困難な場合が多いものと考えられることから、議決権制限株式については、商法における親子会社の判定(商法211ノ2④)と同様に、普通株式と同様の議決権があるものとし、その議決権の数を「株主の有する議決権の数」及び「評価会社の議決権総数」に含めるものとした。
なお、評価会社が、①無議決権株式等の種類株式を普通株式への転換権を付して発行している場合(例えば、無議決権株式を普通株式に転換することにより議決権の数が増えたり、種類株式ごとに一単元の数が普通株式と異なる場合には、種類株式を普通株式に転換することにより議決権の数が変わることになる。)、②会社の買受け又は利益による消却が予定されている株式(償還株式)の中で、会社側が株主の意思に関わらず一方的に強制償還できる株式(強制償還株式)を発行している場合等には、上記の取扱いによったとしても、課税時期における本来の会社支配力が十分に測れないことも予想される。
したがって、これらの場合等に備えた判定方法(従来の潜在的支配力を測る判定方法に相当するもの)を定める必要があるとも考えられるが、商法改正は行われたばかりであり、種類株式の活用実態が明らかではないことから、その判定方法については財産評価基本通達に定めないこととした。
(注)平成13年改正後の商法における親子会社の判定について、「議決権制限株式を有する株主であっても、制限された範囲内で、その会社の経営への関与が可能でありますし、親子会社の基準は法律上明確に定まっている必要がありますが、議決権を行使することができる事項によって経営への関与の度合いを区別することは困難です。そこで、このたびの改正により、議決権制限株式については、親子会社の判定の基準となる議決権に含まれることとしました。(原田晃治編著「平成13年改正商法Q&A株式制度の改善・会社運営の電子化」35ページ、商事法務)」との説明がある。
(参考)種類株式について
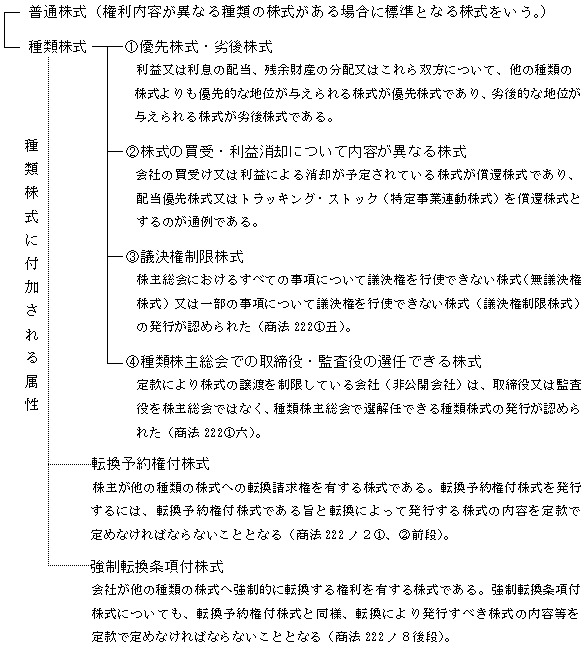
3 改正通達により難い場合の考え方
上記2のなお書のとおり、①普通株式への転換権を付して種類株式を発行している場合、②強制償還株式を発行している場合等には、課税時期における本来の会社支配力が十分に測れないことが予想されるため、次のように判定すべきケースも出てくると考えられる。
(1) 普通株式への転換権を付して種類株式を発行している場合
平成13年の商法改正により、転換予約権付株式(商法222ノ2)のほかに強制転換条項付株式(商法222ノ8)の規定が新設された(両者を併せて「転換株式」という。)。転換株式は、種類株式自体ではなく、種類株式が発行された場合にその株式に付加される属性の1つとされており、種類株式を転換株式とする場合、株式の内容及び転換条件(転換率等)は、原則として、定款に定めることとなっている(商法222ノ2②、222ノ8後段)。転換株式としては、議決権のない配当優先株式に普通株式への転換請求権を付す場合等が典型的と考えられるが、これらの中には、種類株式1株につき普通株式10株に転換するといったものも見受けられ、今後、様々な転換株式である種類株式の発行が予想される。
このような転換株式である種類株式が発行されている場合、種類株式の発行価額(時価)、発行済株式数又は転換条件等にもよるが、その時点での会社支配力とその種類株式が転換されたときの会社支配力には違いが出る場合があると考えられる。したがって、同族株主以外の株主等が取得した株式であるか否かを判定する場合において、これまで議決権のない株式についてのみ普通株式に転換したものとして、潜在的な会社支配力に着目してきたが、議決権のない株式(無議決権株式)に限らず、すべての種類株式(ただし、強制償還株式を除く。下記(2)参照)について、普通株式に転換したものとして潜在的な会社支配力を判定すべきケースが出てくると考えられる。
なお、その種類株式が転換株式であり、転換率が定まっていれば、その転換率に基づき転換したものとみなして潜在的な会社支配力を判定することになるが、種類株式の中には、転換条件等が定まっていないものもあり、この場合には、課税時期における種類株式と普通株式の時価の相違等を確認した上で、転換率を決める必要があると考えられる。
【普通株式への転換権を付して種類株式を発行している場合】
・ 普通株式の一単元の株式の数は100株とする。
・ 株主甲は、株主乙の同族関係者にならない。
・ 株主乙の所有する種類株式の一単元の株式の数は20株であり、種類株式1株につき、普通株式10株に転換する。
・ 「その他」は、株主甲又は株主乙の同族関係者にならない少数株主である。
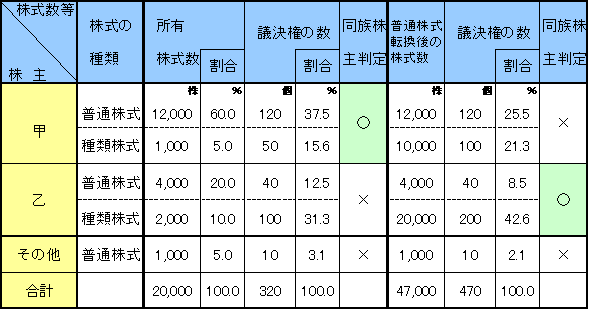
【判定結果】
普通株式転換前の議決権の数により判定すれば、株主甲の議決権総数に占める議決権の数の割合が53.1%(=37.5%+15.6%)となるため、株主甲が同族株主となるが、普通株式転換後の議決権の数で判定すれば、株主乙の議決権総数に占める議決権の数の割合が51.1%(=8.5%+42.6%)となるため、株主甲が同族株主となる。したがって、この場合には、株主甲及び株主乙のいずれもが同族株主となる。
(2) 強制償還株式を発行している場合
種類株式のうちには、株式の発行時点において、会社の買受け又は利益による消却が予定されている償還株式(商法222①三、四)がある。この償還株式の中で、会社側が株主の意思に関わらず一方的に強制償還できる株式(以下「強制償還株式」という。)については、課税時期において議決権があるとしても、将来的には会社に買受けられるか、消却されて確実にその株主の手を離れ、議決権も失うこととなることを踏まえると、その強制償還株式は既に償還されたものとして、潜在的な会社支配力を判定すべきケースが出てくると考えられる。
【強制償還株式を発行している場合】
・ 普通株式の一単元の株式の数は100株とする。
・ 株主甲は、株主乙の同族関係者にならない。
・ 株主乙の所有する種類株式は会社側から償還することができる強制償還株式であり、一単元の株式の数は100株である。
・ 「その他」は、株主甲又は株主乙の同族関係者にならない少数株主である。
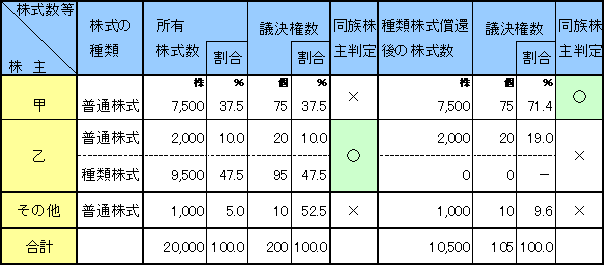
【判定結果】
乙の有する種類株式償還前の議決権の数により判定すれば、株主乙の議決権総数に占める議決権の数の割合が57.5%(=10.0%+47.5%)となるため、株主乙が同族株主となる。種類株式償還後の議決権の数で判定すれば、株主甲の議決権総数に占める議決権の数の割合が71.4%となるため、株主甲が同族株主となる。したがって、この場合には、株主甲及び株主乙のいずれもが同族株主となる。
(3) その他(取締役等を選解任できる種類株式を発行している場合)
平成14年6月に商法改正が行われ、定款により株式の譲渡制限をしている非公開会社は、種類株主総会にて取締役又は監査役を選解任できる種類株式を発行することが可能となった。この種類株式については、一定の発行制限(取締役又は監査役を選解任できない株式の数は、発行済株式総数(単元株制度を採用している会社の場合には、単元が基準となる。)の2分の1を超えることはできない。)があるとはいえ、この種類株式を活用することにより、財産評価基本通達188(同族株主以外の株主等が取得した株式)の判定上は「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当するとしても、会社支配権を有している場合もあり得るのではないかと考えられる。したがって、この取締役又は監査役を選解任できる種類株式が発行されている場合には、潜在的な会社支配力を有しているか否かを個別に判定すべきケースも出てくると考えられる。
(参 考) 種類株式の評価方法
取引相場のない株式の価額は、原則的評価方式である類似業種比準方式、純資産価額方式等又は特例的評価方式である配当還元方式により評価しているが、評価対象としている株式は、議決権制限株式等の種類株式ではなく、普通株式である。
平成13、14年の商法改正により、株式制度が大幅に見直され、従来に比べて議決権制限株式等の様々な種類株式が発行できることとなった。これまで株式の評価は、普通株式の評価を基本としてきたが、今後様々な種類株式が発行されれば、その種類株式に応じた評価方法を定めることが必要になると予想される。上場会社の事例ではあるが、種類株式が普通株式の10倍の価額で発行され、一定の配当が優先的に確保されるとともに、普通株式への当初の転換率も10倍程度となるような種類株式が発行されている。また、普通株式に比べて議決権のみがない無議決権株式(他の権利は普通株式と同じ)の発行価額を決定するに際し、他の銘柄で海外の市場に上場している普通株式と無議決権株式の流通価格差を参考に、普通株式の時価(証券取引所の一定期間の普通株式の平均株価)から5%程度をディスカウントしているものもある。
種類株式については、普通株式に比べて権利内容及び転換条件等がどのように異なるのかにより、個々にその発行価額が設定されるとともに、その後の様々な要因により時価が決まっていくと考えられる。したがって、今後、評価方法が問題となる種類株式が出てきた場合には、その種類株式について普通株式の権利内容に比べてどのような相違があるのか、転換条件はどうなっているのかなどを確認することが重要となる。例えば、種類株式の発行価額が普通株式の時価と同じであり、転換時も種類株式1株に対し普通株式1株となるようなものについては、種類株式の時価と普通株式の時価に価格差がない場合もあると考えられる。また、種類株式の発行価額及び権利内容が普通株式のそれらとかなりの相違があり、普通株式への転換条件も種類株式1株に対し普通株式X株となっているものについては、その種類株式の評価額を決定する場合、それらの内容等を十分に考慮する必要がある。種類株式については、上記を参考にして個別に評価することとする。
4 取引相場のない株式の評価(自己株式を有する場合)
平成13年6月の商法改正等により、自己株式について資産性がないことが明らかになったことから、財産評価基本通達中、自己株式を資産という前提で規定している部分について、所要の改正を行った。(評基通185、同189、同189-3=改正)
1 自己株式に関する取扱い
自己株式(商法241条第2項に規定する自己の株式をいう。)に関しては、平成6年、9年及び11年に商法改正が行われた。その結果、評価会社が自己株式を保有するケースが増加したことから、平成12年に財産評価基本通達を改正し、次のとおり、評価会社が自己株式を保有している場合における取引相場のない株式の評価に関する取扱いを明らかにしていた。
①純資産価額方式における1株当たりの純資産価額は、自己株式以外の財産に係る純資産価額を自己株式の株式数を控除した後の発行済株式数で除して求めた価額とする(評基通185(純資産価額))。
②評価上の株主区分の判定は、発行済株式数から自己株式の株式数を控除した数を評価会社の発行済株式数として判定する(評基通188-3(評価会社が自己株式を有する場合の発行済株式数))。
③株式保有特定会社に該当するか否かの判定は、評価会社の有する資産のうち自己株式を除いた各資産に基づいて行う(評基通189(特定の評価会社の株式)(2)及び(3))。
2 通達改正の趣旨
平成11年の商法改正後においても、自己株式の取得については、①株式消却する場合、②株主から株式の買取請求権の行使がある場合、③ストックオプションや従業員持株会へ譲渡する場合等に限られていた。また、自己株式の保有については、ストックオプション、従業員持株会への譲渡、質権(発行済株式総数の5%まで)の目的とするものに限られ、自己株式の保有期間についても、ストックオプションの場合が10年、従業員持株会への譲渡の場合が6か月と限られていた。
しかし、平成13年6月の商法改正(同年10月施行)により、自己株式の取得・保有に係るすべての規制がなくなり、配当可能利益の範囲内において、所有期間・数量等に制限なく、自己株式を取得・保有することができるようになった(いわゆる「金庫株の解禁」)。また、自己株式が資産の部に計上されることを前提としていた規定(改正前商法290①五、293ノ5③四)は、同商法改正により削除され、商法上、自己株式に資産性はないことが明らかとなった。
(参 考)改正前商法第290条第1項第5号及び第293条の5第3項第4号の規定は、利益配当及び中間配当の限度額の算定に関して、自己株式が貸借対照表上の資産の部に計上されることを前提として、一定範囲の自己株式の計上額を貸借対照表上の純資産額から控除すべきことを定めたものであるが、自己株式が資本の部の控除項目として表示されることを前提とすると、規定を設けることが不要となるため、削除されたものである。
自己株式の保有が原則として禁止されていた平成13年6月の商法改正前は、自己株式は他の有価証券と同様に貸借対照表の「資産の部」に表示することとされていたが、同商法改正後は、自己株式の取得は「一種の減資」と同様な効果があり、「自己株式の資産としての価値を認めない」とする考え方が一般的となったことから、自己株式は資産の部ではなく、資本の控除項目として表示することとされた。
そこで、同商法改正に伴い「株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び付属明細書に関する規則の一部を改正する省令」(現在の商法施行規則)が改正され、平成13年10月1日以降に終了する事業年度の決算に関して作成される貸借対照表から、自己株式は「資本の部」の控除項目として表示されることとなった(下図参照)。
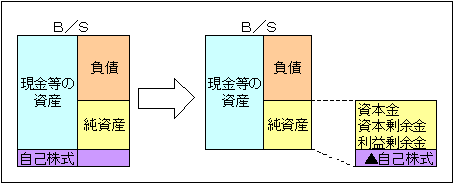
以上のとおり、自己株式に資産性がないことが明らかとなったことから、財産評価基本通達中の自己株式が貸借対照表上「資産」として表示されていることを前提としている規定について、所要の改正を行った(次のアンダーラインを付している部分を削除することとした。)。
①財産評価基本通達185(純資産価額)
「・・・・課税時期における各資産(商法(明治32年法律第48号)第241条第2項に規定する自己の株式(以下「自己株式」という。)を除く。186-2((評価差額に対する法人税額等に相当する金額))の(1)及び186-3((評価会社が有する株式等の純資産価額の計算))において同じ。)・・・・」
②同通達189(特定の評価会社の株式)の「(2) 株式保有特定会社の株式」
「課税時期において評価会社の有する各資産(自己株式を除く。)を・・・・」
③同通達189の「(3) 土地保有特定会社の株式」のイ
「・・・・で、その有する各資産(自己株式を除く。)を・・・・」
④同通達189-3(株式保有特定会社の株式の評価)の「(1) S1の金額」のイ(イ)①
「・・・・の(1)に定める総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)から自己株式の帳簿価額を控除した金額のうちに・・・・」
5 取引相場のない株式の評価(法人税法上の同族会社の判定基準の改正による影響)
法人税における同族会社となる持株割合の基準が「50%以上」から「50%超」へ改正されたことから、同族株主となる判定基準についても「50%以上」から「50%超」へ改正するほか、所要の改正を行った。(評基通185、188、189-2、189-3、189-4=改正)
1 従来の取扱い
取引相場のない株式の評価において、同族株主以外の株主等が取得した株式(評基通188)の価額は、原則的評価方式である類似業種比準方式、純資産価額方式等ではなく、特例的評価方式である配当還元方式により評価することとしている。同族株主以外の株主等が取得した株式であるか否かを判定する上で、同族株主の範囲が重要となるが、一般に、会社を支配するためには、一族でその会社の発行済株式数の50%を占めるか、50%を占めなくても相当数の株式を所有することが必要となる。したがって、同族株主の範囲については、このような会社支配の考え方から、法人税法による同族会社の判定基準(3グループで所有する株式数が発行済株式総数の50%以上)では1グループの持株割合がおおむね17%を中心として考えられていることに着目し、そのおおむね2倍相当の30%を同族株主となる割合としたものである。しかし、1グループの持株割合が30%以上(50%未満)を占めるとしても、他に持株割合50%以上を占めているグループがある場合には、30%以上の持株割合を占めているグループであっても、会社を支配することはできないこととなる。この場合の同族株主の判定は、持株割合50%以上を占めているグループの株主だけを同族株主とし、持株割合30%以上(50%未満)を占めているグループの株主は同族株主以外の株主とすることとしていた。
2 通達改正の趣旨及び概要
平成15年3月の法人税法の一部改正により、法人税における同族会社となる持株割合の基準が50%以上から50%超と改正された。この改正理由については、「ある議案について50:50に分かれた場合には、議案が可決できない事態も生じかねないため、こうした不都合を解消するためにも50%超に改正する」と説明されている。
この改正を受け、「持株割合が50%以上」の場合に同族株主となる基準については、①法人税における同族会社となる持株割合の基準を参考としていること、②法人税法における同族会社となる持株割合の基準の改正理由は、同族株主を判定する場合にも当てはまることから、「持株割合が50%超」という基準に改正した。
なお、この「持株割合が50%超」とする改正に伴い、財産評価基本通達185(純資産価額)に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)に100分の80を乗じて計算した金額とする。」場合を「株式の取得者とその同族関係者・・・・の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下(改正前50%未満)である場合」とするなどの所要の改正を行った。
(注) 従来は同族株主の範囲を「持株割合」等により判定してきたが、前述したとおり、これを「議決権割合」等により判定することとした。
6 ストックオプションの評価
課税時期が権利行使可能期間内にあるストックオプションの価額は、課税時期における 株式の価額から権利行使価格を控除した金額(その金額が負数のときは、0とする。)に、ストックオプション1個の行使により取得することができる株式数を乗じて計算した金額によって評価することとした。(評基通193-2関係=新設)
1 通達制定の趣旨
平成13年11月の商法改正(平成14年4月施行)により新株予約権制度が創設され、これまでのストックオプション、すなわち、会社が自社の取締役、従業員に対して、あらかじめ定められた価額(権利行使価額)で会社の株式を購入する権利を無償で付与するものは、新株予約権制度の一形態として整理された。また、この商法改正により、取締役、従業員のほか、子会社・関係会社の役員、顧問弁護士等、誰に対してもストックオプションを付与できることとされて、付与対象者の制限が撤廃されるとともに、発行済株式総数の10分の1という付与株式数の上限が撤廃されたことなどから、ストックオプション制度を導入する会社が増加し、平成14年8月現在で上場会社の約3割(約1,000社)が導入しているといわれている。
このことは、ストックオプション制度が、取締役等の業績向上に対する意欲や士気を高め、優秀な人材を確保するためのインセンティブプランとして定着しつつある現れと考えられるところであり、今後、ストックオプションの利用の拡大とともに相続税の課税対象となるケースが増加すると予想されることから、その評価方法を明らかにしたものである。
(参 考) 新株予約権制度の概要
新株予約権とは、「会社に対して一定の期間あらかじめ定めた一定の価額で新株の発行を請求することができる権利」であり、その権利が行使されたときは、会社がその権利者に対して新株を発行し、又はこれに代えて会社が有する自己株式を移転する義務を負うものをいう(商法280ノ19以下)。
新株予約権制度は、商法改正前の新株引受権付社債(ワラント債)における新株引受権(改正前商法 341ノ8)及び取締役等に付与する新株引受権(改正前商法280ノ19、いわゆるストックオプション)に相当するものであるが、商法280ノ2に規定する「新株引受権」(新株の発行に際して、株主がその持株数に応じて新株の割当てを受ける権利)と区別する必要があるため、「新株予約権」という名称となったものである。
2 通達の内容
一般に、オプションとは、ある商品を将来の一定期日に特定の価格で買う又は売ることができる権利をいい、前者がコールオプション(買う権利)、後者がプットオプション(売る権利)である。ストックオプションは、将来のある一定時期に特定の株式を特定の価格で買うことができる権利であることから、「特定株式のコールオプション」と考えることができる。
ストックオプションの価額は、他のオプションと同様、現時点でどれくらいの利益が発生しているか、今後どれくらいの利益が得られる可能性があるかということにより決定されるとされ、ストックオプションの価格形成要因は、一般に「本質的価値」と「時間的価値」の2つからなるといわれている。
①本質的価値
本質的価値とは、「現時点で権利を行使した場合の価値」をいい、その時点での株価と権利行使価額の差額をさすものである。
②時間的価値
時間的価値とは、「将来への期待度(株価が変動すれば、そこから利益が生ずるかもしれない)に対するストックオプションの価値」をいい、次の4要素を尺度として計算することとされている。
イ 見積株価変動率(ボラティリティ)[大きいほど、オプションの価値が高い]
ロ オプションの期間[長いほど、オプションの価値が高い]
ハ 金利[高いほど、オプションの価値が高い]
ニ 予想配当[少ないほど、オプションの価値が高い]
ストックオプションを評価するに当たっては、ブラック・ショールズ・モデルなどのいわゆるオプション・プライシング・モデルを使用することも考えられる。しかし、これらのモデルを使用すると、見積株価変動率などの数値の取り方次第で、算出されるストックオプションの評価額が大きく変動してしまうことから、相続税における財産評価の方法としては必ずしも適当ではない。したがって、ストックオプションの価額は、評価の簡便性をも考慮した上で、見積株価変動率等の不確定な要素が含まれている時間的価値を捨象し、課税時期において実際にどれくらいの経済的価値を得ることができるかという「本質的価値」に基づいて評価することとし、具体的には、次の算式によることとした。
(算式)
ストックオプションの価額= 課税時期における株式の価額-権利行使価額
(負数の場合は0とする。)
なお、上記算式中の「課税時期における株式の価額」については、必ずしも課税時期に権利行使が行われるわけではなく、一時点における需給関係による偶発性を排除するなどの必要性があることから、通達の定めに基づいて株式(上場株式及び気配相場等のある株式)を評価することとなる。また、上記算式中の「権利行使価額」については、実際に権利行使する場合、ストックオプションの発行会社が定めた権利行使価額を払い込むことから、発行会社により定められた金額によることとなる。
(参 考)ストックオプションの価値測定方法
ストックオプションの価値測定方法としては、「公正価値法(本質的価値と時間的価値の合計を測定する方法)」や「本質的価値法(現時点で権利を行使した場合の価値を測定する方法)」等があり、公正価値は「オプション・プライシング・モデル」により測定することができる。
オプション・プライシング・モデルの代表的なものには「ブラック・ショールズ・モデル」が ある。ブラック・ショールズ・モデルとは、「オプションの行使日に持っていると期待される本質的価値を現在価値に直したものがオプションの価値であるとして測定する方法」であり、①原資産価格(株価)、②オプションの行使価格、③オプション行使までの見積期間、④見積株価変動率、⑤見積配当率及び⑥リスク・フリー・レート(割引率)の6つの要素からストックオプションの価額が測定されるとしている。
(参考)ストックオプションの付与~課税時期までの株価の推移等(イメージ)
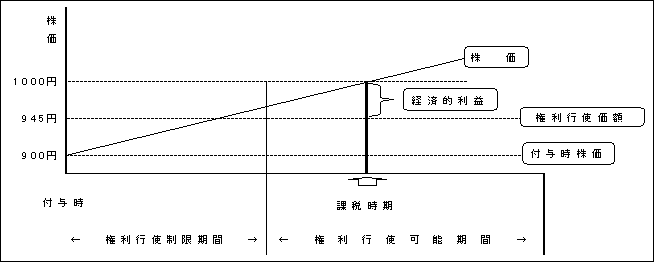
3 通達の適用対象となるストックオプション
(1) 通達の適用対象となるストックオプションの範囲
ストックオプションは、あらかじめ定められた価額(権利行使価額)でその会社の株式を購入することができる権利であり、会社が自社の取締役・従業員等を対象としてこれを付与するものである。ストックオプションを付与された取締役等は、権利行使によって 取得した株式を譲渡して初めて利益が実現できることから、ストックオプションを付与 する会社は、一般的には株式を自由に譲渡できる環境にある会社、換言すれば公開会社又は公開予定会社であると考えられる。このようなことから、通達に定める上場株式、気配相場等のある株式を目的とするストックオプションについて、この通達の対象としている。
なお、非上場会社が発行するストックオプションの価額については、その発行内容等 (権利行使価額の決定方法や権利行使により取得する株式の譲渡方法等を含む。)を勘案し、個別に評価することとする。
(2) 課税時期と権利行使可能期間との関係
通達では「課税時期が権利行使可能期間内にある」ストックオプションについて評価方法を定めているが、課税時期が権利行使可能期間前であっても、相続の開始と同時に、そのストックオプションを取得した相続人が権利行使できる場合もある。このような場合には、課税時期が権利行使可能期間内にある場合と同様、この通達を適用してそのストックオプションを評価することに留意する。なお、ストックオプションを相続により取得することはできても、権利行使可能期間前であることから、その相続人が権利行使できない場合がある。この場合のストックオプションについては、株価及び権利行使できるまでの期間等を考慮に入れて個別に評価することとする。
(参 考) ストックオプションの付与後、権利行使可能期間に入る前に相続が発生した場合の発行会社の取扱いは右のグラフのとおりであり、相続開始と同時に権利行使ができるストックオプションは、全体の14%と想定される。
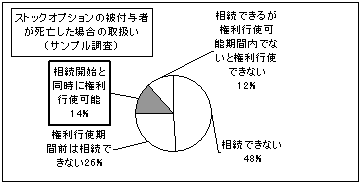
7 利付公社債等の評価
基準気配発表制度が廃止され、売買参考統計値発表制度が創設されたことから、利付公社債又は割引発行の公社債を評価する場合の「基準気配銘柄」を「売買参考統計値が公表される銘柄」に、「基準気配」を「平均値」に改めることとした。(評基通197-2、同197-3=改正)
1 従来の取扱い
利付公社債又は割引発行の公社債を評価する場合において、その公社債が日本証券業協会において基準気配銘柄として選定された銘柄であるときには、その価額は同協会の公表する課税時期の「基準気配」(売買の目安となる価格の平均値)を基に評価することとしていた。
2 通達改正の趣旨
日本証券業協会は、さらなる精緻性の向上、対象銘柄の拡大、迅速な発表等のニーズに応えるため、従来の基準気配発表制度を平成14年8月をもって廃止し、新たに売買参考統計値発表制度を創設した。これにより、「基準気配」という価格は存在しないこととなったが、従来の基準気配発表制度の「基準気配」に相当するものが、新たな売買参考統計値発表制度では「平均値」として引き続き公表されている。この平均値は、基準気配と同様に、課税時期現在の適正な時価を表しているものと認められることから、「基準気配」に代えて「平均値」により評価することとした。
(参 考)売買参考統計値発表制度の概要
売買参考統計値発表制度では、従来の平均値(「基準気配」から「平均値」に名称変更)に、「最高値」、「最低値」、「中央値」を加えた4つの価格を公表している。
| 売買参考統計値発表制度 | 基準気配発表制度 | ||
| 平均値 | 指定報告協会員から報告を受けた気配の平均値 | 基準気配 | 気配報告協会員から報告を受けた気配の平均値 |
| 中央値 | 指定報告協会員から報告を受けた気配の中央値(中央値とは、値を大きい順や小さい順に並べた場合に、その中央に位置する値である。値が偶数個の場合は、真中の2つの平均を算出する。) | - | (公表なし) |
| 最高値 | 指定報告協会員から報告を受けた気配の最高値 | 最高値 | (参考情報として公表) |
| 最低値 | 指定報告協会員から報告を受けた気配の最低値 | 最低値 | (参考情報として公表) |
(注)1 公表される値は、既経過利息の額を含まない金額(いわゆる裸値段)である。
2 売買参考統計値発表制度の選定銘柄から新株予約権付社債は除かれている。
8 不動産投資信託証券等の評価
証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券及び不動産投資信託の受益証券をいう。)の価額は、上場株式と同様に評価することとした。また、不動産投資信託証券に係る投資口の分割等に伴う無償交付期待権の価額は、新株無償交付期待権の評価(評基通192)に準じて評価し、不動産投資信託証券に係る金銭分配期待権の価額(利益超過分配金の額を含む。)は、配当期待権の評価(評基通193)に準じて評価することとした。(評基通213関係=新設)
1 通達制定の趣旨
平成12年5月に投資信託及び投資法人に関する法律が改正(同年11月施行)され、投資信託の運用対象が「主として有価証券」に限定されていたものが、「主として有価証券、不動産その他の資産(特定資産という)」と変更された。この改正により、投資法人又は投資信託委託業者等は、多くの投資家から資金を集め、これを不動産を中心とする資産に投資して運用し、賃料等の収益を投資家に分配することができるようになった。このような投資証券は、一般に不動産投資信託と呼ばれており、アメリカではREIT(Real Estate Investment Trust、リート)と呼ばれているが、我が国の不動産投資信託はアメリカのREITとは制度上の相違があり、この日本版ということからJ-REITと呼ばれている。
また、東京証券取引所が平成13年3月に不動産投資信託証券の流通市場を開設したことから、上場された不動産投資信託証券は市場を通じて自由に売買されることとなった。不動産投資信託証券は、平成13年9月に第1号が上場されて以来、平成15年6月までに6銘柄が東京証券取引所に上場されるとともに、出来高が増加しており、今後、相続税等の課税対象となるケースが増加していくと見込まれることから、その評価方法を明らかにしたものである。
(参 考)不動産投資信託の仕組み
不動産投資信託は、その仕組みから会社型と契約型(信託型)に大別されるが、現在、東京証券取引所に上場されているものは、すべて会社型(その概要は、下の図のとおり)となっている。
なお、会社型とは、資産運用を目的とした投資法人を設立し、投資家から集めた資金で不動産等を運用するファンドである。実際の不動産の選定や投資判断は投資信託委託業者が行い、投資法人が取得した不動産は資産保管会社によって保管される。
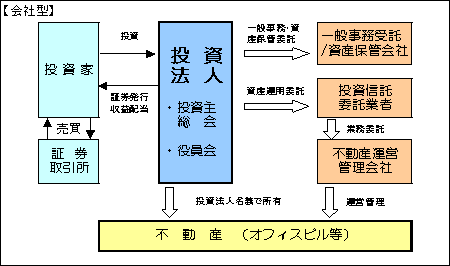
2 通達の内容
上場されている不動産投資信託証券は、上場株式と同様、証券取引所において取引され、日々の取引価格及び最終価格の月平均額が公表されている。上場されている不動産投資信託証券については、日々の取引価格が最も適正な時価を表していると考えられるが、日々の取引価格には変動があることから、上場株式の評価と同様、一時点における需給関係による偶然性を排除して評価する必要がある。
したがって、上場されている不動産投資信託証券の価額(負担付贈与により取得したものを除く。)は、次の①によって評価することを原則とするが、評価上のしんしゃくを行い、次の①から④のうち最も低い価額によって評価することとした。
①課税時期の最終価格
②課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
③課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
④課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
また、不動産投資信託証券には、株式に係る新株交付期待権又は配当期待権と同様に、投資口の分割等に伴う無償交付期待権又は金銭分配期待権があることから、これらの価額は、新株無償交付期待権の評価(評基通192)又は配当期待権の評価(評基通193)に準じて評価することとした。
なお、金銭分配期待権の価額には、利益からの分配である「利益分配金」の額だけでなく、出資の払戻し(利益を上回る金銭の分配)である「利益超過分配金」の額が含まれることに留意する。
(参 考) 非上場不動産投資信託証券の価値測定等
不動産投資信託の資産は、そのほとんどが不動産で占められており、その不動産から安定的な賃料収入が生み出されることになる。また、その賃料収入の大半は、投資家に支払われることになっている。このような不動産投資信託の仕組みからすると、市場における取引価格がない(上場されていない)不動産投資信託証券の場合には、①純資産価値、②配当利回り、③キャッシュフローなどに着目して個別にその価値測定を行うことになると考えられる。ただし、現在のところ、上場されていない不動産投資信託については、投資口のほとんどが投資法人の関係法人等に引き受けられるため、個人投資家が取引することはまずないといわれている。
9 取引相場のない株式等の評価明細書の改正
取引相場のない株式の評価方法等を改正したことに伴い、取引相場のない株式の評価明細書の様式及びその記載方法についても、所要の改正を行った。
平成15年6月25日付課評2-15ほか「財産評価基本通達の一部改正について」により、取引相場のない株式の評価方法の一部を改正したことなどに伴い、平成2年12月27日付直評23ほか「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等の改正について」についても、次のとおり所要の改正を行った(平成15年6月25日付課評2-17ほか「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等の改正について』の一部改正について」)。
1 財産評価基本通達の改正に伴う主な改正事項 (1) 同族株主以外の株主等が取得した株式の判定基準の変更
同族株主以外の株主等が取得した株式の判定基準を「株式数」から「議決権数」に改正したことから、議決権数を記入する欄を設けるとともに、会社支配力を議決権割合により判定できるよう取引相場のない株式等の評価明細書(以下「評価明細書」という。)及びその記載方法を改めた。
・ 「第1表の1 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書」関係
(2) 同族株主以外の株主等の判定をする際の判定割合の変更
同族株主以外の株主等を判定する場合の筆頭株主グループの議決権割合を「50%以上」から「50%超」に改正したことから、評価明細書及びその記載方法を改めた。
・ 「第1表の1 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書」関係
2 明確化のための主な改正事項 (1) 評価会社が種類株式を発行している場合の記載方法
評価会社が種類株式を発行している場合が見込まれることから、評価明細書に株式の種類の記入欄を設けるとともに、その記載方法を明らかにした。
・ 「第1表の1 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書」関係
・ 「第1表の2 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書(続)」関係
(参考)種類株式を発行している場合の記載例
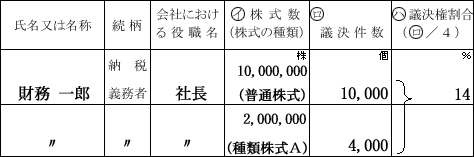
(2) 自己株式の記入欄の追加
平成13年の商法改正により、今後、自己株式を取得する評価会社が増加すると見込まれることから、自己株式の記入欄を設けた。
・「第1表の1 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書」関係
・「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」関係
(3) 額面株式の廃止への対応
平成13年の商法改正により、額面株式制度が廃止されたことから、各明細書の「1株当たりの券面額」の欄を削除した。
・「第3表 一般の評価会社の株式及び株式に関する権利の価額の計算明細書」関係
・「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」関係
・「第6表 特定の評価会社の株式及び株式に関する権利の価額の計算明細書」関係
(4) 評価差額に対する法人税額等相当額の計算方法
評価差額に対する法人税額等相当額を計算するときの「帳簿価額による純資産価額」又は「評価差額に相当する金額」については、それぞれの項目の計算結果がマイナスとなる場合には、「0」とすることを明らかにした。
・「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」関係
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















