解説記事2004年05月17日 【税制改正関連解説】 消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(2004年5月17日号・№066)
新通達解説
消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて
-消費税の総額表示と印紙税の記載金額の取扱い-
植松浩行
印紙税の取扱いにおいては、契約書や領収書等に記載される取引金額や決済金額が、負担する印紙税額に直接影響(階級定額税率の適用や課否の判定に影響)することから、その文書の記載金額がいくらになるのかを確定することが重要となってきます。
なお従来から、国税庁では「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年3月10日付間消3-2、平成8年課消4-56最終改正)(法令解釈通達)」により、印紙税法に規定する「記載金額」の取扱いとして、契約書(第1号及び第2号文書)や領収書(第17号文書)に消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」という。)の金額が区分して記載されている場合には、その消費税額等の金額については印紙税法上の記載金額に含めない取扱いを示してきており、印紙税実務においては定着した取扱いとなっています。
ところで、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第6条の規定による改正後の消費税法第63条の2《価格の表示》においては、課税事業者が消費者に対してあらかじめ値札や広告などにおいて価格を表示する場合に、消費税額等の金額を含んだ税込価格を表示することが義務付けられ、いわゆる「総額表示方式」が平成16年4月1日からスタートしています。
この「総額表示方式」が消費税法で採用されたことが、直ちに契約書(第1号及び第2号文書)や領収書(第17号文書)の金額記載の方法に影響を与えるものではありません(例えば、事業者間で取り交わされる契約書への契約金額の記載やレシートなど決済時に作成される文書への決済金額の記載にまで「総額表示方式」が義務化されるものではありません。)。
ただ、消費税について「総額表示方式」が採用されたことに連動して、契約書(第1号及び第2号文書)や領収書(第17号文書)への金額記載の形態として、①税込価格とともにこれに含まれる消費税額等の金額について明確に記載されるケースや②消費税額等の金額について明確な記載はなく、税込価格と税抜価格が記載されるケースが混在するほか、従来よりも②のケースが増えてくることも予想されることから、その金額記載の形態に応じた印紙税の取扱いについて、改めて明確化することが求められていたところです。
そこで、上記の法令解釈通達について見直しが行われ、このほどその一部改正通達「「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて」の一部改正について(平成16年2月19日付課消3-5)(法令解釈通達)」が発遣されました。
以下、改正通達の概要とその内容についてQ&A形式により解説していくこととします。
1 取扱通達の改正の趣旨
(問) 「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年間消3-2,平成8年課消4-56改正)」の一部が改正されましたが、今回の改正の趣旨はどのようなことですか。
答
1 印紙税法上の記載金額の取扱い
印紙税法では、印紙税法別表第一「課税物件表」に掲げられた課税文書を作成した場合に、原則として収入印紙を貼り付け、消印する方法により納付することとされています。
また、印紙税法上の記載金額は、次の場合の判定要素として重要な意味があります。
(1)免税点がある文書に係る印紙税の課否判定の場合
(2)階級定額税率の適用を受ける課税文書の税額算定の場合
(3)一の文書で課税物件表の2以上の号に該当することとなる文書で、各号に係る記載金額により当該文書の所属が決定される場合
このため、文書の作成者は、自ら作成した文書の記載金額を把握し、これにより文書の課否判定や所属の決定を行ったり、また、階級定額税率の適用を受ける課税文書である場合には記載金額に応じた税額相応の収入印紙を貼付、消印することにより印紙税を納付する必要があります。
2 消費税額等取扱通達の取扱いの概要
「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年間消3-2,平成8年課消4-56改正)」通達(以下「消費税額等取扱通達」といいます。)においては、消費税額等の金額が記載された場合等の契約書や領収書における印紙税の記載金額の取扱いについて明らかにしているところです。
すなわち、印紙税の課税の対象となる契約書(第1号及び第2号文書)や領収書(第17号文書)に契約金額や領収金額を記載する場合において、消費税額等の金額が区分記載されている場合等には、当該消費税額等の金額は印紙税法上の記載金額に含めない旨明確にしているところです。
(参考)
① 消費税法においては、消費税額が転嫁されることを前提として製造業者から小売業者までの各取引段階で課税される多段階課税制度が採用されており(税の累積を避けるため仕入税額控除制度が採用され、売上げに係る消費税額等から仕入れに係る消費税額等を控除して、その残額を納付(控除しきれない時は還付)することとされています。)、各事業者においては消費税額を明確にして当該消費税額を損益に影響させない税抜経理方式(外税方式)の採用も認められています。
すなわち、課税事業者は、売上げに係る消費税額等を仮受消費税額等として、仕入れに係る消費税額等を仮払消費税額等として経理することにより、消費税額等は商品等の取得価格の一部を構成するものではなく、一種の税金の仮払金(又は単なる通過勘定)とすることができることとされています。
② また、税制改革法(昭和63年法律第107号)第11条において、「事業者は必要と認めるときは、取引の相手方である他の事業者又は消費者にその取引に課せられる消費税の額が明らかとなる措置を講ずるものとする」及び「国は消費税の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため必要な施策を講ずるものとする」旨の規定が置かれた経緯があります。
③ ①の消費税の性格及び②の趣旨にかんがみ、「消費税額等取扱通達」が制定されたものです。
3 今回改正の趣旨
契約書等に契約金額を記載する場合において消費税額等の金額を区分記載する場合の取扱いは上記のとおりですが、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)」により消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日から、いわゆる「総額表示義務」規定が適用されたところです。
この規定は、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいてあらかじめ価格を表示する場合に、消費税相当額(地方消費税相当額を含む。以下同じ)を含んだ消費者の支払総額の表示を義務付けるものであって、契約書(第1号文書及び第2号文書)又は領収書(第17号文書)への金額記載の方法に直ちに影響を与えるものではありません(例えば、事業者間で取り交わされる契約書への契約金額の記載やレシートなど決済時に作成される文書への領収金額の記載方法についてまで、総額表示方式が義務化されているものではありません。)。
ただ、契約書や領収書等の作成に当たって、総額表示義務に連動した形態の表示により契約金額等の記載がなされる場合など、これまでにない形態の表示により契約金額や領収金額等の記載がなされることが想定されるところです。
そこで、「消費税額等取扱通達」における消費税額等が区分記載されている場合の従来からの取扱いを踏襲するほか、税込価格及び税抜価格の双方が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかにされている場合についても当該消費税額等は記載金額に含まれない旨を新たに規定するなど、契約金額等の記載形態に応じた取扱いについて明確化を図ったものです。
2 取扱通達の改正の内容
(問) 「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年3月10日付間消3-2)」の一部が改正されましたが、今回の改正の内容を教えてください。
答
今回の改正内容は、契約書や領収書等に消費税額等が明記されている場合の従来の取扱規定を踏襲しつつ、消費税額等が明記されていないものの、取引総額(税込価格)とともにいわゆる税抜価格とが併記されている場合の事例を追加するなどして、その取扱いについて明確化を図ったものです。
改正の内容については、「消費税額等取扱通達新旧対照表」に記載のとおりであり、平成16年4月1日から適用されています。
(編注:「消費税額等取扱通達新旧対照表」は本誌No.61号30頁をご参照下さい。)
3 記載金額の具体的な取扱い
(問) 印紙税の記載金額の考え方については、今回の消費税額等取扱通達の改正により具体的にどのような取扱いになるのですか。
答
1 消費税額等取扱通達改正前の取扱い
従来から、契約書や領収書において、消費税額等が区分記載された場合、当該消費税額等は印紙税法上の記載金額に含めないこととする取扱いをしているところです。
例えば、次のような場合には、いずれも印紙税法上の記載金額は1,000万円として取り扱うことを明らかにしています。
イ 請負金額1,000万円、消費税額等50万円、 計1,050万円
ロ 請負金額1,050万円(うち消費税額等50万円)
2 改正後の取扱い
改正後においても、改正前の取扱いの考え方が踏襲されており、その取扱いの趣旨は異なることはありませんが、今回の改正においては、契約書や領収書等の作成に当たって、例えば消費税の総額表示義務に連動した形態の表示により契約金額等の記載がなされる場合も含めて、印紙税法上の記載金額の取扱いを明確化しています。
具体的には、次の区分に応じて、それぞれ次のとおり例示を掲げ、いずれの場合にも印紙税法上の記載金額は1,000万円として取り扱うこととしています。
(1)「消費税額等が区分記載されている場合」
イ 請負金額1,000万円 消費税額等50万円 計1,050万円
ロ 請負金額1,050万円 うち消費税額等50万円
ハ 請負金額1,050万円 税抜価格1,000万円 消費税額等50万円
(注)「消費税額等が区分記載されている」とは、その取引に当たって課されるべき消費税額等が具体的に記載されていることをいいます。
(2)「税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合」
ニ 請負金額1,050万円 税抜価格1,000万円
(注)「税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである」とは、その取引に係る消費税額等を含む金額と消費税額等を含まない金額の両方を具体的に記載していることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が容易に計算できることをいいます。
(参考)
個別間接税の取扱い
酒税や揮発油税等は製造場移出課税制度(単段階課税制度)であり、課税原因である酒類や揮発油等の製造場からの移出数量を課税標準として課税されるものです。
例えば、酒類を課税物件とする酒税は、一旦、製造場(メーカー)から移出された段階で課税され、その後の流通段階でどのような価格で販売されるかにかかわらず、酒税相当額はその他の販売経費等と同様に価格に織り込まれ、販売原価の一部を構成するものとして取引されるものです。
この点が一種の仮払金として処理することができる消費税額等とは、その性格及び取引段階における取扱いの実態において異なっています。
このことから、これらの個別間接税については、契約書や領収書に税相当額を区分して記載したとしても、単に課税対象物の原価を構成する内訳の一部を記載しているものに過ぎないことから、従来から印紙税の記載金額から除外することはできないものとして取り扱っており、これは消費税の導入以前から定着した考え方となっています。
4 「本体価格」表示の取扱い
(問) 「税抜価格」の表示を、「本体価格」と表示した場合、取扱いに違いがありますか。
答
1 「税抜価格」の意義
印紙税法上の記載金額として取り扱うこととなる「税抜価格」とは、消費税額等の金額を含めた取引価格から消費税額等の金額(課されるべき消費税額等相当額)を控除した残額をいいます。
2 「本体価格」の取扱い
契約書又は領収書等の課税文書上に「本体価格」と表示した場合であっても、その価格が消費税額等の金額を含めた取引価格から消費税額等の金額を控除した残額であることが、記載文言や表示金額によって明らかであれば「税抜価格」と同じ金額と認められます。
したがって、表示された「本体価格」が、消費税額等の金額を含めた取引価格に含まれている消費税額等の金額を控除した金額として記載されている場合には、「税抜価格」と表示されている場合と同様に取り扱われます。
5 税抜価格とは異なる「本体価格」表示の取扱い
(問) 「本体価格」を表示する場合で、例えば、領収書に次のような表示をした時はどのような取扱いになりますか。
(例)エアコン 105,000円(本体価格80,000円)
(注)この場合の(本体価格80,000円)は、エアコンの本体価格であり、本来の税抜価格は、105,000円から消費税額等の金額に相当する5,000円を除いた価額としての100,000円(エアコンの本体価格80,000円と取付工事費本体価格20,000円の合計額)である。
答
1 事例の場合のように、消費税額等の金額を含めた取引価格(105,000円)を表示する一方、いわゆる「税抜価格」とは異なった「本体価格」(質問の場合はエアコンの本体価格)を表示しても、取引価格に含まれる消費税額等の金額(5,000円)を控除した残額としての「本体価格」を表示するものではありません。
(質問の場合はエアコンの本体価格のみを表示しているものです。)
したがって、質問の場合の印紙税法上の記載金額は、取引価格合計105,000円となります。
2 なお、領収書に次のように表示をした場合には、取引価格の合計額から消費税額等を控除した残額が「本体価格」として表示されているものと認められますから、その金額(100,000円)が記載金額となります。
① 105,000円(うちエアコン本体価格80,000円 取付工事費20,000円)
② 105,000円(うちエアコン本体及び取付工事費合計100,000円)
6 「記載金額に含めない」の意義
(問) 消費税額等の金額を「記載金額に含めない」場合というのは、具体的にはどのような場合をいうのですか。
答
1 印紙税は、印紙税法別表第一「課税物件表」に掲げられた課税文書を作成した場合に、原則として収入印紙を貼り付け、消印する方法により納付することとされています。
また、印紙税法上の記載金額は、次の場合の判定要素として重要な意味があります。
(1)免税点がある文書に係る印紙税の課否判定の場合
(2)階級定額税率の適用を受ける課税文書の税額算定の場合
(3)一の文書で課税物件表の2以上の号に該当することとなる文書で、各号の記載金額により当該文書の所属が決定される場合
そこで、消費税額等取扱通達においては、次の契約書や領収書等において、消費税額等の金額が区分記載されている場合及び消費税額等の金額を含めた税込価格と合わせて税抜価格が具体的に記載されていることによりその取引に当たって課されるべき消費税額等が容易に計算できる場合には、その消費税額等の金額は、印紙税法上の「記載金額に含めない」こととなります。
イ 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
ロ 第2号文書(請負に関する契約書)
ハ 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
2 これを、例えば第17号の1文書(売上代金の金銭又は有価証券の受取書)により例示すれば次のとおりです。
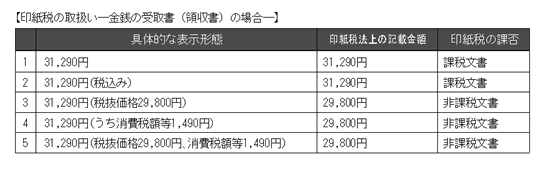
(参考)
① 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)は、記載金額が30,000円未満の場合には非課税文書となります。
② 一つの取引に係る代金を分割して受領する場合に、消費税額等の金額を当初に又は最後に受領することとしている場合などにおいて、消費税額等の金額のみが記載された領収書が作成される場合の取扱いは、次のとおりとなります。
イ 消費税額等の金額が30,000円未満の場合には非課税
ロ 消費税額等の金額が30,000円以上の場合には、記載金額のない領収書(第17号の2文書)となり、記載された金額にかかわらず印紙税額は200円
7 「消費税額等を含む」等と記載した場合の取扱い
(問) 「消費税及び地方消費税を含む。」又は「消費税額等5%を含む。」と記載した場合には、明示されている取引価格金額から計算すれば消費税額等の金額が明らかとなりますから、計算した後の金額を印紙税法上の記載金額として取り扱うこととなりますか。
答
1 印紙税は課税文書の記載金額により、課税文書の所属の決定や非課税文書の判定及び適用する税率が確定することとなりますから、具体的な円単位までの金額を文書上の記載金額により適正に判定できることが必要となります。
このようなことから、「消費税及び地方消費税を含む。」又は「消費税額等5%を含む。」などと記載され、具体的な消費税額等の金額又は税抜価格が明示されていない場合においては、次のような問題が生じます。
① 例えば、土地付き建物を一括して譲渡した場合の不動産の譲渡契約書の場合には、消費税の課税取引と非課税取引が混在する取引であることから、取引価格から逆算しても消費税額等の金額が明らかとはなりません。
すなわち、消費税の観点からは、建物部分は課税取引であり、土地部分は非課税取引となりますから、課税となる建物部分に課されるべき具体的な消費税額等の金額又は税抜価格が明示されていない場合には、計算しても消費税額等の金額が明らかとはならない場合があります。
② 一つの取引に係る代金を分割して受領するような場合において、消費税額等の金額を当初に又は最後に受領することとしている場合などにおいては、分割金の領収書上において必ずしもその領収金額が消費税額を含んだ売上代金の領収書かどうか判明しないことから、消費税額等の金額が明らかとはなりません。
2 したがって、「消費税及び地方消費税を含む。」又は「消費税額等5%を含む。」などの表示がなされているときは、取引価格から計算したとしても、取引価格に含まれる課されるべき消費税額等の金額が必ずしも明らかにならないため、結果的に印紙税の記載金額の判定上から除かれる消費税額等の金額が適正に算定できないこととなります。
このため、ご質問のようなケースにおいては、消費税額等取扱通達の適用上においては明示されている取引価格金額が記載金額として取り扱われることとなります。
8 「課されるべき消費税額等の金額」の意義
(問) 不動産の譲渡に関する契約書において、次のような記載がなされた場合の取扱いはどのようになりますか。なお、その明細は土地の譲渡価格が2,100万円、建物の譲渡価格が2,100万円(うち消費税額等100万円)ですが、この明細は契約書上明記されていません。
譲渡価格 土地及び建物価格 4,200万円(うち消費税額等100万円)
答
1 土地付建物等の不動産の譲渡に関する契約書において、土地と建物それぞれの譲渡価格と建物部分に係る消費税額等とが、明記されていない場合には、譲渡価格の総額が印紙税法上の記載金額として取り扱われます。
ただし、ご質問のように、不動産の譲渡価格の総額のほか、建物部分に係る消費税額等が記載されているようなケースでは、土地及び建物の譲渡価格の総額に対応する課されるべき消費税額等の金額が明記されているか否かにより、その取扱いを異にします。
すなわち、表示されている消費税額等が、土地及び建物の譲渡価格の総額に対応する課されるべき消費税額等の金額(建物部分の消費税額等に相当する金額)である場合には、消費税額等取扱通達の規定を適用して当該消費税額等の金額は記載金額から除外することができますが、土地及び建物の譲渡価格の総額に対応する課されるべき消費税額等の金額と認められない場合には、当該通達の適用はありません。
2 ご質問の場合には、うち書き表示されている消費税額等の金額(100万円)は建物部分について課されるべき消費税額等の金額であることが明らかですから、土地及び建物の譲渡価格の総額のほか、これに対応する課されるべき消費税額等の金額が明確に記載されていることになります。
3 したがって、ご質問の契約書に係る印紙税法上の記載金額は、譲渡価格総額4,200万円から課されるべき消費税額等の金額100万円を除いた4,100万円となります。
9 手形金額と印紙税の記載金額
(問) 商品の購入代金を支払うために、第3号文書となる「約束手形」を振り出す場合に、消費税額等の金額を区分して記載した場合であっても消費税額等の金額を含めて印紙税法上の記載金額となるのはなぜですか。
答
約束手形又は為替手形の印紙税の課税標準は、手形に記載された手形金額となります。この場合の手形金額とは、手形法上の金銭の給付を内容とする手形債権の金額をいうこととされています。
つまり、手形金額について消費税額等の金額を区分記載したとしても、その手形の最初の振出原因にかかわらず、消費税額等の金額を含めた総額が手形債権として確立することとなりますから、消費税額等の金額を区分して記載した場合であっても消費税額等の金額を含めて記載金額とされます。
(参考)
1 例えば、買掛金の支払いのために振り出した約束手形は、手形の振出人から最初に受領した受取人がそのまま決済するものとは限らず、裏書されることにより転々と流通する場合やその手形金額をもとに支払期日前に割り引くことにより決済する場合もあります。
このように、手形債権については、手形の振出人の振り出し原因にかかわらず手形に記載した手形金額の総額に対して成立することとなります。
2 手形は、手形法に定められた記載方法や様式について遵守した上で作成する必要がある要式証券であり、要件を欠くもの又は手形の効力を失わせる有害的な記載をしたものは無効な手形となる場合があり、そのような約束手形や為替手形は印紙税の課税の対象となる約束手形や為替手形には該当しないこととなります。
10 債権譲渡金額と印紙税の記載金額
(問) 第15号文書となる「債権譲渡の契約書」を作成した場合に、消費税額等の金額を区分して記載した場合であっても消費税額等の金額を含めて印紙税法上の記載金額となるのはなぜですか。
答
債権の譲渡があった場合の債権の価格は、その債権が発生した原因のいかんにかかわらず、譲受人が取得することとなる債権の総額となります。したがって、消費税額等の金額を区分記載したとしても、その消費税額等の金額を含めた総額が印紙税法上の記載金額となります。
また、例えば、譲渡の対象となった金銭債権が課税資産の譲渡等に係る売掛債権であった場合には、当該売掛債権には消費税額等の金額が含まれていますが、金銭債権の譲渡については、消費税は非課税となりますから、当該債権譲渡の契約書上に売掛債権に含まれる消費税額等の金額相当額が区分記載されていても、当該債権譲渡取引に対して課される消費税額等の金額は存せず、譲渡金額の総額が譲渡される金銭債権の金額となります。
このように、債権の譲渡に関する契約書については、従来から、仮に消費税額等の金額を区分して記載した場合であっても消費税額等の金額を含めて印紙税法上の記載金額となる旨を明らかにしています。
11 免税事業者が作成する領収書の取扱い
(問) いわゆる消費税の免税事業者が、領収書を作成するに当たって消費税額等の金額を区分記載した場合には、その消費税額等として記載された金額は印紙税法上の記載金額に含めないこととなるのですか。
答
いわゆる消費税の免税事業者が、ある商品の値決めとして売上価格を決定する場合は、その原価として仕入れの際に支払っている消費税額等の金額が加味されて決定されるものと考えられます。
しかしながら、免税事業者は課税資産の譲渡等について消費税を納める義務が免除されますから、課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等のうちには、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額等に相当する金額は含まれていないこととなります。
したがって、免税事業者の方が消費税額等の金額を区分して記載したとしても、その金額は消費税法により課されるべき消費税額等の金額ではないこととなりますから、印紙税法上の取扱いにおいては、記載金額から除かれることにはなりません。
なお、この取扱いは、従来から同様です。
12 課税事業者と免税事業者が共同で作成する文書の取扱い
(問) いわゆる消費税の課税事業者と免税事業者が、共同で作成する契約書などの課税文書については、記載金額の取扱いはどのようになるのですか。
答
印紙税の課税文書となる契約書などを共同作成することにより連帯納税義務となる場合には、次のとおり取り扱われます。
例えば、課税事業者であるA建設株式会社と免税事業者であるB商店との間において、両者が署名押印し、A建設株式会社を請負人とする「建設請負契約書」を締結した場合には、消費税の課税の対象となる資産の譲渡等を行う者は、課税事業者であるA建設株式会社となります。
したがって、このような「建設請負契約書」において消費税額等の金額を区分して記載した場合には、その消費税額等の金額は記載金額に含まれないこととなります。
一方、いわゆる免税事業者が資産の譲渡等を行う場合の契約書においては、消費税額等が課されない取引であることから、消費税額等の金額を区分記載したとしてもこれを記載金額から除くこととはなりません。
なお、この考え方は、契約当事者の一方が消費者であった場合を含め、従来から同様の取扱いです。
13 一括値引きした場合の取扱い
(問) 消費税額等を区分記載した後、又は税込価格と税抜価格をそれぞれ記載した後に、一括して値引きをした場合の記載金額の取扱いはどのようになるのですか。
答
印紙税の記載金額とは、契約当事者においてその契約書に記載することにより直接証明しようとしている金額をいいます。契約時に一括して値引きがあったような場合には、契約当事者間においては値引き後の金額による契約が成立したことを証明するものとなりますから、値引き後の金額の記載方法によりそれぞれ以下のとおり取り扱われます。
1 消費税額等の区分記載がある場合
(1)第1号文書、第2号文書の契約書及び第17号文書の受取書について、一括して値引きした後の金額(契約金額や受取金額となる税込価格)に係る消費税額等の金額が区分記載されている場合には、その一括値引き後の金額から消費税額等の金額を控除した残額が記載金額になります。
例えば、第2号文書(請負に関する契約書)において、
(例1)
請負金額 5,000,000円
消費税等 250,000円
計 5,250,000円
値 引 100,000円
差引請負金額 5,150,000円
(うち消費税等 245,238円)
と記載されている場合には、値引き後の請負金額(差引請負金額5,150,000円)に含まれる消費税額等の具体的な金額(245,238円)が区分記載されていますから、消費税額等の金額を除いた残額(4,904,762円)が記載金額となります。
(2)第1号文書、第2号文書の契約書及び第17号文書の受取書について、一括して値引きした後の金額(契約金額や受取金額となる税込価格)に係る消費税額等の金額が区分記載されていない場合には、その一括値引き後の金額が記載金額になります。
例えば、第2号文書(請負に関する契約書)において、
(例2)
請負金額 5,000,000円
消費税等 250,000円
計 5,250,000円
値 引 100,000円
差引請負金額 5,150,000円
と記載されている場合には、値引き前の請負金額5,000,000円に係る消費税額等250,000円が区分記載されていますが、税込価格5,250,000円から一括値引きした後の請負金額(差引請負金額5,150,000円)が記載されているのみで、これに含まれる消費税額等の具体的な金額が区分記載されていませんので、差引請負金額(5,150,000円)が記載金額となります。
2 税込価格と税抜価格の記載がある場合
(1)第1号文書、第2号文書の契約書及び第17号文書の受取書について、一括して値引きした後の金額(契約金額や受取金額となる税込価格)の記載とともに、これに係る課されるべき消費税額等を控除した金額(税抜価格)とが区分記載されている場合には、その税抜価格が記載金額になります。
例えば、第2号文書(請負に関する契約書)において、
(例3)
請負金額 5,250,000円
(税抜金額 5,000,000円)
値 引 100,000円
差引請負金額 5,150,000円
(税抜金額 4,904,762円)
と記載されている場合には、値引き後の請負金額(差引請負金額5,150,000円)とともに、課されるべき消費税額等を控除した金額(税抜価格4,904,762円)とが区分記載されていますから、税抜価格(4,904,762円)が記載金額となります。
(2)第1号文書、第2号文書の契約書及び第17号文書の受取書について、一括して値引きした後の金額(契約金額や受取金額となる税込価格)の記載はあるものの、これに係る課されるべき消費税額等を控除した金額(税抜価格)が区分記載されていない場合には、その一括値引後の金額が記載金額になります。
例えば、第2号文書(請負に関する契約書)において、
(例4)
請負金額 5,250,000円
(税抜金額 5,000,000円)
値 引 100,000円
差引請負金額 5,150,000円
と記載されている場合には、値引き前の請負金額5,250,000円に係る消費税額等を控除した金額(税抜金額5,000,000円)が区分記載されていますが、税込価格5,250,000円から一括値引きした後の請負金額(差引請負金額5,150,000円)が記載されているのみで、これに係る税抜価格の金額が区分記載されていませんので、差引請負金額(5,150,000円)が記載金額となります。
14 通帳等のみなし作成の取扱い
(問) 受取通帳や判取帳に一定金額以上の付込みをすると、その付け込んだ事項の文書が別に作成されたものとして課税されると聞きましたが、その取扱いについて説明してください。
また、付込みの際に消費税額等の金額を区分記載した場合や、税込価格と税抜価格をそれぞれ記載した場合については、どのように取り扱うのでしょうか。
答
1 通帳等のみなし作成
課税物件表の第19号(第1号、第2号、第14号又は第17号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳)又は第20号(判取帳)の課税文書(以下「通帳等」といいます。)は、1冊1年以内の付込みにつき、第19号文書は400円、第20号文書は4,000円の印紙税を納付することになっています。
しかし、この通帳等に次の事項の付込みがされた場合において、その付込みがされた事項に係る記載金額が次に掲げる金額であるときは、その付込みがされた事項に係る部分については、通帳等への付込みがなく、次に掲げる課税文書の作成があったものとみなされます(法第4条第4項)。
(1)第1号(不動産の譲渡等に関する契約書)の課税文書により証されるべき事項
10万円を超える金額 ⇒ 第1号文書
例えば、貸付金通帳に10万円を超える貸付金額50万円を付込み証明したときには、その50万円の付込みは、貸付金通帳への付込みにはならず、新たな「消費貸借に関する契約書(第1号の3文書)」を作成したものとみなされます。
(2)第2号(請負に関する契約書)の課税文書により証されるべき事項
100万円を超える金額 ⇒ 第2号文書
例えば、注文請負通帳に100万円を超える請負金額200万円を付込み証明したときには、その200万円の付込みは、注文請負通帳への付込みにはならず、新たな「請負に関する契約書(第2号文書)」を作成したものとみなされます。
(3)第17号の1(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)の課税文書により証されるべき事項
100万円を超える金額 ⇒ 第17号の1文書
例えば、受取通帳に100万円を超える売上代金に係る受取金額300万円を付込み証明したときには、その300万円の付込みは、受取通帳への付込みにはならず、新たな「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号の1文書)」を作成したものとみなされます。
2 付込み金額に消費税額等の金額を含む場合
通帳等に運送金額、請負金額又は受取金額等を付込み証明する場合において、これらの金額に消費税額等の金額が含まれている場合には、その含まれている金額で「10万円」又は「100万円」を超えるかどうかを判定します。
3 付込み金額に消費税額等の金額を含まない場合
通帳等に運送金額、請負金額又は受取金額等を付込み証明する場合において、これらの金額と消費税額等の金額とが区分記載されている場合には、消費税額等の金額を含まない金額で「10万円」又は「100万円」を超えるかどうかを判定します。
4 付込み金額に税込価格と税抜価格が記載されている場合
通帳等に運送金額、請負金額又は受取金額等を付込み証明する場合において、税込価格と税抜価格(税込価格から消費税額等の金額を控除した金額)とがそれぞれ記載されている場合には、消費税額等取扱通達の1及び2により、その取引に係る消費税額等を含む金額と含まない金額の両方が具体的に記載されていて、その取引に当たって課されるべき消費税額等が容易に計算できることから、税抜価格で「10万円」又は「100万円」を超えるかどうかを判定します。
5 付込み金額が消費税額等の金額のみである場合
通帳等に消費税額等のみを付込み証明した場合には、その消費税額等が「10万円」又は「100万円」を超えていても、消費税額等取扱通達の2により、新たな課税文書の作成として取り扱われることはありません。
消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて
-消費税の総額表示と印紙税の記載金額の取扱い-
植松浩行
印紙税の取扱いにおいては、契約書や領収書等に記載される取引金額や決済金額が、負担する印紙税額に直接影響(階級定額税率の適用や課否の判定に影響)することから、その文書の記載金額がいくらになるのかを確定することが重要となってきます。
なお従来から、国税庁では「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年3月10日付間消3-2、平成8年課消4-56最終改正)(法令解釈通達)」により、印紙税法に規定する「記載金額」の取扱いとして、契約書(第1号及び第2号文書)や領収書(第17号文書)に消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」という。)の金額が区分して記載されている場合には、その消費税額等の金額については印紙税法上の記載金額に含めない取扱いを示してきており、印紙税実務においては定着した取扱いとなっています。
ところで、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第6条の規定による改正後の消費税法第63条の2《価格の表示》においては、課税事業者が消費者に対してあらかじめ値札や広告などにおいて価格を表示する場合に、消費税額等の金額を含んだ税込価格を表示することが義務付けられ、いわゆる「総額表示方式」が平成16年4月1日からスタートしています。
この「総額表示方式」が消費税法で採用されたことが、直ちに契約書(第1号及び第2号文書)や領収書(第17号文書)の金額記載の方法に影響を与えるものではありません(例えば、事業者間で取り交わされる契約書への契約金額の記載やレシートなど決済時に作成される文書への決済金額の記載にまで「総額表示方式」が義務化されるものではありません。)。
ただ、消費税について「総額表示方式」が採用されたことに連動して、契約書(第1号及び第2号文書)や領収書(第17号文書)への金額記載の形態として、①税込価格とともにこれに含まれる消費税額等の金額について明確に記載されるケースや②消費税額等の金額について明確な記載はなく、税込価格と税抜価格が記載されるケースが混在するほか、従来よりも②のケースが増えてくることも予想されることから、その金額記載の形態に応じた印紙税の取扱いについて、改めて明確化することが求められていたところです。
そこで、上記の法令解釈通達について見直しが行われ、このほどその一部改正通達「「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて」の一部改正について(平成16年2月19日付課消3-5)(法令解釈通達)」が発遣されました。
以下、改正通達の概要とその内容についてQ&A形式により解説していくこととします。
1 取扱通達の改正の趣旨
(問) 「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年間消3-2,平成8年課消4-56改正)」の一部が改正されましたが、今回の改正の趣旨はどのようなことですか。
答
1 印紙税法上の記載金額の取扱い
印紙税法では、印紙税法別表第一「課税物件表」に掲げられた課税文書を作成した場合に、原則として収入印紙を貼り付け、消印する方法により納付することとされています。
また、印紙税法上の記載金額は、次の場合の判定要素として重要な意味があります。
(1)免税点がある文書に係る印紙税の課否判定の場合
(2)階級定額税率の適用を受ける課税文書の税額算定の場合
(3)一の文書で課税物件表の2以上の号に該当することとなる文書で、各号に係る記載金額により当該文書の所属が決定される場合
このため、文書の作成者は、自ら作成した文書の記載金額を把握し、これにより文書の課否判定や所属の決定を行ったり、また、階級定額税率の適用を受ける課税文書である場合には記載金額に応じた税額相応の収入印紙を貼付、消印することにより印紙税を納付する必要があります。
2 消費税額等取扱通達の取扱いの概要
「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年間消3-2,平成8年課消4-56改正)」通達(以下「消費税額等取扱通達」といいます。)においては、消費税額等の金額が記載された場合等の契約書や領収書における印紙税の記載金額の取扱いについて明らかにしているところです。
すなわち、印紙税の課税の対象となる契約書(第1号及び第2号文書)や領収書(第17号文書)に契約金額や領収金額を記載する場合において、消費税額等の金額が区分記載されている場合等には、当該消費税額等の金額は印紙税法上の記載金額に含めない旨明確にしているところです。
(参考)
① 消費税法においては、消費税額が転嫁されることを前提として製造業者から小売業者までの各取引段階で課税される多段階課税制度が採用されており(税の累積を避けるため仕入税額控除制度が採用され、売上げに係る消費税額等から仕入れに係る消費税額等を控除して、その残額を納付(控除しきれない時は還付)することとされています。)、各事業者においては消費税額を明確にして当該消費税額を損益に影響させない税抜経理方式(外税方式)の採用も認められています。
すなわち、課税事業者は、売上げに係る消費税額等を仮受消費税額等として、仕入れに係る消費税額等を仮払消費税額等として経理することにより、消費税額等は商品等の取得価格の一部を構成するものではなく、一種の税金の仮払金(又は単なる通過勘定)とすることができることとされています。
② また、税制改革法(昭和63年法律第107号)第11条において、「事業者は必要と認めるときは、取引の相手方である他の事業者又は消費者にその取引に課せられる消費税の額が明らかとなる措置を講ずるものとする」及び「国は消費税の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため必要な施策を講ずるものとする」旨の規定が置かれた経緯があります。
③ ①の消費税の性格及び②の趣旨にかんがみ、「消費税額等取扱通達」が制定されたものです。
3 今回改正の趣旨
契約書等に契約金額を記載する場合において消費税額等の金額を区分記載する場合の取扱いは上記のとおりですが、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)」により消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日から、いわゆる「総額表示義務」規定が適用されたところです。
この規定は、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいてあらかじめ価格を表示する場合に、消費税相当額(地方消費税相当額を含む。以下同じ)を含んだ消費者の支払総額の表示を義務付けるものであって、契約書(第1号文書及び第2号文書)又は領収書(第17号文書)への金額記載の方法に直ちに影響を与えるものではありません(例えば、事業者間で取り交わされる契約書への契約金額の記載やレシートなど決済時に作成される文書への領収金額の記載方法についてまで、総額表示方式が義務化されているものではありません。)。
ただ、契約書や領収書等の作成に当たって、総額表示義務に連動した形態の表示により契約金額等の記載がなされる場合など、これまでにない形態の表示により契約金額や領収金額等の記載がなされることが想定されるところです。
そこで、「消費税額等取扱通達」における消費税額等が区分記載されている場合の従来からの取扱いを踏襲するほか、税込価格及び税抜価格の双方が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかにされている場合についても当該消費税額等は記載金額に含まれない旨を新たに規定するなど、契約金額等の記載形態に応じた取扱いについて明確化を図ったものです。
2 取扱通達の改正の内容
(問) 「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年3月10日付間消3-2)」の一部が改正されましたが、今回の改正の内容を教えてください。
答
今回の改正内容は、契約書や領収書等に消費税額等が明記されている場合の従来の取扱規定を踏襲しつつ、消費税額等が明記されていないものの、取引総額(税込価格)とともにいわゆる税抜価格とが併記されている場合の事例を追加するなどして、その取扱いについて明確化を図ったものです。
改正の内容については、「消費税額等取扱通達新旧対照表」に記載のとおりであり、平成16年4月1日から適用されています。
(編注:「消費税額等取扱通達新旧対照表」は本誌No.61号30頁をご参照下さい。)
3 記載金額の具体的な取扱い
(問) 印紙税の記載金額の考え方については、今回の消費税額等取扱通達の改正により具体的にどのような取扱いになるのですか。
答
1 消費税額等取扱通達改正前の取扱い
従来から、契約書や領収書において、消費税額等が区分記載された場合、当該消費税額等は印紙税法上の記載金額に含めないこととする取扱いをしているところです。
例えば、次のような場合には、いずれも印紙税法上の記載金額は1,000万円として取り扱うことを明らかにしています。
イ 請負金額1,000万円、消費税額等50万円、 計1,050万円
ロ 請負金額1,050万円(うち消費税額等50万円)
2 改正後の取扱い
改正後においても、改正前の取扱いの考え方が踏襲されており、その取扱いの趣旨は異なることはありませんが、今回の改正においては、契約書や領収書等の作成に当たって、例えば消費税の総額表示義務に連動した形態の表示により契約金額等の記載がなされる場合も含めて、印紙税法上の記載金額の取扱いを明確化しています。
具体的には、次の区分に応じて、それぞれ次のとおり例示を掲げ、いずれの場合にも印紙税法上の記載金額は1,000万円として取り扱うこととしています。
(1)「消費税額等が区分記載されている場合」
イ 請負金額1,000万円 消費税額等50万円 計1,050万円
ロ 請負金額1,050万円 うち消費税額等50万円
ハ 請負金額1,050万円 税抜価格1,000万円 消費税額等50万円
(注)「消費税額等が区分記載されている」とは、その取引に当たって課されるべき消費税額等が具体的に記載されていることをいいます。
(2)「税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合」
ニ 請負金額1,050万円 税抜価格1,000万円
(注)「税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである」とは、その取引に係る消費税額等を含む金額と消費税額等を含まない金額の両方を具体的に記載していることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が容易に計算できることをいいます。
(参考)
個別間接税の取扱い
酒税や揮発油税等は製造場移出課税制度(単段階課税制度)であり、課税原因である酒類や揮発油等の製造場からの移出数量を課税標準として課税されるものです。
例えば、酒類を課税物件とする酒税は、一旦、製造場(メーカー)から移出された段階で課税され、その後の流通段階でどのような価格で販売されるかにかかわらず、酒税相当額はその他の販売経費等と同様に価格に織り込まれ、販売原価の一部を構成するものとして取引されるものです。
この点が一種の仮払金として処理することができる消費税額等とは、その性格及び取引段階における取扱いの実態において異なっています。
このことから、これらの個別間接税については、契約書や領収書に税相当額を区分して記載したとしても、単に課税対象物の原価を構成する内訳の一部を記載しているものに過ぎないことから、従来から印紙税の記載金額から除外することはできないものとして取り扱っており、これは消費税の導入以前から定着した考え方となっています。
4 「本体価格」表示の取扱い
(問) 「税抜価格」の表示を、「本体価格」と表示した場合、取扱いに違いがありますか。
答
1 「税抜価格」の意義
印紙税法上の記載金額として取り扱うこととなる「税抜価格」とは、消費税額等の金額を含めた取引価格から消費税額等の金額(課されるべき消費税額等相当額)を控除した残額をいいます。
2 「本体価格」の取扱い
契約書又は領収書等の課税文書上に「本体価格」と表示した場合であっても、その価格が消費税額等の金額を含めた取引価格から消費税額等の金額を控除した残額であることが、記載文言や表示金額によって明らかであれば「税抜価格」と同じ金額と認められます。
したがって、表示された「本体価格」が、消費税額等の金額を含めた取引価格に含まれている消費税額等の金額を控除した金額として記載されている場合には、「税抜価格」と表示されている場合と同様に取り扱われます。
5 税抜価格とは異なる「本体価格」表示の取扱い
(問) 「本体価格」を表示する場合で、例えば、領収書に次のような表示をした時はどのような取扱いになりますか。
(例)エアコン 105,000円(本体価格80,000円)
(注)この場合の(本体価格80,000円)は、エアコンの本体価格であり、本来の税抜価格は、105,000円から消費税額等の金額に相当する5,000円を除いた価額としての100,000円(エアコンの本体価格80,000円と取付工事費本体価格20,000円の合計額)である。
答
1 事例の場合のように、消費税額等の金額を含めた取引価格(105,000円)を表示する一方、いわゆる「税抜価格」とは異なった「本体価格」(質問の場合はエアコンの本体価格)を表示しても、取引価格に含まれる消費税額等の金額(5,000円)を控除した残額としての「本体価格」を表示するものではありません。
(質問の場合はエアコンの本体価格のみを表示しているものです。)
したがって、質問の場合の印紙税法上の記載金額は、取引価格合計105,000円となります。
2 なお、領収書に次のように表示をした場合には、取引価格の合計額から消費税額等を控除した残額が「本体価格」として表示されているものと認められますから、その金額(100,000円)が記載金額となります。
① 105,000円(うちエアコン本体価格80,000円 取付工事費20,000円)
② 105,000円(うちエアコン本体及び取付工事費合計100,000円)
6 「記載金額に含めない」の意義
(問) 消費税額等の金額を「記載金額に含めない」場合というのは、具体的にはどのような場合をいうのですか。
答
1 印紙税は、印紙税法別表第一「課税物件表」に掲げられた課税文書を作成した場合に、原則として収入印紙を貼り付け、消印する方法により納付することとされています。
また、印紙税法上の記載金額は、次の場合の判定要素として重要な意味があります。
(1)免税点がある文書に係る印紙税の課否判定の場合
(2)階級定額税率の適用を受ける課税文書の税額算定の場合
(3)一の文書で課税物件表の2以上の号に該当することとなる文書で、各号の記載金額により当該文書の所属が決定される場合
そこで、消費税額等取扱通達においては、次の契約書や領収書等において、消費税額等の金額が区分記載されている場合及び消費税額等の金額を含めた税込価格と合わせて税抜価格が具体的に記載されていることによりその取引に当たって課されるべき消費税額等が容易に計算できる場合には、その消費税額等の金額は、印紙税法上の「記載金額に含めない」こととなります。
イ 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
ロ 第2号文書(請負に関する契約書)
ハ 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
2 これを、例えば第17号の1文書(売上代金の金銭又は有価証券の受取書)により例示すれば次のとおりです。
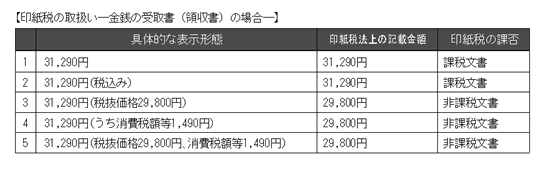
(参考)
① 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)は、記載金額が30,000円未満の場合には非課税文書となります。
② 一つの取引に係る代金を分割して受領する場合に、消費税額等の金額を当初に又は最後に受領することとしている場合などにおいて、消費税額等の金額のみが記載された領収書が作成される場合の取扱いは、次のとおりとなります。
イ 消費税額等の金額が30,000円未満の場合には非課税
ロ 消費税額等の金額が30,000円以上の場合には、記載金額のない領収書(第17号の2文書)となり、記載された金額にかかわらず印紙税額は200円
7 「消費税額等を含む」等と記載した場合の取扱い
(問) 「消費税及び地方消費税を含む。」又は「消費税額等5%を含む。」と記載した場合には、明示されている取引価格金額から計算すれば消費税額等の金額が明らかとなりますから、計算した後の金額を印紙税法上の記載金額として取り扱うこととなりますか。
答
1 印紙税は課税文書の記載金額により、課税文書の所属の決定や非課税文書の判定及び適用する税率が確定することとなりますから、具体的な円単位までの金額を文書上の記載金額により適正に判定できることが必要となります。
このようなことから、「消費税及び地方消費税を含む。」又は「消費税額等5%を含む。」などと記載され、具体的な消費税額等の金額又は税抜価格が明示されていない場合においては、次のような問題が生じます。
① 例えば、土地付き建物を一括して譲渡した場合の不動産の譲渡契約書の場合には、消費税の課税取引と非課税取引が混在する取引であることから、取引価格から逆算しても消費税額等の金額が明らかとはなりません。
すなわち、消費税の観点からは、建物部分は課税取引であり、土地部分は非課税取引となりますから、課税となる建物部分に課されるべき具体的な消費税額等の金額又は税抜価格が明示されていない場合には、計算しても消費税額等の金額が明らかとはならない場合があります。
② 一つの取引に係る代金を分割して受領するような場合において、消費税額等の金額を当初に又は最後に受領することとしている場合などにおいては、分割金の領収書上において必ずしもその領収金額が消費税額を含んだ売上代金の領収書かどうか判明しないことから、消費税額等の金額が明らかとはなりません。
2 したがって、「消費税及び地方消費税を含む。」又は「消費税額等5%を含む。」などの表示がなされているときは、取引価格から計算したとしても、取引価格に含まれる課されるべき消費税額等の金額が必ずしも明らかにならないため、結果的に印紙税の記載金額の判定上から除かれる消費税額等の金額が適正に算定できないこととなります。
このため、ご質問のようなケースにおいては、消費税額等取扱通達の適用上においては明示されている取引価格金額が記載金額として取り扱われることとなります。
8 「課されるべき消費税額等の金額」の意義
(問) 不動産の譲渡に関する契約書において、次のような記載がなされた場合の取扱いはどのようになりますか。なお、その明細は土地の譲渡価格が2,100万円、建物の譲渡価格が2,100万円(うち消費税額等100万円)ですが、この明細は契約書上明記されていません。
譲渡価格 土地及び建物価格 4,200万円(うち消費税額等100万円)
答
1 土地付建物等の不動産の譲渡に関する契約書において、土地と建物それぞれの譲渡価格と建物部分に係る消費税額等とが、明記されていない場合には、譲渡価格の総額が印紙税法上の記載金額として取り扱われます。
ただし、ご質問のように、不動産の譲渡価格の総額のほか、建物部分に係る消費税額等が記載されているようなケースでは、土地及び建物の譲渡価格の総額に対応する課されるべき消費税額等の金額が明記されているか否かにより、その取扱いを異にします。
すなわち、表示されている消費税額等が、土地及び建物の譲渡価格の総額に対応する課されるべき消費税額等の金額(建物部分の消費税額等に相当する金額)である場合には、消費税額等取扱通達の規定を適用して当該消費税額等の金額は記載金額から除外することができますが、土地及び建物の譲渡価格の総額に対応する課されるべき消費税額等の金額と認められない場合には、当該通達の適用はありません。
2 ご質問の場合には、うち書き表示されている消費税額等の金額(100万円)は建物部分について課されるべき消費税額等の金額であることが明らかですから、土地及び建物の譲渡価格の総額のほか、これに対応する課されるべき消費税額等の金額が明確に記載されていることになります。
3 したがって、ご質問の契約書に係る印紙税法上の記載金額は、譲渡価格総額4,200万円から課されるべき消費税額等の金額100万円を除いた4,100万円となります。
9 手形金額と印紙税の記載金額
(問) 商品の購入代金を支払うために、第3号文書となる「約束手形」を振り出す場合に、消費税額等の金額を区分して記載した場合であっても消費税額等の金額を含めて印紙税法上の記載金額となるのはなぜですか。
答
約束手形又は為替手形の印紙税の課税標準は、手形に記載された手形金額となります。この場合の手形金額とは、手形法上の金銭の給付を内容とする手形債権の金額をいうこととされています。
つまり、手形金額について消費税額等の金額を区分記載したとしても、その手形の最初の振出原因にかかわらず、消費税額等の金額を含めた総額が手形債権として確立することとなりますから、消費税額等の金額を区分して記載した場合であっても消費税額等の金額を含めて記載金額とされます。
(参考)
1 例えば、買掛金の支払いのために振り出した約束手形は、手形の振出人から最初に受領した受取人がそのまま決済するものとは限らず、裏書されることにより転々と流通する場合やその手形金額をもとに支払期日前に割り引くことにより決済する場合もあります。
このように、手形債権については、手形の振出人の振り出し原因にかかわらず手形に記載した手形金額の総額に対して成立することとなります。
2 手形は、手形法に定められた記載方法や様式について遵守した上で作成する必要がある要式証券であり、要件を欠くもの又は手形の効力を失わせる有害的な記載をしたものは無効な手形となる場合があり、そのような約束手形や為替手形は印紙税の課税の対象となる約束手形や為替手形には該当しないこととなります。
10 債権譲渡金額と印紙税の記載金額
(問) 第15号文書となる「債権譲渡の契約書」を作成した場合に、消費税額等の金額を区分して記載した場合であっても消費税額等の金額を含めて印紙税法上の記載金額となるのはなぜですか。
答
債権の譲渡があった場合の債権の価格は、その債権が発生した原因のいかんにかかわらず、譲受人が取得することとなる債権の総額となります。したがって、消費税額等の金額を区分記載したとしても、その消費税額等の金額を含めた総額が印紙税法上の記載金額となります。
また、例えば、譲渡の対象となった金銭債権が課税資産の譲渡等に係る売掛債権であった場合には、当該売掛債権には消費税額等の金額が含まれていますが、金銭債権の譲渡については、消費税は非課税となりますから、当該債権譲渡の契約書上に売掛債権に含まれる消費税額等の金額相当額が区分記載されていても、当該債権譲渡取引に対して課される消費税額等の金額は存せず、譲渡金額の総額が譲渡される金銭債権の金額となります。
このように、債権の譲渡に関する契約書については、従来から、仮に消費税額等の金額を区分して記載した場合であっても消費税額等の金額を含めて印紙税法上の記載金額となる旨を明らかにしています。
11 免税事業者が作成する領収書の取扱い
(問) いわゆる消費税の免税事業者が、領収書を作成するに当たって消費税額等の金額を区分記載した場合には、その消費税額等として記載された金額は印紙税法上の記載金額に含めないこととなるのですか。
答
いわゆる消費税の免税事業者が、ある商品の値決めとして売上価格を決定する場合は、その原価として仕入れの際に支払っている消費税額等の金額が加味されて決定されるものと考えられます。
しかしながら、免税事業者は課税資産の譲渡等について消費税を納める義務が免除されますから、課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等のうちには、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額等に相当する金額は含まれていないこととなります。
したがって、免税事業者の方が消費税額等の金額を区分して記載したとしても、その金額は消費税法により課されるべき消費税額等の金額ではないこととなりますから、印紙税法上の取扱いにおいては、記載金額から除かれることにはなりません。
なお、この取扱いは、従来から同様です。
12 課税事業者と免税事業者が共同で作成する文書の取扱い
(問) いわゆる消費税の課税事業者と免税事業者が、共同で作成する契約書などの課税文書については、記載金額の取扱いはどのようになるのですか。
答
印紙税の課税文書となる契約書などを共同作成することにより連帯納税義務となる場合には、次のとおり取り扱われます。
例えば、課税事業者であるA建設株式会社と免税事業者であるB商店との間において、両者が署名押印し、A建設株式会社を請負人とする「建設請負契約書」を締結した場合には、消費税の課税の対象となる資産の譲渡等を行う者は、課税事業者であるA建設株式会社となります。
したがって、このような「建設請負契約書」において消費税額等の金額を区分して記載した場合には、その消費税額等の金額は記載金額に含まれないこととなります。
一方、いわゆる免税事業者が資産の譲渡等を行う場合の契約書においては、消費税額等が課されない取引であることから、消費税額等の金額を区分記載したとしてもこれを記載金額から除くこととはなりません。
なお、この考え方は、契約当事者の一方が消費者であった場合を含め、従来から同様の取扱いです。
13 一括値引きした場合の取扱い
(問) 消費税額等を区分記載した後、又は税込価格と税抜価格をそれぞれ記載した後に、一括して値引きをした場合の記載金額の取扱いはどのようになるのですか。
答
印紙税の記載金額とは、契約当事者においてその契約書に記載することにより直接証明しようとしている金額をいいます。契約時に一括して値引きがあったような場合には、契約当事者間においては値引き後の金額による契約が成立したことを証明するものとなりますから、値引き後の金額の記載方法によりそれぞれ以下のとおり取り扱われます。
1 消費税額等の区分記載がある場合
(1)第1号文書、第2号文書の契約書及び第17号文書の受取書について、一括して値引きした後の金額(契約金額や受取金額となる税込価格)に係る消費税額等の金額が区分記載されている場合には、その一括値引き後の金額から消費税額等の金額を控除した残額が記載金額になります。
例えば、第2号文書(請負に関する契約書)において、
(例1)
請負金額 5,000,000円
消費税等 250,000円
計 5,250,000円
値 引 100,000円
差引請負金額 5,150,000円
(うち消費税等 245,238円)
と記載されている場合には、値引き後の請負金額(差引請負金額5,150,000円)に含まれる消費税額等の具体的な金額(245,238円)が区分記載されていますから、消費税額等の金額を除いた残額(4,904,762円)が記載金額となります。
(2)第1号文書、第2号文書の契約書及び第17号文書の受取書について、一括して値引きした後の金額(契約金額や受取金額となる税込価格)に係る消費税額等の金額が区分記載されていない場合には、その一括値引き後の金額が記載金額になります。
例えば、第2号文書(請負に関する契約書)において、
(例2)
請負金額 5,000,000円
消費税等 250,000円
計 5,250,000円
値 引 100,000円
差引請負金額 5,150,000円
と記載されている場合には、値引き前の請負金額5,000,000円に係る消費税額等250,000円が区分記載されていますが、税込価格5,250,000円から一括値引きした後の請負金額(差引請負金額5,150,000円)が記載されているのみで、これに含まれる消費税額等の具体的な金額が区分記載されていませんので、差引請負金額(5,150,000円)が記載金額となります。
2 税込価格と税抜価格の記載がある場合
(1)第1号文書、第2号文書の契約書及び第17号文書の受取書について、一括して値引きした後の金額(契約金額や受取金額となる税込価格)の記載とともに、これに係る課されるべき消費税額等を控除した金額(税抜価格)とが区分記載されている場合には、その税抜価格が記載金額になります。
例えば、第2号文書(請負に関する契約書)において、
(例3)
請負金額 5,250,000円
(税抜金額 5,000,000円)
値 引 100,000円
差引請負金額 5,150,000円
(税抜金額 4,904,762円)
と記載されている場合には、値引き後の請負金額(差引請負金額5,150,000円)とともに、課されるべき消費税額等を控除した金額(税抜価格4,904,762円)とが区分記載されていますから、税抜価格(4,904,762円)が記載金額となります。
(2)第1号文書、第2号文書の契約書及び第17号文書の受取書について、一括して値引きした後の金額(契約金額や受取金額となる税込価格)の記載はあるものの、これに係る課されるべき消費税額等を控除した金額(税抜価格)が区分記載されていない場合には、その一括値引後の金額が記載金額になります。
例えば、第2号文書(請負に関する契約書)において、
(例4)
請負金額 5,250,000円
(税抜金額 5,000,000円)
値 引 100,000円
差引請負金額 5,150,000円
と記載されている場合には、値引き前の請負金額5,250,000円に係る消費税額等を控除した金額(税抜金額5,000,000円)が区分記載されていますが、税込価格5,250,000円から一括値引きした後の請負金額(差引請負金額5,150,000円)が記載されているのみで、これに係る税抜価格の金額が区分記載されていませんので、差引請負金額(5,150,000円)が記載金額となります。
14 通帳等のみなし作成の取扱い
(問) 受取通帳や判取帳に一定金額以上の付込みをすると、その付け込んだ事項の文書が別に作成されたものとして課税されると聞きましたが、その取扱いについて説明してください。
また、付込みの際に消費税額等の金額を区分記載した場合や、税込価格と税抜価格をそれぞれ記載した場合については、どのように取り扱うのでしょうか。
答
1 通帳等のみなし作成
課税物件表の第19号(第1号、第2号、第14号又は第17号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳)又は第20号(判取帳)の課税文書(以下「通帳等」といいます。)は、1冊1年以内の付込みにつき、第19号文書は400円、第20号文書は4,000円の印紙税を納付することになっています。
しかし、この通帳等に次の事項の付込みがされた場合において、その付込みがされた事項に係る記載金額が次に掲げる金額であるときは、その付込みがされた事項に係る部分については、通帳等への付込みがなく、次に掲げる課税文書の作成があったものとみなされます(法第4条第4項)。
(1)第1号(不動産の譲渡等に関する契約書)の課税文書により証されるべき事項
10万円を超える金額 ⇒ 第1号文書
例えば、貸付金通帳に10万円を超える貸付金額50万円を付込み証明したときには、その50万円の付込みは、貸付金通帳への付込みにはならず、新たな「消費貸借に関する契約書(第1号の3文書)」を作成したものとみなされます。
(2)第2号(請負に関する契約書)の課税文書により証されるべき事項
100万円を超える金額 ⇒ 第2号文書
例えば、注文請負通帳に100万円を超える請負金額200万円を付込み証明したときには、その200万円の付込みは、注文請負通帳への付込みにはならず、新たな「請負に関する契約書(第2号文書)」を作成したものとみなされます。
(3)第17号の1(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)の課税文書により証されるべき事項
100万円を超える金額 ⇒ 第17号の1文書
例えば、受取通帳に100万円を超える売上代金に係る受取金額300万円を付込み証明したときには、その300万円の付込みは、受取通帳への付込みにはならず、新たな「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号の1文書)」を作成したものとみなされます。
2 付込み金額に消費税額等の金額を含む場合
通帳等に運送金額、請負金額又は受取金額等を付込み証明する場合において、これらの金額に消費税額等の金額が含まれている場合には、その含まれている金額で「10万円」又は「100万円」を超えるかどうかを判定します。
3 付込み金額に消費税額等の金額を含まない場合
通帳等に運送金額、請負金額又は受取金額等を付込み証明する場合において、これらの金額と消費税額等の金額とが区分記載されている場合には、消費税額等の金額を含まない金額で「10万円」又は「100万円」を超えるかどうかを判定します。
4 付込み金額に税込価格と税抜価格が記載されている場合
通帳等に運送金額、請負金額又は受取金額等を付込み証明する場合において、税込価格と税抜価格(税込価格から消費税額等の金額を控除した金額)とがそれぞれ記載されている場合には、消費税額等取扱通達の1及び2により、その取引に係る消費税額等を含む金額と含まない金額の両方が具体的に記載されていて、その取引に当たって課されるべき消費税額等が容易に計算できることから、税抜価格で「10万円」又は「100万円」を超えるかどうかを判定します。
5 付込み金額が消費税額等の金額のみである場合
通帳等に消費税額等のみを付込み証明した場合には、その消費税額等が「10万円」又は「100万円」を超えていても、消費税額等取扱通達の2により、新たな課税文書の作成として取り扱われることはありません。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















