資料2004年06月30日 【裁決事例】 譲渡担保財産が将来債権である場合、当該債権が譲渡担保財産となった時期は、債権が具体的に発生した時であるとした事例(納税者株式会社Aの滞納国税に係る債権の差押処分/棄却)
(平15.2.19裁決、裁決事例集No.65 1010頁)
《裁決書(抄)》
1 事実
(1)事案の概要
本件は、原処分庁が、国税徴収法(以下「徴収法」という。)第24条《譲渡担保権者の物的納税責任》の規定に基づいて、審査請求人(以下「請求人」という。)の譲渡担保財産となっている債権の差押処分をしたのに対し、請求人が、当該債権は国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となったものであるから、同条第6項により当該債権から滞納国税を徴収することができず、上記差押処分は違法であるとして、その全部の取消しを求めるものである。
(2)審査請求に至る経緯
イ 原処分庁は、株式会社A(以下「A社」という。)に係る別表記載の滞納国税(以下「本件滞納国税」という。)を徴収するため、平成10年4月10日付の「譲渡担保権者に対する告知書」を請求人に送達して、譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知をし、平成13年11月22日付の差押通知書を請求人に送達して、請求人の譲渡担保財産である別紙供託目録記載の各供託金についての還付請求権(以下「本件債権」という。)を差し押さえた(以下、この差押処分を「本件差押処分」という。)。
ロ 請求人は、本件差押処分に不服があるとして、平成14年1月22日に審査請求をした。
ハ なお、請求人は、平成14年9月1日に商号を株式会社Bから株式会社Cに変更した。
(3)関係法令等
徴収法第24条は、譲渡担保権者の物的納税責任について、要旨次のとおり規定している。
(第1項)納税者が国税を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となっている譲渡担保財産があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者の国税を徴収することができる。
(第2項)税務署長は、前項の規定により徴収しようとするときは、譲渡担保権者に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。
(第3項)前項の告知書を発した日から10日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴収職員は、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分を執行することができる。
(第6項)第1項の規定は、国税の法定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は譲渡担保権者が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている事実を、その財産の売却決定の前日までに、証明した場合は、適用しない。
(4)基礎事実
以下の事実は、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる。
イ A社は、請求人との間で、平成9年3月31日、株式会社D(以下「D社」という。)が請求人に対して負担する一切の債務の担保として、次の内容の債権(以下「本件担保目的債権」という。)を請求人に譲渡する旨の債権譲渡担保設定契約(以下「本件契約」という。)を締結した。
(イ)債権者 A社
(ロ)債務者 株式会社E(以下「E社」という。)
(ハ)債 権 債権者が債務者との間の継続的取引契約に基づき、〔1〕平成9年3月31日現在有する商品売掛代金債権及び商品販売受託手数料債権、〔2〕同日から1年の間に取得する商品売掛代金債権及び商品販売受託手数料債権
ロ A社は、E社に対し、平成9年6月4日、確定日付のある内容証明郵便をもって、債権譲渡担保設定通知をし、同通知は同月5日にE社に到達した。
ハ 平成10年3月25日、A社が手形不渡りを出したことにより、D社は請求人に対する債務の期限の利益を喪失し、本件契約において定める担保権実行の事由が発生した。請求人は、E社に対し、同月31日、書面をもって本件契約について譲渡担保権実行の通知をした。
ニ 原処分庁は、平成10年4月3日付及び同月6日付の差押通知書をE社に送達して、同年3月11日から同月20日まで及び同月21日から同月30日までの商品売掛代金債権及び商品販売受託手数料債権(以下「本件商品売掛代金債権等」という。)について、A社に対する滞納処分による差押えをした。
ホ E社は、平成10年5月26日、本件商品売掛代金債権等について、債権者を確知することができないことを理由に、別紙供託目録記載のとおり、被供託者をA社又は請求人とする供託をした。
ヘ 請求人と原処分庁の間には、最高裁判所平成13年○月○日第一小法廷判決(平成○年(○)第○○号供託金還付請求権確認請求事件、以下「平成13年最高裁判決」という。)があり、同判決は、請求人と原処分庁との間において、請求人が本件債権を有することを確認している。
2 主張
(1)請求人
イ 原処分は、徴収法第24条に基づいて、請求人の譲渡担保財産となっている本件債権を差し押さえたものであるが、本件債権は、以下のとおり、法定納期限等以前に譲渡担保財産となったものであり、その事実を証明しているから、同条第6項により同条第1項を適用することができないのであって、本件差押処分は違法であり、その全部の取消しを求める。
ロ 徴収法第24条第6項の解釈
(イ)徴収法は、私法上の権利の公示の原則と租税確定の効果とを両立させることによって、私法秩序の尊重と租税徴収の確保との調整を図ろうとしており、私法上の担保権と租税債権との調整についても、同法第15条《法定納期限等以前に設定された質権の優先》及び同法第16条《法定納期限等以前に設定された抵当権の優先》等において、担保権の対抗要件を具備した時と国税の法定納期限等の先後によって調整を図っている。このことからすれば、譲渡担保権と租税債権との調整規定である同法第24条第6項も、譲渡担保権の対抗要件を具備した時と国税の法定納期限等との先後をもって譲渡担保権と租税債権との調整を図った規定と解すべきである。
これを本件についてみると、請求人は、法定納期限等以前に、本件担保目的債権を目的とする譲渡担保権の対抗要件を具備しているから、本件債権は、国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となったものである。
(ロ)ところで、原処分庁が主張するような差押禁止財産創出の懸念については、最高裁判所平成11年1月29日第三小法廷判決(平成9年(オ)第219号供託金還付請求権確認請求事件、以下「平成11年最高裁判決」という。)において判示されたとおり、他の債権者と均衡を著しく失するなどの事情がある場合には、将来債権の譲渡担保契約自体の有効性を否定するなど、公序良俗違反の妥当性によって判断されるべきものである。
(ハ)また、原処分庁は、徴収法第24条第6項が差押禁止財産創出の問題についての調整機能を果たす規定である旨主張するが、同項は、将来債権譲渡をめぐる議論が未成熟であった時代に置かれた規定であり、差押禁止財産創出の問題について、その調整機能を持たされたものとは到底解し得ない。確かに、立法論としては、譲渡担保設定者の精算金請求権(これに類するもの)の発生根拠規定及び譲渡担保権者の被担保債権制限規定が必要であると考えられるものの、これらは、譲渡担保対象財産を将来債権の場合に限って制限することで代置できるものではない。
ハ 将来債権を譲渡した場合における債権の移転時期
(イ)将来債権を譲渡した場合、債権の移転の効力は、譲渡契約を締結した時に生じるのであって、債権が現実に発生した時ではないと解すべきである。
かかる解釈は、平成11年最高裁判決において、将来債権を譲渡した場合、債権の発生以前に具備された対抗要件を有効とし、同判決が、債権の発生以前に権利変動が既に生じていることを前提としていると解されることや、平成13年最高裁判決において、いわゆる集合債権を対象とした譲渡担保契約を締結した場合、「既に生じ、又は将来生ずべき債権は、甲から乙に確定的に譲渡されており」と判示し、同判決が、集合債権に含まれる将来債権について、譲渡契約を締結した時に、債権の移転の効力が生じると明示していることにも合致する。
そうすると、将来債権を対象として譲渡担保契約を締結した場合においても、債権が譲渡担保権者に移転して譲渡担保財産となる時期は、譲渡担保契約を締結した時であると解すべきである。
(ロ)これを本件についてみると、譲渡担保契約を締結した時に、本件担保目的債権が移転して譲渡担保財産となっており、それは法定納期限等以前であるから、本件債権は、国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となったものである。
(2)原処分庁
イ 原処分は、A社に係る本件滞納国税を徴収するため、徴収法第24条に基づいて、請求人の譲渡担保財産である本件債権を差し押さえたもので適法であるから、本件審査請求を棄却するとの裁決を求める。
ところで、請求人は、本件債権が法定納期限等以前に譲渡担保財産となったものであり、その事実を証明しているから、徴収法第24条第6項により同条第1項を適用することができないのであって、本件差押処分が違法である旨主張するところ、以下の理由から、本件の場合に同条第6項を適用することはできない。
ロ 徴収法第24条第6項の解釈
(イ)徴収法は、質権ないし抵当権等の担保権者が予測できない国税の発生によって不当にその利益を侵害されることを防止する措置を講ずることを前提に、すべての担保制度が租税の徴収面からはできる限り同一の取扱いを受けることが望ましいとの観点に立って、同法第24条第6項を規定したものである。そして、質権によって担保される債権と国税との調整を定める同法第15条、抵当権によって担保される債権と国税との調整を定める同法第16条が、いずれも現に存在する財産について担保権が設定されている場合を想定し、担保権を設定した時点と国税の法定納期限等との先後により調整していることは明らかであるから、そうであれば、同法第24条第6項も、将来債権について譲渡担保権が設定された場合、債権が現実に発生した時を譲渡担保財産となった時とし、その時点と国税の法定納期限等の先後により、同項が適用できるか否かを定めた規定であると解すべきである。
また、徴収法第24条第6項が、国税の法定納期限等を基準として譲渡担保によって担保される債権と国税の調整を図ったのは、譲渡担保権者が国税債権の存在を知り得ない時期に設定した担保財産についてまで、国税債権が優先することになると、譲渡担保権者が不測の損害を受けることになりかねないからであり、そうすると、集合債権の譲渡担保の場合、予測可能性の保護の観点からは、国税の法定納期限等以前に現実に発生した債権から被担保債権の回収ができるとすれば十分であり、国税の法定納期限等に遅れて発生した債権から被担保債権の回収ができるとするまでの必要はない。よって、徴収法第24条第6項は、集合債権について譲渡担保権が設定された場合、債権が現実に発生した時を譲渡担保財産となった時とし、その時点と国税の法定納期限等の先後により、同項が適用できるか否かを定めた規定であると解すべきである。
(ロ)請求人は、徴収法第24条第6項が、債権譲渡の第三者対抗要件を具備した時点と国税の法定納期限等の先後をもって同項の適用の可否を決しようとする規定である旨主張する。
しかし、仮に請求人の主張のとおりだとすると、相当長期間にわたる将来債権譲渡担保設定契約を締結し、債権譲渡の第三者対抗要件を具備することによって、当該債権から国税を徴収することができなくなるが、これは、実質的に差押禁止財産を創出することにほかならず、国税の引き当てとなる財産が原則として納税者の総財産であることを前提として、国税の一般的優先の原則を定めた徴収法の趣旨を没却することになる。
ハ 将来債権を譲渡した場合における債権の移転時期
(イ)将来債権の譲渡契約とは、将来生ずべき債権が現実に発生した場合に、直ちにこれを譲受人に譲渡する旨の契約であるから、将来債権が譲受人に移転する時期は債権が現実に発生した時であると解される。このことは、大審院昭和9年12月28日判決(以下「昭和9年大審院判決」という。)も同様に解している。とすれば、本件のように、将来債権を対象とした譲渡担保契約を締結した場合においても、債権が譲渡担保権者に移転し譲渡担保財産となる時期は、債権が現実に発生した時と解すべきである。
(ロ)請求人は、将来債権を譲渡した場合、譲渡契約を締結した時に債権が譲受人に移転すると解すべきである旨主張するが、そうすると、現実に債権が発生した時点では、契約当事者以外の間に債権が発生するという不合理を生じる。
また、請求人は、平成11年最高裁判決が、将来債権を譲渡した場合において、債権が現実に発生する以前に具備した対抗要件を有効としていることから、将来債権の移転時期を譲渡契約を締結した時であることを前提とした判決であるとするが、同判決が、債権の発生前に具備した対抗要件を有効としたのは、債権が発生した時に二重譲渡や差押えとの競合も想定されることからにすぎず、将来債権の移転時期については、昭和9年大審院判決と同様、当該債権が現実に発生した時であることを前提としていると解すべきである。
さらに、請求人は、平成13年最高裁判決における、「既に生じ、又は将来生ずべき債権は、甲から乙に確定的に譲渡されており」の部分を引用し、同判決が将来債権の移転時期について譲渡契約を締結した時であると判示したものであるとするが、「確定的に譲渡され」というのは、その後何らの行為を要することなく債権が移転することを判示したにすぎず、将来債権の移転時期については、昭和9年大審院判決と同様、債権が現実に発生した時であることを前提としていると解すべきである。
ニ 以上のことからすれば、本件の場合、将来債権である本件担保目的債権が現実に発生した時は、いずれも法定納期限等より後であるから、本件債権は、国税の法定納期限等後に譲渡担保財産となったものであり、徴収法第24条第6項を適用することはできない。
3 判断
本件の争点は、徴収法第24条第6項の適用の可否、すなわち、本件差押処分の対象とされた本件債権が、法定納期限等以前に請求人の譲渡担保財産となっていたか否かであるので、審理したところ、次のとおりである。
(1)徴収法第24条第6項の解釈
イ 徴収法第24条第6項は、租税債権と譲渡担保の被担保債権との優先劣後について、国税の法定納期限等と「譲渡担保財産となっ」た時との先後により判定することで国税と譲渡担保権との調整を図った規定であるところ、かかる規定は、いわゆる予測可能性の理論、すなわち担保権を設定するときに、国税があることを知りながら設定したときは国税に劣後することが妥当ということを出発点とし、現実に知っているということではなく、知り得る状態にあるときで国税との優先劣後を判定するという考え方に基づくものと解される。そうであるなら、租税債権と譲渡担保の被担保債権との優劣を判定する徴収法第24条第6項の「譲渡担保財産となっ」た時の解釈においても、予測可能性の理論に基づいて解釈すべきである。
本件契約は、いわゆる集合債権を対象とした譲渡担保契約といわれるものの一つと解されるところ、集合債権に含まれる将来債権については、将来生ずべき債権であることから、当該債権が現実に発生する前に租税債権が発生し、当該債権が国税の徴収の対象となる可能性があり、集合債権に譲渡担保権を設定する者はそれを設定するときにそのことを知り得るのであるから、国税の法定納期限等の後に発生した債権について譲渡担保権より国税を優先させて国税の徴収の対象としても、譲渡担保権者が不測の損害を被ったとはいえないものと解される。
とすれば、集合債権に対して譲渡担保権を設定した場合において、徴収法第24条第6項の「譲渡担保財産となっ」た時とは、担保の目的となっている将来債権が現実に発生した時と解すべきである。
ロ ところで、請求人は、徴収法が同法第15条以下において、被担保債権の対抗要件の具備時を基準として国税と被担保債権の対抗要件との調整を図っていることからすると、同法第24条第6項においても、国税の法定納期限等と譲渡担保の対抗要件との先後をもって租税債権と私債権との調整を図った規定であると解すべきである旨主張する。
しかしながら、仮に、請求人の主張のとおり解すると、長期間にわたる将来債権譲渡担保設定契約を締結し、債権譲渡の第三者対抗要件を具備することによって、当該債権から国税を徴収することができなくなり、これでは、実質的に差押禁止財産を創出することにほかならず、国税が強制換価手続において他の債権と競合する場合には、国税は他の債権に優先して徴収することができるという国税の優先の原則を定めた徴収法の趣旨を没却することになる。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(2)将来債権を譲渡した場合における債権の移転時期
また、集合債権に譲渡担保権を設定した場合において、徴収法第24条第6項の「譲渡担保財産となっ」た時を、担保目的となっている将来債権が現実に発生した時と解すべきであることは、次に述べるとおり、将来債権を譲渡した場合における債権の移転時期の解釈とも矛盾しない。
イ 将来債権は、将来の時期に発生するものであり、現在、存在しないものであるから、将来債権を譲渡する契約が結ばれたとしても、当該債権は当該契約と共に移転することはできない。したがって、将来債権の譲渡契約は、将来、債権が現実に発生したときに、その権利を直ちに取得できるという一種の期待権を譲受人に取得せしめることを目的とするものであると解するのが合理的である。よって、譲渡の目的たる将来債権は、それが現実に発生した時に債権者から譲受人に移転すると解される。
このことは、昭和9年大審院判決において「将来ノ債権ニ付テモ譲渡契約ハ有効ニ之ヲ為シ得ヘク此ノ場合ハ後日債権カ譲渡人ニ付成立シタルトキ何等ノ行為ヲ要セスシテ譲受人ニ移転スルモノトス」旨判示していることとも合致する。
したがって、将来債権を譲渡した場合の債権の移転時期を、債権が現実に発生した時と解せば、将来債権を含む集合債権を譲渡担保した場合に債権が移転し「譲渡担保財産となっ」た時についても、債権が現実に発生した時と解される。
ロ これに対して、請求人は、平成11年最高裁判決が将来債権の移転時期は譲渡契約を締結した時とすることを前提としている旨主張するが、同判決は、将来債権を譲渡した場合、債権が具体的に発生する以前に具備された対抗要件を有効と判示したものにすぎず、将来債権の移転時期については明示しておらず、その点については、昭和9年大審院判決を踏襲したものと解され、よって、請求人の主張は採用できない。
また、請求人は、平成13年最高裁判決において、「既に生じ、又は将来生ずべき債権は、甲から乙に確定的に譲渡されており」と判示したことをもって、同判決が将来債権の移転時期について譲渡契約を締結した時と判示したものというが、これは、その後何等の行為を要せずして移転することを明示したにすぎず、将来債権の移転時期については明示しておらず、その点については、昭和9年大審院判決を踏襲としたものと解される。よって、かかる請求人の主張も採用できない。
(3)結論
以上のとおり、集合債権に対して譲渡担保権を設定した場合において、徴収法第24条第6項の「譲渡担保財産となっ」た時とは、担保目的となっている将来債権が現実に発生した時と解すべきであるから、本件の場合に、本件債権が譲渡担保財産となった時は、本件担保目的債権が現実に発生した時であり、いずれも法定納期限等より後であるから、徴収法第24条第6項は適用できない。
(4)本件差押処分の適法性に関するその他の要件
本件差押処分の適法性に関するその他の要件の充足については、請求人及び原処分庁との間に争いがなく、当審判所の調査によってもその事実が認められる。
したがって、本件差押処分は適法である。
(5)その他
原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。
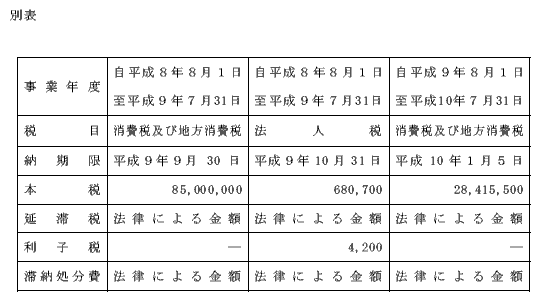
別紙 供託目録
1 供託所 F地方法務局G支局
供託年月日 平成10年5月26日
供託番号 平成10年度金第○○号
供託金額 138,343,792円
供託者 株式会社E
被供託者 株式会社A又は審査請求人
2 供託所 F地方法務局G支局
供託年月日 平成10年5月26日
供託番号 平成10年度金第○○号
供託金額 143,783,031円
供託者 株式会社E
被供託者 株式会社A又は審査請求人
《裁決書(抄)》
1 事実
(1)事案の概要
本件は、原処分庁が、国税徴収法(以下「徴収法」という。)第24条《譲渡担保権者の物的納税責任》の規定に基づいて、審査請求人(以下「請求人」という。)の譲渡担保財産となっている債権の差押処分をしたのに対し、請求人が、当該債権は国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となったものであるから、同条第6項により当該債権から滞納国税を徴収することができず、上記差押処分は違法であるとして、その全部の取消しを求めるものである。
(2)審査請求に至る経緯
イ 原処分庁は、株式会社A(以下「A社」という。)に係る別表記載の滞納国税(以下「本件滞納国税」という。)を徴収するため、平成10年4月10日付の「譲渡担保権者に対する告知書」を請求人に送達して、譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知をし、平成13年11月22日付の差押通知書を請求人に送達して、請求人の譲渡担保財産である別紙供託目録記載の各供託金についての還付請求権(以下「本件債権」という。)を差し押さえた(以下、この差押処分を「本件差押処分」という。)。
ロ 請求人は、本件差押処分に不服があるとして、平成14年1月22日に審査請求をした。
ハ なお、請求人は、平成14年9月1日に商号を株式会社Bから株式会社Cに変更した。
(3)関係法令等
徴収法第24条は、譲渡担保権者の物的納税責任について、要旨次のとおり規定している。
(第1項)納税者が国税を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となっている譲渡担保財産があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者の国税を徴収することができる。
(第2項)税務署長は、前項の規定により徴収しようとするときは、譲渡担保権者に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。
(第3項)前項の告知書を発した日から10日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴収職員は、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分を執行することができる。
(第6項)第1項の規定は、国税の法定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は譲渡担保権者が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている事実を、その財産の売却決定の前日までに、証明した場合は、適用しない。
(4)基礎事実
以下の事実は、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる。
イ A社は、請求人との間で、平成9年3月31日、株式会社D(以下「D社」という。)が請求人に対して負担する一切の債務の担保として、次の内容の債権(以下「本件担保目的債権」という。)を請求人に譲渡する旨の債権譲渡担保設定契約(以下「本件契約」という。)を締結した。
(イ)債権者 A社
(ロ)債務者 株式会社E(以下「E社」という。)
(ハ)債 権 債権者が債務者との間の継続的取引契約に基づき、〔1〕平成9年3月31日現在有する商品売掛代金債権及び商品販売受託手数料債権、〔2〕同日から1年の間に取得する商品売掛代金債権及び商品販売受託手数料債権
ロ A社は、E社に対し、平成9年6月4日、確定日付のある内容証明郵便をもって、債権譲渡担保設定通知をし、同通知は同月5日にE社に到達した。
ハ 平成10年3月25日、A社が手形不渡りを出したことにより、D社は請求人に対する債務の期限の利益を喪失し、本件契約において定める担保権実行の事由が発生した。請求人は、E社に対し、同月31日、書面をもって本件契約について譲渡担保権実行の通知をした。
ニ 原処分庁は、平成10年4月3日付及び同月6日付の差押通知書をE社に送達して、同年3月11日から同月20日まで及び同月21日から同月30日までの商品売掛代金債権及び商品販売受託手数料債権(以下「本件商品売掛代金債権等」という。)について、A社に対する滞納処分による差押えをした。
ホ E社は、平成10年5月26日、本件商品売掛代金債権等について、債権者を確知することができないことを理由に、別紙供託目録記載のとおり、被供託者をA社又は請求人とする供託をした。
ヘ 請求人と原処分庁の間には、最高裁判所平成13年○月○日第一小法廷判決(平成○年(○)第○○号供託金還付請求権確認請求事件、以下「平成13年最高裁判決」という。)があり、同判決は、請求人と原処分庁との間において、請求人が本件債権を有することを確認している。
2 主張
(1)請求人
イ 原処分は、徴収法第24条に基づいて、請求人の譲渡担保財産となっている本件債権を差し押さえたものであるが、本件債権は、以下のとおり、法定納期限等以前に譲渡担保財産となったものであり、その事実を証明しているから、同条第6項により同条第1項を適用することができないのであって、本件差押処分は違法であり、その全部の取消しを求める。
ロ 徴収法第24条第6項の解釈
(イ)徴収法は、私法上の権利の公示の原則と租税確定の効果とを両立させることによって、私法秩序の尊重と租税徴収の確保との調整を図ろうとしており、私法上の担保権と租税債権との調整についても、同法第15条《法定納期限等以前に設定された質権の優先》及び同法第16条《法定納期限等以前に設定された抵当権の優先》等において、担保権の対抗要件を具備した時と国税の法定納期限等の先後によって調整を図っている。このことからすれば、譲渡担保権と租税債権との調整規定である同法第24条第6項も、譲渡担保権の対抗要件を具備した時と国税の法定納期限等との先後をもって譲渡担保権と租税債権との調整を図った規定と解すべきである。
これを本件についてみると、請求人は、法定納期限等以前に、本件担保目的債権を目的とする譲渡担保権の対抗要件を具備しているから、本件債権は、国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となったものである。
(ロ)ところで、原処分庁が主張するような差押禁止財産創出の懸念については、最高裁判所平成11年1月29日第三小法廷判決(平成9年(オ)第219号供託金還付請求権確認請求事件、以下「平成11年最高裁判決」という。)において判示されたとおり、他の債権者と均衡を著しく失するなどの事情がある場合には、将来債権の譲渡担保契約自体の有効性を否定するなど、公序良俗違反の妥当性によって判断されるべきものである。
(ハ)また、原処分庁は、徴収法第24条第6項が差押禁止財産創出の問題についての調整機能を果たす規定である旨主張するが、同項は、将来債権譲渡をめぐる議論が未成熟であった時代に置かれた規定であり、差押禁止財産創出の問題について、その調整機能を持たされたものとは到底解し得ない。確かに、立法論としては、譲渡担保設定者の精算金請求権(これに類するもの)の発生根拠規定及び譲渡担保権者の被担保債権制限規定が必要であると考えられるものの、これらは、譲渡担保対象財産を将来債権の場合に限って制限することで代置できるものではない。
ハ 将来債権を譲渡した場合における債権の移転時期
(イ)将来債権を譲渡した場合、債権の移転の効力は、譲渡契約を締結した時に生じるのであって、債権が現実に発生した時ではないと解すべきである。
かかる解釈は、平成11年最高裁判決において、将来債権を譲渡した場合、債権の発生以前に具備された対抗要件を有効とし、同判決が、債権の発生以前に権利変動が既に生じていることを前提としていると解されることや、平成13年最高裁判決において、いわゆる集合債権を対象とした譲渡担保契約を締結した場合、「既に生じ、又は将来生ずべき債権は、甲から乙に確定的に譲渡されており」と判示し、同判決が、集合債権に含まれる将来債権について、譲渡契約を締結した時に、債権の移転の効力が生じると明示していることにも合致する。
そうすると、将来債権を対象として譲渡担保契約を締結した場合においても、債権が譲渡担保権者に移転して譲渡担保財産となる時期は、譲渡担保契約を締結した時であると解すべきである。
(ロ)これを本件についてみると、譲渡担保契約を締結した時に、本件担保目的債権が移転して譲渡担保財産となっており、それは法定納期限等以前であるから、本件債権は、国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となったものである。
(2)原処分庁
イ 原処分は、A社に係る本件滞納国税を徴収するため、徴収法第24条に基づいて、請求人の譲渡担保財産である本件債権を差し押さえたもので適法であるから、本件審査請求を棄却するとの裁決を求める。
ところで、請求人は、本件債権が法定納期限等以前に譲渡担保財産となったものであり、その事実を証明しているから、徴収法第24条第6項により同条第1項を適用することができないのであって、本件差押処分が違法である旨主張するところ、以下の理由から、本件の場合に同条第6項を適用することはできない。
ロ 徴収法第24条第6項の解釈
(イ)徴収法は、質権ないし抵当権等の担保権者が予測できない国税の発生によって不当にその利益を侵害されることを防止する措置を講ずることを前提に、すべての担保制度が租税の徴収面からはできる限り同一の取扱いを受けることが望ましいとの観点に立って、同法第24条第6項を規定したものである。そして、質権によって担保される債権と国税との調整を定める同法第15条、抵当権によって担保される債権と国税との調整を定める同法第16条が、いずれも現に存在する財産について担保権が設定されている場合を想定し、担保権を設定した時点と国税の法定納期限等との先後により調整していることは明らかであるから、そうであれば、同法第24条第6項も、将来債権について譲渡担保権が設定された場合、債権が現実に発生した時を譲渡担保財産となった時とし、その時点と国税の法定納期限等の先後により、同項が適用できるか否かを定めた規定であると解すべきである。
また、徴収法第24条第6項が、国税の法定納期限等を基準として譲渡担保によって担保される債権と国税の調整を図ったのは、譲渡担保権者が国税債権の存在を知り得ない時期に設定した担保財産についてまで、国税債権が優先することになると、譲渡担保権者が不測の損害を受けることになりかねないからであり、そうすると、集合債権の譲渡担保の場合、予測可能性の保護の観点からは、国税の法定納期限等以前に現実に発生した債権から被担保債権の回収ができるとすれば十分であり、国税の法定納期限等に遅れて発生した債権から被担保債権の回収ができるとするまでの必要はない。よって、徴収法第24条第6項は、集合債権について譲渡担保権が設定された場合、債権が現実に発生した時を譲渡担保財産となった時とし、その時点と国税の法定納期限等の先後により、同項が適用できるか否かを定めた規定であると解すべきである。
(ロ)請求人は、徴収法第24条第6項が、債権譲渡の第三者対抗要件を具備した時点と国税の法定納期限等の先後をもって同項の適用の可否を決しようとする規定である旨主張する。
しかし、仮に請求人の主張のとおりだとすると、相当長期間にわたる将来債権譲渡担保設定契約を締結し、債権譲渡の第三者対抗要件を具備することによって、当該債権から国税を徴収することができなくなるが、これは、実質的に差押禁止財産を創出することにほかならず、国税の引き当てとなる財産が原則として納税者の総財産であることを前提として、国税の一般的優先の原則を定めた徴収法の趣旨を没却することになる。
ハ 将来債権を譲渡した場合における債権の移転時期
(イ)将来債権の譲渡契約とは、将来生ずべき債権が現実に発生した場合に、直ちにこれを譲受人に譲渡する旨の契約であるから、将来債権が譲受人に移転する時期は債権が現実に発生した時であると解される。このことは、大審院昭和9年12月28日判決(以下「昭和9年大審院判決」という。)も同様に解している。とすれば、本件のように、将来債権を対象とした譲渡担保契約を締結した場合においても、債権が譲渡担保権者に移転し譲渡担保財産となる時期は、債権が現実に発生した時と解すべきである。
(ロ)請求人は、将来債権を譲渡した場合、譲渡契約を締結した時に債権が譲受人に移転すると解すべきである旨主張するが、そうすると、現実に債権が発生した時点では、契約当事者以外の間に債権が発生するという不合理を生じる。
また、請求人は、平成11年最高裁判決が、将来債権を譲渡した場合において、債権が現実に発生する以前に具備した対抗要件を有効としていることから、将来債権の移転時期を譲渡契約を締結した時であることを前提とした判決であるとするが、同判決が、債権の発生前に具備した対抗要件を有効としたのは、債権が発生した時に二重譲渡や差押えとの競合も想定されることからにすぎず、将来債権の移転時期については、昭和9年大審院判決と同様、当該債権が現実に発生した時であることを前提としていると解すべきである。
さらに、請求人は、平成13年最高裁判決における、「既に生じ、又は将来生ずべき債権は、甲から乙に確定的に譲渡されており」の部分を引用し、同判決が将来債権の移転時期について譲渡契約を締結した時であると判示したものであるとするが、「確定的に譲渡され」というのは、その後何らの行為を要することなく債権が移転することを判示したにすぎず、将来債権の移転時期については、昭和9年大審院判決と同様、債権が現実に発生した時であることを前提としていると解すべきである。
ニ 以上のことからすれば、本件の場合、将来債権である本件担保目的債権が現実に発生した時は、いずれも法定納期限等より後であるから、本件債権は、国税の法定納期限等後に譲渡担保財産となったものであり、徴収法第24条第6項を適用することはできない。
3 判断
本件の争点は、徴収法第24条第6項の適用の可否、すなわち、本件差押処分の対象とされた本件債権が、法定納期限等以前に請求人の譲渡担保財産となっていたか否かであるので、審理したところ、次のとおりである。
(1)徴収法第24条第6項の解釈
イ 徴収法第24条第6項は、租税債権と譲渡担保の被担保債権との優先劣後について、国税の法定納期限等と「譲渡担保財産となっ」た時との先後により判定することで国税と譲渡担保権との調整を図った規定であるところ、かかる規定は、いわゆる予測可能性の理論、すなわち担保権を設定するときに、国税があることを知りながら設定したときは国税に劣後することが妥当ということを出発点とし、現実に知っているということではなく、知り得る状態にあるときで国税との優先劣後を判定するという考え方に基づくものと解される。そうであるなら、租税債権と譲渡担保の被担保債権との優劣を判定する徴収法第24条第6項の「譲渡担保財産となっ」た時の解釈においても、予測可能性の理論に基づいて解釈すべきである。
本件契約は、いわゆる集合債権を対象とした譲渡担保契約といわれるものの一つと解されるところ、集合債権に含まれる将来債権については、将来生ずべき債権であることから、当該債権が現実に発生する前に租税債権が発生し、当該債権が国税の徴収の対象となる可能性があり、集合債権に譲渡担保権を設定する者はそれを設定するときにそのことを知り得るのであるから、国税の法定納期限等の後に発生した債権について譲渡担保権より国税を優先させて国税の徴収の対象としても、譲渡担保権者が不測の損害を被ったとはいえないものと解される。
とすれば、集合債権に対して譲渡担保権を設定した場合において、徴収法第24条第6項の「譲渡担保財産となっ」た時とは、担保の目的となっている将来債権が現実に発生した時と解すべきである。
ロ ところで、請求人は、徴収法が同法第15条以下において、被担保債権の対抗要件の具備時を基準として国税と被担保債権の対抗要件との調整を図っていることからすると、同法第24条第6項においても、国税の法定納期限等と譲渡担保の対抗要件との先後をもって租税債権と私債権との調整を図った規定であると解すべきである旨主張する。
しかしながら、仮に、請求人の主張のとおり解すると、長期間にわたる将来債権譲渡担保設定契約を締結し、債権譲渡の第三者対抗要件を具備することによって、当該債権から国税を徴収することができなくなり、これでは、実質的に差押禁止財産を創出することにほかならず、国税が強制換価手続において他の債権と競合する場合には、国税は他の債権に優先して徴収することができるという国税の優先の原則を定めた徴収法の趣旨を没却することになる。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(2)将来債権を譲渡した場合における債権の移転時期
また、集合債権に譲渡担保権を設定した場合において、徴収法第24条第6項の「譲渡担保財産となっ」た時を、担保目的となっている将来債権が現実に発生した時と解すべきであることは、次に述べるとおり、将来債権を譲渡した場合における債権の移転時期の解釈とも矛盾しない。
イ 将来債権は、将来の時期に発生するものであり、現在、存在しないものであるから、将来債権を譲渡する契約が結ばれたとしても、当該債権は当該契約と共に移転することはできない。したがって、将来債権の譲渡契約は、将来、債権が現実に発生したときに、その権利を直ちに取得できるという一種の期待権を譲受人に取得せしめることを目的とするものであると解するのが合理的である。よって、譲渡の目的たる将来債権は、それが現実に発生した時に債権者から譲受人に移転すると解される。
このことは、昭和9年大審院判決において「将来ノ債権ニ付テモ譲渡契約ハ有効ニ之ヲ為シ得ヘク此ノ場合ハ後日債権カ譲渡人ニ付成立シタルトキ何等ノ行為ヲ要セスシテ譲受人ニ移転スルモノトス」旨判示していることとも合致する。
したがって、将来債権を譲渡した場合の債権の移転時期を、債権が現実に発生した時と解せば、将来債権を含む集合債権を譲渡担保した場合に債権が移転し「譲渡担保財産となっ」た時についても、債権が現実に発生した時と解される。
ロ これに対して、請求人は、平成11年最高裁判決が将来債権の移転時期は譲渡契約を締結した時とすることを前提としている旨主張するが、同判決は、将来債権を譲渡した場合、債権が具体的に発生する以前に具備された対抗要件を有効と判示したものにすぎず、将来債権の移転時期については明示しておらず、その点については、昭和9年大審院判決を踏襲したものと解され、よって、請求人の主張は採用できない。
また、請求人は、平成13年最高裁判決において、「既に生じ、又は将来生ずべき債権は、甲から乙に確定的に譲渡されており」と判示したことをもって、同判決が将来債権の移転時期について譲渡契約を締結した時と判示したものというが、これは、その後何等の行為を要せずして移転することを明示したにすぎず、将来債権の移転時期については明示しておらず、その点については、昭和9年大審院判決を踏襲としたものと解される。よって、かかる請求人の主張も採用できない。
(3)結論
以上のとおり、集合債権に対して譲渡担保権を設定した場合において、徴収法第24条第6項の「譲渡担保財産となっ」た時とは、担保目的となっている将来債権が現実に発生した時と解すべきであるから、本件の場合に、本件債権が譲渡担保財産となった時は、本件担保目的債権が現実に発生した時であり、いずれも法定納期限等より後であるから、徴収法第24条第6項は適用できない。
(4)本件差押処分の適法性に関するその他の要件
本件差押処分の適法性に関するその他の要件の充足については、請求人及び原処分庁との間に争いがなく、当審判所の調査によってもその事実が認められる。
したがって、本件差押処分は適法である。
(5)その他
原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。
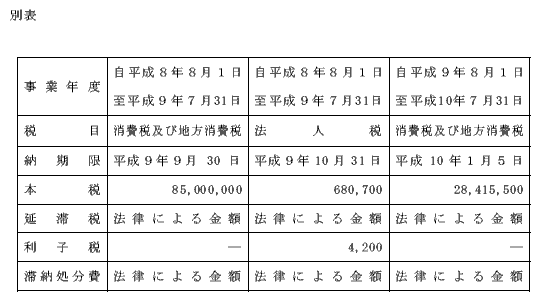
別紙 供託目録
1 供託所 F地方法務局G支局
供託年月日 平成10年5月26日
供託番号 平成10年度金第○○号
供託金額 138,343,792円
供託者 株式会社E
被供託者 株式会社A又は審査請求人
2 供託所 F地方法務局G支局
供託年月日 平成10年5月26日
供託番号 平成10年度金第○○号
供託金額 143,783,031円
供託者 株式会社E
被供託者 株式会社A又は審査請求人
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















