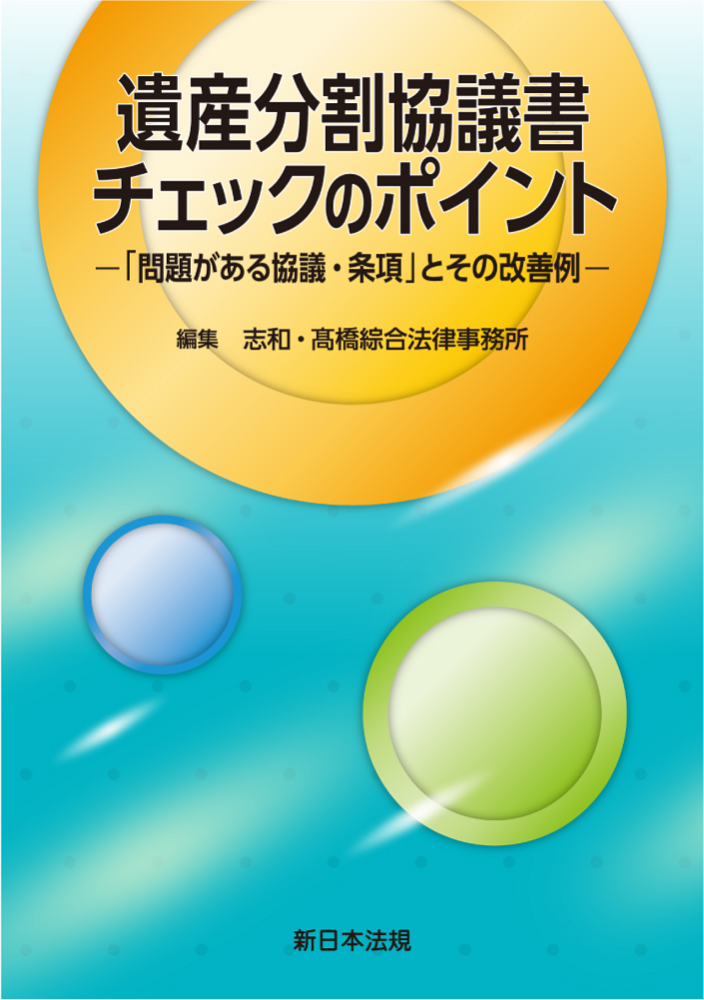資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(消費税)仕入税額控除(課税仕入れの範囲)
(仕入税額控除(課税仕入れの範囲))
1 試作用、サンプル用資材の税額控除
2 株主総会の会場費等の課税関係
3 新株発行費用等
4 損害を被った場合の修理の費用
5 物品切手の購入費用
6 広告宣伝用のテレホンカードの製作費用
7 野球場のシーズン予約席料
8 給与とされた交通費
9 通勤手当、住居手当
10 単身赴任手当等
11 社員の通信教育費を負担するときの仕入税額控除の可否
12 社内提案報償金
13 一時所得となる社内提案報償金
14 大学で行う社員研修の授業料
15 会社が一部負担する外部食堂の食事代金
16 国内における課税売上げがない場合の仕入税額控除
17 質物を流質した場合の課税仕入れに係る支払対価の額
18 共同保険事務に係る経費の配分
19 JV工事に係る請求書等
試作用、サンプル用資材の税額控除
【 照会要旨】
試作目的又はサンプル提供のために無償で引き渡す物品に用いた原材料等についても、仕入税額控除が認められるのでしょうか。
【 回答要旨】
他の者からの仕入れが課税仕入れに該当するものであれば、それが試作目的、サンプル提供等のために無償で引き渡されるものであっても、仕入税額控除の対象となります。
なお、試作品、サンプルが課税資産の譲渡等に係る販売促進等のために配付されるものであるときは、当該原材料等の課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します(基通11-2-14)。
【 関係法令通達】
消費税法第30条第1項、消費税法基本通達11-2-14
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
株主総会の会場費等の課税関係
【 照会要旨】
株主総会のための費用(会場費等)は仕入税額控除の対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
株主総会の費用も課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります。
なお、課税事業と非課税事業を行っている場合には、株主総会の費用は課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当します。
【 関係法令通達】
消費税法第30条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
新株発行費用等
【 照会要旨】
繰延資産とされる新株発行又は社債発行を行う場合の事務委託費等についても、この課税仕入れに係る消費税額は、その支払時に一括して控除することができるのでしょうか。
【 回答要旨】
新株発行又は社債発行を行う場合の事務委託費等も課税仕入れに該当しますから、その課税仕入れを行った日の属する課税期間において仕入税額控除をすることができます(基通11-3-4)。
なお、その者が課税業務と非課税業務を兼業している場合には、これらの課税仕入れに係る消費税額は、課税・非課税共通用となります。
【 関係法令通達】
消費税法第30条第1項、消費税法基本通達11-3-4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
損害を被った場合の修理の費用
【 照会要旨】
事業用資産について被った損害を事業者自身において修理した場合、その修理費用は、仕入税額控除の対象となるのでしょうか。
また、当該損害について修理後に自己の契約している保険会社から保険金が支払われた場合はどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
破損した事業用資産を自己において修理した場合には、その支払った修理の費用については課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります(基通11-2-10)。
なお、その費用について加害者から補償金を受け入れた場合には、その受入れ補償金については課税関係は生じません(基通5-2-5)。損害に係る保険金収入についても同様です(基通5-2-4)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、第30条第1項、消費税法基本通達5-2-4、5-2-5、11-2-10
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
物品切手の購入費用
【 照会要旨】
物品切手の譲渡は非課税とされていますが、物品切手を購入した場合はどのように取り扱われるのでしょうか。
【 回答要旨】
物品切手の譲渡は非課税とされていますので、それを購入した段階では課税仕入れに該当しませんが、物品又は役務の提供の引換給付を受けた時にその引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなります。
ただし、購入した物品切手で自ら引換給付を受けるものについて、継続して購入する日の属する課税期間における課税仕入れとして処理しているときは、この処理は認められます(基通11-3-7)。
【 関係法令通達】
消費税法基本通達11-3-7
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
広告宣伝用のテレホンカードの製作費用
【 照会要旨】
事業者が、広告宣伝用にテレホンカード(本体)を購入した上で、他の事業者に依頼し、広告宣伝用図柄を印刷して製作した場合の次の費用の課税関係はどうなるのでしょうか。 (1) カード(本体)の購入費用
(2) カードに対する広告宣伝用図柄の印刷費用
【 回答要旨】
この場合の課税関係は、次のとおりです。
(1)のカード(本体)の購入費用は、非課税取引に係る仕入れの対価となります。
(2)のカードに対する広告宣伝用図柄の印刷費用は、課税取引に係る仕入れ(課税仕入れ)の対価となります。
なお、既製の図柄入りのテレホンカードを「テレホンカード」として購入する場合には、その購入は非課税取引に該当します。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、第30条第2項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
野球場のシーズン予約席料
【 照会要旨】
当社は3月決算の法人ですが、得意先の接待のためAスタジアムのシーズン予約席(ボックスシート)を確保し、3月中にシーズン予約席料を支払うことにしています。このシーズン予約席料は、仕入税額控除の対象となるのでしょうか。
また、仕入税額控除の対象となる場合、いつの課税期間において仕入税額控除を行うことになるのでしょうか。
【 回答要旨】
野球場のシーズン予約席料は、主催者と予約者の間の契約に基づくシーズン中における野球観戦を目的とした席料であるとともに、野球を観戦させるという役務の提供の対価と考えられますから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象となります。
なお、シーズン予約者には試合ごとの入場券が交付されますが、この入場券はシーズン予約者であることを証する一種の整理券と考えるのが妥当であり物品切手には該当しません。
また、課税仕入れの時期は、現実に役務の提供を受ける日つまり観戦をする日ですが、交際費等の算入時期(中途解約はできないものであるから、接待等のあった日として交際費等に直接関連する行為のあった開幕日)に課税仕入れがあったとしても差し支えありません。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、消費税法基本通達11-3-7
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
給与とされた交通費
【 照会要旨】
税務上、出張旅費のうち、その旅行について通常必要と認められる範囲を超える金額は、所得税では従業員に対する給与として課税されることとなっていますが、消費税ではどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
出張旅費のうち、その旅行について通常必要と認められる範囲のものは課税仕入れに該当するものとして取り扱います(基通11-2-1)。
しかし、通常必要と認められる範囲を超える部分は、所得税法上給与として課税されることとなり、給与を対価とする役務を受けることは課税仕入れに該当しません(法2①十二)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、消費税法基本通達11-2-1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
通勤手当、住居手当
【 照会要旨】
従業員に対する通勤手当、住居手当等は課税仕入れに該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
1 事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れに該当するものとして取り扱います(基通11-2-2)。
2 住居手当については、事業者の事業遂行上直接必要なものとはいえず、その所得の種類も給与等に該当することから、課税仕入れには該当しません。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、消費税法基本通達11-2-2
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
単身赴任手当等
【 照会要旨】
従業員等のうち単身赴任をしている者に対して支給する単身赴任手当等について、次のように支給する場合の金銭はそれぞれ仕入税額控除の対象となるのでしょうか。 (1) 単身赴任者に対し単身赴任手当として毎月一定額を支給する場合
(2) 単身赴任者が、帰宅するための旅費として月又は年を単位として支給する場合
【 回答要旨】
いずれの場合も仕入税額控除の対象とはなりません。 ( 理由)
(1) 単身赴任者に対し単身赴任手当として毎月一定額を支給する場合
単身赴任手当は、家族と離れて生活することに伴い、そうでない勤務者に比し生活費等の負担が大きくなることに配意して、当該単身赴任者に対する給与等の補填として支給されるものと考えられ、所得税においても非課税所得に該当せず、給与所得として支払者においてこれに対する所得税額を源泉徴収すべきものとされています。
したがって、当該事業者における単身赴任手当の支払は、給与等を対価とする役務の提供に対する支払であることから消費税の課税仕入れに係る支払対価には該当しません(法2①十二)。
(2) 単身赴任者が、帰宅するための旅費として月又は年を単位として支給する場合
消費税における出張旅費、宿泊費、日当は、その事業者が事業遂行のために必要な費用を旅行をした者を通じて支出しているものと認識し、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱われているところです(基通11-2-1)。
これに対し、質問の単身赴任者に支給される旅費は、職務の遂行に必要な旅行の費用として支給されるものとは認められず、また、その旅費は給与に該当するものであることからすると、(1)の単身赴任手当と同様の性格のものと考えられますから、これを支払う事業者においては課税仕入れに係る支払対価に該当しません。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、消費税法基本通達11-2-1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
社員の通信教育費を負担するときの仕入税額控除の可否
【 照会要旨】
当社は、社員に対して業務に必要な知識、技能等を習得させるために通信教育を受講するよう奨励しており、受講した通信教育を終了したときにはその費用の半分を負担しています。この場合、当社が負担した費用の額については、仕入税額控除の対象とすることができるのでしょうか。
【 回答要旨】
会社において通信教育の申込みを行い、通信教育を行っている事業者に対して直接受講料を支払っている場合は、課税仕入れに該当します。
しかし、受講料相当額を従業員に対して現金で支給する場合、その額は給与の一部であるから、課税仕入れには該当しないこととなります。
ただし、その通信教育の受講が会社の業務上の必要性に基づくものであるということを前提として、会社がその受講料の支払に係る領収証(当該企業宛)を徴した分については、会社が支出した費用が通信教育の受講料としてのものであることは明らかであり、また、実質的に会社が直接通信教育を行う事業者に支払う場合と同様であることから、課税仕入れに該当するものとして取り扱われます。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
社内提案報償金
【 照会要旨】
当社では社内提案制度を設けており、業務上有益な発明、考案又は創作をした者が、その発明、考案又は創作に係る特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利を使用者に承継させた場合には、その発明等をした社員に報償金を交付しています。
この報償金は、課税仕入れに該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
質問の社員等に対して交付する報償金のうち、次に掲げる金銭については、課税仕入れに該当します(基通11-2-4)。 (1) 業務上有益な発明、考案又は創作をした使用人等から当該発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権若しくは意匠権を承継したことにより支給するもの
(2) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得した使用人等にこれらの権利に係る実施権の対価として支給するもの
(3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質改良又は経費の節約等に寄与する工夫、考案(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限り、その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合を除く。)をした使用人等に支給するもの
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、消費税法基本通達11-2-4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
一時所得となる社内提案報償金
【 照会要旨】
社内提案報償金で、所基通23~35共-1(使用人等の発明等に係る報償金)に掲げるような報償金のケースのうち報償金が一時所得となるものについては課税仕入れに該当すると考えてよいでしょうか。
【 回答要旨】
所基通23~35共-1(3)~(5)に規定する一時所得とされる報償金は、その支払いについて、法人からの贈与として対価関係が認められないことから、資産の譲渡等の対価には該当せず、課税仕入れとなりません。 ( 理由)
「一時所得とは、雑所得を除く他の所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう(所法34①)。」とされ、法人からの贈与により取得する金品は一時所得に該当するとされています(所基通34-1(5))。
消費税法では、贈与は資産の譲渡等の対価としての性質を有しないことから課税の対象外としています。
したがって、一時所得とされた報償金については、資産の譲渡等の対価に該当しないため、消費税の課税の対象となりません。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
大学で行う社員研修の授業料
【 照会要旨】
社員研修の一環として社員を社外に派遣し、定期的に研修を受けさせていますが、派遣先は大学、大学院、各種学校、研究機関などさまざまです。この場合、当社が派遣先に支払う授業料や受講料などは支払先に関係なく課税仕入れとなるのでしょうか。
【 回答要旨】
会社が社員研修の一環として社員を大学等に派遣する場合において、その会社が支払う授業料や受講料などの取扱いは、それが非課税とされる教育役務の提供の対価に該当するかどうかによって、次のように取り扱われます。 (1) 大学、大学院等(学校教育法第1条に規定する学校)における研修 〇 大学公開講座等の受講
大学等における正規の授業科目ではなく、一般社会人等を対象に一般教養の習得等を目的として開講されるものであり、消費税法別表第一第11号に規定する教育に関する役務の提供とは認められませんから、受講の対価である受講料等は課税の対象となります。したがって、会社が支払う受講料等は課税仕入れとなります。
〇 大学等の授業の聴講
大学等における正規の授業科目について聴講生として授業を受け、その結果、一般には単位を取得することとなっているような大学等における聴講については、消費税法別表第一第11号に規定する教育に関する役務の提供と認められますから、聴講の対価である授業料や聴講料は非課税です。したがって、会社が支払う授業料等は課税仕入れとはなりません。
(2) 外国語学校、ビジネス学校等の各種学校(学校教育法第83条第1項に規定する学校)における研修 〇 修学年限が1年以上で、その1年間の授業時間数が680時間以上であること等消費税法別表第一第11号(基通6-11-1(3)参照)に規定する各種学校における教育の役務提供として非課税とされる要件に該当する場合……会社が支払う授業料等は課税仕入れとはなりません。
〇 その他の場合……授業料は課税の対象となりますから、会社が支払う授業料等は課税仕入れとなります。
(3) 研究機関における研修
大学等に設置された研究機関における研修であっても、その研修が非課税とされている教育として行う役務の提供に該当しない場合の研修料等は課税の対象となります。したがって、会社が支払う授業料等は課税仕入れとなります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、別表第一第11号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
会社が一部負担する外部食堂の食事代金
【 照会要旨】
当社は、他の事業者が経営する食堂を社員食堂として利用しており、当該他の事業者は、当社が社員に交付する社員利用券と引換えに通常の代金から100円引にて社員に食事を提供することとしています。
そして、当該他の事業者は、社員利用券の利用枚数に基づいて計算した金額をまとめて当社宛請求し、当社は、その支払額を福利厚生費として経理しています。
この場合、当社は、その支払額を課税仕入れに係る支払対価として取り扱うことはできるのでしょうか。
【 回答要旨】
課税仕入れに係る支払対価となります。 (注) 照会の場合には、社員に交付する社員利用券が給与課税の対象となるかどうかにかかわらず、課税仕入れとして取り扱って差し支えありません。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国内における課税売上げがない場合の仕入税額控除
【 照会要旨】
A社は、国外における資産の貸付けだけを行うために設立された会社ですが、A社に従業員はおらず、会社の設立、国外における資産の貸付けの実行、その他A社に係る業務の一切をA社の親会社が代行しています。このため、A社は親会社に業務代行手数料を支払っていますが、A社は、資本金を預金していることから、毎期受取利息があります。
このことから、A社の国内での収入は、当該受取利息だけであり、課税売上割合はゼロとなります。
この場合、A社が親会社に支払った業務代行手数料に対する仕入控除税額の計算は、次のいずれによるべきでしょうか。 (1) A社は、国外における資産の貸付けを行うために設立された会社であり、その会社の業務の全てを委託したことにより支払われる対価は、この国外における資産の貸付けのために要する費用であることから、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当し、個別対応方式を採ることにより全額控除できます。
(2) 親会社への委託内容は、国外における資産の貸付けの業務のほかに会社自体の管理業務も含まれているので、支払われる対価は、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れには該当しません。
したがって、国外における資産の貸付けの業務に係るものだけが課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当するものであるが、この部分の金額が区分されていない場合は、課税・非課税共通用の課税仕入れとなり、結果として課税売上割合がゼロとなることから、控除できる税額はないことになります。
【 回答要旨】
照会の(1)によることとなります。 ( 理由)
1 個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合において、課税仕入れが課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当するのは、販売商品の仕入れのように、その課税仕入れが直接課税資産の譲渡等に供されるものに限定されません。例えば、課税売上げのみを行っている会社の自社ビルの建設のための土地造成費、商品券の印刷費は、いずれも課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当することとされています。
したがって、本件のように、資産の貸付けを国外において行うために設立された会社の業務の全てを委託した場合において、当該委託した業務から生ずる収入は、すべて課税資産の譲渡等の対価に該当することから、当該業務代行手数料は、消費税法第30条第2項第1号に規定する「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当します。
2 本件のように、業務の委託の対象となる会社の収入に預金利息があるとしても、その預金に関する業務を特に委託している事実がない場合には、利息収入があることをもって、業務代行手数料が課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れに該当することにはなりません。
3 したがって、当該代行手数料は、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当します。
【 関係法令通達】
消費税法第30条第2項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
質物を流質した場合の課税仕入れに係る支払対価の額
【 照会要旨】
質物が流質した場合には、質屋営業者の課税仕入れとなりますが、その場合の課税仕入れに係る支払対価の額はどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
次のとおりとなります。 1 入質から流質までの期間に対応する利子相当額を未収金として経理している場合……元利金の合計額が課税仕入れに係る支払対価の額となります。
2 1の利子相当額を未収金として経理していない場合……貸付金の元本の額が課税仕入れに係る支払対価の額となります。
なお、流質物の課税仕入れの時期は、流質期限の経過した時となりますが、流質期限を経過しても、それを他へ売却等により処分するまでの間は返還に応じている実情もありますので、便宜上、流質物の他への売却等により処分した時に課税仕入れをしたものとしても差し支えありません。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
共同保険事務に係る経費の配分
【 照会要旨】
共同保険事務に係る経費については幹事会社が一括して支払い、幹事会社と非幹事会社との間で負担分の精算を行っている場合、非幹事会社の仕入れに係る消費税額の控除に係る請求書等は幹事会社が非幹事会社に交付する当該幹事会社の支払いに係るコピーでもよいでしょうか。
【 回答要旨】
共同事業として課税仕入れを行った場合において、幹事会社が課税仕入れの名義人となっていること等の事由により各人の持分に応じて請求書等の交付を受けることができないときには、当該課税仕入れに係る課税資産の譲渡等を行った者が発行した請求書のコピーに、それぞれの配分内容を記載したものをもって各社の仕入れに係る消費税額の控除に係る請求書等としても差し支えありません。
【 関係法令通達】
消費税法第30条第7項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
JV工事に係る請求書等
【 照会要旨】
JV工事においては、資産の譲渡等及び課税仕入れはJVの各構成員が出資金等の割合に応じて行ったことになりますが(基通1-3-1)、課税仕入れに係る請求書等は幹事会社が保管し、各構成員は幹事会社から精算書(各構成員別に工事原価を計算した「完成工事原価報告書」が添付されている。)の交付を受け、これに基づき法人税、消費税の申告を行っています。
この精算書は、消費税法第30条第7項に規定する請求書等に該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
JV工事等の共同事業として、課税仕入れを行った場合に、幹事会社が課税仕入れの名義人となっていること等の事由により各構成員の持分に応じて請求書等の交付を受けることができないときには、課税仕入れに係る課税資産の譲渡等を行った者が発行した請求書等のコピーに各構成員の出資金等の割合に応じた課税仕入れに係る対価の額の配分内容を記載したものを消費税法第30条第7項に規定する請求書等に該当するものとして取り扱うほか、コピーが大量になるとの事情により、前記の方法により難い場合には、幹事会社が課税仕入れに係る請求書等を保存することを条件に、各構成員が参加しているJVを課税仕入れの相手方と擬制し、照会の精算書を同項に規定する請求書等に該当するものとして取り扱うことも差し支えありません。
【 関係法令通達】
消費税法第30条第7項、消費税法基本通達1-3-1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
1 試作用、サンプル用資材の税額控除
2 株主総会の会場費等の課税関係
3 新株発行費用等
4 損害を被った場合の修理の費用
5 物品切手の購入費用
6 広告宣伝用のテレホンカードの製作費用
7 野球場のシーズン予約席料
8 給与とされた交通費
9 通勤手当、住居手当
10 単身赴任手当等
11 社員の通信教育費を負担するときの仕入税額控除の可否
12 社内提案報償金
13 一時所得となる社内提案報償金
14 大学で行う社員研修の授業料
15 会社が一部負担する外部食堂の食事代金
16 国内における課税売上げがない場合の仕入税額控除
17 質物を流質した場合の課税仕入れに係る支払対価の額
18 共同保険事務に係る経費の配分
19 JV工事に係る請求書等
試作用、サンプル用資材の税額控除
【 照会要旨】
試作目的又はサンプル提供のために無償で引き渡す物品に用いた原材料等についても、仕入税額控除が認められるのでしょうか。
【 回答要旨】
他の者からの仕入れが課税仕入れに該当するものであれば、それが試作目的、サンプル提供等のために無償で引き渡されるものであっても、仕入税額控除の対象となります。
なお、試作品、サンプルが課税資産の譲渡等に係る販売促進等のために配付されるものであるときは、当該原材料等の課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します(基通11-2-14)。
【 関係法令通達】
消費税法第30条第1項、消費税法基本通達11-2-14
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
株主総会の会場費等の課税関係
【 照会要旨】
株主総会のための費用(会場費等)は仕入税額控除の対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
株主総会の費用も課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります。
なお、課税事業と非課税事業を行っている場合には、株主総会の費用は課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当します。
【 関係法令通達】
消費税法第30条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
新株発行費用等
【 照会要旨】
繰延資産とされる新株発行又は社債発行を行う場合の事務委託費等についても、この課税仕入れに係る消費税額は、その支払時に一括して控除することができるのでしょうか。
【 回答要旨】
新株発行又は社債発行を行う場合の事務委託費等も課税仕入れに該当しますから、その課税仕入れを行った日の属する課税期間において仕入税額控除をすることができます(基通11-3-4)。
なお、その者が課税業務と非課税業務を兼業している場合には、これらの課税仕入れに係る消費税額は、課税・非課税共通用となります。
【 関係法令通達】
消費税法第30条第1項、消費税法基本通達11-3-4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
損害を被った場合の修理の費用
【 照会要旨】
事業用資産について被った損害を事業者自身において修理した場合、その修理費用は、仕入税額控除の対象となるのでしょうか。
また、当該損害について修理後に自己の契約している保険会社から保険金が支払われた場合はどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
破損した事業用資産を自己において修理した場合には、その支払った修理の費用については課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります(基通11-2-10)。
なお、その費用について加害者から補償金を受け入れた場合には、その受入れ補償金については課税関係は生じません(基通5-2-5)。損害に係る保険金収入についても同様です(基通5-2-4)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、第30条第1項、消費税法基本通達5-2-4、5-2-5、11-2-10
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
物品切手の購入費用
【 照会要旨】
物品切手の譲渡は非課税とされていますが、物品切手を購入した場合はどのように取り扱われるのでしょうか。
【 回答要旨】
物品切手の譲渡は非課税とされていますので、それを購入した段階では課税仕入れに該当しませんが、物品又は役務の提供の引換給付を受けた時にその引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなります。
ただし、購入した物品切手で自ら引換給付を受けるものについて、継続して購入する日の属する課税期間における課税仕入れとして処理しているときは、この処理は認められます(基通11-3-7)。
【 関係法令通達】
消費税法基本通達11-3-7
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
広告宣伝用のテレホンカードの製作費用
【 照会要旨】
事業者が、広告宣伝用にテレホンカード(本体)を購入した上で、他の事業者に依頼し、広告宣伝用図柄を印刷して製作した場合の次の費用の課税関係はどうなるのでしょうか。 (1) カード(本体)の購入費用
(2) カードに対する広告宣伝用図柄の印刷費用
【 回答要旨】
この場合の課税関係は、次のとおりです。
(1)のカード(本体)の購入費用は、非課税取引に係る仕入れの対価となります。
(2)のカードに対する広告宣伝用図柄の印刷費用は、課税取引に係る仕入れ(課税仕入れ)の対価となります。
なお、既製の図柄入りのテレホンカードを「テレホンカード」として購入する場合には、その購入は非課税取引に該当します。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、第30条第2項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
野球場のシーズン予約席料
【 照会要旨】
当社は3月決算の法人ですが、得意先の接待のためAスタジアムのシーズン予約席(ボックスシート)を確保し、3月中にシーズン予約席料を支払うことにしています。このシーズン予約席料は、仕入税額控除の対象となるのでしょうか。
また、仕入税額控除の対象となる場合、いつの課税期間において仕入税額控除を行うことになるのでしょうか。
【 回答要旨】
野球場のシーズン予約席料は、主催者と予約者の間の契約に基づくシーズン中における野球観戦を目的とした席料であるとともに、野球を観戦させるという役務の提供の対価と考えられますから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象となります。
なお、シーズン予約者には試合ごとの入場券が交付されますが、この入場券はシーズン予約者であることを証する一種の整理券と考えるのが妥当であり物品切手には該当しません。
また、課税仕入れの時期は、現実に役務の提供を受ける日つまり観戦をする日ですが、交際費等の算入時期(中途解約はできないものであるから、接待等のあった日として交際費等に直接関連する行為のあった開幕日)に課税仕入れがあったとしても差し支えありません。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、消費税法基本通達11-3-7
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
給与とされた交通費
【 照会要旨】
税務上、出張旅費のうち、その旅行について通常必要と認められる範囲を超える金額は、所得税では従業員に対する給与として課税されることとなっていますが、消費税ではどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
出張旅費のうち、その旅行について通常必要と認められる範囲のものは課税仕入れに該当するものとして取り扱います(基通11-2-1)。
しかし、通常必要と認められる範囲を超える部分は、所得税法上給与として課税されることとなり、給与を対価とする役務を受けることは課税仕入れに該当しません(法2①十二)。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、消費税法基本通達11-2-1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
通勤手当、住居手当
【 照会要旨】
従業員に対する通勤手当、住居手当等は課税仕入れに該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
1 事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れに該当するものとして取り扱います(基通11-2-2)。
2 住居手当については、事業者の事業遂行上直接必要なものとはいえず、その所得の種類も給与等に該当することから、課税仕入れには該当しません。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、消費税法基本通達11-2-2
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
単身赴任手当等
【 照会要旨】
従業員等のうち単身赴任をしている者に対して支給する単身赴任手当等について、次のように支給する場合の金銭はそれぞれ仕入税額控除の対象となるのでしょうか。 (1) 単身赴任者に対し単身赴任手当として毎月一定額を支給する場合
(2) 単身赴任者が、帰宅するための旅費として月又は年を単位として支給する場合
【 回答要旨】
いずれの場合も仕入税額控除の対象とはなりません。 ( 理由)
(1) 単身赴任者に対し単身赴任手当として毎月一定額を支給する場合
単身赴任手当は、家族と離れて生活することに伴い、そうでない勤務者に比し生活費等の負担が大きくなることに配意して、当該単身赴任者に対する給与等の補填として支給されるものと考えられ、所得税においても非課税所得に該当せず、給与所得として支払者においてこれに対する所得税額を源泉徴収すべきものとされています。
したがって、当該事業者における単身赴任手当の支払は、給与等を対価とする役務の提供に対する支払であることから消費税の課税仕入れに係る支払対価には該当しません(法2①十二)。
(2) 単身赴任者が、帰宅するための旅費として月又は年を単位として支給する場合
消費税における出張旅費、宿泊費、日当は、その事業者が事業遂行のために必要な費用を旅行をした者を通じて支出しているものと認識し、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱われているところです(基通11-2-1)。
これに対し、質問の単身赴任者に支給される旅費は、職務の遂行に必要な旅行の費用として支給されるものとは認められず、また、その旅費は給与に該当するものであることからすると、(1)の単身赴任手当と同様の性格のものと考えられますから、これを支払う事業者においては課税仕入れに係る支払対価に該当しません。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、消費税法基本通達11-2-1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
社員の通信教育費を負担するときの仕入税額控除の可否
【 照会要旨】
当社は、社員に対して業務に必要な知識、技能等を習得させるために通信教育を受講するよう奨励しており、受講した通信教育を終了したときにはその費用の半分を負担しています。この場合、当社が負担した費用の額については、仕入税額控除の対象とすることができるのでしょうか。
【 回答要旨】
会社において通信教育の申込みを行い、通信教育を行っている事業者に対して直接受講料を支払っている場合は、課税仕入れに該当します。
しかし、受講料相当額を従業員に対して現金で支給する場合、その額は給与の一部であるから、課税仕入れには該当しないこととなります。
ただし、その通信教育の受講が会社の業務上の必要性に基づくものであるということを前提として、会社がその受講料の支払に係る領収証(当該企業宛)を徴した分については、会社が支出した費用が通信教育の受講料としてのものであることは明らかであり、また、実質的に会社が直接通信教育を行う事業者に支払う場合と同様であることから、課税仕入れに該当するものとして取り扱われます。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
社内提案報償金
【 照会要旨】
当社では社内提案制度を設けており、業務上有益な発明、考案又は創作をした者が、その発明、考案又は創作に係る特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利を使用者に承継させた場合には、その発明等をした社員に報償金を交付しています。
この報償金は、課税仕入れに該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
質問の社員等に対して交付する報償金のうち、次に掲げる金銭については、課税仕入れに該当します(基通11-2-4)。 (1) 業務上有益な発明、考案又は創作をした使用人等から当該発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権若しくは意匠権を承継したことにより支給するもの
(2) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得した使用人等にこれらの権利に係る実施権の対価として支給するもの
(3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質改良又は経費の節約等に寄与する工夫、考案(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限り、その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合を除く。)をした使用人等に支給するもの
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、消費税法基本通達11-2-4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
一時所得となる社内提案報償金
【 照会要旨】
社内提案報償金で、所基通23~35共-1(使用人等の発明等に係る報償金)に掲げるような報償金のケースのうち報償金が一時所得となるものについては課税仕入れに該当すると考えてよいでしょうか。
【 回答要旨】
所基通23~35共-1(3)~(5)に規定する一時所得とされる報償金は、その支払いについて、法人からの贈与として対価関係が認められないことから、資産の譲渡等の対価には該当せず、課税仕入れとなりません。 ( 理由)
「一時所得とは、雑所得を除く他の所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう(所法34①)。」とされ、法人からの贈与により取得する金品は一時所得に該当するとされています(所基通34-1(5))。
消費税法では、贈与は資産の譲渡等の対価としての性質を有しないことから課税の対象外としています。
したがって、一時所得とされた報償金については、資産の譲渡等の対価に該当しないため、消費税の課税の対象となりません。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
大学で行う社員研修の授業料
【 照会要旨】
社員研修の一環として社員を社外に派遣し、定期的に研修を受けさせていますが、派遣先は大学、大学院、各種学校、研究機関などさまざまです。この場合、当社が派遣先に支払う授業料や受講料などは支払先に関係なく課税仕入れとなるのでしょうか。
【 回答要旨】
会社が社員研修の一環として社員を大学等に派遣する場合において、その会社が支払う授業料や受講料などの取扱いは、それが非課税とされる教育役務の提供の対価に該当するかどうかによって、次のように取り扱われます。 (1) 大学、大学院等(学校教育法第1条に規定する学校)における研修 〇 大学公開講座等の受講
大学等における正規の授業科目ではなく、一般社会人等を対象に一般教養の習得等を目的として開講されるものであり、消費税法別表第一第11号に規定する教育に関する役務の提供とは認められませんから、受講の対価である受講料等は課税の対象となります。したがって、会社が支払う受講料等は課税仕入れとなります。
〇 大学等の授業の聴講
大学等における正規の授業科目について聴講生として授業を受け、その結果、一般には単位を取得することとなっているような大学等における聴講については、消費税法別表第一第11号に規定する教育に関する役務の提供と認められますから、聴講の対価である授業料や聴講料は非課税です。したがって、会社が支払う授業料等は課税仕入れとはなりません。
(2) 外国語学校、ビジネス学校等の各種学校(学校教育法第83条第1項に規定する学校)における研修 〇 修学年限が1年以上で、その1年間の授業時間数が680時間以上であること等消費税法別表第一第11号(基通6-11-1(3)参照)に規定する各種学校における教育の役務提供として非課税とされる要件に該当する場合……会社が支払う授業料等は課税仕入れとはなりません。
〇 その他の場合……授業料は課税の対象となりますから、会社が支払う授業料等は課税仕入れとなります。
(3) 研究機関における研修
大学等に設置された研究機関における研修であっても、その研修が非課税とされている教育として行う役務の提供に該当しない場合の研修料等は課税の対象となります。したがって、会社が支払う授業料等は課税仕入れとなります。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号、別表第一第11号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
会社が一部負担する外部食堂の食事代金
【 照会要旨】
当社は、他の事業者が経営する食堂を社員食堂として利用しており、当該他の事業者は、当社が社員に交付する社員利用券と引換えに通常の代金から100円引にて社員に食事を提供することとしています。
そして、当該他の事業者は、社員利用券の利用枚数に基づいて計算した金額をまとめて当社宛請求し、当社は、その支払額を福利厚生費として経理しています。
この場合、当社は、その支払額を課税仕入れに係る支払対価として取り扱うことはできるのでしょうか。
【 回答要旨】
課税仕入れに係る支払対価となります。 (注) 照会の場合には、社員に交付する社員利用券が給与課税の対象となるかどうかにかかわらず、課税仕入れとして取り扱って差し支えありません。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国内における課税売上げがない場合の仕入税額控除
【 照会要旨】
A社は、国外における資産の貸付けだけを行うために設立された会社ですが、A社に従業員はおらず、会社の設立、国外における資産の貸付けの実行、その他A社に係る業務の一切をA社の親会社が代行しています。このため、A社は親会社に業務代行手数料を支払っていますが、A社は、資本金を預金していることから、毎期受取利息があります。
このことから、A社の国内での収入は、当該受取利息だけであり、課税売上割合はゼロとなります。
この場合、A社が親会社に支払った業務代行手数料に対する仕入控除税額の計算は、次のいずれによるべきでしょうか。 (1) A社は、国外における資産の貸付けを行うために設立された会社であり、その会社の業務の全てを委託したことにより支払われる対価は、この国外における資産の貸付けのために要する費用であることから、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当し、個別対応方式を採ることにより全額控除できます。
(2) 親会社への委託内容は、国外における資産の貸付けの業務のほかに会社自体の管理業務も含まれているので、支払われる対価は、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れには該当しません。
したがって、国外における資産の貸付けの業務に係るものだけが課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当するものであるが、この部分の金額が区分されていない場合は、課税・非課税共通用の課税仕入れとなり、結果として課税売上割合がゼロとなることから、控除できる税額はないことになります。
【 回答要旨】
照会の(1)によることとなります。 ( 理由)
1 個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合において、課税仕入れが課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当するのは、販売商品の仕入れのように、その課税仕入れが直接課税資産の譲渡等に供されるものに限定されません。例えば、課税売上げのみを行っている会社の自社ビルの建設のための土地造成費、商品券の印刷費は、いずれも課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当することとされています。
したがって、本件のように、資産の貸付けを国外において行うために設立された会社の業務の全てを委託した場合において、当該委託した業務から生ずる収入は、すべて課税資産の譲渡等の対価に該当することから、当該業務代行手数料は、消費税法第30条第2項第1号に規定する「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当します。
2 本件のように、業務の委託の対象となる会社の収入に預金利息があるとしても、その預金に関する業務を特に委託している事実がない場合には、利息収入があることをもって、業務代行手数料が課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れに該当することにはなりません。
3 したがって、当該代行手数料は、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当します。
【 関係法令通達】
消費税法第30条第2項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
質物を流質した場合の課税仕入れに係る支払対価の額
【 照会要旨】
質物が流質した場合には、質屋営業者の課税仕入れとなりますが、その場合の課税仕入れに係る支払対価の額はどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
次のとおりとなります。 1 入質から流質までの期間に対応する利子相当額を未収金として経理している場合……元利金の合計額が課税仕入れに係る支払対価の額となります。
2 1の利子相当額を未収金として経理していない場合……貸付金の元本の額が課税仕入れに係る支払対価の額となります。
なお、流質物の課税仕入れの時期は、流質期限の経過した時となりますが、流質期限を経過しても、それを他へ売却等により処分するまでの間は返還に応じている実情もありますので、便宜上、流質物の他への売却等により処分した時に課税仕入れをしたものとしても差し支えありません。
【 関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
共同保険事務に係る経費の配分
【 照会要旨】
共同保険事務に係る経費については幹事会社が一括して支払い、幹事会社と非幹事会社との間で負担分の精算を行っている場合、非幹事会社の仕入れに係る消費税額の控除に係る請求書等は幹事会社が非幹事会社に交付する当該幹事会社の支払いに係るコピーでもよいでしょうか。
【 回答要旨】
共同事業として課税仕入れを行った場合において、幹事会社が課税仕入れの名義人となっていること等の事由により各人の持分に応じて請求書等の交付を受けることができないときには、当該課税仕入れに係る課税資産の譲渡等を行った者が発行した請求書のコピーに、それぞれの配分内容を記載したものをもって各社の仕入れに係る消費税額の控除に係る請求書等としても差し支えありません。
【 関係法令通達】
消費税法第30条第7項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
JV工事に係る請求書等
【 照会要旨】
JV工事においては、資産の譲渡等及び課税仕入れはJVの各構成員が出資金等の割合に応じて行ったことになりますが(基通1-3-1)、課税仕入れに係る請求書等は幹事会社が保管し、各構成員は幹事会社から精算書(各構成員別に工事原価を計算した「完成工事原価報告書」が添付されている。)の交付を受け、これに基づき法人税、消費税の申告を行っています。
この精算書は、消費税法第30条第7項に規定する請求書等に該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
JV工事等の共同事業として、課税仕入れを行った場合に、幹事会社が課税仕入れの名義人となっていること等の事由により各構成員の持分に応じて請求書等の交付を受けることができないときには、課税仕入れに係る課税資産の譲渡等を行った者が発行した請求書等のコピーに各構成員の出資金等の割合に応じた課税仕入れに係る対価の額の配分内容を記載したものを消費税法第30条第7項に規定する請求書等に該当するものとして取り扱うほか、コピーが大量になるとの事情により、前記の方法により難い場合には、幹事会社が課税仕入れに係る請求書等を保存することを条件に、各構成員が参加しているJVを課税仕入れの相手方と擬制し、照会の精算書を同項に規定する請求書等に該当するものとして取り扱うことも差し支えありません。
【 関係法令通達】
消費税法第30条第7項、消費税法基本通達1-3-1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.