資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(印紙税)契約書の取扱い
(契約書の取扱い)
1 契約書の意義
2 予約契約書
3 更改契約書
4 変更契約書
5 補充契約書
6 写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い
7 仮契約書・仮文書等の取扱い
8 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
9 契約当事者以外の者に提出する文書の取扱い
契約書の意義
【 照会要旨】
「契約書」という場合は、一般に2以上の契約当事者が共に署名押印する形態のものを指していると考えられますが、印紙税法では「請書」のように当事者の一方だけが署名押印するような文書も契約書に該当するといわれました。どういう理由によるものでしょうか。
【 回答要旨】
課税物件表には、第1号の不動産の譲渡に関する契約書、消費貸借に関する契約書、第2号の請負に関する契約書、第14号の金銭又は有価証券の寄託に関する契約書などのように「○○に関する契約書」という名称で掲げられているものが多くありますが、ここにいう契約書は、一般的に言われるものよりかなり範囲が広く、そのため、通則5にその定義規定を置いています。
すなわち、課税物件表に掲げられているこれらの契約書とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含みます。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」といいます。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することになっているものも含まれます。
したがって、通常、契約の申込みの事実を証明する目的で作成される申込書、注文書、依頼書などと表示された文書であっても、実質的にみて、その文書によって契約の成立等が証明されるものは、契約書に該当することになります。
契約とは、互いに対立する2個以上の意思表示の合致、すなわち一方の申込みと他方の承諾によって成立する法律行為ですから、契約書とは、その2個以上の意思表示の合致の事実を証明する目的で作成される文書をいうことになります。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
予約契約書
【 照会要旨】
ある契約について、後日改めて本契約を締結することとしている場合に作成する予約契約書は、これによって契約の履行を求めることはできないものですから、印紙税法の課税文書には該当しないと考えてよいのでしょうか。
【 回答要旨】
通則5に規定する予約とは、将来本契約を成立させることを約する契約であり、印紙税法上は、本契約と全く同一に取り扱われます。予約契約書は、協定書、念書、覚書、承諾書等様々な名称を用いて作成される場合が多くありますが、その成立させようとする本契約の内容によって課税文書の所属が決定されるほか、予約としての契約金額の記載がある場合には、その金額も印紙税法上の記載金額に該当することになります。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達第15条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
更改契約書
【 照会要旨】
契約を更改する契約書は、印紙税法上の契約書に含まれるとのことですが、「契約の更改」とはどういうことですか。また、どのような文書として課税されますか。
【 回答要旨】
通則5に規定する更改とは、既存の債務を消滅させて新たな債務を成立させることですから、その成立させる新たな債務の内容に従って課税文書の所属が決定されることになります。
更改には、次のようなものがあります。
(1) 債権者の交替による更改
甲の乙に対する債権を消滅させて丙の乙に対する債権を新たに成立させる場合をいいます。
(2) 債務者の交替による更改
甲の乙に対する債権を消滅させて甲の丙に対する債権を新たに成立させる場合をいいます。
(3) 目的の変更による更改
金銭の支払債務を消滅させて土地を給付する債務を新たに成立させるような場合をいいます。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達第16条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
変更契約書
【 照会要旨】
原契約の内容を変更する契約書は、印紙税法上の契約書に含まれるとのことですが、「契約の内容の変更」とはどういうことですか。また、どのような文書として課税されますか。
【 回答要旨】
通則5に規定する「契約の内容の変更」とは、既に存在している契約(以下「原契約」といいます。)の同一性を失わせないで、その内容を変更することをいいます。この場合において、原契約が文書化されていたか、単なる口頭契約であったかは問いません。
法は、契約上重要な事項を変更する変更契約書を課税対象とすることとし、その重要な事項の範囲は基通別表第2に定められていますが、ここに掲げられているものは例示事項であり、これらに密接に関連する事項や例示した事項と比較してこれと同等、若しくはそれ以上に契約上重要な事項を変更するものも課税対象になります。
変更契約書は、変更する事項がどの号に該当する重要な事項であるかにより文書の所属を決定することになるのですが、2以上の号の重要な事項が2以上併記又は混合記載されている場合とか、一つの重要な事項が同時に2以上の号に該当する場合には、それぞれの号に該当する文書として原契約書の所属の決定方法と同様に所属を決定することになります。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達第17条、別表第二
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
補充契約書
【 照会要旨】
原契約の内容を補充する契約書は、印紙税法上の契約書に含まれるとのことですが、「契約の内容の補充」とはどういうことですか。また、どのような文書として課税されますか。
【 回答要旨】
通則5に規定する「契約の内容の補充」とは、原契約の内容として欠けている事項を補充することをいい、原契約が文書化されていたかどうかを問わないこと、契約上重要な事項を補充するものを課税対象とすること、補充する事項がどの号に該当する重要な事項であるかにより文書の所属を決定することは、変更契約書の場合と同じです。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達第18条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い
【 照会要旨】
一つの契約について契約書を正副2通作った場合には、そのうち正本だけに印紙をはればよいのですか。それとも正副の2通とも印紙をはらなければならないのですか。また、副本としないで写しとした場合はどうなりますか。
【 回答要旨】
単なる控えとするための写、副本、謄本等は、原則として課税文書にはなりませんが、写、副本、謄本等であっても、契約当事者の双方又は相手方の署名押印があるなど、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかである場合には、課税文書になります。
すなわち、印紙税は、契約が成立したという事実を課税対象とするのではなく、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものですから、一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、その2通以上の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであるならば、すべて印紙税の課税対象になります。つまり、契約当事者の一方が所持するものには正本又は原本と表示し、他方が所持するものには、写し、副本、謄本などという表示をしても、それが契約の成立を証明する目的で作成されたものであるならば、正本又は原本と同様に印紙税の課税対象になります。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
仮契約書・仮文書等の取扱い
【 照会要旨】
不動産の売買に当たって、当初仮契約を締結し、その後本契約を締結することとしていますが、当初作成する「仮契約書」の取扱いについて説明してください。
【 回答要旨】
後日、正式文書を作成することとしている場合において、一時的にこれに代わるものとして作成する仮契約書・仮文書等であっても、その文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、課税文書になります(基通58)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達第58条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
【 照会要旨】
申込書、注文書、依頼書という標題を用いている文書であっても、その記載内容によっては、課税になるものがあるということですが、具体的にはどんな場合でしょうか。
【 回答要旨】
契約とは、申込みと承諾によって成立するものですから、契約の申込事実を記載した申込書、注文書、依頼書などは、通常、課税対象にはなりません。
しかし、たとえ、これらの標題を用いている文書であっても、その記載内容によっては、契約の成立等を証する文書、すなわち、契約書になるものがあります。
契約の成立等を証する文書かどうかは、文書の記載文言等その文書上から客観的に判断するというのが印紙税の基本的な取扱いですから、申込書等と表示された文書が契約の成立等を証明する目的で作成されたものであるかどうかの判断も、基本的にその文書上から行うことになります(基通第2条、第3条)。
このような契約の成立等を証明する目的で作成される文書は当然に契約書に該当するのですが、実務上、申込書等と表示された文書が契約書に該当するかどうかの判断はなかなか困難なことから、基通第21条において、一般的に契約書に該当するものを次のように例示しています。
(1) 契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。
例えば、次の「互助会加入申込書」は、「貴互助会約款承認の上加入……」となっていますので、約款に基づく申込みであることは明らかであり、原則として契約書に該当します。この場合の約款等に基づく申込みであることが記載されているかどうかは、申込書等に、約款等に基づく申込みである旨の文言が明記されているもののほか、約款等の記号、番号等が記載されていること等により、実質的に約款等に基づく申込みであることが文書上明らかなものも含まれます(このことは、次の(2)の場合も同じです。)。
また、自動的に契約が成立するかどうかは、実態判断によります。すなわち、約款等で、例えば「申込書を提出した時に自動的に契約が成立するものとする。」とされている場合は、その申込書を提出した時に自動的に契約が成立するのは明らかですし、また、「申込書提出後、当方が審査を行った上了解したものについて契約が成立するものとする。」となっている場合は、その申込書を提出しても自動的に契約が成立するものとはいえません。しかし、約款等にそのような明文の記載がない場合は、事実上その申込みによって自動的に契約が成立するかどうかを判断することになるわけです。
ところで、一方の申込みにより自動的に契約が成立する申込書等であっても、それに対して相手方当事者がさらに請書等を作成することとしているものは、契約書に当たらないことに取り扱われています。この場合でも、申込書等の文書上に、さらに請書等を作成する旨が記載されていることが必要であり、請書等を作成する旨が記載されていないときは、申込書等も契約書として、また、請書等も契約書として課税されます(このことは、次の(2)の場合も同じです。)。
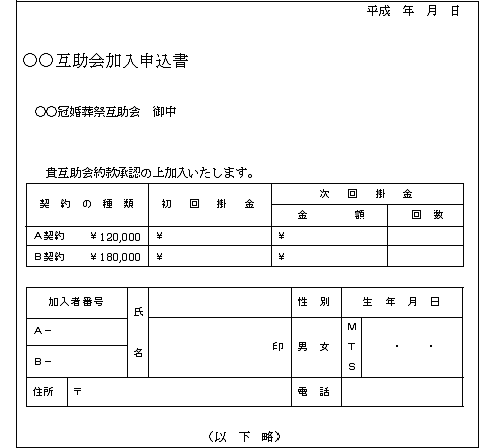
(2) 見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されている当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。
例えば、次に示す「注文書」のように、見積書等契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載された申込書等は、原則として契約書に該当します。この場合は、(1)の場合と違って、申込みにより自動的に契約が成立するかどうかは、契約書に該当することの要件にはなっていません。これは、契約の相手方当事者が作成する見積書等がいわば契約の申込みであり、これに基づく申込書等は、請書と同様の性格を有するからです。
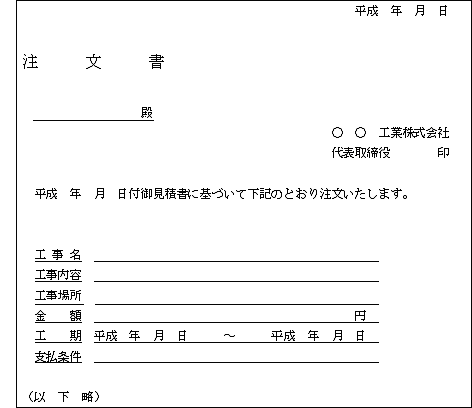
(3) 契約当事者双方の署名又は押印があるもの
契約当事者双方の署名又は押印があるものは、一般に契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成されたものと認められますから、原則として契約書に該当します。例えば、2部提出された申込書のうちの1部に署名又は押印して返却する申込書等がこれに該当します。
なお、申込書控等に署名又は押印して返却する場合であっても、その署名又は押印が意思の合致を証明する目的以外の目的でなされたことが明らかなものは、契約書には該当しません。
例えば、単なる文書の受付印と認められるものや、手付金とか申込証拠金の受領印を押印して返却したものなどがこれに該当します(頭金、初回金などの受領印の場合は、契約の成立に伴って受け取るものといえますから、契約書に該当することになります。)。
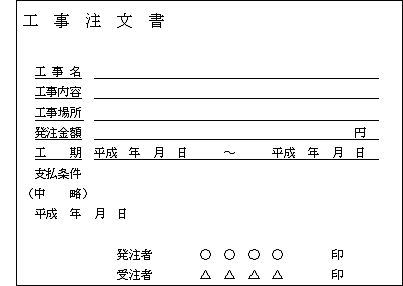
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達第2条、第3条、第21条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
契約当事者以外の者に提出する文書の取扱い
【 照会要旨】
当社は、不動産売買の仲介を行っておりますが、不動産の仲介をした場合、不動産売買契約書の控(売買当事者の署名押印のあるもの)を保管することにしています。この契約書の控も第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)として、印紙税が課税されることになるのでしょうか。
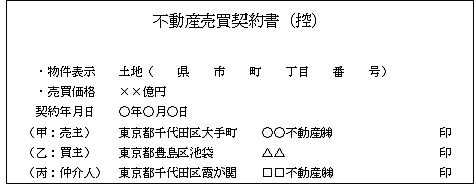
【 回答要旨】
印紙税法は、作成した文書に対して課税するものですから、同一内容の文書を2通以上作成した場合において、それぞれの文書が契約の成立等を証するものである限り、契約当事者の所持するものと、契約当事者以外の者が所持するものとを問わず、原則として課税文書に該当することになります。
しかしながら、契約当事者以外の者に提出する文書であって、かつ、当該文書に提出先が明確に記載されているものについては、課税文書に該当しないものとして取り扱っています(基通第20条)。
ここにいう契約当事者とは、その契約書において直接の当事者となっている者のみではなく、その契約の前提となる契約及びその契約に付随して行われる契約の当事者等、その契約に参加する者のすべてを含みます。例えば、ご質問の不動産売買契約における仲介人、消費貸借契約における保証人は、契約に参加する当事者であることから、ここにいう契約当事者に含まれることになり、その所持する契約書は課税の対象になります。
契約当事者以外の者とは、その契約に直接の利害関係を有しない、例えば、監督官庁や融資銀行のような者をいうことになります。
契約当事者以外の者に提出する文書であっても、提出先が明記されていないものは、課税されることになり、また、「○○提出用」と契約当事者以外の者に提出されることが明記された文書であっても、例えば、監督官庁に提出しないで契約当事者が所持している場合や、当初、契約当事者間の証明目的で作成されたものが、たまたま結果的に契約当事者以外の者に提出された場合等は、課税の対象になりますので注意が必要です。
(注) このように仲介人の所持する契約書は、第1号の1文書に該当することになりますが、仲介人自身は不動産の譲渡に係る契約当事者ではありませんから、不動産売買契約の当事者である甲(売主)と乙(買主)が連帯して納税義務を負うことになります。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達第20条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
1 契約書の意義
2 予約契約書
3 更改契約書
4 変更契約書
5 補充契約書
6 写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い
7 仮契約書・仮文書等の取扱い
8 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
9 契約当事者以外の者に提出する文書の取扱い
契約書の意義
【 照会要旨】
「契約書」という場合は、一般に2以上の契約当事者が共に署名押印する形態のものを指していると考えられますが、印紙税法では「請書」のように当事者の一方だけが署名押印するような文書も契約書に該当するといわれました。どういう理由によるものでしょうか。
【 回答要旨】
課税物件表には、第1号の不動産の譲渡に関する契約書、消費貸借に関する契約書、第2号の請負に関する契約書、第14号の金銭又は有価証券の寄託に関する契約書などのように「○○に関する契約書」という名称で掲げられているものが多くありますが、ここにいう契約書は、一般的に言われるものよりかなり範囲が広く、そのため、通則5にその定義規定を置いています。
すなわち、課税物件表に掲げられているこれらの契約書とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含みます。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」といいます。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することになっているものも含まれます。
したがって、通常、契約の申込みの事実を証明する目的で作成される申込書、注文書、依頼書などと表示された文書であっても、実質的にみて、その文書によって契約の成立等が証明されるものは、契約書に該当することになります。
契約とは、互いに対立する2個以上の意思表示の合致、すなわち一方の申込みと他方の承諾によって成立する法律行為ですから、契約書とは、その2個以上の意思表示の合致の事実を証明する目的で作成される文書をいうことになります。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
予約契約書
【 照会要旨】
ある契約について、後日改めて本契約を締結することとしている場合に作成する予約契約書は、これによって契約の履行を求めることはできないものですから、印紙税法の課税文書には該当しないと考えてよいのでしょうか。
【 回答要旨】
通則5に規定する予約とは、将来本契約を成立させることを約する契約であり、印紙税法上は、本契約と全く同一に取り扱われます。予約契約書は、協定書、念書、覚書、承諾書等様々な名称を用いて作成される場合が多くありますが、その成立させようとする本契約の内容によって課税文書の所属が決定されるほか、予約としての契約金額の記載がある場合には、その金額も印紙税法上の記載金額に該当することになります。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達第15条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
更改契約書
【 照会要旨】
契約を更改する契約書は、印紙税法上の契約書に含まれるとのことですが、「契約の更改」とはどういうことですか。また、どのような文書として課税されますか。
【 回答要旨】
通則5に規定する更改とは、既存の債務を消滅させて新たな債務を成立させることですから、その成立させる新たな債務の内容に従って課税文書の所属が決定されることになります。
更改には、次のようなものがあります。
(1) 債権者の交替による更改
甲の乙に対する債権を消滅させて丙の乙に対する債権を新たに成立させる場合をいいます。
(2) 債務者の交替による更改
甲の乙に対する債権を消滅させて甲の丙に対する債権を新たに成立させる場合をいいます。
(3) 目的の変更による更改
金銭の支払債務を消滅させて土地を給付する債務を新たに成立させるような場合をいいます。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達第16条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
変更契約書
【 照会要旨】
原契約の内容を変更する契約書は、印紙税法上の契約書に含まれるとのことですが、「契約の内容の変更」とはどういうことですか。また、どのような文書として課税されますか。
【 回答要旨】
通則5に規定する「契約の内容の変更」とは、既に存在している契約(以下「原契約」といいます。)の同一性を失わせないで、その内容を変更することをいいます。この場合において、原契約が文書化されていたか、単なる口頭契約であったかは問いません。
法は、契約上重要な事項を変更する変更契約書を課税対象とすることとし、その重要な事項の範囲は基通別表第2に定められていますが、ここに掲げられているものは例示事項であり、これらに密接に関連する事項や例示した事項と比較してこれと同等、若しくはそれ以上に契約上重要な事項を変更するものも課税対象になります。
変更契約書は、変更する事項がどの号に該当する重要な事項であるかにより文書の所属を決定することになるのですが、2以上の号の重要な事項が2以上併記又は混合記載されている場合とか、一つの重要な事項が同時に2以上の号に該当する場合には、それぞれの号に該当する文書として原契約書の所属の決定方法と同様に所属を決定することになります。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達第17条、別表第二
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
補充契約書
【 照会要旨】
原契約の内容を補充する契約書は、印紙税法上の契約書に含まれるとのことですが、「契約の内容の補充」とはどういうことですか。また、どのような文書として課税されますか。
【 回答要旨】
通則5に規定する「契約の内容の補充」とは、原契約の内容として欠けている事項を補充することをいい、原契約が文書化されていたかどうかを問わないこと、契約上重要な事項を補充するものを課税対象とすること、補充する事項がどの号に該当する重要な事項であるかにより文書の所属を決定することは、変更契約書の場合と同じです。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達第18条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い
【 照会要旨】
一つの契約について契約書を正副2通作った場合には、そのうち正本だけに印紙をはればよいのですか。それとも正副の2通とも印紙をはらなければならないのですか。また、副本としないで写しとした場合はどうなりますか。
【 回答要旨】
単なる控えとするための写、副本、謄本等は、原則として課税文書にはなりませんが、写、副本、謄本等であっても、契約当事者の双方又は相手方の署名押印があるなど、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかである場合には、課税文書になります。
すなわち、印紙税は、契約が成立したという事実を課税対象とするのではなく、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものですから、一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、その2通以上の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであるならば、すべて印紙税の課税対象になります。つまり、契約当事者の一方が所持するものには正本又は原本と表示し、他方が所持するものには、写し、副本、謄本などという表示をしても、それが契約の成立を証明する目的で作成されたものであるならば、正本又は原本と同様に印紙税の課税対象になります。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
仮契約書・仮文書等の取扱い
【 照会要旨】
不動産の売買に当たって、当初仮契約を締結し、その後本契約を締結することとしていますが、当初作成する「仮契約書」の取扱いについて説明してください。
【 回答要旨】
後日、正式文書を作成することとしている場合において、一時的にこれに代わるものとして作成する仮契約書・仮文書等であっても、その文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、課税文書になります(基通58)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達第58条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
【 照会要旨】
申込書、注文書、依頼書という標題を用いている文書であっても、その記載内容によっては、課税になるものがあるということですが、具体的にはどんな場合でしょうか。
【 回答要旨】
契約とは、申込みと承諾によって成立するものですから、契約の申込事実を記載した申込書、注文書、依頼書などは、通常、課税対象にはなりません。
しかし、たとえ、これらの標題を用いている文書であっても、その記載内容によっては、契約の成立等を証する文書、すなわち、契約書になるものがあります。
契約の成立等を証する文書かどうかは、文書の記載文言等その文書上から客観的に判断するというのが印紙税の基本的な取扱いですから、申込書等と表示された文書が契約の成立等を証明する目的で作成されたものであるかどうかの判断も、基本的にその文書上から行うことになります(基通第2条、第3条)。
このような契約の成立等を証明する目的で作成される文書は当然に契約書に該当するのですが、実務上、申込書等と表示された文書が契約書に該当するかどうかの判断はなかなか困難なことから、基通第21条において、一般的に契約書に該当するものを次のように例示しています。
(1) 契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。
例えば、次の「互助会加入申込書」は、「貴互助会約款承認の上加入……」となっていますので、約款に基づく申込みであることは明らかであり、原則として契約書に該当します。この場合の約款等に基づく申込みであることが記載されているかどうかは、申込書等に、約款等に基づく申込みである旨の文言が明記されているもののほか、約款等の記号、番号等が記載されていること等により、実質的に約款等に基づく申込みであることが文書上明らかなものも含まれます(このことは、次の(2)の場合も同じです。)。
また、自動的に契約が成立するかどうかは、実態判断によります。すなわち、約款等で、例えば「申込書を提出した時に自動的に契約が成立するものとする。」とされている場合は、その申込書を提出した時に自動的に契約が成立するのは明らかですし、また、「申込書提出後、当方が審査を行った上了解したものについて契約が成立するものとする。」となっている場合は、その申込書を提出しても自動的に契約が成立するものとはいえません。しかし、約款等にそのような明文の記載がない場合は、事実上その申込みによって自動的に契約が成立するかどうかを判断することになるわけです。
ところで、一方の申込みにより自動的に契約が成立する申込書等であっても、それに対して相手方当事者がさらに請書等を作成することとしているものは、契約書に当たらないことに取り扱われています。この場合でも、申込書等の文書上に、さらに請書等を作成する旨が記載されていることが必要であり、請書等を作成する旨が記載されていないときは、申込書等も契約書として、また、請書等も契約書として課税されます(このことは、次の(2)の場合も同じです。)。
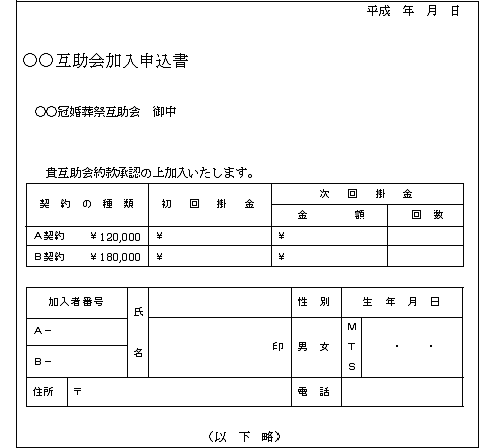
(2) 見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されている当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。
例えば、次に示す「注文書」のように、見積書等契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載された申込書等は、原則として契約書に該当します。この場合は、(1)の場合と違って、申込みにより自動的に契約が成立するかどうかは、契約書に該当することの要件にはなっていません。これは、契約の相手方当事者が作成する見積書等がいわば契約の申込みであり、これに基づく申込書等は、請書と同様の性格を有するからです。
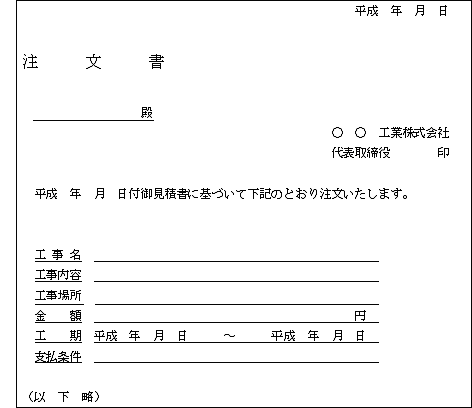
(3) 契約当事者双方の署名又は押印があるもの
契約当事者双方の署名又は押印があるものは、一般に契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成されたものと認められますから、原則として契約書に該当します。例えば、2部提出された申込書のうちの1部に署名又は押印して返却する申込書等がこれに該当します。
なお、申込書控等に署名又は押印して返却する場合であっても、その署名又は押印が意思の合致を証明する目的以外の目的でなされたことが明らかなものは、契約書には該当しません。
例えば、単なる文書の受付印と認められるものや、手付金とか申込証拠金の受領印を押印して返却したものなどがこれに該当します(頭金、初回金などの受領印の場合は、契約の成立に伴って受け取るものといえますから、契約書に該当することになります。)。
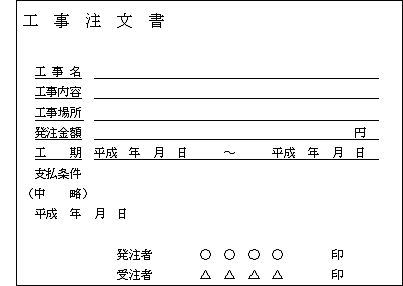
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達第2条、第3条、第21条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
契約当事者以外の者に提出する文書の取扱い
【 照会要旨】
当社は、不動産売買の仲介を行っておりますが、不動産の仲介をした場合、不動産売買契約書の控(売買当事者の署名押印のあるもの)を保管することにしています。この契約書の控も第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)として、印紙税が課税されることになるのでしょうか。
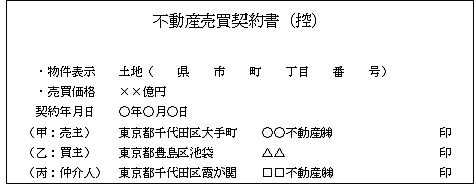
【 回答要旨】
印紙税法は、作成した文書に対して課税するものですから、同一内容の文書を2通以上作成した場合において、それぞれの文書が契約の成立等を証するものである限り、契約当事者の所持するものと、契約当事者以外の者が所持するものとを問わず、原則として課税文書に該当することになります。
しかしながら、契約当事者以外の者に提出する文書であって、かつ、当該文書に提出先が明確に記載されているものについては、課税文書に該当しないものとして取り扱っています(基通第20条)。
ここにいう契約当事者とは、その契約書において直接の当事者となっている者のみではなく、その契約の前提となる契約及びその契約に付随して行われる契約の当事者等、その契約に参加する者のすべてを含みます。例えば、ご質問の不動産売買契約における仲介人、消費貸借契約における保証人は、契約に参加する当事者であることから、ここにいう契約当事者に含まれることになり、その所持する契約書は課税の対象になります。
契約当事者以外の者とは、その契約に直接の利害関係を有しない、例えば、監督官庁や融資銀行のような者をいうことになります。
契約当事者以外の者に提出する文書であっても、提出先が明記されていないものは、課税されることになり、また、「○○提出用」と契約当事者以外の者に提出されることが明記された文書であっても、例えば、監督官庁に提出しないで契約当事者が所持している場合や、当初、契約当事者間の証明目的で作成されたものが、たまたま結果的に契約当事者以外の者に提出された場合等は、課税の対象になりますので注意が必要です。
(注) このように仲介人の所持する契約書は、第1号の1文書に該当することになりますが、仲介人自身は不動産の譲渡に係る契約当事者ではありませんから、不動産売買契約の当事者である甲(売主)と乙(買主)が連帯して納税義務を負うことになります。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達第20条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















