解説記事2005年03月07日 【ニュース特集】 「右山訴訟」を検証する(2005年3月7日号・№105)
ニュース特集
租税実務をひっくり返した画期的判決
「右山訴訟」を検証する
平成17年2月1日、最高裁判所第三小法廷(濱田邦夫裁判長)は、「受贈者が贈与者から資産を取得するために要した付随費用の額は、受贈者が同資産を譲渡した場合に所得税法60条1項に基づいてされる譲渡所得の金額の計算において、同法38条1項にいう『資産の取得に要した金額』に当たる」と判示し、納税者の請求(上告)を容認する判決を言渡しました(判決は最高裁HP「最近の主な最高裁判決」に掲載中)。
これまでの課税上の取扱いと異なる内容の判決であったために、課税庁も早速に取扱いを改めるなど、課税実務に与える影響も大きなものとなりました。この訴訟は、原告(上告人)に由来して、「右山訴訟」と呼ばれていますが、今回の特集は、この「右山訴訟」最高裁判決を中心に検証していきたいと思います。
事件の概要
本件は、父親からゴルフ会員権の贈与を受けた際に名義書換手数料を支払った上告人が、上記ゴルフ会員権を第三者に譲渡し、譲渡所得金額の計算上、上記手数料を取得費に含めて確定申告を行ったところ、被上告人税務署長が、上記手数料を資産の取得費として譲渡所得に係る総収入金額から控除することはできないとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたため、被上告人に対し、本件各処分の取消しを求めた事案である。
第1審・控訴審ともに、上記手数料は、所得税法38条1項にいう「譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費」・同法33条3項の「資産の譲渡に要した費用」のいずれにもあたらないとして、上告人の請求・控訴を棄却したので、上告人が上告した。

納税者(上告人)の主張
名義書換手数料(824,000円)は、所得税法38条1項にいう「資産の取得費」に該当し、本件譲渡所得金額の計算上総収入金額から控除すべきである。
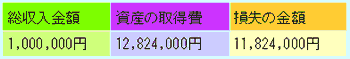
税務署長(被上告人)の主張
所得税法38条1項にいう「資産の取得費」として譲渡所得の金額の計算上総収入金額から控除できるのは、贈与者(父)が取得代金として支払った1200万円のみである。
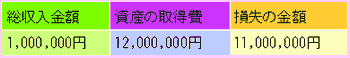
下級審の整理した争点と最高裁が取り上げた争点
右山訴訟は、東京地裁民事3部(藤山雅行裁判長)、東京高裁第9民事部(雛形要松裁判長)で争われてきたが、争点については下記のように整理されている。このような争点の整理は、原告が「本件手数料は、所得税法38条1項にいう『資産の取得費』に該当」と主張する一方で、「仮に本件手数料が、所得税法38条1項にいう『資産の取得費』に当たらないとしても、本件手数料は、所得税法33条3項にいう『資産の譲渡に要した費用』に該当する」と主張してきたことに対応するものである。
争点2について、原告の主張は、第1審・控訴審いずれも斥けられているが、上告審(最高裁)は、本件を上告審として受理した段階で、「譲渡費用該当性」という仮定主張は重要でないとして斥けているため、争点1の「取得費該当性」に絞って判断されることになった。
争点1 本件手数料は、所得税法38条1項にいう「譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費」に該当するか。
争点2 本件手数料は、所得税法33条3項にいう「資産の譲渡に要した費用」に該当するか。
下級審の判示と原告が上告審(最高裁)で主張したこと
争点1について下級審(東京地裁・東京高裁)の判示は次のようなものであった。
第1審 請求棄却 東京地裁民事3部 平成12年(行ウ)57号平12.12.21判決言渡
所得税法が贈与による資産の所有権移転の場合における譲渡所得課税を繰り延べ、その後、当該資産が受贈者の支配を離れて他に移転する機会をとらえて、贈与者の取得の時以来清算されることなく蓄積されてきた資産の増加益を課税の対象としているのであるから、右増加益の算出上、譲渡による収入金額から控除すべき「資産の取得に要した金額」は、贈与者の取得の時において当該資産の客観的価格を構成すべき取得代金の額及び当該資産を取得するための付随費用でなければならない。
すなわち、所得税法60条により、贈与の前後を通じて贈与者が引き続き当該資産を所有していたものとみなされる以上、譲渡所得の算出に当たっては、贈与の事実はなかったものと考えるべきであり、そうである以上受贈者が自己への所有権移転のために支払った費用も一切無視するほかない。
本件手数料は、贈与者である父による本件会員権を取得するための付随費用でもないから、本件会員権との関係で、所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した費用」ということはできない。
控訴審 控訴棄却 東京高裁第9民事部 平成13年(行コ)12号平13.6.27判決言渡
(前略)「資産の取得に要した金額」とは、贈与者の取得の時において当該資産の客観的価格を構成すべき取得代金の額及び当該資産を取得するための付随費用と解すべきである。
本件手数料が、このような「資産の取得に要した金額」に当たるか否かを検討するに、本件会員権は、控訴人が父から贈与を受けたものであり、本件手数料は、本件会員権の名義を父から控訴人に書き換える際の名義書換手数料であるから、贈与者である父が本件会員権を取得した時点における本件会員権の客観的価格を構成するものではないし、父が本件会員権を取得するための付随費用でもない。したがって、本件手数料は、本件会員権との関係で、所得税法38条1項にいう資産の取得費に当たると解することはできない。(略)
受贈者が所有する資産についての譲渡所得課税においては、所得税法60条1項により、贈与の前後を通じて贈与者が引き続き当該資産を所有していたものとみなされるのであるから、課税庁としては、譲渡所得金額を算定するに当たり、中間の贈与の事実はなかったものと扱う以外になく、そうであれば、受贈者が自己への所有権移転のために支払った費用があったとしても、それを一切無視せざるを得ないことになる。
そうすると、本件譲渡所得金額の計算においては、控訴人が父から本件会員権の贈与を受けた事実も、その際に控訴人が本件手数料を支払った事実も、一切なかったものとみなすことになる。
下級審の判断に対して、上告人は次のように主張して、上告審を展開した。(弁論要旨より抜粋)
第1 譲渡所得とは何か(所得税法33条3項、38条1項の解釈)
所得税法の根底には、純所得に対して課税する考え方がある。他方、譲渡所得の本質は所有資産の価値の増加益であるという見方がある。(略)
しかるに被上告人は、所得税法60条1項の「その者が引き続きこれを所有していたものとみなす」との文言のみをもって、贈与によって取得した資産については受贈時の付随費用は取得費にあたらないと主張するにとどまり、贈与等によって取得した資産の譲渡所得の金額の算出上、受贈時における付随費用を控除しない合理的根拠を全く主張していない。このことをもってしても、贈与等によって取得した資産の譲渡所得の金額の算出にあたって受贈時の付随費用を控除しない合理的根拠が存在しないことは明らかである。
第2 所得税法60条1項の解釈
1. 所得税法60条1項の沿革及び立法趣旨
所法60条1項の立法趣旨は、「みなし譲渡課税」を廃止し、贈与者における課税を受贈者に肩代わりさせるところにあるのであり、それ以上でも以下でもない。
いわんや、「みなし譲渡課税」の下では当然控除が可能であった付随費用を控除しないことを目的とするものではない。
したがって、所得税法60条1項の立法趣旨を前提とする限り、贈与等によって取得した資産の譲渡所得金額の算出上、受贈時に支出した付随費用を控除しないという解釈は導き得ない。
2. 所得税法60条1項の文言解釈
所法60条1項からは、贈与者の取得時から受贈者の譲渡時までの増加益を把握する趣旨であることは明確であるが、さらに進んであえて贈与の事実そのものを否定する趣旨まで読むことはできない。
3. 有償譲渡との関係
仮に譲渡所得の本質を資産の増加益とみたとしても、有償譲渡と無償譲渡の場合で増加益が異なるというのは明らかに合理性がない。
また、客観的に測定されるべき課税物権たる所得の金額が有償譲渡と無償譲渡の場合で異なるのは公平でも公正でもない(この部分の主張については、上告受理申立理由書(あるいは、原審における鑑定意見書)において、事例を設けて分析し、「A→B→Cで譲渡があった場合に、A→B間の譲渡が売買か贈与かで、清算される譲渡所得の額が異なるのは、公平でも公正でもない。」としている。)。
かかる視点からも、贈与等の場合に、受贈時の付随費用を控除しないという解釈には合理性がない。
4. 所得税法38条1項との関係
取得代金については、所得税法60条1項により、贈与者のそれを引継ぐとしても、資産の取得に要した付随費用については、受贈者にとって、その資産を使用できるようにするまでの費用として把握されるべきものであるから、受贈時の付随費用は当然に取得費にあたるというべきである。
第3 代償分割に関する最高裁判決との比較
被上告人は代償分割に関する平成6年最高裁判決を自己に有利に援用するが、同判決は、遺産分割の効果は相続開始時に遡ることから、相続人間の譲渡を観念することはできず、したがって、代償金は取得代金にはあたらないとしたものであり、現実の贈与が存在する本件とは全く事案が異なる。
また、代償金は、遺産分割において、相続人間の公平を図るための調整金(たとえば、近い将来に不動産を処分する見込みがある場合には、通常、取得価額の引継ぎも考慮した上で決定される。)であり、自己の相続分を超える部分を相続するための手続費用でもないから、資産の取得に際しての付随費用にもあたらない。
第4 本件手数料が取得費にあたること
本件会員権の場合、これを譲り受けた者が、本件クラブに対して会員としての権利を行使するためには、ゴルフ場経営会社の承認を得て会員名義を書き換え、会員たる地位を取得する必要があるのであるから、これに要する名義書換手数料は当然に取得費にあたる。
なお、実務上も、有償譲渡によってゴルフ会員権を取得した場合、取得時に支出した名義書換手数料は、取得費として扱われており、無償譲渡によって取得した場合にこれと別異に解する理由はない。
したがって、本件手数料は、譲渡所得の算定上、上告人の総収入金額から控除すべき取得費にあたる。
譲渡所得の本質―キャピタル・ゲイン課税か?純所得課税か?
本件では、大阪府立大学の田中治教授が原告側の鑑定意見書を提出している。その内容は、税務事例研究vol.65「資産の取得価額をめぐる近時の紛争例」(財団法人 日本税務研究センター)の事例(1)とほぼ同旨となっている。田中教授は、税務事例研究vol.36「譲渡所得課税における取得費」においても譲渡所得課税における取得費の問題を取り上げている。
原告側では、「譲渡所得の本質は純所得と考えるべきである。」とし、「仮に、キャピタル・ゲインと考えるとしても、純所得としての考え方を大前提に置きながら、キャピタル・ゲインの観点から修正されていると考えるべき」と主張している。
ここでのキャピタル・ゲイン課税と純所得課税は下表のように考えられるが、原告側は、「資産の取得に要した金額」に資産を取得するために支出した付随費用の額も含まれるとするのは、「現行所得税法が純所得課税の考え方を反映したものである。」と主張している。
控訴審判決は、下表のキャピタル・ゲイン課税の判示に続いて、「『資産の取得に要した金額』には、当該資産の客観的価格を構成すべき取得代金の額のほか、登録免許税、仲介手数料等当該資産を取得するための付随費用の額も含まれると解される。」と判示しているが、田中教授がキャピタル・ゲイン課税(客観価値説)について述べているところでは、「この考え方(客観価値説)によれば、資産の保有に要した費用は、譲渡収入から控除することはできない、とされるであろう。また、おそらく、資産の譲渡に要した費用も、資産の客観的価額を左右するものではないから控除できない、とされるであろう。」としている。
上告人・田中教授は、控訴審判決がいう「キャピタル・ゲイン課税」のもつ現行所得税法との不整合を指摘することで、最高裁がより「純所得課税」に近い判断を下すことになったといえるだろう。
また、有償譲渡と無償譲渡との比較について、事例を設けて主張するなど、租税実務として定着していた贈与時等の付随費用を無視する取扱いの問題点を解き明かしている。
代償分割に関する最高裁判決との比較
本件の最高裁判決では、平成6年9月13日の最高裁判決との関連も実質的な争点となっている。すなわち、最高裁平成6年判決は、「相続(代償分割)で取得した不動産を他に売却したときの譲渡所得の計算に当たっては、相続前から引き続き所有していたものとして取得費を考えることになるから、代償金及びその交付のために銀行から借り入れた借入金の利息相当額を相続財産の取得費に算入することはできない。」と判示していた。
この判示をもって、課税庁は、贈与・相続時の付随費用の「取得費該当性」を認めないことの論拠としてきた。
最高裁の判例に反することにはなるが、「代償金は取得費を構成する。」との考え方も十分に成立する。贈与・相続時の付随費用の「取得費該当性」を主張するのであれば、「代償金の取得費該当性」といった問題を巻き込んで主張するという争い方も考えられたことだろう。しかし、上告人は、あえて判例変更を求める主張を行わず、平成6年判決は、代償金が取得費にあたるという納税者の前提にある「相続分の売買」という主張を排斥した事案であるとして、本件とは事案を異にすることを主張した。 上告人の主張を受ける形で、本件の最高裁判決は平成6年判決との整合性には触れられていない。
租税実務をひっくり返した画期的判決
「右山訴訟」を検証する
平成17年2月1日、最高裁判所第三小法廷(濱田邦夫裁判長)は、「受贈者が贈与者から資産を取得するために要した付随費用の額は、受贈者が同資産を譲渡した場合に所得税法60条1項に基づいてされる譲渡所得の金額の計算において、同法38条1項にいう『資産の取得に要した金額』に当たる」と判示し、納税者の請求(上告)を容認する判決を言渡しました(判決は最高裁HP「最近の主な最高裁判決」に掲載中)。
これまでの課税上の取扱いと異なる内容の判決であったために、課税庁も早速に取扱いを改めるなど、課税実務に与える影響も大きなものとなりました。この訴訟は、原告(上告人)に由来して、「右山訴訟」と呼ばれていますが、今回の特集は、この「右山訴訟」最高裁判決を中心に検証していきたいと思います。
事件の概要
本件は、父親からゴルフ会員権の贈与を受けた際に名義書換手数料を支払った上告人が、上記ゴルフ会員権を第三者に譲渡し、譲渡所得金額の計算上、上記手数料を取得費に含めて確定申告を行ったところ、被上告人税務署長が、上記手数料を資産の取得費として譲渡所得に係る総収入金額から控除することはできないとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたため、被上告人に対し、本件各処分の取消しを求めた事案である。
第1審・控訴審ともに、上記手数料は、所得税法38条1項にいう「譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費」・同法33条3項の「資産の譲渡に要した費用」のいずれにもあたらないとして、上告人の請求・控訴を棄却したので、上告人が上告した。

納税者(上告人)の主張
名義書換手数料(824,000円)は、所得税法38条1項にいう「資産の取得費」に該当し、本件譲渡所得金額の計算上総収入金額から控除すべきである。
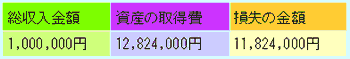
税務署長(被上告人)の主張
所得税法38条1項にいう「資産の取得費」として譲渡所得の金額の計算上総収入金額から控除できるのは、贈与者(父)が取得代金として支払った1200万円のみである。
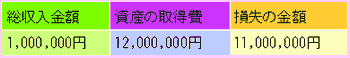
下級審の整理した争点と最高裁が取り上げた争点
右山訴訟は、東京地裁民事3部(藤山雅行裁判長)、東京高裁第9民事部(雛形要松裁判長)で争われてきたが、争点については下記のように整理されている。このような争点の整理は、原告が「本件手数料は、所得税法38条1項にいう『資産の取得費』に該当」と主張する一方で、「仮に本件手数料が、所得税法38条1項にいう『資産の取得費』に当たらないとしても、本件手数料は、所得税法33条3項にいう『資産の譲渡に要した費用』に該当する」と主張してきたことに対応するものである。
争点2について、原告の主張は、第1審・控訴審いずれも斥けられているが、上告審(最高裁)は、本件を上告審として受理した段階で、「譲渡費用該当性」という仮定主張は重要でないとして斥けているため、争点1の「取得費該当性」に絞って判断されることになった。
争点1 本件手数料は、所得税法38条1項にいう「譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費」に該当するか。
争点2 本件手数料は、所得税法33条3項にいう「資産の譲渡に要した費用」に該当するか。
下級審の判示と原告が上告審(最高裁)で主張したこと
争点1について下級審(東京地裁・東京高裁)の判示は次のようなものであった。
第1審 請求棄却 東京地裁民事3部 平成12年(行ウ)57号平12.12.21判決言渡
所得税法が贈与による資産の所有権移転の場合における譲渡所得課税を繰り延べ、その後、当該資産が受贈者の支配を離れて他に移転する機会をとらえて、贈与者の取得の時以来清算されることなく蓄積されてきた資産の増加益を課税の対象としているのであるから、右増加益の算出上、譲渡による収入金額から控除すべき「資産の取得に要した金額」は、贈与者の取得の時において当該資産の客観的価格を構成すべき取得代金の額及び当該資産を取得するための付随費用でなければならない。
すなわち、所得税法60条により、贈与の前後を通じて贈与者が引き続き当該資産を所有していたものとみなされる以上、譲渡所得の算出に当たっては、贈与の事実はなかったものと考えるべきであり、そうである以上受贈者が自己への所有権移転のために支払った費用も一切無視するほかない。
本件手数料は、贈与者である父による本件会員権を取得するための付随費用でもないから、本件会員権との関係で、所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した費用」ということはできない。
控訴審 控訴棄却 東京高裁第9民事部 平成13年(行コ)12号平13.6.27判決言渡
(前略)「資産の取得に要した金額」とは、贈与者の取得の時において当該資産の客観的価格を構成すべき取得代金の額及び当該資産を取得するための付随費用と解すべきである。
本件手数料が、このような「資産の取得に要した金額」に当たるか否かを検討するに、本件会員権は、控訴人が父から贈与を受けたものであり、本件手数料は、本件会員権の名義を父から控訴人に書き換える際の名義書換手数料であるから、贈与者である父が本件会員権を取得した時点における本件会員権の客観的価格を構成するものではないし、父が本件会員権を取得するための付随費用でもない。したがって、本件手数料は、本件会員権との関係で、所得税法38条1項にいう資産の取得費に当たると解することはできない。(略)
受贈者が所有する資産についての譲渡所得課税においては、所得税法60条1項により、贈与の前後を通じて贈与者が引き続き当該資産を所有していたものとみなされるのであるから、課税庁としては、譲渡所得金額を算定するに当たり、中間の贈与の事実はなかったものと扱う以外になく、そうであれば、受贈者が自己への所有権移転のために支払った費用があったとしても、それを一切無視せざるを得ないことになる。
そうすると、本件譲渡所得金額の計算においては、控訴人が父から本件会員権の贈与を受けた事実も、その際に控訴人が本件手数料を支払った事実も、一切なかったものとみなすことになる。
下級審の判断に対して、上告人は次のように主張して、上告審を展開した。(弁論要旨より抜粋)
第1 譲渡所得とは何か(所得税法33条3項、38条1項の解釈)
所得税法の根底には、純所得に対して課税する考え方がある。他方、譲渡所得の本質は所有資産の価値の増加益であるという見方がある。(略)
しかるに被上告人は、所得税法60条1項の「その者が引き続きこれを所有していたものとみなす」との文言のみをもって、贈与によって取得した資産については受贈時の付随費用は取得費にあたらないと主張するにとどまり、贈与等によって取得した資産の譲渡所得の金額の算出上、受贈時における付随費用を控除しない合理的根拠を全く主張していない。このことをもってしても、贈与等によって取得した資産の譲渡所得の金額の算出にあたって受贈時の付随費用を控除しない合理的根拠が存在しないことは明らかである。
第2 所得税法60条1項の解釈
1. 所得税法60条1項の沿革及び立法趣旨
所法60条1項の立法趣旨は、「みなし譲渡課税」を廃止し、贈与者における課税を受贈者に肩代わりさせるところにあるのであり、それ以上でも以下でもない。
いわんや、「みなし譲渡課税」の下では当然控除が可能であった付随費用を控除しないことを目的とするものではない。
したがって、所得税法60条1項の立法趣旨を前提とする限り、贈与等によって取得した資産の譲渡所得金額の算出上、受贈時に支出した付随費用を控除しないという解釈は導き得ない。
2. 所得税法60条1項の文言解釈
所法60条1項からは、贈与者の取得時から受贈者の譲渡時までの増加益を把握する趣旨であることは明確であるが、さらに進んであえて贈与の事実そのものを否定する趣旨まで読むことはできない。
3. 有償譲渡との関係
仮に譲渡所得の本質を資産の増加益とみたとしても、有償譲渡と無償譲渡の場合で増加益が異なるというのは明らかに合理性がない。
また、客観的に測定されるべき課税物権たる所得の金額が有償譲渡と無償譲渡の場合で異なるのは公平でも公正でもない(この部分の主張については、上告受理申立理由書(あるいは、原審における鑑定意見書)において、事例を設けて分析し、「A→B→Cで譲渡があった場合に、A→B間の譲渡が売買か贈与かで、清算される譲渡所得の額が異なるのは、公平でも公正でもない。」としている。)。
かかる視点からも、贈与等の場合に、受贈時の付随費用を控除しないという解釈には合理性がない。
4. 所得税法38条1項との関係
取得代金については、所得税法60条1項により、贈与者のそれを引継ぐとしても、資産の取得に要した付随費用については、受贈者にとって、その資産を使用できるようにするまでの費用として把握されるべきものであるから、受贈時の付随費用は当然に取得費にあたるというべきである。
第3 代償分割に関する最高裁判決との比較
被上告人は代償分割に関する平成6年最高裁判決を自己に有利に援用するが、同判決は、遺産分割の効果は相続開始時に遡ることから、相続人間の譲渡を観念することはできず、したがって、代償金は取得代金にはあたらないとしたものであり、現実の贈与が存在する本件とは全く事案が異なる。
また、代償金は、遺産分割において、相続人間の公平を図るための調整金(たとえば、近い将来に不動産を処分する見込みがある場合には、通常、取得価額の引継ぎも考慮した上で決定される。)であり、自己の相続分を超える部分を相続するための手続費用でもないから、資産の取得に際しての付随費用にもあたらない。
第4 本件手数料が取得費にあたること
本件会員権の場合、これを譲り受けた者が、本件クラブに対して会員としての権利を行使するためには、ゴルフ場経営会社の承認を得て会員名義を書き換え、会員たる地位を取得する必要があるのであるから、これに要する名義書換手数料は当然に取得費にあたる。
なお、実務上も、有償譲渡によってゴルフ会員権を取得した場合、取得時に支出した名義書換手数料は、取得費として扱われており、無償譲渡によって取得した場合にこれと別異に解する理由はない。
したがって、本件手数料は、譲渡所得の算定上、上告人の総収入金額から控除すべき取得費にあたる。
譲渡所得の本質―キャピタル・ゲイン課税か?純所得課税か?
本件では、大阪府立大学の田中治教授が原告側の鑑定意見書を提出している。その内容は、税務事例研究vol.65「資産の取得価額をめぐる近時の紛争例」(財団法人 日本税務研究センター)の事例(1)とほぼ同旨となっている。田中教授は、税務事例研究vol.36「譲渡所得課税における取得費」においても譲渡所得課税における取得費の問題を取り上げている。
原告側では、「譲渡所得の本質は純所得と考えるべきである。」とし、「仮に、キャピタル・ゲインと考えるとしても、純所得としての考え方を大前提に置きながら、キャピタル・ゲインの観点から修正されていると考えるべき」と主張している。
ここでのキャピタル・ゲイン課税と純所得課税は下表のように考えられるが、原告側は、「資産の取得に要した金額」に資産を取得するために支出した付随費用の額も含まれるとするのは、「現行所得税法が純所得課税の考え方を反映したものである。」と主張している。
控訴審判決は、下表のキャピタル・ゲイン課税の判示に続いて、「『資産の取得に要した金額』には、当該資産の客観的価格を構成すべき取得代金の額のほか、登録免許税、仲介手数料等当該資産を取得するための付随費用の額も含まれると解される。」と判示しているが、田中教授がキャピタル・ゲイン課税(客観価値説)について述べているところでは、「この考え方(客観価値説)によれば、資産の保有に要した費用は、譲渡収入から控除することはできない、とされるであろう。また、おそらく、資産の譲渡に要した費用も、資産の客観的価額を左右するものではないから控除できない、とされるであろう。」としている。
上告人・田中教授は、控訴審判決がいう「キャピタル・ゲイン課税」のもつ現行所得税法との不整合を指摘することで、最高裁がより「純所得課税」に近い判断を下すことになったといえるだろう。
また、有償譲渡と無償譲渡との比較について、事例を設けて主張するなど、租税実務として定着していた贈与時等の付随費用を無視する取扱いの問題点を解き明かしている。
| キャピタル・ ゲイン課税 | 譲渡所得の本質は、キャピタル・ゲイン、すなわち、所有資産の価値の増加益であって、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得と見て、その資産が譲渡によって所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、その所有期間中の増加益を課税しようとするものである。(控訴審判決より) |
| 純所得課税 | 「実現した譲渡収入に対応するすべての費用要素を控除すべし」とする考え方。(上記田中治教授「譲渡所得課税における取得費」より) |
代償分割に関する最高裁判決との比較
本件の最高裁判決では、平成6年9月13日の最高裁判決との関連も実質的な争点となっている。すなわち、最高裁平成6年判決は、「相続(代償分割)で取得した不動産を他に売却したときの譲渡所得の計算に当たっては、相続前から引き続き所有していたものとして取得費を考えることになるから、代償金及びその交付のために銀行から借り入れた借入金の利息相当額を相続財産の取得費に算入することはできない。」と判示していた。
この判示をもって、課税庁は、贈与・相続時の付随費用の「取得費該当性」を認めないことの論拠としてきた。
最高裁の判例に反することにはなるが、「代償金は取得費を構成する。」との考え方も十分に成立する。贈与・相続時の付随費用の「取得費該当性」を主張するのであれば、「代償金の取得費該当性」といった問題を巻き込んで主張するという争い方も考えられたことだろう。しかし、上告人は、あえて判例変更を求める主張を行わず、平成6年判決は、代償金が取得費にあたるという納税者の前提にある「相続分の売買」という主張を排斥した事案であるとして、本件とは事案を異にすることを主張した。 上告人の主張を受ける形で、本件の最高裁判決は平成6年判決との整合性には触れられていない。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















