解説記事2005年03月14日 【解説】 LLPの導入と問題点(2005年3月14日号・№106)
解説
LLPの導入と問題点
税理士 高橋昭彦
1 はじめに
1 LLPの概要
①LLPの導入
平成17年2月4日、有限責任事業組合契約に関する法律案(以下「法案」と呼ぶ)が閣議決定された。LLPとの単語が新聞紙面に載るようになり、夏ごろにも成立し、施行されそうである。この記事からは、LLP自体は法人税又は所得税を納める必要がなく、LLPの損益を組合員(出資者)側で課税することになる。
今まで会社で法人税課税され、配当を出すと配当金に所得税が課税されるという二重課税(一部は配当控除で減殺)の状態だったオーナー経営者も注目しているようである。
筆者の所にも既に問い合わせが来ており、そもそもクライアントにこの制度を勧めることができるのか。この制度をクライアントに導入すると、どのような問題が生じるかについて検討を行った。
②有限責任事業組合制度の創設の提案
昨年暮れ、経済産業省より「有限責任事業組合制度の創設の提案」(以下「提案」と呼ぶ)と題される文章が公表された。これによると有限責任事業組合制度(以下「LLP」と呼ぶ)は以下の特徴を持つことになる。
・出資者が出資額までしか事業上の責任を負わない。(有限責任制)
・出資者が自ら経営を行うので組織内部の取り決めは自由に決めることができる。(内部自治原則)
・LLPには課税されずに、その出資者に直接課税される。(構成員課税制度)
以上の3つの特徴を持つことになり、日本では新しいタイプの事業体である。
さらに、不動産の所有について、LLPの肩書き付登記を可能とする方向で検討が進められている。
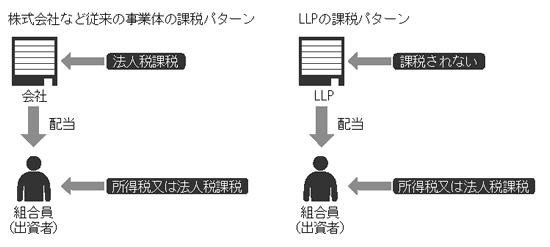
③LLP制度の目的
LLPはどのような利用方法が期待されて作られる制度なのだろうか。この点については経済産業省のHPにて「有限責任事業組合制度(日本版LLP研究会)に関する研究会」の議事録要旨が公表されている。これを見ると、大企業同士・大企業と中小企業あるいは個人を交えたジョイント・ベンチャー、弁護士事務所や会計士事務所の組織体、産学連携やベンチャー企業などにニーズがあるようである。
この制度を利用し、実際に所得計算をする立場から見ると、どのように見えるだろうか。どのような法整備が最低限必要となるのであろうか。
LLPは民法上の組合と類似する制度であり、組合に関する民法の規定が数多く準用される。ただし、民法上の組合は組合員(出資者)が無限責任であるのに対し、LLPは有限責任である点がもっとも異なる。
税制も民法組合と同様あるいは類似すると思われるので、以下では民法組合の税制を引用することが多くなる。民法の組合契約とは「各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。(民法667条)」とされている。
なお、LLPも組合契約の一種であり、LLPという法人格ができるわけではない。
2 税制改正
下記2で概要を説明するが、LLPは構成員課税(パス・スルー課税などとも呼ばれる)という制度が採用される予定である。構成員課税については、特に米国のLLCを題材に、多角的に立法論的検討が行われている。
しかし、今年の「所得税法等を一部改正する法律案(以下「改正所得税法案」という)」では、構成員課税について抜本的改正はなかった。 LLPについては以下のような規定が新設される。
・有限責任事業組合契約に関する法律の制定に伴い、有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書の提出制度等の整備を図ることとする。
・有限責任事業組合の組合員の組合損失額について、その出資の価額を基礎として計算した金額を超える部分の金額は、必要経費及び損金の額に算入しないこととする(注1)。
(以上「法律案要綱」より)
民法組合や匿名組合についても、損失の額について制限が設けられている。レバレッジドリースなどについて訴訟となっているケースに立法的に対応するものであろう(例えば名古屋地裁平成16年10月28日 平成15年(行ウ)第26ないし第31号)。
3 検討の目的
以上のように構成員課税について、一部損金(必要経費)算入規制が創設されるが、いずれも大きな法改正ではない。LLPについても現行法がベースになる。従って、米国で導入されているような本格的な構成員課税が導入、との立法は予定されていない。
構成員課税の計算は、まず「LLPの所得金額」の計算から始まる。
そこで、本稿では実務的観点から、この「LLPの所得金額」を計算する上で、どのような問題が生ずるか検討してみたい。
なお、まだ存在しない法律についての検討のため、以下の記述は、「提案・要綱・法案」に記述されている、あるいは一般に想定されているものをベースとした。
2 税制の概要
1 構成員課税の問題点
「提案」では、LLPは構成員課税が行われるとしている。構成員課税は、諸外国で例を見ることができる。しかし、日本では組合や匿名組合など、ごくわずかに利用されている例があるのみで、法令等の手当てもほとんどなされていない。
構成員課税については、主に下記のような点が立法論として議論されている。
・所得の配賦はどのような基準で行われるべきか
・家族間での所得移転に利用されないか(ファミリーパートナーシップの問題)
・現物出資時、あるいは社員の退社による払戻時にどのような課税を行うべきか
・課税期間を任意に設定することにより、課税の延期を図ることはないか
・構成員課税の事業体が他の構成員課税の事業体に出資することにより、永遠に課税されないことにならないか
・個人の出資者に配賦された所得の所得区分はどのようになるか
以上のような点が検討されている。本稿では、上記のような立法論ではなく、今年の税制改正を踏まえてLLPを導入した際の実務上の問題を検討することとする。
2 構成員課税
ここでまず、LLPを題材に一般に言われている構成員課税について見てみたい。LLPの所得には、所得税又は法人税、地方税の所得割は、LLPに課税されない。この所得は、構成員(出資者)に直接課税される。つまりLLP自体は納税義務者とはならないことになる。
以下、簡単な例を示す。
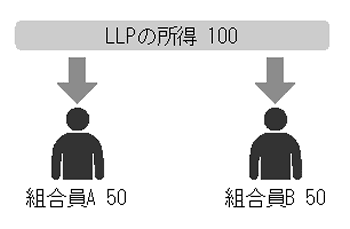
上記のように、LLPの所得は各組合員(構成員)に配賦され、LLPは納税義務者とならず、組合員AおよびBに配賦された所得が、各自の独自の所得と合算されて課税される。LLPの組合員にLLPがなることはない。(注2)
なお、「配賦」とは実際に配当が行われるか否かを問わず、計算上一定の割合で所得を割り当てることをいう。実際に配当を行うことを「分配」と呼ぶこととする。
このように割り当てる際の具体的方法について「提案」では下記のように説明している(3(3)柔軟な損益分配脚注2)。
出資者の課税所得の計算方法としては、総額方式(組合の損益のみならず、組合の収入・支出及び資産・負債も、それぞれ組合員に帰属する方式)、中間方式(組合の損益のみならず、組合の収入・支出が、それぞれ組合員に帰属する方式)、純額方式(組合の損益のみが組合員に帰属する方式)で行うことができる。
これは、現行の法人税基本通達14-1-2あるいは、所得税基本通達36・37共-20と共通している。
ここで問題となるのは「LLPの所得」である。LLPが法人であれば、法人税法の規定により「LLPの所得」を計算すればいいのであり、個人であれば所得税法の規定に従えば計算可能である。
しかし、LLPは組合契約に有限責任という制度を合わせたものであるため、税法上は「LLPの所得」と言うものの固有の計算式は存在しない。各組合員がそれぞれの立場で計算を行うことになる。
本稿では、上記の例で組合員AもしくはBが個人であるか、あるいは法人であるかによって組合の損益が異なることを確認する。そして所得税法または法人税法の規定により、LLPの所得の計算をすると100ではなく、110となったり、90となったりするケースがありえること。また、同じ法人である組合員であっても、経理規定等によって、LLPの所得が異なるものになってしまうこととその経理実務上の複雑さを挙げ、今後の実務上の困難を指摘する。
3 所得課税の問題点
1 問題の所在
LLPのように、事業体に直接課税されず、その組合員に所得が配賦されて課税される方式は、パス・スルー課税・構成員課税あるいは導管課税と呼ばれている。
アメリカでは長い実績がある方式であるが、租税回避が行われやすく、これを防止するために税制が複雑化している。
本稿では、上記2.2のとおり各組合員にとっての「LLPの所得」の相違点を取り上げる。
2 所得金額
LLPの所得が各組合員に配賦され、組合員において課税されるシステムのため、まず所得とは何かを決める必要がある。
所得税法において、所得あるいは所得金額は定義されておらず、総所得金額は、「各種所得の金額の計算」の規定により計算した金額の合計額とするとされている。
法人税法においても同様に所得の定義はない。ただその計算式が「内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額」と定められているのみである。
下記3で見ていくように、各個別規定は所得税法の「総所得金額」と法人税法の「所得の金額」は異なった金額となる。また、同じ個人間、あるいは法人間であっても、各組合員が採用する益金(総収入金額)の認識時期の相違、償却方法、圧縮記帳を採用するか否かなどにより「所得の金額」は異なる。おそらく実務では、下記のように2段階で所得金額を計算することになると思われる。
①取引実態をつかんでいるLLPにおいて相当程度の課税所得計算上の情報を各組合員に提供
②各組合員において、①の金額をもとに、各組合員の経理規定、個人か法人かの相違によりさらに調整をする
改正所得税法案にいう「組合員所得に関する計算書」とは①の段階のことを指すのか、あるいは②の部分まで考慮して行うのか、はっきりしない。改正所得税法案227条の2では「利益の額又は損失の額」といっているのみであり詳細は財務省令に委任されることになる。
上記のように、LLPの所得の金額あるいは所得金額を一つの計算式で求めることは不可能である。どのような点が相違するのか、その代表的な例を次に見ていくこととする。
3 所得税と法人税の相違点
①収入金額と益金の額の相違
所法36条では、「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする。」とされている。
法人税法では、22条により「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。」とされている。
このように両者の規定が異なっており、具体的には以下の点が相違する。
(A)無償による資産の譲渡又は役務の提供
まず法人税法において、無償による資産の譲渡が行われた場合、時価による譲渡があったものとされる。従って、その資産の時価が益金の額に算入される。
一方所得税法において、個人が無償による資産の譲渡を行った場合の取扱いは上記と異なる。個人間の譲渡の場合は贈与税の問題となり、所得税において収入金額を認識することはない。個人が法人に対して行った無償譲渡については所得税法59条により、時価による譲渡があったものとみなされる。
低額譲渡や無償による役務提供が行われた場合も法人税と所得税では異なる取扱いとなる。
(B)認識時期の相違
収入金額あるいは益金の額の計上時期も、所得税と法人税では異なる。代表的なものを以下に挙げる。
ア所得税と法人税
所得税法において、配当所得の収入金額の認識時期は、所基通36-4において具体的に定められている。一方法人税法においても、ほぼ同様の規定が法基通2-1-27に存在する。
しかし法基通2-1-28において、支払を受けた日の収益とすることを認めている点で所得税法と異なる。
法人組合員が、上記の特例を採用し、支払を受けた日に収益とする方法を採用している場合には、法人組合員と個人組合員の所得金額は異なることになる。
イ法人構成員間の相違
益金の認識時期の相違は、法人の組合員間でも問題となる。益金の認識時期は、特定の時期を定めず、継続適用を要件として合理的な時期を選択できるものが数多く存在するからである。
例えば、棚卸資産の認識時期については「出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする(法基通2-1-2)」とされる。
このように益金計上時期は、合理的な範囲で複数存在する。組合員A社と組合員B社では、異なる時期を益金計上時期と定められているケースがある。この場合は、LLPの取引による益金計上時期は、各組合員ごとに異なる日となる可能性がある。各組合員が、LLPの個々の取引まで確認し、それぞれの会社の益金計上時期に合わせる作業が必要となり、実務上煩雑である。
この他継続適用を要件に益金の認識時期が複数存在する規定は、委託販売、建設工事等、不動産の仲介あっせん報酬、運送収入、有価証券の譲渡、貸付金利子等、利益の配当、工業所有権等の使用料、など数多く存在する。
益金認識時期は、業種による慣行もあるため、特に異業種間で契約されたLLPにおいて大きな問題となることが多いと思われる。そこで益金認識時期については、LLP内で継続的統一的に取り扱えば、本体の組合員である法人と異なる時期に認識することも認められるとの取扱いを期待する。
(C)非課税所得の存在
所得税法においては、所法9条その他の条文により非課税規定が定められているものがある。これらの非課税規定の存在により、法人税と所得税の所得金額は異なった額となる。具体的には、所法9条16号の「損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金」などの規定である。
これらは法人税においては益金の額に算入され、一方所得税では非課税とされる。
②必要経費と損金の額の相違
所法37条において、「その年分の不動産所得の金額(一部省略)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。」としている。
一方法人税法では、22条において、「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
◆1 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
◆2 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
◆3 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの」とされている。
両者にも収入金額、益金の額の相違と同様に異なる点がある。具体例をいくつか挙げると下記のようになる。
(A)売上原価
所得税においては、売上原価についても債務の確定が要求(所基通37-1)されている。
ただし、個別に通達において別段の定め(所基通36・37共-4の2、47-17の2、47-18など)がある。
しかし、法人税においては、販売費、一般管理費については債務の確定が要求(法法22③二)されているが、売上原価については債務確定が求められていない(例えば法基通2-2-1、2-2-2、2-2-4など)。
LLPは、産学連携、大企業と中小企業あるいは個人を交えたジョイント・ベンチャーなどにその利用が期待されている(注3)。
したがって、現在のところ個人事業として想定されていない大規模な投資を伴う事業にLLPが進出するケースがありえる。この場合、所得税では債務確定を要求され、法人税では要求されないという相違が生ずる可能性がある。このような場合に個別に別段の定めをおいている所得税と、原則として債務確定を求めず、通達で例示している法人税とで、異なる取扱いとなることが予想される。
(B)減価償却資産
ア取得価額
法人が保険金により減価償却資産を取得した場合には、法法47条の規定により圧縮記帳を行うことができる。
しかし、個人にはこのような制度はなく、所法9①十六号の規定により非課税の取扱いを受けることができる場合があるのみである。ただし必要経費に算入される金額を補てんするための金額が除かれる。
このように減価償却資産の取得価額が法人税と所得税では異なる取扱いとなる。さらに除却資産の簿価や、取りこわしによる損失の金額が損金の額または必要経費となるか否かについても異なる取扱いとなる。
この他、より日常的に生じるであろう相違点として支払利息の取扱いがある。
法人税では、固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、損金の額に算入することができ、また固定資産の取得価額に算入することもできる(法基通7-3-1の2)。
一方所得税では、原則として必要経費に算入され、その資産の使用開始の日までの期間に対応する金額は取得価額に算入することができるとしている(所基通37-27)。
しかし、事業をまったく営んでいない者が、新たに事業を開始する際に支出する事業開始前の利子は家事費となり必要経費に算入できない。もちろん資産の取得価額とすることは可能である(所基通38-8)(注4)。LLPの契約当初の初期投資について、法人と個人では異なる取扱いになる可能性がある。
以上のように、減価償却資産の取得価額は、法人税と所得税で異なる。
イ減価償却費の損金経理
法人税においては、減価償却費として損金の額に算入するために、損金経理が要求されている(法法31①)。
しかし、所得税においてはそのような定めはない。したがって、法人税の規定による償却限度額が、LLPにおいて損金経理した償却費より大きい場合には、法人税法上損金の額に算入されないこととなる(償却不足が生ずる)。所得税法上は、償却費の額はLLPの計算と異なったとしても、あくまで所得税法の規定により計算した額が必要経費となる。
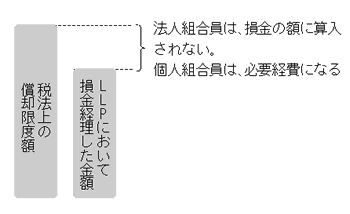
(C)その他
このほかに交際費、寄付金、諸会費(ロータリークラブの会費等)など、あらゆる点で法人税と所得税では異なる規定がある。
③小括
以上主だったものを取り上げたが、上記以外にも多々法人税と所得税で取扱いが異なる点があると思われる。
また、本稿では検討しないが、所得税においては所得区分の問題もある。LLPが獲得した所得は、個人組合員の所得区分上どの所得区分に該当することとなるかという点である。LLPの所得を現行の10種類の所得区分のそれぞれに当てはめることになるのであろう。この場合、間接経費をどの所得区分の経費とするか、収入の区分は実務上可能か、などの検討が必要になる。
これらを適正に経理し、修正を図るにはかなり複雑な経理と税務知識が要求されることとなる。この点については最後に若干の提案をする。
4 給与
個人組合員が、LLPから業務執行の対価として給与の支給を受けることは可能であろうか。
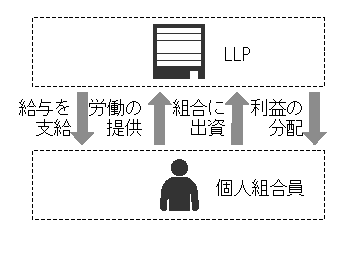
おそらく、このような給与の支払は認められないものと予想している(注5)。なお、LLPは労務出資が禁止されている(注6)が、上記の問題はこれとは別に生じうる。
このような場合には給与の支給に代え、利益の分配につき個人組合員に対し、優先的配当を認めるなどの契約で対応することとなろう。
しかし産学連携など研究開発型LLPの場合、当初の数年間は赤字となり分配可能額(法案第34条)がなく、個人組合員に対する配当が不可能となることが考えられる。このような場合、個人組合員の生活の経済的基礎をどのように確保するかが問題となる。
分配可能額の計算は財務省令に委任されており、現段階で詳細は不明である。しかし、法律案要綱第19「財産分配の制限」によれば「 剰余金に相当する額を超えて組合財産を分配するには、総組合員の同意」を要求している。
ここから、分配可能額は剰余金相当額を原則としている。これを超える場合には、総組合員の同意が必要である。しかしこの同意によっても、純資産額の範囲内でしか分配することはできない(法案第34条括弧書き)。
また、上記法案上の制限のほか、税務上租税回避を防止するための規制が入る可能性が残る。個人がLLPに出資する場合、以上のような点も考慮しておく必要がある。
5 消費税と経理
消費税の経理処理について国税庁は「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて平成元年3月29日」「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて平成元年3月1日」という個別通達を出している。
これによれば、免税事業者等の経理処理は税込経理方式を採用することとされている。
多くの企業(特に上場企業)において税抜経理方式が採用されているものと思われ、組合員によって異なる経理処理が要求されることになる。また、同じ組合員でも、課税期間が異なるごとに異なる経理方式を採用することもありえる。
経理処理により、減価償却資産の取得価額、交際費の額等多くの相違が生じる。この点については、所得税と法人税の相違ではなく、同じ法人の組合員間でも生じうる差異である。
個人の研究者と法人がLLP契約を行う場合は、個人研究者は免税事業者であることが多いものと思われる。上記の相違点は実務上頻繁に生ずるであろう。
6 少額減価償却資産
例えば、LLPが30万円の減価償却資産を購入したとする。この場合、組合員にその資産の取得価額が配賦計算される。配賦比率によっては、ある組合員は10万円未満で損金となり、別の組合員は資産計上となる。このように、LLP自体は資産として経理していても、組合員側で修正経理が必要となるケースが多いであろう。(注7)
7 所得課税のまとめ
以上見てきたとおり、法人税と所得税において、「所得金額」とは異なったものであり、両者の金額が一致することはまれであろう。
おそらくLLPの帳簿はLLP自体が作成し、保存するものと思われる。そこで、詳細な資料が手元にない組合員が、独自に法人所得または個人所得を計算する資料を作成することは不可能であろう。
このため、LLPにおいて、法人所得および個人所得計算の資料をそれぞれ作成する必要がある。さらに同じ法人税用あるいは所得税用の所得計算資料であっても、税込経理と税抜経理の資料を提供する必要がある。
益金の認識時期など継続適用が要求される部分については、組合員本体の処理とはなれて、LLP内部において継続適用すれば認められる、との取扱いが期待される。
組合員側でも、独自にLLPから提供された資料を修正するなど、複雑な経理が要求されるものと思われる。
以上、代表的な例を見てきた。通達改正により簡素化が可能なものもあるが、これによってもなお組合員間の差異が生ずる。
4 シュミレーション
典型的なパターンを挙げて、所得の違いの具体例を検討する。
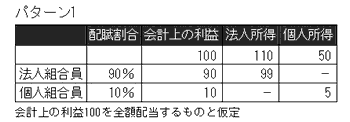
法人組合員は、利益を超える所得9(99-90)を別表4で加算留保する。
個人組合員は、非課税所得が多額にあったパターンを想定している。この場合5はどの所得区分に属することになるのであろうか。
上記個人組合員の内訳を、利子所得1・不動産所得2・事業所得2・非課税所得7・不動産の譲渡所得△2(損益通算不可)と仮定する。
この場合、個人所得5の部分については、それぞれ利子所得が1、不動産所得が2、事業所得が2、課税されない利益が5となるのであろう。
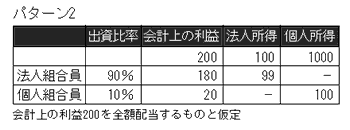
法人組合員は、法人所得を超える81(180-99)の部分について別表4で減算留保(あるいは一部流出もありえる)する。
個人組合員は、多額の不動産の譲渡損失が生じているケースを想定している。
上記個人組合員の内訳を、事業所得100、不動産の譲渡所得△80(損益通算不可)と仮定する。この場合は、上記個人所得100がそのまま事業所得とされ、課税される。実際には20の配当しか受けれないため、納税資金にも事欠く結果となる。
5 最後に
LLPの制度の導入を実際に検討してみると、数多くの実務上の難しさに遭遇する。LLPの経理担当者は、法人税の知識のみならず、所得税の知識も必要とされ、なおかつ各組合員の会社内部の益金認識時期に関する規定等の経理規定にまで通じている必要がある。
しかしこれまで見てきた問題点は、従来から組合契約等を行っている場合には存在していた問題である。従来、ジョイントベンチャーなど法人間で組まれるケースは多々あったと思われるが、これに個人の組合員が絡むことにより、数段複雑さを増すことになりそうである。さらに、有限責任制度が導入されるため、従来と比べると多くの事業者がこの制度を採用する可能性があり、今まで表面化しなかった点もクローズアップされることとなると思われる。
最後に若干の提案をしたい。上記に述べてきた所得金額計算上の困難さに対応するため、現行法の措法40条の4に類似する規定を設けてはどうだろうか。つまり、個人所得の計算において、当該LLPの所得を法人税の例によって計算することとする。その所得区分を事業所得(注8)(措法40条の4では雑所得)に係る収入金額とみなす。以上の2点を付け加えることで、多くの問題を解決することができるように思う。
(注)
(注1)
負担するリスクの範囲を損失の取込限度額とする趣旨であるのであれば、出資額を上回った場合にも、保証債務等があればその範囲で損失の取込を認めるべきである。
(注2)
法案第3条では「有限責任事業組合契約(以下「組合契約」という。)は、個人又は法人が出資して」とされている。従って、LLPはLLPに出資することはできないものと思われる。
(注3)
経済産業省HP、事業組合制度(日本版LLP研究会)に関する研究会第1回議事要旨http://www.meti.go.jp/policy/economic_industrial/gather/0000611/index.html参照
(注4)
所得税基本通達逐条解説平成16年版(財)大蔵財務協会P319参照
(注5)
本稿の予想と異なり、給与の支払を認めるものとして、最高裁平成13年7月13日第2小法廷判決、平成12年(行ツ)第13号、所得税更正処分取消請求事件、原判決破棄自判、判例時報1763号195頁・判例タイムズ1073号139頁
(注6)
提案1(2)②において「労務出資の禁止(ただし、労務などの提供を反映した柔軟な損益分配は可能、2.(2)、3.(3)参照)」としている。
法案では第11条において「組合員は、金銭その他の財産のみをもって出資の目的とすることができる。」としている。
(注7)
この問題については、取扱いがはっきりしているわけではない。組合に財産を現物出資した場合、財産の共有となり譲渡所得課税され、一つの財産を各組合員が共有(合有)する関係となる。この点を従来からある共有物についての過去の組合に関する質疑応答を参考として、取扱いの予想をした。
なお、現物出資時の課税については提案において「現物出資に関しては、原則として組合員間で譲渡が行われることから譲渡益課税の対象となるが、現物出資時の課税の繰り延べについては、将来の実ニーズ及び個別の事情に応じて対応すべきと考える。」としている。
(注8)
措法40条の4では「雑所得とみなし」ているが本稿の提案では事業所得としている。
これは、LLPの利用が期待されている事業を意識したためである。
LLPはジョイントベンチャーや産学連携に使われることが期待されている。この場合研究開発期間の当初数年間は赤字が見込まれる。もし雑所得とみなされれば、この赤字は税制上なんらの手当てもないことになり、黒字となった瞬間から課税されてしまう。そこで、事業所得とみなすか、何らかの方法で赤字の繰越を認める制度が必要となる。
LLPの導入と問題点
税理士 高橋昭彦
1 はじめに
1 LLPの概要
①LLPの導入
平成17年2月4日、有限責任事業組合契約に関する法律案(以下「法案」と呼ぶ)が閣議決定された。LLPとの単語が新聞紙面に載るようになり、夏ごろにも成立し、施行されそうである。この記事からは、LLP自体は法人税又は所得税を納める必要がなく、LLPの損益を組合員(出資者)側で課税することになる。
今まで会社で法人税課税され、配当を出すと配当金に所得税が課税されるという二重課税(一部は配当控除で減殺)の状態だったオーナー経営者も注目しているようである。
筆者の所にも既に問い合わせが来ており、そもそもクライアントにこの制度を勧めることができるのか。この制度をクライアントに導入すると、どのような問題が生じるかについて検討を行った。
②有限責任事業組合制度の創設の提案
昨年暮れ、経済産業省より「有限責任事業組合制度の創設の提案」(以下「提案」と呼ぶ)と題される文章が公表された。これによると有限責任事業組合制度(以下「LLP」と呼ぶ)は以下の特徴を持つことになる。
・出資者が出資額までしか事業上の責任を負わない。(有限責任制)
・出資者が自ら経営を行うので組織内部の取り決めは自由に決めることができる。(内部自治原則)
・LLPには課税されずに、その出資者に直接課税される。(構成員課税制度)
以上の3つの特徴を持つことになり、日本では新しいタイプの事業体である。
さらに、不動産の所有について、LLPの肩書き付登記を可能とする方向で検討が進められている。
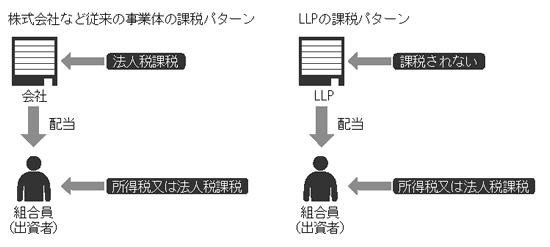
③LLP制度の目的
LLPはどのような利用方法が期待されて作られる制度なのだろうか。この点については経済産業省のHPにて「有限責任事業組合制度(日本版LLP研究会)に関する研究会」の議事録要旨が公表されている。これを見ると、大企業同士・大企業と中小企業あるいは個人を交えたジョイント・ベンチャー、弁護士事務所や会計士事務所の組織体、産学連携やベンチャー企業などにニーズがあるようである。
この制度を利用し、実際に所得計算をする立場から見ると、どのように見えるだろうか。どのような法整備が最低限必要となるのであろうか。
LLPは民法上の組合と類似する制度であり、組合に関する民法の規定が数多く準用される。ただし、民法上の組合は組合員(出資者)が無限責任であるのに対し、LLPは有限責任である点がもっとも異なる。
税制も民法組合と同様あるいは類似すると思われるので、以下では民法組合の税制を引用することが多くなる。民法の組合契約とは「各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。(民法667条)」とされている。
なお、LLPも組合契約の一種であり、LLPという法人格ができるわけではない。
2 税制改正
下記2で概要を説明するが、LLPは構成員課税(パス・スルー課税などとも呼ばれる)という制度が採用される予定である。構成員課税については、特に米国のLLCを題材に、多角的に立法論的検討が行われている。
しかし、今年の「所得税法等を一部改正する法律案(以下「改正所得税法案」という)」では、構成員課税について抜本的改正はなかった。 LLPについては以下のような規定が新設される。
・有限責任事業組合契約に関する法律の制定に伴い、有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書の提出制度等の整備を図ることとする。
・有限責任事業組合の組合員の組合損失額について、その出資の価額を基礎として計算した金額を超える部分の金額は、必要経費及び損金の額に算入しないこととする(注1)。
(以上「法律案要綱」より)
民法組合や匿名組合についても、損失の額について制限が設けられている。レバレッジドリースなどについて訴訟となっているケースに立法的に対応するものであろう(例えば名古屋地裁平成16年10月28日 平成15年(行ウ)第26ないし第31号)。
3 検討の目的
以上のように構成員課税について、一部損金(必要経費)算入規制が創設されるが、いずれも大きな法改正ではない。LLPについても現行法がベースになる。従って、米国で導入されているような本格的な構成員課税が導入、との立法は予定されていない。
構成員課税の計算は、まず「LLPの所得金額」の計算から始まる。
そこで、本稿では実務的観点から、この「LLPの所得金額」を計算する上で、どのような問題が生ずるか検討してみたい。
なお、まだ存在しない法律についての検討のため、以下の記述は、「提案・要綱・法案」に記述されている、あるいは一般に想定されているものをベースとした。
2 税制の概要
1 構成員課税の問題点
「提案」では、LLPは構成員課税が行われるとしている。構成員課税は、諸外国で例を見ることができる。しかし、日本では組合や匿名組合など、ごくわずかに利用されている例があるのみで、法令等の手当てもほとんどなされていない。
構成員課税については、主に下記のような点が立法論として議論されている。
・所得の配賦はどのような基準で行われるべきか
・家族間での所得移転に利用されないか(ファミリーパートナーシップの問題)
・現物出資時、あるいは社員の退社による払戻時にどのような課税を行うべきか
・課税期間を任意に設定することにより、課税の延期を図ることはないか
・構成員課税の事業体が他の構成員課税の事業体に出資することにより、永遠に課税されないことにならないか
・個人の出資者に配賦された所得の所得区分はどのようになるか
以上のような点が検討されている。本稿では、上記のような立法論ではなく、今年の税制改正を踏まえてLLPを導入した際の実務上の問題を検討することとする。
2 構成員課税
ここでまず、LLPを題材に一般に言われている構成員課税について見てみたい。LLPの所得には、所得税又は法人税、地方税の所得割は、LLPに課税されない。この所得は、構成員(出資者)に直接課税される。つまりLLP自体は納税義務者とはならないことになる。
以下、簡単な例を示す。
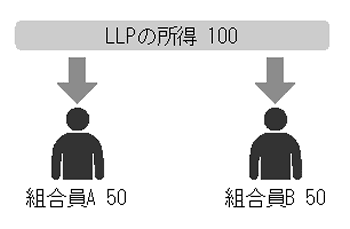
上記のように、LLPの所得は各組合員(構成員)に配賦され、LLPは納税義務者とならず、組合員AおよびBに配賦された所得が、各自の独自の所得と合算されて課税される。LLPの組合員にLLPがなることはない。(注2)
なお、「配賦」とは実際に配当が行われるか否かを問わず、計算上一定の割合で所得を割り当てることをいう。実際に配当を行うことを「分配」と呼ぶこととする。
このように割り当てる際の具体的方法について「提案」では下記のように説明している(3(3)柔軟な損益分配脚注2)。
出資者の課税所得の計算方法としては、総額方式(組合の損益のみならず、組合の収入・支出及び資産・負債も、それぞれ組合員に帰属する方式)、中間方式(組合の損益のみならず、組合の収入・支出が、それぞれ組合員に帰属する方式)、純額方式(組合の損益のみが組合員に帰属する方式)で行うことができる。
これは、現行の法人税基本通達14-1-2あるいは、所得税基本通達36・37共-20と共通している。
ここで問題となるのは「LLPの所得」である。LLPが法人であれば、法人税法の規定により「LLPの所得」を計算すればいいのであり、個人であれば所得税法の規定に従えば計算可能である。
しかし、LLPは組合契約に有限責任という制度を合わせたものであるため、税法上は「LLPの所得」と言うものの固有の計算式は存在しない。各組合員がそれぞれの立場で計算を行うことになる。
本稿では、上記の例で組合員AもしくはBが個人であるか、あるいは法人であるかによって組合の損益が異なることを確認する。そして所得税法または法人税法の規定により、LLPの所得の計算をすると100ではなく、110となったり、90となったりするケースがありえること。また、同じ法人である組合員であっても、経理規定等によって、LLPの所得が異なるものになってしまうこととその経理実務上の複雑さを挙げ、今後の実務上の困難を指摘する。
3 所得課税の問題点
1 問題の所在
LLPのように、事業体に直接課税されず、その組合員に所得が配賦されて課税される方式は、パス・スルー課税・構成員課税あるいは導管課税と呼ばれている。
アメリカでは長い実績がある方式であるが、租税回避が行われやすく、これを防止するために税制が複雑化している。
本稿では、上記2.2のとおり各組合員にとっての「LLPの所得」の相違点を取り上げる。
2 所得金額
LLPの所得が各組合員に配賦され、組合員において課税されるシステムのため、まず所得とは何かを決める必要がある。
所得税法において、所得あるいは所得金額は定義されておらず、総所得金額は、「各種所得の金額の計算」の規定により計算した金額の合計額とするとされている。
法人税法においても同様に所得の定義はない。ただその計算式が「内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額」と定められているのみである。
下記3で見ていくように、各個別規定は所得税法の「総所得金額」と法人税法の「所得の金額」は異なった金額となる。また、同じ個人間、あるいは法人間であっても、各組合員が採用する益金(総収入金額)の認識時期の相違、償却方法、圧縮記帳を採用するか否かなどにより「所得の金額」は異なる。おそらく実務では、下記のように2段階で所得金額を計算することになると思われる。
①取引実態をつかんでいるLLPにおいて相当程度の課税所得計算上の情報を各組合員に提供
②各組合員において、①の金額をもとに、各組合員の経理規定、個人か法人かの相違によりさらに調整をする
改正所得税法案にいう「組合員所得に関する計算書」とは①の段階のことを指すのか、あるいは②の部分まで考慮して行うのか、はっきりしない。改正所得税法案227条の2では「利益の額又は損失の額」といっているのみであり詳細は財務省令に委任されることになる。
上記のように、LLPの所得の金額あるいは所得金額を一つの計算式で求めることは不可能である。どのような点が相違するのか、その代表的な例を次に見ていくこととする。
3 所得税と法人税の相違点
①収入金額と益金の額の相違
所法36条では、「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする。」とされている。
法人税法では、22条により「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。」とされている。
このように両者の規定が異なっており、具体的には以下の点が相違する。
(A)無償による資産の譲渡又は役務の提供
まず法人税法において、無償による資産の譲渡が行われた場合、時価による譲渡があったものとされる。従って、その資産の時価が益金の額に算入される。
一方所得税法において、個人が無償による資産の譲渡を行った場合の取扱いは上記と異なる。個人間の譲渡の場合は贈与税の問題となり、所得税において収入金額を認識することはない。個人が法人に対して行った無償譲渡については所得税法59条により、時価による譲渡があったものとみなされる。
低額譲渡や無償による役務提供が行われた場合も法人税と所得税では異なる取扱いとなる。
(B)認識時期の相違
収入金額あるいは益金の額の計上時期も、所得税と法人税では異なる。代表的なものを以下に挙げる。
ア所得税と法人税
所得税法において、配当所得の収入金額の認識時期は、所基通36-4において具体的に定められている。一方法人税法においても、ほぼ同様の規定が法基通2-1-27に存在する。
しかし法基通2-1-28において、支払を受けた日の収益とすることを認めている点で所得税法と異なる。
法人組合員が、上記の特例を採用し、支払を受けた日に収益とする方法を採用している場合には、法人組合員と個人組合員の所得金額は異なることになる。
イ法人構成員間の相違
益金の認識時期の相違は、法人の組合員間でも問題となる。益金の認識時期は、特定の時期を定めず、継続適用を要件として合理的な時期を選択できるものが数多く存在するからである。
例えば、棚卸資産の認識時期については「出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする(法基通2-1-2)」とされる。
このように益金計上時期は、合理的な範囲で複数存在する。組合員A社と組合員B社では、異なる時期を益金計上時期と定められているケースがある。この場合は、LLPの取引による益金計上時期は、各組合員ごとに異なる日となる可能性がある。各組合員が、LLPの個々の取引まで確認し、それぞれの会社の益金計上時期に合わせる作業が必要となり、実務上煩雑である。
この他継続適用を要件に益金の認識時期が複数存在する規定は、委託販売、建設工事等、不動産の仲介あっせん報酬、運送収入、有価証券の譲渡、貸付金利子等、利益の配当、工業所有権等の使用料、など数多く存在する。
益金認識時期は、業種による慣行もあるため、特に異業種間で契約されたLLPにおいて大きな問題となることが多いと思われる。そこで益金認識時期については、LLP内で継続的統一的に取り扱えば、本体の組合員である法人と異なる時期に認識することも認められるとの取扱いを期待する。
(C)非課税所得の存在
所得税法においては、所法9条その他の条文により非課税規定が定められているものがある。これらの非課税規定の存在により、法人税と所得税の所得金額は異なった額となる。具体的には、所法9条16号の「損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金」などの規定である。
これらは法人税においては益金の額に算入され、一方所得税では非課税とされる。
②必要経費と損金の額の相違
所法37条において、「その年分の不動産所得の金額(一部省略)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。」としている。
一方法人税法では、22条において、「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
◆1 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
◆2 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
◆3 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの」とされている。
両者にも収入金額、益金の額の相違と同様に異なる点がある。具体例をいくつか挙げると下記のようになる。
(A)売上原価
所得税においては、売上原価についても債務の確定が要求(所基通37-1)されている。
ただし、個別に通達において別段の定め(所基通36・37共-4の2、47-17の2、47-18など)がある。
しかし、法人税においては、販売費、一般管理費については債務の確定が要求(法法22③二)されているが、売上原価については債務確定が求められていない(例えば法基通2-2-1、2-2-2、2-2-4など)。
LLPは、産学連携、大企業と中小企業あるいは個人を交えたジョイント・ベンチャーなどにその利用が期待されている(注3)。
したがって、現在のところ個人事業として想定されていない大規模な投資を伴う事業にLLPが進出するケースがありえる。この場合、所得税では債務確定を要求され、法人税では要求されないという相違が生ずる可能性がある。このような場合に個別に別段の定めをおいている所得税と、原則として債務確定を求めず、通達で例示している法人税とで、異なる取扱いとなることが予想される。
(B)減価償却資産
ア取得価額
法人が保険金により減価償却資産を取得した場合には、法法47条の規定により圧縮記帳を行うことができる。
しかし、個人にはこのような制度はなく、所法9①十六号の規定により非課税の取扱いを受けることができる場合があるのみである。ただし必要経費に算入される金額を補てんするための金額が除かれる。
このように減価償却資産の取得価額が法人税と所得税では異なる取扱いとなる。さらに除却資産の簿価や、取りこわしによる損失の金額が損金の額または必要経費となるか否かについても異なる取扱いとなる。
この他、より日常的に生じるであろう相違点として支払利息の取扱いがある。
法人税では、固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、損金の額に算入することができ、また固定資産の取得価額に算入することもできる(法基通7-3-1の2)。
一方所得税では、原則として必要経費に算入され、その資産の使用開始の日までの期間に対応する金額は取得価額に算入することができるとしている(所基通37-27)。
しかし、事業をまったく営んでいない者が、新たに事業を開始する際に支出する事業開始前の利子は家事費となり必要経費に算入できない。もちろん資産の取得価額とすることは可能である(所基通38-8)(注4)。LLPの契約当初の初期投資について、法人と個人では異なる取扱いになる可能性がある。
以上のように、減価償却資産の取得価額は、法人税と所得税で異なる。
イ減価償却費の損金経理
法人税においては、減価償却費として損金の額に算入するために、損金経理が要求されている(法法31①)。
しかし、所得税においてはそのような定めはない。したがって、法人税の規定による償却限度額が、LLPにおいて損金経理した償却費より大きい場合には、法人税法上損金の額に算入されないこととなる(償却不足が生ずる)。所得税法上は、償却費の額はLLPの計算と異なったとしても、あくまで所得税法の規定により計算した額が必要経費となる。
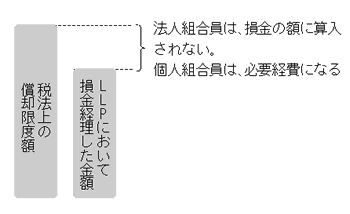
(C)その他
このほかに交際費、寄付金、諸会費(ロータリークラブの会費等)など、あらゆる点で法人税と所得税では異なる規定がある。
③小括
以上主だったものを取り上げたが、上記以外にも多々法人税と所得税で取扱いが異なる点があると思われる。
また、本稿では検討しないが、所得税においては所得区分の問題もある。LLPが獲得した所得は、個人組合員の所得区分上どの所得区分に該当することとなるかという点である。LLPの所得を現行の10種類の所得区分のそれぞれに当てはめることになるのであろう。この場合、間接経費をどの所得区分の経費とするか、収入の区分は実務上可能か、などの検討が必要になる。
これらを適正に経理し、修正を図るにはかなり複雑な経理と税務知識が要求されることとなる。この点については最後に若干の提案をする。
4 給与
個人組合員が、LLPから業務執行の対価として給与の支給を受けることは可能であろうか。
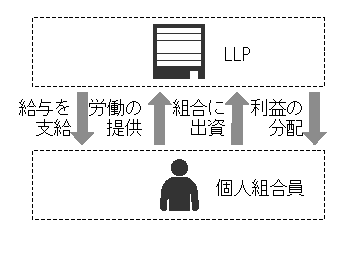
おそらく、このような給与の支払は認められないものと予想している(注5)。なお、LLPは労務出資が禁止されている(注6)が、上記の問題はこれとは別に生じうる。
このような場合には給与の支給に代え、利益の分配につき個人組合員に対し、優先的配当を認めるなどの契約で対応することとなろう。
しかし産学連携など研究開発型LLPの場合、当初の数年間は赤字となり分配可能額(法案第34条)がなく、個人組合員に対する配当が不可能となることが考えられる。このような場合、個人組合員の生活の経済的基礎をどのように確保するかが問題となる。
分配可能額の計算は財務省令に委任されており、現段階で詳細は不明である。しかし、法律案要綱第19「財産分配の制限」によれば「 剰余金に相当する額を超えて組合財産を分配するには、総組合員の同意」を要求している。
ここから、分配可能額は剰余金相当額を原則としている。これを超える場合には、総組合員の同意が必要である。しかしこの同意によっても、純資産額の範囲内でしか分配することはできない(法案第34条括弧書き)。
また、上記法案上の制限のほか、税務上租税回避を防止するための規制が入る可能性が残る。個人がLLPに出資する場合、以上のような点も考慮しておく必要がある。
5 消費税と経理
消費税の経理処理について国税庁は「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて平成元年3月29日」「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて平成元年3月1日」という個別通達を出している。
これによれば、免税事業者等の経理処理は税込経理方式を採用することとされている。
多くの企業(特に上場企業)において税抜経理方式が採用されているものと思われ、組合員によって異なる経理処理が要求されることになる。また、同じ組合員でも、課税期間が異なるごとに異なる経理方式を採用することもありえる。
経理処理により、減価償却資産の取得価額、交際費の額等多くの相違が生じる。この点については、所得税と法人税の相違ではなく、同じ法人の組合員間でも生じうる差異である。
個人の研究者と法人がLLP契約を行う場合は、個人研究者は免税事業者であることが多いものと思われる。上記の相違点は実務上頻繁に生ずるであろう。
6 少額減価償却資産
例えば、LLPが30万円の減価償却資産を購入したとする。この場合、組合員にその資産の取得価額が配賦計算される。配賦比率によっては、ある組合員は10万円未満で損金となり、別の組合員は資産計上となる。このように、LLP自体は資産として経理していても、組合員側で修正経理が必要となるケースが多いであろう。(注7)
7 所得課税のまとめ
以上見てきたとおり、法人税と所得税において、「所得金額」とは異なったものであり、両者の金額が一致することはまれであろう。
おそらくLLPの帳簿はLLP自体が作成し、保存するものと思われる。そこで、詳細な資料が手元にない組合員が、独自に法人所得または個人所得を計算する資料を作成することは不可能であろう。
このため、LLPにおいて、法人所得および個人所得計算の資料をそれぞれ作成する必要がある。さらに同じ法人税用あるいは所得税用の所得計算資料であっても、税込経理と税抜経理の資料を提供する必要がある。
益金の認識時期など継続適用が要求される部分については、組合員本体の処理とはなれて、LLP内部において継続適用すれば認められる、との取扱いが期待される。
組合員側でも、独自にLLPから提供された資料を修正するなど、複雑な経理が要求されるものと思われる。
以上、代表的な例を見てきた。通達改正により簡素化が可能なものもあるが、これによってもなお組合員間の差異が生ずる。
4 シュミレーション
典型的なパターンを挙げて、所得の違いの具体例を検討する。
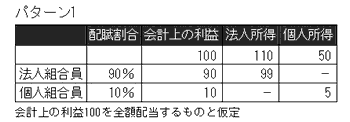
法人組合員は、利益を超える所得9(99-90)を別表4で加算留保する。
個人組合員は、非課税所得が多額にあったパターンを想定している。この場合5はどの所得区分に属することになるのであろうか。
上記個人組合員の内訳を、利子所得1・不動産所得2・事業所得2・非課税所得7・不動産の譲渡所得△2(損益通算不可)と仮定する。
この場合、個人所得5の部分については、それぞれ利子所得が1、不動産所得が2、事業所得が2、課税されない利益が5となるのであろう。
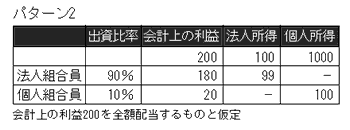
法人組合員は、法人所得を超える81(180-99)の部分について別表4で減算留保(あるいは一部流出もありえる)する。
個人組合員は、多額の不動産の譲渡損失が生じているケースを想定している。
上記個人組合員の内訳を、事業所得100、不動産の譲渡所得△80(損益通算不可)と仮定する。この場合は、上記個人所得100がそのまま事業所得とされ、課税される。実際には20の配当しか受けれないため、納税資金にも事欠く結果となる。
5 最後に
LLPの制度の導入を実際に検討してみると、数多くの実務上の難しさに遭遇する。LLPの経理担当者は、法人税の知識のみならず、所得税の知識も必要とされ、なおかつ各組合員の会社内部の益金認識時期に関する規定等の経理規定にまで通じている必要がある。
しかしこれまで見てきた問題点は、従来から組合契約等を行っている場合には存在していた問題である。従来、ジョイントベンチャーなど法人間で組まれるケースは多々あったと思われるが、これに個人の組合員が絡むことにより、数段複雑さを増すことになりそうである。さらに、有限責任制度が導入されるため、従来と比べると多くの事業者がこの制度を採用する可能性があり、今まで表面化しなかった点もクローズアップされることとなると思われる。
最後に若干の提案をしたい。上記に述べてきた所得金額計算上の困難さに対応するため、現行法の措法40条の4に類似する規定を設けてはどうだろうか。つまり、個人所得の計算において、当該LLPの所得を法人税の例によって計算することとする。その所得区分を事業所得(注8)(措法40条の4では雑所得)に係る収入金額とみなす。以上の2点を付け加えることで、多くの問題を解決することができるように思う。
(注)
(注1)
負担するリスクの範囲を損失の取込限度額とする趣旨であるのであれば、出資額を上回った場合にも、保証債務等があればその範囲で損失の取込を認めるべきである。
(注2)
法案第3条では「有限責任事業組合契約(以下「組合契約」という。)は、個人又は法人が出資して」とされている。従って、LLPはLLPに出資することはできないものと思われる。
(注3)
経済産業省HP、事業組合制度(日本版LLP研究会)に関する研究会第1回議事要旨http://www.meti.go.jp/policy/economic_industrial/gather/0000611/index.html参照
(注4)
所得税基本通達逐条解説平成16年版(財)大蔵財務協会P319参照
(注5)
本稿の予想と異なり、給与の支払を認めるものとして、最高裁平成13年7月13日第2小法廷判決、平成12年(行ツ)第13号、所得税更正処分取消請求事件、原判決破棄自判、判例時報1763号195頁・判例タイムズ1073号139頁
(注6)
提案1(2)②において「労務出資の禁止(ただし、労務などの提供を反映した柔軟な損益分配は可能、2.(2)、3.(3)参照)」としている。
法案では第11条において「組合員は、金銭その他の財産のみをもって出資の目的とすることができる。」としている。
(注7)
この問題については、取扱いがはっきりしているわけではない。組合に財産を現物出資した場合、財産の共有となり譲渡所得課税され、一つの財産を各組合員が共有(合有)する関係となる。この点を従来からある共有物についての過去の組合に関する質疑応答を参考として、取扱いの予想をした。
なお、現物出資時の課税については提案において「現物出資に関しては、原則として組合員間で譲渡が行われることから譲渡益課税の対象となるが、現物出資時の課税の繰り延べについては、将来の実ニーズ及び個別の事情に応じて対応すべきと考える。」としている。
(注8)
措法40条の4では「雑所得とみなし」ているが本稿の提案では事業所得としている。
これは、LLPの利用が期待されている事業を意識したためである。
LLPはジョイントベンチャーや産学連携に使われることが期待されている。この場合研究開発期間の当初数年間は赤字が見込まれる。もし雑所得とみなされれば、この赤字は税制上なんらの手当てもないことになり、黒字となった瞬間から課税されてしまう。そこで、事業所得とみなすか、何らかの方法で赤字の繰越を認める制度が必要となる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























