解説記事2005年04月11日 【編集部解説】 税務代理権の侵害、控訴審も国家賠償請求を認めず(2005年4月11日号・№110)
税務代理権の侵害、控訴審も国家賠償請求を認めず
税理士の心情は理解できるが税務署員の違法は認め難い
text T&Amaster編集部 佐治俊夫
大阪高裁第14民事部(井垣敏生裁判長)は、3月29日、無予告調査や税務署員の言動等により税理士の税務代理権が侵害されたとして、国家賠償法に基づく請求が行われていた事案に対し、「控訴人(税理士)の対応には全く理由がないとはいえないが、本件税務署員らに違法行為・違法事由があったとまでは認め難い」などと判示し、税理士の請求を棄却した原判決を相当とし、税理士の控訴を棄却した(平成16年(ネ)第1049号)。
事件の概要
本件は、A社及びB社の顧問税理士(本坊美通税理士)が、A社及びB社の税務調査に際し、税務署員らの種々の違法な職務行為によって税務代理権を侵害され、これによって税理士の信用と誇りが著しく傷つけられ、更にA社・B社から委任契約を解除されたとして、国を相手取り、国家賠償法1条1項に基づいて損害を請求する事案である。第一審(神戸地裁)では、「税理士の主張する税務署員の種々の違法な職務行為は認められない」として、請求が棄却されていた(平成16年2月26日判決、本誌No.068(2004.5.31)8頁参照)。
また、A社は、税理士と税務署との対立において、帳簿書類等を適時に提示しなかったとして、消費税の仕入税額控除の否認による更正処分・青色申告取消処分を受けることになり、当該処分の取消しを求めて、最高裁まで争っていた。最高裁第一小法廷は、平成17年3月10日、「税務調査における帳簿等の提示の要望に応じがたいとする理由も格別なかった。」などと判示して、A社の請求(上告)を棄却している(本誌No.107(2005.3.21)8頁参照)。
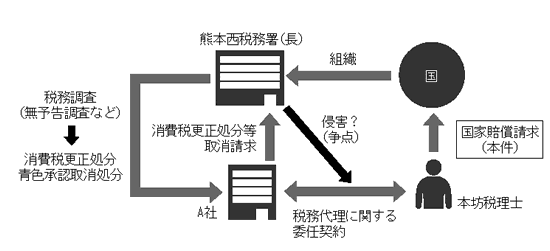
第一審の認定に比べ、税理士の心情に配慮しているが
大阪高裁での控訴審は、39名の補佐人税理士が判決書に掲載されるなど、税理士の強い関心の中で、審理が行われていた。主たる争点が「税理士の税務代理権」と「税務署の質問検査権」の衝突であるだけに、補佐人税理士からは白熱した口頭意見陳述が行われたりもしてきた。
本件控訴審では、税務署員らの控訴人(税理士)に対する違法行為の存否(争点1)、控訴人の権利・利益の侵害の有無(争点2)、損害額(争点3)が争点となった。なかでも無予告調査から始まる税理士の税務代理権と税務署員の質問検査権を巡る厳しい対立(争点1)について、①臨場に当たり事前通知を欠如したことは違法か、②税務代理権を無視する言動があったか、③税務調査を打ち切ったことは違法か、④調査理由を開示しなかったことは違法か、⑤脅迫的言動があったか、⑥その他本件税務職員らの違法行為があったか、という争点が設定されている。
原審(神戸地裁)は、税理士の主張に対して、全て否定的な判断を示してきたが、控訴審は税理士の役割・税理士の心情に一定の肯定的な評価を判示している。控訴審判決は、税理士の主張・心情に肯定的に評価できる部分があるとしても、税務職員の質問検査権の行使にも必要性があるとして、違法とは認め難いとする判断を行っている(控訴審の判示は次頁に掲載)。
一から書き改めた控訴審判決の評価は?
本件控訴審判決は、原審(神戸地裁)の事実認定及び課税処分等の取消が争われた別件の税務訴訟(熊本地裁・福岡高裁・最高裁)における事実認定とは、かなり趣を異にした判示を行っている。「税理士の主張に対して一定の評価を判示する」ために、棄却の結論は同じであるものの、原審の判決を一から書き改めたものとなっている。
しかし、結論において、税理士の主張はことごとく採用されるまでには至っていない。裁判所が、事実認定で踏み込めずにいること(事実認定の立証が困難?)、税務署員らの質問検査権の行使に理解を示していることから、「税理士の主張に対して一定の評価を判示するに、留まらざるを得ない」との印象だ。
勘ぐれば、控訴人を含む本件訴訟に参加した多数の税理士へのリップ・サービス、見方を変えれば、「税理士の税務代理権」と「税務署の質問検査権」の範囲についての、貴重な判示ということにもなろう。
控訴人は「結論ありき」の事実認定に不満
原告・控訴人である本坊美通税理士は、控訴審判決について「事実を否定する姿勢にたっての判決であり、『結論(棄却)ありき』の事実認定が行われている。それでは何も出てこない。」との不満を語っている。本坊税理士が本件訴訟で求めていたものは、税務署員らの違法な職務行為の認定であり、控訴審判決の判示する「心情の理解」とはかけ離れている。本坊税理士は、控訴審判決に「納得できない」としているが、これまでの訴訟の経過を踏まえ、税務代理権の侵害について、司法(裁判所)の判断に期待することの無力感をも感じているようだ。
控訴審(大阪高裁)の主たる判示事項
税理士の心情は理解できるが税務署員の違法は認め難い
text T&Amaster編集部 佐治俊夫
大阪高裁第14民事部(井垣敏生裁判長)は、3月29日、無予告調査や税務署員の言動等により税理士の税務代理権が侵害されたとして、国家賠償法に基づく請求が行われていた事案に対し、「控訴人(税理士)の対応には全く理由がないとはいえないが、本件税務署員らに違法行為・違法事由があったとまでは認め難い」などと判示し、税理士の請求を棄却した原判決を相当とし、税理士の控訴を棄却した(平成16年(ネ)第1049号)。
事件の概要
本件は、A社及びB社の顧問税理士(本坊美通税理士)が、A社及びB社の税務調査に際し、税務署員らの種々の違法な職務行為によって税務代理権を侵害され、これによって税理士の信用と誇りが著しく傷つけられ、更にA社・B社から委任契約を解除されたとして、国を相手取り、国家賠償法1条1項に基づいて損害を請求する事案である。第一審(神戸地裁)では、「税理士の主張する税務署員の種々の違法な職務行為は認められない」として、請求が棄却されていた(平成16年2月26日判決、本誌No.068(2004.5.31)8頁参照)。
また、A社は、税理士と税務署との対立において、帳簿書類等を適時に提示しなかったとして、消費税の仕入税額控除の否認による更正処分・青色申告取消処分を受けることになり、当該処分の取消しを求めて、最高裁まで争っていた。最高裁第一小法廷は、平成17年3月10日、「税務調査における帳簿等の提示の要望に応じがたいとする理由も格別なかった。」などと判示して、A社の請求(上告)を棄却している(本誌No.107(2005.3.21)8頁参照)。
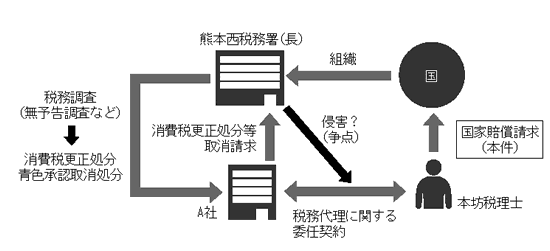
第一審の認定に比べ、税理士の心情に配慮しているが
大阪高裁での控訴審は、39名の補佐人税理士が判決書に掲載されるなど、税理士の強い関心の中で、審理が行われていた。主たる争点が「税理士の税務代理権」と「税務署の質問検査権」の衝突であるだけに、補佐人税理士からは白熱した口頭意見陳述が行われたりもしてきた。
本件控訴審では、税務署員らの控訴人(税理士)に対する違法行為の存否(争点1)、控訴人の権利・利益の侵害の有無(争点2)、損害額(争点3)が争点となった。なかでも無予告調査から始まる税理士の税務代理権と税務署員の質問検査権を巡る厳しい対立(争点1)について、①臨場に当たり事前通知を欠如したことは違法か、②税務代理権を無視する言動があったか、③税務調査を打ち切ったことは違法か、④調査理由を開示しなかったことは違法か、⑤脅迫的言動があったか、⑥その他本件税務職員らの違法行為があったか、という争点が設定されている。
原審(神戸地裁)は、税理士の主張に対して、全て否定的な判断を示してきたが、控訴審は税理士の役割・税理士の心情に一定の肯定的な評価を判示している。控訴審判決は、税理士の主張・心情に肯定的に評価できる部分があるとしても、税務職員の質問検査権の行使にも必要性があるとして、違法とは認め難いとする判断を行っている(控訴審の判示は次頁に掲載)。
一から書き改めた控訴審判決の評価は?
本件控訴審判決は、原審(神戸地裁)の事実認定及び課税処分等の取消が争われた別件の税務訴訟(熊本地裁・福岡高裁・最高裁)における事実認定とは、かなり趣を異にした判示を行っている。「税理士の主張に対して一定の評価を判示する」ために、棄却の結論は同じであるものの、原審の判決を一から書き改めたものとなっている。
しかし、結論において、税理士の主張はことごとく採用されるまでには至っていない。裁判所が、事実認定で踏み込めずにいること(事実認定の立証が困難?)、税務署員らの質問検査権の行使に理解を示していることから、「税理士の主張に対して一定の評価を判示するに、留まらざるを得ない」との印象だ。
勘ぐれば、控訴人を含む本件訴訟に参加した多数の税理士へのリップ・サービス、見方を変えれば、「税理士の税務代理権」と「税務署の質問検査権」の範囲についての、貴重な判示ということにもなろう。
控訴人は「結論ありき」の事実認定に不満
原告・控訴人である本坊美通税理士は、控訴審判決について「事実を否定する姿勢にたっての判決であり、『結論(棄却)ありき』の事実認定が行われている。それでは何も出てこない。」との不満を語っている。本坊税理士が本件訴訟で求めていたものは、税務署員らの違法な職務行為の認定であり、控訴審判決の判示する「心情の理解」とはかけ離れている。本坊税理士は、控訴審判決に「納得できない」としているが、これまでの訴訟の経過を踏まえ、税務代理権の侵害について、司法(裁判所)の判断に期待することの無力感をも感じているようだ。
控訴審(大阪高裁)の主たる判示事項
争点 | 一般的認定 | 本件へのあてはめ |
| 争点1-① 臨場に当たり事前通知を欠如したことは違法か | ・前提事実及び認定事実によれば、この臨場は、税務調査のための質問検査権(法人税法153条)の行使の一環であったことが明らかである。 ・(税務職員と調査対象者との間の)トラブルを回避し、納税者の権利が不当に侵害されることを防止するためには、税務行政における適正かつ具体的な手続規定を定めること等とともに、税務の専門家であり、税務代理・代行権を有する税理士が調査に立ち会ったり、調査対象者に適切な助言・指導・援助を与えることは重要である。 ・これらの諸規定(税務運営方針・事務運営指針・現況調査の手引、など)が定める事項は、税務調査について、法が求める一般的要件ではなく、これらに違反したからといって、直ちにその調査が違法となるというものではないが、適正・妥当な課税のための調査の実施と、税務調査における納税者の権利保護との調整の観点から定められたものであるから、十分に尊重されて然るべきであって、著しく逸脱する場合は、違法性を帯びる場合もあるというべきである。 | ・客観的に過少申告の疑いが存在しない場合であったとしても、また、過去に優良企業と評価されていたとしても、そのことから直ちに質問検査の必要性がないとすることはできないのであって、課税庁において、納税者の申告税額等が申告者の所得等を正しく反映しているか否かを、帳簿上の調査だけでなく、在りのままの状況を認識するための現況調査と併せて確認しておくことは、所得税額等の適正な把握の面ではもとより、適正な税務処理を誘導する上でも重要であることからすれば、長期間にわたって調査の実績がないことだけであっても、質問検査の必要性があるというべきである。 ・本件の場合は、あえて無予告で調査をしなければならないほどの必要性があったかは、かなり疑問というべきである。 しかし、課税庁が「在りのままの実態」を調査するために、今回は無予告で調査を実施しようと判断したことは格別不合理なこととまではいえず、現場に臨場した直後には、控訴人と電話で連絡され、控訴人及び調査対象者の反対で実際には調査は行われていないことも考慮すれば、無予告であったのみを捉えて、これを違法と判断するのは相当でない。 ・経過を総合考慮すると、本件税務署員らが事前通知なく、調査対象会社に臨場して税務調査を行おうとしたことは、質問検査の必要性と調査対象会社の利益との衡量の見地からみて、社会通念上相当な範囲を逸脱したものとまでいうことはできない。 |
| 争点1-② 税務代理権を無視する言動があったか | ・税理士が調査対象者から税務調査を含めて委任を受けている場合は、その間に債権・債務関係が生じており、税理士は、必要がある場合は委任者のために税務調査に立ち会い、委任の趣旨に応じた対応をする義務があり、その履行によって報酬を請求できることにもなり、委任者も受任者である税理士に対し、そのような義務の履行を求める権利があるというべきであって、第三者たる税務職員において、この権利を侵害することは、その方法・態様等のいかんによっては、債権侵害として違法となることもないとはいえない。そして、受任者である税理士の明確な拒絶にもかかわらず、調査対象者に直接承諾を求めることは、その限りにおいて、委任契約を部分解除することを要求することにもなるのであって、任意の説得の限度を超えれば、違法となることもあり得るというべきである。 | ・税務調査への協力要請が多数回にわたったことのみをとらえて違法と評価することはできない。 ・本件税務署員らの要請がいささか過度であったきらいがあるにせよ、これをもって、控訴人の税務代理権を違法に侵害するような言動があったと認めることは到底できないというべきである。そして、本件税務署員らの言動が上記の趣旨のものにとどまる限り、それは、適正・公平な課税を実現すべく行動することが義務づけられている税務職員の言動として、許容される範囲内のものというべきである。 ・本件税務署員らが控訴人の立会いを排除して税務調査をしようとしたこと自体認められないのであるから、本件税務署員らにおいて税務代理権を無視ないし軽視するような態度があったとの理由で同職員の行為を違法視することは困難というべきである。 |
| 争点1-③ 税務調査を打ち切ったことは違法か | ・控訴人立会の下、税務調査が行われたが、案内された部屋にはビデオカメラ等の準備がされており、会社側から帳簿等の提示の申し出もないまま、控訴人らがビデオカメラの撮影を開始したことから、これを中止するように税務署員が求めたところこれに応じなかったために、調査拒否と判断して調査を打ち切った。 | ・国家公務員の守秘義務の対象であると考えられる税務調査の様子が一般私人によって不特定多数の部外者に明らかにされる危険が予想される状況において、守秘義務を負う国家公務員が撮影されることを回避するため中止を求め、それに応じない場合には、後日の説得が功を奏することを期待して、撮影の対象となっている当日の税務調査自体をひとまず打ち切るという対応が不相当なものということはできない。 |
| 争点1-④ 調査理由を開示しなかったことは違法か | ・控訴人は、両税務署の長又は署員に対し、書面又は口頭で、複数回にわたり、①調査理由の開示、②税務代理権侵害にわたる発言についての納得すべき説明、③調査理由を開示することの必要性をどのように理解しているのかの説明、④これらに関する適切な対応がされていないことについての抗議に対する回答等を書面で求めたが、そのいずれについても、両税務署の長又は署員がこれに応じたことはなかった。 | ・質問検査権の行使に当たり、調査理由の個別的、具体的告知が法律上一律に要件とされているわけではなく、そのことを前提とし、更に上記認定・判示したところを総合考慮すると、両税務署において、控訴人に対し本件両会社の調査の具体的理由を明示しないことが違法を招来するとまでいうことのできる事情は見当たらない。 ・そもそも、質問検査権行使に当たり、理由を開示しないことが、検査権行使の相手方たる納税者の手続保障の見地から違法とされる場合が絶無とはいえないとしても、そのような場合に、税務代理契約に基づき代理人となっている税理士のいかなる法的利益が害されることになるのかは明らかでない。 |
| 争点1-⑤ 脅迫的言動があったか | ・反面調査は、調査対象者の信用を毀損する場合もあり、金融機関に対する調査によっては、融資の打切等の深刻な事態に陥ることもあり、青色の承認取消等のような処分が、企業の存立にも影響しかねないことは事実である。したがって、これらを口実にして調査を強行しようとしたのであれば、脅迫的言動といい得るであろう。 | ・本件税務職員らにそのような意図があったと認めるに足りる証拠はない。 ・反面調査や処分(青色承認取消・消費税の仕入税額控除の否認等)が極めて厳しいものであることから、本件各会社が畏怖・困惑を感じたことは容易に推測されるが、そのような結果を知らせない方が調査対象者に判断を誤らせる危険があるのであって、許されないものというべきである。 |
| 結論 | 税理士は、税務に関する専門家として、独立かつ公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする職業人であり(税理士法1条)、そのような見地からすると、税理士は、税務代理に関する委任契約を締結した納税義務者が課税庁の質問検査権を行使されるに当たり、納税義務の適正な実現に資するべく、その現場に立ち会い、検査の対象となっている納税義務者のすべき主張・陳述について代理・代行することができるのは当然であり、望ましいことでもある。そして、そのような立場に自覚的な税理士であるほど、課税庁が税理士の立会いなしにする質問検査権の行使に警戒的になることは容易に想定されるとともに、本件における控訴人もそのような立場から本件税務職員らに対応したものと認められ、その心情には理解できるものがある。 そして、既に説示したとおり、本件の無予告調査の正当性には相当の疑問があることなどからすれば、本件における控訴人の対応には全く理由がないとはいえないが、本件税務署員らに違法行為・違法事由があったとまでは認め難いことからすれば、結局、控訴人の本訴請求は排斥するほかはない。 | |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























