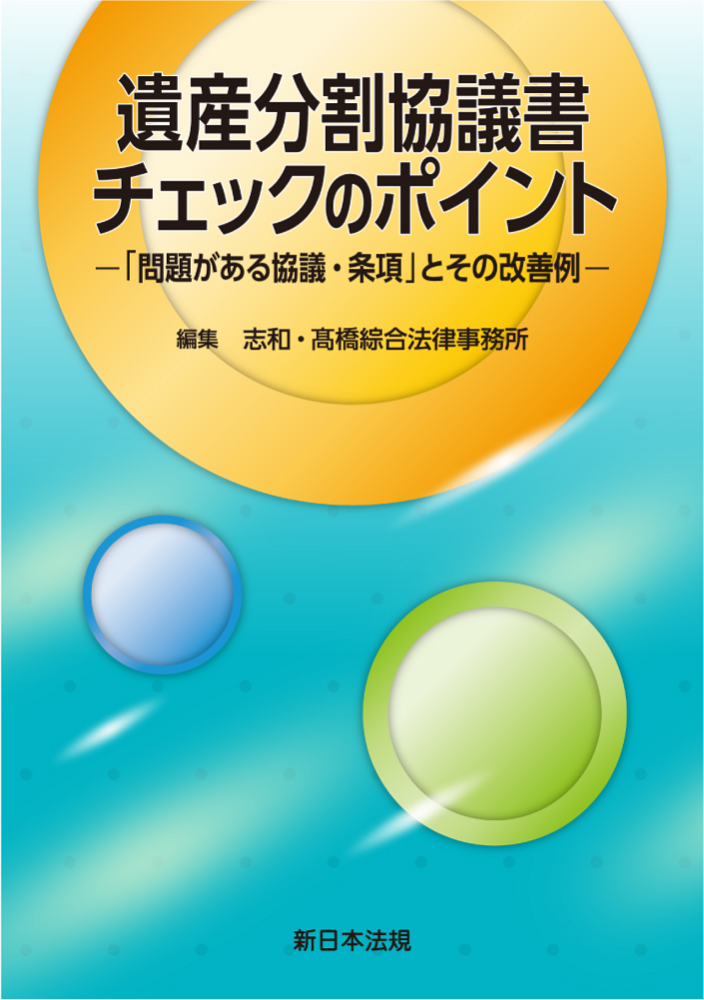解説記事2005年04月18日 【編集部レポート】 航空機リースなど組合損失算入制限の詳細が明らかに(2005年4月18日号・№111)
レポート
航空機リースなど組合損失算入制限の詳細が明らかに
平成17年度税制改正で規制されることになった航空機リース事業など組合事業の損失制限の要件(民法組合等の法人税法上の取扱い)が、租税特別措置法の政省令が公布されたことによって明らかになった(法律、政令、省令の各条文は30頁参照)。省令(規則)には、「組合事業について相応のリスクを負っていないと認められる場合」に該当するか否かの判断基準について、「組合債務のうちに占めるノンリコースローンの割合が概ね80%以上のとき」などと具体的な解釈規定が設けられているので要注意だ。
リスクの程度によっては全額損金不算入も
平成17年度税制改正において手当てされた民法組合等に係る法人税の取扱いは、「重要業務の決定に関与しない、又はその決定された重要業務の執行を自ら行わない(投資するだけ)など、組合事業への実質的な関与度合いが低い組合員が、組合事業について相応のリスクを負っていないと認められる場合は、組合損失の損金算入を制限する」というもの。
この損金算入制限の内容は、「組合事業について相応のリスクを負っていないと認められる場合」の程度に応じて、右頁の図表のような取扱いになっている。
「80%以上」と数値基準が示された
財務省は、右頁①のケースの損金算入制限について、「組合財産の価額を超えて債務を弁済する責任を負っていないと認められる場合には、損失の取り込みは、自らがリスクを負う出資額までに制限すべき」とコメントしている。
また、右頁①に該当する具体的な事例の一つとして、ノンリコースローン等により組合債務の責任の範囲を組合財産に限定しているケースを想定している。このほど公布された租税特別措置法67条の12、同政令39条の31第3項各号には、①のケースに該当するか否かの判定基準について、「全体の状況をみて判定する」というような抽象的な規定内容になっているが、同省令(規則)22条の18の2には、「組合債務のうちに占めるノンリコースローン割合が概ね80%以上の場合」など具体的な数値基準まで規定されている。
ノンリコースローンとは
ノンリコースローンとは、非遡及(借主責任限定)型の借入金のこと。政令上は、「責任限定特約債務」と表現されており、担保となっている資産にのみ債権者の求償権が及ぶ貸付のことを意味する。例えば、航空機を購入するために金融機関等からノンリコースローンで借入金をする場合、仮に、借りたお金が返済できない状態に陥っても、その返済は、ノンリコースローンで購入した航空機から得られる収益のみに限定されているため、その航空機の売却代金以上は免責となるしくみである。
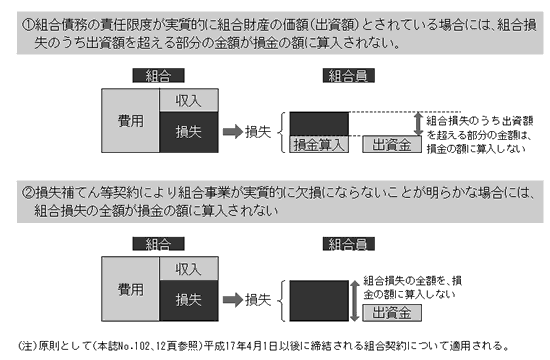
何故、具体的な数値基準を明示したか
一方、「ノンリコースローン割合」は、組合債務のうちに占めるノンリコースローンの割合を意味する。例えば、飛行機の価格が100だとすると、そのうち20を組合員からの出資金でまかない、80をノンリコースローンによる貸付金でまかなったとすると、組合債務80のうちノンリコースローン80(80/80=100%)となるので、ノンリコースローン割合が概ね80%以上である場合に該当することになる。
財務省は、“組合事業について相応のリスクを負っていないと認められる場合”の一つの例示としてノンリコースローン割合「80%」という具体的な数値基準を示した理由について、「納税者の予測可能性の確保などの観点から、一定の数値基準を示し、解釈的な規定を設ける必要があると判断した。」と話している。
損失補てん等契約による“損失の先出し”は租税回避行為とみなされる
また、財務省は、①のケースの損金算入制限について、ノンリコースローン割合のほかにも、政令で、損失補てん等契約が締結されている場合を規定(租令39の31③二)し、さらに、省令で数値基準を規定(租規22の18の2②)している。省令では、具体的に、「損失補てん等契約が履行される場合に組合事業による累積損失が出資金の概ね120%以下となると見込まれるとき」は、「組合事業について相応のリスクを負っていないと認められる場合」に該当するとされた。
これは、リース商品などを購入する際に、結果的にその事業の損益が赤字となっても、その損失分の補填特約を結んでおくなどして、相当程度のリスク軽減をしているケースのこと。民法上の組合は無限責任のため、リスクがあれば投資しない人も多い。このため、リース商品などを販売する際に、損失が生じても、最終的にはその損失を補填する契約を結び、リース商品を販売しているケースも多かった。
さらに、②の損金算入制限にように、損失補てん等契約などによって組合事業が実質的に欠損にならないことが明らかな場合は、まさに、“損失の先出し”による租税回避行為とみなされ、組合損失の全額が損金の額に算入されないことになるので注意が必要だ。
航空機リースなど組合損失算入制限の詳細が明らかに
平成17年度税制改正で規制されることになった航空機リース事業など組合事業の損失制限の要件(民法組合等の法人税法上の取扱い)が、租税特別措置法の政省令が公布されたことによって明らかになった(法律、政令、省令の各条文は30頁参照)。省令(規則)には、「組合事業について相応のリスクを負っていないと認められる場合」に該当するか否かの判断基準について、「組合債務のうちに占めるノンリコースローンの割合が概ね80%以上のとき」などと具体的な解釈規定が設けられているので要注意だ。
リスクの程度によっては全額損金不算入も
平成17年度税制改正において手当てされた民法組合等に係る法人税の取扱いは、「重要業務の決定に関与しない、又はその決定された重要業務の執行を自ら行わない(投資するだけ)など、組合事業への実質的な関与度合いが低い組合員が、組合事業について相応のリスクを負っていないと認められる場合は、組合損失の損金算入を制限する」というもの。
この損金算入制限の内容は、「組合事業について相応のリスクを負っていないと認められる場合」の程度に応じて、右頁の図表のような取扱いになっている。
「80%以上」と数値基準が示された
財務省は、右頁①のケースの損金算入制限について、「組合財産の価額を超えて債務を弁済する責任を負っていないと認められる場合には、損失の取り込みは、自らがリスクを負う出資額までに制限すべき」とコメントしている。
また、右頁①に該当する具体的な事例の一つとして、ノンリコースローン等により組合債務の責任の範囲を組合財産に限定しているケースを想定している。このほど公布された租税特別措置法67条の12、同政令39条の31第3項各号には、①のケースに該当するか否かの判定基準について、「全体の状況をみて判定する」というような抽象的な規定内容になっているが、同省令(規則)22条の18の2には、「組合債務のうちに占めるノンリコースローン割合が概ね80%以上の場合」など具体的な数値基準まで規定されている。
ノンリコースローンとは
ノンリコースローンとは、非遡及(借主責任限定)型の借入金のこと。政令上は、「責任限定特約債務」と表現されており、担保となっている資産にのみ債権者の求償権が及ぶ貸付のことを意味する。例えば、航空機を購入するために金融機関等からノンリコースローンで借入金をする場合、仮に、借りたお金が返済できない状態に陥っても、その返済は、ノンリコースローンで購入した航空機から得られる収益のみに限定されているため、その航空機の売却代金以上は免責となるしくみである。
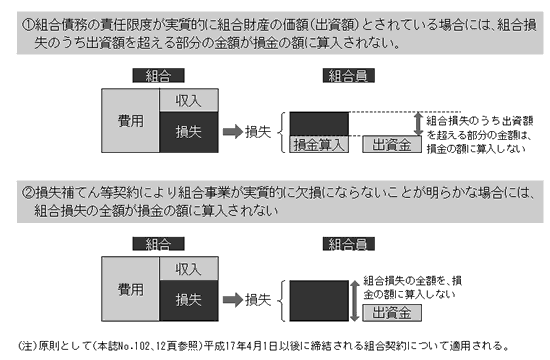
何故、具体的な数値基準を明示したか
一方、「ノンリコースローン割合」は、組合債務のうちに占めるノンリコースローンの割合を意味する。例えば、飛行機の価格が100だとすると、そのうち20を組合員からの出資金でまかない、80をノンリコースローンによる貸付金でまかなったとすると、組合債務80のうちノンリコースローン80(80/80=100%)となるので、ノンリコースローン割合が概ね80%以上である場合に該当することになる。
財務省は、“組合事業について相応のリスクを負っていないと認められる場合”の一つの例示としてノンリコースローン割合「80%」という具体的な数値基準を示した理由について、「納税者の予測可能性の確保などの観点から、一定の数値基準を示し、解釈的な規定を設ける必要があると判断した。」と話している。
損失補てん等契約による“損失の先出し”は租税回避行為とみなされる
また、財務省は、①のケースの損金算入制限について、ノンリコースローン割合のほかにも、政令で、損失補てん等契約が締結されている場合を規定(租令39の31③二)し、さらに、省令で数値基準を規定(租規22の18の2②)している。省令では、具体的に、「損失補てん等契約が履行される場合に組合事業による累積損失が出資金の概ね120%以下となると見込まれるとき」は、「組合事業について相応のリスクを負っていないと認められる場合」に該当するとされた。
これは、リース商品などを購入する際に、結果的にその事業の損益が赤字となっても、その損失分の補填特約を結んでおくなどして、相当程度のリスク軽減をしているケースのこと。民法上の組合は無限責任のため、リスクがあれば投資しない人も多い。このため、リース商品などを販売する際に、損失が生じても、最終的にはその損失を補填する契約を結び、リース商品を販売しているケースも多かった。
さらに、②の損金算入制限にように、損失補てん等契約などによって組合事業が実質的に欠損にならないことが明らかな場合は、まさに、“損失の先出し”による租税回避行為とみなされ、組合損失の全額が損金の額に算入されないことになるので注意が必要だ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.