解説記事2005年06月13日 【商法関連解説】 国際的M&A(合併・買収)と比較法・抵触法―ライブドア事件を機縁として―(2005年6月13日号・№118)
実 務 解 説
国際的M&A(合併・買収)と比較法・抵触法
―ライブドア事件を機縁として―
椙山女学園大学現代マネジメント学部教授 上田純子
1. はじめに
2005年4月18日、ライブドアvsフジサンケイ・グループの株式取得合戦に終止符が打たれた。周知のように、同年2月8日のマスコミに、ニッポン放送の筆頭株主として突如現れたライブドアの堀江貴文社長に対し、フジサンケイ・グループはあの手この手で対抗した。ニッポン放送との資本関係のねじれを是正すべく株式公開買付(以下、TOBという)によって一応公明正大にニッポン放送株を買い集め、同社を子会社化しようとしていたフジテレビジョン(以下、フジという)にとって、堀江氏の株式取得が非礼かつ卑怯な手法と映ったのは当然ともいえる。ポイズン・ピル(毒薬)、クラウン・ジュエル(焦土作戦)、ホワイト・ナイト(白馬の騎士)などの米国の企業買収実務では耳慣れた用語がわが国で飛び交い、当事者たちの株式取得合戦に優るとも劣らないマスコミの情報合戦に国民が踊らされた。2月、3月のうちはニュース画面に両者の攻防の様子が映し出されない日は一日たりともないほどであった。そして、4月になると膠着状態になり、事態は和解に向けて急転回した。しかし、プロローグに比べると何と予想に反するエピローグであったことか。
2005年4月18日の報道各社は、ライブドアが自ら買い占めたニッポン放送株のすべてをフジにTOB価格より高値で売り、フジは、ライブドアの第三者割当増資を引き受けることで合意した旨を一斉に報じた。すなわち、ライブドアはミイラ取りがミイラになったごとく、フジサンケイ・グループの傘下に収まったことになる。ライブドアは1473億円の資金(自己保有株式の売却分と新たにフジが引き受ける第三者割当増資分)を手にするも、フジサンケイ・グループは、将来にわたり、ライブドアの敵対的行動を抑止できるのである。
ライブドアとニッポン放送・フジの“70日戦争”は、とりわけ、ライブドアの奇襲が法律の抜け穴をくぐりぬけるものであっただけに、立法に対する多方面でのインパクトを残した。目下、少なくとも四省庁(金融庁、総務省、法務省、および、経済産業省)がライブドア効果を受け、立法作業に忙殺されている。
第一に、ToSTNeT取引といわれる東京証券取引所(以下、東証という)の時間外取引システムを利用した株式の大量取得は、相対取引に限りなく近い市場取引であることは疑いなく、東証のルール見直しや証券取引法改正の声を呼んだ。ニッポン放送のフジに対する新株予約権の発行についてライブドアの差止請求を認めた東京地裁の決定においては、ToSTNeT取引は、証券取引法上の市場取引にあたり、TOB手続きを強制されないとしながらも(東京高裁決定も同旨)、傍論において、ルール見直しの必要性に触れている。第二に、外国資本によるメディア株式取得規制の改正の検討の契機となった。現行の電波法では、外資の直接出資しか規制しておらず(放送事業者の株式における外国人の議決権を20%に制限しており、放送事業者は、放送法に基づき、この制限比率を超える株式について株主名簿への登載を拒否できる)、ライブドア事件をきっかけに、与党議員らが中心となって内国企業を通じた外資の間接出資をも規制の対象とするよう総務省に強く働きかけ、総務省は、今国会への改正法案提出を決めた。第三に、現在国会にて審議中の新会社法(衆議院では可決済み)のうち、合併対価の柔軟化の部分の施行が一年凍結された。外国会社の株式を対価とする合併(ただし、内国殻会社を通じた三角合併)を可能とする合併対価の柔軟化に関する改正は、新会社法のうち米国の通商担当者に最もアピールする部分であったにもかかわらず、である。さらに、「事業結合規制法」なる、買収者側に事前に標的会社の取締役会に対し、買収の目的や事業の将来計画などを提示のうえ同意を求めさせることなどを含む立法もまた、与党内に設置された「企業統治委員会」を中心に検討されている模様である。同時に、過剰防衛を抑制する方向での検討成果として、各企業に対する合理的範囲内での防衛措置に関する経済産業省と法務省の合同指針が2005年5月27日に公表された(指針全文は、http://www.meti.go.jp/press/20050527005/3-shishinn-honntai-set.pdfからダウンロードできる)。第四に、上場会社ではいよいよ企業買収の脅威が現実化し、2005年3月14日に制御機器メーカーのニレコが初めてポイズン・ピル条項を導入したのを皮切に、おのおの定款変更によって防衛措置を盛り込もうという動きが広がっている。
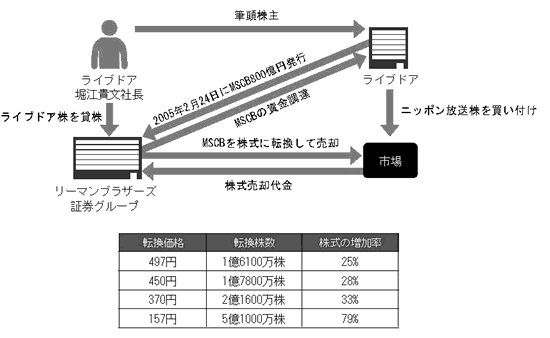
(注)株数はMSCB発行額を転換価格で単純に除したもの。転換価格は、直近3営業日に市場で取引された株価の売買高加重平均価格の平均値の90%。
※図表は、日本経済新聞2005年2月17日付、同2月23日付をもとに作成。
本稿の関心は上記のうち第三点に関わる。第二点も含め、与党議員や企業経営者を中心にいささか興奮気味に外国資本の締め出し策(電波法上の規制に関しては、国家安全保障上の見地も加わるので、必ずしも締め出しの動機や目的は一致しないものの)を講じようという動きが広がるなか、諸外国の企業結合の状況とその規制を概観し、国際的な企業結合規制にともなう法律問題を検討することとしたい。「外国企業との三角合併を可能とする新会社法を先取りする動き」との観測が広がったように、ライブドアは純粋な内国会社であるが、買収の原資は、米国系投資銀行リーマン・ブラザーズ証券グループへの修正条項付転換社債型新株予約権付社債(MSCB)の発行によってまかなわれたため、これを間接的な外国資本による買収とみることも可能である。ライブドアへの株式の実質譲渡人は、外国人投資家ではないかとの憶測もあり、リーマン・ブラザーズ証券が一連の買収工作を指揮したようにもみえる(リーマン自身は否定しているが)。ライブドアは、2005年2月8日のニッポン放送株取得(当日午前9時の取引開始前に、東証の立会外取引システムToSTNeTを利用して、わずか30分足らずの間にニッポン放送株の30%近くを買い入れ、前日までに取得していた分と併せて35%を取得)にあたり、リーマン・ブラザーズから、588億円のつなぎ融資を受けており、融資への返済と投資のための800億円を調達するために、同証券グループにMSCBを発行した(MSCBを利用した資金調達の仕組みについては、前頁の図を参照されたい)。
以下、本稿では国際的な企業結合法制に関する諸問題の検討素材とすべく、ヨーロッパおよびアメリカの状況を概観する。
2. ヨーロッパ
ここでは、域内の越境企業結合規制の採択が進められているヨーロッパ連合(以下、EUという)とその構成国でもある英国およびドイツの企業結合規制について取り上げる。ヨーロッパ委員会は2003年に会社法・企業統治に関するアクション・プランを採択して、この分野における構成国の立法間のギャップの調整を行うべく、統一的なEU立法を模索してきた。
1. EU
東方拡大の途をたどるEUでは、構成国の多様性はますます増大し、各国の企業結合規制もまた多様である。EUにおいて、国際的な企業結合に関する統一的な枠組みを採択しようという動きは早くからあった。このことは、「ヨーロッパ会社」構想が共同体発足とほぼ同時期にスタートしたという事実と無縁ではない。
すなわち、1951年に閣僚理事会において公共サーヴィス事業向けに、多国(構成国)籍資本によって登記地を域内に自由に設定できるヨーロッパ会社(Societas Europaea; SE)という概念が公表され、それは、ロッテルダム大学のサンダーズ教授により、通常の事業会社形態をとってより具体的に構想され、1960年に再公表された。最終的には、2001年にSEに関する規則およびダイレクティヴ(指令、命令ともいう)が採択され、基本的には定款自治と構成国裁量の幅を広く認め、SEが設立される構成国の会社立法に基づいた会社の機関構成や意思決定方式が採用できるようになっている。また、従業員参加については、上記ダイレクティヴにより、従業員参加に関して労使協議を行うことがSE設立の前提として義務づけられ、域内に広がるいわゆるソーシャル・ダンピングの懸念を払拭している。
さて、以上のSEは、構成員が有限責任を負う公開会社でなければならず、域内の複数の法域にまたがる合併や持株会社設立等の方法により設立される。上記の2001年の規則等の採択により、SE化のための域内企業の結合が加速している。また、域外の第三国にあっても、既存の域内子会社や現地法人をSE成りさせ、たとえば税金や人件費がより割安な他の構成国に移転させることも可能となる。
このことと相俟って、TOBに関するダイレクティヴが2004年4月に採択され、越境合併に関するダイレクティヴ案も2003年5月に提出された。後者は、前述のヨーロッパ委員会のアクション・プランに基づいて提案された初めてのダイレクティヴ案である。2005年5月にヨーロッパ委員会意見が採択されたところであり、採択に向け閣僚理事会とヨーロッパ議会との共同手続きの段階に入っている。両者ともに、原始提案は1980年代にまで遡る、採択が相当に難航した(している)ダイレクティヴである。
前者に関しては、英国のシティ・コードを基盤としながら、手続きの細部(たとえば、TOBの公表時期や買付期間など)について、構成国間の多様性を参酌して、幅を持たせた内容となっている。採択が難航した理由として、そもそも、TOBは英国やアイルランドの主要な企業結合手法であり、株式が金融機関等によって集中保有される傾向が強いヨーロッパ大陸においては一般的ではなかったこと、強制買付や対抗措置の導入の可否についての議論が収束しなかったこと、および、構成国が自国の制度(たとえば、ドイツの従業員の機関参加やスウェーデンの対抗措置としての複数議決権株式の発行)が越境TOBによって潜脱されないとの保証を求めたこと、などが挙げられよう。その内容については、シティ・コードに関する後述の節において一括して述べることとする。後者については、公開会社・閉鎖会社の区別なく、すべての株式会社の越境合併を容易にすべく、国内法間のギャップを調整するものである。上記のSEが公開会社のみを対象としているため、このダイレクティヴ案は、採択されれば、SE規則を補完すべく、とりわけ複数の国で営業を展開しようとする閉鎖会社にとって有意義である。
2. 英国
英国の主たる企業結合手法は、上述のように株式取得である。その手続きおよび規定は、会社法およびシティ・コード(City Code on Takeovers and Mergers)(以下、単にコードという場合には、シティ・コードのことを指す)に見出されうる。1985年会社法によるTOBの規定は、Part XIIIAに収められている(第428条ないし第430F条)。会社法では詳細を定めず、もっぱら、標的会社の少数株主保護に主眼を置く。すなわち、TOBに反対する標的会社株主の公正価格での株式買取請求権や、また逆に買収会社側が標的会社の一定多数株式を買い占めた場合の当該会社の少数株主のスクィーズ・アウト(締め出し)権も認められている。以上の会社法の規定は閉鎖会社にも適用されるのに対し、シティ・コードの規定は、連合王国、チャネル島、および、マン島に本店を置くすべての公開会社(listed companiesとquoted companies)に対して適用される。コードは制定法とは異なり理念や原則を中心に定められているが、会社法の規定に比べれば、詳細である。株式取得による企業結合であるから内国会社と外国会社とが当事会社となることも当然ありうる。上述のコードの適用原則によれば、内国会社同士のTOBについては、コードは問題なく適用されることになる。しかし、外国会社によるTOB、外国会社に対するTOB、内国会社であってもそのなかに外国人株主がいる場合、などの際のコードの適用範囲については、コードは何も規定しておらず、また、コードの執行機関であるTOBパネル(Panel on Takeovers and Mergers)もこの点について必ずしも客観的指針を策定しているわけではない。パネルは、抵触法が問題となる場合には、事前の相談を促している。これまでの事例で問題が顕在化したのは、米国の株式公開買付に関するウィリアムズ法との抵触である。とりわけ、規制枠組みの相違から、市場買付、買付期間、買付承諾撤回権、開示要件などに関して、抵触が生じうる。後述するように、この問題は米国サイドでもアプローチされ、証券取引委員会(Securities and Exchange Commission; SEC)の適用免除命令などにより、柔軟な解決が図られてきている。英国のパネルは、米国のTOB規制との抵触については、SEC基準を目安に判断しているようである。
たとえば、米国居住株主の保有株式割合が発行済株式の10%以下である場合、米国SECのTier Iの例外にあたり、標的会社の母国法が適用される。同様に、10%超40%以下である場合はTier IIの例外にあたり、両規制が並列的に適用されうるが、米国法が適用免除になる場合であっても、買付者は、不実開示や不開示、詐欺的または欺罔的行為に起因するウィリアムズ法上のいかなる責任をも免れることはできない。
コードは、イントロダクション、一般原則、定義、および、規則の4部から成る。一般原則では、たとえば、標的会社の同種類株主の平等扱い、買付計画中および買付期間中の買付会社、標的会社、および、それらの会社のアドヴァイザーの平等情報提供義務、買付会社の買付計画確定後の公開買付アナウンス義務、株主に対する十分かつ適切な情報、および、考慮に必要十分な時間の提供、買付文書作成にかかる標的会社およびそのアドヴァイザーの注意義務、買付関係者の相場操縦防止義務、標的会社による対抗措置の原則禁止(株主総会決議がある場合を除く)、少数株主に対する抑圧の禁止、標的会社取締役の利益相反行為の禁止、ならびに、強制買付義務および強制買付遂行予見義務が定められている。これらの総則規定は、コードの理念を抽象的な文言で表したものであり、パネルは、総則をパネルやコードの精神に反しない範囲で適用する。個別事項に関する規則は、細部まで具体的に規定していないので、解釈の疑義等に関してはパネルに個別に問い合わせることになる。
EUダイレクティヴ採択の際に構成国間でその制度設計に関し最も議論されたのは、上述のように、強制買付と対抗措置である。この2つは、それぞれコードのRule 9とRule 21に規定されている。Rule 9によれば、標的会社の株式の一部を取得した者に、残部株式を当該会社の同一株式における過去12か月間の最高値株価で買い取る申し込みをなすことを義務づける。標的会社の株式の一部とは、①30%を超えて取得した場合、または、②申込者が標的会社の議決権の30%ないし50%を取得し、その後12か月以内にさらに議決権の1%以上を取得する場合である。会社の支配権が、公開買付、相対取引、あるいは市場取引のいずれで取得されようが、標的会社の残存株主は、最高の価格で株式を売却して当該会社を去ることが認められるところにその意義がある。
Rule 21によれば、標的会社の取締役・執行役員は、株主総会の承認がない限り、買収会社の買付申込を阻害する行為を行ってはならない。この規定は、買付申込に際してばかりでなく、買付申込前であっても、標的会社の取締役会に買付が切迫していると信ずるに足る理由がある場合に適用される。このような対抗措置としては、新株発行(授権枠外の発行をも含む)、オプションまたは転換証券の発行、資産の売却、会社の通常の営業の部類に属さない契約の締結などが含まれる。買付前に新株発行や資産の売却を行う場合には、当該対抗措置と買付申込との因果関係によりRule 21の適用の可否が判断されることになる。標的会社は、さらに、買付申込に対抗して増配計画や収益の増加を情報開示して株式価値を高め、買付に応じようとする株主にディスインセンティヴを与え、また、ホワイト・ナイトを探すことも可能である。
ちなみに、強制買付および対抗措置について、前述の2004年のEUのTOBダイレクティヴは次のように規定している。すなわち、前者については、構成国に対し、標的会社の少数株主保護の見地から買収者が所定割合の株式を買い付けた場合の強制買付制度の確立を求めている(5条)。構成国は、所定割合について、自国の規制のなかで自由に設定できる。また、後者については、標的会社の株主総会の事前承認(普通決議で可)を条件に、標的会社が対抗措置をとることを認めている(9条)。このEUダイレクティヴの採択によって英国のシティ・コードの規定が変容を迫られることはほとんどないと思われる。すなわち、前言のように、ダイレクティヴは、構成国の多様性に鑑み、細部の規制は構成国の裁量にゆだねる形をとっているためである。ただし、同ダイレクティヴがTOBに関する制定法上の規制機関を求めている点(1条1項)は、英国においてパネルの性格や構造のあり方をめぐる白熱した議論をもたらしている。
3. ドイツ
ドイツでは、第二次世界大戦後、1999年に同国のマンネスマン社が英国のヴォーダフォン社に敵対的TOBをしかけられるまで、敵対的企業買収はわずか3件しかなかった。前述のように、ドイツでは金融機関による株式の集中保有傾向が強く、少なくとも敵対的企業買収は起こりえない環境にあったからである。たとえば、1990年代の平均GDPにおいて、ドイツ、フランス、および、英国は、EU全体のそれぞれ28%、18%、および、13%を占めていたが、M&A総額でみると、それぞれ17%、14%、および、30%であった。すなわち、ドイツのGDPは英国のそれの約2倍であるが、M&A総額でみると約半分でしかない。したがって、少なくとも1990年代時点では、たしかにドイツにおけるM&Aは相対的に少なかったことがデータ的にも裏づけられうる。
株式取得型の企業結合に代わってドイツで利用されてきたのは「一方の会社の財産全体が他方の会社または合併によって新設される会社に包括承継され、財産を移転した会社は清算手続きを経ずして解散し、その株主は財産移転を受けた会社の株主となる」合併であった。外国会社との合併の可否に関するドイツの議論は、組織変更法上は外国会社との合併は可能であるが、抵触法上の観点からは認められないというものであった。すなわち、抵触法の分野の議論において有力であった単一準拠法説(合併当事会社の一方の従属法のみを適用すると解する)は、一方の合併当事会社の利害関係者の保護が図られなくなるとして、国際的な合併を認めてこなかったのである。もっとも、近年のドイツにおける議論は両当事会社の従属法を適用することによって国際的な合併を認める方向に変わってきている。
さらに、ドイツにおける近年の注目すべき動きとして、TOB規制を整備したことが挙げられる。1995年には連邦財務省所管の取引専門家委員会によってTOBコードが策定されたが、コードより強制力が強い制定法レヴェルの規制の採択が望まれた結果、2001年に公募、証券売買・事業承継法(Gesetz zur Regelung von ・fentlichen Angeboten, Erwerb von Wertpapieren und von Unternehmens歟ernahmen; 以下、TOB法という)が制定されるに至った。
同法は、スクィーズ・アウトの手続きを株式法中に導入するなど注目すべき点も多い。公開株式会社、株式合資会社に対して適用され、次のような一般原則を規定する。すなわち、標的会社の同種類株主の平等扱い、買付申込への応募を検討する標的会社株主に対する十分かつ適切な時間・情報の提供、標的会社の取締役の利益相反行為の禁止、買収会社および標的会社における手続き遅延の禁止、相場操縦の禁止、などである。
英国のシティ・コードと比較して、ドイツTOB法の特徴は、強制買付の根拠を「買収者の支配」に置いていることである。すなわち、標的会社の発行済株式に対する割合でなく、標的会社の議決権の30%以上を取得すれば、強制買付制度の適用を受けるとされている。もっとも、TOB法は、強制買付に関し多くの例外を置く。例外事例は、連邦証券取引監視機構(Bundesaufsichtamt f殲 den Wertpapierhandel)が策定したデクレに列挙されている。
対抗措置については、ドイツTOB法によっても制限されている。もっとも、対抗措置が例外的に認められる範囲は英国より広い。たとえば、標的会社の経営陣が合理的注意と権限でもって対抗措置を採択する場合や対抗措置が標的会社の監査役会の承認を得る場合である。また、買収者の買付申込の意思が公表される前の18か月以内に、標的会社の株主が取締役会に対抗措置を講ずる権限を付与すれば、買収者の買付手続きに際して、取締役会は株主総会を開催せずにいかなる対抗措置をも採ることができるとされている。もっとも、このような対抗措置に関する取締役会の広範な裁量権は、TOB法導入以来批判に曝されてきた。
なお、ドイツにおける外国会社との、または外国人株主を含むTOBに関する例外措置も連邦証券取引監視機構の裁量的判断にゆだねられていると解せられる。
3. 米国
米国では、1934年証券取引法をTOBに関して改正する1968年ウィリアムズ法が公開会社に関するTOB規制である(英国のシティ・コードとほぼ同時期に制定されていることは、国際的な企業買収ブームを背景にしてのことであったと思われるが、偶然の一致とも思えない)。規制の執行機関はSECである。以上の連邦の権限に負う立法に加え、米国では会社法や反TOB法は州の立法権に属し、合併、三角合併、株式交換などの他のタイプの組織変更やTOBの対抗措置については、厳密には、連邦立法と州立法の双方を精査しなければその全体像が明らかにならない。とはいえ、本稿では、紙幅の関係上、また、上述のヨーロッパの制度との比肩の観点から、もっぱらウィリアムズ法に焦点を当てる。なお、米国の会社法が州間で異なる以上、外国会社との合併の可否もまた、州によって異なる。一例として、米国における大規模公開会社の多くが設立準拠法とするデラウェア州会社法は、合併相手の外国会社の従属法が外国会社との合併を認める限りにおいて可能としている(252条)。
ウィリアムズ法は、米国国内の全居住者に向けてなされる直接または間接のTOBに対して、また、買付対象が所定の株式証券である場合に、証券取引法およびその関連規則における買付時期や情報開示に関する他の要件とともに適用される。外国会社によるTOBに対してウィリアムズ法が適用されうるのかについては、判然としない。そもそも、ウィリアムズ法には、「公開買付(tender offer;英国のtakeover bidsに相当する)」の概念規定がなく、外国会社からの買付が同法の捕捉範囲か否かが定かでないからである。
したがって、法解釈リスクを回避し、確実にTOBを成功させるために、実務は米国居住株主に対し買付申込をしない形を採ってきた。しかし、このような実務には米国居住株主とその他の株主との平等取り扱いの観点からは相当に問題がある。彼らは、買付申込がなされないため自己の投資価値の実現の機会を奪われるうえ、米国法のもとでの保護も受けられないからである。裁判所もまた、米国居住株主の割合が顕著でない限り、自己の裁判管轄を主張してこなかったので、この問題が法廷で真摯に議論される機会もまたなかった。そこで、SECがこの問題へ対応して設定したのが、前述の米国居住株主の株式保有割合を基準とするTier IおよびTier IIのウィリアムズ法の適用除外要件である。そのほか、SECは、ノー・アクション・レターを発行して買付関係者にウィリアムズ法の適用免除を個別具体的に認定することもできる。SECが個別具体的に認定するこの適用免除が例外基準を形成してきた側面があることは否めない。
1997年にベル・ケイブルメディア社がヴィデオトロン社を株式公開買付によって買収し、ケイブル・アンド・ワイアレス・コミュニケーションズ社を設立した事例では、買収会社も標的会社もともに英国会社であったが、標的会社の株式の一部が米国居住株主によって保有されていた。SECは、適用免除命令を出し、英国のシティ・コードにしたがって、14日の延長買付期間を認めたが、シティ・コードとは異なり、この期間中も買付承諾の撤回権を標的会社の株主に認めた。
また、やや遡るが、1989年に米国のフォード社が英国のジャガー社をTOBによって買収した事例では、ジャガー社の株式の約4分の1が米国居住株主に保有されていた。フォード社は、米国と英国において同時に買付申込を行ったが、その際、SECの適用免除命令により、ウィリアムズ法に基づく買付申込とシティ・コードに基づく買付申込との同時遂行については、ウィリアムズ法上の標的会社の株主平等扱い義務に抵触しないことの確認を行った。
4. おわりに
以上、ヨーロッパ(EU、英国、および、ドイツ)ならびに米国における企業結合規制について、その内容を概観するとともに、国際的企業結合の際の法抵触の問題を検討してきた。わが国において、1999年に株式交換・株式移転制度が導入された際、英フィナンシャル・タイムズ紙は、規制競争上の優位を日本にのみもたらす卑怯な手法と非難した(1999年7月13日付;この記事は、実際には、株式交換・株式移転制度を可能とする商法改正が成立する直前に掲載された。)。日本企業のみが、日本の会社法の適用の恩恵を受け、同法に基づく簡易な買収が可能となり、外国法人が日本市場において間違いなく不利に扱われる、との懸念からである。
そのような懸念が今わが国で現実となっている。もっとも、わが国の懸念は、自国の制度を柔軟化しようとしたところ、黒船に襲われて命からがら引き返すという独り芝居によってもたらされている。冒頭に述べたように、ライブドア事件を契機に外国資本の参入に対する警戒感は、株式交換ではなく三角合併という形で、多少規制のハードルを上げて外国会社との結合を認めたはずであった新会社法の規定の施行さえ、一年凍結させた。また、各会社の定款自治の範囲が拡大し、より企業買収への対抗措置がとりやすくなる新会社法の施行を待たずして、各会社において定款変更により防衛措置を盛り込もうとする動きが実質化しつつある。TOBの際の被買収側の対抗措置については、英国およびドイツでは標的会社の株主意思を尊重し、対抗措置をフリーハンドで認めることはしていない。これに対し、米国では、州会社法上TOBに対する標的会社の対抗措置は会社経営者の裁量措置として許容される傾向にある。州裁判所もまた、対抗措置に合理性が認められる限り認めてきたので、米国では標的会社の発行済株式の10%程度が取得された段階で、すでに対抗措置に乗り出すのが一般的であるという。フリップ・インと呼ばれ、ポイズン・ピルの一種に分類される対抗措置は、買収者が一定割合を買い付けた時点で他の全株主に対し新株予約権を発行して買収者の投資価値を希釈し、さらに標的会社の取締役会にそのようにして発行された新株式の償還権を付与するというもので、実務ではよく利用されている。また、近年では、たとえば、買収者の買付の失敗を条件に株主に高額の配当金を分配する旨の文書を標的会社の取締役が株主に対し配布するなどして、TOBを失敗させる誘因をつくる、いわゆる(ディス)インセンティヴ措置にシフトする傾向があるともいわれる。
もっとも、以上のような米国の企業買収実務は、裁判所による事後規制がよく機能する制度インフラに基づいており、わが国に導入する際には何らかの事前抑制装置が検討されるべきである。この文脈においては、対抗措置の可否をあくまでも株主判断にゆだねるヨーロッパの制度のほうにむしろ学ぶべき点が少なくない。経済産業省と法務省が合同で発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」では、標的会社によるポイズン・ピルの導入に株主総会特別決議を要求しており、わが国における指針のあり方として評価されてよい。
上田純子 (うえだじゅんこ)
名古屋大学法学部卒業、名古屋大学大学院法学研究科博士前期課程修了(法学修士号取得)、名古屋大学大学院法学研究科博士後期課程中退、英国ロンドン大学にてPh.D. in Law(法学博士号)取得、椙山女学園大学現代マネジメント学部教授(現職)
【主要著作】
株式会社における経営の監督と検査役制度(上・下)(民商法雑誌;有斐閣)116巻1号、2号、現代企業取引法(税務経理研究会)(共著)、日本会社立法の歴史的展開(商事法務)(共著)、ほか
国際的M&A(合併・買収)と比較法・抵触法
―ライブドア事件を機縁として―
椙山女学園大学現代マネジメント学部教授 上田純子
1. はじめに
2005年4月18日、ライブドアvsフジサンケイ・グループの株式取得合戦に終止符が打たれた。周知のように、同年2月8日のマスコミに、ニッポン放送の筆頭株主として突如現れたライブドアの堀江貴文社長に対し、フジサンケイ・グループはあの手この手で対抗した。ニッポン放送との資本関係のねじれを是正すべく株式公開買付(以下、TOBという)によって一応公明正大にニッポン放送株を買い集め、同社を子会社化しようとしていたフジテレビジョン(以下、フジという)にとって、堀江氏の株式取得が非礼かつ卑怯な手法と映ったのは当然ともいえる。ポイズン・ピル(毒薬)、クラウン・ジュエル(焦土作戦)、ホワイト・ナイト(白馬の騎士)などの米国の企業買収実務では耳慣れた用語がわが国で飛び交い、当事者たちの株式取得合戦に優るとも劣らないマスコミの情報合戦に国民が踊らされた。2月、3月のうちはニュース画面に両者の攻防の様子が映し出されない日は一日たりともないほどであった。そして、4月になると膠着状態になり、事態は和解に向けて急転回した。しかし、プロローグに比べると何と予想に反するエピローグであったことか。
2005年4月18日の報道各社は、ライブドアが自ら買い占めたニッポン放送株のすべてをフジにTOB価格より高値で売り、フジは、ライブドアの第三者割当増資を引き受けることで合意した旨を一斉に報じた。すなわち、ライブドアはミイラ取りがミイラになったごとく、フジサンケイ・グループの傘下に収まったことになる。ライブドアは1473億円の資金(自己保有株式の売却分と新たにフジが引き受ける第三者割当増資分)を手にするも、フジサンケイ・グループは、将来にわたり、ライブドアの敵対的行動を抑止できるのである。
ライブドアとニッポン放送・フジの“70日戦争”は、とりわけ、ライブドアの奇襲が法律の抜け穴をくぐりぬけるものであっただけに、立法に対する多方面でのインパクトを残した。目下、少なくとも四省庁(金融庁、総務省、法務省、および、経済産業省)がライブドア効果を受け、立法作業に忙殺されている。
第一に、ToSTNeT取引といわれる東京証券取引所(以下、東証という)の時間外取引システムを利用した株式の大量取得は、相対取引に限りなく近い市場取引であることは疑いなく、東証のルール見直しや証券取引法改正の声を呼んだ。ニッポン放送のフジに対する新株予約権の発行についてライブドアの差止請求を認めた東京地裁の決定においては、ToSTNeT取引は、証券取引法上の市場取引にあたり、TOB手続きを強制されないとしながらも(東京高裁決定も同旨)、傍論において、ルール見直しの必要性に触れている。第二に、外国資本によるメディア株式取得規制の改正の検討の契機となった。現行の電波法では、外資の直接出資しか規制しておらず(放送事業者の株式における外国人の議決権を20%に制限しており、放送事業者は、放送法に基づき、この制限比率を超える株式について株主名簿への登載を拒否できる)、ライブドア事件をきっかけに、与党議員らが中心となって内国企業を通じた外資の間接出資をも規制の対象とするよう総務省に強く働きかけ、総務省は、今国会への改正法案提出を決めた。第三に、現在国会にて審議中の新会社法(衆議院では可決済み)のうち、合併対価の柔軟化の部分の施行が一年凍結された。外国会社の株式を対価とする合併(ただし、内国殻会社を通じた三角合併)を可能とする合併対価の柔軟化に関する改正は、新会社法のうち米国の通商担当者に最もアピールする部分であったにもかかわらず、である。さらに、「事業結合規制法」なる、買収者側に事前に標的会社の取締役会に対し、買収の目的や事業の将来計画などを提示のうえ同意を求めさせることなどを含む立法もまた、与党内に設置された「企業統治委員会」を中心に検討されている模様である。同時に、過剰防衛を抑制する方向での検討成果として、各企業に対する合理的範囲内での防衛措置に関する経済産業省と法務省の合同指針が2005年5月27日に公表された(指針全文は、http://www.meti.go.jp/press/20050527005/3-shishinn-honntai-set.pdfからダウンロードできる)。第四に、上場会社ではいよいよ企業買収の脅威が現実化し、2005年3月14日に制御機器メーカーのニレコが初めてポイズン・ピル条項を導入したのを皮切に、おのおの定款変更によって防衛措置を盛り込もうという動きが広がっている。
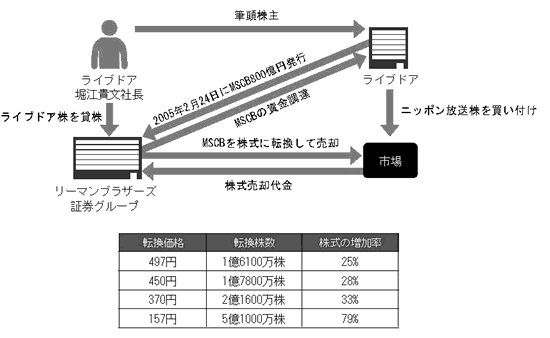
(注)株数はMSCB発行額を転換価格で単純に除したもの。転換価格は、直近3営業日に市場で取引された株価の売買高加重平均価格の平均値の90%。
※図表は、日本経済新聞2005年2月17日付、同2月23日付をもとに作成。
本稿の関心は上記のうち第三点に関わる。第二点も含め、与党議員や企業経営者を中心にいささか興奮気味に外国資本の締め出し策(電波法上の規制に関しては、国家安全保障上の見地も加わるので、必ずしも締め出しの動機や目的は一致しないものの)を講じようという動きが広がるなか、諸外国の企業結合の状況とその規制を概観し、国際的な企業結合規制にともなう法律問題を検討することとしたい。「外国企業との三角合併を可能とする新会社法を先取りする動き」との観測が広がったように、ライブドアは純粋な内国会社であるが、買収の原資は、米国系投資銀行リーマン・ブラザーズ証券グループへの修正条項付転換社債型新株予約権付社債(MSCB)の発行によってまかなわれたため、これを間接的な外国資本による買収とみることも可能である。ライブドアへの株式の実質譲渡人は、外国人投資家ではないかとの憶測もあり、リーマン・ブラザーズ証券が一連の買収工作を指揮したようにもみえる(リーマン自身は否定しているが)。ライブドアは、2005年2月8日のニッポン放送株取得(当日午前9時の取引開始前に、東証の立会外取引システムToSTNeTを利用して、わずか30分足らずの間にニッポン放送株の30%近くを買い入れ、前日までに取得していた分と併せて35%を取得)にあたり、リーマン・ブラザーズから、588億円のつなぎ融資を受けており、融資への返済と投資のための800億円を調達するために、同証券グループにMSCBを発行した(MSCBを利用した資金調達の仕組みについては、前頁の図を参照されたい)。
以下、本稿では国際的な企業結合法制に関する諸問題の検討素材とすべく、ヨーロッパおよびアメリカの状況を概観する。
2. ヨーロッパ
ここでは、域内の越境企業結合規制の採択が進められているヨーロッパ連合(以下、EUという)とその構成国でもある英国およびドイツの企業結合規制について取り上げる。ヨーロッパ委員会は2003年に会社法・企業統治に関するアクション・プランを採択して、この分野における構成国の立法間のギャップの調整を行うべく、統一的なEU立法を模索してきた。
1. EU
東方拡大の途をたどるEUでは、構成国の多様性はますます増大し、各国の企業結合規制もまた多様である。EUにおいて、国際的な企業結合に関する統一的な枠組みを採択しようという動きは早くからあった。このことは、「ヨーロッパ会社」構想が共同体発足とほぼ同時期にスタートしたという事実と無縁ではない。
すなわち、1951年に閣僚理事会において公共サーヴィス事業向けに、多国(構成国)籍資本によって登記地を域内に自由に設定できるヨーロッパ会社(Societas Europaea; SE)という概念が公表され、それは、ロッテルダム大学のサンダーズ教授により、通常の事業会社形態をとってより具体的に構想され、1960年に再公表された。最終的には、2001年にSEに関する規則およびダイレクティヴ(指令、命令ともいう)が採択され、基本的には定款自治と構成国裁量の幅を広く認め、SEが設立される構成国の会社立法に基づいた会社の機関構成や意思決定方式が採用できるようになっている。また、従業員参加については、上記ダイレクティヴにより、従業員参加に関して労使協議を行うことがSE設立の前提として義務づけられ、域内に広がるいわゆるソーシャル・ダンピングの懸念を払拭している。
さて、以上のSEは、構成員が有限責任を負う公開会社でなければならず、域内の複数の法域にまたがる合併や持株会社設立等の方法により設立される。上記の2001年の規則等の採択により、SE化のための域内企業の結合が加速している。また、域外の第三国にあっても、既存の域内子会社や現地法人をSE成りさせ、たとえば税金や人件費がより割安な他の構成国に移転させることも可能となる。
このことと相俟って、TOBに関するダイレクティヴが2004年4月に採択され、越境合併に関するダイレクティヴ案も2003年5月に提出された。後者は、前述のヨーロッパ委員会のアクション・プランに基づいて提案された初めてのダイレクティヴ案である。2005年5月にヨーロッパ委員会意見が採択されたところであり、採択に向け閣僚理事会とヨーロッパ議会との共同手続きの段階に入っている。両者ともに、原始提案は1980年代にまで遡る、採択が相当に難航した(している)ダイレクティヴである。
前者に関しては、英国のシティ・コードを基盤としながら、手続きの細部(たとえば、TOBの公表時期や買付期間など)について、構成国間の多様性を参酌して、幅を持たせた内容となっている。採択が難航した理由として、そもそも、TOBは英国やアイルランドの主要な企業結合手法であり、株式が金融機関等によって集中保有される傾向が強いヨーロッパ大陸においては一般的ではなかったこと、強制買付や対抗措置の導入の可否についての議論が収束しなかったこと、および、構成国が自国の制度(たとえば、ドイツの従業員の機関参加やスウェーデンの対抗措置としての複数議決権株式の発行)が越境TOBによって潜脱されないとの保証を求めたこと、などが挙げられよう。その内容については、シティ・コードに関する後述の節において一括して述べることとする。後者については、公開会社・閉鎖会社の区別なく、すべての株式会社の越境合併を容易にすべく、国内法間のギャップを調整するものである。上記のSEが公開会社のみを対象としているため、このダイレクティヴ案は、採択されれば、SE規則を補完すべく、とりわけ複数の国で営業を展開しようとする閉鎖会社にとって有意義である。
2. 英国
英国の主たる企業結合手法は、上述のように株式取得である。その手続きおよび規定は、会社法およびシティ・コード(City Code on Takeovers and Mergers)(以下、単にコードという場合には、シティ・コードのことを指す)に見出されうる。1985年会社法によるTOBの規定は、Part XIIIAに収められている(第428条ないし第430F条)。会社法では詳細を定めず、もっぱら、標的会社の少数株主保護に主眼を置く。すなわち、TOBに反対する標的会社株主の公正価格での株式買取請求権や、また逆に買収会社側が標的会社の一定多数株式を買い占めた場合の当該会社の少数株主のスクィーズ・アウト(締め出し)権も認められている。以上の会社法の規定は閉鎖会社にも適用されるのに対し、シティ・コードの規定は、連合王国、チャネル島、および、マン島に本店を置くすべての公開会社(listed companiesとquoted companies)に対して適用される。コードは制定法とは異なり理念や原則を中心に定められているが、会社法の規定に比べれば、詳細である。株式取得による企業結合であるから内国会社と外国会社とが当事会社となることも当然ありうる。上述のコードの適用原則によれば、内国会社同士のTOBについては、コードは問題なく適用されることになる。しかし、外国会社によるTOB、外国会社に対するTOB、内国会社であってもそのなかに外国人株主がいる場合、などの際のコードの適用範囲については、コードは何も規定しておらず、また、コードの執行機関であるTOBパネル(Panel on Takeovers and Mergers)もこの点について必ずしも客観的指針を策定しているわけではない。パネルは、抵触法が問題となる場合には、事前の相談を促している。これまでの事例で問題が顕在化したのは、米国の株式公開買付に関するウィリアムズ法との抵触である。とりわけ、規制枠組みの相違から、市場買付、買付期間、買付承諾撤回権、開示要件などに関して、抵触が生じうる。後述するように、この問題は米国サイドでもアプローチされ、証券取引委員会(Securities and Exchange Commission; SEC)の適用免除命令などにより、柔軟な解決が図られてきている。英国のパネルは、米国のTOB規制との抵触については、SEC基準を目安に判断しているようである。
たとえば、米国居住株主の保有株式割合が発行済株式の10%以下である場合、米国SECのTier Iの例外にあたり、標的会社の母国法が適用される。同様に、10%超40%以下である場合はTier IIの例外にあたり、両規制が並列的に適用されうるが、米国法が適用免除になる場合であっても、買付者は、不実開示や不開示、詐欺的または欺罔的行為に起因するウィリアムズ法上のいかなる責任をも免れることはできない。
コードは、イントロダクション、一般原則、定義、および、規則の4部から成る。一般原則では、たとえば、標的会社の同種類株主の平等扱い、買付計画中および買付期間中の買付会社、標的会社、および、それらの会社のアドヴァイザーの平等情報提供義務、買付会社の買付計画確定後の公開買付アナウンス義務、株主に対する十分かつ適切な情報、および、考慮に必要十分な時間の提供、買付文書作成にかかる標的会社およびそのアドヴァイザーの注意義務、買付関係者の相場操縦防止義務、標的会社による対抗措置の原則禁止(株主総会決議がある場合を除く)、少数株主に対する抑圧の禁止、標的会社取締役の利益相反行為の禁止、ならびに、強制買付義務および強制買付遂行予見義務が定められている。これらの総則規定は、コードの理念を抽象的な文言で表したものであり、パネルは、総則をパネルやコードの精神に反しない範囲で適用する。個別事項に関する規則は、細部まで具体的に規定していないので、解釈の疑義等に関してはパネルに個別に問い合わせることになる。
EUダイレクティヴ採択の際に構成国間でその制度設計に関し最も議論されたのは、上述のように、強制買付と対抗措置である。この2つは、それぞれコードのRule 9とRule 21に規定されている。Rule 9によれば、標的会社の株式の一部を取得した者に、残部株式を当該会社の同一株式における過去12か月間の最高値株価で買い取る申し込みをなすことを義務づける。標的会社の株式の一部とは、①30%を超えて取得した場合、または、②申込者が標的会社の議決権の30%ないし50%を取得し、その後12か月以内にさらに議決権の1%以上を取得する場合である。会社の支配権が、公開買付、相対取引、あるいは市場取引のいずれで取得されようが、標的会社の残存株主は、最高の価格で株式を売却して当該会社を去ることが認められるところにその意義がある。
Rule 21によれば、標的会社の取締役・執行役員は、株主総会の承認がない限り、買収会社の買付申込を阻害する行為を行ってはならない。この規定は、買付申込に際してばかりでなく、買付申込前であっても、標的会社の取締役会に買付が切迫していると信ずるに足る理由がある場合に適用される。このような対抗措置としては、新株発行(授権枠外の発行をも含む)、オプションまたは転換証券の発行、資産の売却、会社の通常の営業の部類に属さない契約の締結などが含まれる。買付前に新株発行や資産の売却を行う場合には、当該対抗措置と買付申込との因果関係によりRule 21の適用の可否が判断されることになる。標的会社は、さらに、買付申込に対抗して増配計画や収益の増加を情報開示して株式価値を高め、買付に応じようとする株主にディスインセンティヴを与え、また、ホワイト・ナイトを探すことも可能である。
ちなみに、強制買付および対抗措置について、前述の2004年のEUのTOBダイレクティヴは次のように規定している。すなわち、前者については、構成国に対し、標的会社の少数株主保護の見地から買収者が所定割合の株式を買い付けた場合の強制買付制度の確立を求めている(5条)。構成国は、所定割合について、自国の規制のなかで自由に設定できる。また、後者については、標的会社の株主総会の事前承認(普通決議で可)を条件に、標的会社が対抗措置をとることを認めている(9条)。このEUダイレクティヴの採択によって英国のシティ・コードの規定が変容を迫られることはほとんどないと思われる。すなわち、前言のように、ダイレクティヴは、構成国の多様性に鑑み、細部の規制は構成国の裁量にゆだねる形をとっているためである。ただし、同ダイレクティヴがTOBに関する制定法上の規制機関を求めている点(1条1項)は、英国においてパネルの性格や構造のあり方をめぐる白熱した議論をもたらしている。
3. ドイツ
ドイツでは、第二次世界大戦後、1999年に同国のマンネスマン社が英国のヴォーダフォン社に敵対的TOBをしかけられるまで、敵対的企業買収はわずか3件しかなかった。前述のように、ドイツでは金融機関による株式の集中保有傾向が強く、少なくとも敵対的企業買収は起こりえない環境にあったからである。たとえば、1990年代の平均GDPにおいて、ドイツ、フランス、および、英国は、EU全体のそれぞれ28%、18%、および、13%を占めていたが、M&A総額でみると、それぞれ17%、14%、および、30%であった。すなわち、ドイツのGDPは英国のそれの約2倍であるが、M&A総額でみると約半分でしかない。したがって、少なくとも1990年代時点では、たしかにドイツにおけるM&Aは相対的に少なかったことがデータ的にも裏づけられうる。
株式取得型の企業結合に代わってドイツで利用されてきたのは「一方の会社の財産全体が他方の会社または合併によって新設される会社に包括承継され、財産を移転した会社は清算手続きを経ずして解散し、その株主は財産移転を受けた会社の株主となる」合併であった。外国会社との合併の可否に関するドイツの議論は、組織変更法上は外国会社との合併は可能であるが、抵触法上の観点からは認められないというものであった。すなわち、抵触法の分野の議論において有力であった単一準拠法説(合併当事会社の一方の従属法のみを適用すると解する)は、一方の合併当事会社の利害関係者の保護が図られなくなるとして、国際的な合併を認めてこなかったのである。もっとも、近年のドイツにおける議論は両当事会社の従属法を適用することによって国際的な合併を認める方向に変わってきている。
さらに、ドイツにおける近年の注目すべき動きとして、TOB規制を整備したことが挙げられる。1995年には連邦財務省所管の取引専門家委員会によってTOBコードが策定されたが、コードより強制力が強い制定法レヴェルの規制の採択が望まれた結果、2001年に公募、証券売買・事業承継法(Gesetz zur Regelung von ・fentlichen Angeboten, Erwerb von Wertpapieren und von Unternehmens歟ernahmen; 以下、TOB法という)が制定されるに至った。
同法は、スクィーズ・アウトの手続きを株式法中に導入するなど注目すべき点も多い。公開株式会社、株式合資会社に対して適用され、次のような一般原則を規定する。すなわち、標的会社の同種類株主の平等扱い、買付申込への応募を検討する標的会社株主に対する十分かつ適切な時間・情報の提供、標的会社の取締役の利益相反行為の禁止、買収会社および標的会社における手続き遅延の禁止、相場操縦の禁止、などである。
英国のシティ・コードと比較して、ドイツTOB法の特徴は、強制買付の根拠を「買収者の支配」に置いていることである。すなわち、標的会社の発行済株式に対する割合でなく、標的会社の議決権の30%以上を取得すれば、強制買付制度の適用を受けるとされている。もっとも、TOB法は、強制買付に関し多くの例外を置く。例外事例は、連邦証券取引監視機構(Bundesaufsichtamt f殲 den Wertpapierhandel)が策定したデクレに列挙されている。
対抗措置については、ドイツTOB法によっても制限されている。もっとも、対抗措置が例外的に認められる範囲は英国より広い。たとえば、標的会社の経営陣が合理的注意と権限でもって対抗措置を採択する場合や対抗措置が標的会社の監査役会の承認を得る場合である。また、買収者の買付申込の意思が公表される前の18か月以内に、標的会社の株主が取締役会に対抗措置を講ずる権限を付与すれば、買収者の買付手続きに際して、取締役会は株主総会を開催せずにいかなる対抗措置をも採ることができるとされている。もっとも、このような対抗措置に関する取締役会の広範な裁量権は、TOB法導入以来批判に曝されてきた。
なお、ドイツにおける外国会社との、または外国人株主を含むTOBに関する例外措置も連邦証券取引監視機構の裁量的判断にゆだねられていると解せられる。
3. 米国
米国では、1934年証券取引法をTOBに関して改正する1968年ウィリアムズ法が公開会社に関するTOB規制である(英国のシティ・コードとほぼ同時期に制定されていることは、国際的な企業買収ブームを背景にしてのことであったと思われるが、偶然の一致とも思えない)。規制の執行機関はSECである。以上の連邦の権限に負う立法に加え、米国では会社法や反TOB法は州の立法権に属し、合併、三角合併、株式交換などの他のタイプの組織変更やTOBの対抗措置については、厳密には、連邦立法と州立法の双方を精査しなければその全体像が明らかにならない。とはいえ、本稿では、紙幅の関係上、また、上述のヨーロッパの制度との比肩の観点から、もっぱらウィリアムズ法に焦点を当てる。なお、米国の会社法が州間で異なる以上、外国会社との合併の可否もまた、州によって異なる。一例として、米国における大規模公開会社の多くが設立準拠法とするデラウェア州会社法は、合併相手の外国会社の従属法が外国会社との合併を認める限りにおいて可能としている(252条)。
ウィリアムズ法は、米国国内の全居住者に向けてなされる直接または間接のTOBに対して、また、買付対象が所定の株式証券である場合に、証券取引法およびその関連規則における買付時期や情報開示に関する他の要件とともに適用される。外国会社によるTOBに対してウィリアムズ法が適用されうるのかについては、判然としない。そもそも、ウィリアムズ法には、「公開買付(tender offer;英国のtakeover bidsに相当する)」の概念規定がなく、外国会社からの買付が同法の捕捉範囲か否かが定かでないからである。
したがって、法解釈リスクを回避し、確実にTOBを成功させるために、実務は米国居住株主に対し買付申込をしない形を採ってきた。しかし、このような実務には米国居住株主とその他の株主との平等取り扱いの観点からは相当に問題がある。彼らは、買付申込がなされないため自己の投資価値の実現の機会を奪われるうえ、米国法のもとでの保護も受けられないからである。裁判所もまた、米国居住株主の割合が顕著でない限り、自己の裁判管轄を主張してこなかったので、この問題が法廷で真摯に議論される機会もまたなかった。そこで、SECがこの問題へ対応して設定したのが、前述の米国居住株主の株式保有割合を基準とするTier IおよびTier IIのウィリアムズ法の適用除外要件である。そのほか、SECは、ノー・アクション・レターを発行して買付関係者にウィリアムズ法の適用免除を個別具体的に認定することもできる。SECが個別具体的に認定するこの適用免除が例外基準を形成してきた側面があることは否めない。
1997年にベル・ケイブルメディア社がヴィデオトロン社を株式公開買付によって買収し、ケイブル・アンド・ワイアレス・コミュニケーションズ社を設立した事例では、買収会社も標的会社もともに英国会社であったが、標的会社の株式の一部が米国居住株主によって保有されていた。SECは、適用免除命令を出し、英国のシティ・コードにしたがって、14日の延長買付期間を認めたが、シティ・コードとは異なり、この期間中も買付承諾の撤回権を標的会社の株主に認めた。
また、やや遡るが、1989年に米国のフォード社が英国のジャガー社をTOBによって買収した事例では、ジャガー社の株式の約4分の1が米国居住株主に保有されていた。フォード社は、米国と英国において同時に買付申込を行ったが、その際、SECの適用免除命令により、ウィリアムズ法に基づく買付申込とシティ・コードに基づく買付申込との同時遂行については、ウィリアムズ法上の標的会社の株主平等扱い義務に抵触しないことの確認を行った。
4. おわりに
以上、ヨーロッパ(EU、英国、および、ドイツ)ならびに米国における企業結合規制について、その内容を概観するとともに、国際的企業結合の際の法抵触の問題を検討してきた。わが国において、1999年に株式交換・株式移転制度が導入された際、英フィナンシャル・タイムズ紙は、規制競争上の優位を日本にのみもたらす卑怯な手法と非難した(1999年7月13日付;この記事は、実際には、株式交換・株式移転制度を可能とする商法改正が成立する直前に掲載された。)。日本企業のみが、日本の会社法の適用の恩恵を受け、同法に基づく簡易な買収が可能となり、外国法人が日本市場において間違いなく不利に扱われる、との懸念からである。
そのような懸念が今わが国で現実となっている。もっとも、わが国の懸念は、自国の制度を柔軟化しようとしたところ、黒船に襲われて命からがら引き返すという独り芝居によってもたらされている。冒頭に述べたように、ライブドア事件を契機に外国資本の参入に対する警戒感は、株式交換ではなく三角合併という形で、多少規制のハードルを上げて外国会社との結合を認めたはずであった新会社法の規定の施行さえ、一年凍結させた。また、各会社の定款自治の範囲が拡大し、より企業買収への対抗措置がとりやすくなる新会社法の施行を待たずして、各会社において定款変更により防衛措置を盛り込もうとする動きが実質化しつつある。TOBの際の被買収側の対抗措置については、英国およびドイツでは標的会社の株主意思を尊重し、対抗措置をフリーハンドで認めることはしていない。これに対し、米国では、州会社法上TOBに対する標的会社の対抗措置は会社経営者の裁量措置として許容される傾向にある。州裁判所もまた、対抗措置に合理性が認められる限り認めてきたので、米国では標的会社の発行済株式の10%程度が取得された段階で、すでに対抗措置に乗り出すのが一般的であるという。フリップ・インと呼ばれ、ポイズン・ピルの一種に分類される対抗措置は、買収者が一定割合を買い付けた時点で他の全株主に対し新株予約権を発行して買収者の投資価値を希釈し、さらに標的会社の取締役会にそのようにして発行された新株式の償還権を付与するというもので、実務ではよく利用されている。また、近年では、たとえば、買収者の買付の失敗を条件に株主に高額の配当金を分配する旨の文書を標的会社の取締役が株主に対し配布するなどして、TOBを失敗させる誘因をつくる、いわゆる(ディス)インセンティヴ措置にシフトする傾向があるともいわれる。
もっとも、以上のような米国の企業買収実務は、裁判所による事後規制がよく機能する制度インフラに基づいており、わが国に導入する際には何らかの事前抑制装置が検討されるべきである。この文脈においては、対抗措置の可否をあくまでも株主判断にゆだねるヨーロッパの制度のほうにむしろ学ぶべき点が少なくない。経済産業省と法務省が合同で発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」では、標的会社によるポイズン・ピルの導入に株主総会特別決議を要求しており、わが国における指針のあり方として評価されてよい。
上田純子 (うえだじゅんこ)
名古屋大学法学部卒業、名古屋大学大学院法学研究科博士前期課程修了(法学修士号取得)、名古屋大学大学院法学研究科博士後期課程中退、英国ロンドン大学にてPh.D. in Law(法学博士号)取得、椙山女学園大学現代マネジメント学部教授(現職)
【主要著作】
株式会社における経営の監督と検査役制度(上・下)(民商法雑誌;有斐閣)116巻1号、2号、現代企業取引法(税務経理研究会)(共著)、日本会社立法の歴史的展開(商事法務)(共著)、ほか
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























