コラム2005年06月13日 【SCOPE】 東京地裁がニレコの新株予約権発行を差し止め(2005年6月13日号・№118)
取締役会決議で導入する事前対抗策の基準を示す
東京地裁がニレコの新株予約権発行を差し止め
東京地裁は6月1日、ニレコの新株予約権の発行を差し止める仮処分命令を下した。ニレコの新株予約権の発行については、5月9日付けで投資ファンドであるザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテッドより差し止めの仮処分申請が行われていたもの。東京地裁では、本件について、①株主総会の意思を反映させる仕組みに欠ける、②取締役会の恣意的判断の防止が担保される仕組みに欠ける、③買収者とは関係のない株主に不測の損害を与えるなどの理由を挙げている。また、取締役会決議により事前の対抗策として新株予約権の発行を認める基準も示しており、注目される。なお、ニレコは6月2日付けで東京地裁に対して異議申立てを行っている。
東京高裁での例示に準拠
JASDAQに上場する株式会社ニレコは3月14日、株主全員に新株予約権の無償発行(「セキュリティ・プラン」)を行うことを公表した。企業買収によって、企業価値が害されることを未然に防止する目的から導入するもので、日本初のポイズン・ピルとして注目を浴びていた。具体的には、3月末の株主に対し、1株につき2個の割合で新株予約権を無償で割当てるというもの。新株予約権の行使期間中である平成17年6月16日から平成20年6月16日までの間に、ある者がニレコの発行済議決権付株式総数の20%以上を取得した場合に行使することが可能。一方、企業買収がニレコの企業価値の最大化に資するような提案であれば、取締役会決議により、新株予約権の全部が無償で消却される。
また、取締役会が①企業価値の最大化の観点から手続開始要件の「20%」の割合を引き上げる必要があるか、②企業価値の最大化のために新株予約権を消却するかといった判断については、利害関係のない弁護士等から構成される3名の特別委員会で判断を行うとしている。
なお、ニレコでは、新株予約権の無償消却をしない旨を決議する場合の基準を定めたガイドラインを策定している。ガイドラインでは、(ア)グリーンメイラーである場合、(イ)焦土化経営目的、(ウ)LBO、(エ)株式の高値売り抜け、(オ)買収者が債務者の経営を支配した場合、株主、取引先、顧客、地域社会、従業員その他の債務者の利害関係者を含むグループの企業価値が毀損されるおそれがある場合を挙げている。(ア)から(エ)については、ニッポン放送の新株予約権発行差止保全抗告事件(東京地裁平成17年3月23日、本誌№109参照)で示された例示と同様である。
しかし、ニレコの新株予約権の発行については、事前に新株予約権を割当てるため、敵対的買収者が現れた時点の株主と新株予約権を持つ者とが一致せず、新株予約権を保有していない株主が不利になる点が指摘されていた(右上図参照)。東京証券取引所が通知した「敵対的買収防衛策の導入に際しての投資者保護上の留意事項について」や先日公表された企業価値指針などでも適当でない旨が明記されており、今回の東京地裁での判断が注目されていた。
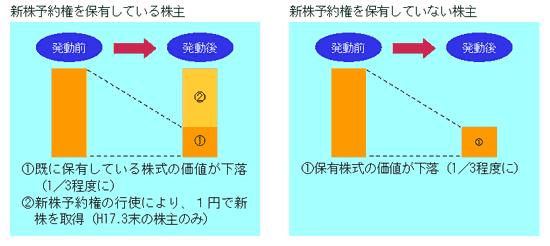
社外者の意見を尊重するだけでは不十分
東京地裁では、まず、事前の防衛策としての新株予約権の発行は、原則として株主総会の意思に基づいて行うべきとしながらも、取締役会の決議により、事前の対抗策として新株予約権の発行を行うための基準を示している。具体的には、①新株予約権が株主総会の判断により消却可能なもの、②新株予約権の行使が敵対的買収者による支配権取得が会社に回復し難い損害をもたらす事業がある場合(グリーンメイラーなど)に限定されるとともに客観的な消却条件の設定や独立性の高い社外者が消却の判断を行うなど、取締役会の恣意的判断が防止される仕組みのもの、③買収者とは無関係の株主に不測の損害を与えるものではないことを挙げた。
ニレコの新株予約権の発行についてみると、デッドハンド条項はなく、新株予約権の行使可能期間は発行日から3年間とされているほか、取締役会決議により無償での消却が可能となっている。しかし、東京地裁では、新株予約権発行後の平成17年6月の株主総会において、新株予約権導入に関する定款変更は議題として行われていないほか、取締役の任期も平成18年6月までであるため、株主総会の意思を反映させる仕組みは設けられていないと判断した。また、ニレコのガイドラインについては、前記(ア)から(エ)までの基準は合理的であるとしたが、(オ)の基準は、取締役会の恣意的判断を防止するための判断基準としては、明確性を欠く部分があると指摘。加えて、特別委員会については、独立性を有するものの、取締役会が特別委員会の勧告をすべて受け入れるわけではないと指摘した。
なお、権利落ち日以降に株式を取得した株主は、持株比率の希薄化するリスクを理解したともいえるが、既存株主にとっては、投資対象としての魅力の減少による価値の低下は看過できない不測の損害であるという判断を示している。
ポイント
原則は株主総会⇒取締役会決議で行うには、
① 新株予約権が株主総会の判断により消却可能
② 敵対的買収者による支配権取得が会社に回復し難い損害をもたらす事業がある場合に限定
③ 客観的な消却条件の設定や独立性の高い社外者が消却の判断できる仕組み
④ 買収者とは無関係の株主に不測の損害を与えるものではないこと
東京地裁がニレコの新株予約権発行を差し止め
東京地裁は6月1日、ニレコの新株予約権の発行を差し止める仮処分命令を下した。ニレコの新株予約権の発行については、5月9日付けで投資ファンドであるザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテッドより差し止めの仮処分申請が行われていたもの。東京地裁では、本件について、①株主総会の意思を反映させる仕組みに欠ける、②取締役会の恣意的判断の防止が担保される仕組みに欠ける、③買収者とは関係のない株主に不測の損害を与えるなどの理由を挙げている。また、取締役会決議により事前の対抗策として新株予約権の発行を認める基準も示しており、注目される。なお、ニレコは6月2日付けで東京地裁に対して異議申立てを行っている。
東京高裁での例示に準拠
JASDAQに上場する株式会社ニレコは3月14日、株主全員に新株予約権の無償発行(「セキュリティ・プラン」)を行うことを公表した。企業買収によって、企業価値が害されることを未然に防止する目的から導入するもので、日本初のポイズン・ピルとして注目を浴びていた。具体的には、3月末の株主に対し、1株につき2個の割合で新株予約権を無償で割当てるというもの。新株予約権の行使期間中である平成17年6月16日から平成20年6月16日までの間に、ある者がニレコの発行済議決権付株式総数の20%以上を取得した場合に行使することが可能。一方、企業買収がニレコの企業価値の最大化に資するような提案であれば、取締役会決議により、新株予約権の全部が無償で消却される。
また、取締役会が①企業価値の最大化の観点から手続開始要件の「20%」の割合を引き上げる必要があるか、②企業価値の最大化のために新株予約権を消却するかといった判断については、利害関係のない弁護士等から構成される3名の特別委員会で判断を行うとしている。
なお、ニレコでは、新株予約権の無償消却をしない旨を決議する場合の基準を定めたガイドラインを策定している。ガイドラインでは、(ア)グリーンメイラーである場合、(イ)焦土化経営目的、(ウ)LBO、(エ)株式の高値売り抜け、(オ)買収者が債務者の経営を支配した場合、株主、取引先、顧客、地域社会、従業員その他の債務者の利害関係者を含むグループの企業価値が毀損されるおそれがある場合を挙げている。(ア)から(エ)については、ニッポン放送の新株予約権発行差止保全抗告事件(東京地裁平成17年3月23日、本誌№109参照)で示された例示と同様である。
しかし、ニレコの新株予約権の発行については、事前に新株予約権を割当てるため、敵対的買収者が現れた時点の株主と新株予約権を持つ者とが一致せず、新株予約権を保有していない株主が不利になる点が指摘されていた(右上図参照)。東京証券取引所が通知した「敵対的買収防衛策の導入に際しての投資者保護上の留意事項について」や先日公表された企業価値指針などでも適当でない旨が明記されており、今回の東京地裁での判断が注目されていた。
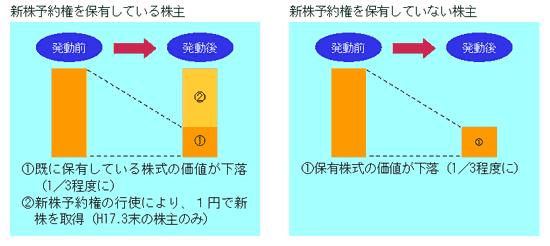
社外者の意見を尊重するだけでは不十分
東京地裁では、まず、事前の防衛策としての新株予約権の発行は、原則として株主総会の意思に基づいて行うべきとしながらも、取締役会の決議により、事前の対抗策として新株予約権の発行を行うための基準を示している。具体的には、①新株予約権が株主総会の判断により消却可能なもの、②新株予約権の行使が敵対的買収者による支配権取得が会社に回復し難い損害をもたらす事業がある場合(グリーンメイラーなど)に限定されるとともに客観的な消却条件の設定や独立性の高い社外者が消却の判断を行うなど、取締役会の恣意的判断が防止される仕組みのもの、③買収者とは無関係の株主に不測の損害を与えるものではないことを挙げた。
ニレコの新株予約権の発行についてみると、デッドハンド条項はなく、新株予約権の行使可能期間は発行日から3年間とされているほか、取締役会決議により無償での消却が可能となっている。しかし、東京地裁では、新株予約権発行後の平成17年6月の株主総会において、新株予約権導入に関する定款変更は議題として行われていないほか、取締役の任期も平成18年6月までであるため、株主総会の意思を反映させる仕組みは設けられていないと判断した。また、ニレコのガイドラインについては、前記(ア)から(エ)までの基準は合理的であるとしたが、(オ)の基準は、取締役会の恣意的判断を防止するための判断基準としては、明確性を欠く部分があると指摘。加えて、特別委員会については、独立性を有するものの、取締役会が特別委員会の勧告をすべて受け入れるわけではないと指摘した。
なお、権利落ち日以降に株式を取得した株主は、持株比率の希薄化するリスクを理解したともいえるが、既存株主にとっては、投資対象としての魅力の減少による価値の低下は看過できない不測の損害であるという判断を示している。
ポイント
原則は株主総会⇒取締役会決議で行うには、
① 新株予約権が株主総会の判断により消却可能
② 敵対的買収者による支配権取得が会社に回復し難い損害をもたらす事業がある場合に限定
③ 客観的な消却条件の設定や独立性の高い社外者が消却の判断できる仕組み
④ 買収者とは無関係の株主に不測の損害を与えるものではないこと
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























