コラム2005年07月11日 【SCOPE】 会社法の子会社の会計帳簿閲覧権に疑問(2005年7月11日号・№122)
単独株主権でもOK?
会社法の子会社の会計帳簿閲覧権に疑問
会社法案及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案が6月29日、国会で成立した。施行日については、公布の日から1年6ヶ月を超えない範囲において政令で定める日とされている(合併対価の柔軟化に関する部分は施行日から1年は適用しない)。平成18年4月頃には施行される見込みだ。
会社法については、979条にも及ぶ膨大な条文から構成されているため、法律の作成についてもたいへんな労力を要したものといえよう。ただ、法律の文言の一部には疑義が生じる部分も見受けられる。それが子会社の会計帳簿閲覧権だ。今回のスコープでは、会社法第433条(会計帳簿の閲覧等の請求)の詳細についてみてみることにする。
現行の商法では総株主の議決権の3%以上が必要
会社の会計帳簿閲覧権は、現行の商法では総株主の議決権の3%以上を有する少数株主について認められている権利である。また、親会社の会計帳簿閲覧権を有する親会社株主については、子会社の会計帳簿閲覧権も有することとされている(商法第293ノ8①)。
法制審議会が2月9日に公表した「会社法制の現代化に関する要綱」では、「取締役会を設置しない株式会社においても、少数株主権の要件については、現行の株式会社と同様のものとする。」(要綱第4・5(2)③)とされている。したがって、少数株主権の要件の内容については、従来どおりであり、特段の改正は行わないものと推察されていた。
直接株主でも少数株主権なのに
この点、会社法第433条第1項をみると、会計帳簿閲覧権について、株式会社の直接の株主については、従来どおり、総株主の議決権の3%以上の議決権を有する株主とされている。しかし、その一方で、子会社の会計帳簿閲覧権については、「親会社社員」が行使できるとされている(第433条第3項)。一見、単独株主権(※1株の株主であっても行使できる権利)と読むことができる。
疑問が生じるのは、株式会社の直接の株主については、少数株主権であるにもかかわらず、子会社に対しては単独株主権になるという点だ。通常は考えられず、会社法を作成した際における誤りではないかと考えられそうだ。
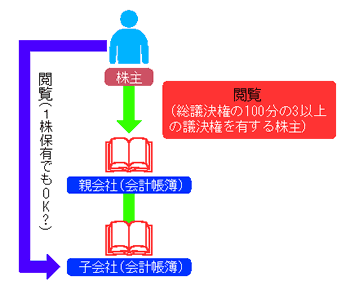
法務省は従来の解釈と同じと説明
この点、法務省では、現行どおりの解釈と同じであると説明している。
つまり、親会社社員であっても、子会社の帳簿閲覧権は、総株主の議決権の3%以上を有することが必要になる。また、「疑義が生じるかもしれないが、現時点では、修正する予定はない」と述べている。
今後の対応が注目される点である。
【現行商法】
第293条ノ8 親会社ノ株主ニシテ其ノ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スルモノハ其ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ子会社ノ会計ノ帳簿及資料ニ係ル第二百九十三条ノ六第一項ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得
【会社法制の現代化に関する要綱】
第4 株式・新株予約権・新株予約権付社債関係(5(2)少数株主権等)
③ 行使要件
取締役会を設置しない株式会社においても、少数株主権の要件については、現行の株式会社と同様のものとする。
(注1)定款をもって、少数株主権とされている権利の全部について、その行使要件を引き下げ、又は単独株主権とすることは妨げられないものとする。
(注2)株式譲渡制限会社においては、単独株主権・少数株主権における6 か月の保有期間制限は課さないものとする。
【会社法】
(会計帳簿の閲覧等の請求)
第433条 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2 (略)
3 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第一項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
4 (略)
会社法の子会社の会計帳簿閲覧権に疑問
会社法案及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案が6月29日、国会で成立した。施行日については、公布の日から1年6ヶ月を超えない範囲において政令で定める日とされている(合併対価の柔軟化に関する部分は施行日から1年は適用しない)。平成18年4月頃には施行される見込みだ。
会社法については、979条にも及ぶ膨大な条文から構成されているため、法律の作成についてもたいへんな労力を要したものといえよう。ただ、法律の文言の一部には疑義が生じる部分も見受けられる。それが子会社の会計帳簿閲覧権だ。今回のスコープでは、会社法第433条(会計帳簿の閲覧等の請求)の詳細についてみてみることにする。
現行の商法では総株主の議決権の3%以上が必要
会社の会計帳簿閲覧権は、現行の商法では総株主の議決権の3%以上を有する少数株主について認められている権利である。また、親会社の会計帳簿閲覧権を有する親会社株主については、子会社の会計帳簿閲覧権も有することとされている(商法第293ノ8①)。
法制審議会が2月9日に公表した「会社法制の現代化に関する要綱」では、「取締役会を設置しない株式会社においても、少数株主権の要件については、現行の株式会社と同様のものとする。」(要綱第4・5(2)③)とされている。したがって、少数株主権の要件の内容については、従来どおりであり、特段の改正は行わないものと推察されていた。
直接株主でも少数株主権なのに
この点、会社法第433条第1項をみると、会計帳簿閲覧権について、株式会社の直接の株主については、従来どおり、総株主の議決権の3%以上の議決権を有する株主とされている。しかし、その一方で、子会社の会計帳簿閲覧権については、「親会社社員」が行使できるとされている(第433条第3項)。一見、単独株主権(※1株の株主であっても行使できる権利)と読むことができる。
疑問が生じるのは、株式会社の直接の株主については、少数株主権であるにもかかわらず、子会社に対しては単独株主権になるという点だ。通常は考えられず、会社法を作成した際における誤りではないかと考えられそうだ。
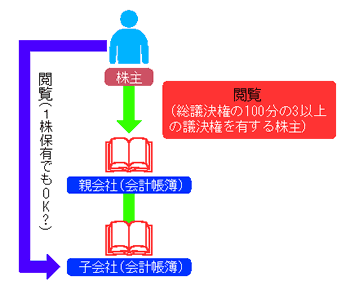
法務省は従来の解釈と同じと説明
この点、法務省では、現行どおりの解釈と同じであると説明している。
つまり、親会社社員であっても、子会社の帳簿閲覧権は、総株主の議決権の3%以上を有することが必要になる。また、「疑義が生じるかもしれないが、現時点では、修正する予定はない」と述べている。
今後の対応が注目される点である。
【現行商法】
第293条ノ8 親会社ノ株主ニシテ其ノ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スルモノハ其ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ子会社ノ会計ノ帳簿及資料ニ係ル第二百九十三条ノ六第一項ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得
【会社法制の現代化に関する要綱】
第4 株式・新株予約権・新株予約権付社債関係(5(2)少数株主権等)
③ 行使要件
取締役会を設置しない株式会社においても、少数株主権の要件については、現行の株式会社と同様のものとする。
(注1)定款をもって、少数株主権とされている権利の全部について、その行使要件を引き下げ、又は単独株主権とすることは妨げられないものとする。
(注2)株式譲渡制限会社においては、単独株主権・少数株主権における6 か月の保有期間制限は課さないものとする。
【会社法】
(会計帳簿の閲覧等の請求)
第433条 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2 (略)
3 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第一項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
4 (略)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























