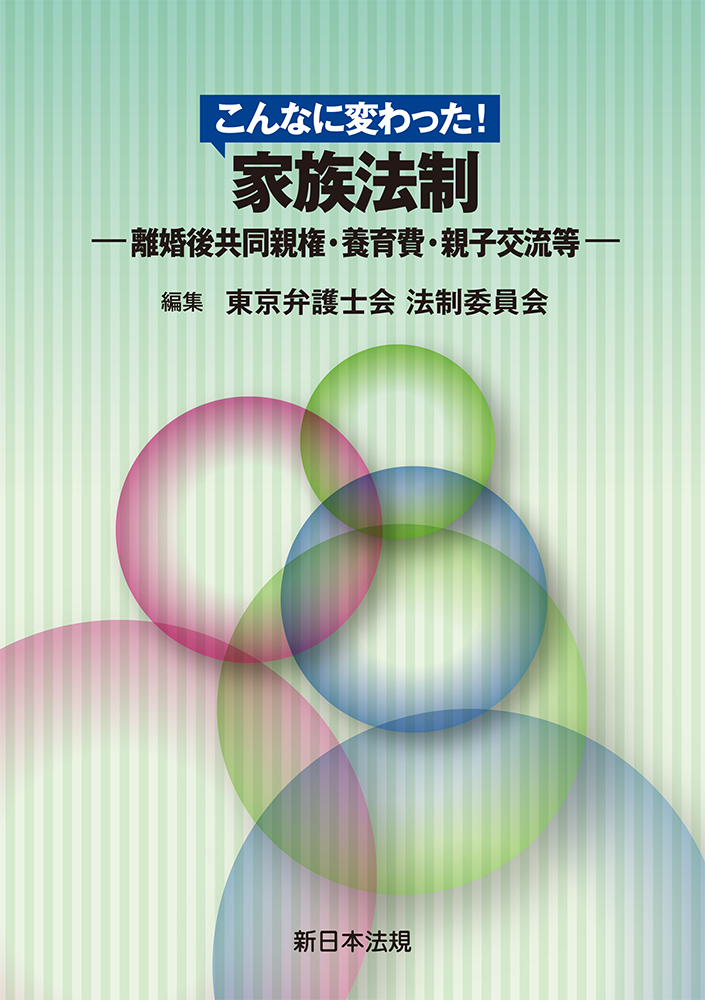税務ニュース2003年01月06日 孫養子・生命保険権利評価の見直しでタックスプランニングは大混乱 15年改正 税率構造見直し実現も、課税ベ-スの拡大は先送り
孫養子・生命保険権利評価の見直しでタックスプランニングは大混乱
15年改正 税率構造見直し実現も、課税ベ-スの拡大は先送り
相続税・贈与税では、最高税率の引下げ及び税率区分の見直しが行われ、孫養子・生命保険権利評価の取扱いも見直されることになった。タックスプランニングを再検討する必要がありそうだ。
相続税・贈与税の税率構造の見直し
相続税・贈与税ともに最高税率が70%から50%に引き下げられるとともに、税率区分を簡素化・拡大した。新税率区分に基づく相続税・贈与税の速算表は、次のとおり。相続税の基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)・贈与税の基礎控除(110万円)は、据え置かれる。
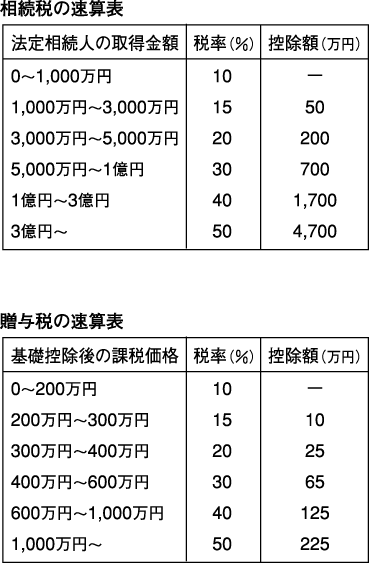
孫養子の相続税は、2割加算制度の対象に
相続税法18条では、「被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含む。)及び配偶者以外の者の相続税額は、算出した相続税額の20%相当額を加算した金額とする。」と規定している。
養子については、一親等の血族として、この2割加算制度の対象とはなっていなかった。しかし、租税回避目的と思われる孫養子が横行していることもあり、2割加算の対象として取り扱うことにしたようだ。
生命保険の権利評価が解約返戻金相当額に
相続税法26条では、「保険事故が発生していないものに関する生命保険契約に関する権利の価額は、払い込まれた保険料の合計金額の70%から保険金額の2%を控除した金額とする(一時払い契約を除く。)。」と規定している。
大綱では、この法定評価を所要の経過措置を講じたうえ廃止し、解約返戻金の額を用いて評価することとしている。
現在、解約返戻金と法定評価額に乖離のある保険商品が、相続税の節税・資金対策として広く販売されている。生命保険の権利評価を利用した手法は、相続人全員を被保険者とすることもできるので、相続税対策には重宝なものとなっていた反面、この数年、毎年改正の噂が流布されていた。
経過措置の内容と生命保険会社の対応が注目される。
15年改正 税率構造見直し実現も、課税ベ-スの拡大は先送り
相続税・贈与税では、最高税率の引下げ及び税率区分の見直しが行われ、孫養子・生命保険権利評価の取扱いも見直されることになった。タックスプランニングを再検討する必要がありそうだ。
相続税・贈与税の税率構造の見直し
相続税・贈与税ともに最高税率が70%から50%に引き下げられるとともに、税率区分を簡素化・拡大した。新税率区分に基づく相続税・贈与税の速算表は、次のとおり。相続税の基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)・贈与税の基礎控除(110万円)は、据え置かれる。
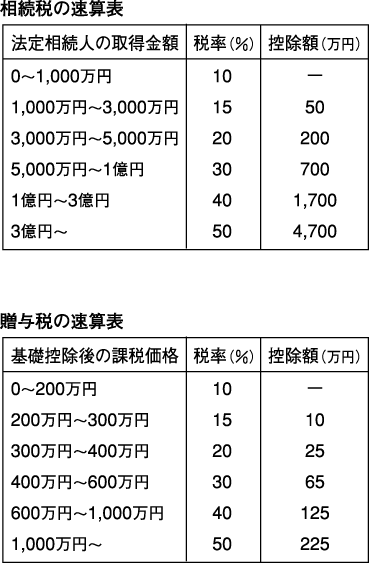
孫養子の相続税は、2割加算制度の対象に
相続税法18条では、「被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含む。)及び配偶者以外の者の相続税額は、算出した相続税額の20%相当額を加算した金額とする。」と規定している。
養子については、一親等の血族として、この2割加算制度の対象とはなっていなかった。しかし、租税回避目的と思われる孫養子が横行していることもあり、2割加算の対象として取り扱うことにしたようだ。
生命保険の権利評価が解約返戻金相当額に
相続税法26条では、「保険事故が発生していないものに関する生命保険契約に関する権利の価額は、払い込まれた保険料の合計金額の70%から保険金額の2%を控除した金額とする(一時払い契約を除く。)。」と規定している。
大綱では、この法定評価を所要の経過措置を講じたうえ廃止し、解約返戻金の額を用いて評価することとしている。
現在、解約返戻金と法定評価額に乖離のある保険商品が、相続税の節税・資金対策として広く販売されている。生命保険の権利評価を利用した手法は、相続人全員を被保険者とすることもできるので、相続税対策には重宝なものとなっていた反面、この数年、毎年改正の噂が流布されていた。
経過措置の内容と生命保険会社の対応が注目される。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.