解説記事2005年10月17日 【制度解説】 LLP制度の概要―経済活力の向上のための新しいパートナーシップ―(2005年10月17日号・№134)
実 務 解 説
LLP制度の概要―経済活力の向上のための新しいパートナーシップ―
経済産業省 経済産業政策局 産業組織課 課長補佐 石井芳明
はじめに
LLP(Limited Liability Partnership)制度を創設する「有限責任事業組合契約に関する法律」(平成17年法律第40号)が平成17年4月27日に第162回国会において成立し、8月1日に施行された。
LLPは、①構成員の有限責任、②組織の内部自治、③構成員課税という3つの特徴を合わせ持つ組織で、企業同士のジョイント・ベンチャーや専門人材の共同事業を振興し、創業を促進する効果がある。本稿においては、LLP制度創設の背景と法律の概要について紹介する。
1.LLP制度の背景
近年、ビジネスを巡る環境が大きく変化している。情報化や国際化の進展により国境を越えた企業間競争が激化し、市場の成熟化や多様化に伴い顧客ニーズが複雑化している。このような状況を受けて、企業が優位性を持つための経営資源として「人的資産」の重要性がクローズアップされている。これからの時代において企業の競争力は人的資本の蓄積と活用による。(脚注1)
また、企業同士が「共同事業」を実施することの重要性も高まっている。人的資本や物的資本を出し合って、相互補完、資源共有、リスク共有の共同事業を実施することによって、より強固な競争力、より大きな価値を創出することが可能となる。
こうした中、人的資産を活かす組織形態、共同事業のための組織形態として、コアとなる人材や企業が出資者と経営者を兼ねているようなパートナーシップ型の組織形態が欧米で注目されている。パートナーシップは、日本でいう組合であり、個性を有する個人・法人が一定の目的のもと出資をして共同事業を営む組織形態である。資金供給者である「株主」対「経営者・従業員」という所有と経営の分離の構図でなく、「出資者=経営者(パートナー)」というのが基本の組織で、所有と経営が一致しているため、業務執行、利益分配等の組織の内部ルールをパートナー間で柔軟に設定できる。専門的な能力を有する個人にとっては「会社に雇われる」のではなく、「自らが自らのボスとなる」ので、自分たちの能力を引き出しやすい組織づくりができる。また、企業同士の連携においても、資本の論理でなく、より柔軟な組織設計が可能となる。
特に、欧米では、従前のパートナーシップに構成員の有限責任制(構成員が出資額を限度に組織の責任を負う仕組み)を付与したLLC(Limited Liability Company)・LLP(Limited Liability Partnership)のような組織形態の利用が進んでいる。日本の組合を含めパートナーシップのほとんどは、構成員が無限責任(構成員が自分の個人的な財産を含めて組織の責任を負う仕組み)となっているため、利用が限定されていたが、この有限責任制の導入により、格段に利用の幅が広がっている。
これらの事業体は、出資者が出資額までしか事業上の責任を負わず(有限責任制)、出資者が自ら経営を行うので組織設計や権限・利益の分配など組織内部の取り決めは、出資者同士で柔軟に決めることができる(内部自治原則)。さらに税制面では、事業体には課税されずに、その出資者に直接課税される(構成員課税)。
2.LLP制度の創設への動き
経済産業省においては、日本でも早期に海外のLLPやLLCに類似した有限責任のパートナーシップを実現するため、民法組合の特例制度として、有限責任事業組合(LLP)制度を創設することを検討してきた。(脚注2) 16年9月から、経済産業政策局長の私的研究会として、有限責任事業組合制度に関する研究会(略称:日本版LLP研究会、座長:能見東京大学教授)を開催し、12月に中間とりまとめを公表した。
これを受けて17年の通常国会での法案を提出し、17年4月27日に「有限責任事業組合契約に関する法律(LLP法)」が成立し、8月1日に施行となり、LLP制度が誕生することとなった。
LLP(有限責任事業組合)は民法上の任意組合(民法組合)の特例制度として、民法組合の内部ルールと課税上の特徴を維持しつつ、組合員全員の有限責任制を導入することによって、①有限責任制、②内部自治原則の徹底、③構成員課税の3つの特徴を有する組織形態を実現する。
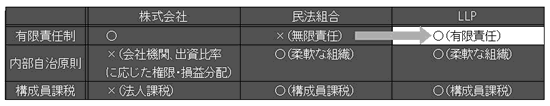
3.LLP法の概要
LLP法は、民法組合への有限責任制の導入とそれに伴う債権者保護のための措置、民法組合の内部自治を確保しながらも共同事業性を高めるための措置を講じているところに特徴がある。法律の概要を以下で説明する。
1 有限責任制と債権者保護規定
民法組合の特例として、組合の柔軟性を維持しつつ組合員全員に有限責任を確保することが、本法律のもっとも大きな特徴である。他方、組合員の有限責任を確保することに伴い、組合事業から発生するリスクについて、一定程度をLLPと取引等を行う債権者に転嫁することとなる。したがって、本法律では、組合員の有限責任の確保(15条)と併せて、組合債権者の保護のために以下のような措置を講じている。
① 予見可能性の確保及び債権者への財務情報の開示
(組合契約登記)
LLPでは、組合員の責任制限について組合と取引関係に入ってくる第三者の予見可能性を確保することが必要となる。このため、組合契約のうち一定の事項を登記させることにより、取引にあたっての重要事項を公示し、第三者に対する予見可能性を確保している(第7章)。なお、本法律における組合契約の登記は、商業登記の一類型であり、登記事項についての対抗要件ではなく、登記すれば登記事項について第三者の悪意を擬制するという公示力を付与するものである(8条1項)。
(組合の名称)
組合契約登記と同様に、第三者の予見可能性を確保するとともに、他の組織形態との混同を避ける目的から、名称中に「有限責任事業組合」という文字の使用を義務付けている(9条1項)。なお、通称として「LLP」を名刺や看板などに用いることは差し支えない。
(財務諸表の作成・開示義務)
LLPにおいては、組合債権者に対する財務情報の開示の観点から、組合の財務諸表(貸借対照表、損益計算書及びこれらの附属明細書)を作成した上で、組合契約書とともに、組合の事務所において備え置き、債権者の閲覧に供すべきこととしている。これにより、組合債権者は、LLPの事業に関する基礎的事項や、組合財産およびLLPの損益の状況に関する情報を得ることが可能となる(31条)。
② 組合財産の維持
組合員の有限責任が確保されるLLPでは、組合財産が不当に流出して組合債権者が害されることを防止する必要性が高い。そこで、本法律では、組合財産の維持のための以下の規定を設けている。
(設立時の出資の確保の規律)
民法上の組合契約は、各当事者が出資を行い、共同の事業を営むことを約した時点で契約の効力が発生する(民法667条)。これに対して、LLPでは、履行可能性の低い過大な出資を組合契約書に記載してLLPの信用力を過大にみせかけるといった悪用を防止し、出資の確実な履行を確保するため、各当事者による出資の履行を組合契約の効力発生要件としている(3条1項)。
(出資種類の制限)
民法組合では、労務も出資の対象とすることができるが、LLPでは、組合事業の財産的基礎となる組合財産を適切に保持するため、貸借対照表に計上し得ない労務出資は認めず、「金銭その他の財産のみ」を出資の目的とできることとしている(11条)。そのため、組合員の人的貢献は、出資の価額ではなく、損益分配の割合を通じて評価することとなる。
(組合財産の分配規制)
民法組合では、組合員の同意により、組合財産をいつでも制限なく分配できる。しかし、LLPにおいてこれを認めると、組合債権者への弁済に必要な組合財産を確保できず、組合債権者を害するおそれがある。そこで、本法律においては、組合財産の分配について一定の制限を設けるほか、組合財産の分配によって組合財産が毀損された場合における組合員の責任を強化している。
LLPでは、組合財産の分配によって組合債権者が害されることのないよう、分配日における純資産額から300万円(組合員の出資の総額が300万円に満たない場合は出資の総額)を控除した額を超える組合財産の分配を禁止している(34条1項)。
また、分配可能額の範囲内の分配であっても、組合員の出資総額を超えて組合財産の分配を行う場合には、常に総組合員の同意を義務付けるとともに、組合債権者への適切な情報開示の観点から、当該超過額等を組合契約書に記載すべきこととしている(34条2項、3項)。
また、違法分配を受けた組合員に対して組合財産への返還義務を課すとともに、違法分配を受けた組合員は、違法分配額について連帯して組合債権者への直接弁済責任を負うこととしている(35条)。
③ 債権者の事後的救済のための措置
LLPの事業活動によって第三者に損害が生じた場合については、当該第三者の事後的救済を充実させる観点から、組合の業務に関して第三者に損害が生じた場合の賠償責任が、組合債務として各組合員に帰属する旨の明文の規定を設けている(17条)。この際、当該責任と併せて、自ら不法行為を行った組合員個人は、一般原則どおり個人財産をもって当該損害を賠償する責任を負うこととなる。
また、株式会社や有限会社などの他の有限責任組織と同様、組合員が自己の職務を行うについて悪意または重過失があったときは、当該組合員はそれによって第三者に生じた損害を連帯して賠償する責任を負うこととしている(18条)。
なお、18条に基づいて組合員が責任を負うのは、あくまで自己の職務を行うについて悪意または重過失がある場合であって、他の組合員の責任について同条に基づいて当然に連帯責任を負うものではなく、またこれにより他の組合員の業務執行の監督義務を負うこととなるものでもない。
④ その他濫用防止措置
本法律では、以上に述べたような各種の債権者保護規定を設けているが、組合員が極めて悪質な組合契約の濫用を行っている場合においては、かかる組合債権者保護規定による対応にとどまらず、信義則に基づいて組合契約そのものを否認することにより、もって第三者の保護を図るべきであると考えられる。
この点、法人については、法人格の濫用・形骸化について、法人格の独立性を否認して衡平な解決を図る「法人格否認の法理」が判例上確立されているが、組合についてはこのような明確な判例法理は存在しない。
そこで、本法律においては、不当に債務を免れる目的で組合契約を濫用することを禁止する旨の明文の規定を設けている(3条3項)。
2 内部自治原則と共同事業要件
民法組合は、株式会社等とは異なり、組織の運営方法は組合員相互で自由に決定でき、また、出資額の多寡にとらわれず、人的資産による貢献を勘案した権限や損益を自由に配分することが可能である(内部自治原則)。LLPにおいても、基本的には、この民法組合の特徴を活かすため、柔軟な意思決定・損益分配など民法組合の内部ルールを承継している。
しかしながら、組合員全員がそれぞれの個性や能力を活かしつつ、共通の目的に向かって主体的に組合事業に参画するというLLPの特徴にかんがみ、組合員全員が業務執行の過程に関与することを義務づける共同事業要件を規定している。これによって組合事業の健全性が高まり、組合債権者への容易なリスク転嫁や租税回避的な利用が防止されるという効果も期待されている。
① 意思決定への全員参加
LLPでは、民法組合と同様、業務執行の決定のための特別な機関は設けられておらず、組合員の同意によって意思決定がなされることとなる。意思決定は原則として、総組合員の同意によることとしている(12条1項本文)。
ただし、業務執行の決定について常に総組合員の同意を義務付けると、業務執行の機動性が著しく損なわれることにもなりかねない。そこで、特に重要な事項の決定を除いては、組合契約書に定めを設けることにより、決定の要件を緩和できることとしている(12条ただし書)。
なお、業務執行に関する特に重要な事項として、重要な財産の処分および譲受け、ならびに多額の借財を規定しているが(12条1項各号)、これらの決定に関しても、純資産(純資産が20億円を上回る場合には、20億円。)を下回るものについては、その要件を総組合員の三分の二以上の同意にまで緩和することができる(12条2項)。
② 業務執行への全員参加
業務執行の決定に基づく具体的な業務の執行についても、組合員全員が自らこれに携わる権利を有するとともに、携わるべき義務を負うこととしている(13条1項)。したがって、株式会社における代表取締役や民法組合における業務執行者のように、一部の者に業務執行権限を集中させることはできない。
ただし、各組合員の個性や能力を十分に発揮するためには、強固な共同事業性が損なわれない範囲で業務執行の分担を認めることが望ましい。そこで、業務執行の一部のみであれば、これを委任することもできることとしている(13条2項)。
なお、ここでいう業務執行とは、LLPの営業に関する事務を執行することであり、対外的な契約締結のための交渉、あるいは、具体的な研究開発計画の策定・設計、帳簿の記入、商品の管理、使用人の指揮・監督等、組合の事業の運営に関する行為が広く含まれる。
③ 柔軟な損益分配
民法組合では、特段の定めがなければ、出資比率に比例して損益の分配がなされるが、組合員間の合意により出資比率と異なる柔軟な損益分配を行うことが認められており(民法674条)、本法律においても同様の考え方を採用している(33条)。したがって、各組合員の人的貢献については、損益分配の割合に反映することが可能となる。
ただし、組合員の損益分配の割合は、組合員の利害に直接関係するものであり、共同事業の根幹にかかわる重要な事項であることから、本法律においては、常に総組合員の同意をもってあらかじめ定め、書面に記載するとともに、その理由を当該書面に明記することとしている。
なお、どのような損益分配の割合を定めることができるかについては、本法律では特段の制限を設けていないが、税務上の取り扱いについては、その定め方が税務上の観点からみて合理性を有するものである必要がある。
3 LLPと法人格
LLPは民法組合の特例制度であり法人格を持たないために、事業上の不都合があるのではないかとの指摘もある。しかし、契約の締結や、組合財産の保有は、組合独自の手法を取ることにより実務的には不都合はないと考えられる。
LLPは有限責任事業組合の肩書き付き名義で組合員が契約を締結することができる(例えば、ABC有限責任事業組合 組合員A 職務執行者X名義)。この契約の効果は、組合債権又は組合債務として全組合員に(合有的・合手的に)帰属する。売買、口座開設・融資、業務委託、雇用、ライセンス、電話加入など多様な契約においてこのような契約の締結が可能である。
LLPでは財産を組合員の共有(合有)として所有する(この財産を「組合財産」という)。組合財産については、その処分や分割に一定の制限がかかっている(民法676条)。このため、組合員やその債権者は、組合財産を分割、差し押さえることはできない。
また、登記制度上も、有限責任事業組合契約に基づく共有物不分割の登記を導入し、LLPの組合財産であることを明確にする措置を講じている(74条)。
4.構成員課税
LLPの課税上の扱いについては、組合員全員の有限責任が確保される民法組合の特例制度として、LLPの各組合員がそれぞれ組合事業の主体となり、組合としての法的な実質が備わっているということに対応して、組合員について構成員課税の適用を受けることとなる。
すなわち、LLP自体は納税主体とならず、組合事業から生じた所得については、LLP段階には課税されず、LLPの組合員段階に直接課税されることとなる。
これにより、①LLPの事業で利益が出た場合には、LLP段階で課税された上に、LLPの組合員に対する利益の分配にも課税されるということがなく、②LLPの事業で損失が出た場合には、出資の価額を基礎として定められる一定額の範囲内でLLPの組合員の他の所得と損益通算を行うことが可能となる。
税務上のルールについては詳細な規定があるが、主要なものとしては以下がある。
1 損失の取り込み制限
税法で特に規定されているものとして、事業上の損失の取り込み制限の規定がある。民法組合であれば、そのまま損益を出資者に帰属させることとなるが、LLPの組合員は有限責任なので、LLPの事業上の損失を無制限に取り込むのでなく、その責任の範囲で損失の取り込みが止まるため、税法上も損失の取り込み制限をかけている。これは、所得税、法人税、それぞれの税法の特徴等を踏まえ、若干異なっているが、基本的には、どちらも各組合員の有限責任の範囲(税法上は調整出資金額として計算)内で損失の取り込みを止めることとなる。
2 組合員所得に関する計算書等
また、LLPの税務申告に関して「組合員所得に関する計算書」の提出が必要となる。これは、組合の会計帳簿を作成した組合員が作成する書類で、組合の計算期間の終了の日の属する年の翌年1月31日までに、一定の書式の計算書を、組合の主たる所在地の所轄の税務署長に提出するというもの。提出の内容としては、各組合員の氏名又は名称及び住所もしくは居所、会計帳簿を作成した組合員の氏名又は名称、組合の計算期間等々、当該組合の計算期間における当該組合の損益計算書に計上されている収益及び費用の内訳、並びに当該収益及び費用のうち、当該組合にかかる組合員の当該収益及び費用の額に相当する額、損益分配の割合などとなる。
また、この計算書とは別に、各組合員が税務申告時に提出すべき書類が、個人と法人についてそれぞれ規定されている。個人であれば、調整出資金額等に係る事項を記載した書類の添付、その年における不動産所得、事業所得、山林所得の収入明細、経費明細のようなものを別途つけることとなる。また、個人で、確定申告書を提出しない場合は、調整出資金額がわかるように、別途、書類を提出するという規定がある。法人に関しては、組合の損失超過合計額、調整出資金額に関する明細書、組合損失超過額を利益と相殺したときの明細書等が、提出する書類として義務づけられている。これに関しても、別途、別表が既に設けられており、これを申告書に添付することになる。
その他、非居住者や外国法人が組合員である場合に、源泉徴収義務がかかり、支払い調書を提出するというような規定も設けられている。
5.LLPへの期待
日本版LLPの活用については、日本版LLP研究会や制度検討の過程でのヒアリングにおいて、さまざまなビジネスモデルにおける活用の可能性が示されている。類型化すると、個人同士の共同事業、個人と企業の共同事業、企業同士の共同事業となる。
1 専門人材の共同組織(個人同士の共同事業)
専門的な能力を有する人材が事業の幅を広げるために、それぞれの技術、ノウハウ、経験、顧客などを持ち寄り、共同組織で事業をする際にLLPは有効と考えられる。この場合、LLPを使うと権限や利益分配も事業への貢献を勘案して決定できる。金銭的な出資金額にとらわれず、人的資本を出す側のインセンティブを重視した組織設計が可能である。また、取締役会や監査役も強制されないので、組織の運営コストも必要最小限に抑えることができる。さらに、構成員課税が適用されるために、LLPの事業の損益と各個人の事業の損益の通算が可能となり、組織体にではなく構成員段階での一段階の課税となるため、課税上のメリットも大きい。
2 ジョイント・ベンチャーの新しい受け皿(企業同士の共同事業)
研究開発、製造、流通、販売などバリューチェーンの多様な場面で企業同士が連携をするケースが増えているが、この場合もLLPが効果を発揮する場面が多い。例えば、共同研究開発をジョイント・ベンチャーで行う場合は、取締役会や監査役などの会社機関は通常必要はなく、出資者である親会社が相互に話し合って意志決定する場合が多い。LLPであれば、必要最小限の組織設計により機動的、効率的な組織とすることが可能である。また、出資金額に比例しない権限分配や損益分配ができるため、人的資産を重視したルール決めによる新しい連携が模索できる。すなわち、資金力に差がある大企業とベンチャー企業において、資金を出せないベンチャー企業が、技術力やノウハウを拠出する際に、重点的に利益配分するなど、株式会社形態では実現できないインセンティブ形成が可能である。
さらに、研究開発投資の結果として計上される損失は、親会社の利益と通算できる。多数の企業が参加する共同研究開発の場合、株式会社形態で実施すると子会社との損益通算ができず、投資へのブレーキとなるが、LLPであれば、あたかも自社の内部で研究開発投資をする場合と同様に新しい事業にチャレンジすることが可能となる。また、共同事業で利益が出た場合にも、出資者段階のみで課税を受けるため、税額を抑えることが可能となり、その費用を更なる研究開発投資に振り向けることができる。3
3 産学連携やスピンオフの新しい受け皿(企業と個人の共同事業)
大学教授と企業が連携する産学連携や企業からスピンオフした個人と親元の企業が連携する場合などにLLPの活用が考えられる。資金力に差がある企業と個人の間で、金銭的な出資にとらわれないインセンティブ付与のためにLLPの柔軟な組織設計が効果的と考えられる。
また、企業の側は、企業同士のジョイント・ベンチャーと同様に組織上、税務上のメリットを享受することが可能となる。
6.おわりに
以上、LLP制度についてその背景、法律等の内容を概観してきた。LLPやLLCの創設については、10年以上前から産業界の強い要望があり、組織法制上の大きな課題と認識されていた。今般、海外制度の研究や日本版LLP研究会による制度の検討、有識者や産業界のアドバイス、財務省、法務省、内閣法制局をはじめとする関係省庁の御協力の結果、ようやく創設に至った。しかし、制度導入は政策のゴールでなくスタートである。新制度の利用状況を丁寧にモニターし、必要に応じて随時改善を加えることが必要と考える。本制度が積極的に活用されつつ発展し、日本経済の活性化に貢献することを期待する。
脚注
1 「会社はこれからどうなるのか」, 岩井克人, 平凡社, 2003.1
2 「人的資産を活用する新しい組織形態の提案」,経済産業省, 2003.11
「日本版LLC 新しい会社のかたち」,日下部聡・石井芳明(監修)経済産業省(編),金融財政事情研究会,2004.7において、有限責任のパートナーシップ実現のためのアプローチの検討がなされている。
3 LLP研究会委員発言。
LLP制度の概要―経済活力の向上のための新しいパートナーシップ―
経済産業省 経済産業政策局 産業組織課 課長補佐 石井芳明
はじめに
LLP(Limited Liability Partnership)制度を創設する「有限責任事業組合契約に関する法律」(平成17年法律第40号)が平成17年4月27日に第162回国会において成立し、8月1日に施行された。
LLPは、①構成員の有限責任、②組織の内部自治、③構成員課税という3つの特徴を合わせ持つ組織で、企業同士のジョイント・ベンチャーや専門人材の共同事業を振興し、創業を促進する効果がある。本稿においては、LLP制度創設の背景と法律の概要について紹介する。
1.LLP制度の背景
近年、ビジネスを巡る環境が大きく変化している。情報化や国際化の進展により国境を越えた企業間競争が激化し、市場の成熟化や多様化に伴い顧客ニーズが複雑化している。このような状況を受けて、企業が優位性を持つための経営資源として「人的資産」の重要性がクローズアップされている。これからの時代において企業の競争力は人的資本の蓄積と活用による。(脚注1)
また、企業同士が「共同事業」を実施することの重要性も高まっている。人的資本や物的資本を出し合って、相互補完、資源共有、リスク共有の共同事業を実施することによって、より強固な競争力、より大きな価値を創出することが可能となる。
こうした中、人的資産を活かす組織形態、共同事業のための組織形態として、コアとなる人材や企業が出資者と経営者を兼ねているようなパートナーシップ型の組織形態が欧米で注目されている。パートナーシップは、日本でいう組合であり、個性を有する個人・法人が一定の目的のもと出資をして共同事業を営む組織形態である。資金供給者である「株主」対「経営者・従業員」という所有と経営の分離の構図でなく、「出資者=経営者(パートナー)」というのが基本の組織で、所有と経営が一致しているため、業務執行、利益分配等の組織の内部ルールをパートナー間で柔軟に設定できる。専門的な能力を有する個人にとっては「会社に雇われる」のではなく、「自らが自らのボスとなる」ので、自分たちの能力を引き出しやすい組織づくりができる。また、企業同士の連携においても、資本の論理でなく、より柔軟な組織設計が可能となる。
特に、欧米では、従前のパートナーシップに構成員の有限責任制(構成員が出資額を限度に組織の責任を負う仕組み)を付与したLLC(Limited Liability Company)・LLP(Limited Liability Partnership)のような組織形態の利用が進んでいる。日本の組合を含めパートナーシップのほとんどは、構成員が無限責任(構成員が自分の個人的な財産を含めて組織の責任を負う仕組み)となっているため、利用が限定されていたが、この有限責任制の導入により、格段に利用の幅が広がっている。
これらの事業体は、出資者が出資額までしか事業上の責任を負わず(有限責任制)、出資者が自ら経営を行うので組織設計や権限・利益の分配など組織内部の取り決めは、出資者同士で柔軟に決めることができる(内部自治原則)。さらに税制面では、事業体には課税されずに、その出資者に直接課税される(構成員課税)。
2.LLP制度の創設への動き
経済産業省においては、日本でも早期に海外のLLPやLLCに類似した有限責任のパートナーシップを実現するため、民法組合の特例制度として、有限責任事業組合(LLP)制度を創設することを検討してきた。(脚注2) 16年9月から、経済産業政策局長の私的研究会として、有限責任事業組合制度に関する研究会(略称:日本版LLP研究会、座長:能見東京大学教授)を開催し、12月に中間とりまとめを公表した。
これを受けて17年の通常国会での法案を提出し、17年4月27日に「有限責任事業組合契約に関する法律(LLP法)」が成立し、8月1日に施行となり、LLP制度が誕生することとなった。
LLP(有限責任事業組合)は民法上の任意組合(民法組合)の特例制度として、民法組合の内部ルールと課税上の特徴を維持しつつ、組合員全員の有限責任制を導入することによって、①有限責任制、②内部自治原則の徹底、③構成員課税の3つの特徴を有する組織形態を実現する。
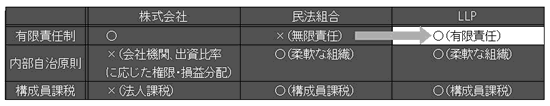
3.LLP法の概要
LLP法は、民法組合への有限責任制の導入とそれに伴う債権者保護のための措置、民法組合の内部自治を確保しながらも共同事業性を高めるための措置を講じているところに特徴がある。法律の概要を以下で説明する。
1 有限責任制と債権者保護規定
民法組合の特例として、組合の柔軟性を維持しつつ組合員全員に有限責任を確保することが、本法律のもっとも大きな特徴である。他方、組合員の有限責任を確保することに伴い、組合事業から発生するリスクについて、一定程度をLLPと取引等を行う債権者に転嫁することとなる。したがって、本法律では、組合員の有限責任の確保(15条)と併せて、組合債権者の保護のために以下のような措置を講じている。
① 予見可能性の確保及び債権者への財務情報の開示
(組合契約登記)
LLPでは、組合員の責任制限について組合と取引関係に入ってくる第三者の予見可能性を確保することが必要となる。このため、組合契約のうち一定の事項を登記させることにより、取引にあたっての重要事項を公示し、第三者に対する予見可能性を確保している(第7章)。なお、本法律における組合契約の登記は、商業登記の一類型であり、登記事項についての対抗要件ではなく、登記すれば登記事項について第三者の悪意を擬制するという公示力を付与するものである(8条1項)。
(組合の名称)
組合契約登記と同様に、第三者の予見可能性を確保するとともに、他の組織形態との混同を避ける目的から、名称中に「有限責任事業組合」という文字の使用を義務付けている(9条1項)。なお、通称として「LLP」を名刺や看板などに用いることは差し支えない。
(財務諸表の作成・開示義務)
LLPにおいては、組合債権者に対する財務情報の開示の観点から、組合の財務諸表(貸借対照表、損益計算書及びこれらの附属明細書)を作成した上で、組合契約書とともに、組合の事務所において備え置き、債権者の閲覧に供すべきこととしている。これにより、組合債権者は、LLPの事業に関する基礎的事項や、組合財産およびLLPの損益の状況に関する情報を得ることが可能となる(31条)。
② 組合財産の維持
組合員の有限責任が確保されるLLPでは、組合財産が不当に流出して組合債権者が害されることを防止する必要性が高い。そこで、本法律では、組合財産の維持のための以下の規定を設けている。
(設立時の出資の確保の規律)
民法上の組合契約は、各当事者が出資を行い、共同の事業を営むことを約した時点で契約の効力が発生する(民法667条)。これに対して、LLPでは、履行可能性の低い過大な出資を組合契約書に記載してLLPの信用力を過大にみせかけるといった悪用を防止し、出資の確実な履行を確保するため、各当事者による出資の履行を組合契約の効力発生要件としている(3条1項)。
(出資種類の制限)
民法組合では、労務も出資の対象とすることができるが、LLPでは、組合事業の財産的基礎となる組合財産を適切に保持するため、貸借対照表に計上し得ない労務出資は認めず、「金銭その他の財産のみ」を出資の目的とできることとしている(11条)。そのため、組合員の人的貢献は、出資の価額ではなく、損益分配の割合を通じて評価することとなる。
(組合財産の分配規制)
民法組合では、組合員の同意により、組合財産をいつでも制限なく分配できる。しかし、LLPにおいてこれを認めると、組合債権者への弁済に必要な組合財産を確保できず、組合債権者を害するおそれがある。そこで、本法律においては、組合財産の分配について一定の制限を設けるほか、組合財産の分配によって組合財産が毀損された場合における組合員の責任を強化している。
LLPでは、組合財産の分配によって組合債権者が害されることのないよう、分配日における純資産額から300万円(組合員の出資の総額が300万円に満たない場合は出資の総額)を控除した額を超える組合財産の分配を禁止している(34条1項)。
また、分配可能額の範囲内の分配であっても、組合員の出資総額を超えて組合財産の分配を行う場合には、常に総組合員の同意を義務付けるとともに、組合債権者への適切な情報開示の観点から、当該超過額等を組合契約書に記載すべきこととしている(34条2項、3項)。
また、違法分配を受けた組合員に対して組合財産への返還義務を課すとともに、違法分配を受けた組合員は、違法分配額について連帯して組合債権者への直接弁済責任を負うこととしている(35条)。
③ 債権者の事後的救済のための措置
LLPの事業活動によって第三者に損害が生じた場合については、当該第三者の事後的救済を充実させる観点から、組合の業務に関して第三者に損害が生じた場合の賠償責任が、組合債務として各組合員に帰属する旨の明文の規定を設けている(17条)。この際、当該責任と併せて、自ら不法行為を行った組合員個人は、一般原則どおり個人財産をもって当該損害を賠償する責任を負うこととなる。
また、株式会社や有限会社などの他の有限責任組織と同様、組合員が自己の職務を行うについて悪意または重過失があったときは、当該組合員はそれによって第三者に生じた損害を連帯して賠償する責任を負うこととしている(18条)。
なお、18条に基づいて組合員が責任を負うのは、あくまで自己の職務を行うについて悪意または重過失がある場合であって、他の組合員の責任について同条に基づいて当然に連帯責任を負うものではなく、またこれにより他の組合員の業務執行の監督義務を負うこととなるものでもない。
④ その他濫用防止措置
本法律では、以上に述べたような各種の債権者保護規定を設けているが、組合員が極めて悪質な組合契約の濫用を行っている場合においては、かかる組合債権者保護規定による対応にとどまらず、信義則に基づいて組合契約そのものを否認することにより、もって第三者の保護を図るべきであると考えられる。
この点、法人については、法人格の濫用・形骸化について、法人格の独立性を否認して衡平な解決を図る「法人格否認の法理」が判例上確立されているが、組合についてはこのような明確な判例法理は存在しない。
そこで、本法律においては、不当に債務を免れる目的で組合契約を濫用することを禁止する旨の明文の規定を設けている(3条3項)。
2 内部自治原則と共同事業要件
民法組合は、株式会社等とは異なり、組織の運営方法は組合員相互で自由に決定でき、また、出資額の多寡にとらわれず、人的資産による貢献を勘案した権限や損益を自由に配分することが可能である(内部自治原則)。LLPにおいても、基本的には、この民法組合の特徴を活かすため、柔軟な意思決定・損益分配など民法組合の内部ルールを承継している。
しかしながら、組合員全員がそれぞれの個性や能力を活かしつつ、共通の目的に向かって主体的に組合事業に参画するというLLPの特徴にかんがみ、組合員全員が業務執行の過程に関与することを義務づける共同事業要件を規定している。これによって組合事業の健全性が高まり、組合債権者への容易なリスク転嫁や租税回避的な利用が防止されるという効果も期待されている。
① 意思決定への全員参加
LLPでは、民法組合と同様、業務執行の決定のための特別な機関は設けられておらず、組合員の同意によって意思決定がなされることとなる。意思決定は原則として、総組合員の同意によることとしている(12条1項本文)。
ただし、業務執行の決定について常に総組合員の同意を義務付けると、業務執行の機動性が著しく損なわれることにもなりかねない。そこで、特に重要な事項の決定を除いては、組合契約書に定めを設けることにより、決定の要件を緩和できることとしている(12条ただし書)。
なお、業務執行に関する特に重要な事項として、重要な財産の処分および譲受け、ならびに多額の借財を規定しているが(12条1項各号)、これらの決定に関しても、純資産(純資産が20億円を上回る場合には、20億円。)を下回るものについては、その要件を総組合員の三分の二以上の同意にまで緩和することができる(12条2項)。
② 業務執行への全員参加
業務執行の決定に基づく具体的な業務の執行についても、組合員全員が自らこれに携わる権利を有するとともに、携わるべき義務を負うこととしている(13条1項)。したがって、株式会社における代表取締役や民法組合における業務執行者のように、一部の者に業務執行権限を集中させることはできない。
ただし、各組合員の個性や能力を十分に発揮するためには、強固な共同事業性が損なわれない範囲で業務執行の分担を認めることが望ましい。そこで、業務執行の一部のみであれば、これを委任することもできることとしている(13条2項)。
なお、ここでいう業務執行とは、LLPの営業に関する事務を執行することであり、対外的な契約締結のための交渉、あるいは、具体的な研究開発計画の策定・設計、帳簿の記入、商品の管理、使用人の指揮・監督等、組合の事業の運営に関する行為が広く含まれる。
③ 柔軟な損益分配
民法組合では、特段の定めがなければ、出資比率に比例して損益の分配がなされるが、組合員間の合意により出資比率と異なる柔軟な損益分配を行うことが認められており(民法674条)、本法律においても同様の考え方を採用している(33条)。したがって、各組合員の人的貢献については、損益分配の割合に反映することが可能となる。
ただし、組合員の損益分配の割合は、組合員の利害に直接関係するものであり、共同事業の根幹にかかわる重要な事項であることから、本法律においては、常に総組合員の同意をもってあらかじめ定め、書面に記載するとともに、その理由を当該書面に明記することとしている。
なお、どのような損益分配の割合を定めることができるかについては、本法律では特段の制限を設けていないが、税務上の取り扱いについては、その定め方が税務上の観点からみて合理性を有するものである必要がある。
3 LLPと法人格
LLPは民法組合の特例制度であり法人格を持たないために、事業上の不都合があるのではないかとの指摘もある。しかし、契約の締結や、組合財産の保有は、組合独自の手法を取ることにより実務的には不都合はないと考えられる。
LLPは有限責任事業組合の肩書き付き名義で組合員が契約を締結することができる(例えば、ABC有限責任事業組合 組合員A 職務執行者X名義)。この契約の効果は、組合債権又は組合債務として全組合員に(合有的・合手的に)帰属する。売買、口座開設・融資、業務委託、雇用、ライセンス、電話加入など多様な契約においてこのような契約の締結が可能である。
LLPでは財産を組合員の共有(合有)として所有する(この財産を「組合財産」という)。組合財産については、その処分や分割に一定の制限がかかっている(民法676条)。このため、組合員やその債権者は、組合財産を分割、差し押さえることはできない。
また、登記制度上も、有限責任事業組合契約に基づく共有物不分割の登記を導入し、LLPの組合財産であることを明確にする措置を講じている(74条)。
4.構成員課税
LLPの課税上の扱いについては、組合員全員の有限責任が確保される民法組合の特例制度として、LLPの各組合員がそれぞれ組合事業の主体となり、組合としての法的な実質が備わっているということに対応して、組合員について構成員課税の適用を受けることとなる。
すなわち、LLP自体は納税主体とならず、組合事業から生じた所得については、LLP段階には課税されず、LLPの組合員段階に直接課税されることとなる。
これにより、①LLPの事業で利益が出た場合には、LLP段階で課税された上に、LLPの組合員に対する利益の分配にも課税されるということがなく、②LLPの事業で損失が出た場合には、出資の価額を基礎として定められる一定額の範囲内でLLPの組合員の他の所得と損益通算を行うことが可能となる。
税務上のルールについては詳細な規定があるが、主要なものとしては以下がある。
1 損失の取り込み制限
税法で特に規定されているものとして、事業上の損失の取り込み制限の規定がある。民法組合であれば、そのまま損益を出資者に帰属させることとなるが、LLPの組合員は有限責任なので、LLPの事業上の損失を無制限に取り込むのでなく、その責任の範囲で損失の取り込みが止まるため、税法上も損失の取り込み制限をかけている。これは、所得税、法人税、それぞれの税法の特徴等を踏まえ、若干異なっているが、基本的には、どちらも各組合員の有限責任の範囲(税法上は調整出資金額として計算)内で損失の取り込みを止めることとなる。
2 組合員所得に関する計算書等
また、LLPの税務申告に関して「組合員所得に関する計算書」の提出が必要となる。これは、組合の会計帳簿を作成した組合員が作成する書類で、組合の計算期間の終了の日の属する年の翌年1月31日までに、一定の書式の計算書を、組合の主たる所在地の所轄の税務署長に提出するというもの。提出の内容としては、各組合員の氏名又は名称及び住所もしくは居所、会計帳簿を作成した組合員の氏名又は名称、組合の計算期間等々、当該組合の計算期間における当該組合の損益計算書に計上されている収益及び費用の内訳、並びに当該収益及び費用のうち、当該組合にかかる組合員の当該収益及び費用の額に相当する額、損益分配の割合などとなる。
また、この計算書とは別に、各組合員が税務申告時に提出すべき書類が、個人と法人についてそれぞれ規定されている。個人であれば、調整出資金額等に係る事項を記載した書類の添付、その年における不動産所得、事業所得、山林所得の収入明細、経費明細のようなものを別途つけることとなる。また、個人で、確定申告書を提出しない場合は、調整出資金額がわかるように、別途、書類を提出するという規定がある。法人に関しては、組合の損失超過合計額、調整出資金額に関する明細書、組合損失超過額を利益と相殺したときの明細書等が、提出する書類として義務づけられている。これに関しても、別途、別表が既に設けられており、これを申告書に添付することになる。
その他、非居住者や外国法人が組合員である場合に、源泉徴収義務がかかり、支払い調書を提出するというような規定も設けられている。
5.LLPへの期待
日本版LLPの活用については、日本版LLP研究会や制度検討の過程でのヒアリングにおいて、さまざまなビジネスモデルにおける活用の可能性が示されている。類型化すると、個人同士の共同事業、個人と企業の共同事業、企業同士の共同事業となる。
1 専門人材の共同組織(個人同士の共同事業)
専門的な能力を有する人材が事業の幅を広げるために、それぞれの技術、ノウハウ、経験、顧客などを持ち寄り、共同組織で事業をする際にLLPは有効と考えられる。この場合、LLPを使うと権限や利益分配も事業への貢献を勘案して決定できる。金銭的な出資金額にとらわれず、人的資本を出す側のインセンティブを重視した組織設計が可能である。また、取締役会や監査役も強制されないので、組織の運営コストも必要最小限に抑えることができる。さらに、構成員課税が適用されるために、LLPの事業の損益と各個人の事業の損益の通算が可能となり、組織体にではなく構成員段階での一段階の課税となるため、課税上のメリットも大きい。
2 ジョイント・ベンチャーの新しい受け皿(企業同士の共同事業)
研究開発、製造、流通、販売などバリューチェーンの多様な場面で企業同士が連携をするケースが増えているが、この場合もLLPが効果を発揮する場面が多い。例えば、共同研究開発をジョイント・ベンチャーで行う場合は、取締役会や監査役などの会社機関は通常必要はなく、出資者である親会社が相互に話し合って意志決定する場合が多い。LLPであれば、必要最小限の組織設計により機動的、効率的な組織とすることが可能である。また、出資金額に比例しない権限分配や損益分配ができるため、人的資産を重視したルール決めによる新しい連携が模索できる。すなわち、資金力に差がある大企業とベンチャー企業において、資金を出せないベンチャー企業が、技術力やノウハウを拠出する際に、重点的に利益配分するなど、株式会社形態では実現できないインセンティブ形成が可能である。
さらに、研究開発投資の結果として計上される損失は、親会社の利益と通算できる。多数の企業が参加する共同研究開発の場合、株式会社形態で実施すると子会社との損益通算ができず、投資へのブレーキとなるが、LLPであれば、あたかも自社の内部で研究開発投資をする場合と同様に新しい事業にチャレンジすることが可能となる。また、共同事業で利益が出た場合にも、出資者段階のみで課税を受けるため、税額を抑えることが可能となり、その費用を更なる研究開発投資に振り向けることができる。3
3 産学連携やスピンオフの新しい受け皿(企業と個人の共同事業)
大学教授と企業が連携する産学連携や企業からスピンオフした個人と親元の企業が連携する場合などにLLPの活用が考えられる。資金力に差がある企業と個人の間で、金銭的な出資にとらわれないインセンティブ付与のためにLLPの柔軟な組織設計が効果的と考えられる。
また、企業の側は、企業同士のジョイント・ベンチャーと同様に組織上、税務上のメリットを享受することが可能となる。
6.おわりに
以上、LLP制度についてその背景、法律等の内容を概観してきた。LLPやLLCの創設については、10年以上前から産業界の強い要望があり、組織法制上の大きな課題と認識されていた。今般、海外制度の研究や日本版LLP研究会による制度の検討、有識者や産業界のアドバイス、財務省、法務省、内閣法制局をはじめとする関係省庁の御協力の結果、ようやく創設に至った。しかし、制度導入は政策のゴールでなくスタートである。新制度の利用状況を丁寧にモニターし、必要に応じて随時改善を加えることが必要と考える。本制度が積極的に活用されつつ発展し、日本経済の活性化に貢献することを期待する。
脚注
1 「会社はこれからどうなるのか」, 岩井克人, 平凡社, 2003.1
2 「人的資産を活用する新しい組織形態の提案」,経済産業省, 2003.11
「日本版LLC 新しい会社のかたち」,日下部聡・石井芳明(監修)経済産業省(編),金融財政事情研究会,2004.7において、有限責任のパートナーシップ実現のためのアプローチの検討がなされている。
3 LLP研究会委員発言。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























