解説記事2005年12月26日 【ニュース特集】 適格又は不適格?物納制度が見直しへ(2005年12月26日号・№144)
ニュース特集
取引相場のない株式も物納可能
適格又は不適格?物納制度が見直しへ
平成18年度税制改正大綱が12月15日に決定された。大綱では、納税環境整備の一環として、物納制度の見直しが行われている。取引相場のない株式については、一定の要件を満たせば、物納財産として認められることになるほか、物納不適格財産の明確化などが行われている。平成18年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税から適用される。
1 物納不適格財産の明確化を図る
今回、物納制度については、①物納不適格財産の明確化等、②物納手続の明確化・迅速化、③納税者の利便の向上等の3点から見直しが行われる。
①については、まず、法令上明確でなかった物納不適格財産の範囲(管理処分不適格要件)について、例えば、抵当権が設定されている不動産、境界が不明確な土地等の一定の財産などを法令において明記する。現在、相続税基本通達42-2において、管理又は処分をするのに不適当な財産が例示されているが、これを法令において限定するというものだ。
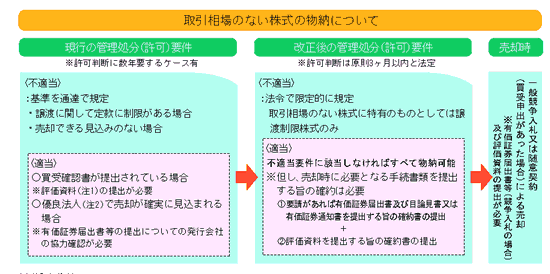
(注1)評価資料
①貸借対照表(直前期)②損益計算書(直前期)③営業報告書(直前期)④利益処分報告書(直近二期)⑤財務諸表附属明細書(直前期)⑥その他必要資料
(注2)優良法人の業績要件
①直近二期の当期利益がマイナスとなっていない、②直近二期の総資本経常利益率・売上高経常利益率・総資本回転率のうち2つが同業種平均超、③直近二期において配当可能利益有、のいずれも満たすこと
譲渡制限株式のみが物納不適格
また、取引相場のない株式等については、現行、買受確認書が提出されており、優良法人で売却が確実に見込まれることを条件に物納が認められている。
しかし、今回の見直しにより、譲渡制限株式のみが物納不適格とされ、それ以外の株式の物納については、優良法人かどうかなどに関わらず認められることになる。ただし、有価証券届出書及び目論見書又は有価証券通知書を提出する旨の確約書の提出、評価資料を提出する旨の確約書を提出する必要がある。
取引相場のない株式等の物納許可基準の大幅な緩和により、自社株式の物納が増加することも予想されそうだ。
なお、物納不適格財産の例としては、以下の表のとおりとなる。
2 物納劣後財産の明確化を図る
その一方で、物納劣後財産(他に物納適格財産がない場合に限り物納を認める財産)として、市街化調整区域内の土地、接道条件を充足していない土地(いわゆる無道路地)等を定め、その範囲の明確化も図る。物納財産は基本的に売却により歳入に充てるべきものであることから、市場で処分し易い財産の物納を優先することを明確化する趣旨でもある。
具体的には、以下の表のとおりとなるが、無道路地や維持又は管理に特殊技能を要する劇場、工場、浴場その他大建築物及びその敷地については、従来、相続税基本通達42-2に明記されていた管理又は処分をするのに不適当な財産であったが、物納劣後財産とされ、他に売却し易い不動産がない場合に限り物納が可能になる。
なお、物納申請された財産が物納不適格財産又は物納劣後財産に該当する場合であって、他に物納適格財産を有するときは、税務署長は物納申請を却下することになるが、その場合、納税者は、却下の日から20日以内であれば、1度に限り物納の再申請を可能としている。
 工場は物納劣後財産に
工場は物納劣後財産に
3 物納手続の明確化・迅速化
②の物納手続の明確化・迅速化では、まず、物納の許可に係る審査期間の法定化が行われる。物納の許可又は却下については、物納申請期限から3ヶ月以内に行うことを原則とする。
ただし、物納財産が多数となるなど、調査等に相当の期間を要すると見込まれる場合には、6ヶ月以内(積雪など特別な事情による場合は9ヶ月以内)とすることができる。審査期間内に許可又は却下が行われない場合には、物納を許可したものとみなされる。
実際、物納の許可については、ケースによっては、数年を要するものもあるため、今回の審査期間の法定化により、スピードアップが図られることになる。
物納手続に必要な書類を明確化
物納財産を国が収納するために必要な書類をあらかじめ法令において明確化するとともに、物納申請時に申請書と併せて提出することとされている。例えば、不動産であれば、登記事項証明書、測量図、境界確認書等、有価証券であれば、要請により有価証券届出書等を提出する旨の確約書等ということになる。また、提出された物納手続に必要な書類の記載に不備があった場合又は物納手続に必要な書類の提出漏れがあった場合には、これらの書類の補正又は提出を申請者に請求することができることとする。この請求後20日以内に物納手続に必要な書類について補正又は提出がされなかった場合には、物納申請を取り下げたものとみなされる。
4 納税者の利便向上
③の納税者の利便の向上という観点からは、まず、延納中の物納の選択を可能とする制度を創設する。現在、延納から物納に変更することは認められていない。しかし、延納による納付が困難になった場合には、申告期限から10年以内に限り、延納税額からその納期限の到来した分納税額を控除した残額を限度に、物納を選択することができるようにする。いわゆるバブル崩壊後、長期にわたる地価の急落により、結果的に相続税の延納税額の納付が困難となっている者に対する緊急避難措置として平成6年に導入された特例物納と同様のものである。
ただし、収納価額については、相続開始時の価額ではなく、物納申請時の価額とされている。なお、税務署長は、収納時までにその物納財産の状況に著しい変化が生じたときには、収納時の現況により、その物納財産の収納価額を定めることができるとされている。
物納完了まで利子税を求める
その他、物納の許可に係る審査期間の法定、納税者による書類提出期限の延長手続
の整備などに伴い、期限内に納付した者や延納による納付する者との均衡を図る等の観点から、物納により納付が完了されるまでの間について利子税を課すことにする。ただし、審査事務に要する期間については、利子税は免除される。
COLUMN
物納申請は年々減少へ
国税については、金銭による納付が原則。しかし、相続税については、財産課税という性格上、延納によっても金銭で納付することが困難である場合には、一定の財産による物納制度が認められている(相続税法41条~43条)。物納の申請件数については、平成11年度以降減少しており、平成16年度では、3,065件(1,288億円)。問題が指摘されていた未済件数についても、年々減少し、平成16年度では、5,968件となっている。今回の見直しにより、未済件数も大幅に縮小することになりそうだ。
【未済件数】
平成14年度 9,702件(対前年度比 95.2%) 8,356億円(対前年度比 92.0%)
平成15年度 8,217件(対前年度比 84.7%) 6,547億円(対前年度比 78.4%)
平成16年度 5,968件(対前年度比 72.6%) 4,777億円(対前年度比 73.0%)
取引相場のない株式も物納可能
適格又は不適格?物納制度が見直しへ
平成18年度税制改正大綱が12月15日に決定された。大綱では、納税環境整備の一環として、物納制度の見直しが行われている。取引相場のない株式については、一定の要件を満たせば、物納財産として認められることになるほか、物納不適格財産の明確化などが行われている。平成18年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税から適用される。
1 物納不適格財産の明確化を図る
今回、物納制度については、①物納不適格財産の明確化等、②物納手続の明確化・迅速化、③納税者の利便の向上等の3点から見直しが行われる。
①については、まず、法令上明確でなかった物納不適格財産の範囲(管理処分不適格要件)について、例えば、抵当権が設定されている不動産、境界が不明確な土地等の一定の財産などを法令において明記する。現在、相続税基本通達42-2において、管理又は処分をするのに不適当な財産が例示されているが、これを法令において限定するというものだ。
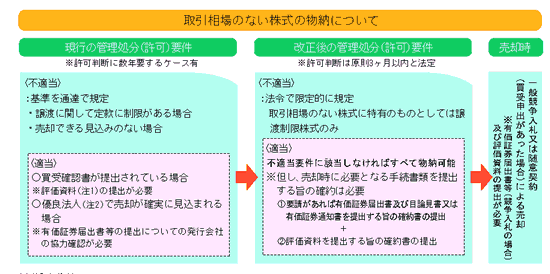
(注1)評価資料
①貸借対照表(直前期)②損益計算書(直前期)③営業報告書(直前期)④利益処分報告書(直近二期)⑤財務諸表附属明細書(直前期)⑥その他必要資料
(注2)優良法人の業績要件
①直近二期の当期利益がマイナスとなっていない、②直近二期の総資本経常利益率・売上高経常利益率・総資本回転率のうち2つが同業種平均超、③直近二期において配当可能利益有、のいずれも満たすこと
譲渡制限株式のみが物納不適格
また、取引相場のない株式等については、現行、買受確認書が提出されており、優良法人で売却が確実に見込まれることを条件に物納が認められている。
しかし、今回の見直しにより、譲渡制限株式のみが物納不適格とされ、それ以外の株式の物納については、優良法人かどうかなどに関わらず認められることになる。ただし、有価証券届出書及び目論見書又は有価証券通知書を提出する旨の確約書の提出、評価資料を提出する旨の確約書を提出する必要がある。
取引相場のない株式等の物納許可基準の大幅な緩和により、自社株式の物納が増加することも予想されそうだ。
なお、物納不適格財産の例としては、以下の表のとおりとなる。
2 物納劣後財産の明確化を図る
その一方で、物納劣後財産(他に物納適格財産がない場合に限り物納を認める財産)として、市街化調整区域内の土地、接道条件を充足していない土地(いわゆる無道路地)等を定め、その範囲の明確化も図る。物納財産は基本的に売却により歳入に充てるべきものであることから、市場で処分し易い財産の物納を優先することを明確化する趣旨でもある。
具体的には、以下の表のとおりとなるが、無道路地や維持又は管理に特殊技能を要する劇場、工場、浴場その他大建築物及びその敷地については、従来、相続税基本通達42-2に明記されていた管理又は処分をするのに不適当な財産であったが、物納劣後財産とされ、他に売却し易い不動産がない場合に限り物納が可能になる。
なお、物納申請された財産が物納不適格財産又は物納劣後財産に該当する場合であって、他に物納適格財産を有するときは、税務署長は物納申請を却下することになるが、その場合、納税者は、却下の日から20日以内であれば、1度に限り物納の再申請を可能としている。
 工場は物納劣後財産に
工場は物納劣後財産に物納不適格財産の例 | 物納劣後財産の例 |
| ・国が完全な所有権を取得できない財産 →抵当権付の不動産、所有権の帰属が係争中の財産など ・境界が特定できない財産、借地契約の効力の及ぶ範囲が特定できない財産等 →境界線が明確でない土地(但し、山林は原則として測量不要)、借地権の及ぶ範囲が不明確な貸地など ・通常、他の財産と一体で管理処分される財産で、単独で処分することが不適当なもの →共有財産、稼動工場の一部など ・物納財産に債務が付随することにより負担が国に移転することとなる財産 →敷金等の債務を国が負担しなければならなくなる貸地、貸家等 ・争訟事件となる蓋然性が高い財産 →越境している建物、契約内容が貸主に著しく不利な貸地など ・法令等により譲渡にあたり特定の手続が求められる財産で、その手続が行われないもの →証券取引法上の所要の手続が取られていない株式、定款に譲渡制限がある株式など | ・法令の規定に違反して建築した建物及びその敷地 ・地上権、永小作権その他の用益権の設定されている土地 ・接道条件を充足していない土地(いわゆる無道路地) ・都市計画法に基づく開発許可が得られない道路条件の土地 ・法令・条例の規定により、物納申請地の大部分に建築制限が課される土地 ・維持又は管理に特殊技能を要する劇場、工場、浴場その他大建築物及びその敷地 ・土地区画整理事業の施行地内にある土地で、仮換地が指定されていないもの ・生産緑地の指定を受けている農地及び農業振興地域内の農地 ・市街化調整区域内の土地等 ・市街化区域外の山林及び入会慣習のある土地 ・忌み地 ・相続人が居住又は事業の用に供している家屋及び土地 ・ 休眠会社の株式 |
3 物納手続の明確化・迅速化
②の物納手続の明確化・迅速化では、まず、物納の許可に係る審査期間の法定化が行われる。物納の許可又は却下については、物納申請期限から3ヶ月以内に行うことを原則とする。
ただし、物納財産が多数となるなど、調査等に相当の期間を要すると見込まれる場合には、6ヶ月以内(積雪など特別な事情による場合は9ヶ月以内)とすることができる。審査期間内に許可又は却下が行われない場合には、物納を許可したものとみなされる。
実際、物納の許可については、ケースによっては、数年を要するものもあるため、今回の審査期間の法定化により、スピードアップが図られることになる。
物納手続に必要な書類を明確化
物納財産を国が収納するために必要な書類をあらかじめ法令において明確化するとともに、物納申請時に申請書と併せて提出することとされている。例えば、不動産であれば、登記事項証明書、測量図、境界確認書等、有価証券であれば、要請により有価証券届出書等を提出する旨の確約書等ということになる。また、提出された物納手続に必要な書類の記載に不備があった場合又は物納手続に必要な書類の提出漏れがあった場合には、これらの書類の補正又は提出を申請者に請求することができることとする。この請求後20日以内に物納手続に必要な書類について補正又は提出がされなかった場合には、物納申請を取り下げたものとみなされる。
4 納税者の利便向上
③の納税者の利便の向上という観点からは、まず、延納中の物納の選択を可能とする制度を創設する。現在、延納から物納に変更することは認められていない。しかし、延納による納付が困難になった場合には、申告期限から10年以内に限り、延納税額からその納期限の到来した分納税額を控除した残額を限度に、物納を選択することができるようにする。いわゆるバブル崩壊後、長期にわたる地価の急落により、結果的に相続税の延納税額の納付が困難となっている者に対する緊急避難措置として平成6年に導入された特例物納と同様のものである。
ただし、収納価額については、相続開始時の価額ではなく、物納申請時の価額とされている。なお、税務署長は、収納時までにその物納財産の状況に著しい変化が生じたときには、収納時の現況により、その物納財産の収納価額を定めることができるとされている。
物納完了まで利子税を求める
その他、物納の許可に係る審査期間の法定、納税者による書類提出期限の延長手続
の整備などに伴い、期限内に納付した者や延納による納付する者との均衡を図る等の観点から、物納により納付が完了されるまでの間について利子税を課すことにする。ただし、審査事務に要する期間については、利子税は免除される。
COLUMN
物納申請は年々減少へ
国税については、金銭による納付が原則。しかし、相続税については、財産課税という性格上、延納によっても金銭で納付することが困難である場合には、一定の財産による物納制度が認められている(相続税法41条~43条)。物納の申請件数については、平成11年度以降減少しており、平成16年度では、3,065件(1,288億円)。問題が指摘されていた未済件数についても、年々減少し、平成16年度では、5,968件となっている。今回の見直しにより、未済件数も大幅に縮小することになりそうだ。
【未済件数】
平成14年度 9,702件(対前年度比 95.2%) 8,356億円(対前年度比 92.0%)
平成15年度 8,217件(対前年度比 84.7%) 6,547億円(対前年度比 78.4%)
平成16年度 5,968件(対前年度比 72.6%) 4,777億円(対前年度比 73.0%)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























