解説記事2006年02月20日 【会社法解説】 図解でわかる法務省令講座―新法下の株主総会―(2006年2月20日号・№151)
図解でわかる法務省令講座
―新法下の株主総会―
法務省民事局付 郡谷大輔
前回の講座「会社法関係法務省令の全体像」では、パブリック・コメントに付された9本の法務省令案と公布された3本の会社法施行規則・会社計算規則・電子公告規則について、その構成の違いを俯瞰するとともに、規定の移動・整理状況を明らかにしたところである。今回は、会社法施行規則(以下「施行規則」という)の総則について触れた上、株主総会に関する規律を解説する。株主総会参考書類の記載事項については、現行法制からの変更が相当程度あるので、特に注意が必要である。
人物紹介
マミ
霞が関の監査法人に勤める公認会計士。経済産業省・法務省において政策立案・立法作業に携わる。そのビボウに加え、ポンチ絵や図表の作成でも非凡な才能を発揮することから、同僚は「ビジュアル・クィーン」と呼ぶ。
カナ
赤坂の法律事務所に勤める弁護士。法務省において立法作業に携わる。各方面からの問合せや同僚の不適切な発言をときに厳しく、ときに平然とさばく姿勢には定評がある。マミの指導のもと、会計の勉強中。
Ⅰ 施行規則総則の概要
施行規則の総則は、4条からなる。
1条は目的、2条は定義、3条と4条は親子会社に関する規律である。
1 定 義
施行規則2条1項と2項は、会社法の中で定義され、または略語として設けられている用語を、施行規則でもそのまま用いることを規定している。
したがって、施行規則2条において、会社法における定義とは別に独自に定義を設けているのは、3項だけということになる。
このうち、会社法と施行規則でその用法が異なり、注意を要する用語は、図表1のとおりである。「最終事業年度」は、会社法上、持分会社には相当する概念がないため、施行規則において規定することとしたものである。
また、「計算関係書類」(施行規則2条3項11号)は、株式会社が作成する計算関係の書類全般を意味する。
2 親子会社
(1)実質子会社概念
会社法では、実質子会社概念が採用されている(施行規則3条・4条)。
規定の実質は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の8条4項に規定する親子会社と同じである。
旧商法と比較すると、50%以上の議決権を有していない場合であっても子会社に該当する場合がある(施行規則3条3項2号・3号)一方で、50%以上の議決権を有していても倒産手続中である場合(同項1号イ~ニ)、特別目的会社(施行規則4条)である場合には、子会社とならない場合もある。
また、子会社となりうるものも会社のみならず、他の法人や人格のない事業体等も対象となる。
なお、形式基準と実質基準における子会社の範囲の差異については、図表2を参照されたい。
(2)親子会社に関する経過措置
施行規則附則2条では、子会社概念が変更されることに伴う経過措置が設けられている。
具体的には、形式基準では子会社に該当しなかったが、実質基準では子会社に該当する会社等の使用人等を兼ねている場合における、社外取締役(施行規則附則2条1項)、社外監査役(同条2項)、監査役の兼任禁止(同条3項・4項)についての取扱いを定めるものである。
社外取締役・社外監査役については、この省令の施行後最初に開催される定時株主総会まで、兼任については当該監査役の任期が満了するまで、それぞれ猶予期間が設けられている。
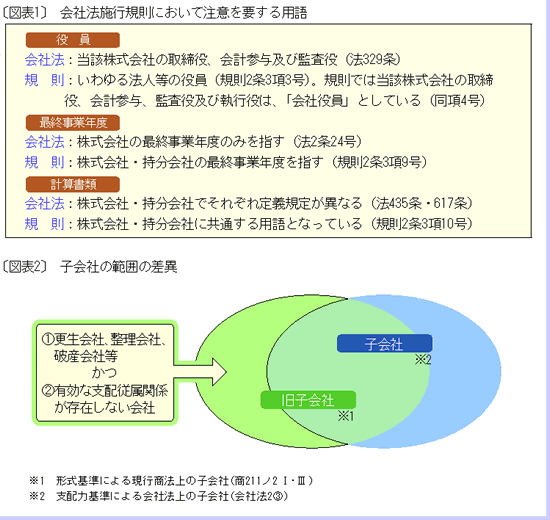
point
定 義
~施行規則で独自に定義規定を設けているものは2条3項のみである。
~定義語の中には、役員、最終事業年度など会社法と異なる意味で用いられている場合がある。
親子会社
~形式基準から実質基準に変更されている。
子会社の範囲変更に関する経過措置
~社外取締役・社外監査役については、施行後最初に開催される定時株主総会まで猶予されている。
Ⅱ 株主総会総論
1 省令委任事項
株主総会に関して会社法が委任する省令委任事項と施行規則における規定は、図表3のとおりである。
2 適用時期
(1)会社法・現行商法
施行規則とは直接の関係はないが、特に3月決算会社について、本年6月の株主総会を会社法により開催するのか、現行商法により開催するのかは、難しい問題である。
会社法の整備法90条は、「施行日前に株主総会……の招集の手続が開始された場合」には、なお従前の例によるとしており、ここでいう「招集の手続」の開始とは、株主総会を開催する旨の株式会社の意思決定(日時・場所等についての取締役会の決議)によって決せられる。
したがって、現在予定している施行日5月1日を前提とすると、図表4のような整理となる。
(2)この省令の施行後最初に開催する株主総会についての経過措置
施行規則では、株主総会参考書類・事業報告等の内容が、現行商法施行規則よりも充実している。
もっとも、施行規則附則5条・6条では、この省令の施行後最初に開催する株主総会に限り、施行規則で増加した開示内容は適用しないこととしている。
これは、後述するWEB開示のための定款規定の整備がされるまで、開示を猶予しようとするものである。
なお、これは最初の株主総会についての特例であり、その株主総会は必ずしも定時株主総会に限られていない点に留意すべきである。
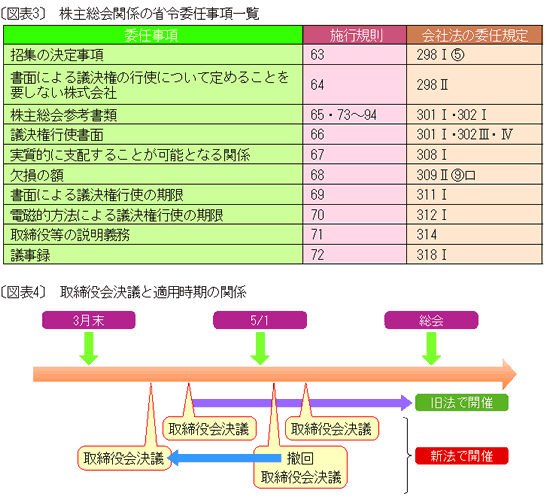
3 相互保有株主
施行規則67条は、いわゆる相互保有株主の議決権の停止に関する要件を定める規定である。
25%を保有する場合という要件は、現行商法241条3項とほぼ変わるところはないが、会社法では、次の点について変更が加えられている。
① 相互保有株主の対象となる者(相手方)は現行法の株式会社・有限会社に限られず、外国会社、組合その他の事業体が含まれている。
② 25%保有の議決権の内容として、完全無議決権株式のみを除外するのではなく(現行商法241条4項において準用する商法211条ノ2第4項)、役員等の選任および定款の変更に関する議案の全部について議決権を行使できないものを除外した。
③ 相互保有の結果、一の議案につき、議決権を行使することができる者が存しない場合(例えば、完全子会社が親会社の株式を25%超保有している場合)には、相互保有株主が議決権を行使することができることとした。
相互保有株主(そうごほゆうかぶぬし)
AとBが相互に相手方の株式を保有している場合、一般に、株式を相互保有株式といい、株主を相互保有株主という。現行商法241条3項は、「総株主の議決権の4分の1を超える議決権を有する」場合等に相互保有株式は議決権を有しないものとしている。会社法308条1項は、「4分の1以上を有する」場合等を、一株一議決権原則から「除く」形で議決権を有しないとした。
Ⅲ 株主総会各論
1 招集の決定事項
施行規則63条は、招集の決定事項について規定している。もっとも、招集の決定事項の基本的な事項は、法298条1項に規定されているので、これらも併せて考慮する必要がある。
なお、項目ごとに決定事項を整理すると、図表5のとおりとなる。
招集の決定事項に係る留意点は、次のとおりである。
(1)書面投票・電子投票の双方を採用した場合(施 行規則63条4号)
実務的には、書面投票が義務付けられている会社の多くが書面投票・電子投票の双方を採用することとなる。
会社法では、書面投票・電子投票の双方を採用した場合に生ずる重複議決権行使の問題に対応するために、次のような措置を講じている。
① 電子投票に承諾している株主には、請求があるまでは、書面投票に係る議決権行使書面を送付しない旨を決定できるようにし、物理的に、二以上の議決権行使手段が株主に与えられることを防ぐことができる。
② 同一の議案について重複して議決権行使がされ、かつ、その内容が異なる場合の取扱いを予め決定しておくことができるものとし、重複して行使された場合であっても、会社は予め定めたとおりに取り扱うことができる。
なお、この取扱方法には、特に制限はないので、書面・電子のいずれかを優先する方法、時間を優先する方法、すべてを無効とする方法、当該事項について賛否の記載がないものとする方法(この場合には、賛否の記載がない場合の取扱いに従って処理されることとなる)などが考えられる。
(2)代理人に関する事項(施行規則63条5号)
例えば、代理権を証明する方法としては、会社法上委任状を提出すべきこととされている(会社法310条1項後段)が、これに加え、議決権行使書面を持参すべきであるなどの付加的な手続を定めることができる。
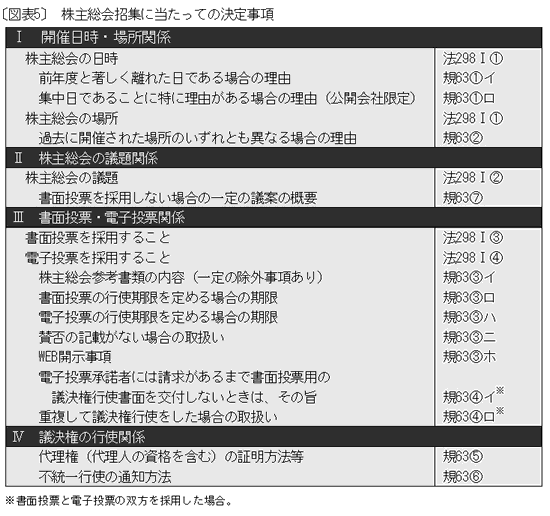
point
招集の決定事項
~現行商法とは異なり、招集の決定事項が明確にされた。
~書面投票・電子投票の双方を採用する会社には、議決権の重複行使を回避するための手段が用意されている。
2 株主総会参考書類
以下では、株主総会参考書類に関する施行規則の規律の内容を紹介する。なお、社外取締役等の選任議案に関する開示事項については、開示事項が重複している事業報告の解説時にまとめて解説することとし、今回は割愛する。
(1)現行法との比較
株主総会参考書類については、現行商法施行規則と比較すると、図表6のように記載内容が一部変更されている。
(2)招集通知・事業報告との重複についての調整
施行規則73条3項は、同一の株主総会に提供される他の資料に株主総会参考書類に記載すべき事項が表示されている場合には、株主総会参考書類の記載を省略することができるとし、同条4項は、その逆に、招集通知・事業報告に表示すべき事項を株主総会参考書類に記載した場合には、当該事項は招集通知および株主に提供すべき事業報告から省略することができることとしている(図表7参照)。
もっとも、事業報告については、その内容を株主に提供するに際しての提供すべき事項との関係で省略することができるのであって、事業報告自体の内容から省略することができるわけでないことに注意を要する。
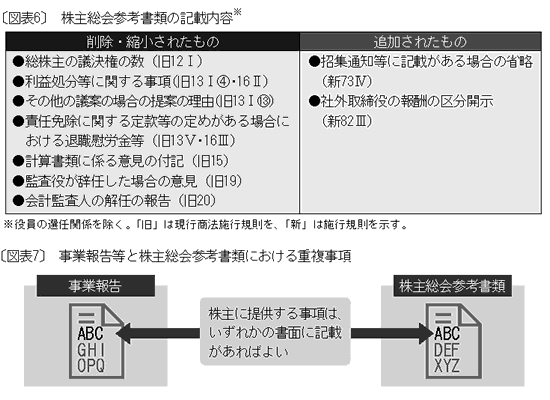
(3)WEB開示
WEB開示制度とは、会社法の下で新たに導入された制度である。
株主総会参考書類、事業報告、個別注記表および連結計算書類など、株主総会の招集通知とともに株主に提供すべき資料に表示すべき事項の一部を、インターネットのホームページに掲載するとともに、当該ホームページのアドレスのみを株主に通知すれば、これらの事項は株主に提供されたものとみなして、物理的な書面等による提供を省略することを認めている。
以下では、株主総会参考書類についてのWEB開示制度について解説する。
① WEB開示制度の対象となる事項
株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、次の事項を除いた事項は、すべてWEB開示制度の対象となる。
議案(施行規則94条1項1号)
事業報告に表示すべき事項であったものを株主総会参考書類に記載した場合の当該事項(同項2号)
WEB開示を行うホームページのアドレス(同項3号)
監査役または監査委員会がWEB開示制度を利用することについて異議を述べた事項(同項4号)
なお、WEB開示制度により、株主に提供する株主総会参考書類から記載を省略する事項については、招集の決定事項として定めなければならない(施行規則63条3号ホ)。
② WEB開示をすべき期間
WEB開示は、招集通知を発出した時から開示を開始し、株主総会の日から3か月を経過する日までの間、継続して行わなければならない。
なお、電子公告とは異なり、開示の中断や情報の変更等については、特に制限はない。
したがって、開示の中断が生じた場合には、ただちに違法となるわけではなく、開示期間全体として継続して行ったと評価しうるかどうかという点から実質的に判断すべきこととなる。
また、情報の変更については、別途、修正事項の周知方法に関する通知制度(施行規則65条3項)を利用することになる。
③ 定款の定め
WEB開示制度を採用するために、WEB開示制度を採用する旨の定款の定めが必要である(施行規則94条1項ただし書等)。
④ その他の留意事項
WEB開示制度の概要は、以上のとおりであるが、いくつかの留意すべき事項がある。
まず、インターネットのホームページに開示するとはいっても、必ずしも不特定多数の者がアクセス可能となっている必要はなく、株主のみがアクセス可能な設定をしておくことは妨げられない(条文上も「株主が提供を受けることができる状態に置く措置」としており、電子公告等とは異なっている)。
次に、WEB開示制度においては、株主総会参考書類の一部が対象となっているが、情報の一覧性の観点から、WEB開示制度の対象となっていない情報を参考情報として、併せて開示することも妨げられない。
なお、会社法施行後最初に開催される株主総会については、③に述べた定款の定めは設けられていないことが通常である。したがって、当該総会に関してWEB開示制度を利用することはできない。
WEB開示は会社法において開示事項が増えたことに伴うものであるから、施行規則附則5条において経過措置を定め、当該総会に係る株主総会参考書類については、新しい施行規則に基づく内容としなくてよいように手当てしている。
(4)修正事項の通知
施行規則65条3項は、株主総会参考書類の記載に印刷ミスその他の事情で誤りがある場合や、株主総会参考書類の発出後の事情変更等(議案の撤回や差替え等)があった場合に、修正後の事項を株主に周知させる方法を、招集通知と併せて通知することができることとしている。
なお、株主に周知させる方法としては、WEB開示等と同様の方法が考えられる。
(5)パブリック・コメント版からの変更
最後に、株主総会参考書類の記載事項について、パブリック・コメント版から公布版で変更された主な事項(社外取締役等の選任議案に関するものを除く)を紹介する。
① 集中日の理由決定は、特に理由がある場合に限定(施行規則63条1号イ)
② 書面投票等の行使期限や賛否の記載がない場合の取扱いにつき取締役への委任を許容(同条3号)
③ 書面投票を採用しない場合の議案の概要の通知義務の範囲の拡大(同条7号)
④ 株主総会参考書類の修正事項の通知方法に関する規定の整備(施行規則65条3項)
⑤ 議決権行使書面と招集通知との重複記載の調整規定(施行規則66条3項・4項)
⑥ 株主総会参考書類記載事項を他の書面に記載する場合の明示の義務付け(施行規則73条3項後段)
⑦ 組織再編行為に関する議案についての株主総会参考書類記載事項を拡大(施行規則86条3号・4号、87条3号・4号、88条3号・4号等)
⑧ WEB開示制度の導入(94条)
3 取締役の説明義務
施行規則71条は、株主総会において、取締役等が説明を拒絶することができる場合について定めるものである。
同条1号および同号イは、当該株主総会の日より相当の期間前に説明を求める事項を株式会社に対して通知した場合には、説明をするために調査をすることが必要であることを理由に拒絶することができないとするものである。
その他の拒絶できる場合を現行法と比較すると、図表8のとおりとなる。
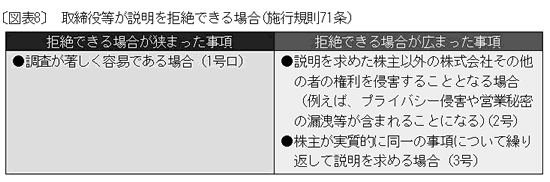
4 株主総会の議事録
株主総会の議事録については、現行法と同様、議事の経過の概要およびその結果(施行規則72条3項2号)をその内容とするほか、会社法の下では、次のような改正が行われている。
① 株主総会の日時・場所のほか、一部の取締役等や株主がインターネットや電話等を通じて参加した場合には、その出席方法を明らかにすることとしている(施行規則72条3項1号)。
② 株主総会において、会社法の規定に基づき述べられた意見・発言について特記することとしている(施行規則72条3項3号)。
③ 株主総会の議事録に対する出席取締役等の署名義務を、原則として廃止した(商業登記規則その他の法令の規定により義務付けられる場合がある)。
④ 総株主の同意の場合においても、議事録の作成が必要となっている(施行規則72条4項)。
point
株主総会参考書類
~株主総会参考書類の記載事項は、現行商法施行規則から相当程度変更されている。
~株主総会参考書類に記載した事項は、招集通知・株主に提供すべき事業報告から省略可能である。
~株主への書面等による直接開示に代えて、WEB開示が可能になる。
~WEB開示制度の要件は、次のようなものである。
①WEB開示をする旨の定款の定めが必要
②招集通知の発出時から、株主総会終了後3か月経過するまで継続開示
③株主がアクセス可能なインターネット上のホームページで開示
~招集通知・株主総会参考書類の事後的な修正方法が明確化された。
株主総会の議事録
~インターネット会議・電話会議による株主総会の開催が明確化された。
~出席した取締役等の署名義務は原則廃止している。
~総株主の同意による決議省略の場合にも議事録作成義務がある。
今週のおさらい
施行規則2条3項に会社法と用法が異なる用語を列挙
役員、最終事業年度など会社法と異なる意味のものがある。
親子会社について財務諸表等規則の実質子会社概念を採用
子会社の範囲の変更に伴う猶予期間が設けられている。
株主総会招集の際の決定事項を明確化
会社法298条1項と施行規則63条を併せて参照する。
株主総会参考書類の記載事項は相当程度の変更
現行規則、パブコメ版との差異がある上、WEB開示制度の対象ともなった。
―新法下の株主総会―
法務省民事局付 郡谷大輔
前回の講座「会社法関係法務省令の全体像」では、パブリック・コメントに付された9本の法務省令案と公布された3本の会社法施行規則・会社計算規則・電子公告規則について、その構成の違いを俯瞰するとともに、規定の移動・整理状況を明らかにしたところである。今回は、会社法施行規則(以下「施行規則」という)の総則について触れた上、株主総会に関する規律を解説する。株主総会参考書類の記載事項については、現行法制からの変更が相当程度あるので、特に注意が必要である。
人物紹介
マミ
霞が関の監査法人に勤める公認会計士。経済産業省・法務省において政策立案・立法作業に携わる。そのビボウに加え、ポンチ絵や図表の作成でも非凡な才能を発揮することから、同僚は「ビジュアル・クィーン」と呼ぶ。
カナ
赤坂の法律事務所に勤める弁護士。法務省において立法作業に携わる。各方面からの問合せや同僚の不適切な発言をときに厳しく、ときに平然とさばく姿勢には定評がある。マミの指導のもと、会計の勉強中。
Ⅰ 施行規則総則の概要
施行規則の総則は、4条からなる。
1条は目的、2条は定義、3条と4条は親子会社に関する規律である。
1 定 義
施行規則2条1項と2項は、会社法の中で定義され、または略語として設けられている用語を、施行規則でもそのまま用いることを規定している。
したがって、施行規則2条において、会社法における定義とは別に独自に定義を設けているのは、3項だけということになる。
このうち、会社法と施行規則でその用法が異なり、注意を要する用語は、図表1のとおりである。「最終事業年度」は、会社法上、持分会社には相当する概念がないため、施行規則において規定することとしたものである。
また、「計算関係書類」(施行規則2条3項11号)は、株式会社が作成する計算関係の書類全般を意味する。
2 親子会社
(1)実質子会社概念
会社法では、実質子会社概念が採用されている(施行規則3条・4条)。
規定の実質は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の8条4項に規定する親子会社と同じである。
旧商法と比較すると、50%以上の議決権を有していない場合であっても子会社に該当する場合がある(施行規則3条3項2号・3号)一方で、50%以上の議決権を有していても倒産手続中である場合(同項1号イ~ニ)、特別目的会社(施行規則4条)である場合には、子会社とならない場合もある。
また、子会社となりうるものも会社のみならず、他の法人や人格のない事業体等も対象となる。
なお、形式基準と実質基準における子会社の範囲の差異については、図表2を参照されたい。
(2)親子会社に関する経過措置
施行規則附則2条では、子会社概念が変更されることに伴う経過措置が設けられている。
具体的には、形式基準では子会社に該当しなかったが、実質基準では子会社に該当する会社等の使用人等を兼ねている場合における、社外取締役(施行規則附則2条1項)、社外監査役(同条2項)、監査役の兼任禁止(同条3項・4項)についての取扱いを定めるものである。
社外取締役・社外監査役については、この省令の施行後最初に開催される定時株主総会まで、兼任については当該監査役の任期が満了するまで、それぞれ猶予期間が設けられている。
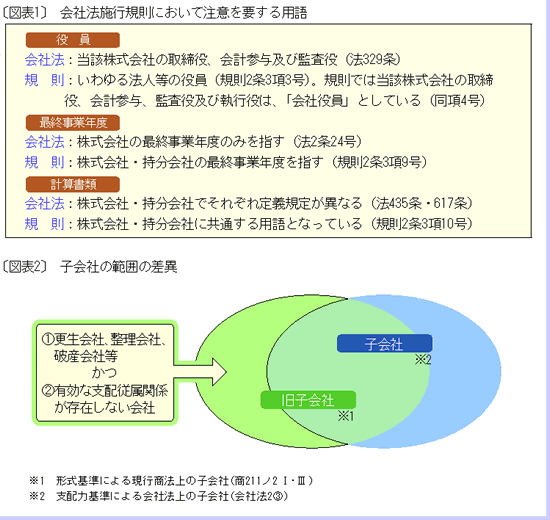
point
定 義
~施行規則で独自に定義規定を設けているものは2条3項のみである。
~定義語の中には、役員、最終事業年度など会社法と異なる意味で用いられている場合がある。
親子会社
~形式基準から実質基準に変更されている。
子会社の範囲変更に関する経過措置
~社外取締役・社外監査役については、施行後最初に開催される定時株主総会まで猶予されている。
Ⅱ 株主総会総論
1 省令委任事項
株主総会に関して会社法が委任する省令委任事項と施行規則における規定は、図表3のとおりである。
2 適用時期
(1)会社法・現行商法
施行規則とは直接の関係はないが、特に3月決算会社について、本年6月の株主総会を会社法により開催するのか、現行商法により開催するのかは、難しい問題である。
会社法の整備法90条は、「施行日前に株主総会……の招集の手続が開始された場合」には、なお従前の例によるとしており、ここでいう「招集の手続」の開始とは、株主総会を開催する旨の株式会社の意思決定(日時・場所等についての取締役会の決議)によって決せられる。
したがって、現在予定している施行日5月1日を前提とすると、図表4のような整理となる。
(2)この省令の施行後最初に開催する株主総会についての経過措置
施行規則では、株主総会参考書類・事業報告等の内容が、現行商法施行規則よりも充実している。
もっとも、施行規則附則5条・6条では、この省令の施行後最初に開催する株主総会に限り、施行規則で増加した開示内容は適用しないこととしている。
これは、後述するWEB開示のための定款規定の整備がされるまで、開示を猶予しようとするものである。
なお、これは最初の株主総会についての特例であり、その株主総会は必ずしも定時株主総会に限られていない点に留意すべきである。
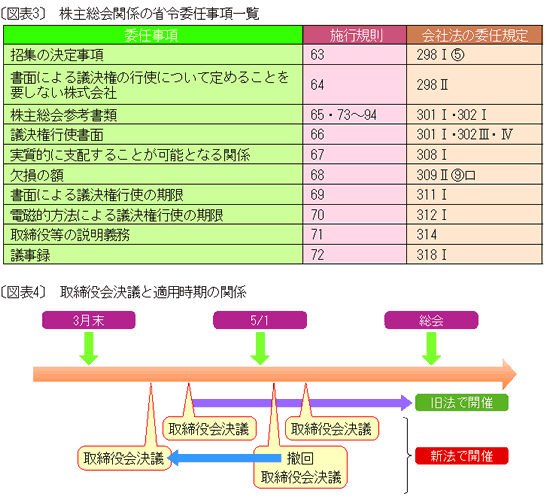
3 相互保有株主
施行規則67条は、いわゆる相互保有株主の議決権の停止に関する要件を定める規定である。
25%を保有する場合という要件は、現行商法241条3項とほぼ変わるところはないが、会社法では、次の点について変更が加えられている。
① 相互保有株主の対象となる者(相手方)は現行法の株式会社・有限会社に限られず、外国会社、組合その他の事業体が含まれている。
② 25%保有の議決権の内容として、完全無議決権株式のみを除外するのではなく(現行商法241条4項において準用する商法211条ノ2第4項)、役員等の選任および定款の変更に関する議案の全部について議決権を行使できないものを除外した。
③ 相互保有の結果、一の議案につき、議決権を行使することができる者が存しない場合(例えば、完全子会社が親会社の株式を25%超保有している場合)には、相互保有株主が議決権を行使することができることとした。
相互保有株主(そうごほゆうかぶぬし)
AとBが相互に相手方の株式を保有している場合、一般に、株式を相互保有株式といい、株主を相互保有株主という。現行商法241条3項は、「総株主の議決権の4分の1を超える議決権を有する」場合等に相互保有株式は議決権を有しないものとしている。会社法308条1項は、「4分の1以上を有する」場合等を、一株一議決権原則から「除く」形で議決権を有しないとした。
Ⅲ 株主総会各論
1 招集の決定事項
施行規則63条は、招集の決定事項について規定している。もっとも、招集の決定事項の基本的な事項は、法298条1項に規定されているので、これらも併せて考慮する必要がある。
なお、項目ごとに決定事項を整理すると、図表5のとおりとなる。
招集の決定事項に係る留意点は、次のとおりである。
(1)書面投票・電子投票の双方を採用した場合(施 行規則63条4号)
実務的には、書面投票が義務付けられている会社の多くが書面投票・電子投票の双方を採用することとなる。
会社法では、書面投票・電子投票の双方を採用した場合に生ずる重複議決権行使の問題に対応するために、次のような措置を講じている。
① 電子投票に承諾している株主には、請求があるまでは、書面投票に係る議決権行使書面を送付しない旨を決定できるようにし、物理的に、二以上の議決権行使手段が株主に与えられることを防ぐことができる。
② 同一の議案について重複して議決権行使がされ、かつ、その内容が異なる場合の取扱いを予め決定しておくことができるものとし、重複して行使された場合であっても、会社は予め定めたとおりに取り扱うことができる。
なお、この取扱方法には、特に制限はないので、書面・電子のいずれかを優先する方法、時間を優先する方法、すべてを無効とする方法、当該事項について賛否の記載がないものとする方法(この場合には、賛否の記載がない場合の取扱いに従って処理されることとなる)などが考えられる。
(2)代理人に関する事項(施行規則63条5号)
例えば、代理権を証明する方法としては、会社法上委任状を提出すべきこととされている(会社法310条1項後段)が、これに加え、議決権行使書面を持参すべきであるなどの付加的な手続を定めることができる。
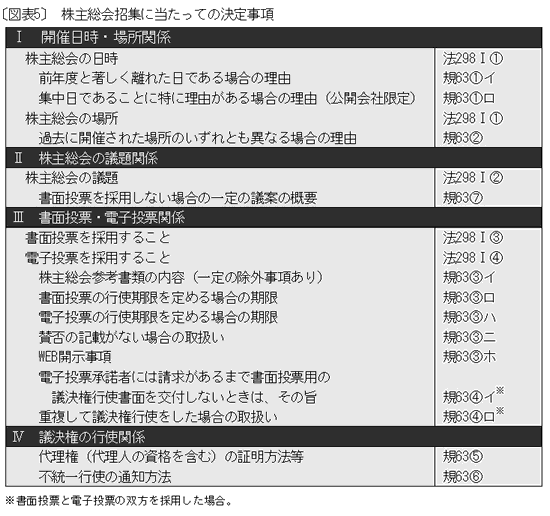
point
招集の決定事項
~現行商法とは異なり、招集の決定事項が明確にされた。
~書面投票・電子投票の双方を採用する会社には、議決権の重複行使を回避するための手段が用意されている。
2 株主総会参考書類
以下では、株主総会参考書類に関する施行規則の規律の内容を紹介する。なお、社外取締役等の選任議案に関する開示事項については、開示事項が重複している事業報告の解説時にまとめて解説することとし、今回は割愛する。
(1)現行法との比較
株主総会参考書類については、現行商法施行規則と比較すると、図表6のように記載内容が一部変更されている。
(2)招集通知・事業報告との重複についての調整
施行規則73条3項は、同一の株主総会に提供される他の資料に株主総会参考書類に記載すべき事項が表示されている場合には、株主総会参考書類の記載を省略することができるとし、同条4項は、その逆に、招集通知・事業報告に表示すべき事項を株主総会参考書類に記載した場合には、当該事項は招集通知および株主に提供すべき事業報告から省略することができることとしている(図表7参照)。
もっとも、事業報告については、その内容を株主に提供するに際しての提供すべき事項との関係で省略することができるのであって、事業報告自体の内容から省略することができるわけでないことに注意を要する。
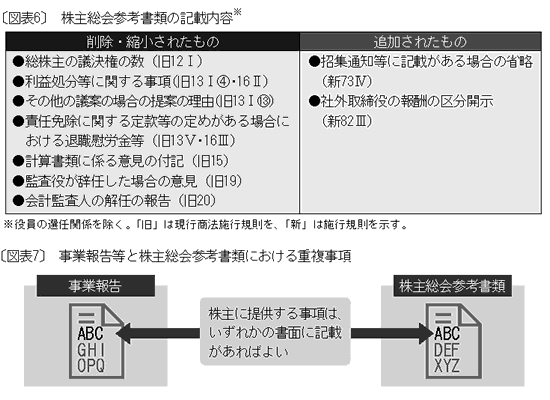
(3)WEB開示
WEB開示制度とは、会社法の下で新たに導入された制度である。
株主総会参考書類、事業報告、個別注記表および連結計算書類など、株主総会の招集通知とともに株主に提供すべき資料に表示すべき事項の一部を、インターネットのホームページに掲載するとともに、当該ホームページのアドレスのみを株主に通知すれば、これらの事項は株主に提供されたものとみなして、物理的な書面等による提供を省略することを認めている。
以下では、株主総会参考書類についてのWEB開示制度について解説する。
① WEB開示制度の対象となる事項
株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、次の事項を除いた事項は、すべてWEB開示制度の対象となる。
議案(施行規則94条1項1号)
事業報告に表示すべき事項であったものを株主総会参考書類に記載した場合の当該事項(同項2号)
WEB開示を行うホームページのアドレス(同項3号)
監査役または監査委員会がWEB開示制度を利用することについて異議を述べた事項(同項4号)
なお、WEB開示制度により、株主に提供する株主総会参考書類から記載を省略する事項については、招集の決定事項として定めなければならない(施行規則63条3号ホ)。
② WEB開示をすべき期間
WEB開示は、招集通知を発出した時から開示を開始し、株主総会の日から3か月を経過する日までの間、継続して行わなければならない。
なお、電子公告とは異なり、開示の中断や情報の変更等については、特に制限はない。
したがって、開示の中断が生じた場合には、ただちに違法となるわけではなく、開示期間全体として継続して行ったと評価しうるかどうかという点から実質的に判断すべきこととなる。
また、情報の変更については、別途、修正事項の周知方法に関する通知制度(施行規則65条3項)を利用することになる。
③ 定款の定め
WEB開示制度を採用するために、WEB開示制度を採用する旨の定款の定めが必要である(施行規則94条1項ただし書等)。
④ その他の留意事項
WEB開示制度の概要は、以上のとおりであるが、いくつかの留意すべき事項がある。
まず、インターネットのホームページに開示するとはいっても、必ずしも不特定多数の者がアクセス可能となっている必要はなく、株主のみがアクセス可能な設定をしておくことは妨げられない(条文上も「株主が提供を受けることができる状態に置く措置」としており、電子公告等とは異なっている)。
次に、WEB開示制度においては、株主総会参考書類の一部が対象となっているが、情報の一覧性の観点から、WEB開示制度の対象となっていない情報を参考情報として、併せて開示することも妨げられない。
なお、会社法施行後最初に開催される株主総会については、③に述べた定款の定めは設けられていないことが通常である。したがって、当該総会に関してWEB開示制度を利用することはできない。
WEB開示は会社法において開示事項が増えたことに伴うものであるから、施行規則附則5条において経過措置を定め、当該総会に係る株主総会参考書類については、新しい施行規則に基づく内容としなくてよいように手当てしている。
(4)修正事項の通知
施行規則65条3項は、株主総会参考書類の記載に印刷ミスその他の事情で誤りがある場合や、株主総会参考書類の発出後の事情変更等(議案の撤回や差替え等)があった場合に、修正後の事項を株主に周知させる方法を、招集通知と併せて通知することができることとしている。
なお、株主に周知させる方法としては、WEB開示等と同様の方法が考えられる。
(5)パブリック・コメント版からの変更
最後に、株主総会参考書類の記載事項について、パブリック・コメント版から公布版で変更された主な事項(社外取締役等の選任議案に関するものを除く)を紹介する。
① 集中日の理由決定は、特に理由がある場合に限定(施行規則63条1号イ)
② 書面投票等の行使期限や賛否の記載がない場合の取扱いにつき取締役への委任を許容(同条3号)
③ 書面投票を採用しない場合の議案の概要の通知義務の範囲の拡大(同条7号)
④ 株主総会参考書類の修正事項の通知方法に関する規定の整備(施行規則65条3項)
⑤ 議決権行使書面と招集通知との重複記載の調整規定(施行規則66条3項・4項)
⑥ 株主総会参考書類記載事項を他の書面に記載する場合の明示の義務付け(施行規則73条3項後段)
⑦ 組織再編行為に関する議案についての株主総会参考書類記載事項を拡大(施行規則86条3号・4号、87条3号・4号、88条3号・4号等)
⑧ WEB開示制度の導入(94条)
3 取締役の説明義務
施行規則71条は、株主総会において、取締役等が説明を拒絶することができる場合について定めるものである。
同条1号および同号イは、当該株主総会の日より相当の期間前に説明を求める事項を株式会社に対して通知した場合には、説明をするために調査をすることが必要であることを理由に拒絶することができないとするものである。
その他の拒絶できる場合を現行法と比較すると、図表8のとおりとなる。
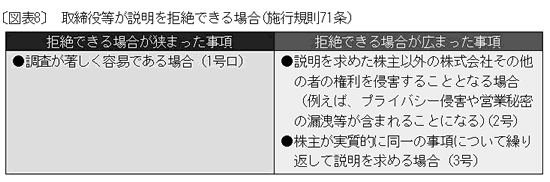
4 株主総会の議事録
株主総会の議事録については、現行法と同様、議事の経過の概要およびその結果(施行規則72条3項2号)をその内容とするほか、会社法の下では、次のような改正が行われている。
① 株主総会の日時・場所のほか、一部の取締役等や株主がインターネットや電話等を通じて参加した場合には、その出席方法を明らかにすることとしている(施行規則72条3項1号)。
② 株主総会において、会社法の規定に基づき述べられた意見・発言について特記することとしている(施行規則72条3項3号)。
③ 株主総会の議事録に対する出席取締役等の署名義務を、原則として廃止した(商業登記規則その他の法令の規定により義務付けられる場合がある)。
④ 総株主の同意の場合においても、議事録の作成が必要となっている(施行規則72条4項)。
point
株主総会参考書類
~株主総会参考書類の記載事項は、現行商法施行規則から相当程度変更されている。
~株主総会参考書類に記載した事項は、招集通知・株主に提供すべき事業報告から省略可能である。
~株主への書面等による直接開示に代えて、WEB開示が可能になる。
~WEB開示制度の要件は、次のようなものである。
①WEB開示をする旨の定款の定めが必要
②招集通知の発出時から、株主総会終了後3か月経過するまで継続開示
③株主がアクセス可能なインターネット上のホームページで開示
~招集通知・株主総会参考書類の事後的な修正方法が明確化された。
株主総会の議事録
~インターネット会議・電話会議による株主総会の開催が明確化された。
~出席した取締役等の署名義務は原則廃止している。
~総株主の同意による決議省略の場合にも議事録作成義務がある。
今週のおさらい
施行規則2条3項に会社法と用法が異なる用語を列挙
役員、最終事業年度など会社法と異なる意味のものがある。
親子会社について財務諸表等規則の実質子会社概念を採用
子会社の範囲の変更に伴う猶予期間が設けられている。
株主総会招集の際の決定事項を明確化
会社法298条1項と施行規則63条を併せて参照する。
株主総会参考書類の記載事項は相当程度の変更
現行規則、パブコメ版との差異がある上、WEB開示制度の対象ともなった。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























