解説記事2006年04月17日 【解説】 議案の決定と定款変更(4)計算に関する定款変更事項(2006年4月17日号・№159)
議案の決定と定款変更
会社法下の株主総会関係書類・直前総チェック(4)計算に関する定款変更事項
三菱UFJ信託銀行 執行役員証券代行部長 中西敏和
Ⅰ 定款変更の概要
定款は、会社の計算に関して、営業年度、利益配当、中間配当、配当金等の除斥期間について規定しているのが一般的である。
このうち、中間配当は制度導入のための必須要件であるが、利益配当は配当支払のための基準日としての、除斥期間については消滅時効に先立ち配当の支払義務を免れるための規定であり、絶対に必要的な記載事項とはいえない。
会社法は、計算書類の内容を一新し、用語、もとになる条数についても大きな変更を加えているところから、定款もその影響を受ける。
具体的には、「営業年度」を「事業年度」へ、「利益配当」を「剰余金の配当」へといった字句の修正に加え、中間配当の根拠条文を「商法第293条ノ5」から「会社法第454条第5項」に改めるといった形式的変更が生じるが、現行の配当等のスタイルを維持するのであれば、これだけでも十分であり、実務に影響を及ぼすものではない。
また、計算書類および連結計算書類の作成・承認等の決算手続については、施行日前に到来した最終の決算期に関するものについては、なお従前の例による旨が定められているところから(整備法56条、99条)、実質的な影響を受けるのは5月期決算会社からということになる。
Ⅱ 定款変更上の留意点
1 剰余金の処分と決定機関
計算書類の内容の変更として「利益処分案」が廃止され、「株主資本等変動計算書」が導入されたが、これは、単なる計算書類の名称変更にとどまらない大きな意味を持つ。
すなわち、現行法は、貸借対照表、損益計算書によって確定された利益を「利益処分案」という形で株主総会に諮るという仕組みが前提となっているのに対し、会社法は、配当を決算の確定手続と切り離し、分配可能額の範囲で、いつでも行うことができることとしている。
そして、従前の利益処分案または損失処理案については、剰余金の配当、資本の部の計数変動、役員賞与等に整理され、決算の確定手続と無関係に随時行うことができることになった。
剰余金および資本の部の計数変動は、定時株主総会に限定せずに、分配時の分配可能額の範囲内で、期中の臨時株主総会においても随時決議をとることができる。また、役員賞与は、役員の報酬制度の中に包含されるため、利益の処分として支給することは想定されていない。
現行法では、配当、中間配当それぞれ個別に財源規制が行われており、配当については商法290条1項が、中間配当については商法293条ノ5第3項がそれぞれ配当限度額を定めていた。
会社法では、株主等に対する金銭等の分配と自己株式の有償取得は、株主に対して剰余金を払い戻す行為であるという点で共通しているため、統一的に財源規制を課すものとされる。
すなわち、剰余金の分配可能額を算定し、その範囲内で図表1にあるような行為を行うことが要求される。
なお、最低資本金の撤廃に伴い、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合は、株主に対して剰余金の配当を行うことが禁じられているので、小規模会社については、この点別に留意することが必要である。
会社法はさらに、剰余金の配当その他の一定事項を株主総会ではなく取締役会の決議によって決定することを認めた。現行の委員会等設置会社においては、配当の決定権限を取締役会に授権することが認められているが、会社法は、委員会設置会社に限定していない。
ただし、会計監査人設置会社であり、取締役の任期を1年とする監査役会設置会社であることが要件であり、実質的に公開大会社が対象となる。
導入する場合には、定款に図表2のような規定を設けることが要件であり、その際、併せて当該事項は株主総会によっては決めない旨を定めることができる(「決定機関変更モデル」参照)。
この制度をいち早く導入するのであれば、本年6月の定時総会での定款変更決議に盛り込む必要がある。会社法においては、配当の回数制限がないため、四半期配当を行うことも不可能ではないが、株主総会を頻繁に開催することの煩雑さを考えると、これを志向する場合には、取締役会の決定に授権することが必要となる。
定款の規定により、剰余金の配当等を取締役会の決議に授権しない場合は、従来どおり株主総会の決議が必要である。
ただし、中間配当については、以上の要件を備えない会社でも、取締役会設置会社であれば、定款の定めにより、取締役会の決議によって中間配当をすることができる(会社法454条5項)。
また、すでに述べたとおり、自己株式取得についても、定款に規定することにより、取締役会の決議によって取得することが認められている。
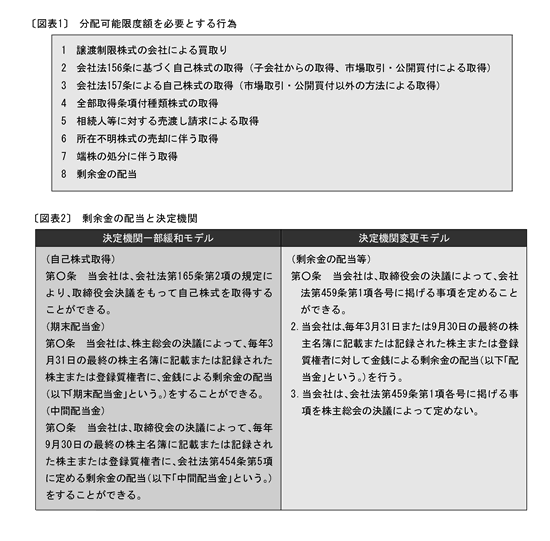
2 臨時決算
剰余金の分配額の算定は、最終事業年度に係る貸借対照表から算出される分配可能限度額を基準とし、最終事業年度末日後、当該分配を行うときまでの分配可能額の増減を反映させたものとされるが(会社法461条2項)、そこには最終事業年度末日後の期間損益による変動は含まれない。
しかし、期中に配当を行うとすると、それまでの損益を反映させたものとしなければ、期中に行う意義が薄れる。
会社法は、事業年度ごとに行う通常の決算制度のほかに、期中の特定の日までの財産および損益を反映した貸借対照表および損益計算書を作成する臨時決算制度を設けている(会社法441条)。
期中において、臨時決算手続を行うことにより、その時までの期間損益を分配可能額に反映させることができ(会社法461条2項2号・5号)、より柔軟に株主に対して利益を還元することができることになる(図表3参照)。
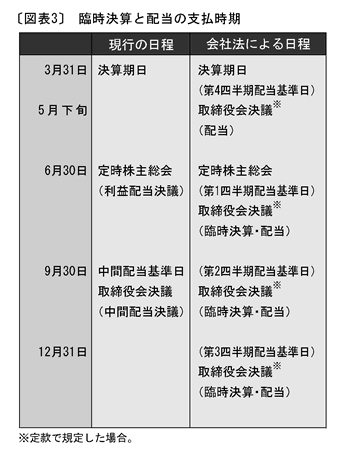
会社法下の株主総会関係書類・直前総チェック(4)計算に関する定款変更事項
三菱UFJ信託銀行 執行役員証券代行部長 中西敏和
Ⅰ 定款変更の概要
定款は、会社の計算に関して、営業年度、利益配当、中間配当、配当金等の除斥期間について規定しているのが一般的である。
このうち、中間配当は制度導入のための必須要件であるが、利益配当は配当支払のための基準日としての、除斥期間については消滅時効に先立ち配当の支払義務を免れるための規定であり、絶対に必要的な記載事項とはいえない。
会社法は、計算書類の内容を一新し、用語、もとになる条数についても大きな変更を加えているところから、定款もその影響を受ける。
具体的には、「営業年度」を「事業年度」へ、「利益配当」を「剰余金の配当」へといった字句の修正に加え、中間配当の根拠条文を「商法第293条ノ5」から「会社法第454条第5項」に改めるといった形式的変更が生じるが、現行の配当等のスタイルを維持するのであれば、これだけでも十分であり、実務に影響を及ぼすものではない。
また、計算書類および連結計算書類の作成・承認等の決算手続については、施行日前に到来した最終の決算期に関するものについては、なお従前の例による旨が定められているところから(整備法56条、99条)、実質的な影響を受けるのは5月期決算会社からということになる。
Ⅱ 定款変更上の留意点
1 剰余金の処分と決定機関
計算書類の内容の変更として「利益処分案」が廃止され、「株主資本等変動計算書」が導入されたが、これは、単なる計算書類の名称変更にとどまらない大きな意味を持つ。
すなわち、現行法は、貸借対照表、損益計算書によって確定された利益を「利益処分案」という形で株主総会に諮るという仕組みが前提となっているのに対し、会社法は、配当を決算の確定手続と切り離し、分配可能額の範囲で、いつでも行うことができることとしている。
そして、従前の利益処分案または損失処理案については、剰余金の配当、資本の部の計数変動、役員賞与等に整理され、決算の確定手続と無関係に随時行うことができることになった。
剰余金および資本の部の計数変動は、定時株主総会に限定せずに、分配時の分配可能額の範囲内で、期中の臨時株主総会においても随時決議をとることができる。また、役員賞与は、役員の報酬制度の中に包含されるため、利益の処分として支給することは想定されていない。
現行法では、配当、中間配当それぞれ個別に財源規制が行われており、配当については商法290条1項が、中間配当については商法293条ノ5第3項がそれぞれ配当限度額を定めていた。
会社法では、株主等に対する金銭等の分配と自己株式の有償取得は、株主に対して剰余金を払い戻す行為であるという点で共通しているため、統一的に財源規制を課すものとされる。
すなわち、剰余金の分配可能額を算定し、その範囲内で図表1にあるような行為を行うことが要求される。
なお、最低資本金の撤廃に伴い、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合は、株主に対して剰余金の配当を行うことが禁じられているので、小規模会社については、この点別に留意することが必要である。
会社法はさらに、剰余金の配当その他の一定事項を株主総会ではなく取締役会の決議によって決定することを認めた。現行の委員会等設置会社においては、配当の決定権限を取締役会に授権することが認められているが、会社法は、委員会設置会社に限定していない。
ただし、会計監査人設置会社であり、取締役の任期を1年とする監査役会設置会社であることが要件であり、実質的に公開大会社が対象となる。
導入する場合には、定款に図表2のような規定を設けることが要件であり、その際、併せて当該事項は株主総会によっては決めない旨を定めることができる(「決定機関変更モデル」参照)。
この制度をいち早く導入するのであれば、本年6月の定時総会での定款変更決議に盛り込む必要がある。会社法においては、配当の回数制限がないため、四半期配当を行うことも不可能ではないが、株主総会を頻繁に開催することの煩雑さを考えると、これを志向する場合には、取締役会の決定に授権することが必要となる。
定款の規定により、剰余金の配当等を取締役会の決議に授権しない場合は、従来どおり株主総会の決議が必要である。
ただし、中間配当については、以上の要件を備えない会社でも、取締役会設置会社であれば、定款の定めにより、取締役会の決議によって中間配当をすることができる(会社法454条5項)。
また、すでに述べたとおり、自己株式取得についても、定款に規定することにより、取締役会の決議によって取得することが認められている。
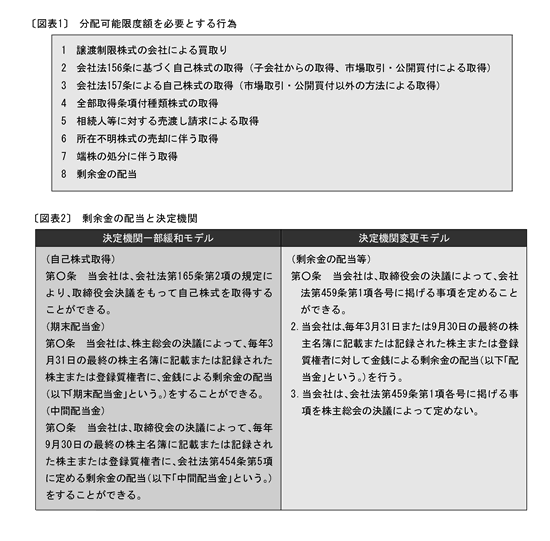
2 臨時決算
剰余金の分配額の算定は、最終事業年度に係る貸借対照表から算出される分配可能限度額を基準とし、最終事業年度末日後、当該分配を行うときまでの分配可能額の増減を反映させたものとされるが(会社法461条2項)、そこには最終事業年度末日後の期間損益による変動は含まれない。
しかし、期中に配当を行うとすると、それまでの損益を反映させたものとしなければ、期中に行う意義が薄れる。
会社法は、事業年度ごとに行う通常の決算制度のほかに、期中の特定の日までの財産および損益を反映した貸借対照表および損益計算書を作成する臨時決算制度を設けている(会社法441条)。
期中において、臨時決算手続を行うことにより、その時までの期間損益を分配可能額に反映させることができ(会社法461条2項2号・5号)、より柔軟に株主に対して利益を還元することができることになる(図表3参照)。
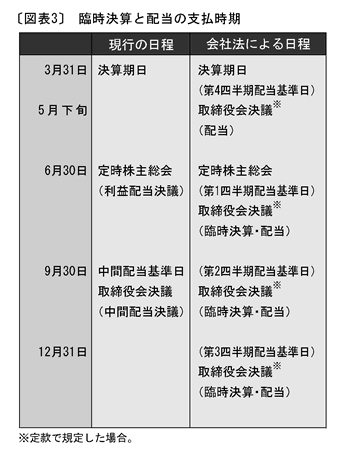
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















