解説記事2006年06月26日 【会社法関連解説】 会社法の施行に伴う商業・法人登記関係政省令の改正の要点(3)(2006年6月26日号・№168)
解説
会社法の施行に伴う
商業・法人登記関係政省令の改正の要点(3)
法務省民事局商事課法規係長 西田淳二
法務省民事局商事課法規係員 吉田一作
Ⅲ 改正省令による改正点
1 商登規の一部改正(承前)
(3)一部の支配人についての登記事項証明書
旧商登法では、会社支配人区の一部事項証明書を請求した場合は、会社支配人区全体が一部事項証明書中に記載されるが、会社法では、本店所在地において当該会社全部の支配人の登記がされるため、ある支配人1人の証明書を取得したい場合も会社支配人区全体の証明書を請求せざるを得ず、証明書の枚数が必要以上に多くなって、登記手数料の点で利用者に過重な負担をかけることとなりかねない。
そこで、会社支配人区のうち一部の支配人を選択して一部事項証明書を作成することが可能とされた(商登規30条2項)。この証明書の申請書には、当該支配人の氏名を記載するものとされた(商登規19条1項4号)。
(4)添付書面に関する改正(商登規61条)
株式会社及び合同会社の登記の添付書面について、次のとおりとされたが、取扱いが変更となるのは、④から⑥までである。
① 総株主の同意書に関する規定の位置(1項)
総株主の同意を証する書面については、商登法46条1項に規定されることとなったため、旧商登規80条1項から削除された。
② 取締役の就任承諾書の印鑑に係る印鑑証明書の添付(2項、3項)
これまでの制度では、有限会社については、原則として取締役が各自会社を代表するとされていたため(有限会社法27条)、各取締役の就任承諾書の印鑑について市区町村長の印鑑証明書が必要であり、定款、定款に基づく互選又は社員総会で代表取締役を定めても、代表取締役としての就任承諾書の印鑑についての印鑑証明書は不要とされていた。
一方、株式会社については、取締役会により選任された代表取締役が会社を代表するとされていたため(旧商法261条)、代表取締役の就任承諾書の印鑑に限り、市区町村長の印鑑証明書が必要とされていた。
会社法において株式会社と有限会社が一体化されたことに伴い、商登規61条2項、3項において取締役会を設置していない場合と設置している場合とに分けて、これまでの取扱い(旧商登規80条2項、93条)を維持することとされた。
すなわち、取締役会が設置されていない会社において、株主総会で選任されたすべての取締役は、その就任承諾書に市区町村長が作成した証明書に係る印鑑を押印することを要し、定款に基づく取締役の互選等により代表取締役が定められた場合であっても、当該代表取締役の就任承諾書には、市区町村長が作成した証明書に係る印鑑を押印する必要はない。
③ 代表者の選定を証する書面の印鑑に係る印鑑証明書の添付(4項)
会社法において株式会社と有限会社が一体化されたことに伴い、代表取締役について、株主総会で選定される場合が生ずるため(会社法349条3項)、添付書面として、株主総会議事録が追加して規定された。さらに種類株主総会において取締役を選任することが可能であるため(会社法108条1項9号)、種類株主総会の議事録についても併せて規定されている。
代表者の選定に関する株主総会及び種類株主総会議事録については、従前の有限会社の社員総会の議事録と同様に、議長及び出席取締役が当該議事録に押印した印鑑について市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(商登規61条4項1号)。
なお、定款に基づき取締役の互選により選定する場合が規定され(会社法349条3項)、この場合は取締役の互選を証する書面に押印した印鑑について市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(商登規61条4項2号)が、これも現行有限会社と同様である。
④ 資本金の額の計上に関する書面(5項)
株式会社の資本金の額は、会社法に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に払込み又は給付をした財産の額の2分の1以上とされ(会社法445条1項、2項)、払込み又は給付された財産の額は会社計算規則74条の規定等に従って計算を行った額とされた。
そのため、実際に銀行等に払い込まれた額等(払込金保管証明書等に記載された額)のみでは適正に資本金の額が計上されているかを確認することができないところ、適正な計算書類の作成及び開示が債権者保護の観点から重要であることを踏まえ、会社の設立の登記又は資本金の額の変更の登記の際には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計算されたことを証する書面の添付を要するとされた。
この規定は、準備金等の資本組入れの場合における商登法69条に規定する資本準備金や剰余金の額が計上されていたことを証する書面又は吸収合併による変更の登記の場合における商登法80条4号等に規定する資本金の額が会社法445条の規定に従って計上されたことを証する書面と同種のもので、設立の登記又は資本金の増加若しくは減少による変更の登記のすべて(商登法に規定のあるものを除く)について適用がある。
この書面は、代表者の作成に係る証明書(例えば、設立の登記にあっては、会社計算規則74条1項1号イからハまで及び2号の額又はその概算額を示す等の方法により、資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを確認することができるもの)であって、登記所に届け出た印鑑を押印したもので足りる。
なお、この規定は、合同会社についても準用される(商登規92条)。
⑤ 分配可能額又は欠損の額が存在することを証する書面(6項)
(ア)登記すべき事項につき一定の分配可能額が存在することを要するとき
商登規61条6項の「登記すべき事項につき一定の分配可能額が存在することを要するとき」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の取得の対価として新株予約権を交付する場合をいう。
この場合において、当該新株予約権に係る帳簿価額が分配可能額(会社法461条2項)を超えるときは、これらの株式を取得することができないとされた(会社法166条1項、170条5項、461条1項4号)ため、取得の対価として交付する新株予約権の発行の登記の申請に当たっては、この分配可能額が存在することを明らかにしなければならない。
(イ)登記すべき事項につき一定の欠損の額が存在することを要するとき
「登記すべき事項につき一定の欠損の額が存在することを要するとき」とは、会社法309条2項9号括弧書の場合をいう。
具体的には、資本金の額の減少をする場合には、株主総会の特別決議で行うこととされているが、定時株主総会において資本金の額を減少する場合であって、減少額が欠損の額を超えないときは、その決議要件は、普通決議で足りるとされた(会社法309条2項9号)ため、上記の普通決議による資本金の減少の登記の申請をする際には、欠損額が存在することを明らかにしなければならない。
なお、この書面も、④に準じた代表者の証明書で足りる。
⑥ 資本準備金の額の減少による資本金の額の増加の場合の添付書面(7項)
旧商法においては、取締役会の決議により資本準備金を減少し、資本金に組み入れるとされていたが(旧商法293条ノ3)、準備金を資本金に組み入れることは配当が受けにくくなるとの観点からみると株主にとって不利益となることから、資本準備金の額を減少させて、減少額の全部又は一部をもって資本金の額を増額することは株主総会の普通決議によるとされた(会社法448条1項)。
ただし、株式の発行と同時に当該準備金の額を減少する場合において、準備金の減少の効力が発生する日後の準備金の額が効力発生前の準備金の額を下回らないときは、取締役の決定(取締役会設置会社である場合には、取締役会の決議)で足りるとされている(会社法448条3項)。
これに伴い、資本準備金の額の減少による資本金の額の増加の登記を申請する場合において、会社法448条3項の適用がある場合(取締役の決定又は取締役会の決議により資本準備金の額を減少する場合)には、これに該当することを明らかにする書面を添付するとされた。
なお、この書面も、④に準じた代表者の証明書で足りる。
(5)本店移転の登記の取扱い
旧商登法では、支店所在地に本店移転をするときは、支店所在地登記所における既存の登記記録をそのまま継続して使用することとされていたが、改正後は支店所在地における登記事項が簡略化されたことから、支店所在地における既存の登記記録は閉鎖し、新たに登記記録を設けることとされた(商登法53条、商登規65条4項、5項)。
なお、旧商登法においても、新本店所在地における役員変更登記の際に任期を確認する必要があることから、新本店所在地においては任期の定めのある役員の就任年月日を登記していたところであるが、その取扱いが明文化された(商登規65条2項)。
(6)各種機関設計に関する登記の取扱い
会社法では、株式会社と有限会社が一体化されたことに伴い、会社として設けることが可能な機関構成が多様化された。
これに伴い、例えばある機関の定めを廃止した場合においては、併せて役員の変更や他の機関について変更すべき登記事項が生ずる場合がある。
改正後においては、このような同時に変更すべき登記について、登記官が職権では抹消せず、当事者の変更登記申請によるものと整理された。
これは、①会社の機関設計の変更はすべて定款変更によるところ、これを原因として変更登記申請をすることが会社法の理念に沿うこと、②登記官が職権で抹消することになると、会社の定款の記載と齟齬が生じ、会社が念頭に置いていない状態の登記がされるおそれがあること、③機関の廃止に伴い任期の満了する役員(会社法332条4項、336条4項等)について、他の事由による退任の登記と同様に申請によるとすることが整合的であること等の理由に基づくものである(必要となる登記申請の組合せの1例については、図表6・7参照)。このような観点から旧商登規82条、83条は、削除された。
一例を挙げると、監査役設置会社の定めを定款変更により廃止した場合は、当該効力発生日に監査役は退任することから(会社法336条4項1号)、監査役設置会社の定めの廃止の登記申請と併せて、監査役の退任登記を申請しなければならない。
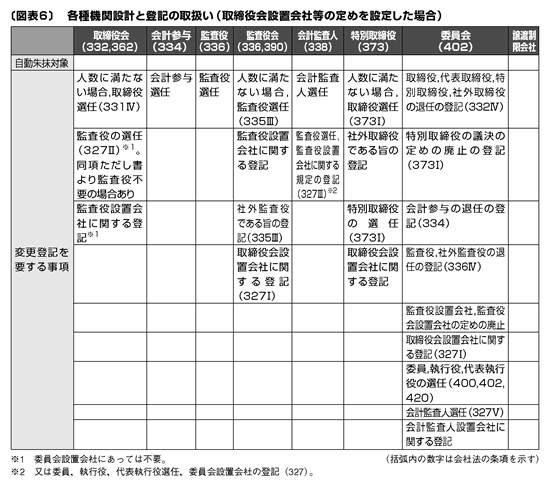
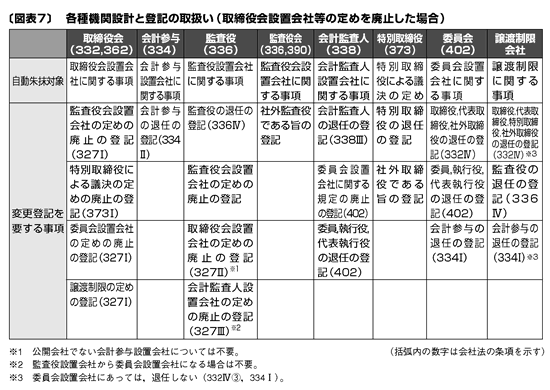
(7)その他
① 36条の2関係
今回の改正においては、会社法において法人が持分会社の代表者となることができる旨の改正がされたことに伴い、登記申請や印鑑届出等の場合において当該法人の登記事項証明書や登記所が作成する印鑑証明書を添付する規定が多数設けられている。
そこで、登記事項証明書及び登記所が作成する印鑑証明書の有効期限について、通則規定として商登規36条の2が設けられた。
なお、本条の規定は、商登法や商登規の明文の規定により要求される添付書面についてのみ適用がある。
② 70条関係
会社法においては、資本金の額と株式数との関係が連動しないものとされ、仮に株式の発行の無効判決が確定したとしても、資本金の額は減少しないとされた(会社計算規則48条2項)ため、株式の発行の無効の登記に当たり、資本金の額については回復しないものとされた。
③ 75条関係
特別清算終結の登記がされたときは、特別清算開始の登記に抹消する記号を記録しなければならないが、特別清算結了による特別清算終結の登記をしたときは、当該会社の登記記録が閉鎖されるので(商登規80条1項6号)、特段抹消する記号を記録することは要しないとされた(会社法938条、商登規75条)。
2 法人登記規則の一部改正
整備法により、各種法人のうち、一定のものについては、従たる事務所の所在地における登記事項が簡略化された(なお、それ以外の法人については、従たる事務所の登記事項は現行制度のままであるので、注意を要する)。
このように、従たる事務所の登記事項の在り方が2つの類型に分かれることとなったため、従たる事務所の登記事項が簡略化されない法人の管轄転属については、改正前の商登規11条と同内容の規定が新たに設けられた(法人登記規則8条)。
なお、従たる事務所の登記事項が簡略化される法人は、①信用金庫、②信用金庫連合会、③労働金庫、④労働金庫連合会、⑤相互会社、⑥特定目的会社、⑦農業協同組合、⑧農業協同組合連合会、⑨農事組合法人、⑩農業協同組合中央会、⑪漁業協同組合、⑫漁業生産組合、⑬漁業協同組合連合会、⑭水産加工業協同組合、⑮水産加工業協同組合連合会、⑯共済水産業協同組合連合会、⑰輸出水産業組合、⑱商工組合中央金庫、⑲中小企業等協同組合、⑳中小企業団体中央会、澡輸出組合、澤輸入組合、澹協業組合、濆商工組合、澪商工組合連合会、濟鉱工業技術研究組合である(改正省令附則7条2項参照)。 (了)
会社法の施行に伴う
商業・法人登記関係政省令の改正の要点(3)
法務省民事局商事課法規係長 西田淳二
法務省民事局商事課法規係員 吉田一作
Ⅲ 改正省令による改正点
1 商登規の一部改正(承前)
(3)一部の支配人についての登記事項証明書
旧商登法では、会社支配人区の一部事項証明書を請求した場合は、会社支配人区全体が一部事項証明書中に記載されるが、会社法では、本店所在地において当該会社全部の支配人の登記がされるため、ある支配人1人の証明書を取得したい場合も会社支配人区全体の証明書を請求せざるを得ず、証明書の枚数が必要以上に多くなって、登記手数料の点で利用者に過重な負担をかけることとなりかねない。
そこで、会社支配人区のうち一部の支配人を選択して一部事項証明書を作成することが可能とされた(商登規30条2項)。この証明書の申請書には、当該支配人の氏名を記載するものとされた(商登規19条1項4号)。
(4)添付書面に関する改正(商登規61条)
株式会社及び合同会社の登記の添付書面について、次のとおりとされたが、取扱いが変更となるのは、④から⑥までである。
① 総株主の同意書に関する規定の位置(1項)
総株主の同意を証する書面については、商登法46条1項に規定されることとなったため、旧商登規80条1項から削除された。
② 取締役の就任承諾書の印鑑に係る印鑑証明書の添付(2項、3項)
これまでの制度では、有限会社については、原則として取締役が各自会社を代表するとされていたため(有限会社法27条)、各取締役の就任承諾書の印鑑について市区町村長の印鑑証明書が必要であり、定款、定款に基づく互選又は社員総会で代表取締役を定めても、代表取締役としての就任承諾書の印鑑についての印鑑証明書は不要とされていた。
一方、株式会社については、取締役会により選任された代表取締役が会社を代表するとされていたため(旧商法261条)、代表取締役の就任承諾書の印鑑に限り、市区町村長の印鑑証明書が必要とされていた。
会社法において株式会社と有限会社が一体化されたことに伴い、商登規61条2項、3項において取締役会を設置していない場合と設置している場合とに分けて、これまでの取扱い(旧商登規80条2項、93条)を維持することとされた。
すなわち、取締役会が設置されていない会社において、株主総会で選任されたすべての取締役は、その就任承諾書に市区町村長が作成した証明書に係る印鑑を押印することを要し、定款に基づく取締役の互選等により代表取締役が定められた場合であっても、当該代表取締役の就任承諾書には、市区町村長が作成した証明書に係る印鑑を押印する必要はない。
③ 代表者の選定を証する書面の印鑑に係る印鑑証明書の添付(4項)
会社法において株式会社と有限会社が一体化されたことに伴い、代表取締役について、株主総会で選定される場合が生ずるため(会社法349条3項)、添付書面として、株主総会議事録が追加して規定された。さらに種類株主総会において取締役を選任することが可能であるため(会社法108条1項9号)、種類株主総会の議事録についても併せて規定されている。
代表者の選定に関する株主総会及び種類株主総会議事録については、従前の有限会社の社員総会の議事録と同様に、議長及び出席取締役が当該議事録に押印した印鑑について市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(商登規61条4項1号)。
なお、定款に基づき取締役の互選により選定する場合が規定され(会社法349条3項)、この場合は取締役の互選を証する書面に押印した印鑑について市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(商登規61条4項2号)が、これも現行有限会社と同様である。
④ 資本金の額の計上に関する書面(5項)
株式会社の資本金の額は、会社法に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に払込み又は給付をした財産の額の2分の1以上とされ(会社法445条1項、2項)、払込み又は給付された財産の額は会社計算規則74条の規定等に従って計算を行った額とされた。
そのため、実際に銀行等に払い込まれた額等(払込金保管証明書等に記載された額)のみでは適正に資本金の額が計上されているかを確認することができないところ、適正な計算書類の作成及び開示が債権者保護の観点から重要であることを踏まえ、会社の設立の登記又は資本金の額の変更の登記の際には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計算されたことを証する書面の添付を要するとされた。
この規定は、準備金等の資本組入れの場合における商登法69条に規定する資本準備金や剰余金の額が計上されていたことを証する書面又は吸収合併による変更の登記の場合における商登法80条4号等に規定する資本金の額が会社法445条の規定に従って計上されたことを証する書面と同種のもので、設立の登記又は資本金の増加若しくは減少による変更の登記のすべて(商登法に規定のあるものを除く)について適用がある。
この書面は、代表者の作成に係る証明書(例えば、設立の登記にあっては、会社計算規則74条1項1号イからハまで及び2号の額又はその概算額を示す等の方法により、資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを確認することができるもの)であって、登記所に届け出た印鑑を押印したもので足りる。
なお、この規定は、合同会社についても準用される(商登規92条)。
⑤ 分配可能額又は欠損の額が存在することを証する書面(6項)
(ア)登記すべき事項につき一定の分配可能額が存在することを要するとき
商登規61条6項の「登記すべき事項につき一定の分配可能額が存在することを要するとき」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の取得の対価として新株予約権を交付する場合をいう。
この場合において、当該新株予約権に係る帳簿価額が分配可能額(会社法461条2項)を超えるときは、これらの株式を取得することができないとされた(会社法166条1項、170条5項、461条1項4号)ため、取得の対価として交付する新株予約権の発行の登記の申請に当たっては、この分配可能額が存在することを明らかにしなければならない。
(イ)登記すべき事項につき一定の欠損の額が存在することを要するとき
「登記すべき事項につき一定の欠損の額が存在することを要するとき」とは、会社法309条2項9号括弧書の場合をいう。
具体的には、資本金の額の減少をする場合には、株主総会の特別決議で行うこととされているが、定時株主総会において資本金の額を減少する場合であって、減少額が欠損の額を超えないときは、その決議要件は、普通決議で足りるとされた(会社法309条2項9号)ため、上記の普通決議による資本金の減少の登記の申請をする際には、欠損額が存在することを明らかにしなければならない。
なお、この書面も、④に準じた代表者の証明書で足りる。
⑥ 資本準備金の額の減少による資本金の額の増加の場合の添付書面(7項)
旧商法においては、取締役会の決議により資本準備金を減少し、資本金に組み入れるとされていたが(旧商法293条ノ3)、準備金を資本金に組み入れることは配当が受けにくくなるとの観点からみると株主にとって不利益となることから、資本準備金の額を減少させて、減少額の全部又は一部をもって資本金の額を増額することは株主総会の普通決議によるとされた(会社法448条1項)。
ただし、株式の発行と同時に当該準備金の額を減少する場合において、準備金の減少の効力が発生する日後の準備金の額が効力発生前の準備金の額を下回らないときは、取締役の決定(取締役会設置会社である場合には、取締役会の決議)で足りるとされている(会社法448条3項)。
これに伴い、資本準備金の額の減少による資本金の額の増加の登記を申請する場合において、会社法448条3項の適用がある場合(取締役の決定又は取締役会の決議により資本準備金の額を減少する場合)には、これに該当することを明らかにする書面を添付するとされた。
なお、この書面も、④に準じた代表者の証明書で足りる。
(5)本店移転の登記の取扱い
旧商登法では、支店所在地に本店移転をするときは、支店所在地登記所における既存の登記記録をそのまま継続して使用することとされていたが、改正後は支店所在地における登記事項が簡略化されたことから、支店所在地における既存の登記記録は閉鎖し、新たに登記記録を設けることとされた(商登法53条、商登規65条4項、5項)。
なお、旧商登法においても、新本店所在地における役員変更登記の際に任期を確認する必要があることから、新本店所在地においては任期の定めのある役員の就任年月日を登記していたところであるが、その取扱いが明文化された(商登規65条2項)。
(6)各種機関設計に関する登記の取扱い
会社法では、株式会社と有限会社が一体化されたことに伴い、会社として設けることが可能な機関構成が多様化された。
これに伴い、例えばある機関の定めを廃止した場合においては、併せて役員の変更や他の機関について変更すべき登記事項が生ずる場合がある。
改正後においては、このような同時に変更すべき登記について、登記官が職権では抹消せず、当事者の変更登記申請によるものと整理された。
これは、①会社の機関設計の変更はすべて定款変更によるところ、これを原因として変更登記申請をすることが会社法の理念に沿うこと、②登記官が職権で抹消することになると、会社の定款の記載と齟齬が生じ、会社が念頭に置いていない状態の登記がされるおそれがあること、③機関の廃止に伴い任期の満了する役員(会社法332条4項、336条4項等)について、他の事由による退任の登記と同様に申請によるとすることが整合的であること等の理由に基づくものである(必要となる登記申請の組合せの1例については、図表6・7参照)。このような観点から旧商登規82条、83条は、削除された。
一例を挙げると、監査役設置会社の定めを定款変更により廃止した場合は、当該効力発生日に監査役は退任することから(会社法336条4項1号)、監査役設置会社の定めの廃止の登記申請と併せて、監査役の退任登記を申請しなければならない。
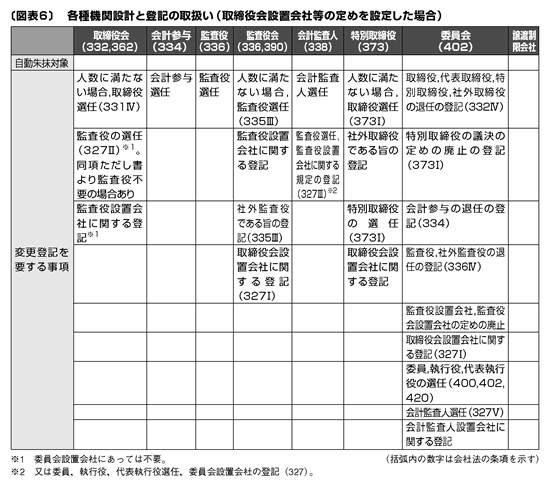
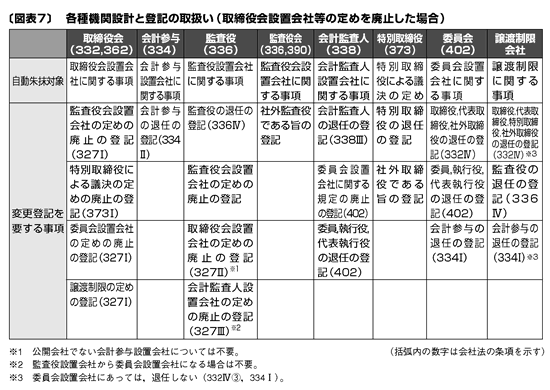
(7)その他
① 36条の2関係
今回の改正においては、会社法において法人が持分会社の代表者となることができる旨の改正がされたことに伴い、登記申請や印鑑届出等の場合において当該法人の登記事項証明書や登記所が作成する印鑑証明書を添付する規定が多数設けられている。
そこで、登記事項証明書及び登記所が作成する印鑑証明書の有効期限について、通則規定として商登規36条の2が設けられた。
なお、本条の規定は、商登法や商登規の明文の規定により要求される添付書面についてのみ適用がある。
② 70条関係
会社法においては、資本金の額と株式数との関係が連動しないものとされ、仮に株式の発行の無効判決が確定したとしても、資本金の額は減少しないとされた(会社計算規則48条2項)ため、株式の発行の無効の登記に当たり、資本金の額については回復しないものとされた。
③ 75条関係
特別清算終結の登記がされたときは、特別清算開始の登記に抹消する記号を記録しなければならないが、特別清算結了による特別清算終結の登記をしたときは、当該会社の登記記録が閉鎖されるので(商登規80条1項6号)、特段抹消する記号を記録することは要しないとされた(会社法938条、商登規75条)。
2 法人登記規則の一部改正
整備法により、各種法人のうち、一定のものについては、従たる事務所の所在地における登記事項が簡略化された(なお、それ以外の法人については、従たる事務所の登記事項は現行制度のままであるので、注意を要する)。
このように、従たる事務所の登記事項の在り方が2つの類型に分かれることとなったため、従たる事務所の登記事項が簡略化されない法人の管轄転属については、改正前の商登規11条と同内容の規定が新たに設けられた(法人登記規則8条)。
なお、従たる事務所の登記事項が簡略化される法人は、①信用金庫、②信用金庫連合会、③労働金庫、④労働金庫連合会、⑤相互会社、⑥特定目的会社、⑦農業協同組合、⑧農業協同組合連合会、⑨農事組合法人、⑩農業協同組合中央会、⑪漁業協同組合、⑫漁業生産組合、⑬漁業協同組合連合会、⑭水産加工業協同組合、⑮水産加工業協同組合連合会、⑯共済水産業協同組合連合会、⑰輸出水産業組合、⑱商工組合中央金庫、⑲中小企業等協同組合、⑳中小企業団体中央会、澡輸出組合、澤輸入組合、澹協業組合、濆商工組合、澪商工組合連合会、濟鉱工業技術研究組合である(改正省令附則7条2項参照)。 (了)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























