解説記事2006年07月03日 【税制改正関連解説】 平成17年度における法人税基本通達等の一部改正について 第6回(2006年7月3日号・№169)
実務解説
平成17年度における法人税基本通達等の一部改正について 第6回
浅井祥行
(5)会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入(承前)
【新設】(第3号に掲げる場合に該当しない場合)
12-3-5 法第59条第2項《会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入》に規定する「第3号に掲げる場合」に該当しない場合には、法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》又は第33条第3項《資産評定による評価損の損金算入》に規定する評価益の額又は評価損の額について法第25条第5項又は第33条第5項に規定する添付要件を満たさない場合(法第25条第6項又は第33条第6項の規定の適用があるものを除く。)が含まれるほか、法第25条第3項又は第33条第3項に規定する評定を行った資産のすべてが令第24条の2第4項各号に掲げる資産又は令第68条の2第3項に規定する資産に該当する場合も含まれることに留意する。
解説
1 法人について民事再生法の規定による再生手続開始の決定があった場合その他これに準ずる一定の事実が生じた場合において、青色欠損金額等の繰越控除制度の規定を適用する前に、期限切れ欠損金額(繰越欠損金額から青色欠損金額等を控除した金額をいう。以下同じ。)から優先的に損金の額に算入する規定(法59②三該当)が適用できるのは、その法人について民事再生法の規定による再生計画認可の決定があったことその他これに準ずる一定の事実が生じた場合において、その法人の有する資産の価額につき一定の評定を行い、かつ、その資産の評価損益の額につき益金算入の規定(法25③)又は損金算入の規定(法33③)の適用を受けるときに限られる。
したがって、該当する事実が生じた場合において、その法人の有する資産の価額につき一定の評定を行い、その資産の評価損益が生じるときであっても、その評価損益に関する明細の確定申告書への記載及び評価損益関係書類の添付要件を満たさないことにより、評価益の益金算入の規定(法25③)又は評価損の損金算入の規定(法33③)の適用がない場合(宥恕規定(法25⑥・33⑥)の適用があるものを除く。)には、期限切れ欠損金額から優先的に損金の額に算入する規定(法59②三該当)が適用できないことになる。
本通達の前段において、このことを明らかにしている。
2 また、その資産の評価損益につき評価益の益金算入の規定(法25③)又は評価損の損金算入の規定(法33③)の適用を受けるに当たっては、次に掲げる資産は対象資産から除かれている(法令24の2④)。
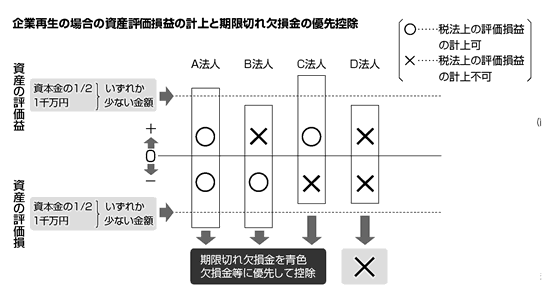
イ 該当する事実が生じた日の属する事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度等(以下「前5年内事業年度等」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産
(イ)法人税法第42条第1項、第2項、第5項又は第6項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
(ロ)法人税法第44条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
(ハ)法人税法第45条第1項、第2項、第5項又は第6項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
(ニ)法人税法第46条第1項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
(ホ)法人税法第47条第1項、第2項、第5項又は第6項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
(ヘ)法人税法第49条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
(ト)法人税法第81条の3第1項((イ)から(ヘ)までに掲げる規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)
(チ)租税特別措置法第67条の4第1項若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第9項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)
(リ)租税特別措置法第68条の102第1項若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第10項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第11項において準用する場合を含む。)
ロ 売買目的有価証券
ハ 償還有価証券
ニ 資産を一定の単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とその帳簿価額との差額がその資産を有する法人の資本等の金額の2分の1に相当する金額と1千万円とのいずれか少ない金額に満たない場合のその資産
(注)前5年内事業年度等においてイに掲げる規定の適用を受けた固定資産(イの減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、上記の「資産の価額とその帳簿価額との差額」は、その前5年内事業年度等においてイに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額となる。
したがって、その法人の有する資産の価額につき一定の評定を行い、その資産の評価損益が生じる場合であっても、それらの資産のすべてが上記イからニまでに掲げる資産のいずれかに該当するときは、それらの資産の評価損益につき評価益の益金算入の規定(法25③)又は評価損の損金算入の規定(法33③)の適用がないのであるから、当然のことながら期限切れ欠損金から優先的に損金の額に算入する規定(法59②三該当)を適用することができない。
本通達の後段において、このことを明らかにしている。
3 なお、連結納税制度においても、同様の通達(連基通11-2-5)を定めている。
(6)特殊な団体の損益
【新設】(任意組合等の組合事業から生ずる利益等の帰属)
14-1-1 任意組合等において営まれる事業(以下14-1-2までにおいて「組合事業」という。)から生ずる利益金額又は損失金額については、各組合員に直接帰属することに留意する。
(注)任意組合等とは、民法第667条第1項に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約により成立する組合並びに外国におけるこれらに類するものをいう。以下14―1―2までにおいて同じ。
解説
1 本通達において、任意組合等とは、民法に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律に規定する有限責任事業組合契約により成立する組合並びに外国におけるこれらに類するものをいうことを明らかにした上で、その組合事業から生ずる利益等の帰属についての基本的な考え方を明らかにしている。
2 これらの任意組合等は、組合員同士の一種の契約関係であっていずれも法人格を有さず、法人税法上法人とみなされる人格のない社団等としての社団性や財団性を有するものではないことから、それ自体は納税義務の主体とはならない。
また、任意組合等においては、組合財産は組合員の共有(合有)に属していることに加え、損益分配割合の定め(その定めがない場合には出資割合)があることから組合収益の増加が各組合員の収益の増加として認識されること、さらに、各組合員は組合債務に対し直接責任を負うものとされていることなどから、組合事業から生ずる利益等は、各組合員に直接帰属することになる。
3 そこで、本通達において、任意組合等にあっては、税務上、各組合員(構成員)を直接納税義務者とするいわゆる構成員課税の適用を前提に、その組合事業から生ずる利益金額又は損失金額については、帰属主体たる各組合員に直接帰属する旨を留意的に明らかにしている。
4 なお、連結納税制度においても、同様の通達(連基通18-1-1)を定めている。
○ 民法(抄)
(組合契約)
第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 省略
○ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(抄)
(投資事業有限責任組合契約)
第三条 投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。
一 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに有限会社又は企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有
二 株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この項において同じ。)又は有限会社若しくは企業組合の持分の取得及び保有
三 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券(株式及び新株予約権を除き、同項第一号から第十号までに掲げる有価証券(株式及び新株予約権を除く。)に表示されるべき権利であって同条第二項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)のうち社債その他の事業者の資金調達に資するものとして政令で定めるもの(以下「指定有価証券」という。)の取得及び保有
四 事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有
五 事業者に対する金銭の新たな貸付け
六 事業者を相手方とする匿名組合契約(商法第五百三十五条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有
七 事業者の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有(これらの権利に関して利用を許諾することを含む。)
八 前各号の規定により投資事業有限責任組合(次号を除き、以下「組合」という。)がその株式、持分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業
九 投資事業有限責任組合若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資
十 前各号の事業に付随する事業であって、政令で定めるもの
十一 外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有であって、政令で定めるところにより、前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度において行うもの
十二 組合契約の目的を達成するため、政令で定める方法により行う業務上の余裕金の運用
2・3 省略
○ 有限責任事業組合契約に関する法律(抄)
(有限責任事業組合契約)
第三条 有限責任事業組合契約(以下「組合契約」という。)は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生ずる。
2・3 省略
【改正】(任意組合等の組合事業から受ける利益等の帰属の時期)
14-1-1の2 法人が組合員となっている組合事業に係る利益金額又は損失金額のうち分配割合に応じて利益の分配を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額(以下14―1―2までにおいて「帰属損益額」という。)は、たとえ現実に利益の分配を受け又は損失の負担をしていない場合であっても、当該法人の各事業年度の期間に対応する組合事業に係る個々の損益を計算して当該法人の当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
ただし、当該組合事業に係る損益を毎年1回以上一定の時期において計算し、かつ、当該法人への個々の損益の帰属が当該損益発生後1年以内である場合には、帰属損益額は、当該組合事業の計算期間を基として計算し、当該計算期間の終了の日の属する当該法人の事業年度の益金の額又は損金の額に算入するものとする。
(注)1 分配割合とは、組合契約により定める損益分配の割合又は民法第674条《組合員の損益分配の割合》、投資事業有限責任組合契約に関する法律第16条《民法の準用》及び有限責任事業組合契約に関する法律第33条《組合員の損益分配の割合》の規定による損益分配の割合をいう。以下14―1―2までにおいて同じ。
2 同業者の組織する団体で営業活動を行わないものは、この取扱いの適用はない。
解説
1 本通達において、組合員となっている組合事業
に係る利益等のうち利益の分配を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額について、各組合員に対する帰属の時期を明らかにしている。
2 任意組合等の組合事業から生ずる利益等については各組合員に直接帰属することを法人税基本通達14-1-1で明らかにしているが、この基本的な考え方からすれば、組合員となっている組合事業から利益の分配を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額(以下「帰属損益額」という。)は、各組合員の課税期間すなわち法人にあっては各事業年度に合わせてその期間の損益を計算すべきものである。
したがって、各組合員の帰属損益額は、原則として、組合員たる法人の各事業年度の期間に対応する組合事業に係る個々の損益を計算して、当該法人の当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入することになる。
なお、組合事業から生ずる利益等は、各組合員に直接帰属するものであるため、各組合員が現実の分配を受けているかどうかは問わない。
3 他方、組合事業から生ずる利益等の帰属の時期について上記の取扱いを徹底させることは、組合課税に関する基本的な考え方に立つものであるが、次の①及び②のいずれにも該当する場合には、実務上の事務負担に配慮し、組合事業の計算期間を基として帰属損益額を計算し、当該計算期間の終了の日の属する当該法人の事業年度の益金の額又は損金の額に算入するものとしている。
① 組合事業に係る損益を毎年1回以上一定の時期において計算すること。
② 法人への個々の損益の帰属が当該損益発生後1年以内であること。
したがって、組合事業の計算期間が異なる任意組合等を複数介在させ、当初の損益取引を行った任意組合等で発生した個々の損益が1年を超えて法人に帰属し、損益に対する課税が繰り延べられるような場合には、原則に立ち返って、当該法人の各事業年度の期間に対応する帰属損益額の計算を行うことになる。
本通達において、これらのことを明らかにしている。
4 なお、連結納税制度においても、同様の通達(連基通18-1-1の2)を定めており、同様の改正を行っている。
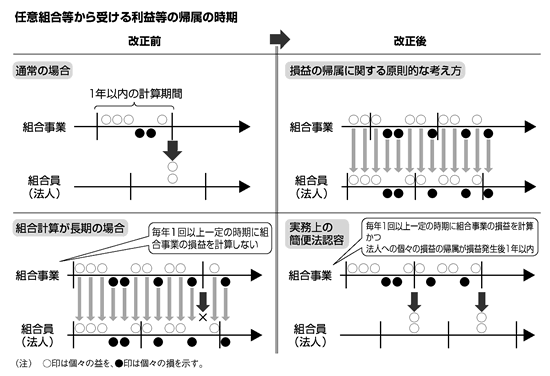
○ 民法(抄)
(組合員の損益分配の割合)
第六百七十四条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
○ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(抄)
(民法の準用)
第十六条 組合については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十八条(組合財産の共有)、第六百六十九条(金銭出資の不履行の責任)、第六百七十一条から第六百七十四条まで(委任の規定の準用、業務執行組合員の辞任及び解任、組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査並びに組合員の損益分配の割合)、第六百七十六条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)、第六百七十七条(組合の債務者による相殺の禁止)、第六百八十条(組合員の除名)、第六百八十一条(脱退した組合員の持分の払戻し)、第六百八十三条(組合の解散の請求)、第六百八十四条(組合契約の解除の効力)、第六百八十七条(組合員である清算人の辞任及び解任)及び第六百八十八条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)の規定を準用する。
○ 有限責任事業組合契約に関する法律(抄)
(組合員の損益分配の割合)
第三十三条 組合員の損益分配の割合は、総組合員の同意により、経済産業省令で定めるところにより別段の定めをした場合を除き、会計帳簿に記載された各組合員が履行した出資の価額に応じて定める。
平成17年度における法人税基本通達等の一部改正について 第6回
浅井祥行
(5)会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入(承前)
【新設】(第3号に掲げる場合に該当しない場合)
12-3-5 法第59条第2項《会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入》に規定する「第3号に掲げる場合」に該当しない場合には、法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》又は第33条第3項《資産評定による評価損の損金算入》に規定する評価益の額又は評価損の額について法第25条第5項又は第33条第5項に規定する添付要件を満たさない場合(法第25条第6項又は第33条第6項の規定の適用があるものを除く。)が含まれるほか、法第25条第3項又は第33条第3項に規定する評定を行った資産のすべてが令第24条の2第4項各号に掲げる資産又は令第68条の2第3項に規定する資産に該当する場合も含まれることに留意する。
解説
1 法人について民事再生法の規定による再生手続開始の決定があった場合その他これに準ずる一定の事実が生じた場合において、青色欠損金額等の繰越控除制度の規定を適用する前に、期限切れ欠損金額(繰越欠損金額から青色欠損金額等を控除した金額をいう。以下同じ。)から優先的に損金の額に算入する規定(法59②三該当)が適用できるのは、その法人について民事再生法の規定による再生計画認可の決定があったことその他これに準ずる一定の事実が生じた場合において、その法人の有する資産の価額につき一定の評定を行い、かつ、その資産の評価損益の額につき益金算入の規定(法25③)又は損金算入の規定(法33③)の適用を受けるときに限られる。
したがって、該当する事実が生じた場合において、その法人の有する資産の価額につき一定の評定を行い、その資産の評価損益が生じるときであっても、その評価損益に関する明細の確定申告書への記載及び評価損益関係書類の添付要件を満たさないことにより、評価益の益金算入の規定(法25③)又は評価損の損金算入の規定(法33③)の適用がない場合(宥恕規定(法25⑥・33⑥)の適用があるものを除く。)には、期限切れ欠損金額から優先的に損金の額に算入する規定(法59②三該当)が適用できないことになる。
本通達の前段において、このことを明らかにしている。
2 また、その資産の評価損益につき評価益の益金算入の規定(法25③)又は評価損の損金算入の規定(法33③)の適用を受けるに当たっては、次に掲げる資産は対象資産から除かれている(法令24の2④)。
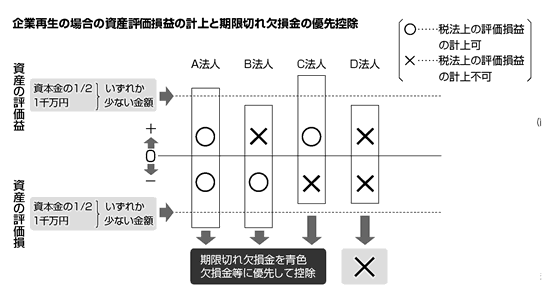
イ 該当する事実が生じた日の属する事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度等(以下「前5年内事業年度等」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産
(イ)法人税法第42条第1項、第2項、第5項又は第6項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
(ロ)法人税法第44条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
(ハ)法人税法第45条第1項、第2項、第5項又は第6項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
(ニ)法人税法第46条第1項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
(ホ)法人税法第47条第1項、第2項、第5項又は第6項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
(ヘ)法人税法第49条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
(ト)法人税法第81条の3第1項((イ)から(ヘ)までに掲げる規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)
(チ)租税特別措置法第67条の4第1項若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第9項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)
(リ)租税特別措置法第68条の102第1項若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第10項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第11項において準用する場合を含む。)
ロ 売買目的有価証券
ハ 償還有価証券
ニ 資産を一定の単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とその帳簿価額との差額がその資産を有する法人の資本等の金額の2分の1に相当する金額と1千万円とのいずれか少ない金額に満たない場合のその資産
(注)前5年内事業年度等においてイに掲げる規定の適用を受けた固定資産(イの減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、上記の「資産の価額とその帳簿価額との差額」は、その前5年内事業年度等においてイに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額となる。
したがって、その法人の有する資産の価額につき一定の評定を行い、その資産の評価損益が生じる場合であっても、それらの資産のすべてが上記イからニまでに掲げる資産のいずれかに該当するときは、それらの資産の評価損益につき評価益の益金算入の規定(法25③)又は評価損の損金算入の規定(法33③)の適用がないのであるから、当然のことながら期限切れ欠損金から優先的に損金の額に算入する規定(法59②三該当)を適用することができない。
本通達の後段において、このことを明らかにしている。
3 なお、連結納税制度においても、同様の通達(連基通11-2-5)を定めている。
(6)特殊な団体の損益
【新設】(任意組合等の組合事業から生ずる利益等の帰属)
14-1-1 任意組合等において営まれる事業(以下14-1-2までにおいて「組合事業」という。)から生ずる利益金額又は損失金額については、各組合員に直接帰属することに留意する。
(注)任意組合等とは、民法第667条第1項に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約により成立する組合並びに外国におけるこれらに類するものをいう。以下14―1―2までにおいて同じ。
解説
1 本通達において、任意組合等とは、民法に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律に規定する有限責任事業組合契約により成立する組合並びに外国におけるこれらに類するものをいうことを明らかにした上で、その組合事業から生ずる利益等の帰属についての基本的な考え方を明らかにしている。
2 これらの任意組合等は、組合員同士の一種の契約関係であっていずれも法人格を有さず、法人税法上法人とみなされる人格のない社団等としての社団性や財団性を有するものではないことから、それ自体は納税義務の主体とはならない。
また、任意組合等においては、組合財産は組合員の共有(合有)に属していることに加え、損益分配割合の定め(その定めがない場合には出資割合)があることから組合収益の増加が各組合員の収益の増加として認識されること、さらに、各組合員は組合債務に対し直接責任を負うものとされていることなどから、組合事業から生ずる利益等は、各組合員に直接帰属することになる。
3 そこで、本通達において、任意組合等にあっては、税務上、各組合員(構成員)を直接納税義務者とするいわゆる構成員課税の適用を前提に、その組合事業から生ずる利益金額又は損失金額については、帰属主体たる各組合員に直接帰属する旨を留意的に明らかにしている。
4 なお、連結納税制度においても、同様の通達(連基通18-1-1)を定めている。
○ 民法(抄)
(組合契約)
第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 省略
○ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(抄)
(投資事業有限責任組合契約)
第三条 投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。
一 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに有限会社又は企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有
二 株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。以下この項において同じ。)又は有限会社若しくは企業組合の持分の取得及び保有
三 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券(株式及び新株予約権を除き、同項第一号から第十号までに掲げる有価証券(株式及び新株予約権を除く。)に表示されるべき権利であって同条第二項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)のうち社債その他の事業者の資金調達に資するものとして政令で定めるもの(以下「指定有価証券」という。)の取得及び保有
四 事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有
五 事業者に対する金銭の新たな貸付け
六 事業者を相手方とする匿名組合契約(商法第五百三十五条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有
七 事業者の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有(これらの権利に関して利用を許諾することを含む。)
八 前各号の規定により投資事業有限責任組合(次号を除き、以下「組合」という。)がその株式、持分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業
九 投資事業有限責任組合若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資
十 前各号の事業に付随する事業であって、政令で定めるもの
十一 外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有であって、政令で定めるところにより、前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度において行うもの
十二 組合契約の目的を達成するため、政令で定める方法により行う業務上の余裕金の運用
2・3 省略
○ 有限責任事業組合契約に関する法律(抄)
(有限責任事業組合契約)
第三条 有限責任事業組合契約(以下「組合契約」という。)は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生ずる。
2・3 省略
【改正】(任意組合等の組合事業から受ける利益等の帰属の時期)
14-1-1の2 法人が組合員となっている組合事業に係る利益金額又は損失金額のうち分配割合に応じて利益の分配を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額(以下14―1―2までにおいて「帰属損益額」という。)は、たとえ現実に利益の分配を受け又は損失の負担をしていない場合であっても、当該法人の各事業年度の期間に対応する組合事業に係る個々の損益を計算して当該法人の当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
ただし、当該組合事業に係る損益を毎年1回以上一定の時期において計算し、かつ、当該法人への個々の損益の帰属が当該損益発生後1年以内である場合には、帰属損益額は、当該組合事業の計算期間を基として計算し、当該計算期間の終了の日の属する当該法人の事業年度の益金の額又は損金の額に算入するものとする。
(注)1 分配割合とは、組合契約により定める損益分配の割合又は民法第674条《組合員の損益分配の割合》、投資事業有限責任組合契約に関する法律第16条《民法の準用》及び有限責任事業組合契約に関する法律第33条《組合員の損益分配の割合》の規定による損益分配の割合をいう。以下14―1―2までにおいて同じ。
2 同業者の組織する団体で営業活動を行わないものは、この取扱いの適用はない。
解説
1 本通達において、組合員となっている組合事業
に係る利益等のうち利益の分配を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額について、各組合員に対する帰属の時期を明らかにしている。
2 任意組合等の組合事業から生ずる利益等については各組合員に直接帰属することを法人税基本通達14-1-1で明らかにしているが、この基本的な考え方からすれば、組合員となっている組合事業から利益の分配を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額(以下「帰属損益額」という。)は、各組合員の課税期間すなわち法人にあっては各事業年度に合わせてその期間の損益を計算すべきものである。
したがって、各組合員の帰属損益額は、原則として、組合員たる法人の各事業年度の期間に対応する組合事業に係る個々の損益を計算して、当該法人の当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入することになる。
なお、組合事業から生ずる利益等は、各組合員に直接帰属するものであるため、各組合員が現実の分配を受けているかどうかは問わない。
3 他方、組合事業から生ずる利益等の帰属の時期について上記の取扱いを徹底させることは、組合課税に関する基本的な考え方に立つものであるが、次の①及び②のいずれにも該当する場合には、実務上の事務負担に配慮し、組合事業の計算期間を基として帰属損益額を計算し、当該計算期間の終了の日の属する当該法人の事業年度の益金の額又は損金の額に算入するものとしている。
① 組合事業に係る損益を毎年1回以上一定の時期において計算すること。
② 法人への個々の損益の帰属が当該損益発生後1年以内であること。
したがって、組合事業の計算期間が異なる任意組合等を複数介在させ、当初の損益取引を行った任意組合等で発生した個々の損益が1年を超えて法人に帰属し、損益に対する課税が繰り延べられるような場合には、原則に立ち返って、当該法人の各事業年度の期間に対応する帰属損益額の計算を行うことになる。
本通達において、これらのことを明らかにしている。
4 なお、連結納税制度においても、同様の通達(連基通18-1-1の2)を定めており、同様の改正を行っている。
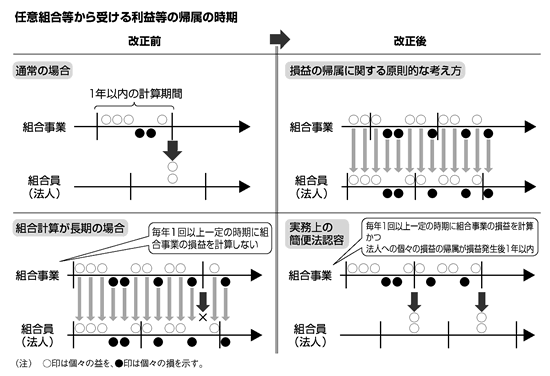
○ 民法(抄)
(組合員の損益分配の割合)
第六百七十四条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
○ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(抄)
(民法の準用)
第十六条 組合については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十八条(組合財産の共有)、第六百六十九条(金銭出資の不履行の責任)、第六百七十一条から第六百七十四条まで(委任の規定の準用、業務執行組合員の辞任及び解任、組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査並びに組合員の損益分配の割合)、第六百七十六条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)、第六百七十七条(組合の債務者による相殺の禁止)、第六百八十条(組合員の除名)、第六百八十一条(脱退した組合員の持分の払戻し)、第六百八十三条(組合の解散の請求)、第六百八十四条(組合契約の解除の効力)、第六百八十七条(組合員である清算人の辞任及び解任)及び第六百八十八条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)の規定を準用する。
○ 有限責任事業組合契約に関する法律(抄)
(組合員の損益分配の割合)
第三十三条 組合員の損益分配の割合は、総組合員の同意により、経済産業省令で定めるところにより別段の定めをした場合を除き、会計帳簿に記載された各組合員が履行した出資の価額に応じて定める。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























