解説記事2006年07月24日 【会計解説】 実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理社の会計処理に関する当面の取扱る当面の取扱い」について(2006年7月24日号・№172)
実務解説
実務対応報告第18号
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理社の会計処理に関する当面の取扱る当面の取扱い」について
企業会計基準委員会 専門研究員 清水夕起子
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(以下「実務対応報告」という。)を平成18年5月17日に公表した(脚注1)。
ここでは、実務対応報告の概要を紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りする。
Ⅱ.公表の経緯
平成9年6月改正の連結財務諸表原則においては、同一の環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一しなければならないとされており、この原則は、在外子会社の会計処理にも適用される。しかしながら、平成9年12月に公表された日本公認会計士協会監査委員会報告第56号「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」(以下「監査委員会報告第56号」という。)では、在外子会社の所在地国の会計基準において認められている会計処理が、企業集団として統一しようとする会計処理と異なる場合でも、当該会計処理が明らかに合理的でないと認められるときを除き、当面、親会社と子会社との間で会計処理を統一する必要はないものとされている。この現行の取扱いは、実務上の実行可能性に配慮するとともに、各国の採用している会計基準に多少なりとも差異があることを前提としている(脚注2)。
その後、退職給付、金融商品、固定資産の減損及び企業結合のそれぞれに係る会計基準が公表されるなど、我が国の会計基準は、国際財務報告基準(IFRSs)や米国会計基準といった国際的な会計基準と同等の水準まで整備がなされてきている。一方、欧州をはじめ多くの国々において、IFRSsが採用されつつあり、国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)とのコンバージェンス・プロジェクトにおいて、両会計基準間の相違は削減される方向で検討がなされている。
また、ASBJでは、平成16年10月以降、IASBとの間で両会計基準のコンバージェンスに向けた作業を進めており、平成17年3月の第1回会議において、その第1フェーズの検討項目(脚注3)の1つとして在外子会社の会計方針の統一が採り上げられた。
このような経緯により、ASBJでは連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理について検討を重ねた結果、現行実務における取扱いを見直し、当面の取扱いを改めることを定めた実務対応報告を公表することとしたものである。
なお、在外子会社の会計基準の統一は、平成17年7月に公表された欧州証券規制当局委員会(CESR)の同等性評価に関する技術的助言において、補完計算書が求められる項目となっている。
Ⅲ.実務対応報告の概要
1 原則的な取扱い
連結財務諸表作成においては同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社の採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一しなければならない(連結財務諸表原則第三三)。
原則的な取扱いによれば、連結財務諸表の作成上、在外子会社における同一の環境下で行われた同一の性質の取引等については、我が国の会計基準に基づき会計処理を統一することとなる。原則的な取扱いは、従来と変わるものではない。
2 当面の取扱い
(1)連結決算手続上のIFRSs又は米国会計基準に準拠して作成された財務諸表の利用
在外子会社の財務諸表が、IFRSs又は米国会計基準に準拠して作成されている場合には、当面の間、それらを連結決算手続上利用することができるものとする。(連結決算手続上利用するために内部的に作成された、いわゆる連結パッケージ等も含まれる。)
これは、国際的な会計基準間の相違点が縮小傾向にあるため、IFRSs又は米国会計基準に準拠して作成された在外子会社の財務諸表を基礎としても、わが国の会計基準の下での連結財務諸表が企業集団の財務状況の適切な表示を損なうものではないという見方や、それらに基づく財務諸表の利用であれば実務上の実行可能性が高いという見方を踏まえたものである。
(2)当面の取扱いに示されている修正項目
IFRSs又は米国会計基準に準拠して作成された在外子会社の財務諸表を連結決算上利用する場合であっても、次に示す項目については、当該修正額に重要性が乏しい場合を除き、連結決算手続上、当期純利益が適切に計上されるよう当該在外子会社の会計処理を修正しなければならない。
① のれんの償却
在外子会社において、IFRS第3号「企業結合」や米国財務会計基準書(SFAS)第142号「のれん及びその他の無形資産」を適用してのれんの償却を行っていない場合には、連結決算手続上、その計上後20年以内の効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却し、当該金額を当期の費用とするよう修正する。ただし、減損処理が行われたことにより、減損処理後の帳簿価額が規則的な償却を行った場合における金額を下回っている場合には、連結決算手続上、修正は不要であるが、それ以降、減損処理後の帳簿価額に基づき規則的な償却を行い、修正する必要があることに留意する。
なお、負ののれんについては、在外子会社での会計処理を必ずしも修正する必要はない(実務対応報告[設例1]参照)。
② 退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理
在外子会社において、退職給付会計における数理計算上の差異を国際会計基準(IAS)第19号「従業員給付」で認められている純資産の部に直接計上する会計処理方法を採用している場合には、連結決算手続上、当該金額を平均残存勤務期間以内の一定の年数で規則的に処理すること(発生した期に全額を処理する方法を継続して採用することも含む。)により、当期の損益とするよう修正する。
③ 研究開発費の支出時費用処理
在外子会社において、「研究開発費等に係る会計基準」の対象となる研究開発費に該当する開発活動に係る支出を、IAS第38号「無形資産」を適用して資産に計上している場合には、連結決算手続上、当該金額を支出時の費用とするよう修正する。
④ 投資不動産の時価評価及び固定資産の再評価
在外子会社において、IAS第40号「投資不動産」で認められている投資不動産の時価評価、又はIAS第16号「有形固定資産」及びIAS第38号「無形資産」で認められている固定資産の再評価を採用している場合には、連結決算手続上、取得原価を基礎として、正規の減価償却によって算定された減価償却費(減損処理を行う必要がある場合には、当該減損損失を含む。)を計上するよう修正する。
⑤ 会計方針の変更に伴う財務諸表の遡及的修正
在外子会社において、IAS第8号「会計方針、会計上の見積の変更と誤謬」やSFAS第154号「会計上の変更及び誤謬の修正」を適用して、会計方針の変更に伴い財務諸表の遡及的修正を行った場合には、連結決算手続上、当該遡及修正額を当期の損益とするよう修正する。
⑥ 少数株主損益の会計処理
IAS第1号「財務諸表の表示」を適用し、在外子会社における当期純利益に少数株主損益が含まれている(脚注4)場合には、連結決算手続上、当該少数株主損益を加減し、当期純利益が親会社持分相当額となるよう修正する。
なお、①~⑥以外の項目についても、明らかに合理的でないと認められる場合には、連結決算手続上で修正を行う必要があることに留意する必要がある。
これら、当面の取扱いに示されている修正項目は、IFRSs又は米国会計基準に従った会計処理が、当期純利益を測定する上での費用配分、当期純利益と株主資本との連繋及び投資の性格に応じた資産及び負債の評価など、我が国の会計基準に共通する考え方と乖離するものであり、一般に当該差異に重要性があるため、修正なしに連結財務諸表に反映することは合理的でなく、その修正に実務上の支障は少ないと考えられるものである。また、連結上の当期純損益に重要な影響を与える場合には修正しなければならないとしたのは、財務報告において提供される情報のなかで、特に重要なのは投資の成果を示す利益情報と考えられることによるものである。
現行のIFRSs及び米国会計基準を前提とした場合、明らかに合理的でないと認められる項目に該当するのは、以上の①~⑥の項目であると考えられる。しかしながら、今後、IFRSs又は米国会計基準が将来的に変化し得る中では、①~⑥の項目以外にも明らかに合理的でないと認められる項目が出てくる可能性はある。また、現時点では在外子会社における取引の規模が小さいなどの理由により、会計処理の差異に重要性がないとされているものが、将来において重要性がないとはいえなくなった際にも、①~⑥以外の明らかに合理的でないと認められる項目が出てくる可能性はある。そのような場合には、新たに上記の要素を満たすこととなり、「明らかに合理的でないと認められる場合」に該当すると思われる。
(3)その他の修正項目
実務対応報告では、上記当面の取扱いに示されている修正項目以外についても、継続して適用することを条件として、修正を行うことができるとされている。
その場合、重要性が増しているわけではないが、これまでと同一の会計事実について新たに修正を行う場合には、会計方針の変更として取り扱われることになることに留意する必要がある。
(4)変更点のまとめと連結決算手続
現行実務における取扱いから、実務対応報告の当面の取扱いへの変更点は、図表1のとおりである。
また、原則的な取扱いと当面の取扱いの連結決算手続を、従来(監査委員会報告第56号)及び実務対応報告に基づく連結決算手続、それぞれについて図表2及び図表3に図示した。
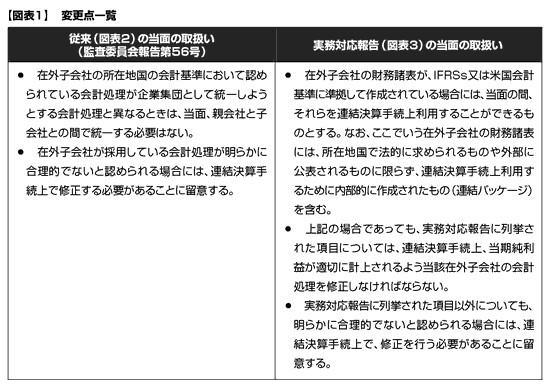
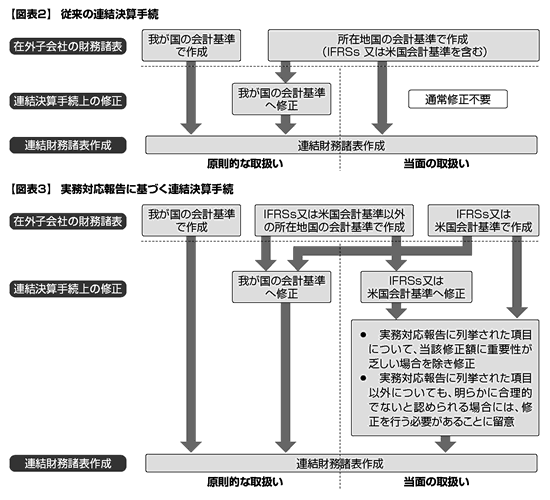
Ⅳ.適用時期等
1 適用時期
平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。早期適用も認められている。
2 適用初年度の会計処理
(1)過年度の税引後損益として会計処理しなければならない額
適用初年度の期首における在外子会社の貸借対照表上の資産または負債の残高のうち、実務対応報告の適用の結果、過年度の税引後損益として会計処理しなければならない額が生じた場合、その純額を、実務対応報告の適用初年度の期首の利益剰余金に加減する。
実務対応報告がこのような適用初年度の会計処理を定めたのは、1つには、IFRSs又は米国会計基準に基づく在外子会社の会計処理において、適用初年度の期首の利益剰余金を修正する場合があることによる。また、連結財務諸表原則改訂の際、支配力基準導入による連結範囲の変更があった場合、過去に遡って株式取得日の時価に基づき連結調整勘定を計算し、過年度償却費相当額を期首連結剰余金の増減高として計上する会計処理がこれまであったことなどによる(日本公認会計士協会「改訂連結原則の適用初年度における資本連結手続に関するQ&A」平成11年7月1日を参照)。
(2)過年度の評価・換算差額として会計処理しなければならない額
(1)と同様に、その他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定等、過年度の評価・換算差額等として会計処理しなければならない額は、その純額を、当該科目に加減することとなる。
(3)少数株主が存在する場合
在外子会社に少数株主が存在する場合には、在外子会社の過年度の税引後損益及び評価・換算差額として会計処理しなければならない額のうち、親会社に帰属しない部分は少数株主持分に加減することとなる。
(4)在外子会社の取得時の利益剰余金や評価・換算差額等に変動が生ずる場合
在外子会社の取得時の利益剰余金や評価・換算差額等に変動が生ずる場合でも、資本連結をやり直さず、在外子会社の取得時に算定されたのれんの金額については修正を行わないことができる。
(5)在外子会社がIFRSs又は米国会計基準を適用することにより連結子会社の範囲に修正が生じた場合
在外子会社がIFRSs又は米国会計基準を適用することにより、連結子会社の範囲に修正が生じた場合には、資本連結の修正に伴う利益剰余金、評価・換算差額等、少数株主持分に対する影響額は、それぞれ実務対応報告の適用初年度の期首利益剰余金、評価・換算差額等及び少数株主持分に加減する。この場合、資本連結の修正により生じたのれんは、取得時から償却し、過年度分は期首利益剰余金に計上することとなる(実務対応報告脚注5参照)。
開示に関しては、実務対応報告では特に示していない。しかしながら、以下のとおり、会計処理基準の差異の概要及び会計基準の変更に伴う会計方針の変更の開示対象となることに留意する必要がある。
Ⅴ.開 示
1 会計処理基準の差異の概要
実務対応報告の当面の取扱いを採用している場合には、これまでの実務対応報告適用前と同様に、連結財務諸表規則ガイドライン13-1-4及び中間連結ガイドライン10-1-4に定める、「会計処理基準の差異の概要」の注記の対象となることに留意する必要がある。
2 会計基準の変更に伴う連結財務諸表に与える影響額の開示
会計基準の変更に伴い会計方針が変更された場合には、現状では、変更を行った連結会計年度に、連結財務諸表規則第14条及び連結財務諸表規則ガイドライン14-2に基づき、会計基準の変更が、営業損益、経常損益、税引前損益、当期純損益又は連結財務諸表のその他の重要な項目に与える影響額を開示しなければならない。
これに対しては、実務対応報告の適用に伴う連結財務諸表に与える影響額の開示について、影響額の開示は実務上困難である、損益への影響額を適用初年度の会計処理にある期首の利益剰余金の影響額に代える、段階利益をひとつに絞る(税引前損益又は税引後損益)等の意見がある。
この会計基準の変更に伴う連結財務諸表に与える影響額の開示については、連結財務諸表規則ガイドラインに係ることであり、実務対応報告では言及されていない。(しみず・ゆきこ)
脚注
1 ASBJのホームページ( http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/zaigai/ )を参照。
2 この点については、日本公認会計士協会「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」に関するQ&AQ18参照。
3 IASBとのコンバージェンスに向けた共同プロジェクトにおける第1フェーズの当初の検討5項目は、①棚卸資産の評価基準(IAS第2号)、②セグメント情報(IAS第14号)、③関連当事者の開示(IAS第24号)、④在外子会社の会計基準の統一(IAS第27号)、⑤投資不動産(IAS第40号)である。なお、平成18年3月の会議において、差異のあるすべての会計基準について広く今後の取組みを明示する方式(全体像アプローチ)に移行することで合意した。全体像アプローチでは、上記5項目を含めた、2008年までに解決するか、少なくともその方向性を決めようとする項目が短期プロジェクトに、それ以外が長期プロジェクトに分類されている。
4 なお、米国財務会計基準審議会(FASB)から2005年6月に公表された公開草案「子会社の非支配持分の会計処理及び報告を含む、連結財務諸表-会計調査広報(ARB)第51号差替え」でも、同様の会計処理が提案されている。
実務対応報告第18号
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理社の会計処理に関する当面の取扱る当面の取扱い」について
企業会計基準委員会 専門研究員 清水夕起子
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(以下「実務対応報告」という。)を平成18年5月17日に公表した(脚注1)。
ここでは、実務対応報告の概要を紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りする。
Ⅱ.公表の経緯
平成9年6月改正の連結財務諸表原則においては、同一の環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一しなければならないとされており、この原則は、在外子会社の会計処理にも適用される。しかしながら、平成9年12月に公表された日本公認会計士協会監査委員会報告第56号「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」(以下「監査委員会報告第56号」という。)では、在外子会社の所在地国の会計基準において認められている会計処理が、企業集団として統一しようとする会計処理と異なる場合でも、当該会計処理が明らかに合理的でないと認められるときを除き、当面、親会社と子会社との間で会計処理を統一する必要はないものとされている。この現行の取扱いは、実務上の実行可能性に配慮するとともに、各国の採用している会計基準に多少なりとも差異があることを前提としている(脚注2)。
その後、退職給付、金融商品、固定資産の減損及び企業結合のそれぞれに係る会計基準が公表されるなど、我が国の会計基準は、国際財務報告基準(IFRSs)や米国会計基準といった国際的な会計基準と同等の水準まで整備がなされてきている。一方、欧州をはじめ多くの国々において、IFRSsが採用されつつあり、国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)とのコンバージェンス・プロジェクトにおいて、両会計基準間の相違は削減される方向で検討がなされている。
また、ASBJでは、平成16年10月以降、IASBとの間で両会計基準のコンバージェンスに向けた作業を進めており、平成17年3月の第1回会議において、その第1フェーズの検討項目(脚注3)の1つとして在外子会社の会計方針の統一が採り上げられた。
このような経緯により、ASBJでは連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理について検討を重ねた結果、現行実務における取扱いを見直し、当面の取扱いを改めることを定めた実務対応報告を公表することとしたものである。
なお、在外子会社の会計基準の統一は、平成17年7月に公表された欧州証券規制当局委員会(CESR)の同等性評価に関する技術的助言において、補完計算書が求められる項目となっている。
Ⅲ.実務対応報告の概要
1 原則的な取扱い
連結財務諸表作成においては同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社の採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一しなければならない(連結財務諸表原則第三三)。
原則的な取扱いによれば、連結財務諸表の作成上、在外子会社における同一の環境下で行われた同一の性質の取引等については、我が国の会計基準に基づき会計処理を統一することとなる。原則的な取扱いは、従来と変わるものではない。
2 当面の取扱い
(1)連結決算手続上のIFRSs又は米国会計基準に準拠して作成された財務諸表の利用
在外子会社の財務諸表が、IFRSs又は米国会計基準に準拠して作成されている場合には、当面の間、それらを連結決算手続上利用することができるものとする。(連結決算手続上利用するために内部的に作成された、いわゆる連結パッケージ等も含まれる。)
これは、国際的な会計基準間の相違点が縮小傾向にあるため、IFRSs又は米国会計基準に準拠して作成された在外子会社の財務諸表を基礎としても、わが国の会計基準の下での連結財務諸表が企業集団の財務状況の適切な表示を損なうものではないという見方や、それらに基づく財務諸表の利用であれば実務上の実行可能性が高いという見方を踏まえたものである。
(2)当面の取扱いに示されている修正項目
IFRSs又は米国会計基準に準拠して作成された在外子会社の財務諸表を連結決算上利用する場合であっても、次に示す項目については、当該修正額に重要性が乏しい場合を除き、連結決算手続上、当期純利益が適切に計上されるよう当該在外子会社の会計処理を修正しなければならない。
① のれんの償却
在外子会社において、IFRS第3号「企業結合」や米国財務会計基準書(SFAS)第142号「のれん及びその他の無形資産」を適用してのれんの償却を行っていない場合には、連結決算手続上、その計上後20年以内の効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却し、当該金額を当期の費用とするよう修正する。ただし、減損処理が行われたことにより、減損処理後の帳簿価額が規則的な償却を行った場合における金額を下回っている場合には、連結決算手続上、修正は不要であるが、それ以降、減損処理後の帳簿価額に基づき規則的な償却を行い、修正する必要があることに留意する。
なお、負ののれんについては、在外子会社での会計処理を必ずしも修正する必要はない(実務対応報告[設例1]参照)。
② 退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理
在外子会社において、退職給付会計における数理計算上の差異を国際会計基準(IAS)第19号「従業員給付」で認められている純資産の部に直接計上する会計処理方法を採用している場合には、連結決算手続上、当該金額を平均残存勤務期間以内の一定の年数で規則的に処理すること(発生した期に全額を処理する方法を継続して採用することも含む。)により、当期の損益とするよう修正する。
③ 研究開発費の支出時費用処理
在外子会社において、「研究開発費等に係る会計基準」の対象となる研究開発費に該当する開発活動に係る支出を、IAS第38号「無形資産」を適用して資産に計上している場合には、連結決算手続上、当該金額を支出時の費用とするよう修正する。
④ 投資不動産の時価評価及び固定資産の再評価
在外子会社において、IAS第40号「投資不動産」で認められている投資不動産の時価評価、又はIAS第16号「有形固定資産」及びIAS第38号「無形資産」で認められている固定資産の再評価を採用している場合には、連結決算手続上、取得原価を基礎として、正規の減価償却によって算定された減価償却費(減損処理を行う必要がある場合には、当該減損損失を含む。)を計上するよう修正する。
⑤ 会計方針の変更に伴う財務諸表の遡及的修正
在外子会社において、IAS第8号「会計方針、会計上の見積の変更と誤謬」やSFAS第154号「会計上の変更及び誤謬の修正」を適用して、会計方針の変更に伴い財務諸表の遡及的修正を行った場合には、連結決算手続上、当該遡及修正額を当期の損益とするよう修正する。
⑥ 少数株主損益の会計処理
IAS第1号「財務諸表の表示」を適用し、在外子会社における当期純利益に少数株主損益が含まれている(脚注4)場合には、連結決算手続上、当該少数株主損益を加減し、当期純利益が親会社持分相当額となるよう修正する。
なお、①~⑥以外の項目についても、明らかに合理的でないと認められる場合には、連結決算手続上で修正を行う必要があることに留意する必要がある。
これら、当面の取扱いに示されている修正項目は、IFRSs又は米国会計基準に従った会計処理が、当期純利益を測定する上での費用配分、当期純利益と株主資本との連繋及び投資の性格に応じた資産及び負債の評価など、我が国の会計基準に共通する考え方と乖離するものであり、一般に当該差異に重要性があるため、修正なしに連結財務諸表に反映することは合理的でなく、その修正に実務上の支障は少ないと考えられるものである。また、連結上の当期純損益に重要な影響を与える場合には修正しなければならないとしたのは、財務報告において提供される情報のなかで、特に重要なのは投資の成果を示す利益情報と考えられることによるものである。
現行のIFRSs及び米国会計基準を前提とした場合、明らかに合理的でないと認められる項目に該当するのは、以上の①~⑥の項目であると考えられる。しかしながら、今後、IFRSs又は米国会計基準が将来的に変化し得る中では、①~⑥の項目以外にも明らかに合理的でないと認められる項目が出てくる可能性はある。また、現時点では在外子会社における取引の規模が小さいなどの理由により、会計処理の差異に重要性がないとされているものが、将来において重要性がないとはいえなくなった際にも、①~⑥以外の明らかに合理的でないと認められる項目が出てくる可能性はある。そのような場合には、新たに上記の要素を満たすこととなり、「明らかに合理的でないと認められる場合」に該当すると思われる。
(3)その他の修正項目
実務対応報告では、上記当面の取扱いに示されている修正項目以外についても、継続して適用することを条件として、修正を行うことができるとされている。
その場合、重要性が増しているわけではないが、これまでと同一の会計事実について新たに修正を行う場合には、会計方針の変更として取り扱われることになることに留意する必要がある。
(4)変更点のまとめと連結決算手続
現行実務における取扱いから、実務対応報告の当面の取扱いへの変更点は、図表1のとおりである。
また、原則的な取扱いと当面の取扱いの連結決算手続を、従来(監査委員会報告第56号)及び実務対応報告に基づく連結決算手続、それぞれについて図表2及び図表3に図示した。
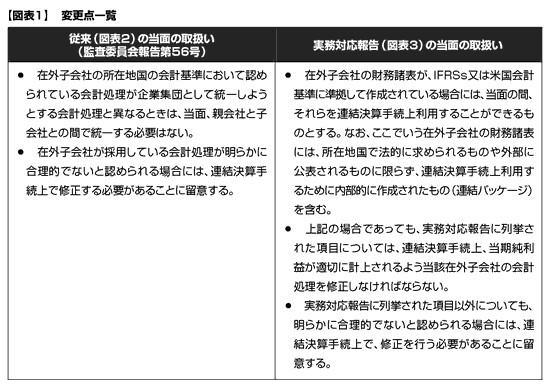
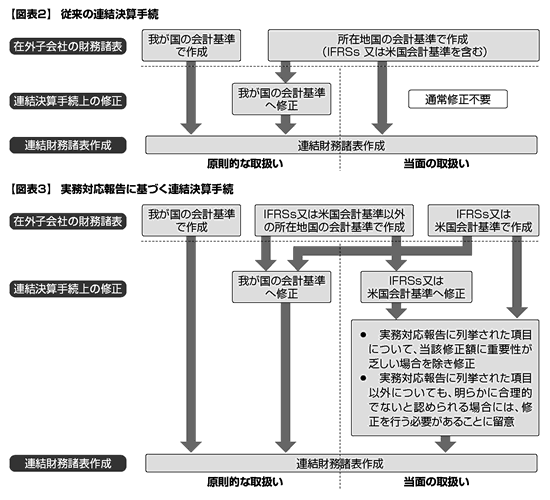
Ⅳ.適用時期等
1 適用時期
平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。早期適用も認められている。
2 適用初年度の会計処理
(1)過年度の税引後損益として会計処理しなければならない額
適用初年度の期首における在外子会社の貸借対照表上の資産または負債の残高のうち、実務対応報告の適用の結果、過年度の税引後損益として会計処理しなければならない額が生じた場合、その純額を、実務対応報告の適用初年度の期首の利益剰余金に加減する。
実務対応報告がこのような適用初年度の会計処理を定めたのは、1つには、IFRSs又は米国会計基準に基づく在外子会社の会計処理において、適用初年度の期首の利益剰余金を修正する場合があることによる。また、連結財務諸表原則改訂の際、支配力基準導入による連結範囲の変更があった場合、過去に遡って株式取得日の時価に基づき連結調整勘定を計算し、過年度償却費相当額を期首連結剰余金の増減高として計上する会計処理がこれまであったことなどによる(日本公認会計士協会「改訂連結原則の適用初年度における資本連結手続に関するQ&A」平成11年7月1日を参照)。
(2)過年度の評価・換算差額として会計処理しなければならない額
(1)と同様に、その他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定等、過年度の評価・換算差額等として会計処理しなければならない額は、その純額を、当該科目に加減することとなる。
(3)少数株主が存在する場合
在外子会社に少数株主が存在する場合には、在外子会社の過年度の税引後損益及び評価・換算差額として会計処理しなければならない額のうち、親会社に帰属しない部分は少数株主持分に加減することとなる。
(4)在外子会社の取得時の利益剰余金や評価・換算差額等に変動が生ずる場合
在外子会社の取得時の利益剰余金や評価・換算差額等に変動が生ずる場合でも、資本連結をやり直さず、在外子会社の取得時に算定されたのれんの金額については修正を行わないことができる。
(5)在外子会社がIFRSs又は米国会計基準を適用することにより連結子会社の範囲に修正が生じた場合
在外子会社がIFRSs又は米国会計基準を適用することにより、連結子会社の範囲に修正が生じた場合には、資本連結の修正に伴う利益剰余金、評価・換算差額等、少数株主持分に対する影響額は、それぞれ実務対応報告の適用初年度の期首利益剰余金、評価・換算差額等及び少数株主持分に加減する。この場合、資本連結の修正により生じたのれんは、取得時から償却し、過年度分は期首利益剰余金に計上することとなる(実務対応報告脚注5参照)。
開示に関しては、実務対応報告では特に示していない。しかしながら、以下のとおり、会計処理基準の差異の概要及び会計基準の変更に伴う会計方針の変更の開示対象となることに留意する必要がある。
Ⅴ.開 示
1 会計処理基準の差異の概要
実務対応報告の当面の取扱いを採用している場合には、これまでの実務対応報告適用前と同様に、連結財務諸表規則ガイドライン13-1-4及び中間連結ガイドライン10-1-4に定める、「会計処理基準の差異の概要」の注記の対象となることに留意する必要がある。
2 会計基準の変更に伴う連結財務諸表に与える影響額の開示
会計基準の変更に伴い会計方針が変更された場合には、現状では、変更を行った連結会計年度に、連結財務諸表規則第14条及び連結財務諸表規則ガイドライン14-2に基づき、会計基準の変更が、営業損益、経常損益、税引前損益、当期純損益又は連結財務諸表のその他の重要な項目に与える影響額を開示しなければならない。
これに対しては、実務対応報告の適用に伴う連結財務諸表に与える影響額の開示について、影響額の開示は実務上困難である、損益への影響額を適用初年度の会計処理にある期首の利益剰余金の影響額に代える、段階利益をひとつに絞る(税引前損益又は税引後損益)等の意見がある。
この会計基準の変更に伴う連結財務諸表に与える影響額の開示については、連結財務諸表規則ガイドラインに係ることであり、実務対応報告では言及されていない。(しみず・ゆきこ)
脚注
1 ASBJのホームページ( http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/zaigai/ )を参照。
2 この点については、日本公認会計士協会「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」に関するQ&AQ18参照。
3 IASBとのコンバージェンスに向けた共同プロジェクトにおける第1フェーズの当初の検討5項目は、①棚卸資産の評価基準(IAS第2号)、②セグメント情報(IAS第14号)、③関連当事者の開示(IAS第24号)、④在外子会社の会計基準の統一(IAS第27号)、⑤投資不動産(IAS第40号)である。なお、平成18年3月の会議において、差異のあるすべての会計基準について広く今後の取組みを明示する方式(全体像アプローチ)に移行することで合意した。全体像アプローチでは、上記5項目を含めた、2008年までに解決するか、少なくともその方向性を決めようとする項目が短期プロジェクトに、それ以外が長期プロジェクトに分類されている。
4 なお、米国財務会計基準審議会(FASB)から2005年6月に公表された公開草案「子会社の非支配持分の会計処理及び報告を含む、連結財務諸表-会計調査広報(ARB)第51号差替え」でも、同様の会計処理が提案されている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















