解説記事2006年10月02日 【ニュース特集】 公開買付制度の整備に係る政令等改正案を読み解く(2006年10月2日号・№181)
スケジュールでみる金融商品取引法 第3弾!
公開買付制度の整備に係る政令等改正案を読み解く
金融商品取引法へと改編される証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)と整備法案(平成18年法律第66号)が6月14日に公布され、開示書類の虚偽記載や不公正取引の罰則強化等に係る改正項目については7月4日、施行されている(特集第1弾・本誌167号4頁参照)。特集第2弾では、「公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」に施行される主な改正項目と見込まれる施行時期を紹介したところであるが(本誌172号4頁参照)、このたび、これらの改正項目に係る政令および関係内閣府令の改正案が公表された。法律の規定からは明らかでなかった見直しの細目や施行予定時期が示されている。今号では、これらの改正に関する施行予定時期を確認するとともに、公開買付制度の整備における細目を紹介する。
公開買付け・大量保有報告見直しの施行時期が判明
公開買付けなど「公布日から6月内」の施行日は?
「公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行される改正項目は、公開買付制度と大量保有報告制度の見直しに係るもの。公布日から6月内の政令で定める日が「平成18年12月13日まで」、1年内の政令で定める日が「平成19年6月13日まで」に相当することはお伝えしたとおりである。
公開買付制度においては、「公開買付規制の適用範囲の明確化」「投資者への情報提供の充実」「公開買付期間の伸長」「公開買付けの撤回等の柔軟化」「応募株式の全部買付けの一部義務化」「買付者間の公平性の確保」が図られる。
また、大量保有報告制度については、①特例報告制度が適用されない「事業支配目的」での保有が「重要提案行為等を行うこと」と明確化され、②特例報告の報告期限・頻度が短縮されるなどの改正が図られるほか、③大量保有報告書のEDINETによる提出が義務付けられることとなる。
EDINETによる提出義務化は来年4月から
これらについて、金融庁が10月13日までの意見募集に付した「証券取引法等の一部改正に伴う証券取引法施行令等の改正案」(9月13日付公表)では、公開買付制度の見直し全般、大量保有報告制度の見直し中①の部分が今年11月中に施行される予定であることが明らかにされた。大量保有報告制度に係る②は平成19年1月1日に、③は19年4月1日の施行がそれぞれ予定されている(図表1参照)。
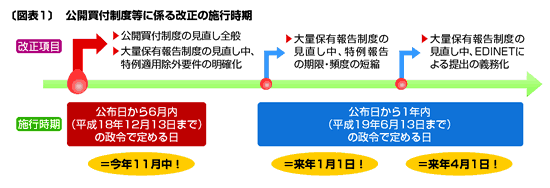
なお、改正案で改正方針が明らかにされたのは、「証券取引法施行令」(昭和40年政令第321号)(以下「施行令」という)、「株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令」(平成2年大蔵省令第36号)、「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」(平成2年大蔵省令第38号)(以下「他社株公開買付府令」という)、「発行者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」(平成6年大蔵省令)、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(昭和48年大蔵省令第5号)の1政令と4府令である。
改正案に基づく公開買付けの対象、開示の充実
公開買付規制の対象範囲
「公開買付規制の適用範囲の明確化」「買付者間の公平性の確保」の観点から、公開買付規制の対象範囲が見直され、①脱法的な態様の取引への対応、②買付者が競合する場合の手続の公正性・透明性確保のために、それぞれ改正法27条の2第1項において、
① 取引所内外の取引を組み合わせた、政令で定める6月内の期間内に政令で定める割合を超える株券等の取得を買付け・新規発行取得により行う場合で、買付け・新規発行取得後の株券等所有割合が3分の1超となるもの(同項4号)
② ある者の公開買付けが行われている場合に株券等所有割合が3分の1超の別の者により行われる買付けで、政令で定める6月内の期間内に政令で定める割合を超えてなされるもの(同項5号)が新たに規制対象と定められていた。
市場内外の取引を組み合わせた一連の取引を①により規制対象として公開買付けを義務付けるほか、第三者割当増資を受けることにより3分の1超となる場合も規制する。②は、公開買付け中のある者が規制に則って買付けを行う一方で、会社の支配権をめぐり競合する別の者が行う買付けが市場内で行われる場合については規制対象とはされていなかったことから、対応が図られたものである。
今回公表された改正案では、上記①・②における「政令で定める」内容が示されており、これらを踏まえ、改正法の施行後に公開買付規制の対象となる株券・新株予約権付社債券等の買付けその他の有償の譲受けを概観すると、図表2のとおりとなる(改正法27条の2第1項、施行令改正案6条・7条)(上記①・②については、図表2の④・⑤参照)。
〔図表2〕 政令案に基づく公開買付規制の対象
① 取引所有価証券市場外での買付け(店頭売買有価証券市場での店頭売買有価証券の取引を除く)で、買付け後の株券等所有割合が5%超となるもの(著しく少数の者から行う買付けとして、「株券等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前60日間に、取引所有価証券市場外において行った当該株券等の発行者の発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等を除く)の相手方の人数との合計が10名以下である場合」を除く)
② 取引所有価証券市場外での著しく少数の者から行う買付けとして、「株券等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前60日間に、取引所有価証券市場外において行った当該株券等の発行者の発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等を除く)の相手方の人数との合計が10名以下である場合」で、買付け後の株券等所有割合が3分の1超となるもの
③ 取引所有価証券市場での特定売買等(ToSTNeTなど)による買付けで、買付け後の株券等所有割合が3分の1超となるもの
④ 取引所有価証券市場内外での取引を組み合わせた、3月内に10%を超える株券等の取得を買付け・新規発行取得により行う場合であって、そのうち5%超が市場外での買付けにより行われ、買付け・新規発行取得後の株券等所有割合が3分の1超となるもの(①~③を除く)
⑤ ある者の公開買付けが行われている場合に株券等所有割合が3分の1超の別の者により行われる買付けで、ある者の公開買付期間中に5%を超えてなされるもの(①~④を除く)
⑥ その他①~⑤に準ずるものとして、株券等の取得を行う者の特別関係者が行う株券等の買付け・新規発行取得を当該株券等取得者が行うものとみなした場合
意見表明報告書は公告後10営業日以内に
「投資者への情報提供の充実」の観点から、公開買付けの対象会社による意見表明報告書の提出が義務付けられたほか、対象会社は、意見表明報告書において公開買付開始公告に記載された買付期間を延長することを請求する旨およびその理由を記載することもでき、いわば公開買付期間の延長請求という「公開買付期間の伸長」が可能とされている(改正法27条の10第1項、2項)。
公開買付期間の伸長については、そもそも暦日ベースであった「20日以上60日以内」が、「20日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日(以下この節及び第3章の2において「行政機関の休日」という。)の日数は、参入しない。以下この章において同じ。)以上で60日(行政機関の休日の日数は、参入しない。以下この章において同じ。)以内」へと、営業日ベースへの実質的な伸長も図られている(施行令改正案8条1項)。
意見表明報告書の提出義務付けにより、公開買付けに関する対象会社の意見や公開買付者に対する質問が開示されることとなるが、改正案によると、対象会社は公開買付開始公告の日から「10日(行政機関の休日の日数は、参入しない。)」(以下「10営業日」という)以内にこの書類を提出しなければならないこととされた(施行令改正案13条の2第1項)。
公開買付期間の延長請求は、当該買付け等の期間が「30営業日」未満の場合に限り、「30営業日」までの延長の請求が可能とされている(改正法27条の10第2項2号、施行令改正案9条の3第6項)。対象会社は、意見表明報告書提出期限の翌日までに「期間延長請求公告」を行うこととなり(改正法27条の10第4項)、公開買付者には、「30営業日」への延長が求められることとなる(改正法27条の10第3項、施行令改正案9条の3第6項)。
「期間延長請求公告」においては、
① 対象者の名称および所在地
② 法第27条の10第2項の規定により意見表明報告書に期間延長請求をする旨の記載をした旨
③ 法第27条の10第3項の規定による延長後の買付け等の期間が30営業日となる旨
④ 延長後の公開買付期間の末日
⑤ 公開買付けに関する事項のうち、(イ)公開買付者の氏名または名称および住所または所在地、
(ロ)買付け等を行う株券等の種類
を記載しなければならない(他社株公開買付府令改正案25条の2)。
意見表明報告書・公開買付届出書の記載が充実
意見表明報告書は現行法にも規定されているものであるが、改正案によると、施行後に求められる記載は、図表3のとおりとなっている(他社株公開買付府令改正案25条1項)。
〔図表3〕 府令案に基づく意見表明報告書の記載事項※
① 公開買付者の氏名または名称および住所または所在地
② 当該公開買付けに関する意見の内容および根拠
③ 当該意見を決定した取締役会の決議(委員会設置会社においては、会社法416条4項の規定による取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定)または役員会(投資信託及び投資法人に関する法律112条に規定する役員会をいう)の決議の内容
④ 当該発行者の役員が所有する当該公開買付けに係る株券等の数および当該株券等に係る議決権の数
⑤ 当該発行者の役員に対し公開買付者またはその特別関係者が利益の供与を約した場合には、その利益の内容
⑥ 当該発行者の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって当該発行者の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みを行っている場合には、その内容
⑦ 公開買付者に対する質問、延長請求およびその理由があるときは、当該事項
※ ①・②・⑤は改正なし、③・④は一部に改正あり、⑥・⑦は新設である。
また、公開買付届出書の記載ぶりも充実され、他社株公開買付府令の第2号様式「公開買付届出書」改正案によると、「第1 公開買付要項」中の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」における「(1)買付け等の期間」では、もともと買付け等の期間、公告日、公告掲載新聞名を開示するものとされていたところ、これらは次の①の項目で明らかにするものとされるとともに、
① 届出当初の期間
② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無
③ 期間延長の確認連絡先
を開示すべきものとされている。
①は、届出日現在における公開買付期間等を記載するもので、②は、その可能性がある場合に「法第27条の10第3項の規定により、公開買付対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、買付け等の期間は30営業日、公開買付期間は○月○日までとなります」といった詳細を記載する。この場合、延長の可能性がない場合には、「該当事項なし」と記載する。③では、連絡先のほか、確認受付時間等の記載が求められている(同様式「記載上の注意」参照)。
また、「(2)買付け等の価格」では「算定の経緯」を、さらに、「11 その他買付け等の条件及び方法」においては「(3)買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法」(買付価格の引下げについて、今号8頁参照)を示さなければならない。
「算定の経緯」欄では、「算定の際に第三者の意見を聴取した場合に、当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて買付価格を決定するに至った経緯を具体的に記載すること。公開買付者が対象者の経営者、経営者の依頼に基づき当該公開買付けを行う者又は対象者を子会社(会社法第2条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする会社その他対象者を実質的に支配する法人である場合であって、買付価格の公正性を担保するためのその他の措置を講じているときは、その具体的内容も記載すること」とされている(同様式「記載上の注意」参照)。
同様に「記載上の注意」をみると、「(5)買付け等の目的」をより具体的に記すような改正が図られており、次の記載がみられる(改正のあった項目のみを抜粋)。
a 支配権取得又は経営参加を目的とする場合には、支配権取得又は経営参加の方法及び支配権取得後の経営方針又は経営参加後の計画について具体的に記載すること。組織再編、企業集団の再編、解散、重要な財産の処分又は譲受け、多額の借財、代表取締役等の選解任、役員の構成の変更、配当・資本政策に関する重要な変更、その他対象者の経営方針に対して重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為を予定している場合には、その内容及び必要性も記載すること。
b 純投資又は政策投資を目的とする場合には、株券等を取得した後の当該株券等の保有方針、売買方針及び議決権の行使方針並びにそれらの理由を記載し、長期的な資本提携を目的とする政策投資として買付け等を行う場合には、その必要性を具体的に記載すること。
c 買付け等の後、当該株券等の発行者の株券等を更に取得する予定の有無、その理由及びその内容を具体的に記載すること。
d (現行bと同一)
e 買付け等の後、当該株券等の発行者の株券等が上場又は店頭登録の廃止となる見込みがある場合には、その旨及びその理由について具体的に記載すること。
新設された「対質問回答報告書」
意見表明報告書に公開買付者に対する質問が記載された場合、公開買付者には「対質問回答報告書」の提出が義務付けられている(改正法27条の10第11項)。
改正案によれば、対質問回答報告書は、意見表明報告書の送付を受けた日から「5営業日」以内に提出しなければならず(施行令改正案13条の2)、その具体的な記載については他社株公開買付府令の第8号様式として新設されることとなっている(図表4参照)。
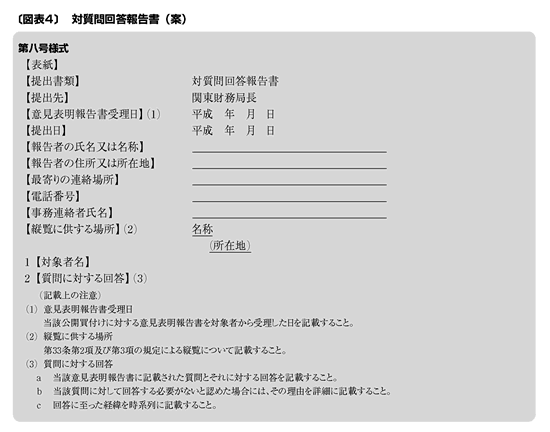
公開買付けにおける撤回・買付条件変更の柔軟化など
撤回では買収防衛策発動の場合など追加
法改正により、従来は原則として許されていなかった公開買付けにおける買付条件の変更を始め、公開買付けの撤回においても柔軟化が図られた。
具体的な場合については、その規定を政令に委任するものとされていたので注目されていたところであるが、改正案によると、公開買付けの撤回は、図表5のように柔軟化されることとなっている(改正法27条の11第1項、施行令改正案14条、他社株公開買付府令改正案26条2項)。
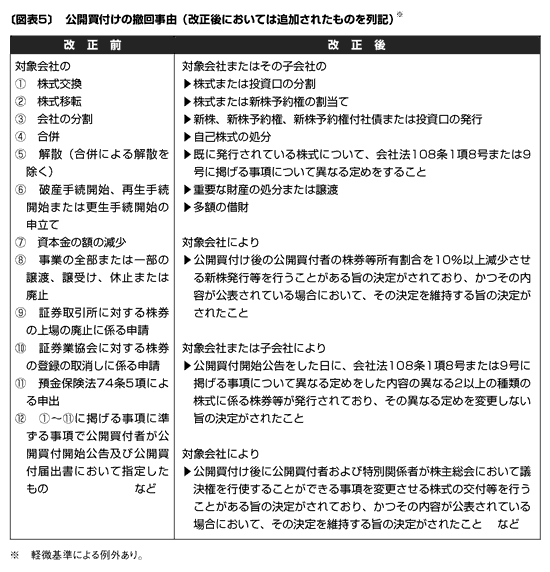
買付条件変更では株式等の無償割当てを規定
公開買付けにおける買付条件の変更等では、法改正により、買付価格の引下げの場合における「対象者が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたとき」に、一定の要件のもとで買付価格の引下げが認められることとなった(改正法27条の6第1項1号)。買付予定株式数の減少、買付期間の短縮といった買付条件の変更は依然容認されていない。
買付価格の引下げにおける「その他の政令で定める行為」は、改正案によると、①株式または投資口の分割、②株主に対する株式または新株予約権の割当てと規定される方針である(施行令改正案13条1項)。
全部買付けの義務化基準は「3分の2」に
公開買付開始公告等で条件を付した場合、公開買付け後の応募株券等の数の合計が買付予定数を上回った公開買付者には、従前、その超える部分の買付けをしないことが認められていた。
改正法は、公開買付成立後の所有割合が一定割合を超えた場合に限って全部買付義務を課す「一部義務化」を導入し、条件を付した場合であっても、公開買付け後の株券等所有割合が政令で定める割合を下回らない場合には、公開買付者に応募株券等の全部の買付けを義務付けることとした(改正法27条の13第4項)。
施行令改正案14条の2の2は、その割合を「3分の2」と規定し、買付け後の株券等所有割合が3分の2以上となる場合には、応募株券等の全部の買付義務が生じるものとしている。
また、買付け後の株券等所有割合が3分の2以上となるときは、公益または投資者保護に欠けることがないものとして定められた「株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘が行われないことに同意することにつき、当該株券等に係る種類株主総会の決議が行われている場合における当該株券等」「当該株券等の所有者が25名未満である場合であって、買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘が行われないことにつき、当該株券等のすべての所有者が同意している場合における当該株券等」を除くすべての株券等について公開買付けを行うものとされたほか(施行令改正案8条5項3号、他社株公開買付府令改正案5条3項・4項)、買付対象となるすべての株券等について同一の公開買付けによるものとされている(施行令改正案8条5項3号、他社株公開買付府令改正案5条5項)。
子会社株式買付けに係る公開買付けの義務化
議決権の50%超を所有する子会社株式を著しく少数の者から買い付ける場合、従来は公開買付けによる必要はなかったが、買付け後の株券等所有割合が3分の2以上となる場合には、全部買付義務の一部義務化が導入されたのと同様に零細株主の保護を図る必要があるため、公開買付けが義務付けられることとなった(施行令改正案6条の2第1項4号)。
株式交換等に係る開示充実も11月中に施行
改正案では、証券取引法等改正に伴う政令等改正と併せ、①株式交換等に係る開示の充実、②会社法に対応した開示事項の整備が内閣府令の改正により図られ、これらも今年11月中に施行される方針である(会社法に対応した有価証券報告書・半期報告書の開示事項の整備に関しては、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書および同日以後終了する中間会計期間に係る半期報告書から適用される)。改正の概要については、本誌180号15頁を参照されたい。
公開買付制度の整備に係る政令等改正案を読み解く
金融商品取引法へと改編される証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)と整備法案(平成18年法律第66号)が6月14日に公布され、開示書類の虚偽記載や不公正取引の罰則強化等に係る改正項目については7月4日、施行されている(特集第1弾・本誌167号4頁参照)。特集第2弾では、「公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」に施行される主な改正項目と見込まれる施行時期を紹介したところであるが(本誌172号4頁参照)、このたび、これらの改正項目に係る政令および関係内閣府令の改正案が公表された。法律の規定からは明らかでなかった見直しの細目や施行予定時期が示されている。今号では、これらの改正に関する施行予定時期を確認するとともに、公開買付制度の整備における細目を紹介する。
公開買付け・大量保有報告見直しの施行時期が判明
公開買付けなど「公布日から6月内」の施行日は?
「公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行される改正項目は、公開買付制度と大量保有報告制度の見直しに係るもの。公布日から6月内の政令で定める日が「平成18年12月13日まで」、1年内の政令で定める日が「平成19年6月13日まで」に相当することはお伝えしたとおりである。
公開買付制度においては、「公開買付規制の適用範囲の明確化」「投資者への情報提供の充実」「公開買付期間の伸長」「公開買付けの撤回等の柔軟化」「応募株式の全部買付けの一部義務化」「買付者間の公平性の確保」が図られる。
また、大量保有報告制度については、①特例報告制度が適用されない「事業支配目的」での保有が「重要提案行為等を行うこと」と明確化され、②特例報告の報告期限・頻度が短縮されるなどの改正が図られるほか、③大量保有報告書のEDINETによる提出が義務付けられることとなる。
EDINETによる提出義務化は来年4月から
これらについて、金融庁が10月13日までの意見募集に付した「証券取引法等の一部改正に伴う証券取引法施行令等の改正案」(9月13日付公表)では、公開買付制度の見直し全般、大量保有報告制度の見直し中①の部分が今年11月中に施行される予定であることが明らかにされた。大量保有報告制度に係る②は平成19年1月1日に、③は19年4月1日の施行がそれぞれ予定されている(図表1参照)。
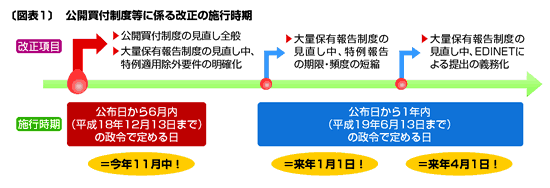
なお、改正案で改正方針が明らかにされたのは、「証券取引法施行令」(昭和40年政令第321号)(以下「施行令」という)、「株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令」(平成2年大蔵省令第36号)、「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」(平成2年大蔵省令第38号)(以下「他社株公開買付府令」という)、「発行者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」(平成6年大蔵省令)、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(昭和48年大蔵省令第5号)の1政令と4府令である。
改正案に基づく公開買付けの対象、開示の充実
公開買付規制の対象範囲
「公開買付規制の適用範囲の明確化」「買付者間の公平性の確保」の観点から、公開買付規制の対象範囲が見直され、①脱法的な態様の取引への対応、②買付者が競合する場合の手続の公正性・透明性確保のために、それぞれ改正法27条の2第1項において、
① 取引所内外の取引を組み合わせた、政令で定める6月内の期間内に政令で定める割合を超える株券等の取得を買付け・新規発行取得により行う場合で、買付け・新規発行取得後の株券等所有割合が3分の1超となるもの(同項4号)
② ある者の公開買付けが行われている場合に株券等所有割合が3分の1超の別の者により行われる買付けで、政令で定める6月内の期間内に政令で定める割合を超えてなされるもの(同項5号)が新たに規制対象と定められていた。
市場内外の取引を組み合わせた一連の取引を①により規制対象として公開買付けを義務付けるほか、第三者割当増資を受けることにより3分の1超となる場合も規制する。②は、公開買付け中のある者が規制に則って買付けを行う一方で、会社の支配権をめぐり競合する別の者が行う買付けが市場内で行われる場合については規制対象とはされていなかったことから、対応が図られたものである。
今回公表された改正案では、上記①・②における「政令で定める」内容が示されており、これらを踏まえ、改正法の施行後に公開買付規制の対象となる株券・新株予約権付社債券等の買付けその他の有償の譲受けを概観すると、図表2のとおりとなる(改正法27条の2第1項、施行令改正案6条・7条)(上記①・②については、図表2の④・⑤参照)。
〔図表2〕 政令案に基づく公開買付規制の対象
① 取引所有価証券市場外での買付け(店頭売買有価証券市場での店頭売買有価証券の取引を除く)で、買付け後の株券等所有割合が5%超となるもの(著しく少数の者から行う買付けとして、「株券等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前60日間に、取引所有価証券市場外において行った当該株券等の発行者の発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等を除く)の相手方の人数との合計が10名以下である場合」を除く)
② 取引所有価証券市場外での著しく少数の者から行う買付けとして、「株券等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前60日間に、取引所有価証券市場外において行った当該株券等の発行者の発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等を除く)の相手方の人数との合計が10名以下である場合」で、買付け後の株券等所有割合が3分の1超となるもの
③ 取引所有価証券市場での特定売買等(ToSTNeTなど)による買付けで、買付け後の株券等所有割合が3分の1超となるもの
④ 取引所有価証券市場内外での取引を組み合わせた、3月内に10%を超える株券等の取得を買付け・新規発行取得により行う場合であって、そのうち5%超が市場外での買付けにより行われ、買付け・新規発行取得後の株券等所有割合が3分の1超となるもの(①~③を除く)
⑤ ある者の公開買付けが行われている場合に株券等所有割合が3分の1超の別の者により行われる買付けで、ある者の公開買付期間中に5%を超えてなされるもの(①~④を除く)
⑥ その他①~⑤に準ずるものとして、株券等の取得を行う者の特別関係者が行う株券等の買付け・新規発行取得を当該株券等取得者が行うものとみなした場合
意見表明報告書は公告後10営業日以内に
「投資者への情報提供の充実」の観点から、公開買付けの対象会社による意見表明報告書の提出が義務付けられたほか、対象会社は、意見表明報告書において公開買付開始公告に記載された買付期間を延長することを請求する旨およびその理由を記載することもでき、いわば公開買付期間の延長請求という「公開買付期間の伸長」が可能とされている(改正法27条の10第1項、2項)。
公開買付期間の伸長については、そもそも暦日ベースであった「20日以上60日以内」が、「20日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日(以下この節及び第3章の2において「行政機関の休日」という。)の日数は、参入しない。以下この章において同じ。)以上で60日(行政機関の休日の日数は、参入しない。以下この章において同じ。)以内」へと、営業日ベースへの実質的な伸長も図られている(施行令改正案8条1項)。
意見表明報告書の提出義務付けにより、公開買付けに関する対象会社の意見や公開買付者に対する質問が開示されることとなるが、改正案によると、対象会社は公開買付開始公告の日から「10日(行政機関の休日の日数は、参入しない。)」(以下「10営業日」という)以内にこの書類を提出しなければならないこととされた(施行令改正案13条の2第1項)。
公開買付期間の延長請求は、当該買付け等の期間が「30営業日」未満の場合に限り、「30営業日」までの延長の請求が可能とされている(改正法27条の10第2項2号、施行令改正案9条の3第6項)。対象会社は、意見表明報告書提出期限の翌日までに「期間延長請求公告」を行うこととなり(改正法27条の10第4項)、公開買付者には、「30営業日」への延長が求められることとなる(改正法27条の10第3項、施行令改正案9条の3第6項)。
「期間延長請求公告」においては、
① 対象者の名称および所在地
② 法第27条の10第2項の規定により意見表明報告書に期間延長請求をする旨の記載をした旨
③ 法第27条の10第3項の規定による延長後の買付け等の期間が30営業日となる旨
④ 延長後の公開買付期間の末日
⑤ 公開買付けに関する事項のうち、(イ)公開買付者の氏名または名称および住所または所在地、
(ロ)買付け等を行う株券等の種類
を記載しなければならない(他社株公開買付府令改正案25条の2)。
意見表明報告書・公開買付届出書の記載が充実
意見表明報告書は現行法にも規定されているものであるが、改正案によると、施行後に求められる記載は、図表3のとおりとなっている(他社株公開買付府令改正案25条1項)。
〔図表3〕 府令案に基づく意見表明報告書の記載事項※
① 公開買付者の氏名または名称および住所または所在地
② 当該公開買付けに関する意見の内容および根拠
③ 当該意見を決定した取締役会の決議(委員会設置会社においては、会社法416条4項の規定による取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定)または役員会(投資信託及び投資法人に関する法律112条に規定する役員会をいう)の決議の内容
④ 当該発行者の役員が所有する当該公開買付けに係る株券等の数および当該株券等に係る議決権の数
⑤ 当該発行者の役員に対し公開買付者またはその特別関係者が利益の供与を約した場合には、その利益の内容
⑥ 当該発行者の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって当該発行者の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みを行っている場合には、その内容
⑦ 公開買付者に対する質問、延長請求およびその理由があるときは、当該事項
※ ①・②・⑤は改正なし、③・④は一部に改正あり、⑥・⑦は新設である。
また、公開買付届出書の記載ぶりも充実され、他社株公開買付府令の第2号様式「公開買付届出書」改正案によると、「第1 公開買付要項」中の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」における「(1)買付け等の期間」では、もともと買付け等の期間、公告日、公告掲載新聞名を開示するものとされていたところ、これらは次の①の項目で明らかにするものとされるとともに、
① 届出当初の期間
② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無
③ 期間延長の確認連絡先
を開示すべきものとされている。
①は、届出日現在における公開買付期間等を記載するもので、②は、その可能性がある場合に「法第27条の10第3項の規定により、公開買付対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、買付け等の期間は30営業日、公開買付期間は○月○日までとなります」といった詳細を記載する。この場合、延長の可能性がない場合には、「該当事項なし」と記載する。③では、連絡先のほか、確認受付時間等の記載が求められている(同様式「記載上の注意」参照)。
また、「(2)買付け等の価格」では「算定の経緯」を、さらに、「11 その他買付け等の条件及び方法」においては「(3)買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法」(買付価格の引下げについて、今号8頁参照)を示さなければならない。
「算定の経緯」欄では、「算定の際に第三者の意見を聴取した場合に、当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて買付価格を決定するに至った経緯を具体的に記載すること。公開買付者が対象者の経営者、経営者の依頼に基づき当該公開買付けを行う者又は対象者を子会社(会社法第2条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする会社その他対象者を実質的に支配する法人である場合であって、買付価格の公正性を担保するためのその他の措置を講じているときは、その具体的内容も記載すること」とされている(同様式「記載上の注意」参照)。
同様に「記載上の注意」をみると、「(5)買付け等の目的」をより具体的に記すような改正が図られており、次の記載がみられる(改正のあった項目のみを抜粋)。
a 支配権取得又は経営参加を目的とする場合には、支配権取得又は経営参加の方法及び支配権取得後の経営方針又は経営参加後の計画について具体的に記載すること。組織再編、企業集団の再編、解散、重要な財産の処分又は譲受け、多額の借財、代表取締役等の選解任、役員の構成の変更、配当・資本政策に関する重要な変更、その他対象者の経営方針に対して重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為を予定している場合には、その内容及び必要性も記載すること。
b 純投資又は政策投資を目的とする場合には、株券等を取得した後の当該株券等の保有方針、売買方針及び議決権の行使方針並びにそれらの理由を記載し、長期的な資本提携を目的とする政策投資として買付け等を行う場合には、その必要性を具体的に記載すること。
c 買付け等の後、当該株券等の発行者の株券等を更に取得する予定の有無、その理由及びその内容を具体的に記載すること。
d (現行bと同一)
e 買付け等の後、当該株券等の発行者の株券等が上場又は店頭登録の廃止となる見込みがある場合には、その旨及びその理由について具体的に記載すること。
新設された「対質問回答報告書」
意見表明報告書に公開買付者に対する質問が記載された場合、公開買付者には「対質問回答報告書」の提出が義務付けられている(改正法27条の10第11項)。
改正案によれば、対質問回答報告書は、意見表明報告書の送付を受けた日から「5営業日」以内に提出しなければならず(施行令改正案13条の2)、その具体的な記載については他社株公開買付府令の第8号様式として新設されることとなっている(図表4参照)。
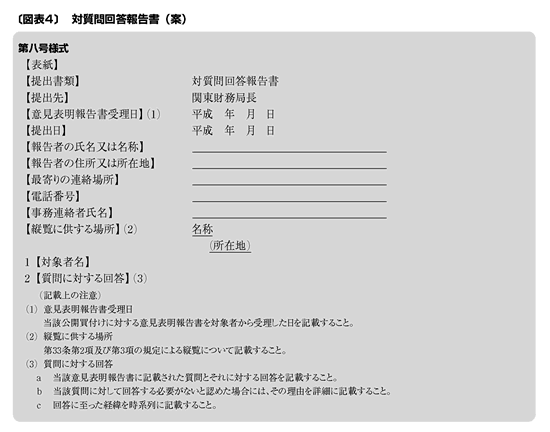
公開買付けにおける撤回・買付条件変更の柔軟化など
撤回では買収防衛策発動の場合など追加
法改正により、従来は原則として許されていなかった公開買付けにおける買付条件の変更を始め、公開買付けの撤回においても柔軟化が図られた。
具体的な場合については、その規定を政令に委任するものとされていたので注目されていたところであるが、改正案によると、公開買付けの撤回は、図表5のように柔軟化されることとなっている(改正法27条の11第1項、施行令改正案14条、他社株公開買付府令改正案26条2項)。
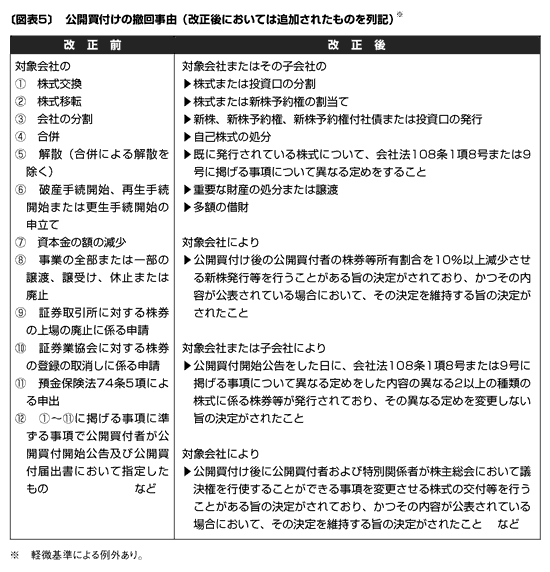
買付条件変更では株式等の無償割当てを規定
公開買付けにおける買付条件の変更等では、法改正により、買付価格の引下げの場合における「対象者が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたとき」に、一定の要件のもとで買付価格の引下げが認められることとなった(改正法27条の6第1項1号)。買付予定株式数の減少、買付期間の短縮といった買付条件の変更は依然容認されていない。
買付価格の引下げにおける「その他の政令で定める行為」は、改正案によると、①株式または投資口の分割、②株主に対する株式または新株予約権の割当てと規定される方針である(施行令改正案13条1項)。
全部買付けの義務化基準は「3分の2」に
公開買付開始公告等で条件を付した場合、公開買付け後の応募株券等の数の合計が買付予定数を上回った公開買付者には、従前、その超える部分の買付けをしないことが認められていた。
改正法は、公開買付成立後の所有割合が一定割合を超えた場合に限って全部買付義務を課す「一部義務化」を導入し、条件を付した場合であっても、公開買付け後の株券等所有割合が政令で定める割合を下回らない場合には、公開買付者に応募株券等の全部の買付けを義務付けることとした(改正法27条の13第4項)。
施行令改正案14条の2の2は、その割合を「3分の2」と規定し、買付け後の株券等所有割合が3分の2以上となる場合には、応募株券等の全部の買付義務が生じるものとしている。
また、買付け後の株券等所有割合が3分の2以上となるときは、公益または投資者保護に欠けることがないものとして定められた「株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘が行われないことに同意することにつき、当該株券等に係る種類株主総会の決議が行われている場合における当該株券等」「当該株券等の所有者が25名未満である場合であって、買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘が行われないことにつき、当該株券等のすべての所有者が同意している場合における当該株券等」を除くすべての株券等について公開買付けを行うものとされたほか(施行令改正案8条5項3号、他社株公開買付府令改正案5条3項・4項)、買付対象となるすべての株券等について同一の公開買付けによるものとされている(施行令改正案8条5項3号、他社株公開買付府令改正案5条5項)。
子会社株式買付けに係る公開買付けの義務化
議決権の50%超を所有する子会社株式を著しく少数の者から買い付ける場合、従来は公開買付けによる必要はなかったが、買付け後の株券等所有割合が3分の2以上となる場合には、全部買付義務の一部義務化が導入されたのと同様に零細株主の保護を図る必要があるため、公開買付けが義務付けられることとなった(施行令改正案6条の2第1項4号)。
株式交換等に係る開示充実も11月中に施行
改正案では、証券取引法等改正に伴う政令等改正と併せ、①株式交換等に係る開示の充実、②会社法に対応した開示事項の整備が内閣府令の改正により図られ、これらも今年11月中に施行される方針である(会社法に対応した有価証券報告書・半期報告書の開示事項の整備に関しては、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書および同日以後終了する中間会計期間に係る半期報告書から適用される)。改正の概要については、本誌180号15頁を参照されたい。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























