解説記事2006年11月27日 【巻頭特集】 新しい公開買付制度・大量保有報告制度と実務への影響(1)(2006年11月27日号・№188)
改正法による新制度がいよいよ施行へ!
新しい公開買付制度・大量保有報告制度と実務への影響(1)
森・濱田松本法律事務所 弁護士 中村 聡/弁護士 久保田修平
Ⅰ はじめに
平成18年6月14日に公布された「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)により、公開買付制度、大量保有報告制度および組織再編等に係る開示制度が整備され、また、これらの改正項目に係る次の政省令も改正されることとなった(以下、改正後の証券取引法(政省令を含む)を「新法」、改正前のものを「旧法」という)。
① 証券取引法施行令(以下「施行令」という。以下同様)
② 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(「大量保有府令」)
③ 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(「他社株公開買付府令」)
④ 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(「自社株公開買付府令」)
⑤ 企業内容等の開示に関する内閣府令(「開示府令」)
公開買付制度、大量保有報告制度および組織再編等に係る開示制度における改正の概要は、図表1に記載のとおりである。これらの改正の多くは、平成18年11月中(遅くとも平成18年12月13日まで)に施行が予定されている(一部の改正は平成19年1月1日または同年4月1日に施行が予定されている)。
本稿は、政省令を含めた改正点の概要を紹介するとともに、実務上のポイントを検討するものである。今回は改正点の概要について紹介し、各改正点の詳細および実務上のポイントの検討は次回以降に論ずることとする。
【図表1】改正点の概要
◎公開買付制度の見直し
強制的公開買付規制の対象となる取引の範囲の見直しおよび明確化
▼市場内外等の取引を組み合わせた急速な買付けを行う場合についての規制(新設)
▼他者の公開買付期間中に大株主が急速な買増しを行う場合についての規制(新設)
▼子会社株券等の特定買付け等の適用除外の範囲の見直し(変更)
▼株券等の所有者が少数である場合の特定買付け等の適用除外の範囲の見直し(変更)
株主・投資者への情報提供の充実化・熟慮期間の確保
▼意見表明報告書の提出義務化(新設)と開示の充実化(変更)
▼対象者の公開買付者に対する質問権と公開買付者の回答義務(新設)
▼公開買付期間の見直し(変更)と対象者の期間延長請求権(新設)
▼公開買付届出書における開示の充実化(変更)
その他
▼全部買付義務規制(新設)
▼公開買付けの撤回・買付条件の変更の柔軟化(変更)
◎大量保有報告制度の見直し
特例報告制度の見直し
▼特例報告制度に係る報告期限・頻度の短縮等(変更)
▼特例報告制度が適用されない重要提案行為等の明確化(変更)
▼機関投資家による10%超→10%未満保有となる場合の報告期限の短縮(変更)
その他
▼株券等保有割合の計算における共同保有者間の重複計上に係る見直し(変更)
▼対象有価証券の拡大(変更)
▼EDINET提出の義務化(新設)
◎組織再編等に係る開示制度の充実
▼臨時報告書の提出基準の引下げ(変更)
▼臨時報告書の提出時期の前倒し(変更)
▼臨時報告書の記載内容の拡充(変更)
▼会社法に対応した有価証券報告書等の開示事項の整備(変更)
Ⅱ 公開買付制度の改正の概要
1 公開買付規制の対象取引の範囲の見直しおよび明確化
強制的公開買付けの対象となる取引の範囲の見直しおよび明確化が図られ、①株券等の取得者またはその特別関係者が3か月以内に行う取引所市場内外の取引および新規発行取得を組み合わせた急速な買付け等の後に株券等所有割合が3分の1を超える場合に、公開買付規制の対象となることが明確化され(証券取引法(「法」)27条の2第1項4号・6号、施行令7条7項)、②第三者による公開買付けが行われている間に株券等所有割合が3分の1を超える大株主が急速な買増しを行う場合に、公開買付けが強制されることとなった(法27条の2第1項5号)。
また、③50%超の株券等所有割合(旧法においては、顕在的な議決権ベースであったのが、潜在的な議決権も含まれることとなった)を有する株主による特定買付け等は公開買付けの適用除外とされるが、当該特定買付け等の後の株券等所有割合が3分の2以上となる場合には、少数株主保護のため、公開買付けが義務付けられた(施行令6条の2第1項4号)。
さらに、④25名未満であるすべての株券等の所有者が公開買付けによらないことにつき同意している場合の特定買付け等も公開買付けの適用除外とされるが、その要件として、当該特定買付け等の後の株券等所有割合が3分の2未満であること、または当該買付け等の対象にならない株券等に係る種類株主総会の決議もしくは25名未満であるすべての所有者の同意があることが追加された(同項7号、他社株公開買付府令2条の5・2条の6)。
2 株主・投資者への情報提供の充実化、熟慮期間の確保
投資家に対する情報提供を充実させるために、公開買付開始公告から10営業日以内の対象者による意見表明報告書の提出が義務付けられ(法27条の10第1項、施行令13条の2第1項)、意見表明報告書においても買収防衛策を含む「会社の支配に関する基本方針に係る対応方針」等の記載が必要となり、開示内容が拡充された(他社株公開買付府令第4号様式)。
また、敵対的な公開買付けの場面において、従来証券取引所を通じたプレスリリースや自社のホームページで行われていた対象者による質問と公開買付者による回答については、対象者が意見表明報告書に公開買付者に対する質問を記載できることとなり、その場合、公開買付者は対質問回答報告書を提出することが義務付けられた(法27条の10第2項1号・11項)。
公開買付期間については、旧法では暦日ベースであったが、対象者の経営陣が対抗提案を検討し、株主・投資者等に対する十分な情報提供およびその熟慮期間を確保するため、新法では営業日ベース(行政機関の休日は算入しない)で公開買付開始公告日から起算して20日以上で60日以内の期間となった(施行令8条1項)。
また、対象者の意見表明報告書における一方的な請求により、最短期間を30営業日まで延長することができることとなった(法27条の10第2項2号・3項)。
公開買付届出書(他社株公開買付府令第2号様式)の記載事項の改正点のうち、実務上重要なものは次のとおりである。
① 「買付け等の目的」……支配権取得または経営参加を目的とする場合のその方法やその後の対象者の再編、多額の借財、役員の構成の変更、配当・資本政策の変更等、純投資・政策投資の場合の保有・売買・議決権行使方針等、追加取得の予定の有無、上場廃止の見込み
② 「算定の基礎」……算定根拠の具体化、最近取引の価格との相違等
③ 「算定の経緯」……第三者の意見を聴取したこと等
④ 公開買付者が経営者(MBOの場合)、親会社等一定の場合……開示事項・添付書類の追加
3 その他
改正の前後を問わず、公開買付者が公開買付開始公告等において買付予定数の上限を記載した場合には、その上限を超える応募株券等について買付義務を負わないが、新法では、このような上限を設定することができる場合を公開買付け後における株券等所有割合が3分の2未満の場合に限定した(法27条の13第4項1号)。
この結果、買付け等の後の株券等所有割合が3分の2以上となる場合については、応募株券等の全部について買付義務が生じることとなる。また、買付け等の後の株券等所有割合が3分の2以上となる場合には、対象者の発行するすべての株券等について、原則として同一の公開買付手続において勧誘を行う必要がある(施行令8条5項3号、他社株公開買付府令5条3項~5項)(図表2参照)。
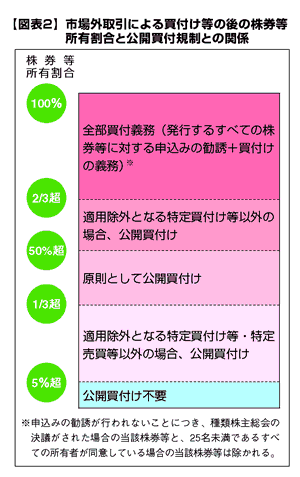
また、新法においては、公開買付けの撤回が、対象者だけではなく、その子会社の業務・財産に関する重要な変更等が生じた場合に認められたほか(法27条の11第1項)、各撤回事由についても株式分割、株式の無償割当て、新株・新株予約権の発行、重要な財産の処分・譲渡、多額の借財、既存の買収防衛策の維持等大幅な拡充が図られた(施行令14条1項)。
さらに、公開買付価格の引下げは、旧法では認められていなかったが、対象者による株式分割や株式、新株予約権等の無償割当てが行われる場合、一定の要件のもと公開買付価格の引下げが認められることとなった(法27条の6第1項1号、施行令13条1項、他社株公開買付府令19条1項)。
Ⅲ 大量保有報告制度の改正の概要
1 特例報告制度の見直し
通常の大量保有報告書・変更報告書の提出期限が5営業日であるのに対し、機関投資家に認められている特例報告制度の提出期限は、旧法では原則3か月ごと15日以内であった。しかし、株券等保有割合に係る開示をより迅速に行い、投資者等に対して一層の透明性を確保するため、新法ではおおむね毎月2回5営業日以内と改正された(法27条の26第1項~3項、施行令14条の8の2第2項)。
また、特例報告制度が適用されない「発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為」(重要提案行為等)が重要な財産の処分・譲受け、多額の借財、役員構成の重大な変更、組織再編、配当・資本政策の重要な変更等の場合と具体的に規定された(法27条の26第1項、施行令14条の8の2第1項、大量保有府令16条)。
機関投資家が、5%超保有した日(1%超以上増加した日)以降最初に到来する基準日から5営業日後までに重要提案行為等を行う場合には、当該重要提案行為等の5営業日前までに大量保有報告書・変更報告書の提出が義務付けられている(法27条の26第4項・5項、施行令14条の8の2第3項)。
さらに、10%超保有している機関投資家が、10%を下回る取引を行った場合、新法においては、特例報告ではなく、5営業日以内の一般報告を行う必要がある(法27条の26第2項3号)。
2 その他
その他の改正点としては、①貸株・借株取引等において、貸主および借主の双方において同一の株式について重複して株券等保有割合を計算する場合があるが、新法においては、共同保有者間においてかかる重複部分はネットアウトして株券等保有割合を計算すること(法27条の23第4項、施行令14条の6の2)、②対象有価証券として投資法人の発行する「投資証券」が加わったこと(法27条の23第1項、施行令14条の4第1項3号)、③EDINETによる大量保有報告書の提出が義務付けられたこと(法27条の30の2)が挙げられる。
Ⅳ 組織再編等に係る開示制度の改正の概要
新法においては、株式交換等の組織再編に係る臨時報告書による開示制度についての見直しが行われた(開示府令19条2項6号の2等)。
まず、開示を行うべき場合が拡充され、提出会社の最近の事業年度末日の純資産額の10%以上(旧法では30%以上)または提出会社の最近の事業年度の売上高の3%以上(旧法では10%以上)となる株式交換等を行う場合には臨時報告書の提出が必要となる。
臨時報告書の提出時期も「提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合」とされ、旧法の「株式交換に係る契約が締結された場合(これらの契約が締結されることが確実に見込まれ、かつ、その旨が公表された場合を含む。)」等に比べると、タイミングが早くなっている。
開示内容も、相手会社に係る最近3年間に終了した各事業年度の売上高・営業利益、大株主の名称等、株式交換等の比率の算定根拠等について記載するなどの拡充が図られた。
Ⅴ 改正の施行時期
公開買付制度、大量保有報告制度のうち「重要提案行為等」の明確化、組織再編に係る開示制度の充実については、平成18年11月中(遅くとも平成18年12月13日)より適用が開始される。
公開買付制度に関して、法27条の2第1項4号・5号は、施行後に開始する期間内における株券等の買付け等に新法が適用されるため(証券取引法等の一部を改正する法律附則7条2号・3号)、施行日前に行った買付け等については同規制が適用されない。
なお、有価証券報告書・半期報告書における会社法に対応した開示事項の整備については、施行日以降に終了する事業年度に係る有価証券報告書および同日以降に終了する中間会計期間に係る半期報告書から適用される。
その他、大量保有報告制度のうち、上記以外の点は平成19年1月1日(EDINETによる提出義務付けは平成19年4月1日)から施行される予定である。
(なかむら・さとし/くぼた・しゅうへい)
本稿は、Ⅰ①~⑤に掲げた政省令について、改正案に基づき、確定された政省令の公布前にご執筆いただいたものである。(編集部)
新しい公開買付制度・大量保有報告制度と実務への影響(1)
森・濱田松本法律事務所 弁護士 中村 聡/弁護士 久保田修平
Ⅰ はじめに
平成18年6月14日に公布された「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)により、公開買付制度、大量保有報告制度および組織再編等に係る開示制度が整備され、また、これらの改正項目に係る次の政省令も改正されることとなった(以下、改正後の証券取引法(政省令を含む)を「新法」、改正前のものを「旧法」という)。
① 証券取引法施行令(以下「施行令」という。以下同様)
② 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(「大量保有府令」)
③ 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(「他社株公開買付府令」)
④ 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(「自社株公開買付府令」)
⑤ 企業内容等の開示に関する内閣府令(「開示府令」)
公開買付制度、大量保有報告制度および組織再編等に係る開示制度における改正の概要は、図表1に記載のとおりである。これらの改正の多くは、平成18年11月中(遅くとも平成18年12月13日まで)に施行が予定されている(一部の改正は平成19年1月1日または同年4月1日に施行が予定されている)。
本稿は、政省令を含めた改正点の概要を紹介するとともに、実務上のポイントを検討するものである。今回は改正点の概要について紹介し、各改正点の詳細および実務上のポイントの検討は次回以降に論ずることとする。
【図表1】改正点の概要
◎公開買付制度の見直し
強制的公開買付規制の対象となる取引の範囲の見直しおよび明確化
▼市場内外等の取引を組み合わせた急速な買付けを行う場合についての規制(新設)
▼他者の公開買付期間中に大株主が急速な買増しを行う場合についての規制(新設)
▼子会社株券等の特定買付け等の適用除外の範囲の見直し(変更)
▼株券等の所有者が少数である場合の特定買付け等の適用除外の範囲の見直し(変更)
株主・投資者への情報提供の充実化・熟慮期間の確保
▼意見表明報告書の提出義務化(新設)と開示の充実化(変更)
▼対象者の公開買付者に対する質問権と公開買付者の回答義務(新設)
▼公開買付期間の見直し(変更)と対象者の期間延長請求権(新設)
▼公開買付届出書における開示の充実化(変更)
その他
▼全部買付義務規制(新設)
▼公開買付けの撤回・買付条件の変更の柔軟化(変更)
◎大量保有報告制度の見直し
特例報告制度の見直し
▼特例報告制度に係る報告期限・頻度の短縮等(変更)
▼特例報告制度が適用されない重要提案行為等の明確化(変更)
▼機関投資家による10%超→10%未満保有となる場合の報告期限の短縮(変更)
その他
▼株券等保有割合の計算における共同保有者間の重複計上に係る見直し(変更)
▼対象有価証券の拡大(変更)
▼EDINET提出の義務化(新設)
◎組織再編等に係る開示制度の充実
▼臨時報告書の提出基準の引下げ(変更)
▼臨時報告書の提出時期の前倒し(変更)
▼臨時報告書の記載内容の拡充(変更)
▼会社法に対応した有価証券報告書等の開示事項の整備(変更)
Ⅱ 公開買付制度の改正の概要
1 公開買付規制の対象取引の範囲の見直しおよび明確化
強制的公開買付けの対象となる取引の範囲の見直しおよび明確化が図られ、①株券等の取得者またはその特別関係者が3か月以内に行う取引所市場内外の取引および新規発行取得を組み合わせた急速な買付け等の後に株券等所有割合が3分の1を超える場合に、公開買付規制の対象となることが明確化され(証券取引法(「法」)27条の2第1項4号・6号、施行令7条7項)、②第三者による公開買付けが行われている間に株券等所有割合が3分の1を超える大株主が急速な買増しを行う場合に、公開買付けが強制されることとなった(法27条の2第1項5号)。
また、③50%超の株券等所有割合(旧法においては、顕在的な議決権ベースであったのが、潜在的な議決権も含まれることとなった)を有する株主による特定買付け等は公開買付けの適用除外とされるが、当該特定買付け等の後の株券等所有割合が3分の2以上となる場合には、少数株主保護のため、公開買付けが義務付けられた(施行令6条の2第1項4号)。
さらに、④25名未満であるすべての株券等の所有者が公開買付けによらないことにつき同意している場合の特定買付け等も公開買付けの適用除外とされるが、その要件として、当該特定買付け等の後の株券等所有割合が3分の2未満であること、または当該買付け等の対象にならない株券等に係る種類株主総会の決議もしくは25名未満であるすべての所有者の同意があることが追加された(同項7号、他社株公開買付府令2条の5・2条の6)。
2 株主・投資者への情報提供の充実化、熟慮期間の確保
投資家に対する情報提供を充実させるために、公開買付開始公告から10営業日以内の対象者による意見表明報告書の提出が義務付けられ(法27条の10第1項、施行令13条の2第1項)、意見表明報告書においても買収防衛策を含む「会社の支配に関する基本方針に係る対応方針」等の記載が必要となり、開示内容が拡充された(他社株公開買付府令第4号様式)。
また、敵対的な公開買付けの場面において、従来証券取引所を通じたプレスリリースや自社のホームページで行われていた対象者による質問と公開買付者による回答については、対象者が意見表明報告書に公開買付者に対する質問を記載できることとなり、その場合、公開買付者は対質問回答報告書を提出することが義務付けられた(法27条の10第2項1号・11項)。
公開買付期間については、旧法では暦日ベースであったが、対象者の経営陣が対抗提案を検討し、株主・投資者等に対する十分な情報提供およびその熟慮期間を確保するため、新法では営業日ベース(行政機関の休日は算入しない)で公開買付開始公告日から起算して20日以上で60日以内の期間となった(施行令8条1項)。
また、対象者の意見表明報告書における一方的な請求により、最短期間を30営業日まで延長することができることとなった(法27条の10第2項2号・3項)。
公開買付届出書(他社株公開買付府令第2号様式)の記載事項の改正点のうち、実務上重要なものは次のとおりである。
① 「買付け等の目的」……支配権取得または経営参加を目的とする場合のその方法やその後の対象者の再編、多額の借財、役員の構成の変更、配当・資本政策の変更等、純投資・政策投資の場合の保有・売買・議決権行使方針等、追加取得の予定の有無、上場廃止の見込み
② 「算定の基礎」……算定根拠の具体化、最近取引の価格との相違等
③ 「算定の経緯」……第三者の意見を聴取したこと等
④ 公開買付者が経営者(MBOの場合)、親会社等一定の場合……開示事項・添付書類の追加
3 その他
改正の前後を問わず、公開買付者が公開買付開始公告等において買付予定数の上限を記載した場合には、その上限を超える応募株券等について買付義務を負わないが、新法では、このような上限を設定することができる場合を公開買付け後における株券等所有割合が3分の2未満の場合に限定した(法27条の13第4項1号)。
この結果、買付け等の後の株券等所有割合が3分の2以上となる場合については、応募株券等の全部について買付義務が生じることとなる。また、買付け等の後の株券等所有割合が3分の2以上となる場合には、対象者の発行するすべての株券等について、原則として同一の公開買付手続において勧誘を行う必要がある(施行令8条5項3号、他社株公開買付府令5条3項~5項)(図表2参照)。
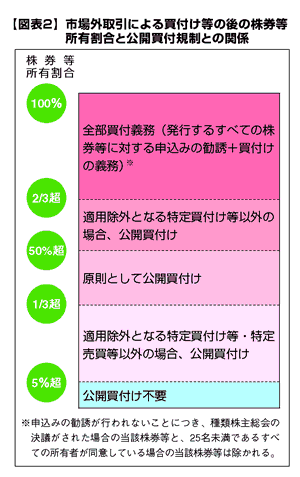
また、新法においては、公開買付けの撤回が、対象者だけではなく、その子会社の業務・財産に関する重要な変更等が生じた場合に認められたほか(法27条の11第1項)、各撤回事由についても株式分割、株式の無償割当て、新株・新株予約権の発行、重要な財産の処分・譲渡、多額の借財、既存の買収防衛策の維持等大幅な拡充が図られた(施行令14条1項)。
さらに、公開買付価格の引下げは、旧法では認められていなかったが、対象者による株式分割や株式、新株予約権等の無償割当てが行われる場合、一定の要件のもと公開買付価格の引下げが認められることとなった(法27条の6第1項1号、施行令13条1項、他社株公開買付府令19条1項)。
Ⅲ 大量保有報告制度の改正の概要
1 特例報告制度の見直し
通常の大量保有報告書・変更報告書の提出期限が5営業日であるのに対し、機関投資家に認められている特例報告制度の提出期限は、旧法では原則3か月ごと15日以内であった。しかし、株券等保有割合に係る開示をより迅速に行い、投資者等に対して一層の透明性を確保するため、新法ではおおむね毎月2回5営業日以内と改正された(法27条の26第1項~3項、施行令14条の8の2第2項)。
また、特例報告制度が適用されない「発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為」(重要提案行為等)が重要な財産の処分・譲受け、多額の借財、役員構成の重大な変更、組織再編、配当・資本政策の重要な変更等の場合と具体的に規定された(法27条の26第1項、施行令14条の8の2第1項、大量保有府令16条)。
機関投資家が、5%超保有した日(1%超以上増加した日)以降最初に到来する基準日から5営業日後までに重要提案行為等を行う場合には、当該重要提案行為等の5営業日前までに大量保有報告書・変更報告書の提出が義務付けられている(法27条の26第4項・5項、施行令14条の8の2第3項)。
さらに、10%超保有している機関投資家が、10%を下回る取引を行った場合、新法においては、特例報告ではなく、5営業日以内の一般報告を行う必要がある(法27条の26第2項3号)。
2 その他
その他の改正点としては、①貸株・借株取引等において、貸主および借主の双方において同一の株式について重複して株券等保有割合を計算する場合があるが、新法においては、共同保有者間においてかかる重複部分はネットアウトして株券等保有割合を計算すること(法27条の23第4項、施行令14条の6の2)、②対象有価証券として投資法人の発行する「投資証券」が加わったこと(法27条の23第1項、施行令14条の4第1項3号)、③EDINETによる大量保有報告書の提出が義務付けられたこと(法27条の30の2)が挙げられる。
Ⅳ 組織再編等に係る開示制度の改正の概要
新法においては、株式交換等の組織再編に係る臨時報告書による開示制度についての見直しが行われた(開示府令19条2項6号の2等)。
まず、開示を行うべき場合が拡充され、提出会社の最近の事業年度末日の純資産額の10%以上(旧法では30%以上)または提出会社の最近の事業年度の売上高の3%以上(旧法では10%以上)となる株式交換等を行う場合には臨時報告書の提出が必要となる。
臨時報告書の提出時期も「提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合」とされ、旧法の「株式交換に係る契約が締結された場合(これらの契約が締結されることが確実に見込まれ、かつ、その旨が公表された場合を含む。)」等に比べると、タイミングが早くなっている。
開示内容も、相手会社に係る最近3年間に終了した各事業年度の売上高・営業利益、大株主の名称等、株式交換等の比率の算定根拠等について記載するなどの拡充が図られた。
Ⅴ 改正の施行時期
公開買付制度、大量保有報告制度のうち「重要提案行為等」の明確化、組織再編に係る開示制度の充実については、平成18年11月中(遅くとも平成18年12月13日)より適用が開始される。
公開買付制度に関して、法27条の2第1項4号・5号は、施行後に開始する期間内における株券等の買付け等に新法が適用されるため(証券取引法等の一部を改正する法律附則7条2号・3号)、施行日前に行った買付け等については同規制が適用されない。
なお、有価証券報告書・半期報告書における会社法に対応した開示事項の整備については、施行日以降に終了する事業年度に係る有価証券報告書および同日以降に終了する中間会計期間に係る半期報告書から適用される。
その他、大量保有報告制度のうち、上記以外の点は平成19年1月1日(EDINETによる提出義務付けは平成19年4月1日)から施行される予定である。
(なかむら・さとし/くぼた・しゅうへい)
本稿は、Ⅰ①~⑤に掲げた政省令について、改正案に基づき、確定された政省令の公布前にご執筆いただいたものである。(編集部)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























