解説記事2006年12月04日 【ニュース特集】 来年度から外形標準課税の適用対象になる法人が続出も(2006年12月4日号・№189)
ニュース特集
中小企業に激震!「資本金等の額」1億円超で外形標準課税の対象
来年度から外形標準課税の適用対象になる法人が続出も
19年度税制改正で、外形標準課税の適用対象が見直されることがほぼ確実となった。具体的には、現行「資本金1億円超」とされている適用基準を「資本金等の額1億円超」とし、横行していた減資による外形標準課税逃れをシャットアウトする方向だ。
これにより、資本金1億円以下で現在外形標準課税の対象となっていない法人も、たとえば資本金と資本準備金の合計額が1億円超なら、外形標準課税の対象に取り込まれることになる。
この改正をにらみ、法人やその顧問税理士は、早くも新たな外形標準課税の回避策を検討しているが、適用基準に「資本金等の額」が採用されれば、小手先の適用回避策は通用しない可能性が高い。中小企業には大きな影響が出ることになりそうだ。
改正の背景
経済界などの大反対のなか、平成15年度税制改正で実現し、平成16年4月1日から適用開始となった外形標準課税。
導入への猛烈な反対意見に配慮してか、導入当初、総務省は、資本金を1億円以下に減資することによる外形標準課税の適用回避について、「特に問題視はしない」との見解を示していた。
その総務省が今回、一転して減資による適用回避を封じる動きに出たのは、自動車ディーラーなどにおいて、外形標準課税の適用を逃れるための「目に余る減資」(総務省幹部)が相次いでいるとの実態を受けたものだ。
総務省から各都道府県への照会の結果によると、前事業年度末まで資本金が1億円超であった法人のうち、減資により今事業年度から資本金が1億円以下となった法人(平成17年2月~平成18年1月決算法人)の数は1,961社にものぼっているという。
表1、1-2は、減資を行った法人数を前事業年度の資本金別にカウントしたものだ。資本金100億円以上から一気に1億円以下に減資する法人が40社もあるのをはじめ、かなりの数の法人が思い切った減資を行っていることが目を引く。
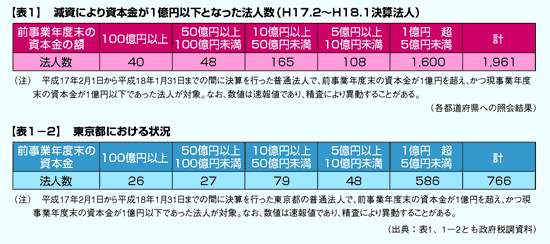
新・外形標準課税の適用対象はこうなる
今回の見直しのポイントは、外形標準課税の適用基準が現行の「資本金」から「資本金等の額」へと変更される点にある。
ここでいう「資本金等の額」とは、法人税法2条16号に規定する「資本金等の額」を指すことになる方向だ。「資本金等の額」とは、具体的には「法人が株主等から出資を受けた金額」のことを指す。
このため、たとえ資本金を資本準備金などに振り替えても、それが元々「法人が株主等から出資を受けた金額」である以上、「資本金等の額」は変わらないことになる。
平成17年2月1日から平成18年1月31日までに決算を行った東京都の普通法人のうち減資を実施した766社の減資目的を分類したのが表2だ。これをみると、資本剰余金等への振替えや、欠損てん補を目的とした減資が圧倒的に多く、両者で全体の82.1%を占めている。
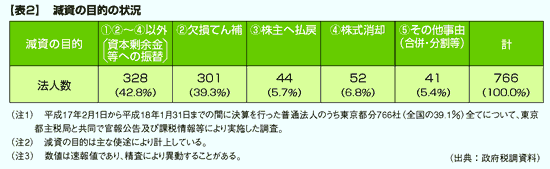
しかし、外形標準課税が法人税法上の「資本金等の額」を適用基準として採用することで、今後は資本を資本剰余金等へ振り替えたり、欠損てん補を目的とした減資を行っても、「資本金等の額」は変わらず、引き続き外形標準課税の適用対象とされることになろう。
たとえば、「資本金+資本準備金」で1億円超の会社が、資本準備金をその他資本剰余金に振り替えて「資本金+資本準備金」を1億円以下にしたとしても、「法人が株主等から出資を受けた金額」を指す「資本金等の額」は変わらない。
また、資本金や資本準備金、その他資本剰余金を欠損金額と相殺したとしても、やはり「資本金等の額」は変わらない。これは、「資本金等の額」の計算方法を規定する法人税法施行令8条1項において、資本金等の金額の減算項目(同条1項15号から21号まで)に、「欠損金」は含まれていないからだ。
なお、総務省は「1億円超」という金額基準は改正しない方針を示しているが、改正のインパクトは金額基準が大幅に引き上げられたに等しいといっていいだろう。
COLUMN 会計上の株主資本と会社法上の株主資本
会計上、株主資本は①資本金、②資本剰余金(資本準備金、その他資本剰余金)、③利益剰余金(利益準備金、その他利益剰余金)、④自己株式に分類される一方、会社法上の株主資本は①資本金、②準備金(資本準備金、利益準備金)、③剰余金(その他資本剰余金、その他利益剰余金)、④自己株式に分類される。会計が「資本」「利益」をキーワードに株主資本を整理しているのに対し、会社法は、「準備金」「剰余金」をキーワードにしている点が特徴といえる。
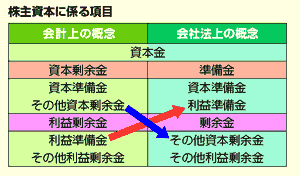
外形標準課税の適用を回避する残された方法とは?
前述のとおり、資本金を資本剰余金等に振り替える手法や、欠損てん補を目的とした減資を行っても「資本金等の額」は変わらず、外形標準課税の適用を回避することはできないこととなる。
こうしたなか、残された手法としては、法人税法施行令8条1項に規定する資本金等の金額の減算項目(同条1項15号から21号まで)に規定する資本の払戻し(法令8条1項19号)、自己株式の取得等(同条1項20号、21号)など限られた選択肢しかなくなったことになる。
このように、資本性の金額を操作することで外形標準課税の適用を逃れることは困難となったうえ、総務省は一度外形標準課税の対象となった法人については、「5年間」は外形標準課税の適用対象とする方針を示している。
適用回避の途は、あったとしても非常に狭いものとなりそうだ。
一部には「減税」となる法人も
外形標準課税の適用基準の見直しは、自動車ディーラーなどによる「目に余る減資」が引き金になっていると述べたが、これが実現すれば、その影響は、減資により課税回避を図った法人だけでなく、元々資本金が1億円以下の法人にも及ぶことになる。これらの法人のなかには、資本金と資本準備金等を合わせれば「1億円超」となるところも少なくないからだ。
ただ、業績好調で課税所得が大きい法人の場合、従来の事業税課税よりも外形標準課税の適用を受けた方が税額が小さくなるケースも出てきそうだ。
実際、自動車会社など業績好調な企業が集積する愛知県などでは、景気回復に伴い、今年度の事業税収入が減収になる可能性も指摘されている(本誌160号参照)。
とはいえ、中小企業にあっては、継続的に赤字となっているところが多く、外形標準課税の適用を受けることになれば、税負担の増加は避けられないことになりそうだ。
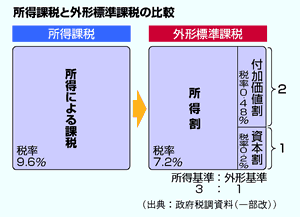
中小企業が恐れる法人税法の改正
外形標準課税の適用対象見直しに関連し、中小企業が恐れるのが、法人税法の改正だ。
法人税法上、資本金が1億円以下の法人は「中小法人」とされ、法人税率が30%から22%に軽減(所得800万円以下の部分)されているほか、交際費課税や特別償却等においても特典が設けられており、こうした特典を受けるために、資本金を1億円以下に抑える法人は少なくない。
仮に、法人税法上も中小法人の定義を現行の「資本金1億円以下」から「資本金等の額1億円以下」に改正することになれば、大量の法人が中小法人に該当しなくなり、その影響度は外形標準課税の比ではないだろう。
ただ、この点について財務省は本誌取材に対し、19年度改正での改正の可能性について、「もし改正するのであれば、会社法と同時にやっていたであろう」と回答している。この回答からすると、19年度税制改正での実施の可能性は低いといってよいだろう。
その一方で、外形標準課税の適用対象が「資本金等の額」となる方向のなか、財務省としては、「中小法人の線引きをどうするかについては、今はまだ勉強段階」とも述べており、将来の見直しを完全には否定していない。
いずれにせよ、影響は甚大となるだけに、慎重な検討が求められることになるだろう。
中小企業に激震!「資本金等の額」1億円超で外形標準課税の対象
来年度から外形標準課税の適用対象になる法人が続出も
19年度税制改正で、外形標準課税の適用対象が見直されることがほぼ確実となった。具体的には、現行「資本金1億円超」とされている適用基準を「資本金等の額1億円超」とし、横行していた減資による外形標準課税逃れをシャットアウトする方向だ。
これにより、資本金1億円以下で現在外形標準課税の対象となっていない法人も、たとえば資本金と資本準備金の合計額が1億円超なら、外形標準課税の対象に取り込まれることになる。
この改正をにらみ、法人やその顧問税理士は、早くも新たな外形標準課税の回避策を検討しているが、適用基準に「資本金等の額」が採用されれば、小手先の適用回避策は通用しない可能性が高い。中小企業には大きな影響が出ることになりそうだ。
改正の背景
経済界などの大反対のなか、平成15年度税制改正で実現し、平成16年4月1日から適用開始となった外形標準課税。
導入への猛烈な反対意見に配慮してか、導入当初、総務省は、資本金を1億円以下に減資することによる外形標準課税の適用回避について、「特に問題視はしない」との見解を示していた。
その総務省が今回、一転して減資による適用回避を封じる動きに出たのは、自動車ディーラーなどにおいて、外形標準課税の適用を逃れるための「目に余る減資」(総務省幹部)が相次いでいるとの実態を受けたものだ。
総務省から各都道府県への照会の結果によると、前事業年度末まで資本金が1億円超であった法人のうち、減資により今事業年度から資本金が1億円以下となった法人(平成17年2月~平成18年1月決算法人)の数は1,961社にものぼっているという。
表1、1-2は、減資を行った法人数を前事業年度の資本金別にカウントしたものだ。資本金100億円以上から一気に1億円以下に減資する法人が40社もあるのをはじめ、かなりの数の法人が思い切った減資を行っていることが目を引く。
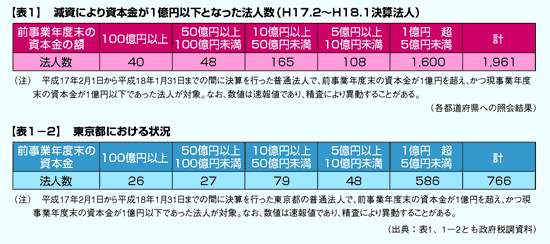
新・外形標準課税の適用対象はこうなる
今回の見直しのポイントは、外形標準課税の適用基準が現行の「資本金」から「資本金等の額」へと変更される点にある。
ここでいう「資本金等の額」とは、法人税法2条16号に規定する「資本金等の額」を指すことになる方向だ。「資本金等の額」とは、具体的には「法人が株主等から出資を受けた金額」のことを指す。
このため、たとえ資本金を資本準備金などに振り替えても、それが元々「法人が株主等から出資を受けた金額」である以上、「資本金等の額」は変わらないことになる。
平成17年2月1日から平成18年1月31日までに決算を行った東京都の普通法人のうち減資を実施した766社の減資目的を分類したのが表2だ。これをみると、資本剰余金等への振替えや、欠損てん補を目的とした減資が圧倒的に多く、両者で全体の82.1%を占めている。
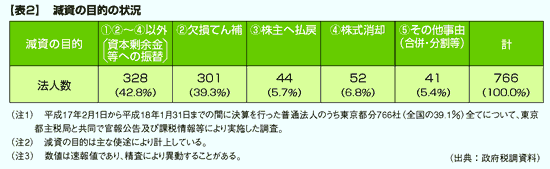
しかし、外形標準課税が法人税法上の「資本金等の額」を適用基準として採用することで、今後は資本を資本剰余金等へ振り替えたり、欠損てん補を目的とした減資を行っても、「資本金等の額」は変わらず、引き続き外形標準課税の適用対象とされることになろう。
たとえば、「資本金+資本準備金」で1億円超の会社が、資本準備金をその他資本剰余金に振り替えて「資本金+資本準備金」を1億円以下にしたとしても、「法人が株主等から出資を受けた金額」を指す「資本金等の額」は変わらない。
また、資本金や資本準備金、その他資本剰余金を欠損金額と相殺したとしても、やはり「資本金等の額」は変わらない。これは、「資本金等の額」の計算方法を規定する法人税法施行令8条1項において、資本金等の金額の減算項目(同条1項15号から21号まで)に、「欠損金」は含まれていないからだ。
なお、総務省は「1億円超」という金額基準は改正しない方針を示しているが、改正のインパクトは金額基準が大幅に引き上げられたに等しいといっていいだろう。
COLUMN 会計上の株主資本と会社法上の株主資本
会計上、株主資本は①資本金、②資本剰余金(資本準備金、その他資本剰余金)、③利益剰余金(利益準備金、その他利益剰余金)、④自己株式に分類される一方、会社法上の株主資本は①資本金、②準備金(資本準備金、利益準備金)、③剰余金(その他資本剰余金、その他利益剰余金)、④自己株式に分類される。会計が「資本」「利益」をキーワードに株主資本を整理しているのに対し、会社法は、「準備金」「剰余金」をキーワードにしている点が特徴といえる。
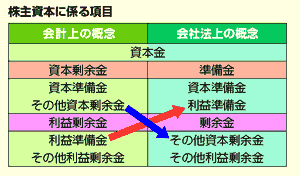
外形標準課税の適用を回避する残された方法とは?
前述のとおり、資本金を資本剰余金等に振り替える手法や、欠損てん補を目的とした減資を行っても「資本金等の額」は変わらず、外形標準課税の適用を回避することはできないこととなる。
こうしたなか、残された手法としては、法人税法施行令8条1項に規定する資本金等の金額の減算項目(同条1項15号から21号まで)に規定する資本の払戻し(法令8条1項19号)、自己株式の取得等(同条1項20号、21号)など限られた選択肢しかなくなったことになる。
このように、資本性の金額を操作することで外形標準課税の適用を逃れることは困難となったうえ、総務省は一度外形標準課税の対象となった法人については、「5年間」は外形標準課税の適用対象とする方針を示している。
適用回避の途は、あったとしても非常に狭いものとなりそうだ。
一部には「減税」となる法人も
外形標準課税の適用基準の見直しは、自動車ディーラーなどによる「目に余る減資」が引き金になっていると述べたが、これが実現すれば、その影響は、減資により課税回避を図った法人だけでなく、元々資本金が1億円以下の法人にも及ぶことになる。これらの法人のなかには、資本金と資本準備金等を合わせれば「1億円超」となるところも少なくないからだ。
ただ、業績好調で課税所得が大きい法人の場合、従来の事業税課税よりも外形標準課税の適用を受けた方が税額が小さくなるケースも出てきそうだ。
実際、自動車会社など業績好調な企業が集積する愛知県などでは、景気回復に伴い、今年度の事業税収入が減収になる可能性も指摘されている(本誌160号参照)。
とはいえ、中小企業にあっては、継続的に赤字となっているところが多く、外形標準課税の適用を受けることになれば、税負担の増加は避けられないことになりそうだ。
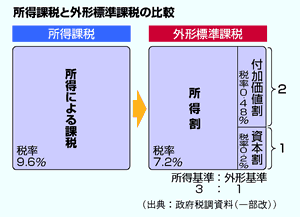
中小企業が恐れる法人税法の改正
外形標準課税の適用対象見直しに関連し、中小企業が恐れるのが、法人税法の改正だ。
法人税法上、資本金が1億円以下の法人は「中小法人」とされ、法人税率が30%から22%に軽減(所得800万円以下の部分)されているほか、交際費課税や特別償却等においても特典が設けられており、こうした特典を受けるために、資本金を1億円以下に抑える法人は少なくない。
仮に、法人税法上も中小法人の定義を現行の「資本金1億円以下」から「資本金等の額1億円以下」に改正することになれば、大量の法人が中小法人に該当しなくなり、その影響度は外形標準課税の比ではないだろう。
ただ、この点について財務省は本誌取材に対し、19年度改正での改正の可能性について、「もし改正するのであれば、会社法と同時にやっていたであろう」と回答している。この回答からすると、19年度税制改正での実施の可能性は低いといってよいだろう。
その一方で、外形標準課税の適用対象が「資本金等の額」となる方向のなか、財務省としては、「中小法人の線引きをどうするかについては、今はまだ勉強段階」とも述べており、将来の見直しを完全には否定していない。
いずれにせよ、影響は甚大となるだけに、慎重な検討が求められることになるだろう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























