解説記事2006年12月18日 【ニュース特集】 e-Taxの普及を優遇税制でバックアップ!(2006年12月18日号・№191)
平成22年までの行政手続のオンライン利用率50%を達成へ
e-Taxの普及を優遇税制でバックアップ!
平成22年度までに行政手続のオンライン利用率を50%とする政府の目標達成のため、自民党税制調査会は平成19年度税制改正において、電子申告における電子証明等の取得費の税額控除やオンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除を創設することを決めた。今回の税制措置が目標達成に向け、どの程度貢献することができるか注目されるが、納税者にとっては朗報といえよう。
1 電子証明書等の取得費、5,000円まで税額控除を認める
国税電子申告システム(e-Tax)関係については、平成22年度までにオンライン利用率を50%とする目標があるが、平成17年度は0.3%にすぎないという現状に配慮し、利便性を向上させるための施策が行われる。
まず、電子申告を行う際のインセンティブの1つとして、電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除制度を創設する。具体的には、電子申告を行う際に取得した電子証明書(住基カード)やカードリーダーを取得した場合、所得税の税額控除を認めるというもの。
平成19年分または平成20年分の所得税に係る確定申告において、それぞれの年の翌年3月15日までに自己の電子証明書および電子署名を添付して電子申告を行った者が対象となる。控除額は5,000円(その年の所得税額が限度となる)。ただし、平成19年分に本税額控除の適用を受けた場合には、平成20年分においてはその適用を受けることができない。
平成20年1月4日以後に電子申告を行った場合に適用
今回の改正は、平成20年1月4日以後に、平成19年分の所得税の確定申告を電子申告により行う場合に適用される。
なお、同日前に出国したことにより平成19年分の所得税の確定申告を電子申告で行っている場合については、同日から1年以内に更正の請求を行うことにより、税額控除の額の還付を受けることができる。
2 医療費の領収書等もデータ送信が可能
また、電子署名の省略や添付書類のデータ送信を認めることで電子申告の利便性を向上させる。現在、電子申告を行う場合でも、医療費の領収書等は別途郵送しなければならないが、これを書類内容のデータ送信でも容認する(前頁図参照)。
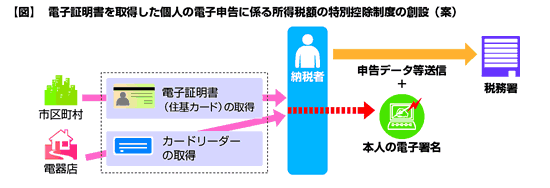
顧問税理士の電子署名だけで電子申告が可能に
また、電子署名の省略については、具体的に①顧問税理士の電子署名だけで電子申告を可能にする、②税務署に来署して電子申告する場合には、電子署名を不要とする、③徴収高計算書(給与等の支払いの内訳)は、電子署名を不要とする改正が行われる。特に①に関しては、顧問税理士に電子申告を依頼している場合でも、現在は、納税者と税理士の双方の電子署名が必要とされており、電子申告の普及を妨げる要因の1つとされていたものである。
源泉徴収関係書類の電子提出も認める
その他、平成18年度税制改正で導入された源泉徴収票等の電子交付の対象となる書類を拡大する。具体的には、公的年金等の源泉徴収票および支払明細書、退職所得の源泉徴収票および支払明細書、配当等とみなす金額に関する支払通知書となっている。また、源泉徴収関係書類の電子提出も認める。具体的には、扶養控除等申告書、配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書、受給に関する申告書(退職所得者)、扶養親族等申告書(公的年金等の受給者)となっている。
書類内容のデータ送信を認める書類
・医療費の領収書
・社会保険料控除証明書
・小規模企業共済等掛金の額を証する書類
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・源泉徴収票(給与・退職・年金)
・特定口座年間取引報告書
3 2年間の措置でオンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除を創設
電子政府の構築に向け、オンライン登記申請の利用促進を図る観点から、オンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除を創設する。平成19年度末までに全国の約9割の登記所でオンライン登記申請が可能となる見込みであるため、平成20年1月1日から2年間の措置として導入する。
税額10%または5,000円のいずれか低い金額
対象となる登記は、①不動産登記(所有権の保存登記、移転登記、(根)抵当権の設定登記)、②商業・法人登記(法人設立の登記)となる。軽減税額(税額控除額)は、登録免許税額の10%または5,000円のいずれか低い金額とされている。
不動産の所有権の保存登記の場合、現行では、不動産の価額の0.4%の登録免許税が課されており、たとえば、不動産の価額が1,000万円の場合であれば、4万円となる。しかし、改正後は、4,000円控除され、3万6,000円となる。
また、株式会社の設立登記の場合、現行では、資本金の額の0.7%(税額が15万円に満たない場合は申請件数1件につき15万円)とされている。仮に資本金300万円で設立した場合であれば、15万円の登録免許税が必要となるが、14万5,000円に軽減されることになる。
対象となる登記
不動産登記:所有権の保存登記(0.4%)・移転登記(2.0%等)・(根)抵当権の設定登記(0.4%)
商業登記:法人の設立登記(0.7%) ※「法人」とは株式会社、合名会社、合資会社等
【例:1,000万円の不動産の所有権の保存登記の場合の登録免許税額】
1,000万円×0.4%=4万円⇒3万6,000円(10%の4,000円を税額控除)
【例:資本金300万円の株式会社の設立登記の場合の登録免許税額】
300万円×0.7%=2万1,000円⇒15万円(税額が15万円に満たない場合は申請件数1件につき15万円)⇒14万5,000円(5,000円を税額控除)
e-Taxの普及を優遇税制でバックアップ!
平成22年度までに行政手続のオンライン利用率を50%とする政府の目標達成のため、自民党税制調査会は平成19年度税制改正において、電子申告における電子証明等の取得費の税額控除やオンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除を創設することを決めた。今回の税制措置が目標達成に向け、どの程度貢献することができるか注目されるが、納税者にとっては朗報といえよう。
1 電子証明書等の取得費、5,000円まで税額控除を認める
国税電子申告システム(e-Tax)関係については、平成22年度までにオンライン利用率を50%とする目標があるが、平成17年度は0.3%にすぎないという現状に配慮し、利便性を向上させるための施策が行われる。
まず、電子申告を行う際のインセンティブの1つとして、電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除制度を創設する。具体的には、電子申告を行う際に取得した電子証明書(住基カード)やカードリーダーを取得した場合、所得税の税額控除を認めるというもの。
平成19年分または平成20年分の所得税に係る確定申告において、それぞれの年の翌年3月15日までに自己の電子証明書および電子署名を添付して電子申告を行った者が対象となる。控除額は5,000円(その年の所得税額が限度となる)。ただし、平成19年分に本税額控除の適用を受けた場合には、平成20年分においてはその適用を受けることができない。
平成20年1月4日以後に電子申告を行った場合に適用
今回の改正は、平成20年1月4日以後に、平成19年分の所得税の確定申告を電子申告により行う場合に適用される。
なお、同日前に出国したことにより平成19年分の所得税の確定申告を電子申告で行っている場合については、同日から1年以内に更正の請求を行うことにより、税額控除の額の還付を受けることができる。
2 医療費の領収書等もデータ送信が可能
また、電子署名の省略や添付書類のデータ送信を認めることで電子申告の利便性を向上させる。現在、電子申告を行う場合でも、医療費の領収書等は別途郵送しなければならないが、これを書類内容のデータ送信でも容認する(前頁図参照)。
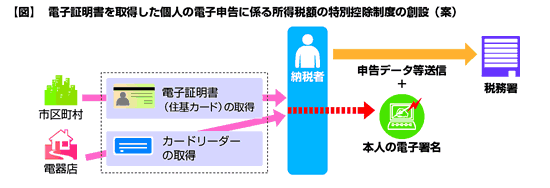
顧問税理士の電子署名だけで電子申告が可能に
また、電子署名の省略については、具体的に①顧問税理士の電子署名だけで電子申告を可能にする、②税務署に来署して電子申告する場合には、電子署名を不要とする、③徴収高計算書(給与等の支払いの内訳)は、電子署名を不要とする改正が行われる。特に①に関しては、顧問税理士に電子申告を依頼している場合でも、現在は、納税者と税理士の双方の電子署名が必要とされており、電子申告の普及を妨げる要因の1つとされていたものである。
源泉徴収関係書類の電子提出も認める
その他、平成18年度税制改正で導入された源泉徴収票等の電子交付の対象となる書類を拡大する。具体的には、公的年金等の源泉徴収票および支払明細書、退職所得の源泉徴収票および支払明細書、配当等とみなす金額に関する支払通知書となっている。また、源泉徴収関係書類の電子提出も認める。具体的には、扶養控除等申告書、配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書、受給に関する申告書(退職所得者)、扶養親族等申告書(公的年金等の受給者)となっている。
書類内容のデータ送信を認める書類
・医療費の領収書
・社会保険料控除証明書
・小規模企業共済等掛金の額を証する書類
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・源泉徴収票(給与・退職・年金)
・特定口座年間取引報告書
3 2年間の措置でオンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除を創設
電子政府の構築に向け、オンライン登記申請の利用促進を図る観点から、オンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除を創設する。平成19年度末までに全国の約9割の登記所でオンライン登記申請が可能となる見込みであるため、平成20年1月1日から2年間の措置として導入する。
税額10%または5,000円のいずれか低い金額
対象となる登記は、①不動産登記(所有権の保存登記、移転登記、(根)抵当権の設定登記)、②商業・法人登記(法人設立の登記)となる。軽減税額(税額控除額)は、登録免許税額の10%または5,000円のいずれか低い金額とされている。
不動産の所有権の保存登記の場合、現行では、不動産の価額の0.4%の登録免許税が課されており、たとえば、不動産の価額が1,000万円の場合であれば、4万円となる。しかし、改正後は、4,000円控除され、3万6,000円となる。
また、株式会社の設立登記の場合、現行では、資本金の額の0.7%(税額が15万円に満たない場合は申請件数1件につき15万円)とされている。仮に資本金300万円で設立した場合であれば、15万円の登録免許税が必要となるが、14万5,000円に軽減されることになる。
対象となる登記
不動産登記:所有権の保存登記(0.4%)・移転登記(2.0%等)・(根)抵当権の設定登記(0.4%)
商業登記:法人の設立登記(0.7%) ※「法人」とは株式会社、合名会社、合資会社等
【例:1,000万円の不動産の所有権の保存登記の場合の登録免許税額】
1,000万円×0.4%=4万円⇒3万6,000円(10%の4,000円を税額控除)
【例:資本金300万円の株式会社の設立登記の場合の登録免許税額】
300万円×0.7%=2万1,000円⇒15万円(税額が15万円に満たない場合は申請件数1件につき15万円)⇒14万5,000円(5,000円を税額控除)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























