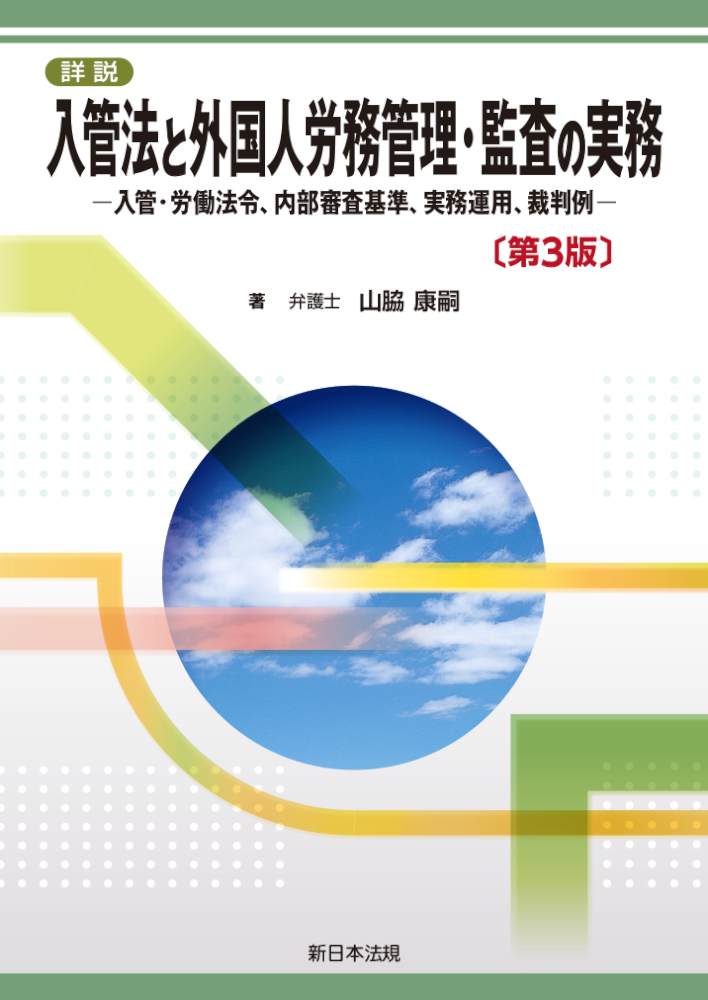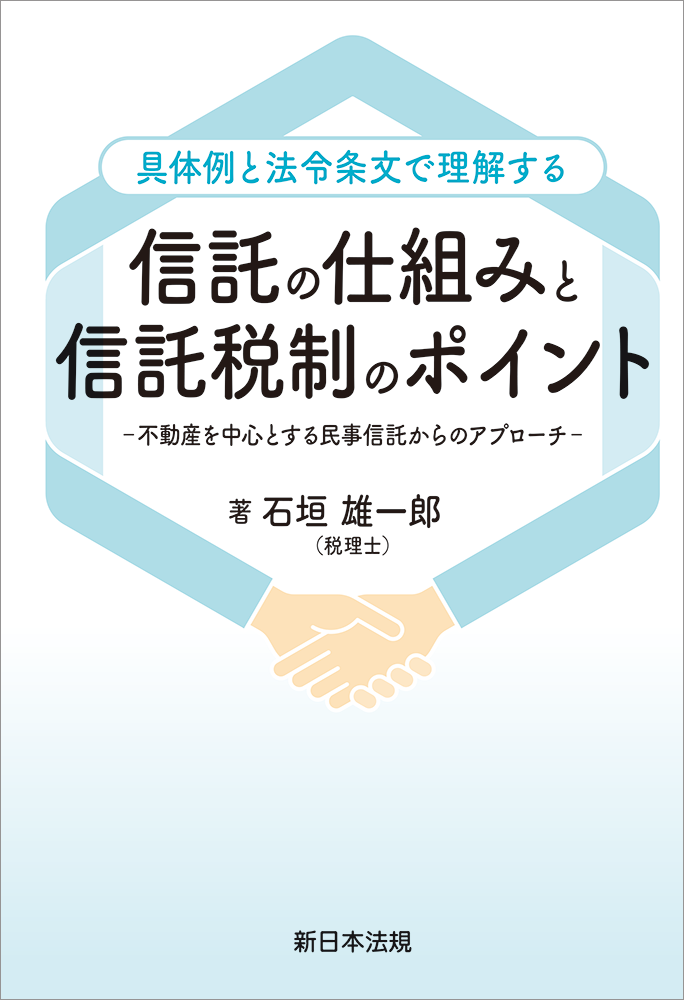コラム2007年01月15日 【SCOPE】 不動産登記における登記識別情報制度の問題と対応(2007年1月15日号・№194)
SCOPE
研究会が存続を前提に改善策を提示
不動産登記における登記識別情報制度の問題と対応
平成16年の不動産登記法の改正により導入された「登記識別情報制度」について、その問題点と改善策を検討してきた研究会の報告「登記識別情報制度についての研究会報告書」が1月4日、法務省のサイトで公表された。今回のスコープでは、同制度の内容と問題点、当面の対応を紹介する。
各界意見のなかには制度廃止の主張も
登記識別情報とは、不動産登記法の改正により、登記済証に代わる不動産登記固有の本人確認制度として導入されたもので、新法の制定により、本人確認手段は図表1に掲げるとおりとなっている。新法では不動産登記のオンライン申請制度が導入されており、登記済証は有体物であるためにオンライン申請には使用できず、これに代わる登記識別情報制度が導入された。
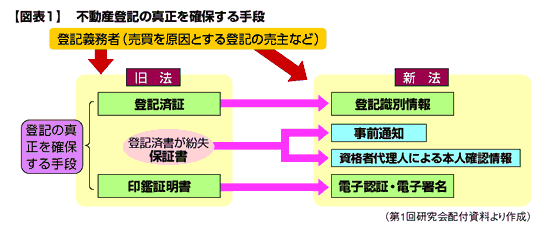
登記識別情報は不動産登記規則の規定により12桁の英数字で表される。前回の登記完了後、登記名義人に交付され、登記名義人しか知りえない情報となる。登記済証の場合と同様、適正な登記識別情報を提供した者を登記義務者本人であると確認することが可能とされている。
ただし、登記済証が果たしていた社会経済上の役割が必ずしも十分に果たされていない、オンライン申請において利用が事実上極めて困難であるなどの問題点が各界から指摘されており、平成18年7月に関係団体等に行われた「登記識別情報に関する意見照会」では、登記識別情報制度を廃止すべきとする意見や廃止して登記済証の制度を復活すべきとする意見も寄せられていた。
改善策を提示するも「不断の検討」求める
そこで、利用者の利便性の一層の向上を図る観点から、司法書士、土地家屋調査士、弁護士、金融機関、宅建業、法律学者、IT専門家等からなる「登記識別情報制度についての研究会」(座長:鎌田薫早稲田大学大学院法務研究科教授)が設置され、8月29日の初会合以降、11月28日まで計6回の会合を経て、報告書がまとめられた。①問題点の改善を図ればよく、制度自体を廃止する必要はない、②制度の存廃は問題点とこれに対する改善策を検討または実施したうえでなければ判断しかねるなどとして、問題点と改善策が検討されている。
問題点として把握されたのは、図表2のとおりである。研究会では、各問題点に対応する改善策を検討し、それぞれを、①検討着手から6か月程度で実施可能な短期的検討課題、②1年程度を要する中期的検討課題、③2年以上を要する長期的検討課題に区分して提示している(短期的検討課題について、図表3参照)。
法務省に対しては、制度面・システム面・費用対効果の面からの検討を行い、実効性があり、かつ、実施可能なものについては実施を図りつつ効果を検証し、制度全体のあり方について不断の検討を進めていくことを要請している。
【図表2】 現状の登記識別情報制度の問題点
1 不動産取引の円滑な実現に支障
(1) 登記識別情報の有効性の確認等に関する問題
~登記識別情報自体は意味を持たない情報であり、かつ、いつでも失効させることができるため、資格者代理人であっても取引の現場でその真偽・有効性を判断できない
①有効証明請求制度の問題(登記識別情報が有効であることの証明請求の制度が導入されているが、現状の有効証明請求制度は資格者代理人が関与することを前提としておらず、事実上利用が困難など)
②登記完了証の問題(申請人に対し登記が完了したことを通知するために登記完了証の制度が導入されているが、現行の登記完了証には登記名義人等が記載されておらず、取引時に権利者本人であることを事実上推定させる手段として利用できない)
(2) 失効申出制度に関する問題
~登記識別情報の漏洩の可能性がある場合等に不正な登記申請を防止するために登記識別情報の失効申出の制度が設けられているが、この制度により登記識別情報は常に失効する可能性がある
2 情報としての登記識別情報の保管・管理が煩雑
~①保管・管理が煩雑であるほか、②複数回の登記申請で同一の登記識別情報を都度利用しなければならないなど漏洩のおそれがある、③失効申出制度を利用した場合には簡易な本人確認手続を採ることができなくなる(再発行手続がない)
3 オンライン申請は事実上利用が困難
~申請における登記識別情報の取扱いが厳格で、資格者代理人が関与することを前提とした手続となっていない
【図表3】 登記識別情報制度の短期的検討課題としての改善策
▲資格者代理人による職務上請求制度(申請者本人の委任状・印鑑証明書が不要)を創設する(問題点1(1)①に対応)
▲登記識別情報を提供しないで失効していることの証明の請求を可能とする(同前)
▲登記識別情報に関する証明について、金融機関の代表者から支店長等に包括委任することを可能とする。併せて、法人の代表者に代わるべき者に関する証明(業務権限証明等)の取扱いを緩和する(問題点1(1)①に関連)
▲失効申出制度を見直す(廃止を含む)(問題点1(2)に対応)
▲オンライン申請の場合にも登記識別情報通知書の交付を可能とする(問題点2①に対応)
▲登記識別情報の提供をすることができない正当理由を追加する(問題点2②に対応)
▲オンライン申請の場合にも登記識別情報通知書の交付を可能とし、加えて、書面申請の場合も含めて登記識別情報通知書の郵送による交付を可能とする(問題点3に対応)
研究会が存続を前提に改善策を提示
不動産登記における登記識別情報制度の問題と対応
平成16年の不動産登記法の改正により導入された「登記識別情報制度」について、その問題点と改善策を検討してきた研究会の報告「登記識別情報制度についての研究会報告書」が1月4日、法務省のサイトで公表された。今回のスコープでは、同制度の内容と問題点、当面の対応を紹介する。
各界意見のなかには制度廃止の主張も
登記識別情報とは、不動産登記法の改正により、登記済証に代わる不動産登記固有の本人確認制度として導入されたもので、新法の制定により、本人確認手段は図表1に掲げるとおりとなっている。新法では不動産登記のオンライン申請制度が導入されており、登記済証は有体物であるためにオンライン申請には使用できず、これに代わる登記識別情報制度が導入された。
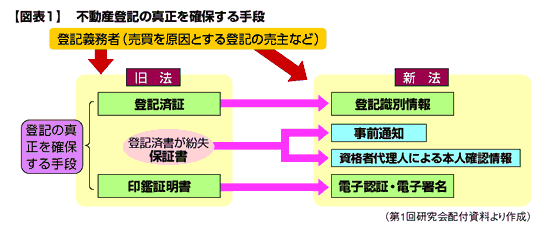
登記識別情報は不動産登記規則の規定により12桁の英数字で表される。前回の登記完了後、登記名義人に交付され、登記名義人しか知りえない情報となる。登記済証の場合と同様、適正な登記識別情報を提供した者を登記義務者本人であると確認することが可能とされている。
ただし、登記済証が果たしていた社会経済上の役割が必ずしも十分に果たされていない、オンライン申請において利用が事実上極めて困難であるなどの問題点が各界から指摘されており、平成18年7月に関係団体等に行われた「登記識別情報に関する意見照会」では、登記識別情報制度を廃止すべきとする意見や廃止して登記済証の制度を復活すべきとする意見も寄せられていた。
改善策を提示するも「不断の検討」求める
そこで、利用者の利便性の一層の向上を図る観点から、司法書士、土地家屋調査士、弁護士、金融機関、宅建業、法律学者、IT専門家等からなる「登記識別情報制度についての研究会」(座長:鎌田薫早稲田大学大学院法務研究科教授)が設置され、8月29日の初会合以降、11月28日まで計6回の会合を経て、報告書がまとめられた。①問題点の改善を図ればよく、制度自体を廃止する必要はない、②制度の存廃は問題点とこれに対する改善策を検討または実施したうえでなければ判断しかねるなどとして、問題点と改善策が検討されている。
問題点として把握されたのは、図表2のとおりである。研究会では、各問題点に対応する改善策を検討し、それぞれを、①検討着手から6か月程度で実施可能な短期的検討課題、②1年程度を要する中期的検討課題、③2年以上を要する長期的検討課題に区分して提示している(短期的検討課題について、図表3参照)。
法務省に対しては、制度面・システム面・費用対効果の面からの検討を行い、実効性があり、かつ、実施可能なものについては実施を図りつつ効果を検証し、制度全体のあり方について不断の検討を進めていくことを要請している。
【図表2】 現状の登記識別情報制度の問題点
1 不動産取引の円滑な実現に支障
(1) 登記識別情報の有効性の確認等に関する問題
~登記識別情報自体は意味を持たない情報であり、かつ、いつでも失効させることができるため、資格者代理人であっても取引の現場でその真偽・有効性を判断できない
①有効証明請求制度の問題(登記識別情報が有効であることの証明請求の制度が導入されているが、現状の有効証明請求制度は資格者代理人が関与することを前提としておらず、事実上利用が困難など)
②登記完了証の問題(申請人に対し登記が完了したことを通知するために登記完了証の制度が導入されているが、現行の登記完了証には登記名義人等が記載されておらず、取引時に権利者本人であることを事実上推定させる手段として利用できない)
(2) 失効申出制度に関する問題
~登記識別情報の漏洩の可能性がある場合等に不正な登記申請を防止するために登記識別情報の失効申出の制度が設けられているが、この制度により登記識別情報は常に失効する可能性がある
2 情報としての登記識別情報の保管・管理が煩雑
~①保管・管理が煩雑であるほか、②複数回の登記申請で同一の登記識別情報を都度利用しなければならないなど漏洩のおそれがある、③失効申出制度を利用した場合には簡易な本人確認手続を採ることができなくなる(再発行手続がない)
3 オンライン申請は事実上利用が困難
~申請における登記識別情報の取扱いが厳格で、資格者代理人が関与することを前提とした手続となっていない
【図表3】 登記識別情報制度の短期的検討課題としての改善策
▲資格者代理人による職務上請求制度(申請者本人の委任状・印鑑証明書が不要)を創設する(問題点1(1)①に対応)
▲登記識別情報を提供しないで失効していることの証明の請求を可能とする(同前)
▲登記識別情報に関する証明について、金融機関の代表者から支店長等に包括委任することを可能とする。併せて、法人の代表者に代わるべき者に関する証明(業務権限証明等)の取扱いを緩和する(問題点1(1)①に関連)
▲失効申出制度を見直す(廃止を含む)(問題点1(2)に対応)
▲オンライン申請の場合にも登記識別情報通知書の交付を可能とする(問題点2①に対応)
▲登記識別情報の提供をすることができない正当理由を追加する(問題点2②に対応)
▲オンライン申請の場合にも登記識別情報通知書の交付を可能とし、加えて、書面申請の場合も含めて登記識別情報通知書の郵送による交付を可能とする(問題点3に対応)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -