解説記事2007年01月22日 【編集部解説】 リース会計基準案の公表とリース会計基準の変更に伴う所要の税制措置について(2007年1月22日号・№195)
解説
リース会計基準案の公表とリース会計基準の変更に伴う所要の税制措置について
T&Amaster編集部 佐治俊夫
企業会計基準委員会は12月27日、リース取引に関する会計基準および同適用指針の公開草案(以下「リース会計基準(案)」という)を公表した(リース会計基準(案)の概要は本誌194号14頁を参照)。また、平成19年度税制改正大綱では、リース会計基準の変更に伴う税制の整備が盛り込まれた。新しいリース会計・リース税制を探ってみることにする。
なお、本稿は平成19年度税制改正大綱とリース会計基準(案)の公表から、リース会計基準の見直しに伴うリース税制との関連に焦点を当てたものであり、リース会計基準(案)の内容を網羅的に解説することを試みたものではない。リース税制についても、今後明らかにされる法令・通達により、具体的かつ精緻な規定が整備されよう。
Ⅰ リース取引の分類
1.リース取引の分類が前提
リース会計基準(案)に定められた会計処理の内容や税制措置を検討する前に、リース取引の分類を確認しておきたい。リース会計基準(案)では以下のようにリース取引を分類したうえで、貸手・借手の会計処理を規定している。これは現行のリース取引に係る会計基準(以下「リース会計基準(現行)」という)が形式的にはリース取引を①ファイナンス・リースと②オペレーティング・リース取引の2種類に分類し、実質的にはファイナンス・リース取引を所有権移転ファインナンス・リース取引と所有権移転外ファイナンス・リース取引に異なる会計処理を認めていたことからすれば、リース取引について、より実態に合致させたものと評価することができる。
また、法人税法(施行令・通達)では、リース会計基準上のファイナンス・リース取引をリース取引と定義したうえで、そのリース取引のうち売買取引として取り扱うものと金融取引として取り扱うものの範囲を定めている。
リース取引については、会計上の分類や税務上売買として取り扱うリース取引に該当するかどうかによって、会計処理(あるいは税務上の取扱い)が定められていることから、まずは、リース取引の分類が実務における会計処理などの前提になってくる。
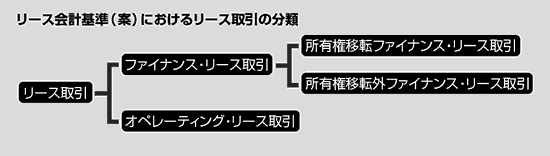
2.ファイナンス・リース取引(税務上の「リース取引」)
リース取引は、「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」に分類される。
「ファイナンス・リース取引」とは、リース期間の中途においてリース契約を解除することができないリース取引またはこれに準ずるリース取引で、借手が、リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。
「オペレーティング・リース取引」とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。
「ファイナンス・リース取引」は、「解約不能」と「フルペイアウト(借手が、リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担すること)」を内容とするものであり、法人税法施行令136条の3(リース取引に係る所得の計算)の3項においても、同旨の要件を満たすものを「リース取引」と定義している。
しかし、第1の条件の「解約不能」については、法的形式上は解約可能であるとしても、解約に際し相当の違約金を支払わなければならない等の理由から事実上解約不能と認められるリース取引(これに準ずるリース取引)を含むものであり、契約条項の内容、商慣習等を勘案し契約の実態に応じ判断される。第2の条件である「フルペイアウト」については、「実質的に」の判断が求められることになる。
リース会計基準の適用指針(案)では、具体的な判定基準(①現在価値基準、②経済的耐用年数基準)が示されている。また、法人税基本通達では、「リース取引」について、①解除をすることができないものに準ずるものの意義(法基通12の5-1-1)、②資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきことの意義(法基通12の5-1-2)、③おおむね全部の判定(法基通12の5-1-3)の解釈を明確化させている。
3.所有権移転外ファイナンス・リース取引
「ファイナンス・リース取引」は、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの(以下「所有権移転ファイナンス・リース取引」という)とそれ以外の取引(以下「所有権移転外ファイナンス・リース取引」という)に分類される。
具体的には、ファイナンス・リース取引のうち、次の①から③のいずれかに該当する場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引に該当するものとし、それ以外のファイナンス・リース取引は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当するものとする。
① リース契約上、リース期間終了後またはリース期間の中途で、リース物件の所有権が借手に移転することとされているリース取引
② リース契約上、借手に対して、リース期間終了後またはリース期間の中途で、名目的価額またはその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利(以下合わせて「割安購入選択権」という)が与えられており、その行使が確実に予想されるリース取引
③リース物件が、借手の用途等に合わせて特別の仕様により製作または建設されたものであって、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再びリースまたは売却することが困難であるため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなリース取引
4.売買とされるリース取引
法人税法では、法人税法上のリース取引が次のいずれかに該当するものまたはこれらに準ずるものであるときは、そのリース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとして計算することが規定されている(法令136の3第1項)。
① リース期間(リース取引に係る賃貸借期間をいう。以下この項において同じ)終了の時またはリース期間の中途において、リース資産が無償または名目的な対価の額でその賃借人に譲渡されるものであること。
② その賃借人に対し、リース期間終了の時またはリース期間の中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
③ リース資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、リース資産がその使用可能期間中その賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであることまたはリース資産の識別が困難であると認められるものであること。
④ リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当の差異があるもの(その賃貸人またはその賃借人の法人税または所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る)であること。
Ⅱ リース会計基準の変更点
リース取引に係る会計基準(案)では、ファイナンス・リース取引に係る会計基準を以下のように変更している。
1.所有権移転外ファイナンス・リース取引の「賃貸借処理」を廃止
リース会計基準(現行)においても、ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理(以下「売買処理」という)を行うことになっていたが、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」については、公認会計士監査を要する上場企業においても、リース会計基準(現行)で例外処理として認められてきた通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理(以下「賃貸借処理」という)を行う例が大多数となっていた(財務諸表には、重要な会計方針(リース取引の処理方法)に、「リース物件の所有権が借主に移転するものと認められるもの以外にファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。」と記載され、リース取引関係の注記としてリース会計基準が定める事項(リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額等)が記載される)。
借手においてはリース資産およびリース債務の計上金額(貸手においてはリース債権の計上価額および受取リース料の処理)などに(複雑な)計算手続が要求される「売買処理」に比べて、「賃貸借処理」の場合は、支払(受取)リース料を費用(収益)に計上することで簡便な方法である。
2.借手側の会計処理
リース会計基準(案)では、所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理の主な内容(借手)を下記のように定めている。
下記の内容を検証すると、「売買処理」では、借手はリース取引開始日において、リース資産(B/S上の資産)およびリース債務(B/S上の負債)を計上する。リース資産(リース負債)として計上する価額は、リース料総額の現在価値や見積現金購入価額などから導き出すことになるが、リース料総額は、減価償却の対象になるリース資産の額と利息相当額の総額に区分されることになる。
リース資産はリース期間を耐用年数として(残存価額は原則0)償却することになり、利息相当額の総額は利息法(各期の支払利息相当額をリース債務の未返済元本残高に一定の利率を乗じて算定する方法)により、各期に配分し、支払利息として計上する。
所有権移転内ファイナンス・リース取引の会計処理の主な内容(借手)
・リース取引開始日に、リース物件とこれに係る負債を、リース資産およびリース債務として計上する。
・リース取引開始日におけるリース資産とリース債務の計上額は、リース料総額の現在価値と貸手の購入価額等(貸手の購入価額等が明らかでない場合は借手の見積現金購入価額)とのいずれか低い額による。
・利息相当額の総額は、原則としてリース期間にわたり利息法により配分するが、リース資産総額に重要性がないと認められる場合は、次のいずれかの方法を採用することができる。
①リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法による。この場合、リース資産およびリース債務は、リース料総額で計上され、支払利息は計上されず、減価償却費のみが計上される。
②利息相当額の総額をリース期間にわたり定額法で配分する。
・リース資産の減価償却費については、原則として、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する。償却方法については自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一である必要はなく、企業の実態に応じたものを選択する。
・リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引など少額のリース資産や、リース期間が1年以内のリース取引については、簡便的に、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができる。
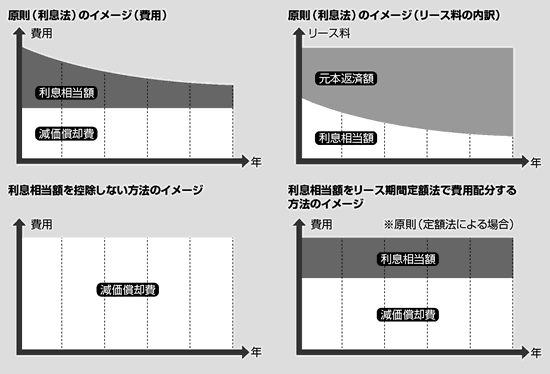
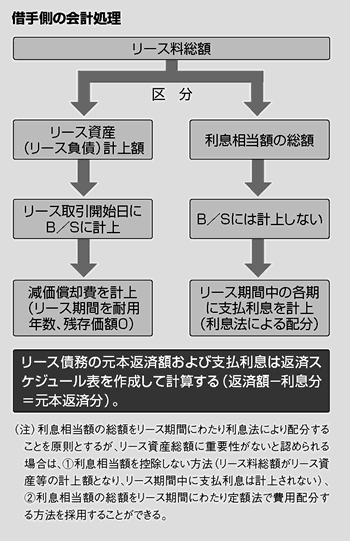
3.貸手側の会計処理
リース会計基準(案)では、所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理の主な内容(貸手)を次頁のように定めている。
適用指針(案)では、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る基本となる会計処理として次の3つの方法を定めており、受取利息相当額の金額は①~③のいずれの方法を採用しても同額であり、各期の利益は同額である。
① リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法
② リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法
③ 売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法
①および②の方法は割賦販売取引と平仄を合わせたものとしたほうがわかりやすいと思われる。①の方法は、リース料総額の売上高を計上したうえで、各期末に代金回収未済の繰延リース利益を繰り入れて利益を繰り延べる。②の方法は、各期での受取リース料を売上高として計上し、売上高に対応する売上原価を計上する。③の方法は、ファイナンス・リース取引の金融取引としての性格から売上高(および売上原価)を計上するのではなく、リース料総額とリース物件の現金購入価額との差額を受取利息相当額として取り扱ったものである。
基本となる会計処理はいずれの方法を採用しても、「売買処理」においては、毎期の収益は利息法で配分される。リース投資資産は元本の回収に伴い逓減することになるため.新会計基準(利息法)では右図のように収益も逓減することになる。
しかしながら、適用指針(案)では、借手側の会計処理と同様に、「貸手としてのリース取引に重要性がないと認められる場合(未経過リース料及び見積残存価額の合計額の期末残高が当該期末残高及び営業債権の期末残高の合計額に占める割合が10%未満の場合)は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額で配分することができる。」(適用指針(案)57、58項)と定めている。
所有権移転内ファイナンス・リース取引の会計処理の主な内容(貸手)
・貸手における利息相当額の総額は、リース取引開始日に合意されたリース料総額および見積残存価額の合計額から、これに対応するリース資産の取得価額を控除することによって算定する。
・利息相当額の総額は、原則として、リース期間にわたり利息法により配分するが、貸手としてのリース取引に重要性がないと認められる場合は、リース期間にわたり定額で配分することができる。
・通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により計上された資産は、「リース投資資産」として表示する。リース投資資産は、当該企業の主目的たる営業取引により生じたものである場合には流動資産に表示する。また、当該企業の営業の主目的以外の取引により発生したものである場合には、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものは流動資産に表示し、入金の期限が1年を超えて到来するものは固定資産に表示する。
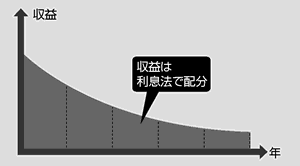
Ⅲ 平成19年度税制改正大綱におけるリース会計基準(案)への対応
(1)ファイナンス・リースに該当するリース取引のうちリース期間の終了の時にリース資産が無償又は名目的な対価の額で賃借人に譲渡されるものであること等の要件に該当しないもの(以下「所有権移転外ファイナンス・リース取引」という。)は、売買取引とみなす。
リース会計基準(案)が「所有権移転外ファイナンス・リース取引」について「売買処理」することに対応させ、税務上「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は売買取引とみなすことにする。
これまでの法人税法施行令136条の3の規定振りで、当該規定が固有に「売買」とする要件の規定部分(前述Ⅰ4(売買とされるリース取引)参照)は見直されることになると予想されるが、一方でリース料を償却費として取り扱うことの規定の整備を行うこと(後述(5)参照)としているため、税法固有の要件の取扱いは予断を許さない(今後の法令等の規定振りに要注目といえよう)。
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃借人のリース資産の償却方法は、リース期間定額法(償却期間をリース期間とし、残存価額をゼロとする定額法をいう。)とする。
リース会計基準(案)では、「所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、原則として、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する。」(リース会計基準(案)12項後段)と定められている。
また、「リース資産の償却方法は、定額法、級数法、生産高比例法等の中から企業の実態に応じたものを選択適用する。この場合、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により減価償却費を算定する必要はない。」(適用指針(案)27項)とされており、「残存価額を10%として計算した定率法による減価償却費に簡便的に10/9を乗じた額を各期の減価償却費相当額とする方法も認められる。」(適用指針(案)105項)と解説されている。
税法が採用することになるリース期間定額法は、必ずしもリース会計基準(案)の内容をすべて容認したものではないが、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、企業のほとんどが「賃貸借処理」により、リース期間において平準して費用計上してきた実態にも合致するものとして、償却方法を「リース期間定額法」に規定するものということになる。
なお、リース資産の償却方法が「リース期間定額法」で行われることになれば、①リース料総額から利息相当額の総額を控除しない場合、②リース料総額から利息相当額の総額をリース期間にわたり定額法で控除する場合には、リース期間中の各期の費用計上額(減価償却費+利息相当額)が定額(リース料総額/リース期間)になるため、現行の「賃貸借処理」と同内容の処理として、リースの簡便性を維持することができる。
(3)所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸人について、リース料総額から減価を控除した金額(以下「リース利益額という。」のうち、実質的に受取利息と認められる部分の金額(リース利益額の20%相当額)を利息法により収益計上し、それ以外の部分の金額をリース期間にわたって均等額により収益計上することができることとする。
リース会計基準(案)では、所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸人について、「売買処理」と見直されることになる。「売買処理」においては、利息相当額の総額は、原則としてリース期間にわたり利息法により各期に配分される。
しかし、所有権移転外ファイナンス・リース取引には、「法的には賃貸借の性格を有し、また、役務提供が組み込まれる場合が多く、複合的な性格を有する。」などの性格も有するため、適用指針(案)においても、「維持管理費用相当額や通常の保守等の役務提供相当額は、原則としてリース料総額とは区分する。」と定められている。
利息法では、収益が前倒しで計上されるため、賃貸人の課税所得に影響を与える懸念が示されていた。維持管理費用等の課税上の取扱いが懸案となっていたのである。
平成19年度税制改正大綱では、所有権移転外ファイナンス・リース取引の性格に基づき、利息法が適用される「実質的に受取利息と認められる部分の金額」をリース利益額の20%相当額に限定することで、収益の前倒し計上による課税所得に与えるインパクトを軽減する措置が設けられる(次頁の図を参照)。
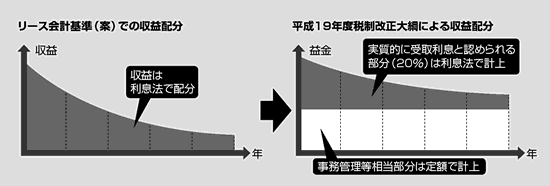
(4)平成20年4月1日前に締結したリース契約に係る所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸資産について、同日以後に終了する事業年度からリース期間定額法により償却できることとする。
平成19年度税制改正大綱における上記(1)から(3)までの改正は、平成20年4月1日以後に締結するリース契約に係る所有権移転外ファイナンス・リース取引について適用するとされており、平成20年4月1日前に締結したリース契約に係る所有権移転外ファイナンス・リース取引の課税関係は、売買とされるリース取引(前述Ⅰ4)に該当しないものについては、賃貸借取引となる。
賃貸人においては、平成20年4月1日前に締結した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る受取リース料が賃貸借処理により益金の額に算入されることになるが、その賃貸資産については、リース会計基準(案)の適用により、売買処理に変更することが原則となっている。すなわち、賃貸人には売却損益などが生じることにはなるが、賃貸資産が売却されていることで、受取リース料に期間的に対応した減価償却費の計上は見込めないことになる。
そのため、賃貸人の平成20年4月1日前に締結したリース契約の賃貸資産について、平成20年4月1日以後に終了する事業年度からリース期間定額法により償却できる措置が税制上手当てされることになる。
(5)所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃借人が賃借料として経理した場合においてもこれを償却費として取り扱うことその他所要の規定の整備を行う。
リース会計基準(案)においては、「個々のリース資産に重要性がないと認められる場合は、「賃貸借処理」を行うことができる。」と簡便的な取扱いを定めており、個々のリース資産に重要性がないと認められる場合を以下のように定めている。
① 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、リース料総額が当該基準額以下のリース取引(ただし書省略)
② リース期間が1年以内のリース取引
③ 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額(維持管理費用相当額または通常の保守等の役務提供相当額のリース料総額に占める割合が重要な場合には、その合理的見積額を除くことができる)が300万円以下のリース取引
平成19年度税制改正大綱では、上記の簡便的な取扱いによった場合(賃借料として経理した場合)においても、当該賃借料を償却費として取り扱うことで、(償却限度額がリース期間定額法で算定されることから)賃借料の損金算入を認めること等の整備が行われる。
(さじ・としお)
リース会計基準案の公表とリース会計基準の変更に伴う所要の税制措置について
T&Amaster編集部 佐治俊夫
企業会計基準委員会は12月27日、リース取引に関する会計基準および同適用指針の公開草案(以下「リース会計基準(案)」という)を公表した(リース会計基準(案)の概要は本誌194号14頁を参照)。また、平成19年度税制改正大綱では、リース会計基準の変更に伴う税制の整備が盛り込まれた。新しいリース会計・リース税制を探ってみることにする。
なお、本稿は平成19年度税制改正大綱とリース会計基準(案)の公表から、リース会計基準の見直しに伴うリース税制との関連に焦点を当てたものであり、リース会計基準(案)の内容を網羅的に解説することを試みたものではない。リース税制についても、今後明らかにされる法令・通達により、具体的かつ精緻な規定が整備されよう。
Ⅰ リース取引の分類
1.リース取引の分類が前提
リース会計基準(案)に定められた会計処理の内容や税制措置を検討する前に、リース取引の分類を確認しておきたい。リース会計基準(案)では以下のようにリース取引を分類したうえで、貸手・借手の会計処理を規定している。これは現行のリース取引に係る会計基準(以下「リース会計基準(現行)」という)が形式的にはリース取引を①ファイナンス・リースと②オペレーティング・リース取引の2種類に分類し、実質的にはファイナンス・リース取引を所有権移転ファインナンス・リース取引と所有権移転外ファイナンス・リース取引に異なる会計処理を認めていたことからすれば、リース取引について、より実態に合致させたものと評価することができる。
また、法人税法(施行令・通達)では、リース会計基準上のファイナンス・リース取引をリース取引と定義したうえで、そのリース取引のうち売買取引として取り扱うものと金融取引として取り扱うものの範囲を定めている。
リース取引については、会計上の分類や税務上売買として取り扱うリース取引に該当するかどうかによって、会計処理(あるいは税務上の取扱い)が定められていることから、まずは、リース取引の分類が実務における会計処理などの前提になってくる。
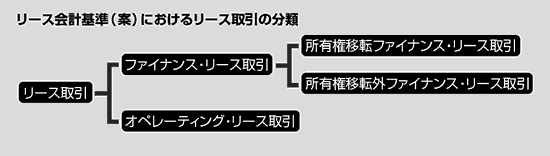
2.ファイナンス・リース取引(税務上の「リース取引」)
リース取引は、「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」に分類される。
「ファイナンス・リース取引」とは、リース期間の中途においてリース契約を解除することができないリース取引またはこれに準ずるリース取引で、借手が、リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。
「オペレーティング・リース取引」とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。
「ファイナンス・リース取引」は、「解約不能」と「フルペイアウト(借手が、リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担すること)」を内容とするものであり、法人税法施行令136条の3(リース取引に係る所得の計算)の3項においても、同旨の要件を満たすものを「リース取引」と定義している。
しかし、第1の条件の「解約不能」については、法的形式上は解約可能であるとしても、解約に際し相当の違約金を支払わなければならない等の理由から事実上解約不能と認められるリース取引(これに準ずるリース取引)を含むものであり、契約条項の内容、商慣習等を勘案し契約の実態に応じ判断される。第2の条件である「フルペイアウト」については、「実質的に」の判断が求められることになる。
リース会計基準の適用指針(案)では、具体的な判定基準(①現在価値基準、②経済的耐用年数基準)が示されている。また、法人税基本通達では、「リース取引」について、①解除をすることができないものに準ずるものの意義(法基通12の5-1-1)、②資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきことの意義(法基通12の5-1-2)、③おおむね全部の判定(法基通12の5-1-3)の解釈を明確化させている。
3.所有権移転外ファイナンス・リース取引
「ファイナンス・リース取引」は、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの(以下「所有権移転ファイナンス・リース取引」という)とそれ以外の取引(以下「所有権移転外ファイナンス・リース取引」という)に分類される。
具体的には、ファイナンス・リース取引のうち、次の①から③のいずれかに該当する場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引に該当するものとし、それ以外のファイナンス・リース取引は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当するものとする。
① リース契約上、リース期間終了後またはリース期間の中途で、リース物件の所有権が借手に移転することとされているリース取引
② リース契約上、借手に対して、リース期間終了後またはリース期間の中途で、名目的価額またはその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利(以下合わせて「割安購入選択権」という)が与えられており、その行使が確実に予想されるリース取引
③リース物件が、借手の用途等に合わせて特別の仕様により製作または建設されたものであって、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再びリースまたは売却することが困難であるため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなリース取引
4.売買とされるリース取引
法人税法では、法人税法上のリース取引が次のいずれかに該当するものまたはこれらに準ずるものであるときは、そのリース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとして計算することが規定されている(法令136の3第1項)。
① リース期間(リース取引に係る賃貸借期間をいう。以下この項において同じ)終了の時またはリース期間の中途において、リース資産が無償または名目的な対価の額でその賃借人に譲渡されるものであること。
② その賃借人に対し、リース期間終了の時またはリース期間の中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
③ リース資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、リース資産がその使用可能期間中その賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであることまたはリース資産の識別が困難であると認められるものであること。
④ リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当の差異があるもの(その賃貸人またはその賃借人の法人税または所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る)であること。
Ⅱ リース会計基準の変更点
リース取引に係る会計基準(案)では、ファイナンス・リース取引に係る会計基準を以下のように変更している。
| リース会計基準(現行) | リース会計基準(案) | |
| 借手側の会計処理 | ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。 | ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う(公開草案9項)。 |
| ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の取引(⇒所有権移転外ファイナンス・リース取引)については、通常の賃貸借に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。ただし、この場合には、次に掲げる事項を財務諸表に注記しなければならない。 | 所有権移転外ファイナンス・リース取引について認められてきた「賃貸借処理」の会計処理を廃止し、「売買処理」の会計処理を行うこととなる。 | |
| 貸手側の会計処理 | ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。 | ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う(公開草案9項)。 |
| ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の取引(⇒所有権移転外ファイナンス・リース取引)については、通常の賃貸借に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。ただし、この場合には、次に掲げる事項を財務諸表に注記しなければならない。 | 所有権移転外ファイナンス・リース取引について認められてきた「賃貸借処理」の会計処理を廃止し、「売買処理」の会計処理を行うこととなる。 |
1.所有権移転外ファイナンス・リース取引の「賃貸借処理」を廃止
リース会計基準(現行)においても、ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理(以下「売買処理」という)を行うことになっていたが、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」については、公認会計士監査を要する上場企業においても、リース会計基準(現行)で例外処理として認められてきた通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理(以下「賃貸借処理」という)を行う例が大多数となっていた(財務諸表には、重要な会計方針(リース取引の処理方法)に、「リース物件の所有権が借主に移転するものと認められるもの以外にファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。」と記載され、リース取引関係の注記としてリース会計基準が定める事項(リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額等)が記載される)。
借手においてはリース資産およびリース債務の計上金額(貸手においてはリース債権の計上価額および受取リース料の処理)などに(複雑な)計算手続が要求される「売買処理」に比べて、「賃貸借処理」の場合は、支払(受取)リース料を費用(収益)に計上することで簡便な方法である。
2.借手側の会計処理
リース会計基準(案)では、所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理の主な内容(借手)を下記のように定めている。
下記の内容を検証すると、「売買処理」では、借手はリース取引開始日において、リース資産(B/S上の資産)およびリース債務(B/S上の負債)を計上する。リース資産(リース負債)として計上する価額は、リース料総額の現在価値や見積現金購入価額などから導き出すことになるが、リース料総額は、減価償却の対象になるリース資産の額と利息相当額の総額に区分されることになる。
リース資産はリース期間を耐用年数として(残存価額は原則0)償却することになり、利息相当額の総額は利息法(各期の支払利息相当額をリース債務の未返済元本残高に一定の利率を乗じて算定する方法)により、各期に配分し、支払利息として計上する。
所有権移転内ファイナンス・リース取引の会計処理の主な内容(借手)
・リース取引開始日に、リース物件とこれに係る負債を、リース資産およびリース債務として計上する。
・リース取引開始日におけるリース資産とリース債務の計上額は、リース料総額の現在価値と貸手の購入価額等(貸手の購入価額等が明らかでない場合は借手の見積現金購入価額)とのいずれか低い額による。
・利息相当額の総額は、原則としてリース期間にわたり利息法により配分するが、リース資産総額に重要性がないと認められる場合は、次のいずれかの方法を採用することができる。
①リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法による。この場合、リース資産およびリース債務は、リース料総額で計上され、支払利息は計上されず、減価償却費のみが計上される。
②利息相当額の総額をリース期間にわたり定額法で配分する。
・リース資産の減価償却費については、原則として、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する。償却方法については自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一である必要はなく、企業の実態に応じたものを選択する。
・リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引など少額のリース資産や、リース期間が1年以内のリース取引については、簡便的に、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができる。
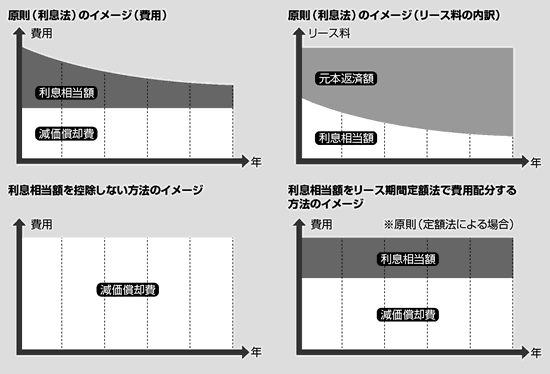
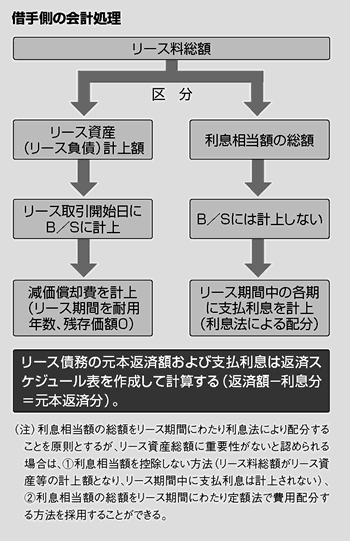
3.貸手側の会計処理
リース会計基準(案)では、所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理の主な内容(貸手)を次頁のように定めている。
適用指針(案)では、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る基本となる会計処理として次の3つの方法を定めており、受取利息相当額の金額は①~③のいずれの方法を採用しても同額であり、各期の利益は同額である。
① リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法
② リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法
③ 売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法
①および②の方法は割賦販売取引と平仄を合わせたものとしたほうがわかりやすいと思われる。①の方法は、リース料総額の売上高を計上したうえで、各期末に代金回収未済の繰延リース利益を繰り入れて利益を繰り延べる。②の方法は、各期での受取リース料を売上高として計上し、売上高に対応する売上原価を計上する。③の方法は、ファイナンス・リース取引の金融取引としての性格から売上高(および売上原価)を計上するのではなく、リース料総額とリース物件の現金購入価額との差額を受取利息相当額として取り扱ったものである。
基本となる会計処理はいずれの方法を採用しても、「売買処理」においては、毎期の収益は利息法で配分される。リース投資資産は元本の回収に伴い逓減することになるため.新会計基準(利息法)では右図のように収益も逓減することになる。
しかしながら、適用指針(案)では、借手側の会計処理と同様に、「貸手としてのリース取引に重要性がないと認められる場合(未経過リース料及び見積残存価額の合計額の期末残高が当該期末残高及び営業債権の期末残高の合計額に占める割合が10%未満の場合)は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額で配分することができる。」(適用指針(案)57、58項)と定めている。
所有権移転内ファイナンス・リース取引の会計処理の主な内容(貸手)
・貸手における利息相当額の総額は、リース取引開始日に合意されたリース料総額および見積残存価額の合計額から、これに対応するリース資産の取得価額を控除することによって算定する。
・利息相当額の総額は、原則として、リース期間にわたり利息法により配分するが、貸手としてのリース取引に重要性がないと認められる場合は、リース期間にわたり定額で配分することができる。
・通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により計上された資産は、「リース投資資産」として表示する。リース投資資産は、当該企業の主目的たる営業取引により生じたものである場合には流動資産に表示する。また、当該企業の営業の主目的以外の取引により発生したものである場合には、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものは流動資産に表示し、入金の期限が1年を超えて到来するものは固定資産に表示する。
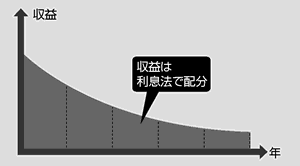
Ⅲ 平成19年度税制改正大綱におけるリース会計基準(案)への対応
(1)ファイナンス・リースに該当するリース取引のうちリース期間の終了の時にリース資産が無償又は名目的な対価の額で賃借人に譲渡されるものであること等の要件に該当しないもの(以下「所有権移転外ファイナンス・リース取引」という。)は、売買取引とみなす。
リース会計基準(案)が「所有権移転外ファイナンス・リース取引」について「売買処理」することに対応させ、税務上「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は売買取引とみなすことにする。
これまでの法人税法施行令136条の3の規定振りで、当該規定が固有に「売買」とする要件の規定部分(前述Ⅰ4(売買とされるリース取引)参照)は見直されることになると予想されるが、一方でリース料を償却費として取り扱うことの規定の整備を行うこと(後述(5)参照)としているため、税法固有の要件の取扱いは予断を許さない(今後の法令等の規定振りに要注目といえよう)。
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃借人のリース資産の償却方法は、リース期間定額法(償却期間をリース期間とし、残存価額をゼロとする定額法をいう。)とする。
リース会計基準(案)では、「所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、原則として、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する。」(リース会計基準(案)12項後段)と定められている。
また、「リース資産の償却方法は、定額法、級数法、生産高比例法等の中から企業の実態に応じたものを選択適用する。この場合、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により減価償却費を算定する必要はない。」(適用指針(案)27項)とされており、「残存価額を10%として計算した定率法による減価償却費に簡便的に10/9を乗じた額を各期の減価償却費相当額とする方法も認められる。」(適用指針(案)105項)と解説されている。
税法が採用することになるリース期間定額法は、必ずしもリース会計基準(案)の内容をすべて容認したものではないが、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、企業のほとんどが「賃貸借処理」により、リース期間において平準して費用計上してきた実態にも合致するものとして、償却方法を「リース期間定額法」に規定するものということになる。
なお、リース資産の償却方法が「リース期間定額法」で行われることになれば、①リース料総額から利息相当額の総額を控除しない場合、②リース料総額から利息相当額の総額をリース期間にわたり定額法で控除する場合には、リース期間中の各期の費用計上額(減価償却費+利息相当額)が定額(リース料総額/リース期間)になるため、現行の「賃貸借処理」と同内容の処理として、リースの簡便性を維持することができる。
(3)所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸人について、リース料総額から減価を控除した金額(以下「リース利益額という。」のうち、実質的に受取利息と認められる部分の金額(リース利益額の20%相当額)を利息法により収益計上し、それ以外の部分の金額をリース期間にわたって均等額により収益計上することができることとする。
リース会計基準(案)では、所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸人について、「売買処理」と見直されることになる。「売買処理」においては、利息相当額の総額は、原則としてリース期間にわたり利息法により各期に配分される。
しかし、所有権移転外ファイナンス・リース取引には、「法的には賃貸借の性格を有し、また、役務提供が組み込まれる場合が多く、複合的な性格を有する。」などの性格も有するため、適用指針(案)においても、「維持管理費用相当額や通常の保守等の役務提供相当額は、原則としてリース料総額とは区分する。」と定められている。
利息法では、収益が前倒しで計上されるため、賃貸人の課税所得に影響を与える懸念が示されていた。維持管理費用等の課税上の取扱いが懸案となっていたのである。
平成19年度税制改正大綱では、所有権移転外ファイナンス・リース取引の性格に基づき、利息法が適用される「実質的に受取利息と認められる部分の金額」をリース利益額の20%相当額に限定することで、収益の前倒し計上による課税所得に与えるインパクトを軽減する措置が設けられる(次頁の図を参照)。
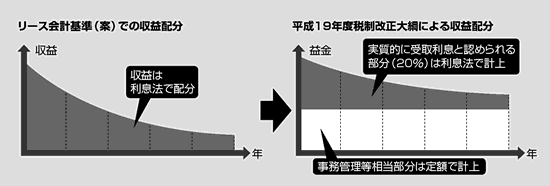
(4)平成20年4月1日前に締結したリース契約に係る所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸資産について、同日以後に終了する事業年度からリース期間定額法により償却できることとする。
平成19年度税制改正大綱における上記(1)から(3)までの改正は、平成20年4月1日以後に締結するリース契約に係る所有権移転外ファイナンス・リース取引について適用するとされており、平成20年4月1日前に締結したリース契約に係る所有権移転外ファイナンス・リース取引の課税関係は、売買とされるリース取引(前述Ⅰ4)に該当しないものについては、賃貸借取引となる。
賃貸人においては、平成20年4月1日前に締結した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る受取リース料が賃貸借処理により益金の額に算入されることになるが、その賃貸資産については、リース会計基準(案)の適用により、売買処理に変更することが原則となっている。すなわち、賃貸人には売却損益などが生じることにはなるが、賃貸資産が売却されていることで、受取リース料に期間的に対応した減価償却費の計上は見込めないことになる。
そのため、賃貸人の平成20年4月1日前に締結したリース契約の賃貸資産について、平成20年4月1日以後に終了する事業年度からリース期間定額法により償却できる措置が税制上手当てされることになる。
(5)所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃借人が賃借料として経理した場合においてもこれを償却費として取り扱うことその他所要の規定の整備を行う。
リース会計基準(案)においては、「個々のリース資産に重要性がないと認められる場合は、「賃貸借処理」を行うことができる。」と簡便的な取扱いを定めており、個々のリース資産に重要性がないと認められる場合を以下のように定めている。
① 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、リース料総額が当該基準額以下のリース取引(ただし書省略)
② リース期間が1年以内のリース取引
③ 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額(維持管理費用相当額または通常の保守等の役務提供相当額のリース料総額に占める割合が重要な場合には、その合理的見積額を除くことができる)が300万円以下のリース取引
平成19年度税制改正大綱では、上記の簡便的な取扱いによった場合(賃借料として経理した場合)においても、当該賃借料を償却費として取り扱うことで、(償却限度額がリース期間定額法で算定されることから)賃借料の損金算入を認めること等の整備が行われる。
(さじ・としお)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















