コラム2007年09月03日 【編集部レポート】 ブルドックソース買収防衛策に係る裁判所決定を読み解く(2)(2007年9月3日号・№225)
ブルドックソース買収防衛策に係る裁判所決定を読み解く(2)
株主平等原則に関する判断は?
text 編集部
前回(本誌224号19頁参照)は事件の経過や申立て時の詳細な主張等について紹介したが、今回は主要争点の1つとなった「株主平等原則に違反するか」を中心に、東京地裁・東京高裁・最高裁がどのように判断したかを決定文を通じて紹介する。なお、スティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンド(オフショア)、エル・ピー(SPJSF)は8月24日、最高裁決定後も条件を変更して継続していたブルドックソース(ブル社)株式の公開買付け(TOB)について、応募株式数が1,318,456株(発行済株式総数の約1.89%)であったと発表。結果、SPJSF側として発行済株式総数の約5.41%を保有することになっている。
決定文の構成をみると……
一連の裁判所決定では、SPJSFの申立てを東京地裁は却下し、これに対する抗告を東京高裁は棄却、さらなる判断を求めて行われた抗告を最高裁も棄却したことから、結論としては共通してブル社の買収防衛策を認容するものとなっているが、各決定で示された判断には差異がみられる。
買収防衛策の導入前か後か、本件割当ての実行前か後かなど事件の経過に応じ(前号19頁図表1参照)、両者の主張にも若干の変遷がみられるが(当初申立段階の主張につき、前号21頁図表3参照)、裁判所の各決定の構成(今号21頁表2参照)をみると、東京地裁と東京高裁においては、まず①新株予約権無償割当てに係る会社法247条の類推適用の可否が検討された後、②本件新株予約権無償割当てが株主平等原則に反し、法令に違反する場合に該当するか、③本件新株予約権無償割当てが著しく不公正な方法により行われる場合に該当するかが検討され、続いて、④本件新株予約権無償割当てが定款に違反する場合に該当するかが述べられている。
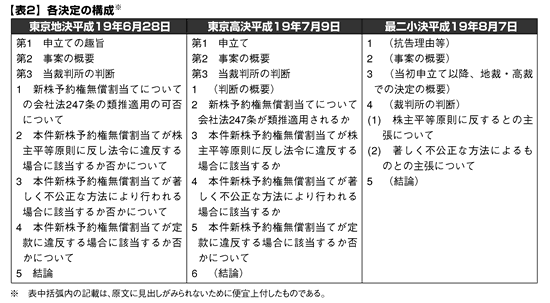
この点、最高裁決定では、事案・経緯は簡潔に整理され、判断も上記②・③に絞って示されるものとなった。
以下では、各決定の内容を紹介するが、決定原文を参照できるよう、SPJSF(側)およびブル社をそれぞれ表1のようにいうことがあるので注意されたい。

会社法247条の類推適用の可否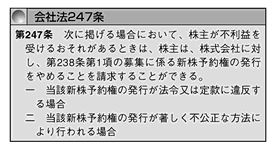
株主平等原則に違反するか否かについては、まず、新株予約権無償割当てについて会社法247条が類推適用され、ひいては新株予約権無償割当てに関する差止請求権が認められるかが前提問題として判断される構成が、東京地裁・東京高裁では採られている。
東京地裁決定は、表3中の前段のように規範を定めたうえで、後段のように本件割当てへの類推適用を肯定している。次の①~④のような論理展開のもと、④の(ア)~(ウ)のように3つの理由を掲げるものであった。
① 新株予約権無償割当てについて247条を直接適用できないことは明らかである。
② 247条の趣旨は、募集新株予約権の発行について、法令もしくは定款違反または不公正な方法による発行により不利益を受けるおそれがある株主を事前に救済するということにある。
③ 一方、新株予約権無償割当ては、通常は株主が不利益を受けるおそれを想定することができない。そのため、差止請求権が規定されなかったものと解される。
④ これに対し、本件割当てにより割り当てられる本件新株予約権には、新株予約権者を差別的に取り扱う行使条件が付されており、その結果、既存株主としての地位に実質的な変動が生じ、持株比率および保有株式の経済的価値の低下という不利益を受けるおそれが生じることになる。(ア)このようなおそれは、募集新株予約権の発行が法令等に違反する場合または当該発行が著しく不公正な方法により行われる場合に既存株主に生ずる不利益のおそれと本質的に異なる性質のものではなく、また、(イ)このような差別的行使条件を付した新株予約権無償割当ては、債権者関係者を除く株主に対する募集新株予約権の発行と実質的には異なるところがないが、後者の場合に差止請求権の行使が可能であるのに対し、前者の場合に差止請求権の行使ができない結果となることに合理的な理由を見出すことは困難で、さらに、(ウ)平成17年法律第87号による改正前の商法では、無償で新株予約権を発行する場合についても新株予約権発行の差止請求権が認められていたところ、会社法では、新株予約権無償割当てが原則として既存株主に不利益を及ぼすものでないため差止請求権を規定しなかったもので、既存株主の地位に実質的な変動を及ぼす場合にまで差止請求権を排除する趣旨であるとは解し難い。
東京高裁決定は、この争点について東京地裁決定を引用する形で肯定した。
最高裁決定は、「法109条1項に定める株主平等の原則の趣旨は、新株予約権無償割当ての場合についても及ぶ」と述べるのみであるが、法令等違反の判断にあたって類推適用を前提としているものと考えられる(表3参照)。
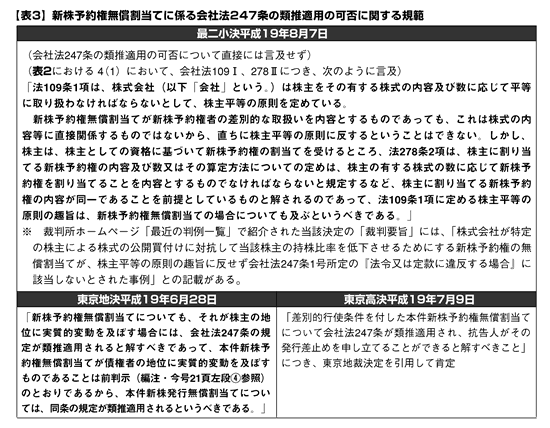
株主平等原則違反への該当性
株主平等原則に違反するか否かについて、次に、株主平等原則とはそもそも何か、これに違反しない場合はどのような場合か、本件割当ては法令等に違反するかが検討されている。
東京地裁決定は、(1)「差別的行使条件等を付した新株予約権無償割当てに株主平等原則の適用があるか否かについて」を述べた後、(2)本件割当てが原則に違反するかどうかを判断する構成である。(1)では、表4の①・②のように述べたうえで、その理由として、(ア)「株主は、新株予約権無償割当てを、株主としての資格に基づいて受けているものというべきであって、当該新株予約権の内容が株主平等原則と関係しないとは解し難い」、(イ)「(会社法278条2項の規定は株式無償割当てに係る)186条2項とほぼ同一の規定であるから、新株予約権無償割当ても、株主に割り当てられる新株予約権が実質的に同一の内容であることを前提とするものと解するのが自然である」など3つを掲げる。
その後、株主平等原則について会社法が定める例外的な取扱いに照らし、本件割当ての定める差別的な行使条件および取得条項に基づく債権者関係者の不利益が許容されるかを検討。
このうえで、③を述べ、既に特別決議は経ているため、「経済的利益が平等に確保されているといえるか」を検討し、「債権者関係者が有する本件新株予約権を債務者が取得した場合に債権者関係者が交付を受ける1個当たり396円という対価は、本件新株予約権の価値に見合ったものということができ、本件新株予約権無償割当てにおいて、債権者関係者の株主としての経済的利益は平等に確保されていると一応認められる」と述べて、本件割当てが株主平等原則にも会社法278条2項にも違反しないと判示した。
なお、SPJSFが、(ア)ブル社が一定の場合にSPJSF側に割り当てられた新株予約権を取得条項に基づいて取得しない余地がある、(イ)ブル社の1個当たり396円の支払いが利益供与に当たる可能性がある、(ウ)新株予約権の時価は396円とは限らず、不服申立ての仕組みもない、(エ)SPJSFの税負担について配慮されていないなどと主張していた点についても仔細に検討。
決定では、それぞれ、(ア)ブル社が396円の対価で譲り受ける旨を取締役会決議し、公表していることに照らすと、「債務者が我が国取引社会においてこれまで培ってきた信用に対する影響を考慮すれば、債務者取締役会が当該決議を撤回することは考えがたく、また、かかる事態を疑わせる事情は何ら認められない」、(イ)「支払は、本件新株予約権の内容としてあらかじめ定められた取得の対価の交付であって、『株主の権利の行使に関して』債権者に供与されるものではない」、(ウ)価格はTOBを実施しているSPVⅡ自身が適切と考える株式の価格に基づき算出されたもので、「債務者による取得又は譲受けの対価として適正を欠くということはできない」「債権者は、本件仮処分申立手続において、……主張、疎明の機会を有する」、(エ)「取得条項に基づく取得の対価又は債務者への譲渡の対価として債務者から金銭の交付を受けた場合に、いかなる課税を受けるのかは不分明であり、新株予約権の行使に基づいて交付を受けた株式を譲渡する場合と比較して債権者関係者が課税面で著しい不利益を受けるものと認めることはできない」などとし、SPJSFの主張を斥けている。
一方、東京高裁決定の枠組みは表4のとおり。新株予約権の発行について、③のように東京地裁決定と同様の解釈を示し、これを前提とする。
しかし、会社法上、特別決議を要件として、新株および新株予約権の有利発行が可能とされ、また、「少数の株主の有する議決権を現金等の対価を供することにより、他のものに代えることも制度上許容している(同法768条)」ことを挙げ、④のように「経済的にも、また、議決権比率の変動の面においても」差別的に取り扱える場合があることを端的に述べて、⑤の場合を原則に反しないと掲げる。
そのうえで、本件割当てについて、「買収防衛策としてその必要性及び相当性を肯定することができ、抗告人関係者に過度ないし不合理に財産的損害を与えないように配慮もされているから、株主間の上記差別的な取扱いについても合理的なものといえる」とし、株主平等原則に反する違法なものとはいえないと判断した。
なお、SPJSFが、株主平等原則の例外となる差別的取扱いについて、法律上明文の規定がある場合や当該取扱いにより不利益を受ける本人の同意が場合に限り認められるにすぎず、仮にこれらの場合以外に認められるとしても極めて高水準の必要性および相当性が要件とされるべき(グリーンメイラーに該当する場合のみ是認されるべき)とした主張については、上述の点からそのように解すべきでないこと、「抗告人関係者が濫用的買収者であることは後に詳述するとおりであ」ることのみを述べて、斥けている。
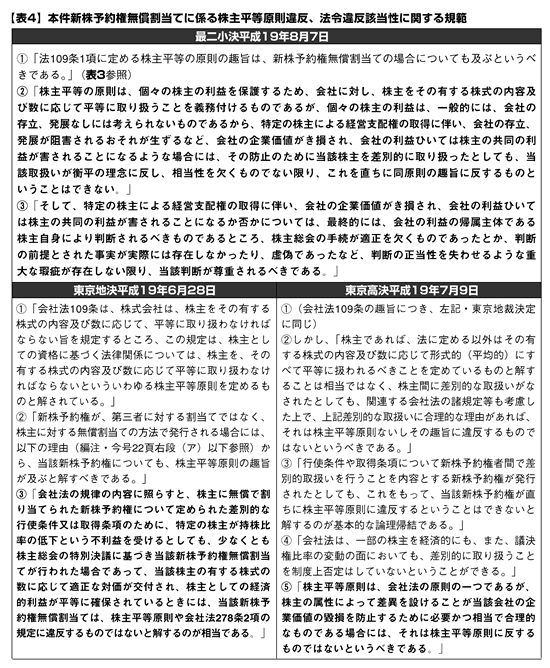
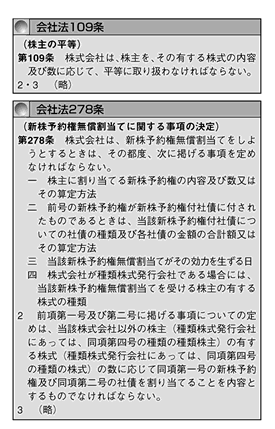
最高裁はどのように判断したか
最高裁で示された判断の枠組みは表4のとおりで、その要点は次のようにまとめられる。
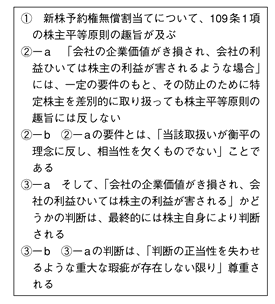
上記②-aの場合としては「特定の株主による経営支配権の取得に伴い、会社の存立、発展が阻害されるおそれが生ずる」場合が、③-bの場合としては「株主総会の手続が適正を欠くものであったとか、判断の前提とされた事実が実際には存在しなかったり、虚偽であった」場合が例示されている。
東京地裁決定・東京高裁決定との相違は、①において、行使条件や取得条項に係る差別的取扱いには言及せずに原則の趣旨が及ぶものとされていること、②において、経済的利益または持株比率変動面における差別的取扱いについても(ここでは)言及していないこと、③において、当該総会判断が「特別決議」によりなされることを求めてはいないことである。
決定は、このような規範に照らし、本件割当てを検討。まず、③-aについて、本件議案が議決権総数の約83.4%の賛成を得て可決されたとし、SPJSFによる経営支配権の取得につき「抗告人関係者以外のほとんどの既存株主が、……相手方の企業価値をき損し、相手方の利益ひいては株主の共同の利益を害することになると判断した」と、次いで、③-bについて、SPJSFが支配権取得後の経営方針を明示しなかったことなどを挙げ、「当該判断に、その正当性を失わせるような重大な瑕疵は認められない」と認定している。
この後、②-bについて検討し、SPJSFの持株比率が大幅に低下することを認定しながらも、(ア)本件割当てが「抗告人関係者も意見を述べる機会のあった本件総会における議論を経て、抗告人関係者以外のほとんどの既存株主が、……必要な措置として是認した」こと、(イ)本件新株予約権の取得の実行により対価として金員の交付を受けられ、また、実行されない場合でも取締役会決議により本件新株予約権の譲渡の申入れによって金員の支払いが受けられること、(ウ)「上記対価は、抗告人関係者が自ら決定した本件公開買付けの買付価格に基づき算定されたもので、本件新株予約権の価値に見合うもの」であることから、本件割当ては衡平の理念に反し、相当性を欠くものとはいえないと判断。
そのうえで結論として、「抗告人関係者が原審(編注・東京高裁決定)のいう濫用的買収者に当たるといえるか否かにかかわらず」、本件割当ては「株主平等の原則の趣旨に反するものではなく、法令等に違反しないというべきである」と述べている。
株主平等原則に関する判断は?
text 編集部
前回(本誌224号19頁参照)は事件の経過や申立て時の詳細な主張等について紹介したが、今回は主要争点の1つとなった「株主平等原則に違反するか」を中心に、東京地裁・東京高裁・最高裁がどのように判断したかを決定文を通じて紹介する。なお、スティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンド(オフショア)、エル・ピー(SPJSF)は8月24日、最高裁決定後も条件を変更して継続していたブルドックソース(ブル社)株式の公開買付け(TOB)について、応募株式数が1,318,456株(発行済株式総数の約1.89%)であったと発表。結果、SPJSF側として発行済株式総数の約5.41%を保有することになっている。
決定文の構成をみると……
一連の裁判所決定では、SPJSFの申立てを東京地裁は却下し、これに対する抗告を東京高裁は棄却、さらなる判断を求めて行われた抗告を最高裁も棄却したことから、結論としては共通してブル社の買収防衛策を認容するものとなっているが、各決定で示された判断には差異がみられる。
買収防衛策の導入前か後か、本件割当ての実行前か後かなど事件の経過に応じ(前号19頁図表1参照)、両者の主張にも若干の変遷がみられるが(当初申立段階の主張につき、前号21頁図表3参照)、裁判所の各決定の構成(今号21頁表2参照)をみると、東京地裁と東京高裁においては、まず①新株予約権無償割当てに係る会社法247条の類推適用の可否が検討された後、②本件新株予約権無償割当てが株主平等原則に反し、法令に違反する場合に該当するか、③本件新株予約権無償割当てが著しく不公正な方法により行われる場合に該当するかが検討され、続いて、④本件新株予約権無償割当てが定款に違反する場合に該当するかが述べられている。
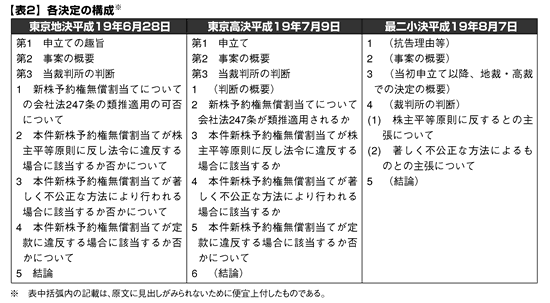
この点、最高裁決定では、事案・経緯は簡潔に整理され、判断も上記②・③に絞って示されるものとなった。
以下では、各決定の内容を紹介するが、決定原文を参照できるよう、SPJSF(側)およびブル社をそれぞれ表1のようにいうことがあるので注意されたい。

会社法247条の類推適用の可否
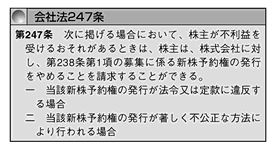
株主平等原則に違反するか否かについては、まず、新株予約権無償割当てについて会社法247条が類推適用され、ひいては新株予約権無償割当てに関する差止請求権が認められるかが前提問題として判断される構成が、東京地裁・東京高裁では採られている。
東京地裁決定は、表3中の前段のように規範を定めたうえで、後段のように本件割当てへの類推適用を肯定している。次の①~④のような論理展開のもと、④の(ア)~(ウ)のように3つの理由を掲げるものであった。
① 新株予約権無償割当てについて247条を直接適用できないことは明らかである。
② 247条の趣旨は、募集新株予約権の発行について、法令もしくは定款違反または不公正な方法による発行により不利益を受けるおそれがある株主を事前に救済するということにある。
③ 一方、新株予約権無償割当ては、通常は株主が不利益を受けるおそれを想定することができない。そのため、差止請求権が規定されなかったものと解される。
④ これに対し、本件割当てにより割り当てられる本件新株予約権には、新株予約権者を差別的に取り扱う行使条件が付されており、その結果、既存株主としての地位に実質的な変動が生じ、持株比率および保有株式の経済的価値の低下という不利益を受けるおそれが生じることになる。(ア)このようなおそれは、募集新株予約権の発行が法令等に違反する場合または当該発行が著しく不公正な方法により行われる場合に既存株主に生ずる不利益のおそれと本質的に異なる性質のものではなく、また、(イ)このような差別的行使条件を付した新株予約権無償割当ては、債権者関係者を除く株主に対する募集新株予約権の発行と実質的には異なるところがないが、後者の場合に差止請求権の行使が可能であるのに対し、前者の場合に差止請求権の行使ができない結果となることに合理的な理由を見出すことは困難で、さらに、(ウ)平成17年法律第87号による改正前の商法では、無償で新株予約権を発行する場合についても新株予約権発行の差止請求権が認められていたところ、会社法では、新株予約権無償割当てが原則として既存株主に不利益を及ぼすものでないため差止請求権を規定しなかったもので、既存株主の地位に実質的な変動を及ぼす場合にまで差止請求権を排除する趣旨であるとは解し難い。
東京高裁決定は、この争点について東京地裁決定を引用する形で肯定した。
最高裁決定は、「法109条1項に定める株主平等の原則の趣旨は、新株予約権無償割当ての場合についても及ぶ」と述べるのみであるが、法令等違反の判断にあたって類推適用を前提としているものと考えられる(表3参照)。
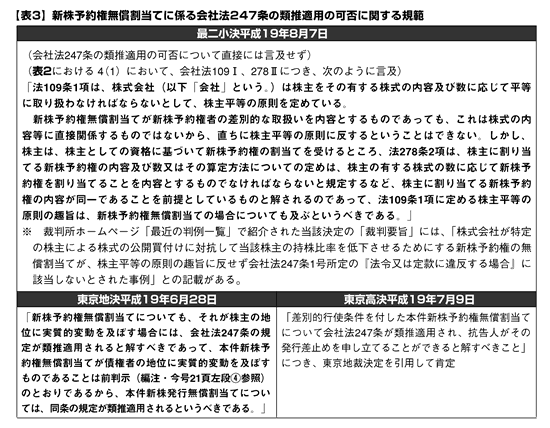
株主平等原則違反への該当性
株主平等原則に違反するか否かについて、次に、株主平等原則とはそもそも何か、これに違反しない場合はどのような場合か、本件割当ては法令等に違反するかが検討されている。
東京地裁決定は、(1)「差別的行使条件等を付した新株予約権無償割当てに株主平等原則の適用があるか否かについて」を述べた後、(2)本件割当てが原則に違反するかどうかを判断する構成である。(1)では、表4の①・②のように述べたうえで、その理由として、(ア)「株主は、新株予約権無償割当てを、株主としての資格に基づいて受けているものというべきであって、当該新株予約権の内容が株主平等原則と関係しないとは解し難い」、(イ)「(会社法278条2項の規定は株式無償割当てに係る)186条2項とほぼ同一の規定であるから、新株予約権無償割当ても、株主に割り当てられる新株予約権が実質的に同一の内容であることを前提とするものと解するのが自然である」など3つを掲げる。
その後、株主平等原則について会社法が定める例外的な取扱いに照らし、本件割当ての定める差別的な行使条件および取得条項に基づく債権者関係者の不利益が許容されるかを検討。
このうえで、③を述べ、既に特別決議は経ているため、「経済的利益が平等に確保されているといえるか」を検討し、「債権者関係者が有する本件新株予約権を債務者が取得した場合に債権者関係者が交付を受ける1個当たり396円という対価は、本件新株予約権の価値に見合ったものということができ、本件新株予約権無償割当てにおいて、債権者関係者の株主としての経済的利益は平等に確保されていると一応認められる」と述べて、本件割当てが株主平等原則にも会社法278条2項にも違反しないと判示した。
なお、SPJSFが、(ア)ブル社が一定の場合にSPJSF側に割り当てられた新株予約権を取得条項に基づいて取得しない余地がある、(イ)ブル社の1個当たり396円の支払いが利益供与に当たる可能性がある、(ウ)新株予約権の時価は396円とは限らず、不服申立ての仕組みもない、(エ)SPJSFの税負担について配慮されていないなどと主張していた点についても仔細に検討。
決定では、それぞれ、(ア)ブル社が396円の対価で譲り受ける旨を取締役会決議し、公表していることに照らすと、「債務者が我が国取引社会においてこれまで培ってきた信用に対する影響を考慮すれば、債務者取締役会が当該決議を撤回することは考えがたく、また、かかる事態を疑わせる事情は何ら認められない」、(イ)「支払は、本件新株予約権の内容としてあらかじめ定められた取得の対価の交付であって、『株主の権利の行使に関して』債権者に供与されるものではない」、(ウ)価格はTOBを実施しているSPVⅡ自身が適切と考える株式の価格に基づき算出されたもので、「債務者による取得又は譲受けの対価として適正を欠くということはできない」「債権者は、本件仮処分申立手続において、……主張、疎明の機会を有する」、(エ)「取得条項に基づく取得の対価又は債務者への譲渡の対価として債務者から金銭の交付を受けた場合に、いかなる課税を受けるのかは不分明であり、新株予約権の行使に基づいて交付を受けた株式を譲渡する場合と比較して債権者関係者が課税面で著しい不利益を受けるものと認めることはできない」などとし、SPJSFの主張を斥けている。
一方、東京高裁決定の枠組みは表4のとおり。新株予約権の発行について、③のように東京地裁決定と同様の解釈を示し、これを前提とする。
しかし、会社法上、特別決議を要件として、新株および新株予約権の有利発行が可能とされ、また、「少数の株主の有する議決権を現金等の対価を供することにより、他のものに代えることも制度上許容している(同法768条)」ことを挙げ、④のように「経済的にも、また、議決権比率の変動の面においても」差別的に取り扱える場合があることを端的に述べて、⑤の場合を原則に反しないと掲げる。
そのうえで、本件割当てについて、「買収防衛策としてその必要性及び相当性を肯定することができ、抗告人関係者に過度ないし不合理に財産的損害を与えないように配慮もされているから、株主間の上記差別的な取扱いについても合理的なものといえる」とし、株主平等原則に反する違法なものとはいえないと判断した。
なお、SPJSFが、株主平等原則の例外となる差別的取扱いについて、法律上明文の規定がある場合や当該取扱いにより不利益を受ける本人の同意が場合に限り認められるにすぎず、仮にこれらの場合以外に認められるとしても極めて高水準の必要性および相当性が要件とされるべき(グリーンメイラーに該当する場合のみ是認されるべき)とした主張については、上述の点からそのように解すべきでないこと、「抗告人関係者が濫用的買収者であることは後に詳述するとおりであ」ることのみを述べて、斥けている。
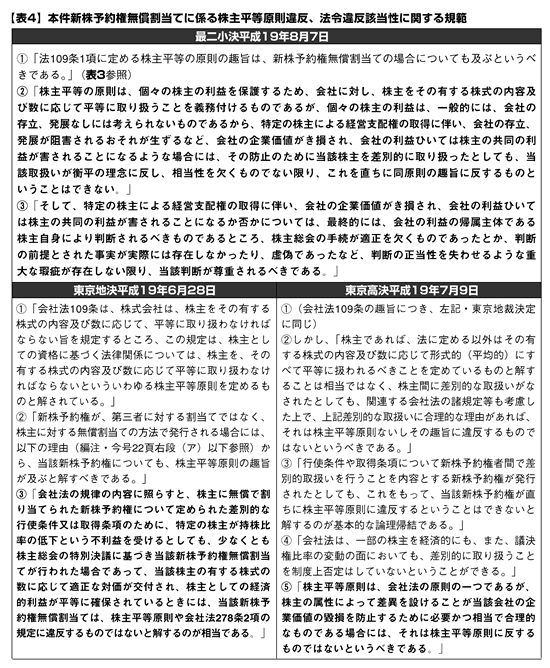
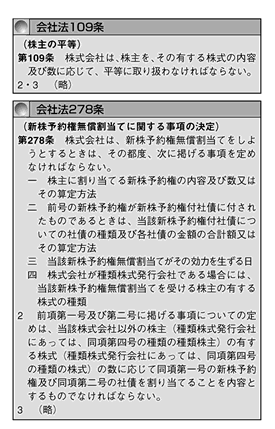
最高裁はどのように判断したか
最高裁で示された判断の枠組みは表4のとおりで、その要点は次のようにまとめられる。
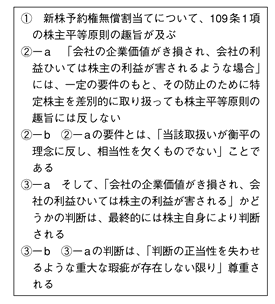
上記②-aの場合としては「特定の株主による経営支配権の取得に伴い、会社の存立、発展が阻害されるおそれが生ずる」場合が、③-bの場合としては「株主総会の手続が適正を欠くものであったとか、判断の前提とされた事実が実際には存在しなかったり、虚偽であった」場合が例示されている。
東京地裁決定・東京高裁決定との相違は、①において、行使条件や取得条項に係る差別的取扱いには言及せずに原則の趣旨が及ぶものとされていること、②において、経済的利益または持株比率変動面における差別的取扱いについても(ここでは)言及していないこと、③において、当該総会判断が「特別決議」によりなされることを求めてはいないことである。
決定は、このような規範に照らし、本件割当てを検討。まず、③-aについて、本件議案が議決権総数の約83.4%の賛成を得て可決されたとし、SPJSFによる経営支配権の取得につき「抗告人関係者以外のほとんどの既存株主が、……相手方の企業価値をき損し、相手方の利益ひいては株主の共同の利益を害することになると判断した」と、次いで、③-bについて、SPJSFが支配権取得後の経営方針を明示しなかったことなどを挙げ、「当該判断に、その正当性を失わせるような重大な瑕疵は認められない」と認定している。
この後、②-bについて検討し、SPJSFの持株比率が大幅に低下することを認定しながらも、(ア)本件割当てが「抗告人関係者も意見を述べる機会のあった本件総会における議論を経て、抗告人関係者以外のほとんどの既存株主が、……必要な措置として是認した」こと、(イ)本件新株予約権の取得の実行により対価として金員の交付を受けられ、また、実行されない場合でも取締役会決議により本件新株予約権の譲渡の申入れによって金員の支払いが受けられること、(ウ)「上記対価は、抗告人関係者が自ら決定した本件公開買付けの買付価格に基づき算定されたもので、本件新株予約権の価値に見合うもの」であることから、本件割当ては衡平の理念に反し、相当性を欠くものとはいえないと判断。
そのうえで結論として、「抗告人関係者が原審(編注・東京高裁決定)のいう濫用的買収者に当たるといえるか否かにかかわらず」、本件割当ては「株主平等の原則の趣旨に反するものではなく、法令等に違反しないというべきである」と述べている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















